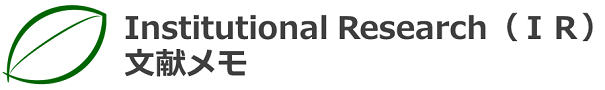
ホーム → 更新履歴
更新履歴
公開日:2012年7月27日 最終更新日:2024年7月19日
ここではサイト公開日から最終更新日までの更新履歴を掲載しています。
- [2024.7.19]ホーム「お知らせ」欄に追加
- スタッフ(セッションチーフ)担当「IR実務担当者セッション(R2)」(大学評価・IR担当者集会2024)
- スタッフ担当「IR初級者セッション(R1)」(大学評価・IR担当者集会2024)
- [2024.5.9]「ホーム」「IRなどについての文献メモ」「これまでの発表・競争的研究資金など」「過去の「お知らせ」」に追加(リポジトリ公開)
- 橋本智也(2024).初年次教育科目「初年次ゼミナール」の目的と到達目標の達成状況を検証する:2022年度受講者アンケートの結果から 大阪公立大学大学教育,2,32-41.[PDF]
- [2024.4.1]「これまでの発表・競争的研究資金など」に追加
- [2024.4.1]「ホーム」「これまでの発表・競争的研究資金など」に追加
- 令和6年度科学研究費助成事業(学術研究助成基金助成金)基盤研究(C)(一般)「理論・実践の融合とデータ活用による初年次教育:授業レベルでの学習評価の枠組み開発」(研究代表者:橋本智也、研究分担者:白石哲也、研究期間:2024~2026年度)※課題番号24K06088を追記
- [2024.3.11]「これまでの発表・競争的研究資金など」に追加
- 口頭発表「初年次教育科目の学習成果を検証する:多様な視点への気づきに着目して」(継続的改善のためのIR/IEセミナー2024「IR/内部質保証実務担当者セッション」)
- [2024.2.29]「ホーム」に追加
- 令和6年度科学研究費助成事業(学術研究助成基金助成金)基盤研究(C)(一般)「理論・実践の融合とデータ活用による初年次教育:授業レベルでの学習評価の枠組み開発」(研究代表者:橋本智也、研究分担者:白石哲也、研究期間:2024~2026年度)
- [2024.2.6]「ホーム」に追加
- 口頭発表「初年次教育科目の学習成果を検証する:多様な視点への気づきに着目して」(継続的改善のためのIR/IEセミナー2024「IR/内部質保証実務担当者セッション」)
- [2024.2.6]「過去の「お知らせ」」に追加
- 全体司会「第2回教育改革フォーラム」(大阪公立大学高等教育研究開発センター、情報学研究科)
- [2023.12.3]「ホーム」
- [2023.12.2]「ホーム」に追加
- 全体司会「第2回教育改革フォーラム」(大阪公立大学高等教育研究開発センター、情報学研究科)
- [2023.11.16]「過去の「お知らせ」」に追加
- 講演会司会「大学IRコンソーシアム会員向け講演会「あらためてIRの活用について考える」」(大学IRコンソーシアム)
- [2023.11.12]「ホーム」「これまでの発表・競争的研究資金など」に追加
- 橋本智也(印刷中).初年次教育科目「初年次ゼミナール」の目的と到達目標の達成状況を検証する:2022年度受講者アンケートの結果から 大阪公立大学大学教育,2.
- [2023.11.8]「ホーム」に追加
- 講演会司会「大学IRコンソーシアム会員向け講演会「あらためてIRの活用について考える」」(大学IRコンソーシアム)
- [2023.9.27]「過去の「お知らせ」」、「IRなどについての文献メモ」、「これまでの発表・競争的研究資金など」に追加
- 研修会講師「初級者のためのIR入門(2023年度版):考え方と実践事例から自大学での応用可能性を考える」(大学IRコンソーシアム23年度第3回(通算第17回)会員向け講演会)※講師依頼
- 43rd Annual Conference on The First-Year Experience(2024年2月、米国ワシントン州)査読者
- [2023.9.12]「過去の「お知らせ」」に追加
- スタッフ担当「IR初級者セッション(R1)」「IR実務担当者セッション(R2)」(大学評価・IR担当者集会2023)
- [2023.8.27]「過去の「お知らせ」」、「IRなどについての文献メモ」、「これまでの発表・競争的研究資金など」に追加
- 橋本智也・白石哲也(2023).データを活用して初年次教育の学習成果を評価する:米国の知見の応用と担当授業での実践 日本教育情報学会第39回年会
- [2023.8.22]「ホーム」に追加
- 研修会講師「初級者のためのIR入門(2023年度版):考え方と実践事例から自大学での応用可能性を考える」(大学IRコンソーシアム23年度第3回(通算第17回)会員向け講演会)※講師依頼
- [2023.8.9]「過去の「お知らせ」」、「IRなどについての文献メモ」、「これまでの発表・競争的研究資金など」に追加
- 橋本智也(2023).生成AIを活用した初年次教育の授業設計と実践 日本教育工学会研究報告集,2023(2),pp. 95-100.[PDF](日本教育工学会研究会<教育DX/一般>、2023年7月)
- [2023.7.24]ホーム「お知らせ」欄に追加
- 座長担当「午後の部②」(日本教育工学会研究会<教育DX/一般>)
- [2023.6.19]ホーム「お知らせ」欄に追加
- スタッフ担当「IR初級者セッション(R1)」「IR実務担当者セッション(R2)」(大学評価・IR担当者集会2023)
- 口頭発表「生成AIを活用した初年次教育の授業設計と実践」(日本教育工学会研究会<教育DX/一般>)※時刻と会場を追記
- [2023.6.19]ホーム「お知らせ」欄に追加
- 「2023年度国際基幹教育機構研究奨励費」採択を掲載
- [2023.6.9]「過去の「お知らせ」」、「IRなどについての文献メモ」、「これまでの発表・競争的研究資金など」に追加
- 橋本智也(2023).質的データから見た、学生および教員の教育実態 第2回大学教育研究セミナー「2021年度実施調査からみた、大阪市立大学学士課程学生、大学院生、教員の教育の実態」(オンライン開催、2023年6月)※大阪公立大学の学内セミナー
- [2023.6.7]ホーム「お知らせ」欄に追加
- 報告「質的データから見た、学生および教員の教育実態」(第2回大学教育研究セミナー)
- 大学IRコンソーシアム広報・ワークショップ部会の副部会長に再任
- [2023.6.5]「過去の「お知らせ」」、「IRなどについての文献メモ」、「これまでの発表・競争的研究資金など」に追加
- 橋本智也・白石哲也(2023).IR担当者の専門性と執行部の期待の関係 大学教育学会第45回大会発表要旨集録 pp.236-237.(口頭発表、大阪大学吹田キャンパス工学部、2023年6月)[プログラム]
- [2023.6.1]ホーム「お知らせ」欄に追加
- 口頭発表「生成AIを活用した初年次教育の授業設計と実践」(日本教育工学会研究会<教育DX/一般>)
- [2023.5.15]ホーム「お知らせ」欄に追加
- 口頭発表「データを活用して初年次教育の学習成果を評価する:米国の知見の応用と担当授業での実践」(日本教育情報学会第39回年会)
- [2023.4.14]ホーム「お知らせ」欄に追加
- 司会担当「部会6 学士課程教育(2)」(大学教育学会第45回大会)
- [2023.4.1]ホーム「お知らせ」欄に追加
- 口頭発表「IR組織・担当者の能力と大学執行部の期待の関係」(大学教育学会第45回大会)
- [2023.3.16]「ホーム」、「過去の「お知らせ」」、「IRなどについての文献メモ」、「これまでの発表・競争的研究資金など」に追加
- 橋本智也(2023).全学に遠隔授業が本格導入された際の実践事例【令和3年度大阪市立大学教育後援会「優秀教育賞」受賞】 大阪公立大学大学教育,1,92-93.[PDF]
- [2023.3.16]「ホーム」、「過去の「お知らせ」」、「IRなどについての文献メモ」、「これまでの発表・競争的研究資金など」に追加
- 口頭発表「IR組織・担当者の能力と大学執行部の期待の関係:全国アンケート調査に基づく検証」(第29回大学教育研究フォーラム)
- [2023.3.14]「ホーム」、「過去の「お知らせ」」、「IRなどについての文献メモ」、「これまでの発表・競争的研究資金など」に追加
- 口頭発表「IR組織・担当者の能力と大学執行部の期待の関係:調査結果の概要報告とIR担当者との意見交換」(継続的改善のためのIR/IEセミナー2023「IR実務担当者セッションA」)
- スタッフ参加「質疑応答・総合討論」(継続的改善のためのIR/IEセミナー2023「IR実務担当者セッションB」)
- [2023.3.8]ホーム「お知らせ」欄に追加
- スタッフ参加「質疑応答・総合討論」(継続的改善のためのIR/IEセミナー2023「IR実務担当者セッションB」)
- [2023.2.26]ホーム「お知らせ」欄に追加
- 口頭発表「IR組織・担当者の能力と大学執行部の期待の関係:調査結果の概要報告とIR担当者との意見交換」(継続的改善のためのIR/IEセミナー2023「IR実務担当者セッションA」)
- [2023.2.26]「ホーム」、「過去の「お知らせ」」、「IRなどについての文献メモ」、「これまでの発表・競争的研究資金など」に追加
- スタッフ参加「総合討論・質疑応答」(教務情報担当者のための教育の内部質保証セミナー)
- [2023.2.6]「ホーム」、「過去の「お知らせ」」、「IRなどについての文献メモ」、「これまでの発表・競争的研究資金など」に追加
- 口頭発表"Bridging executives' expectations for first-year education and institutional researchers' expertise"(42nd Annual Conference on The First-Year Experience)
- [2023.1.28]ホーム「お知らせ」欄に追加
- 口頭発表「IR組織・担当者の能力と大学執行部の期待の関係:全国アンケート調査に基づく検証」(第29回大学教育研究フォーラム)
- [2023.1.26]ホーム「お知らせ」欄に追加
- スタッフ(ファシリテーター)担当「グループ討議、情報共有・総合討論」(教務情報担当者のための教育の内部質保証セミナー)
[2022.11.30]「過去の「お知らせ」」、「IRなどについての文献メモ」、「これまでの発表・競争的研究資金など」に追加
- ポスター発表「大学構成員相互の対話の場づくりをめざす体系的・計画的な教育評価・FD実践:大阪市立大学における教育・学修成果評価サイクルの構築過程からの検討」(大学教育学会2022年度課題研究集会)
- ポスター発表「量的・質的調査結果から見た学生・教員間が共有する学びの場の状況:大阪市立大学における教育・学修成果評価サイクルの構築過程からの検討」(大学教育学会2022年度課題研究集会)
[2022.10.21]「ホーム」、「過去の「お知らせ」」、「IRなどについての文献メモ」、「これまでの発表・競争的研究資金など」に追加
- 研修会講師「初級者のためのIR入門:考え方と実践事例から自大学での応用可能性を考える」(大学IRコンソーシアム第4回会員向け講演会)※講師依頼
[2022.10.14]ホーム「お知らせ」欄に追加
- 口頭発表"Bridging executives' expectations for first-year education and institutional researchers' expertise"(42nd Annual Conference on The First-Year Experience)
[2022.10.4]ホーム「お知らせ」欄に追加
- ポスター発表「大学構成員相互の対話の場づくりをめざす体系的・計画的な教育評価・FD実践:大阪市立大学における教育・学修成果評価サイクルの構築過程からの検討」(大学教育学会2022年度課題研究集会)
- ポスター発表「量的・質的調査結果から見た学生・教員間が共有する学びの場の状況:大阪市立大学における教育・学修成果評価サイクルの構築過程からの検討」(大学教育学会2022年度課題研究集会)
- 研修会講師「初級者のためのIR入門:考え方と実践事例から自大学での応用可能性を考える」(大学IRコンソーシアム第4回会員向け講演会)※講師依頼
- 大学評価コンソーシアムの幹事再任に伴い、任期の記載を更新
[2022.8.24]「ホーム」、「過去の「お知らせ」」、「IRなどについての文献メモ」、「これまでの発表・競争的研究資金など」に追加
- 橋本智也・白石哲也(2022).学生の多様化に対するIRの役割:米国の取組に関する文献調査からの示唆 日本教育情報学会第38回年会(十文字学園女子大学※対面+オンラインのハイフレックス方式、2022年8月)
[2022.8.12]「これまでの発表・競争的研究資金など」に追加
- 研修会講師「遠隔授業におけるアクティブラーニングの方策」(2021年度看護学研究科第1回FD研修会)※講師依頼
[2022.8.10]「ホーム」「これまでの発表・競争的研究資金など」に追加
- 副部会長「大学IRコンソーシアム広報・ワークショップ部会」を掲載
[2022.7.27]ホーム「お知らせ」欄、「過去の「お知らせ」」に追加
- スタッフ(司会)担当「IR実務担当者セッション(R3)」(大学評価・IR担当者集会2022)
[2022.7.25]ホーム「お知らせ」欄、「過去の「お知らせ」」を修正
- 口頭発表「学生の多様化に対するIRの役割:米国の取組に関する文献調査からの示唆」(日本教育情報学会第38回年会)の会場欄に「※対面+オンラインのハイフレックス方式」を追記
[2022.6.11]ホーム「お知らせ」欄、「過去の「お知らせ」」に追加
- 口頭発表「学生の多様化に対するIRの役割:米国の取組に関する文献調査からの示唆」(日本教育情報学会第38回年会)
[2022.6.11]ホーム「お知らせ」欄、「過去の「お知らせ」」に追加
- 口頭発表「学生の多様化に対するIRの役割:米国の取組に関する文献調査からの示唆」(日本教育情報学会第38回年会)
[2022.6.11]「ホーム」を修正
[2022.4.12]「ホーム」、「過去の「お知らせ」」、「これまでの発表・競争的研究資金など」に追加
- 令和4年度科学研究費助成事業(学術研究助成基金助成金)基盤研究(C)(一般)「大学の「学園」としての「場」の学生における価値とその形成に関する実証的探索的研究」採択(研究分担者)を掲載
[2022.4.12]「これまでの発表・競争的研究資金など」に追加
[2022.4.4]「ホーム」を修正
[2022.4.1]「ホーム」を修正
- 大阪公立大学開学に伴い、所属を「大阪市立大学 高等教育研究院 大学教育研究センター」から「大阪公立大学 国際基幹教育機構 高等教育研究開発センター」に変更。
[2022.3.23]「ホーム」、「過去の「お知らせ」」、「IRなどについての文献メモ」、「これまでの発表・競争的研究資金など」に追加
- 橋本智也・白石哲也(2022).IR組織・担当者の能力と大学執行部の期待の関係 : ヒアリング調査に基づく類型化 大阪市立大学大学教育,19(1),1-15.[PDF]
[2022.3.19]IRなどについての文献メモ 文献一覧を更新<テキストマイニング>
- 吉田由似・上田一紀(2021).オンライン (オンデマンド型) 授業の実践とその課題に関する一考察:初年次教育,及び情報教育におけるスタディ・スキル科目を題材に 関西大学高等教育研究,12,71-85.[PDF][概要](Google Scholar「テキストマイニング アンケート」で知る)
- 辻雅子・大園真凜・建路七織・綿貫仁美・吉野知子・馬場修・網干弓子・林一也(2021).女子大学生に対するシリアルを用いた食育の検討 東京家政学院大学紀要,61,1.[PDF][概要](Google Scholar「テキストマイニング アンケート」で知る)
- 髙松直紀(2022).遠隔によるキャリア教育の一手法としてのキャリアインタビュー・テキストマイニングによる教育効果の検証 研究紀要,12,143-154.[PDF][概要](Google Scholar「テキストマイニング アンケート」で知る)
- 空谷知之(2021).緊急事態宣言下における商業高校のオンライン授業の実践 情報教育,3,23-31.[PDF][概要](Google Scholar「テキストマイニング アンケート」で知る)
- 宮﨑英一(2021). テキストマイニングを用いた香川大学における遠隔教育の状況考察:5月の学生のアンケートより 香川大学教育研究,18,67-76.[PDF][概要](Google Scholar「テキストマイニング アンケート」で知る)
- 工藤慈士・佐藤大典・草薙健太・杉山佳生(2022).コロナ禍における大学競泳選手の心理状態に関する内容分析 スポーツ産業学研究,32(1),1_51-1_62.[PDF][概要](Google Scholar「テキストマイニング アンケート」で知る)
- 東尾晃世・香田健治(2021).「学級づくりの理論と実際」 における ICT 活用指導力の育成に関する研究:学生アンケート調査の分析を手がかりにして 関西福祉科学大学紀要,25,17-28.[PDF][概要](Google Scholar「テキストマイニング アンケート」で知る)
- 秀真一郎・若田美香(2021).保育現場における保育者による受容の捉え方に関する計量テキスト分析 応用教育心理学研究,38(1),35-46.[PDF][概要](Google Scholar「テキストマイニング アンケート」で知る)
- 林俊克(2021).新入学生アンケートのテキストマイニングによる大学の価値分析(第二報) 就実経営研究,6,55-71.[PDF][概要](Google Scholar「テキストマイニング アンケート」で知る)
- 後藤和也(2021).キャリア支援科目 「ライフ・キャリアデザイン」 に おける学びと成長-テキストマイニングによる探索的検討 山形県立米沢女子短期大学紀要,57,13-20.[PDF][概要](Google Scholar「テキストマイニング アンケート」で知る)
- 坊垣美也子・松元英理子・杉山育代・澁谷雪子・高松邦彦・中田康夫(2021).コンピテンシーの育成を目指した専門科目「臨床検査学発展演習」の成果と課題 神戸常盤大学紀要,14,58-69.[PDF][概要](Google Scholar「テキストマイニング アンケート」で知る)
[2021.10.25]「ホーム」、「過去の「お知らせ」」、「これまでの発表・競争的研究資金など」に追加
- 令和3年度大阪市立大学教育後援会「優秀教育賞」受賞を追加
[2021.10.17]「これまでの発表・競争的研究資金など」の「教育歴」に追加
[2021.10.14]「ホーム」、「過去の「お知らせ」」、「IRなどについての文献メモ」、「これまでの発表・競争的研究資金など」に追加
- 藤井都百・橋本智也(2021).大学評価・IR担当者が有する素養の醸成に影響を及ぼす要因の推定:大学評価コンソーシアム会員に対する平成30年度調査の結果分析の報告 大学評価とIR,12,36-49.[PDF]
[2021.8.4]「過去の「お知らせ」」、「IRなどについての文献メモ」、「これまでの発表・競争的研究資金など」に追加
- 招待講演"Monitoring and evaluation of the learning outcome"(王立プノンペン大学・大阪府立大学「キックオフシンポジウム」(世界銀行「高等教育高度化プロジェクト」))
- スタッフ参加「テューショナル・リサーチャー養成プログラム「IR初級人材育成研修会」(文部科学省教育関係共同利用拠点事業)」
[2021.7.14]「IRなどについての文献メモ」、「これまでの発表・競争的研究資金など」に追加
- 橋本智也(2021).第27回大学教育研究セミナー:実施報告 大阪市立大学大学教育,18(2),69.[PDF]
[2021.7.6]ホームを更新
- スタッフ参加「テューショナル・リサーチャー養成プログラム「IR初級人材育成研修会」(文部科学省教育関係共同利用拠点事業)」を掲載
[2021.5.24]IRなどについての文献メモ 文献一覧を更新<統計>
- 池田郁男(2019).改訂増補版:統計検定を理解せずに使っている人のためにI 化学と生物,57(8),492-502.[PDF](CiNii Articles「統計検定を理解せずに使っている人のために 改訂増補版」で知る)
- 池田郁男(2019).改訂増補版:統計検定を理解せずに使っている人のためにII 化学と生物,57(9),562-579.[PDF](CiNii Articles「統計検定を理解せずに使っている人のために 改訂増補版」で知る)
- 池田郁男(2019).改訂増補版:統計検定を理解せずに使っている人のためにIII 化学と生物,57(10),629-647.[PDF](Google「"一元配置分散分析" "二元配置分散分析"」で知る)
- 池田郁男(2017).実験で使うとこだけ生物統計1:キホンのキ 羊土社(「改訂増補版:統計検定を理解せずに使っている人のためにI」(池田,2019)で知る)
- 池田郁男(2017).実験で使うとこだけ生物統計2:キホンのホン 羊土社(「改訂増補版:統計検定を理解せずに使っている人のためにI」(池田,2019)で知る)
[2021.4.23]IRなどについての文献メモ 文献一覧を更新<看護、アクティブ・ラーニング>※「IRなどについての文献メモ」のページには追加せず
- 中井俊樹・小林忠資(編)(2015).看護のための教育学 医学書院(Amazon.co.jp「看護、アクティブ・ラーニング」で知る)
- 中井俊樹・小林忠資(編)(2017).授業方法の基礎 医学書院(Amazon.co.jp「看護、アクティブ・ラーニング」で知る)
- 中井俊樹・服部律子(編)(2018).授業設計と教育評価 医学書院(Amazon.co.jp「看護、アクティブ・ラーニング」で知る)
- 小林忠資・鈴木玲子(編)(2018).アクティブラーニングの活用 医学書院(Amazon.co.jp「看護、アクティブ・ラーニング」で知る)
- 新井英靖(編)(2017).アクティブ・ラーニング時代の看護教育:積極性と主体性を育てる授業づくり ミネルヴァ書房(Amazon.co.jp「看護、アクティブ・ラーニング」で知る)
- 新井英靖(2019).看護教育に生かすアクティブ・ラーニング:授業づくりの基本と実践 メヂカルフレンド社(Amazon.co.jp「看護、アクティブ・ラーニング」で知る)
- 鈴木敏恵(2016).アクティブラーニングをこえた看護教育を実現する:与えられた学びから意志ある学びへ 医学書院(Amazon.co.jp「看護、アクティブ・ラーニング」で知る)
- 諏訪茂樹(2019).看護のためのコミュニケーションと人間関係:アクティブ・ラーニングで身につける技術と感性 中央法規出版(Amazon.co.jp「看護、アクティブ・ラーニング」で知る)
- 内藤知佐子・宮下ルリ子・三科志穂(2019).学生・新人看護師の目の色が変わる:アイスブレイク30 医学書院(Amazon.co.jp「看護、アクティブ・ラーニング」で知る)
- 久保健太郎・濱中秀人・徳野実和・倉岡賢治(編著)(2019).先輩ナースが書いた看護のトリセツ 照林社(Amazon.co.jp「看護、アクティブ・ラーニング」で知る)
- 高橋平徳・内藤知佐子(編)(2019).体験学習の展開 医学書院(Amazon.co.jp「看護、アクティブ・ラーニング」で知る)
- 安酸史子・北川明(編)(2018).看護を教える人のための経験型実習教育ワークブック 医学書院(Amazon.co.jp「看護、アクティブ・ラーニング」で知る)
- 但馬まり子・飯田恵子・井田歩美(2021).COVID-19禍における遠隔授業の実践報告:単元「分娩介助技術」に取り入れた反転授業の振り返り 摂南大学看護学研究,9(1),21-28.[PDF](CiNii Articles「看護、アクティブ・ラーニング」で知る)
- 新井英靖(2021).アクティブ・ラーニング時代のオンライン授業:「個別最適化された学び」を実現するには 看護展望,46(1),50-54.(CiNii Articles「看護、アクティブ・ラーニング」で知る)
- 柳田俊彦・金岡麻希・木下由美子・武谷立(2021).看護薬理学教育におけるアクティブラーニングの試み 日本薬理学会年会要旨集,94,1-S06-4.[PDF](CiNii Articles「看護、アクティブ・ラーニング」で知る)
- 土手友太郎(2020).看護学部に導入された授業支援システムのCBT機能を活用した教育技法の検討 大阪医科大学雑誌,79(1・2),29-33.(CiNii Articles「看護、アクティブ・ラーニング」で知る)
- 唐沢博子・板山稔・藤田佳代子・平井佳代(2020).動画配信を利用した学生主体のグループ学習:看護学部2年次の国家試験対策の活動 目白大学高等教育研究,26,23-30.[PDF](CiNii Articles「看護、アクティブ・ラーニング」で知る)
- 栗原律子(2020).在宅看護論演習におけるeラーニングシステムを活用したアクティブ・ラーニングの授業成果 旭川大学保健福祉学部研究紀要,12,35-40.[PDF](CiNii Articles「看護、アクティブ・ラーニング」で知る)
- 古川亮子・西野友子(2020).母性看護学・ウィメンズヘルスにおけるアクティブラーニングに関する文献レビュー 順天堂保健看護研究,8,2-8.[PDF](CiNii Articles「看護、アクティブ・ラーニング」で知る)
- 土井智生・鈴木久美・池西悦子・府川晃子・津田泰宏(2020).チーム医療の理解を促すアクティブ・ラーニングを用いた授業の有用性と看護学生の学び 大阪医科大学看護研究雑誌,10,23-31.[PDF](CiNii Articles「看護、アクティブ・ラーニング」で知る)
- 玉川優芽・福間美紀・宮本まゆみ・坂根可奈子・津本優子(2020).アクティブ・ラーニング型反転授業を導入した基礎看護技術演習科目の評価とその課題 :車椅子移動単元科目における中間評価 島根大学医学部紀要,42,41-46.[PDF](CiNii Articles「看護、アクティブ・ラーニング」で知る)
- 古角好美(2020).2年間にわたり「LTD話し合い学習法」を学校保健論に試行した教育効果 教育カウンセリング研究,10(1),31-39.[PDF](CiNii Articles「看護、アクティブ・ラーニング」で知る)
- 木挽秀夫(2019).精神科看護学におけるアクティブラーニング:課題探索型学修法とジグソー学習法を活用した教育実践報告 中部学院大学・中部学院大学短期大学部教育実践研究,5,215-224.[PDF](CiNii Articles「看護、アクティブ・ラーニング」で知る)
- 川合美奈・光樂香織(2019).小児看護学におけるアクティブラーニングを意識した学習支援:学生による授業評価アンケートの分析結果から 日本看護学教育学会誌,29(2),27-36.(CiNii Articles「看護、アクティブ・ラーニング」で知る)
- 宝田慶子・進藤美樹・藤尾順子・山内京子(2019).小児看護学領域における学生参画型授業展開の学修効果と課題 看護学統合研究,21(1),1-8.[PDF](CiNii Articles「看護、アクティブ・ラーニング」で知る)
- 村中陽子・飯村直子・齋藤泰子・中嶋尚子・石津仁奈子・岡田葉子・片桐いずみ・柴野裕子・茅島江子(2019).看護学の基礎分野「総合教養演習Ⅲ(倫理観)」における アクティブラーニングの授業設計 秀明大学看護学部紀要,1(1),71-78.[PDF](CiNii Articles「看護、アクティブ・ラーニング」で知る)
- 浦川加代子・門脇玲子・小川典子・佐野知世・高橋智子(2019).学内活動報告 本学部におけるアクティブラーニング実施状況について:FD委員会報告 順天堂保健看護研究,7,67-73.[PDF](CiNii Articles「看護、アクティブ・ラーニング」で知る)
- 古田成志(2019).アクティブラーニングを理解する:中京学院大学看護学部FD研修会の講演報告 中京学院大学研究紀要,26,59-73.[PDF](CiNii Articles「看護、アクティブ・ラーニング」で知る)
- 太田美帆・西久保秀子・有澤舞・村上希・加藤和子(2019).慢性病患者の食に関する看護実践力を養うアクティブ・ラーニングの評価 東京家政大学研究紀要,59(2),47-54.[PDF](CiNii Articles「看護、アクティブ・ラーニング」で知る)
- 末次典恵(2019).ジグソー学習法で展開した看護学生を対象としたBasic Life Support(BLS)教育の評価 南九州看護研究誌,17(1),1-7.[PDF](CiNii Articles「看護、アクティブ・ラーニング」で知る)
- 村上大介(2019).看護学教育におけるアクティブラーニングの研究動向 東北文化学園大学看護学科紀要,8(1),19-26.[PDF](CiNii Articles「看護、アクティブ・ラーニング」で知る)
- 岡多枝子・三並めぐる(2019).保健・医療・福祉専門職を志す学生がアクティブラーニングで獲得するレリバンス 健康生活と看護学研究,2,1-6.(CiNii Articles「看護、アクティブ・ラーニング」で知る)
- 友滝愛・柏木公一(2019).多人数授業におけるアクティブ・ラーニング型授業:フルーツカクテル式プレゼンテーションの試み 国立病院看護研究学会誌,15(1),52-59.(CiNii Articles「看護、アクティブ・ラーニング」で知る)
- 吾妻知美・筒井佳澄(2019).看護マネジメント実習にアクティブ・ラーニングを取り入れた効果 京都府立医科大学看護学科紀要,29,21-27.[PDF](CiNii Articles「看護、アクティブ・ラーニング」で知る)
- 天野由貴(2018).学習者の「知りたい」を引き出す:『問いをつくるスパイラル』から始めるアクティブラーニング 看護教育,59(7),542-549.(CiNii Articles「看護、アクティブ・ラーニング」で知る)
- 岡多枝子・眞鍋瑞穂・三並めぐる(2018).看護学生に対する福祉・社会学教育のレリバンス:アクティブラーニングによる実証研究 龍谷教職ジャーナル,5,18.[PDF](CiNii Articles「看護、アクティブ・ラーニング」で知る)
- 杉崎一美・後藤由紀・別所史子・吉川尚美・萩典子(2018).講義からアクティブラーニングへの転換:双方向型授業に向けての環境整備とその活用 四日市看護医療大学紀要,11(1),27-34.(CiNii Articles「看護、アクティブ・ラーニング」で知る)
- 志野泰子(2018).医療者教育におけるアクティブ・ラーニング導入の質的評価:公衆衛生看護学演習の授業実践の成果 大和大学研究紀要. 保健医療学部編,4,23-29.[PDF](CiNii Articles「看護、アクティブ・ラーニング」で知る)
- 中村幸代・宮内清子・佐藤いずみ・竹内翔子(2018).母性看護学におけるTeam Based Learning (TBL)の導入に関する分析と評価 母性衛生,58(4),655-663.(CiNii Articles「看護、アクティブ・ラーニング」で知る)
- 武用百子・岩根直美・明神哲也・山岡由実・川田美和(2018).アクティブラーニングを導入した看護倫理演習が道徳的感受性、職業的アイデンティティ及びプロフェッショナリズムに及ぼす影響:「倫理的判断をした行動を選択できる」という授業設計に基づいた看護倫理演習を教材として 日本シミュレーション医療教育学会雑誌,6,9-17.(CiNii Articles「看護、アクティブ・ラーニング」で知る)
- 松原まなみ・田中千絵・柳本朋子・川口弥恵子・井口亜由・中村登志子(2018).看護学生の学士力を育てるための授業:母性看護学教育におけるアクティブ・ラーニングの取り組み 聖マリア学院大学紀要,9,31-37.(CiNii Articles「看護、アクティブ・ラーニング」で知る)
- 藤田優一・北尾美香・植木慎悟・藤原千惠子(2018).ジグソー法を取り入れたアクティブラーニングに対する学生からの評価::小児看護学演習科目における看護過程展開の実践報告 日本看護科学会誌,38,237-244.[PDF](CiNii Articles「看護、アクティブ・ラーニング」で知る)
- 平山正晃・竹嶋順平・北原信子・林義樹(2018).成人看護学の授業における反転授業とラベルワーク用いた授業効果 帝京大学福岡医療技術学部紀要,13,55-61.[PDF](CiNii Articles「看護、アクティブ・ラーニング」で知る)
- 小川真由子・福田博美・水野昌子・藤井紀子・三尾弘子・永石喜代子・植田ひろみ・林さえ子(2017).養護教諭教育における看護技術修得のためのシミュレーション教育の必要性:文献検討による一考察 生活コミュニケーション学研究所年報 ,8,35-46.[PDF](CiNii Articles「看護、アクティブ・ラーニング」で知る)
- 森田敏子(2017).アクティブラーニング技法を使用したグループワークにおけるルーブリックの活用 看護展望,42(14),1342-1347.(CiNii Articles「看護、アクティブ・ラーニング」で知る)
- 八尋陽子(2017).アクティブ・ラーニングの授業設計:学生間ピア・レビューの導入 インターナショナルnursing care research,16(3),45-53.(CiNii Articles「看護、アクティブ・ラーニング」で知る)
- 貝谷敏子・菅原美樹・川村三希子・神島滋子・藤井瑞恵・工藤京子・柏倉大作・村松真澄・小田和美・中村惠子(2017).看護演習科目へのルーブリック導入の効果・ルーブリック評価の信頼性と妥当性の検討 札幌市立大学研究論文集,11(1),3-11.[PDF](CiNii Articles「看護、アクティブ・ラーニング」で知る)
- 鹿村眞理子・岩根直美・粷谷博子・堀江佳代子(2017).アクティブラーニングを用いた院内研修:看護の本質を再発見する Nursing business,11(5),452-455.(CiNii Articles「看護、アクティブ・ラーニング」で知る)
- 増田美恵子・高島えり子・青柳優子・植竹貴子・大田康江・鈴木紀子・髙橋眞理(2017).『周産期の看護』の授業におけるTeam-based learningの導入 医療看護研究,13(2),76-81.(CiNii Articles「看護、アクティブ・ラーニング」で知る)
- 古角好美(2017).看護学生が受講する「学校保健論」におけるLTD学習の効果:アクティブ・ラーニングによる授業の試み 大和大学研究紀要. 保健医療学部編,3,43-53.[PDF](CiNii Articles「看護、アクティブ・ラーニング」で知る)
- 森慶輔・黒岩初美(2017).養護教諭養成課程「生徒指導論」におけるアクテイブラーニングの試み 看護学研究紀要,5(1),25-34.[PDF](CiNii Articles「看護、アクティブ・ラーニング」で知る)
- 牧野典子・江尻晴美(2017).新しい地域防災リーダーを育てる災害看護科目のアクティブラーニング 日本看護研究学会雑誌,40(3),3_318-3_318.[PDF](CiNii Articles「看護、アクティブ・ラーニング」で知る)
- 高見精一郎・野口眞弓・東野督子・森田一三・平野二郎・上村治(2017).日本赤十字豊田看護大学におけるアクティブラーニング支援のための機器導入と利用の状況 日本赤十字豊田看護大学紀要,12(1),51-56.[PDF](CiNii Articles「看護、アクティブ・ラーニング」で知る)
- 小川真由子・引田郁美(2017).アクティブラーニングによる看護技術の習得を目指して:養護教諭養成課程における小先生制度の授業自己評価から 鈴鹿大学短期大学部紀要,37,59-69.[PDF](CiNii Articles「看護、アクティブ・ラーニング」で知る)
- 有森直子・桐原更織・石田真由美・関島香代子(2016).新潟大学医学部保健学科看護学専攻科目「母性健康支援看護論」におけるアクティブラーニングの試み 新潟大学保健学雑誌,13(1),19-25.[PDF](CiNii Articles「看護、アクティブ・ラーニング」で知る)
- 武用百子・岩根直美・山岡由実・川田美和・明神哲也・岩原昭彦・鹿村眞理子(2016).アクティブラーニングを導入した看護倫理演習前後の道徳的感受性の変化(第1報) 和歌山県立医科大学保健看護学部紀要,13,51-58.[PDF](CiNii Articles「看護、アクティブ・ラーニング」で知る)
- 真嶋由貴恵・中村裕美子・平野加代子(2016).学習者中心のアクティブ・ラーニングに向けたICT活用:看護eラーニングの現在・過去・未来 日本看護研究学会雑誌,39(3),100-100.[PDF](CiNii Articles「看護、アクティブ・ラーニング」で知る)
- 青木雅子・奥野順子・関森みゆき・日沼千尋・櫻田章子(2016).学生が試験問題を作成するアクティブラーニングの展開 東京女子医科大学看護学会誌,11(1),54-60.[PDF](CiNii Articles「看護、アクティブ・ラーニング」で知る)
- 奥山真由美・道繁祐紀恵・杉野美和・甲谷愛子(2016).高齢者の退院支援における看護実践能力育成のためのアクティブ・ラーニングを導入した老年看護学実習の評価 山陽論叢,22,11-20.[PDF](CiNii Articles「看護、アクティブ・ラーニング」で知る)
- 前田隆子・市村久美子・黒田暢子(2015).周手術期看護の演習におけるアクティブラーニングとその評価:学習効果および自己学習の動機づけとその達成感に焦点をあてて 茨城県立医療大学紀要,20,13-24.(CiNii Articles「看護、アクティブ・ラーニング」で知る)
- 武用百子・鹿村眞理子・山口雅子・辻あさみ・服部園美・前馬理恵・岩根直美・田中景子・山本美緒(2015).アクティブラーニングを導入した看護倫理演習による学生の倫理的問題の対処における動機づけの変化 和歌山県立医科大学保健看護学部紀要,12,17-26.(CiNii Articles「看護、アクティブ・ラーニング」で知る)
- 篠原良子(2015).アクティブ・ラーニングに関する文献的考察:母性看護学領域における効果的活用に向けて 三育学院大学紀要,7(1),51-58.[PDF](CiNii Articles「看護、アクティブ・ラーニング」で知る)
- 前田隆子・市村久美子・黒田暢子・梅津百代(2015).周手術期看護におけるアクティブラーニングの効果の検証:課題理解,動機づけ,および達成感への影響 日本看護研究学会雑誌,38(3),150.[PDF](CiNii Articles「看護、アクティブ・ラーニング」で知る)
- 小口多美子・井上ひとみ・田甫久美子・玉村尚子(2015).主体的学修能力を育成するための授業内容の改善の試み 獨協医科大学看護学部紀要,9,61-71.[PDF](CiNii Articles「看護、アクティブ・ラーニング」で知る)
- 花田裕子・永江誠治(2014).学生の学修意欲を刺激する授業づくりの試み:精神看護学のアクティブ・ラーニング 大学教育と情報,2014年度(2),2-8.[PDF](CiNii Articles「看護、アクティブ・ラーニング」で知る)
- 蒋妍(2014).大規模講義で行うアクティブラーニング ピア・インストラクション 看護教育,55(5),398-404.(CiNii Articles「看護、アクティブ・ラーニング」で知る)
- 前田隆子・市村久美子・黒田暢子(2014).急性期看護論に能動的学習法をとりいれた授業の評価:学生レポートにみられた学びの内容からの予備的な評価 茨城県立医療大学紀要,19,139-149.(CiNii Articles「看護、アクティブ・ラーニング」で知る)
- 草刈由美子・内宮律代・鈴木純恵・坂田信裕・藤澤隆一・種市ひろみ・河野かおり・板倉朋世・山下真幸・坂東宏和・上西秀和(2014).学生全員がタブレット端末を持つ看護教育環境における授業の質改革への取り組み 獨協医科大学看護学部紀要,8,69-74.[PDF](CiNii Articles「看護、アクティブ・ラーニング」で知る)
- 草刈由美子・河野かおり・山口久美子・板倉朋世・石綿啓子・鈴木純恵(2014).タブレット端末(iPad)を用いた基礎看護技術講義・演習の授業評価:学生のアンケート結果から 獨協医科大学看護学部紀要,8,31-38.[PDF](CiNii Articles「看護、アクティブ・ラーニング」で知る)
[2021.3.18]「過去の「お知らせ」」、「IRなどについての文献メモ」、「これまでの発表・競争的研究資金など」に追加
- 口頭発表「私立大学における学修成果の評価方針の策定状況と策定内容:アンケート調査による検証」(第27回大学教育研究フォーラム)
[2021.2.26]「過去の「お知らせ」」、「IRなどについての文献メモ」、「これまでの発表・競争的研究資金など」に追加
- 口頭発表「大学評価・IR担当者がもつ素養の醸成に影響を及ぼす要因の推定:設置形態・規模の観点からの追加分析」(継続的改善のためのIR/IEセミナー2021「IR担当者の知識、スキルに関するセッション」)
[2021.2.19]ホームを更新
- 口頭発表「大学評価・IR担当者がもつ素養の醸成に影響を及ぼす要因の推定:設置形態・規模の観点からの追加分析」(継続的改善のためのIR/IEセミナー2021「IR担当者の知識、スキルに関するセッション」)を掲載
[2021.2.19]「過去の「お知らせ」」、「IRなどについての文献メモ」、「これまでの発表・競争的研究資金など」に追加
- 橋本智也(2020).AP総括シンポジウム:パネルディスカッションのまとめ 大学教育,18(1),67-72.[PDF]
[2021.1.29]大学に関わる情報メモ 内容をアップ
[2021.1.26]大学に関わる情報メモ 内容をアップ
[2021.1.17]ホームを更新
[2020.12.3]IRなどについての文献メモ 文献一覧を更新<英語教育、効果検証>
- 大和田和治(2016).東京音楽大学におけるオンライン英会話プログラムの導入とその教育的効果の検証 研究紀要,39,53-66.[PDF](Google Scholar「英語教育 効果検証 大学」で知る)
- 田中博晃・廣森友人(2007).英語学習者の内発的動機づけを高める教育実践的介入とその効果の検証 JALT journal: journal of the Japan Association of Language Teachers,29(1),59-80.[PDF](Google Scholar「英語教育 効果検証 大学」で知る)
- 横山悟(2015).大学における初年次英語教育の効果に関する多角的分析 千葉科学大学紀要,8,17-21.[PDF](Google Scholar「英語教育 効果検証 大学」で知る)
- 馬場﨑賢太・増田由佳(2016).大学英語における反転授業の導入と学習効果 広島修大論集,57,109-113.[PDF](Google Scholar「英語教育 効果検証 大学」で知る)
- 内堀朝子・中條清美(2004). 文法指導による大学初級レベル学習者の英語コミュニケーション能力養成の効果. 日本大学生産工学部研究報告, 37, 75-83.(Google Scholar「英語教育 効果検証 大学」で知る)
- 藤代昇丈・宮地功(2009).ブレンド型授業による英語の音読力と自由発話力に及ぼす効果 日本教育工学会論文誌,32(4),395-404.[PDF](Google Scholar「英語教育 効果検証 大学」で知る)
- 三保紀裕・本田周二・森朋子・溝上慎一(2017).反転授業における予習の仕方とアクティブラーニングの関連 日本教育工学会論文誌,40(Suppl.),161-164.[PDF](Google Scholar「英語教育 効果検証 大学」で知る)
- 渡部良典(2007).教養基礎科目『大学英語 I』の効果検証 秋田大学教養基礎教育研究年報,9,61-67.[PDF](Google Scholar「英語教育 効果検証 大学」で知る)
- 牧野眞貴(2012).英語リスニングにおける洋楽聞き取りの効果検証 リメディアル教育研究,7(2),265-275.[PDF](Google Scholar「英語教育 効果検証 大学」で知る)
- 三上明洋・三上由香(2015).アクション・リサーチによる大学英語授業における多読活動の導入とその改善 全国英語教育学会紀要,26,429-444.[PDF](Google Scholar「英語教育 効果検証 大学」で知る)
- 和田珠実(2019).大学入学時における英語力と英語自己効力感がその後の学習効果と効力感に及ぼす影響 中部地区英語教育学会紀要,48,81-88.[PDF](Google Scholar「英語教育 効果検証 大学」で知る)
[2020.11.20]ホーム「お知らせ」欄に追加
- 口頭発表「私立大学における学修成果の評価方針の策定状況と策定内容:アンケート調査による検証」(第27回大学教育研究フォーラム)を掲載
[2020.9.26]ホームを更新
- 大学評価コンソーシアムの幹事再任に伴い、任期の記載を更新
[2020.9.14]IRなどについての文献メモ 文献一覧を更新<言語学>※「IRなどについての文献メモ」のページには追加せず
- 田窪行則・野田尚史(編)(2020).データに基づく日本語のモダリティ研究 くろしお出版(国立国語研究所の共同プロジェクト「多様な言語資源に基づく総合的日本語研究の開拓」におけるシンポジウムが元となったもの;「学界展望 日本語の歴史的研究 2020年1月〜6月(岩田美穂)」で知る)
- 明治書院(編)(2020).日本語学,39(2) 明治書院(2020年夏号、特集:コーパスによる語史と現代語誌) (「学界展望 日本語の歴史的研究 2020年1月〜6月(岩田美穂)」で知る)
- 柳原恵津子(2020).平安初期訓点資料における不読字の再検討:コーパス・電子化テキストを用いた訓点語研究の試みとして 国立国語研究所論集,19,187-207.[PDF](「学界展望 日本語の歴史的研究 2020年1月〜6月(岩田美穂)」で知る)
- 池田証壽・劉冠偉・鄭門鎬・張馨方・李媛(2020).観智院本『類聚名義抄』全文テキストデータベース:その構築方法と掲出項目数等の計量 訓点語と訓点資料,144,129-105.(「学界展望 日本語の歴史的研究 2020年1月〜6月(岩田美穂)」で知る)
- 大槻信(2020).『新撰字鏡』の編纂過程 国語国文,89(3),45-70.(「学界展望 日本語の歴史的研究 2020年1月〜6月(岩田美穂)」で知る)
- 林淳子(2020).現代日本語疑問文の研究 くろしお出版(「学界展望 日本語の歴史的研究 2020年1月〜6月(岩田美穂)」で知る)
- 三井はるみ(2020).条件表現の全国分布に見られる経年変化:認識的条件文の場合 國學院雜誌,121(2),1-18.(『方言文法全国地図』(GAJ)と「全国方言分布調査」(FPJD)を比較;「学界展望 日本語の歴史的研究 2020年1月〜6月(岩田美穂)」で知る)
- 澤田淳(2020).日本語の直示授与動詞「やる/くれる」の歴史 国立国語研究所論集,18,149-180.[PDF](より多くの資料・事象を視野に入れた体系的な把握とその背後にある要因の解明(一般化・抽象化)、語用論的観点からのアプローチ;「学界展望 日本語の歴史的研究 2020年1月〜6月(岩田美穂)」で知る)
- 矢島正浩(2020).近現代共通語における逆接確定節:運用法の変化を促すもの 国語国文学報,78,61-80.[PDF](より多くの資料・事象を視野に入れた体系的な把握とその背後にある要因の解明(一般化・抽象化)、語用論的観点からのアプローチ;「学界展望 日本語の歴史的研究 2020年1月〜6月(岩田美穂)」で知る)
- 衣畑智秀(編)(2019).基礎日本語学 ひつじ書房(「学界展望 日本語の歴史的研究 2019年1月〜6月 (森 勇太)」で知る)
- 大木一夫(編)(2019).ガイドブック日本語史調査法 ひつじ書房(「学界展望 日本語の歴史的研究 2019年1月〜6月 (森 勇太)」で知る)
- 大木一夫(2013).ガイドブック日本語史 ひつじ書房(Amazon.co.jpレコメンド機能で知る)
- 大木一夫・多門靖容(編)(2016).日本語史叙述の方法 ひつじ書房(Amazon.co.jpレコメンド機能で知る)
- 辻本桜介(2019).中古語の文法研究における訓点資料の活用 米子工業高等専門学校研究報告,54,29.(訓点資料を利用するための手順を丁寧に示す;「学界展望 日本語の歴史的研究 2019年1月〜6月 (森 勇太)」で知る)
- 近藤明日子・田中牧郎(2017).『UniDic』と『分類語彙表』の見出し対応表データの構築 言語資源活用ワークショップ発表論文集,1,79-86.[PDF](CiNii Articles「田中牧郎」で知る)
- 近藤明日子・田中牧郎(2020).「分類語彙表番号-UniDic語彙素番号対応表」の構築 国立国語研究所論集,18,77-91.[PDF](CiNii Articles「田中牧郎」で知る)
- 田中牧郎(2017).日本語一五〇年:明治から平成まで 日本語学,36(12),4-7.(CiNii Aritcles「日本語150年史」で知る)
- 大岡玲(2017).「翻訳」というアイデンティティ 日本語学,36(12),8-17.(CiNii Aritcles「日本語150年史」で知る)
- 湯浅茂雄(2017).明治期における語彙の更新 日本語学,36(12),18-27.(CiNii Aritcles「日本語150年史」で知る)
- 揚妻祐樹(2017).言文一致体 日本語学,36(12),28-37.(CiNii Aritcles「日本語150年史」で知る)
- 田中章夫(2017).東京語から標準語へ 日本語学,36(12),38-47.(CiNii Aritcles「日本語150年史」で知る)
- 甲斐雄一郎(2017).「教育的基礎」の探求過程 日本語学,36(12),48-58.(CiNii Aritcles「日本語150年史」で知る)
- 山東功(2017).国語国字問題の議論 日本語学,36(12),60-68.(CiNii Aritcles「日本語150年史」で知る)
- 屋名池誠(2017).「ありえたもう一つの道」から明治以来の送り仮名法の性格を考える 日本語学,36(12),70-83.(CiNii Aritcles「日本語150年史」で知る)
- 田中牧郎(2017).マスメディアに見る語彙の広がり:雑誌コーパスの外来語調査 日本語学,36(12),84-94.(CiNii Aritcles「日本語150年史」で知る)
- 米川明彦(2017).大衆文化と日本語 日本語学,36(12),96-106.(CiNii Aritcles「日本語150年史」で知る)
- 安田敏朗(2017).植民地支配と日本語 日本語学,36(12),108-117.(CiNii Aritcles「日本語150年史」で知る)
- 桜井隆(2017).戦時下の日本語 日本語学,36(12),118-128.(CiNii Aritcles「日本語150年史」で知る)
- 佐竹秀雄(2017).国字政策と「書く」こと 日本語学,36(12),130-139.(CiNii Aritcles「日本語150年史」で知る)
- 遠藤織枝(2017).戦後、ことばの性差はどう変化したか 日本語学,36(12),140-153.(CiNii Aritcles「日本語150年史」で知る)
- 友定賢治(2017).方言の変容と復権 日本語学,36(12),154-163.(CiNii Aritcles「日本語150年史」で知る)
- 荻野綱男(2017).技術革新と日本語 日本語学,36(12),164-174.(CiNii Aritcles「日本語150年史」で知る)
- 西原鈴子(2017).日本語のグローバル化:インバウンド・アウトバウンドのその先へ 日本語学,36(12),176-186.(CiNii Aritcles「日本語150年史」で知る)
- 田鍋桂子(2017).言文一致会の活動と言文一致文 明海大学外国語学部論集,29,13-25.(CiNii Aritcles「言文一致」で知る)
- 野村剛史(2013).日本語スタンダードの歴史:ミヤコ言葉から言文一致まで 岩波書店(CiNii Aritcles「言文一致」で知る)
- 野村剛史(2019).日本語「標準形(スタンダード)」の歴史:話し言葉・書き言葉・表記 講談社(CiNii Aritcles「言文一致」で知る)
- 高野繁男(1990).言文一致理論の展開:明治期における日本語の「近代化」運動 人文学研究所報,23,1-14.(CiNii Aritcles「言文一致」で知る)
- 高野秀行・清水克行(2018).覆された標準語の通説:『日本語スタンダードの歴史』を読む[野村剛史著] Kotoba,31,170-175.(CiNii Aritcles「日本語スタンダードの歴史」で知る)
- 大木一夫(2015). 日本語の研究,11(1),60-66.[PDF](CiNii Aritcles「言文一致」で知る)
- 金澤裕之(2014).書評 野村剛史著『日本語スタンダードの歴史:ミヤコ言葉から言文一致まで』 国語と国文学,91(8),71-76.(CiNii Aritcles「言文一致」で知る)
- 田中ゆかり(2014).書評 『日本語スタンダードの歴史 ミヤコ言葉から言文一致まで』野村剛史著 Language information text,21,107-112.(CiNii Aritcles「言文一致」で知る)
- 吉田永弘(2019).転換する日本語文法 和泉書院(推量の助動詞「む」・条件表現・可能表現・尊敬表現・断定表現といった文法の変遷が相互に関連しながら起こっている様相を述べる;「学界展望 日本語の歴史的研究 2019年1月〜6月 (森 勇太)」で知る)
- 肥爪周二(2019).日本語音節構造史の研究 汲古書院(拗音・撥音・促音など日本語の音韻史に関する幅広い現象を体系的に説明;「学界展望 日本語の歴史的研究 2019年1月〜6月 (森 勇太)」で知る)
- 田中草大(2019).平安時代における変体漢文の研究 勉誠出版(和文・漢文との共通語彙や表記を比較;「学界展望 日本語の歴史的研究 2019年1月〜6月 (森 勇太)」で知る)
- 福島直恭(2019).訓読と漢語の歴史(ものがたり) 花鳥社(集団規範としての訓読文が歴史的にどのように展開してきたのかを扱う;「学界展望 日本語の歴史的研究 2019年1月〜6月 (森 勇太)」で知る)
- 犬飼隆(2019).木簡を日本語資料として利用する 国語と国文学,96(5),18-31.(CiNii Aritcles「日本語史料と日本語学史の研究」で知る)
- 小助川貞次(2019).訓点の信憑性について 国語と国文学,96(5),32-46.(CiNii Aritcles「日本語史料と日本語学史の研究」で知る)
- 木田章義(2019).抄物研究の視点 国語と国文学,96(5),47-61.(CiNii Aritcles「日本語史料と日本語学史の研究」で知る)
- 山東功(2019).近代文法用語の成立と学校国文法 国語と国文学,96(5),144-157.(CiNii Aritcles「日本語史料と日本語学史の研究」で知る)
- 内田賢徳・乾善彦(編)(2019).万葉仮名と平仮名 : その連続・不連続 三省堂(万葉仮名をくずしていくうちにできたとする通説を批判;「学界展望 日本語の歴史的研究 2019年1月〜6月 (森 勇太)」で知る)
- 岡村弘樹(2019).上代における自他対応と上二段活用 国語国文,88(8),22-42.(自動詞に偏る上二段活用動詞が自他対応形式を生み出さなかった理由を検討、;最も使用頻度の高い連用形が四段活用と形態的に重複するため;「学界展望 日本語の歴史的研究 2019年7月〜12月 (深津周太)」で知る)
- 釘貫亨(1996).古代日本語の形態変化 和泉書院(「学界展望 日本語の歴史的研究 2019年7月〜12月 (深津周太)」で知る)
- 屋名池誠(2019).続日本紀の「宣命書き」システム 藝文研究,(117),18-44.(「宣命書き」を三字種(表意表記の大字漢字/小字の万葉仮名/大字の万葉仮名)の書き分けの問題として捉えると続日本紀の「淳仁・称徳期」とそれ以外の「一般期」における様相は異なる;「学界展望 日本語の歴史的研究 2019年7月〜12月 (深津周太)」で知る)
- 吉田永弘(2019).転換する日本語文法 和泉書院(「学界展望 日本語の歴史的研究 2019年7月〜12月 (深津周太)」で知る)
- 小柳智一(2019).書評 吉田永弘著『転換する日本語文法』 國學院雜誌,120(10),16-20.(「学界展望 日本語の歴史的研究 2019年7月〜12月 (深津周太)」で知る)
- 小柳智一(2018).文法変化の研究 くろしお出版(「学界展望 日本語の歴史的研究 2019年7月〜12月 (深津周太)」で知る)
- 衣畑智秀(2019).書評論文 小柳智一著『文法変化の研究』(くろしお出版, 2018年) 日本語文法,19(2),135-143.(文法史研究の手本となりうる本書の考え方・論じ方を広く知らしめようとする;「学界展望 日本語の歴史的研究 2019年7月〜12月 (深津周太)」で知る)
- ナロックハイコ(2019).小柳智一著『文法変化の研究』 日本語の研究,15(2),118-126.[PDF](研究史に対する精緻な目配りの必要性を指摘;「学界展望 日本語の歴史的研究 2019年7月〜12月 (深津周太)」で知る)
- 青木博史(2019).補助動詞の文法化:「一方向性」をめぐって 日本語文法,19(2),18-34.(「学界展望 日本語の歴史的研究 2019年7月〜12月 (深津周太)」で知る)
- 金澤裕之・矢島正浩(編)(2019).SP盤落語レコードがひらく近代日本語研究 笠間書院(同時代の他資料との比較/近世語との異なり/語彙的特徴といった面から資料的価値を示す:「学界展望 日本語の歴史的研究 2019年7月〜12月 (深津周太)」で知る)
- 日本語学会(編)(2018).日本語学大辞典 東京堂出版(1955年版・1980年版の『国語学大辞典』をうけたものであるが単なる改訂にとどまらない;「学界展望 日本語の歴史的研究 2018年7月〜12月 (藤本真理子)」で知る)
- 沖森卓也(編)(2018).歴史言語学の射程 三省堂(「学界展望 日本語の歴史的研究 2018年7月〜12月 (藤本真理子)」で知る)
- 高山善行・青木博史・福田嘉一郎(編)(2018).日本語文法史研究4 ひつじ書房(「学界展望 日本語の歴史的研究 2018年7月〜12月 (藤本真理子)」で知る)
- 沖森卓也(2018).ことばの時代区分とは何か 日本語学,37(13),2-10.(CiNii Aritcles「日本語史の時代区分」で知る)
- 犬飼隆(2018).「奈良時代語」と平安時代語 日本語学,37(13),12-21.(CiNii Aritcles「日本語史の時代区分」で知る)
- 大木一夫(2018).日本語史をふたつにわけること 日本語学,37(13),22-31.(CiNii Aritcles「日本語史の時代区分」で知る)
- 矢島正浩(2018).条件表現史から見た近世:時代区分と東西差から浮かび上がるもの 日本語学,37(13),32-42.(CiNii Aritcles「日本語史の時代区分」で知る)
- 今野真二(2018).書きことばの史的変遷 日本語学,37(13),44-52.(CiNii Aritcles「日本語史の時代区分」で知る)
- 間淵洋子(2018).近代語から現代語へ:多様性許容の時代から画一性追求の時代へ 日本語学,37(13),54-64.(CiNii Aritcles「日本語史の時代区分」で知る)
- 高田博行・小野寺典子・青木博史(編)(2018).歴史語用論の方法 ひつじ書房(「学界展望 日本語の歴史的研究 2018年1月〜6月 (矢島正浩)」で知る)
- 服部義弘・児馬修(編)(2018).歴史言語学 朝倉書店(「学界展望 日本語の歴史的研究 2018年1月〜6月 (矢島正浩)」で知る)
- 大木一夫(2018).文法形式としての古代日本語補助動詞 訓点語と訓点資料,140,50-70.(古代では助動詞が担っていた文法的機能の多くを中世以降は補助動詞が代わっていくという“常識”に対して古代語の複合動詞後項も文法形式として機能していた部分に着目し切り直す;「学界展望 日本語の歴史的研究 2018年1月〜6月 (矢島正浩)」で知る)
- 小田勝(2018).読解のための古典文法教室:大学生・古典愛好家へ贈る 和泉書院(「学界展望 日本語の歴史的研究 2018年1月〜6月 (矢島正浩)」で知る)
[2020.9.11]ホームを更新
- 「サイトの管理者・経歴」欄の所属に「IR室」を追記。
[2020.9.7]IRなどについての文献メモ 文献一覧を更新<言語学>※「IRなどについての文献メモ」のページには追加せず
- 沖森卓也(2017).日本語全史 筑摩書房(Amazon.co.jp「日本語 歴史」で知る)
- 春日政治(著)・春日和男(編)(1982).假名發達史の研究 勉誠社(春日政治著作集第1冊)(沖森卓也(2017)『日本語全史』で知る)
- 金水敏(2002).日本語文法の歴史的研究における理論と記述 日本語文法,2(2),81-94.(Google Scholar「歴史言語学」で知る)
- 金水敏(2017).文法研究におけるデータについて:文法研究は経験科学たりうるか 日本語文法,17(2),54-63.(CiNii Articles「金水敏」で知る)
- 金水敏(2014).日本語史から見た語彙 語彙研究,11,1-9.(CiNii Articles「金水敏」で知る)
- 金水敏(2012).野村剛史著, 『話し言葉の日本史』, 2011年1月1日発行, 吉川弘文館刊, B6判, 240ページ, 1,700円+税 日本語の研究,8(4),70-74.[PDF](CiNii Articles「金水敏」で知る)
- 金水敏(2011).日本語史とは何か:言語を階層的な資源と見る立場から 早稲田日本語研究,20,3-10.[PDF](CiNii Articles「金水敏」で知る)
- 金水敏(2010).私が勧めるこの一冊(第13回)『助詞の歴史的研究』 石垣謙二【著】 日本語学,29(5),54-61.(CiNii Articles「金水敏」で知る)
- 金水敏(2005).日本語敬語の文法化と意味変化 日本語の研究,1(3),18-31.[PDF](CiNii Articles「金水敏」で知る)
- 山口仲美(2006).日本語の歴史 岩波書店(Amazon.co.jp「日本語 歴史」で知る)
- 田中牧郎(編)(2020).日本語の歴史 朝倉書店(Twitter(@AsakuraPubさん)で知る)
- 今野真二(2015).図説日本語の歴史 河出書房新社(Amazon.co.jp「日本語 歴史」で知る)
- 坂本勝(監修)(2009).図説地図とあらすじでわかる!古事記と日本書紀 青春出版社(Amazon.co.jp「古事記」で知る)
- 大堀壽夫(2004).文法化の広がりと問題点 言語,33(4),26-33.(CiNii Articles「文法化とはなにか--言語変化の謎を解く」で知る)
- 南部智史(2014).コーパス言語学および実験言語学に基づく格助詞交替の分析 博士論文(大阪大学大学院文学研究科) 大阪大学.[PDF](Google Scholar「歴史言語学」で知る)
- クリスタル,D.伊藤盡・藤井香子(訳)(2020).英文法には「意味」がある 大修館書店(Twitter(@editechさん)で知る)
- 井上和子(編)(1989).日本文法小事典 大修館書店(Amazon.co.jp「日本語 文法」で知る)
- 橋本陽介(2020).「文」とは何か:愉しい日本語文法のはなし 光文社(Amazon.co.jp「日本語 文法」で知る)
- オブラー,L.K.,&ジュァロー,K.若林茂則(監訳)・割田杏子(共訳)(2002).言語と脳:神経言語学入門 新曜社(Amazon.co.jp「神経言語学」で知る)
- 萩原裕子(1998).脳にいどむ言語学 岩波書店(Amazon.co.jp「神経言語学」で知る)
- 山鳥重(1985).神経心理学入門 医学書院(Amazon.co.jp「山鳥重」で知る)
- 山崎明夫(2016).にほんごがこんなふうにみえたのよ! QOLサービス(Amazon.co.jp「神経言語学」で知る)
- 小嶋知幸(編著)(2016).図解やさしくわかる言語聴覚障害 ナツメ社(Amazon.co.jp「日本語 文法」で知る)
[2020.9.7]IRなどについての文献メモ 文献一覧を更新<高等教育、大学改革>
- 佐藤郁哉(2019).大学改革の迷走 筑摩書房(Amazon.co.jpレコメンド機能で知る)
- 鳥飼玖美子・苅谷夏子・苅谷剛彦(2019).ことばの教育を問いなおす:国語・英語の現在と未来 筑摩書房(Amazon.co.jpレコメンド機能で知る)
- 隠岐さや香(2018).文系と理系はなぜ分かれたのか 星海社(Amazon.co.jpレコメンド機能で知る)
- 安藤寿康(2018).なぜヒトは学ぶのか:教育を生物学的に考える 講談社(Amazon.co.jpレコメンド機能で知る)
- 白川一郎・富士通総研経済研究所(編著)(2001).NPMによる自治体改革:日本型ニューパブリックマネジメントの展開 経済産業調査会(Amazon.co.jp「ニューパブリックマネジメント」で知る)
- 大住荘四郎(1999).ニュー・パブリック・マネジメント:理念・ビジョン・戦略 日本評論社(Amazon.co.jp「ニューパブリックマネジメント」で知る)
[2020.9.7]IRなどについての文献メモ 文献一覧を更新<FD、インストラクショナルデザイン>
- 向山洋一(2015).続・授業の腕を上げる法則 学芸みらい社(堀田ほか(2019)『“先生の先生"が集中討議』で知る)
- 若松俊介(2020).教師のいらない授業のつくり方 明治図書出版(Amazon.co.jpレコメンド機能で知る)
- 鈴木克明(2002).教材設計マニュアル:独学を支援するために 北大路書房(Amazon.co.jp「鈴木克明」で知る)
- 松田岳士・根本淳子・鈴木克明(編著)(2017).大学授業改善とインストラクショナルデザイン ミネルヴァ書房(Amazon.co.jpレコメンド機能で知る)
[2020.9.7]IRなどについての文献メモ 文献一覧を更新<データリテラシー>
- 田村秀(2006).データの罠:世論はこうしてつくられる 集英社(Amazon.co.jp「データリテラシー」で知る)
- ベスト,J.林大(訳)(2011).あやしい統計フィールドガイド:ニュースのウソの見抜き方 白揚社(Amazon.co.jpレコメンド機能で知る)
- 落合洋文(2010).サイエンス・ライティング練習帳 ナカニシヤ出版(Amazon.co.jpレコメンド機能で知る)
- 神永正博(2011).ウソを見破る統計学:退屈させない統計入門 講談社(Amazon.co.jpレコメンド機能で知る)
- 柴田里程(2001).データリテラシー 共立出版(溝上智恵子ほか(2019)「データリテラシーの論点整理」で知る)
- 田村秀(2019).データ・リテラシーの鍛え方:"思い込み"で社会が歪む イースト・プレス(Amazon.co.jpレコメンド機能で知る)
- 伊藤公一朗(2017).データ分析の力:因果関係に迫る思考法 光文社(Amazon.co.jpレコメンド機能で知る)
- ファクラー,M.(2020).データ・リテラシー:フェイクニュース時代を生き抜く 光文社(Amazon.co.jpレコメンド機能で知る)
[2020.9.7]IRなどについての文献メモ 文献一覧を更新<プレゼンテーション>
- 吉藤智広・渋谷雄大(2019).伝わるプレゼンの法則100 大和書房(Amazon.co.jpレコメンド機能で知る)
[2020.9.7]IRなどについての文献メモ 文献一覧を更新<クリティカルリーディング、アカデミックライティング>
- 大出敦(2015).クリティカル・リーディング入門:人文系のための読書レッスン 慶應義塾大学出版会(Amazon.co.jp「クリティカルリーディング」で知る)
- 小野田博一(2008).論理的に書く方法:説得力ある文章表現が身につく! PHP研究所(Amazon.co.jpレコメンド機能で知る)
- 小野田博一(2018).「論理的に考える力」を伸ばす50の方法 PHP研究所(Amazon.co.jpレコメンド機能で知る)
[2020.9.7]IRなどについての文献メモ 文献一覧を更新<思考法>
- アンド(2019).思考法図鑑:ひらめきを生む問題解決・アイデア発想のアプローチ60 翔泳社(Amazon.co.jp「論理的思考」で知る)
- ソニー・グローバルエデュケーション(2020).5分で論理的思考力ドリル 学研プラス(Amazon.co.jpレコメンド機能で知る)
- ソニー・グローバルエデュケーション(2019).5分で論理的思考力ドリル:ちょっとやさしめ 学研プラス(Amazon.co.jpレコメンド機能で知る)
- 渡辺健介(2007).世界一やさしい問題解決の授業 ダイヤモンド社(Amazon.co.jpレコメンド機能で知る)
- 読書猿(2017).問題解決大全:ビジネスや人生のハードルを乗り越える37のツール フォレスト出版(Amazon.co.jpレコメンド機能で知る)
- 秋田喜代美(2002).読む心・書く心:文章の心理学入門 北大路書房(Amazon.co.jpレコメンド機能で知る)
- 三森ゆりか(2013).大学生・社会人のための言語技術トレーニング 大修館書店(Amazon.co.jpレコメンド機能で知る)
- 松本茂(1996).頭を鍛えるディベート入門:発想と表現の技法 講談社(Amazon.co.jpレコメンド機能で知る)
- 西研・森下育彦(1997).「考える」ための小論文 筑摩書房(Amazon.co.jpレコメンド機能で知る)
- 渡辺健介(2018).世界一やさしい右脳型問題解決の授業 ダイヤモンド社(Amazon.co.jpレコメンド機能で知る)
[2020.9.7]IRなどについての文献メモ 文献一覧を更新<ICT教育>
- 水越敏行・久保田賢一(編著)(2008).ICT教育のデザイン 日本文教出版(Amazon.co.jp「情報教育」で知る)
- 中川一史・苑復傑(編著)(2017).教育のためのICT活用 放送大学教育振興会(Amazon.co.jpレコメンド機能で知る)
- 児玉晴男・小牧省三(編著)(2015).進化する情報社会 放送大学教育振興会(Amazon.co.jpレコメンド機能で知る)
- 学校広報ソーシャルメディア活用勉強会(2017).これからの「教育」の話をしよう2:教育改革×ICT力 インプレスR&D(Amazon.co.jpレコメンド機能で知る)
- 堀田龍也・赤坂真二・谷和樹・佐藤和紀(2019).“先生の先生"が集中討議!子どもも教師も元気になる「これからの教室」のつくりかた:教育技術・学級経営・ICT教育新しい時代のグランドデザイン 学芸みらい社(Amazon.co.jpレコメンド機能で知る)
- 堀田龍也(編著)(2020).PC1人1台時代の間違えない学校ICT 小学館(Amazon.co.jpレコメンド機能で知る)
- ライゲルース,C.M.,&カノップ,J.R.稲垣忠・中嶌康二・野田啓子・細井洋実・林向達(共訳)(2018).情報時代の学校をデザインする:学習者中心の教育に変える6つのアイデア 北大路書房(Amazon.co.jpレコメンド機能で知る)
- 堀田龍也・為田裕行・稲垣忠・佐藤靖泰・安藤明伸(2020).学校アップデート:情報化に対応した整備のための手引き さくら社(Amazon.co.jpレコメンド機能で知る)
[2020.9.7]IRなどについての文献メモ 文献一覧を更新<デザイン>
- 高橋佑磨・片山なつ(2016).伝わるデザインの基本:よい資料を作るためのレイアウトのルール 技術評論社(Amazon.co.jp「伝わるデザインの基本」で知る)
- 岸啓介(2017).一生使えるプレゼン上手の資料作成入門:説得力が劇的アップ インプレス(Amazon.co.jpレコメンド機能で知る)
- 宮城信一(2019).「デザイン」の力で人を動かす!プレゼン資料作成「超」授業:プレゼン上手に明日からなれる SBクリエイティブ(Amazon.co.jpレコメンド機能で知る)
- 藤俊久仁・渡部良一(2019).データビジュアライゼーションの教科書 秀和システム(Amazon.co.jpレコメンド機能で知る)
[2020.9.1]ホーム「お知らせ」欄、「過去の「お知らせ」」、「IRなどについての文献メモ」、「これまでの発表・競争的研究資金など」に追加
- 「IR担当者の専門性と執行部の期待:公立大学の聞き取り調査を中心に」(日本教育情報学会第36回年会)論文集の掲載ページ数を追記
[2020.5.30]ホーム「お知らせ」欄、「過去の「お知らせ」」、「IRなどについての文献メモ」、「これまでの発表・競争的研究資金など」に追加
- 「IR担当者の専門性と執行部の期待:訪問調査に基づく類型化」(大学教育学会第42回大会)要旨集の掲載ページ数を追記
- ポスター発表"Bridging executives' expectations and institutional researchers' expertise"(2020 AIR Forum)採択されたが大会中止の旨を記載
[2020.5.19]大学に関わる情報メモ 内容をアップ
[2020.5.18]大学に関わる情報メモ 内容をアップ
[2020.5.17]ホーム「お知らせ」欄に追加
- 「IR担当者の専門性と執行部の期待:公立大学の聞き取り調査を中心に」(日本教育情報学会第36回年会、現地開催は中止、年会論文集を発行)を掲載
[2020.5.1]ホーム「お知らせ」欄に追加
- ポスター発表"Bridging executives' expectations and institutional researchers' expertise"(2020 AIR Forum)、大会中止とAIR Forum Virtualを追記
[2020.4.24]ホーム「お知らせ」欄に追加
- 「IR担当者の専門性と執行部の期待:訪問調査に基づく類型化」(大学教育学会第42回大会)の記載を変更(口頭発表中止、要旨集への記載のみ)
[2020.4.9]IRなどについての文献メモ 文献一覧を更新<WebClass、遠隔授業>
- 倉澤寿之(2019).WebClass類似レポート検知機能の検証 白梅学園大学・短期大学情報教育研究,22,25-30.[PDF](類似度を加工した模擬レポートを作成して「類似レポート検知」機能の有効性を検証、全般に「控えめな」判定であった、スコアが40程度以上あるレポートのペアが見つかった場合には見比べる必要がある、前段階のチェックとして実用性がある;CiNii Articles「WebClass」で知る)
- 長瀧寛之(2019).岡山大学におけるWebClassからMoodleへの学習管理システム移行 情報教育シンポジウム論文集,2018(39),256-262.[PDF](LMSの移行の背景・経緯・移行後に発生した課題や解決アプローチなどを報告;CiNii Articles「WebClass」で知る)
- 石田弘隆・西澤由輔(2018).数学科目におけるWebclassを用いたCBTの実施 宇部工業高等専門学校研究報告,64,19-25.[PDF](低学年数学教育において従来型の筆記による小テストの代わりとして実施、科目のルーブリックにおける最低限の到達レベルおよび標準的な到達レベルの内容を復習することができる教材を作成;CiNii Articles「WebClass」で知る)
- 瀧端真理子(2018).WebClassを用いた授業改善の試みと今後の展望 コンピュータ&エデュケーション,44,31-35.[PDF](博物館学芸員の資格取得に必要な授業科目での実践例、●写真や動画を閲覧する授業:写真や動画(YouTubeへのリンク掲載あり)を閲覧、チャット欄に意見・質問・感想を書く、それらの共有、教員はコメント書く、保存されるため欠席学生も後から閲覧・書き込み可能、●法制度を学ぶ授業(内容が難しく範囲も膨大):政府統計を使いエクセルで計算演習(各種統計へのリンクを掲載、レポート提出時に作成したエクセルも提出)、市町村合併に伴う事業(必要度の高い順に選択、順序の理由をチャットに記入、意見共有)、●学生の発表:受講生はWordで作成したレジュメを提出、発表者は順番に前に出てきて教員用PCを使って投影・発表、他の学生は意見や質問をチャット欄に記入(従来の授業形式での特定学生しか発言しない問題を回避できる)、発表者は随時口頭で回答、●成績評価:紙媒体の記述式筆記試験の採点結果をWebClassで返却、レポートの点数表示やコメントをつける機能はあるが膨大な時間と手間がかかるため実現できていない;CiNii Articles「WebClass」で知る)
- 濱田陽(2017).WebClassを利用した英語教育の取り組み 秋田大学教養基礎教育研究年報,19,13-18.[PDF](英語教育の授業でどのように使用しどのようなメリットが見られたかを報告する、複雑な使用をしなくとも基本的な機能だけで効果的な教育の展開ができた、学生の「時間外学修」を促進し効率化(回収・提出チェック・点数入力など)により時間の捻出ができる、予習・授業・復習のサイクルを自然に生み出す(高校では課題の出し方や学習方法まで丁寧に「レール」を敷いて指導をしてきていると感じている、大学に入って突然自主性を強調しても対応しきれないか可能性がある)、●担当授業(1年生の「英語特別演習」「文系英会話」)での実践例:学習用スペースで自分の弱い分野を学習する、取り組んだことを英語でまとめて授業前までにアップロード、教員は受講生全員の提出状況・提出日時を一覧で確認できる、「資料」(さらに詳しく学習したい学生のためのサイト紹介等)の利用状況が「学習履歴」で把握できる、「学生としてログインする」機能が学生への説明のために便利、学生のページには課題ごとに自己評価・相互評価・教員評価の欄があり活用が可能、●基本機能以外の機能:成績管理、アンケート集計(一度作成しておけば次年度も利用できる);CiNii Articles「WebClass」で知る)
- 倉田香織・宮川毅・森河良太・土橋朗(2017).アクティブラーニング実践に向けたLMSの有効活用 東京薬科大学研究紀要,20,43-50.[PDF](多くの科目でPPTスライドデータを事前に配布、学生は板書(カメラ撮影)の代わりにて「考える」時間を持てるようになった、PCの基本操作の学習では動画とPDFによる手順書を提供(教材の単位をできるだけ小さくして作成)、LMSでのレポート提出は作成した電子ファイルを登録することが最終目的にすり変わりやすい、提出画面に感想文・ポートフォリオ・ルーブリック評価の入力を用意、課題の採点結果を返却した後の再提出を認めた、出席点・課題点などは公開して学習成果の可視化につなげた、ポートフォリオ機能を活用(チーム内で各自の作業内容を共有、発表会の前にグループ内でルーブリック表を用いた評価、分担以外の内容がわからないという問題を避ける)、知識に関するトレーニング問題をLMSで共有(単位を修得後も利用できる);CiNii Articles「WebClass」で知る)
- 矢田範夫・上藤千佳・平山晴子・樅木勝巳(2016).e-learning システムを用いた動物実験教育訓練知識確認テスト 岡山実験動物研究会報,32,33-36.[PDF](試験の設問と解答例を掲載;CiNii Articles「WebClass」で知る)
- 土橋和之(2016).ウェブクラス予習課題導入による授業改善 崇城大学紀要,41,173-178.[PDF](オンラインの予習課題および授業資料配布を行った、学生の評価は概ね好評であった、学生たちは自宅におけるPCと外出先・学校におけるスマートフォンを使い分けて予習・復習を行っていた;CiNii Articles「WebClass」で知る)
- 前田昭彦(2015).クラウド型授業支援サービス「WebClass」を用いた学生のゼミ振り分け方法 都留文科大學研究紀要,81,85-96.[PDF](約2か月の間にゼミの志望投票を5回実施、具体的な実施手順を紹介;CiNii Articles「WebClass」で知る)
- 秋場勝彦(2013).青山スタンダード「経済学A」でWebClassを活用して 青山スタンダード論集,8,15-25.[PDF](チャット機能の活用事例、受講生120名、リアルタイムに書き込んだ内容が反映される、●5種類の事例:質問・意見・気になること・授業の進行状況・気軽なチャット(雑談)、●学生からの指摘を踏まえた改善点:教室のネットワーク環境環境(学生の通信料)、匿名での参加を可能にする;CiNii Articles「WebClass」で知る)
- 永田奈央美・大石義(2013).e-Learningの実験的運用とその効果:WebClassとMoodleの比較分析を通して 静岡産業大学情報学部研究紀要,15,83-93.[PDF](機能比較、WebClassは学習管理機能(進捗状況・出席状況・確認問題の得点)が充実、Moodleはコミュニケーション機能が充実;CiNii Articles「WebClass」で知る)
- 丸田英徳(2011).長崎大学でのWebClass運用実績について 長崎大学情報メディア基盤センターレポート,2010 (2010),42-47.[PDF](学内でeラーニング普及のについてアンケート調査を実施、学生のスキルは問題視されておらず教員のスキルの問題が重視されていた、そこで導入時に教職員向けハンズオン研修会を推進する方針とした、統計情報を用いた利用状況の推移を報告;CiNii Articles「WebClass」で知る)
- 渡邊光太郎(2011).コンピュータリテラシーにおけるWebClassの活用 城西情報科学研究,21(1),19-36.[PDF](コンピュータリテラシーの毎回の講義でExcelの課題を提供、次回講義までに採点してメッセージをフィードバックとして送信した;CiNii Articles「WebClass」で知る)
- 渡邊光太郎(2011).資格対応科目におけるWebClassの活用 城西情報科学研究,21(1),7-18.[PDF](ITパスポート試験に対応した講義において用語の確認・学習内容の確認・試験対策問題を提供;CiNii Articles「WebClass」で知る)
- 中田友一・山本茂義・小川秀司(2011).e-LearningシステムWebClass導入で見えてきたもの:グローバル戦略としての大学教育 国際教養学部論叢,4(1),1-13.[PDF](統計学、生物学、基礎ゼミ、コンピューター処理論の各授業での実践例を具体的に紹介;CiNii Articles「WebClass」で知る)
- 曽山典子(2005).教育実践報告:基礎ゼミナールにおけるWebClassの利用 総合教育研究センター紀要,4,38-57.[PDF](各種機能の利用例と利点の紹介、;CiNii Articles「WebClass」で知る)
- 曽山典子(2003).教育実践報告:e-Learningシステム(WebClass)の利用方法 総合教育研究センター紀要,2,50-64.[PDF](各種機能の説明;CiNii Articles「WebClass」で知る)
[2020.4.8]IRなどについての文献メモ 文献一覧を更新<Google Classroom、遠隔授業>
- 中田美喜子(2020).Google Classroomを利用した講義の進め方 広島女学院大学人文学部紀要,1,1-10.[PDF](広島女学院大学においてGoogle ClassroomなどのICTを用いて講義を実施している実情を報告;CiNii Articles「Google Classroom」で知る)
- ウンサーシュッツ,G.(2019).反転授業に向けた準備:インターネット上の課題の作成と実用 立正大学心理学研究所紀要,17,35-41.[PDF](筆者が施行した英語授業における反転授業の試みを概説、Google Formsを用いたビデオ課題を作成、実際に出遭った問題点も振り返る;CiNii Articles「Google Classroom」で知る)
- 山川純次(2019).教育ITシステムとしてのGoogle classroomとChromebook 岡山大学教師教育開発センター紀要,9,1-12.[PDF](低コストで導入と運用ができる、スマホ・ネイティブ世代の情報処理能力をスムースに拡張することができる;CiNii Articles「Google Classroom」で知る)
- 松本宗久・落合俊郎(2019).LMS(Learning Management System)を活用した,多人数講義におけるActive Learningの推進及び事務処理の省力化について 大和大学研究紀要,5,45-49.[PDF](大学の多人数講義においてGoogle Classroomを活用した実践(効果・課題・展望)について報告;CiNii Articles「Google Classroom」で知る)
- 内野秀哲・相場徹(2019).アクティブ・ラーニングを意図したICT活用研究:Google Classroomの導入 仙台大学紀要,50(2),9-16.[PDF](担当授業科目(情報処理)でアプリケーションをサイボウズLiveからGoogle Classroomに変更した内容を報告、機能比較による選定、運用、受講生に対する質問紙調査(有効データ394名)の結果;CiNii Articles「Google Classroom」で知る)
- 菊地直子・内野秀哲(2019).大学の大人数授業におけるアクティブ・ラーニングを意図した「Google Classroom」の活用 仙台大学紀要,50(2),1-7.[PDF](Google Classroomを試験的に導入し効果を検証、1クラス250名程度の必修科目「スポーツ心理学」で実施、大人数授業においても学生が主体的に学ぶことを促進させるツールであることが示唆された、学生教員ともに負担が激減した、受講動機がネガティブであった学生にとっても取り組みやすい;CiNii Articles「Google Classroom」で知る)
- Hulse, R.(2019). The Use and Implementation of Google Classroom in a Japanese University. The Centre for the Study of English Language Teaching journal, 7, 71-105.[PDF](アプリケーションに対する評価について女子大学の学生70名を対象にアンケート調査、設問は21、結果は概ね好評であった;CiNii Articles「Google Classroom」で知る)
- 藤澤宜広(2018).経済学教育におけるICTの活用についての考察:沖縄大学におけるペア・デックとグーグル・クラスルームの比較・活用 沖縄大学法経学部紀要,29,1-15.[PDF](Google Trendsを用いて2013年~2018年の認知度を比較、筆者が担当する授業での活用状況を比較、ペア・デックは中規模(40名以上80名未満)から大規模(80名以上)クラスにおいて有用、グーグル・クラスルームについては、小規模(40名未満)において特に有用(中・大規模クラスにおいても利用は可能であるが課題配布・回収・添削や学生との個別のやりとりで運用コストが発生しやすい)、導入のメリット・デメリットの表を掲載;CiNii Articles「Google Classroom」で知る)
- 檀裕也(2018).能動的に学ぶマルチメディアプログラミングの授業デザインについて 第80回全国大会講演論文集,2018(1),411-412.[PDF](マルチメディアの表現と技術について実践的に学ぶ「マルチメディア演習」で実践、講義資料の提示や実習課題の提出および評価で活用;CiNii Articles「Google Classroom」で知る)
- 鈴木寛(2018).講義のロードマップ提示のための新しいGoogleサイトの使い方:Google Classroomなどとの連携も含め 八戸工業大学紀要,37,217-231.[PDF](シラバスより詳しい講義のロードマップ公開のための新しいGoogleサイトの使い方を概説;CiNii Articles「Google Classroom」で知る)
- 山本淳子・大場浩正(2018).日本人EFL大学生の動機付け向上を目指したブレンド型授業におけるe-ラーニングの効果:自己決定理論に基づいて 日本教科教育学会誌,41(2),27-40.[PDF](オンライン学習と対面授業を組み合わせたブレンド型授業を展開した、介入群と統制群で動機付け質問紙調査の前後差を比較;CiNii Articles「Google Classroom」で知る)
- 山岡真理(2017).授業におけるGoogle Classroomの活用に関する一考察 文化ファッション大学院大学紀要論文集ファッションビジネス研究,5,36-43.[PDF](授業内で実験的にパイロット運用し学生と教員の使用実感の検討を行った、検討した5項目:出欠・課題の一元化/通常授業で配布する資料のペーパーレス化/準備資料用のUSB・外部メモリレス化/情報システムとしての一括活用/学生の主体的な授業への参加;CiNii Articles「Google Classroom」で知る)
- 倉掛崇(2017).クラウド型学習管理システムGoogle Classroomを活用した授業実践 日本福祉大学全学教育センター紀要,5,125-134.[PDF](「心理データ処理演習」での授業実践、機能の可能性と課題を議論;CiNii Articles「Google Classroom」で知る)
- 鈴木寛(2017).Googleドライブのアプリおよびそのアドオンを用いた課題の作成:ルーブリックと自動採点・返却 八戸工業大学紀要,36,67-81.[PDF](CiNii Articles「Google Classroom」で知る)
- 田中義幸(2017).アクティブラーニングとe-ラーニングの導入による基礎化学科目の活性化 八戸工業大学紀要,36,205-209.[PDF](1年生対象の一連の基礎化学科目(前期受講生約50名、後期同20名)での実践事例、Google Formsで作成した選択式の問題をGoogle Classroomを通じて受講生に基本的に毎週公開、学生は講義前日の深夜までに回答、できるだけ教科書に触れる機会が増えるような出題を心がけた、選択式の問題については回答送信直後に得点・正解が配信されるよう設定、計算過程も重視して評価すべき文章題などではレポート用紙に手書きで回答させ講義開始時に回収;CiNii Articles「Google Classroom」で知る)
- 鈴木寛(2016).Google Classroomでできること 八戸工業大学紀要,35,107-120.[PDF](2014年に一般公開されてから1年間使用してきた経験に基づきGoogle Classroomでできることを事例を交えて紹介、スクリーンショットを多用しながら基本的な機能を説明;CiNii Articles「Google Classroom」で知る)
- 福井恵子・鵜川義弘・上山由果(2016).Google Classroomを活用した授業の提案 宮城教育大学情報処理センター研究紀要:COMMUE,23,57-62.[PDF](筆者所属大学(宮城教育大学)において学習を支援する教育クラウドとして活用できるかという可能性をMoodleとの比較を通して評価;CiNii Articles「Google Classroom」で知る)
- 山口直木(2018).Google Classroomを用いた授業管理の利点と問題点 研究紀要,70,1-11.[PDF](「経営システム工学」、「情報基礎演習」、ゼミナール(「基礎演習Ⅰ」、「演習Ⅲ」)で授業管理(特にレポートの提出の管理)を行った、その結果から利点と問題点を検討;CiNii Articles「Google Classroom」で知る)
[2020.4.7]IRなどについての文献メモ 文献一覧を更新<授業評価アンケート、自由記述>
- 松河秀哉・大山牧子・根岸千悠・新居佳子・岩﨑千晶・堀田博史(2018).トピックモデルを用いた授業評価アンケートの自由記述の分析 日本教育工学会論文誌,41(3),233-244.[PDF]
- 松河秀哉・大山牧子・根岸千悠・新居佳子・岩﨑千晶・堀田博史・串本剛・川面きよ・杉本和弘(2018).トピックモデルによるテキスト分析を支援するソフトウエアの開発 日本教育工学会論文誌,42(Suppl.),037-040.[PDF]
[2020.4.1]大学に関わる情報メモ リンクを修正
- 教学マネジメント特別委員会(第1~10回)議事録のリンクを修正(文部科学省サイトの常時暗号化によるURL変更)
- 大学分科会(第140回)・将来構想部会(第9期~)(第14回)合同会議議事録のリンクを修正(文部科学省サイトの常時暗号化によるURL変更)
[2020.4.1]ホーム
- 所属変更(四天王寺大学から大阪市立大学)に伴い、「このサイトの紹介」欄の記載を変更
[2020.3.20]「過去の「お知らせ」」、「IRなどについての文献メモ」、「これまでの発表・競争的研究資金など」に追加
- ポスター発表「IRは大学の期待に応えられているのか:小規模大学におけるヒアリング調査を通じて」(第26回大学教育研究フォーラム)
[2020.3.19]大学に関わる情報メモ 内容をアップ
[2020.3.18]ホーム「お知らせ」欄に追加
- 科研費採択のお知らせにKAKEN(科学研究費助成事業データベース)へのリンクを追加
[2020.3.16]ホーム「お知らせ」欄に追加
- 口頭発表「IR担当者の専門性と執行部の期待:訪問調査に基づく類型化」(大学教育学会第42回大会)を掲載
[2020.3.16]IRなどについての文献メモ 文献一覧を更新、内容をアップ<反転授業>
- 森朋子(2017).平成28年度第3回FDセミナー:アクティブラーニングとしての反転授業を考える 学士課程教育機構研究誌,6,65-78.[PDF][概要](CiNii Articles「反転授業」で知る)
- 森朋子 (2017) .「わかったつもり」を「わかった」へ導く反転授業の学び 森朋子・溝上慎一(編)アクティブラーニング型授業としての反転授業[理論編] ナカニシヤ出版 pp.19-35.[概要](澁川ら(2019)「反転授業におけるワークシートの利用が対面授業時の学びへ与える影響」で知る)
- 中川潔美・平良美栄子(2016).大学教育における反転授業の実践に関する文献検討 朝日大学保健医療学部看護学科紀要,2,7-13.[PDF][概要](CiNii Articles「反転授業」で知る)
- 土屋耕治(2018).ラーニングピラミッドの誤謬:モデルの変遷と"神話"の終焉へ向けて 人間関係研究,17,55-73.[PDF][概要](佐藤(2019)「反転授業とe-ラーニングを基礎にした大学教育の標準化構想」で知る)
- 三保紀裕・本田周二・森朋子・溝上慎一(2017).反転授業における予習の仕方とアクティブラーニングの関連 日本教育工学会論文誌,40(Suppl.),161-164.[PDF][概要](CiNii Articles「反転授業」で知る)
- 大内俊二・高遠節夫(2018).自習・反転授業のための音声つきPDF教材の開発 数理解析研究所講究録,2067,183-189.[PDF][概要](CiNii Articles「反転授業」で知る)
- 河津祐之介・堤厚博(2018).反転授業効果の定量的評価の試み 工学教育,66(3),3_88-3_91.[PDF][概要](CiNii Articles「反転授業効果の定量的評価の試み」で知る)
- 松下佳代 (2015) .ディープ・アクティブラーニングへの誘い 松下佳代・京都大学高等教育研究開発推進センター(編) ディープ・アクティブラーニング 勁草書房 pp.1-27.[概要](澁川ら(2019)「反転授業におけるワークシートの利用が対面授業時の学びへ与える影響」で知る)
- 小川勤(2015).反転授業の有効性と課題に関する研究:大学における反転授業の可能性と課題 大学教育,12,1-9.[PDF][概要](大内・高遠(2018)「自習・反転授業のための音声つきPDF教材の開発」で知る)
- 山里敬也(2018).ビデオ教材等を利用しない反転授業でも学習効果があるのか?:貧乏人の反転授業の評価と考察 名古屋高等教育研究,18,267-279.[PDF][概要](CiNii Articles「反転授業」で知る)
- 山里敬也(2016).貧乏人の反転授業 名古屋高等教育研究,16,23-38.[PDF](山里(2018)「ビデオ教材等を利用しない反転授業でも学習効果があるのか?」で知る)
- 稲垣忠・佐藤靖泰(2015).家庭における視聴ログとノート作成に着目した反転授業の分析 日本教育工学会論文誌,39(2),97-105.[PDF][概要](澁川ら(2019)「反転授業におけるワークシートの利用が対面授業時の学びへ与える影響」で知る)
- 小川健(2019).そして誰もいなくなる:学生に嫌がられる動画・音声資料 情報教育シンポジウム論文集,2019,331-335.[PDF][概要](CiNii Articles「反転授業」で知る)
- 中原正樹(2018).大人数を対象とした参加型オリエンテーションの試み 高等教育フォーラム,8,79-85.[PDF][概要](CiNii Articles「反転授業」で知る)
- 上村英男・藤井厚紀(2018).学びのユニバーサルデザイン(UDL)に基づいた授業実践:反転授業の事前学習用コンテンツに着目して コンピュータ&エデュケーション,45,55-60.[PDF][概要](CiNii Articles「反転授業」で知る)
- 金西計英(2019).反転授業における深い学びの検討 徳島大学大学開放実践センター紀要,28,25-33.[PDF][概要](CiNii Articles「反転授業」で知る)
- 水谷元紀(2018).反転授業における予習に対する学生の意識:反転授業受講学生を対象とした意識調査結果 工学教育研究講演会講演論文集,2018,84-85.[PDF][概要](CiNii Articles「反転授業」で知る)
- 佐藤広志(2019).反転授業とe-ラーニングを基礎にした大学教育の標準化構想 研究紀要,20,137-148.[PDF][概要](CiNii Articles「反転授業」で知る)
- 梅澤克之・石田崇・中澤真・平澤茂一(2018).グループ分け反転授業の実授業への適用について 経営情報学会全国研究発表大会要旨集,2018t06,35-38.[PDF][概要](CiNii Articles「反転授業」で知る)
- 澁川幸加・田口真奈・西岡貞一(2019).反転授業におけるワークシートの利用が対面授業時の学びへ与える影響:対面授業時の発話内容と深い学習アプローチに着目して 教育メディア研究,26(1),1-19.[PDF][概要](CiNii Articles「反転授業」で知る)
- 天野由貴・隅谷孝洋・長登康・稲垣知宏(2018).「大学教育入門」における反転授業の実践:講義動画視聴記録とオンラインテスト受験記録の分析 大学ICT推進協議会年次大会論文集,2018.[PDF][概要](CiNii Articles「プレゼンテーション」で知る)(CiNii Articles「反転授業」で知る)
- 永田奈央美(2017).反転授業における対人認知構造図の抽出 情報システム学会全国大会論文集,13,c22.[PDF][概要](CiNii Articles「反転授業」で知る)
- 宗村広昭・鹿住大助・小俣光司(2017).反転授業における講義ビデオの視聴行動と成績との関係性 日本教育工学会論文誌,40(Suppl.),9-12.[PDF][概要](田川・徳田(2018)「初年次教育での文章作成における反転授業の導入と効果の検討」で知る)
- 長瀧寛之(2018).ぺた語義:情報リテラシー授業における反転授業の実践 情報処理,59(8),738-741.[PDF][概要](CiNii Articles「反転授業」で知る)
- 田川麻央・徳田恵(2018).初年次教育での文章作成における反転授業の導入と効果の検討 言語文化硏究,1,51-58.[PDF][概要](CiNii Articles「反転授業」で知る)
- 小野功一郎(2017).オンライン学習と対面型授業によるブレンド学習の研究・開発:反転授業を組み合わせたアクティブ・ラーニングの取り組み 大和大学研究紀要,3,57-66.[PDF][概要](CiNii Articles「反転授業」で知る)
- Rose, D. H., & Meyer, A. with Strangman, N., & Rappolt, G. (2002). Teaching every student in the digital age: Universal design for learning. Alexandria, Va.: Association for Supervision and Curriculum Development.[概要](上村・藤井(2018)「学びのユニバーサルデザイン(UDL)に基づいた授業実践」で知る)
- 大山牧子・根岸千悠・山口和也(2016).学生の理解を深める反転授業の授業デザインの特徴:大学における化学の授業を事例に 大阪大学高等教育研究,4,15-24.[PDF][概要](澁川ら(2019)「反転授業におけるワークシートの利用が対面授業時の学びへ与える影響」で知る)
- 山下祐一郎・中島平(2016).プレゼンテーション型アクティブラーニングの実践に関する検討:教員養成課程の学生を対象とした予備実験 教育情報学研究,15,1-7.[PDF][概要](CiNii Articles「プレゼンテーション」で知る)(大内・高遠(2018)「自習・反転授業のための音声つきPDF教材の開発」で知る)
- 金沢緑・加藤明・山本博和・大和田智文(2018).ブレンド型反転授業が大学生の学びに及ぼす影響 関西福祉大学研究紀要,21, 41-50.[PDF](CiNii Articles「反転授業」で知る)
- 加藤研太郎・高島恵(2019).基礎科目に対する反転授業の効果 理学療法:臨床・研究・教育,26(1),29-35.[PDF](CiNii Articles「反転授業」で知る)
- 河津祐之介・堤厚博(2019).反転授業効果の定量的評価の試み(3):反転授業の効果の検証 工学教育研究講演会講演論文集,2019,290-291.[PDF](CiNii Articles「反転授業効果の定量的評価の試み」で知る)
- 黒田嘉宏(2016).初めての反転授業入門実践編 大阪大学ファカルティ・ディベロップメント(FD)フォーラム報告書,27,85-132.[PDF](CiNii Articles「反転授業」で知る)
- 沖林洋平・宮木秀雄・長友義彦・佐伯英人・岡村吉永(2019).反転授業が授業内容の理解に及ぼす影響:学習アプローチとエンゲージメントと授業理解の関連 教育実践総合センター研究紀要,47,143-151.(CiNii Articles「反転授業」で知る)
- 大谷千恵・田丸恵理子・河野功幸・根津幸徳・池田敦(2017).文系授業における反転授業の事例研究:ブレンド型授業におけるディスカッションと学び合い 論叢:玉川大学教育学部紀要,17,117-142.[PDF](小川(2019)「そして誰もいなくなる:学生に嫌がられる動画・音声資料」で知る)
- 田口真奈・後藤崇志・毛利隆夫(2019).グローバルMOOC を用いた反転授業の事例研究:日本人学生を想定した授業デザインと学生の取り組みの個人差 日本教育工学会論文誌,42(3),255-269.[PDF](CiNii Articles「反転授業」で知る)
[2020.3.8]IRなどについての文献メモ 内容をアップ
- 田島貴裕・大津晶(2018).コミュニケーションを重視した大規模講義向けアクティブラーニング手法の開発 コンピュータ&エデュケーション,45,103-108.[PDF][概要](Google Scholar「"大人数" 反転授業」で知る)
- 岩崎公弥子・大橋陽(2015).反転授業を導入したアクティブラーニングの取り組み コンピュータ&エデュケーション,39,98-103.[PDF](中規模クラスLMSを活用した反転授業を導入、授業時間内にグループワークの時間を十分に確保できた、専門知識に基づくアクティブラーニングが実現可能と報告、■検証すること:①深い学びを促すグループアクティビティ、②予習動画を閲覧させる工夫、③ナレーションに人の声と合成音声を使うのとでは学習意欲・理解度に違いがあるか、■授業:金城学院大学の「国際情報概論」(1年生必修、知識修得・eラーニング活用・授業外学習の習慣化を目的とした初年次教育科目、現代社会と女性をテーマとした授業、3つの領域(3名の教員がそれぞれ担当)について各3回講義(90分×3回×3名))、約200名の学生が3つのクラスに分かれる、■環境:Wi-Fi接続が可能、1人1台PC持参、manaba、■課題:①毎回授業終了後にコメントシートを課す、学生は次回授業までにmanabaに提出、各領域の最後(3回目)に小レポートを課す、学生は期日までにmanabaに提出、■反転授業を導入した領域:3つの領域のうちの1つ「情報デザイン」、■授業の流れ:講義(1回目)→予習動画→講義(2回目)→予習動画→講義(3回目)、■授業(2回目)の時間配分:[5分]前回の振り返り、[10分]動画教材に関する質疑応答、[50分]グループワーク(ワークシート、manabaへのアップロード)、[10分]各グループのワークシートに基づく意見交換、[15分]まとめと振り返り、■予習動画のデザイン」:長さは7~8分、YouTubeで配信、スライドにナレーションを入れた形式(①担当教員の肉声/②合成音声)、動画とは別にリンク集を用意、動画閲覧を促すために動画の途中にコメントシートの課題を入れた、1つの動画を4分程度のトピックに分けて負担なく視聴できるようにした、■授業アンケートによる評価:有効回答数は189、反転授業に関する項目は高い評価結果であった、自由記述も肯定的な意見が多かった(160/167名)、否定的な意見(7/167名)ではグループワークに対する記述(「やる気のない人がいるとそれはそれで進まなくなってしまうので困る。」など)があった、話の中に入っていくことができない学生が1割程度いたため教員が個別に声かけをしてグループの議論へと誘導した、■予習動画の閲覧率:98.7%、予習動画の中で出題した課題(コメントシート)の提出状況と授業の出席から算出、■予習動画の閲覧環境についてのアンケート結果(有効回答数189):[場所]自宅(75%)>大学内(22%)>電車内(2%)、[環境]MacPC(84%)>WindowsPC(7%)>iPhone(7%)、[閲覧時間]:動画1(7分37秒)と動画2(8分25秒)について両者とも10分程度が最多(全体の約40%)、[動画の長さ(5段階で評価)]:「ちょうどよかった」(78%)>「長く感じた」(22%)、[肉声/合成音声の評価]:肉声の評価が高かった(「先生の声の方が集中してできた。」「機械の声は抑揚がなくて,なんだか眠たくなるような気持ちでした。発音が少し違うとそっちに気が入ってしまい,聞き直しなどもしました。」)、一方で合成音声を好む学生も1割程度いた、■まとめ:予習動画は短くまとめた方が良い(バーグマンが15分以内が最適であると述べている)、肉声/合成音声は両方に対応できるデザインにしていきたい、予習動画のなかに宿題の課題を含ませておくことが高い閲覧率につながったと考えられる、;田島・大津(2018)「コミュニケーションを重視した大規模講義向けアクティブラーニング手法の開発」で知る)
[2020.3.7]IRなどについての文献メモ 文献一覧を更新<反転授業>
- 岩崎公弥子・大橋陽(2015).反転授業を導入したアクティブラーニングの取り組み コンピュータ&エデュケーション,39,98-103.[PDF](田島・大津(2018)「コミュニケーションを重視した大規模講義向けアクティブラーニング手法の開発」で知る)
[2020.3.7]IRなどについての文献メモ 文献一覧を更新<反転授業>
- 田島貴裕・大津晶(2018).コミュニケーションを重視した大規模講義向けアクティブラーニング手法の開発 コンピュータ&エデュケーション,45,103-108.[PDF](Google Scholar「"大人数" 反転授業」で知る)
- 大山牧子・根岸千悠・山口和也(2016).学生の理解を深める反転授業の授業デザインの特徴:大学における化学の授業を事例に 大阪大学高等教育研究,4,15-24.[PDF](Google Scholar「"大人数" 反転授業」で知る)
- 岩野雅子(2015).学生の主体的な学びを促進する授業マネジメントに向けて:普通教室で行うアクティブラーニング 山口県立大学学術情報,8,19-27.[PDF](Google Scholar「"大人数" 反転授業」で知る)
- 島田英昭(2018).eラーニングとグループディスカッションを取り入れたマスプロ授業のアクティブ化:改善報告 日本デジタル教科書学会発表予稿集,7,37-38.[PDF](Google Scholar「"大人数" 反転授業」で知る)
- 中越元子・野原幸男・林正彦・川口基一郎・山崎洋次(2014).チーム基盤型学習(TBL)と問題基盤型学習(PBL)を統合した授業「プレゼンテーション」の実践 京都大学高等教育研究,20,17-29.[PDF](Google Scholar「"大人数" 反転授業」で知る)
- 駒崎俊剛(2015).学習管理システムとワークショップを組み合わせた授業設計の試行 東京医療保健大学紀要,10(1),63-68.[PDF](Google Scholar「"大人数" 反転授業」で知る)
- 山口和也・大山牧子(2017).大学におけるアクティブ・ラーニングの動向 高大連携物理教育セミナー報告書,28.[PDF](Google Scholar「"大人数" 反転授業」で知る)
- 竹内光悦・上村尚史・末永勝征(2014).タブレット端末を活用した統計教育の展望 日本計算機統計学会シンポジウム論文集,28,219-220.[PDF](Google Scholar「"大人数" 反転授業」で知る)
- 村中崇信・白水始(2014).宇宙教育プログラムへの知識構成型ジグソー法の導入 京都大学高等教育研究,20,39-48.[PDF](Google Scholar「"大人数" 反転授業」で知る)
- 渡邊席子(2015). 「アクティブ・ラーニング万歳」…それで本当にいいの?本当に? 大学教育,12(2),103-110.[PDF](Google Scholar「"大人数" 反転授業」で知る)
- 湯川恵子・木村尚仁・碇山恵子(2016).学びへのコミットメントを引きだす学習者主体のルーブリック作成と自己評価 国際経営フォーラム,27,217-236.[PDF](Google Scholar「"大人数" 反転授業」で知る)
- 加藤みどり・佐藤修・安田宏樹(2019).アクティブラーニングの教育効果に関する一考察 東京経大学会誌.経営学,302,151-170.[PDF](Google Scholar「"大人数" 反転授業」で知る)
[2020.3.4]ホーム「お知らせ」欄を修正
- ポスター発表「IRは大学の期待に応えられているのか:小規模大学におけるヒアリング調査を通じて」(第26回大学教育研究フォーラム)の日程欄をオンライン開催に修正、場所欄を削除
[2020.2.28]IRなどについての文献メモ 文献一覧を更新<学修成果、質保証>
- 工藤一彦(2019).三つのポリシーとJABEE基準に基づく質保証枠組と学修成果の客観的評価法 工学教育,67(1),1_5-1_10.[PDF](Google Scholar「アセスメント・ポリシー」で知る)
- 汐月哲夫・工藤一彦(2019).学修成果達成のための教育の質保証体制構築:アクティブ・ラーニング,e-ポートフォリオ,ルーブリックの有機的活用 工学教育研究講演会講演論文集,2019,78-79.(CiNii Articles「工藤一彦 質保証」で知る)
- 工藤一彦(2019).ルーブリックを活用した教育の質保証とJABEE認定によるその適切性検証 物理教育,67(2),122-125.(CiNii Articles「工藤一彦 質保証」で知る)
- 工藤一彦(2018).教育の質保証枠組に基づく学修成果の社会への提示法:学生個人の能力を示すディプロマ・サプリメントのありかた 工学教育研究講演会講演論文集,2018,500-501.[PDF](CiNii Articles「工藤一彦 質保証」で知る)
- 工藤一彦(2012).内部・教学監査と教育の内部質保証の関係 大学評価研究,11,47-56.(CiNii Articles「工藤一彦 質保証」で知る)
- 井上雅裕・工藤一彦・小玉嘉洋・山下修・室越昌美・村上雅人(2012).教職協働と全学ワールドカフェによる学習・教育目標の階層的設定:大学教育推進プログラム「PDCA化とIR体制による教育の質保証」の取組として 工学教育研究講演会講演論文集,2012,616-617.[PDF](CiNii Articles「工藤一彦 質保証」で知る)
- 工藤一彦・村上雅人・井上雅裕・中村朝夫・室越昌美・小玉嘉洋(2011).工学リベラルアーツ教育を軸とした体系的カリキュラムの構築とその教育目標の達成度評価:大学教育推進プログラム「PDCA化とIR体制による教育の質保証」の取組として 工学教育研究講演会講演論文集,2011,138-139.[PDF](CiNii Articles「工藤一彦 質保証」で知る)
[2020.2.21]ホーム「お知らせ」欄に追加
- ポスター発表「IRは大学の期待に応えられているのか:小規模大学におけるヒアリング調査を通じて」(第26回大学教育研究フォーラム)を掲載
[2020.2.12]大学に関わる情報メモ 内容をアップ
[2020.2.5]IRなどについての文献メモ 内容をアップ
- 溝上智恵子・大学図書館研究グループ(2019).データリテラシーの論点整理 図書館界,71(2),129-134.[PDF][内容]
[2020.2.2]IRなどについての文献メモ 内容をアップ
- 早田幸政(2017).大学基準協会の活動の航跡を振り返って:協会成立から認証評価制度の始動前までの時期を対象に政策的視点を踏まえた検証 大学評価研究,16,7-19.[PDF][内容](CiNii Articles「大学基準協会」で知る)
[2020.1.23]IRなどについての文献メモ 文献一覧を更新<認証評価、大学基準協会>
- 早田幸政(2017).大学基準協会の活動の航跡を振り返って:協会成立から認証評価制度の始動前までの時期を対象に政策的視点を踏まえた検証 大学評価研究,16,7-19.[PDF](CiNii Articles「大学基準協会」で知る)
- 藤原将人(2017).戦後「適格認定」制度の実施と私立大学:大学基準協会「会員資格審査」をめぐる関西四大学の活動過程 高等教育研究,20,219-238.[PDF](CiNii Articles「大学基準協会」で知る)
- 藤原将人(2014).戦後「適格認定」の形成と大学:各大学の大学基準協会設立過程への参加状況と適格認定の議論をめぐって 名古屋大学大学院教育発達科学研究科紀要.教育科学,61(1),71-83.(CiNii Articles「大学基準協会」で知る)
- 藤原将人(2013).戦後大学改革における適格認定の議論展開:大学基準と大学基準協会に関する教育刷新委員会の議論 大学評価研究,12,175-185.(CiNii Articles「大学基準協会」で知る)
- 林透(2008).臨教審以後のアクレディテーションの展開に関する一考察:大学基準協会と文部省視学委員制度を巡って 名古屋大学大学院教育発達科学研究科紀要.教育科学,55(2),181-189.(CiNii Articles「大学基準協会」で知る)
- 大学基準協会年史編さん室(編)(2005).大学基準協会55年史:「通史編」「資料編」 大学基準協会(CiNii Articles「大学基準協会」で知る)
- 寺崎昌男(2002).大学基準協会の歴史とわが国における大学評価の特質 大学評価研究,2,195-207.(CiNii Articles「大学基準協会」で知る)
[2020.1.22]大学に関わる情報メモ 内容をアップ
[2020.1.17]ホーム「お知らせ」欄に追加
- ポスター発表"Bridging executives' expectations and institutional researchers' expertise"(2020 AIR Forum)を掲載
[2020.1.4]更新履歴 文献のメモ<現代日本語書き言葉均衡コーパス>※「IRなどについての文献メモ」のページには追加せず
- 前川喜久雄・浅原正幸・小木曽智信・小磯花絵・木部暢子・迫田久美子(2017).日本語コーパスの包括的検索環境の実現に向けて 言語資源活用ワークショップ発表論文集,1,170-179.[PDF](CiNii Articles「現代日本語書き言葉均衡コーパス」で知る)
- 丸山岳彦(2014).『現代日本語書き言葉均衡コーパス』による現代日本語文法の研究 日本語学,7,90-95.(CiNii Articles「現代日本語書き言葉均衡コーパス」で知る)
- 小木曽智信(2014).日本語コーパスの今 情報の科学と技術,11,463-468.[PDF](CiNii Articles「現代日本語書き言葉均衡コーパス」で知る)
- 田野村忠温(2012).BCCWJに収められた新種の言語資料の特性について:データ重複の諸相とコーパス使用上の注意点 待兼山論叢,46,59-83.(CiNii Articles「現代日本語書き言葉均衡コーパス」で知る)
- 山崎誠(2011).『現代日本語書き言葉均衡コーパス』の設計 現代の図書館,2,133-139.(CiNii Articles「現代日本語書き言葉均衡コーパス」で知る)
- 前川喜久雄・山崎誠(2009).現代日本語書き言葉均衡コーパス 国文学:解釈と鑑賞,74(1),15-25.(CiNii Articles「現代日本語書き言葉均衡コーパス」で知る)
- 前川喜久雄(2008).国立国語研究所のコーパス整備計画KOTONOHA:その現状と問題点 電子情報通信学会技術研究報告.TL, 思考と言語,108(50),23-28.(CiNii Articles「現代日本語書き言葉均衡コーパス」で知る)
- 前川喜久雄(2008).KOTONOHA『現代日本語書き言葉均衡コーパス』の開発 日本語の研究,4(1),82-95.[PDF](CiNii Articles「現代日本語書き言葉均衡コーパス」で知る)
- 後藤斉(2007).コーパス言語学と日本語研究 日本語科学,22,47-58.[PDF](CiNii Articles「現代日本語書き言葉均衡コーパス」で知る)
- 前川喜久雄(2007).コーパス日本語学の可能性:大規模均衡コーパスがもたらすもの 日本語科学,2213-28.[PDF](CiNii Articles「現代日本語書き言葉均衡コーパス」で知る)
- 丸山岳彦・田野村忠温(2007).コーパス日本語学の射程 日本語科学,225-12.[PDF](CiNii Articles「現代日本語書き言葉均衡コーパス」で知る)
- 田中貴秋・永田昌明(2019).日本語の文法機能タイプ付き単語依存構造解析 自然言語処理,26(2),441-481.[PDF](CiNii Articles「現代日本語書き言葉均衡コーパス」で知る)
- 宮内拓也・浅原正幸・中川奈津子・加藤祥(2018).『現代日本語書き言葉均衡コーパス』への情報構造アノテーションとその分析 国立国語研究所論集,16,19-33.[PDF](CiNii Articles「現代日本語書き言葉均衡コーパス」で知る)
- 浅原正幸・松本裕治(2018).『現代日本語書き言葉均衡コーパス』に対する文節係り受け・並列構造アノテーション 自然言語処理,4,331-356.[PDF](CiNii Articles「現代日本語書き言葉均衡コーパス」で知る)
- 今田水穂(2018).『現代日本語書き言葉均衡コーパス』に対する名詞述語文アノテーション 言語資源活用ワークショップ発表論文集,3,382-398.[PDF](CiNii Articles「現代日本語書き言葉均衡コーパス」で知る)
- 浅原正幸・南部智史・佐野真一郎(2018).日本語の二重目的語構文の基本語順について 言語資源活用ワークショップ発表論文集,3,280-287.[PDF](CiNii Articles「現代日本語書き言葉均衡コーパス」で知る)
- 大村舞・浅原正幸(2018).UD Japanese-BCCWJの構築と分析 言語資源活用ワークショップ発表論文集,3,161-175.[PDF](CiNii Articles「現代日本語書き言葉均衡コーパス」で知る)
- 大村舞・浅原正幸(2017).現代日本語書き言葉均衡コーパスのUniversal Dependencies 言語資源活用ワークショップ発表論文集,2,133-143.[PDF](CiNii Articles「現代日本語書き言葉均衡コーパス」で知る)
- 森秀明(2017).一般的な日本語テキストにおける助詞比率の規則性 言語資源活用ワークショップ発表論文集,2,9-22.[PDF](CiNii Articles「現代日本語書き言葉均衡コーパス」で知る)
- 宮内拓也・浅原正幸・中川奈津子・加藤祥(2017).『現代日本語書き言葉均衡コーパス』への情報構造アノテーションの分析 言語資源活用ワークショップ発表論文集,1,404-415.[PDF](CiNii Articles「現代日本語書き言葉均衡コーパス」で知る)
- 松本理美・浅原正幸・有田節子(2017).『現代日本語書き言葉均衡コーパス』に対する節の意味分類情報アノテーション:基準策定,仕様書作成の必要性について 言語資源活用ワークショップ発表論文集,1,336-346.[PDF](CiNii Articles「現代日本語書き言葉均衡コーパス」で知る)
- 加藤祥・浅原正幸・山崎誠(2017).『現代日本語書き言葉均衡コーパス』に対する分類語彙表番号アノテーションの試行 言語資源活用ワークショップ発表論文集,1,104-113.[PDF](CiNii Articles「現代日本語書き言葉均衡コーパス」で知る)
- 宮嵜由美・柏野和佳子・山崎誠(2017).発話文への発話者情報付与の基本設計:『現代日本語書き言葉均衡コーパス』収録の小説を対象に 言語資源活用ワークショップ発表論文集,1,38-48.[PDF](CiNii Articles「現代日本語書き言葉均衡コーパス」で知る)
- 浅原正幸・小野創・宮本エジソン正(2016).BCCWJ-EyeTracking:『現代日本語書き言葉均衡コーパス』に対する読み時間アノテーション 電子情報通信学会技術研究報告.TL, 思考と言語,159,7-12.(CiNii Articles「現代日本語書き言葉均衡コーパス」で知る)
- 小西光・中村壮範・田中弥生・間淵洋子・浅原正幸・立花幸子・加藤祥・今田水穂・山口昌也・前川喜久雄・小木曽智信・山崎誠・丸山岳彦(2015).『現代日本語書き言葉均衡コーパス』の文境界修正 国立国語研究所論集,9,81-100.[PDF](CiNii Articles「現代日本語書き言葉均衡コーパス」で知る)
- 小西光(2015).小西光,浅原正幸,前川喜久雄「『現代日本語書き言葉均衡コーパス』に対する時間情報アノテーション」:言語処理学会誌『自然言語処理』20(2):201-222.(2013) 国語研プロジェクトレビュー,54-56.[PDF](CiNii Articles「現代日本語書き言葉均衡コーパス」で知る)
- 加藤祥(2015).保田祥,小西光,浅原正幸,今田水穂,前川喜久雄 「『現代日本語書き言葉均衡コーパス』に対する時間情報表現・事象表現間の時間的順序関係アノテーション」 言語処理学会誌『自然言語処理』20(5): 657-681. (2013) 国語研プロジェクトレビュー,3,141-142.[PDF](CiNii Articles「現代日本語書き言葉均衡コーパス」で知る)
- 小木曽智信・中村壮範(2014).『現代日本語書き言葉均衡コーパス』形態論情報アノテーション支援システムの設計・実装・運用 自然言語処理,2,301-332.[PDF](CiNii Articles「現代日本語書き言葉均衡コーパス」で知る)
- 小西光・浅原正幸・前川喜久雄(2013).『現代日本語書き言葉均衡コーパス』に対する時間情報アノテーション 自然言語処理,2,201-221.[PDF](CiNii Articles「現代日本語書き言葉均衡コーパス」で知る)
- 保田祥・小西光・浅原正幸・今田水穂・前川喜久雄(2013).『現代日本語書き言葉均衡コーパス』に対する時間情報表現・事象表現間の時間的順序関係アノテーション 自然言語処理,5,657-681.[PDF](CiNii Articles「現代日本語書き言葉均衡コーパス」で知る)
- 前川喜久雄(2009).KOTONOHA『現代日本語書き言葉均衡コーパス』における著作権処理 漢字文献情報処理研究,10,30-35.(CiNii Articles「現代日本語書き言葉均衡コーパス」で知る)
- 小島健輔・佐藤理史(2009).現代日本語書き言葉均衡コーパスに対する難易度付与 電子情報通信学会技術研究報告.TL, 思考と言語,84,13-18.(CiNii Articles「現代日本語書き言葉均衡コーパス」で知る)
- 山崎誠・丸山岳彦・柏野和佳子(2006).現代日本語書き言葉均衡コーパスのサンプリング方法について 計量国語学,25(7),330-332.(CiNii Articles「現代日本語書き言葉均衡コーパス」で知る)
[2020.1.4]更新履歴 文献のメモ<現代日本語書き言葉均衡コーパス>※「IRなどについての文献メモ」のページには追加せず
- 鈴木類・古宮嘉那子・浅原正幸・佐々木稔・新納浩幸(2019).概念辞書の類義語と分散表現を利用した教師なし all-words WSD 自然言語処理,26(2),361-379.[PDF](CiNii Articles「現代日本語書き言葉均衡コーパス」で知る)
- 浅原正幸(2019).日本語の読み時間と節境界情報:主辞後置言語における wrap-up effect の検証 自然言語処理,26(2),301-327.[PDF](CiNii Articles「現代日本語書き言葉均衡コーパス」で知る)
- 珊瑚彩主紀・西川仁・徳永健伸(2019).外界一人称と二人称を考慮する日本語述語項構造解析の分野適応 自然言語処理,26(2),483-508.[PDF](CiNii Articles「現代日本語書き言葉均衡コーパス」で知る)
- 井上直美(2019).「テミセル」表現に関する一考察:書き言葉における文末「てみせる。」の使用実態 さいたま言語研究,3,26-37.[PDF](CiNii Articles「現代日本語書き言葉均衡コーパス」で知る)
- 劉志偉(2019).撥音は解析システムにとっても簡単ではなかったんだ:BCCWJを中心に 埼玉大学紀要. 教養学部,2,175-200.[PDF](CiNii Articles「現代日本語書き言葉均衡コーパス」で知る)
- 彭玉全(2019).複合助詞「に関して」と「に対して」の誤用分析 筑波日本語研究,23,15-25.(CiNii Articles「現代日本語書き言葉均衡コーパス」で知る)
- 劉芳卉(2018).日本語と中国語における視覚本動詞に関する一考察 千葉大学人文公共学研究論集,37,55-67.[PDF](CiNii Articles「現代日本語書き言葉均衡コーパス」で知る)
- 松本理美(2018).日本語従属節の意味分類基準策定について:「鳥バンク」節間意味分類体系再構築の提案 国立国語研究所論集,15,107-133.[PDF](CiNii Articles「現代日本語書き言葉均衡コーパス」で知る)
- 麻子軒(2018).一対比較法による日本語名詞句階層の測定 現代日本語研究,10,66-80.[PDF](CiNii Articles「現代日本語書き言葉均衡コーパス」で知る)
- 佐々木淳(2018).助詞「の」の構文文法論的考察(序論) 比治山大学紀要,24,147-152.(CiNii Articles「現代日本語書き言葉均衡コーパス」で知る)
- 宮城信・今田水穂(2018).『児童・生徒作文コーパス』を用いた漢字使用能力の発達過程の分析 計量国語学,5,352-369.[PDF](CiNii Articles「現代日本語書き言葉均衡コーパス」で知る)
- 島崎英香(2018).中上級日本語学習者のための副詞選定:「現代日本語書き言葉均衡コーパス(BCCWJ)」・「名大会話コーパス」を基に 日本語教育方法研究会誌,1,62-63.[PDF](CiNii Articles「現代日本語書き言葉均衡コーパス」で知る)
- 岡照晃(2018).『国語研日本語ウェブコーパス』からの新規語彙素獲得の試み 言語資源活用ワークショップ発表論文集,3,586-592.[PDF](CiNii Articles「現代日本語書き言葉均衡コーパス」で知る)
- 清水まさ子・木田真理(2018).ノンネイティブ日本語教師はコーパスでどのように日本語を調べるか:コーパスを用いた課題の分析から 言語資源活用ワークショップ発表論文集,3,568-577.[PDF](CiNii Articles「現代日本語書き言葉均衡コーパス」で知る)
- 西内沙恵(2018).形容詞感動文における曖昧性回避の条件 言語資源活用ワークショップ発表論文集,3,561-567.[PDF](CiNii Articles「現代日本語書き言葉均衡コーパス」で知る)
- 佐々木稔・古宮嘉那子・新納浩幸(2018).単語の分散表現を用いた領域における出現単語の特徴分析 言語資源活用ワークショップ発表論文集,3,553-560.[PDF](CiNii Articles「現代日本語書き言葉均衡コーパス」で知る)
- 本多由美子(2018).二字漢語を構成する漢字の造語力の変化:『現代雑誌九十種の用語用字』データと『現代日本語書き言葉均衡コーパス』の比較を通して 言語資源活用ワークショップ発表論文集,3,531-546.[PDF](CiNii Articles「現代日本語書き言葉均衡コーパス」で知る)
- 今田水穂(2018).語彙多様性指標の可視化と単回帰分析によるTTRの補正 言語資源活用ワークショップ発表論文集,3,519-530.[PDF](CiNii Articles「現代日本語書き言葉均衡コーパス」で知る)
- 間淵洋子(2018).コーパスに基づく字順転倒漢語の網羅的把握の試み 言語資源活用ワークショップ発表論文集,3,452-462.[PDF](CiNii Articles「現代日本語書き言葉均衡コーパス」で知る)
- 加藤祥・櫻井芽衣子・森山奈々美・浅原正幸(2018).『現代日本語書き言葉均衡コーパス』書籍サンプルに対するNDC記号拡張アノテーションとNDC形式区分を用いた「随筆」の文体分析 言語資源活用ワークショップ発表論文集,3,372-381.[PDF](CiNii Articles「現代日本語書き言葉均衡コーパス」で知る)
- 劉志偉(2018).撥音(の解析)は機械(UniDic)にとっても簡単ではなかったんだ!:BCCWJを中心に 言語資源活用ワークショップ発表論文集,3,368-371.[PDF](CiNii Articles「現代日本語書き言葉均衡コーパス」で知る)
- 陳祥(2018).「XX(と)」、「XXな」、「XXしい」の構造・文法機能:畳語による生産性について 言語資源活用ワークショップ発表論文集,3,307-315.[PDF](CiNii Articles「現代日本語書き言葉均衡コーパス」で知る)
- 菊地礼(2018).比喩指標としての「感じる」:文法形式と比喩の関係 言語資源活用ワークショップ発表論文集,3,288-297.[PDF](CiNii Articles「現代日本語書き言葉均衡コーパス」で知る)
- 加藤恵梨・山下紗苗・上泰(2018).Twitterで使われる「深い」の意味:「強い」「すごい」と比較して 言語資源活用ワークショップ発表論文集,3,274-279.[PDF](CiNii Articles「現代日本語書き言葉均衡コーパス」で知る)
- 馬場俊臣(2018).『BCCWJ図書館サブコーパスの文体情報』を利用した語の文体差研究の可能性 言語資源活用ワークショップ発表論文集,3,241-256.[PDF](CiNii Articles「現代日本語書き言葉均衡コーパス」で知る)
- 徐敏徹(2018).「飲み倒す」とはどういう意味なのか:Google検索を利用した日本語の低頻度複合動詞の分析 言語資源活用ワークショップ発表論文集,3,221-235.[PDF](CiNii Articles「現代日本語書き言葉均衡コーパス」で知る)
- 新納浩幸・鈴木類・古宮嘉那子(2018).双方向LSTMによる分類語彙表番号を語義としたall-words WSD 言語資源活用ワークショップ発表論文集,3,192-202.[PDF](CiNii Articles「現代日本語書き言葉均衡コーパス」で知る)
- 劉時珍(2018).副詞の程度性の下位分類の試み:「あまり・そんなに・それほど・たいして」を例に 言語資源活用ワークショップ発表論文集,3,136-141.[PDF](CiNii Articles「現代日本語書き言葉均衡コーパス」で知る)
- 坂本美保・川原典子・久本空海・髙岡一馬・内田佳孝(2018).形態素解析器『Sudachi』のための大規模辞書開発 言語資源活用ワークショップ発表論文集,3,118-129.[PDF](CiNii Articles「現代日本語書き言葉均衡コーパス」で知る)
- 高橋圭子・東泉裕子・佐藤万里(2018).「『了解』は使わないように」「了解です!」 言語資源活用ワークショップ発表論文集,3,57-67.[PDF](CiNii Articles「現代日本語書き言葉均衡コーパス」で知る)
- 森秀明(2018).連体助詞の「ノ」と文体の関係 言語資源活用ワークショップ発表論文集,3,34-46.[PDF](CiNii Articles「現代日本語書き言葉均衡コーパス」で知る)
- 王棟(2018).日本語文における連用修飾語成分に見られるパラレルについての一考察:「赤く変わる」と「赤に変わる」は同じか 言語資源活用ワークショップ発表論文集,3,27-33.[PDF](CiNii Articles「現代日本語書き言葉均衡コーパス」で知る)
- 宮内拓也(2018).『現代日本語書き言葉均衡コーパス』のロシア語翻訳データの構築 言語資源活用ワークショップ発表論文集,3,2-11.[PDF](CiNii Articles「現代日本語書き言葉均衡コーパス」で知る)
- 鈴木智美(2018).サ変動詞を形成するV1+V2型複合名詞:対応する複合動詞の有無に基づく違いの観点から 日本語・日本学研究,37-49.[PDF](CiNii Articles「現代日本語書き言葉均衡コーパス」で知る)
- 野中大輔(2017).調味料をかけることを表す日本語の動詞と場所格交替:現代日本語書き言葉均衡コーパスを用いて 東京大学言語学論集,177-195.[PDF](CiNii Articles「現代日本語書き言葉均衡コーパス」で知る)
- 張潔卉(2017).日中同形異義語の喚情価値の差異について:日本語がプラス、中国語がマイナスのイメージを持つ同形語 地球社会統合科学研究,7,81-88.(CiNii Articles「現代日本語書き言葉均衡コーパス」で知る)
- 間淵洋子(2017).近代雑誌コーパスにおける漢語語彙の特徴:BCCWJとの比較から 国立国語研究所論集,13,143-166.[PDF](CiNii Articles「現代日本語書き言葉均衡コーパス」で知る)
- 陳奕廷(2017).基底と精緻化から見た複合語の分類:日本語複合動詞を中心に 国立国語研究所論集,13,25-50.[PDF](CiNii Articles「現代日本語書き言葉均衡コーパス」で知る)
- 内海陽子(2017).『現代日本語書き言葉均衡コーパス』を利用した上級学習者の文章表現指導の試み:共起表現の自己修正を中心として 東京外国語大学留学生日本語教育センター論集,43,147-160.(CiNii Articles「現代日本語書き言葉均衡コーパス」で知る)
- 趙妍姗(2017).「くらいなら」の意味用法について 言語と文明:論集,61-79.(CiNii Articles「現代日本語書き言葉均衡コーパス」で知る)
- 前田直子(2017).順接条件節「なら」の接続形態 現代日本語研究,9,23-39.[PDF](CiNii Articles「現代日本語書き言葉均衡コーパス」で知る)
- 池谷知子(2017).開始を表す複合動詞「~出す」「~始める」の違い:コーパスを利用した使用実態から トークス,20,35-59.[PDF](CiNii Articles「現代日本語書き言葉均衡コーパス」で知る)
- 石川慎一郎(2017).現代日本語における「デ」格の意味役割の再考:コーパス頻度調査に基づく用法記述の精緻化と認知的意味拡張モデルの検証 計量国語学,2,99-115.[PDF](CiNii Articles「現代日本語書き言葉均衡コーパス」で知る)
- 仁科喜久子・八木豊・ホドシチェックボル・阿辺川武(2017).作文学習支援システ ムのための接続表現辞典構築 計量国語学,2,160-176.[PDF](CiNii Articles「現代日本語書き言葉均衡コーパス」で知る)
- 本多由美子(2017).二字漢語における語の透明性:コーパスを用いた語と構成漢字の分析 計量国語学,1,1-19.[PDF](CiNii Articles「現代日本語書き言葉均衡コーパス」で知る)
- 村井源(2017).日本語小説の会話文タグ付コーパスの開発に向けて 人工知能学会全国大会論文集,1D2OS29a2-1D2OS29a2.[PDF](CiNii Articles「現代日本語書き言葉均衡コーパス」で知る)
- 中俣尚己(2017).接続助詞の前接語に見られる品詞の偏り:コーパスから見える南モデル 日本語の研究,4,1-17.[PDF](CiNii Articles「現代日本語書き言葉均衡コーパス」で知る)
- 山崎誠(2017).レジスター・位相の違いによる会話文の語彙的多様性 言語資源活用ワークショップ発表論文集,2,278-289.[PDF](CiNii Articles「現代日本語書き言葉均衡コーパス」で知る)
- 加藤祥・浅原正幸(2017).分類語彙表番号を用いた比喩表現収集の試み 言語資源活用ワークショップ発表論文集,2,268-277.[PDF](CiNii Articles「現代日本語書き言葉均衡コーパス」で知る)
- 小椋秀樹(2017).書き言葉と話し言葉における外来語語末長音のゆれ 言語資源活用ワークショップ発表論文集,2,223-232.[PDF](CiNii Articles「現代日本語書き言葉均衡コーパス」で知る)
- 遊佐宣彦・佐々木稔・古宮嘉那子・新納浩幸(2017).単義語と共起する多義語に対する分散表現を利用した語義分析 言語資源活用ワークショップ発表論文集,2,216-222.[PDF](CiNii Articles「現代日本語書き言葉均衡コーパス」で知る)
- 岡照晃(2017).CRF素性テンプレートの見直しによるモデルサイズを軽量化した解析用UniDic:unidic-cwj-2.2.0とunidic-csj-2.2.0 言語資源活用ワークショップ発表論文集,2,144-153.[PDF](CiNii Articles「現代日本語書き言葉均衡コーパス」で知る)
- 高橋圭子・東泉裕子(2017).「お/ご~される」とその周辺 言語資源活用ワークショップ発表論文集,2,123-132.[PDF](CiNii Articles「現代日本語書き言葉均衡コーパス」で知る)
- 間淵洋子(2017).近代漢語の品詞性に見る多様性の画一化:形容詞用法を中心に 言語資源活用ワークショップ発表論文集,2,93-106.[PDF](CiNii Articles「現代日本語書き言葉均衡コーパス」で知る)
- 今田水穂(2017).外の関係の連体修飾節を伴う名詞述語について 言語資源活用ワークショップ発表論文集,2,75-84.[PDF](CiNii Articles「現代日本語書き言葉均衡コーパス」で知る)
- 浅原正幸・田中弥生(2017).修辞ユニット分析における脱文脈化指数の妥当性の検証 言語資源活用ワークショップ発表論文集,2,64-74.[PDF](CiNii Articles「現代日本語書き言葉均衡コーパス」で知る)
- 岩崎拓也(2017).読点が接続詞の直後に打たれる要因について:一般化線形モデルを用いた予測モデルの構築 言語資源活用ワークショップ発表論文集,2,56-63.[PDF](CiNii Articles「現代日本語書き言葉均衡コーパス」で知る)
- 松本理美(2017).従属節の意味分類基準策定について:鳥バンク基準互換再構築の検討 言語資源活用ワークショップ発表論文集,2,40-51.[PDF](CiNii Articles「現代日本語書き言葉均衡コーパス」で知る)
- 張莉(2017).非情の受身の状態の意味について 言語資源活用ワークショップ発表論文集,2,34-39.[PDF](CiNii Articles「現代日本語書き言葉均衡コーパス」で知る)
- 金賢眞(2017).ウェブコーパス「梵天」による敬語研究:その活用可能性に関する事例的検討 言語資源活用ワークショップ発表論文集,2,23-33.[PDF](CiNii Articles「現代日本語書き言葉均衡コーパス」で知る)
- 王海涛(2017).日本語特殊形容詞の装定用法の出現傾向について 言語資源活用ワークショップ発表論文集,2,2-8.[PDF](CiNii Articles「現代日本語書き言葉均衡コーパス」で知る)
- 浅原正幸(2017).読み時間と情報構造について(ちょっとながめ) 言語資源活用ワークショップ発表論文集,1,416-427.[PDF](CiNii Articles「現代日本語書き言葉均衡コーパス」で知る)
- 鈴木雅也・古宮嘉那子・岩倉友哉・佐々木稔・新納浩幸(2017).固有表現抽出におけるアノテーション手法の比較 言語資源活用ワークショップ発表論文集,1,385-403.[PDF](CiNii Articles「現代日本語書き言葉均衡コーパス」で知る)
- 藤村逸子・青木繁伸(2017).結合の強度を測る指標としてのLog-rの有用性:日・英語のバイグラムデータに基づくMI,LLRなどとの比較 言語資源活用ワークショップ発表論文集,1,365-376.[PDF](CiNii Articles「現代日本語書き言葉均衡コーパス」で知る)
- 山崎誠(2017).『現代日本語書き言葉均衡コーパス』と『分類語彙表』を利用した漢字3文字略熟語の抽出 言語資源活用ワークショップ発表論文集,1,307-316.[PDF](CiNii Articles「現代日本語書き言葉均衡コーパス」で知る)
- 加藤麟太郎・藤井聖子(2017).『現代日本語書き言葉均衡コーパス』を用いた「~ていく」「~てくる」構文の意味分析 言語資源活用ワークショップ発表論文集,1,273-281.[PDF](CiNii Articles「現代日本語書き言葉均衡コーパス」で知る)
- 鈴木類・古宮嘉那子・浅原正幸・佐々木稔・新納浩幸(2017).『分類語彙表』の類義語と分散表現を利用したall-words語義曖昧性解消 言語資源活用ワークショップ発表論文集,1,258-264.[PDF](CiNii Articles「現代日本語書き言葉均衡コーパス」で知る)
- 間淵洋子(2017).漢語の仮名表記:実態と背景 言語資源活用ワークショップ発表論文集,1,201-213.[PDF](CiNii Articles「現代日本語書き言葉均衡コーパス」で知る)
- 堀恵子・内丸裕佳子・加藤恵梨・小西円・山崎誠・江田すみれ・建石始・中俣尚己・李在鎬(2017).機能語用例文データベース『はごろも』の今後の展開 言語資源活用ワークショップ発表論文集,1,180-189.[PDF](CiNii Articles「現代日本語書き言葉均衡コーパス」で知る)
- 西内沙恵(2017).次元形容詞にみる母語話者らしい日本語形容詞の使用 言語資源活用ワークショップ発表論文集,1,163-169.[PDF](CiNii Articles「現代日本語書き言葉均衡コーパス」で知る)
- 小木曽智信(2017).多重の読みを持つテキストのコーパス化 言語資源活用ワークショップ発表論文集,1,159-162.[PDF](CiNii Articles「現代日本語書き言葉均衡コーパス」で知る)
- 今田水穂(2017).もし小学生が『現代日本語書き言葉均衡コーパス』並みに漢字を使ったら 言語資源活用ワークショップ発表論文集,1,20-29.[PDF](CiNii Articles「現代日本語書き言葉均衡コーパス」で知る)
- 髙野愛子・上村圭介(2017).レジスター別出現頻度に基づく順接接続詞の文体差の評価:現代日本語書き言葉均衡コーパス(BCCWJ)の用例分析から 語学教育研究論叢,34,273-293.(CiNii Articles「現代日本語書き言葉均衡コーパス」で知る)
- 内田ゆず(2017).現代日本語書き言葉均衡コーパスコアデータにおけるオノマトペ出現実態に基づくオノマトペ自動抽出手法 工学研究:北海学園大学大学院工学研究科紀要,17,15-20.(CiNii Articles「現代日本語書き言葉均衡コーパス」で知る)
- 松田謙次郎(2016).大正~昭和戦前期のSP盤演説レコードにおける「場合」の読みについて 国立国語研究所論集,11,63-81.[PDF](CiNii Articles「現代日本語書き言葉均衡コーパス」で知る)
- 加藤恵梨(2016).コーパスに基づく「べきだ」の分析 朝日大学留学生別科紀要,13,15-24.(CiNii Articles「現代日本語書き言葉均衡コーパス」で知る)
- 中溝朋子・坂井美恵子・金森由美(2016).BCCWJを利用した反復相・反復強意相の機能動詞「繰り返す」「積む」「重ねる」の異同:名詞の共起状況を手掛かりに 大学教育,13,24-37.(CiNii Articles「現代日本語書き言葉均衡コーパス」で知る)
- 呉琳(2016).BCCWJを用いた基幹慣用句の選定 北海道大学大学院文学研究科研究論集,16,99-113.[PDF](CiNii Articles「現代日本語書き言葉均衡コーパス」で知る)
- 小椋秀樹(2015).『現代日本語書き言葉均衡コーパス』による表記の研究 日本語学,12,78-83.(CiNii Articles「現代日本語書き言葉均衡コーパス」で知る)
- 柏野和佳子(2015).『現代日本語書き言葉均衡コーパス』による古風な語の研究 日本語学,8,70-75.(CiNii Articles「現代日本語書き言葉均衡コーパス」で知る)
- 加藤祥(2015).テキストからの対象物認識に有用な記述内容:動物を例に 国立国語研究所論集,9,23-50.[PDF](CiNii Articles「現代日本語書き言葉均衡コーパス」で知る)
- 田中牧郎(2015).『太陽コーパス』と『現代日本語書き言葉均衡コーパス』の比較による近現代語彙史の研究 日本語学,3,72-77.(CiNii Articles「現代日本語書き言葉均衡コーパス」で知る)
- Oberwinkler, M.(2015).日本人はどう悲しむか:日独の自死遺族掲示板コーパスと均衡コーパスを用いた「感情」の言語表現比較の試み 同志社大学日本語・日本文化研究,13,25-44.[PDF](CiNii Articles「現代日本語書き言葉均衡コーパス」で知る)
- 陳志文(2015).副詞の「比較的」と「比較的に」についての考察:『現代日本語書き言葉均衡コーパス』における使用実態 国語学研究,54,152-167.(CiNii Articles「現代日本語書き言葉均衡コーパス」で知る)
- 内田ゆず・高丸圭一・乙武北斗・木村泰知(2015).BCCWJコアデータにおけるオノマトペ出現実態の分析 人工知能学会全国大会論文集,3G4OS05b5-3G4OS05b5.[PDF](CiNii Articles「現代日本語書き言葉均衡コーパス」で知る)
- 内田諭・藤井聖子(2015).クラスター分析とフレーム分析による語彙のジャンル別特徴:「現代日本語書き言葉均衡コーパス」を用いて 言語文化論究,34,21-34.[PDF](CiNii Articles「現代日本語書き言葉均衡コーパス」で知る)
- 河内昭浩(2015).「常用漢字表」語例の検討 安田女子大学紀要,43,203-212.(CiNii Articles「現代日本語書き言葉均衡コーパス」で知る)
- 山崎誠・相良かおる(2014).医療経過記録における漢字連続複合語の計量的分析 じんもんこん2014論文集,3,221-226.(CiNii Articles「現代日本語書き言葉均衡コーパス」で知る)
- 穆欣・玉岡架津雄(2014).カラの主語性に関する研究:コーパス検索および文処理実験 ことばの科学,28,71-90.[PDF](CiNii Articles「現代日本語書き言葉均衡コーパス」で知る)
- 河内昭浩(2014).教科学習語彙の選定と活用 全国大学国語教育学会発表要旨集,127,333-336.(CiNii Articles「現代日本語書き言葉均衡コーパス」で知る)
- 小椋秀樹(2014).『現代日本語書き言葉均衡コーパス』による表記の研究 日本語学,13,78-83.(CiNii Articles「現代日本語書き言葉均衡コーパス」で知る)
- 加藤祥・柏野和佳子・立花幸子・丸山岳彦(2014).語りかける書きことばの表現 国立国語研究所論集,8,85-108.[PDF](CiNii Articles「現代日本語書き言葉均衡コーパス」で知る)
- 柏野和佳子(2014).『現代日本語書き言葉均衡コーパス』によるカタカナ表記語の研究 日本語学,10,98-103.(CiNii Articles「現代日本語書き言葉均衡コーパス」で知る)
- 馬場俊臣(2014).接続詞の二重使用の承接順序及び文体差:『現代日本語書き言葉均衡コーパス』全ジャンルによる追加調査 北海道教育大学紀要. 人文科学・社会科学編,1,1-17.(CiNii Articles「現代日本語書き言葉均衡コーパス」で知る)
- 杉浦滋子(2014).「よほど」の意味と用法 言語と文明:論集,1-19.[PDF](CiNii Articles「現代日本語書き言葉均衡コーパス」で知る)
- 加藤恵梨(2014).「-べく」と「-べし」について:日本語教育に役立つ例文づくりのための研究 名古屋大学日本語・日本文化論集,22,105-117.(CiNii Articles「現代日本語書き言葉均衡コーパス」で知る)
- 河内昭浩(2014).「交わり」を導く語彙指導 安田女子大学大学院文学研究科紀要.合冊,1-19.(CiNii Articles「現代日本語書き言葉均衡コーパス」で知る)
- 佐藤栄作(2014).表記資料としての「現代日本語書き言葉均衡コーパス」:「主観的表記頻度」と「中納言」との乖離から 論集,10,161-176.(CiNii Articles「現代日本語書き言葉均衡コーパス」で知る)
- 山崎誠(2014).テキストにおける多義語の語義の分布:『現代日本語書き言葉均衡コーパス』を利用して 計量国語学,7,251-262.(CiNii Articles「現代日本語書き言葉均衡コーパス」で知る)
- 陳志文(2014).「具体的+N」と「具体的な+N」についての考察:『現代日本語書き言葉均衡コーパス』における使用実態 国語学研究,53,1-15.(CiNii Articles「現代日本語書き言葉均衡コーパス」で知る)
- 李文平(2014).日本語教科書におけるコロケーションの取り扱いに関する一考察:中国の日本語教科書と現代日本語書き言葉均衡コーパスとの比較 日本語教育,63-77.[PDF](CiNii Articles「現代日本語書き言葉均衡コーパス」で知る)
- 柏野和佳子・奥村学(2014).「コーパスベース国語辞典」構築のための「古風な語」の分析と記述 自然言語処理,6,1133-1161.[PDF](CiNii Articles「現代日本語書き言葉均衡コーパス」で知る)
- 小澤俊介・内元清貴・伝康晴(2014).長単位解析器の異なる品詞体系への適用 自然言語処理,2,379-401.[PDF](CiNii Articles「現代日本語書き言葉均衡コーパス」で知る)
- 関洋平(2014).コミュニティQAにおける意見分析のためのアノテーションに関する一検討 自然言語処理,2,271-299.[PDF](CiNii Articles「現代日本語書き言葉均衡コーパス」で知る)
- 松吉俊(2014).否定の焦点情報アノテーション 自然言語処理,2,249-270.[PDF](CiNii Articles「現代日本語書き言葉均衡コーパス」で知る)
- 前坊香菜子(2014).「必ず」「絶対」「きっと」の文体的特徴:『現代日本語書き言葉均衡コーパス』の調査から 一橋大学国際教育センター紀要,5,93-104.[PDF](CiNii Articles「現代日本語書き言葉均衡コーパス」で知る)
- 久屋愛実(2013).現代書き言葉における外来語の共時的分布:「ケース」を事例として 国立国語研究所論集,6,45-65.[PDF](CiNii Articles「現代日本語書き言葉均衡コーパス」で知る)
- 掘一成・坂尻彰宏・石島悌(2013).現代日本語書き言葉均衡コーパスより抽出した頻度情報に基づく日本語学術ライティング指導教材の作成電子情報通信学会技術研究報告.TL, 思考と言語,213,1-6.(CiNii Articles「現代日本語書き言葉均衡コーパス」で知る)
- 佐藤理史(2013).テキストの難易度と語の分布 情報処理学会研究報告.自然言語処理研究会報告,6,1-11.(CiNii Articles「現代日本語書き言葉均衡コーパス」で知る)
- 井本亮(2013).『現代日本語書き言葉均衡コーパス』にみられる副詞的修飾関係「赤くV」について 商学論集,1,1-19.(CiNii Articles「現代日本語書き言葉均衡コーパス」で知る)
- 越恩英(2013).類義語「やっと」「ようやく」の文体と共起する述語について:『現代日本語書き言葉均衡コーパス』の「文学」を用いて 日本語研究,33,15-29.(CiNii Articles「現代日本語書き言葉均衡コーパス」で知る)
- 宮内佐夜香(2013).接続詞「なので」の書き言葉における使用について:『現代日本語書き言葉均衡コーパス』を資料として 中京国文学,32,106-93.(CiNii Articles「現代日本語書き言葉均衡コーパス」で知る)
- 金雪花(2013).自称詞用法の「自分」の許容度を上げる要因:「主語・主題」に位置する「自分」について 一橋大学国際教育センター紀要,4,75-86.[PDF](CiNii Articles「現代日本語書き言葉均衡コーパス」で知る)
- 馬場俊臣(2013).接続詞の二重使用の承接順序について:『現代日本語書き言葉均衡コーパス』を用いた再検討 語学文学,52,1-23.(CiNii Articles「現代日本語書き言葉均衡コーパス」で知る)
- 金城克哉(2012).2つの異形態動詞「Xじる」と「Xずる」のジャンルごとの分布とコロケーション特徴:「現代日本語書き言葉均衡コーパス」(BCCWJ)を利用した研究 Southern review:Studies in foreign language & literature,27,69-82.(CiNii Articles「現代日本語書き言葉均衡コーパス」で知る)
- 真田治子(2012).助詞の使用度数と結合価に関する計量的分析方法の検討 経済学季報,2,1-35.(CiNii Articles「現代日本語書き言葉均衡コーパス」で知る)
- 佐野大樹(2012).アプレイザル理論を基底とした評価表現の分類と辞書の構築 国立国語研究所論集,3,53-83.[PDF](CiNii Articles「現代日本語書き言葉均衡コーパス」で知る)
- 宮内佐夜香(2012).接続助詞とジャンル別文体的特徴の関連について:『現代日本語書き言葉均衡コーパス』を資料として 国立国語研究所論集,3,39-52.[PDF](CiNii Articles「現代日本語書き言葉均衡コーパス」で知る)
- 金城克哉(2012).「現代日本語書き言葉均衡コーパス」(BCCWJ)を利用した「くらい」・「ぐらい」の研究 九州地区国立大学間の連携に係る企画委員会リポジトリ部会,2.(CiNii Articles「現代日本語書き言葉均衡コーパス」で知る)
- 中溝朋子・坂井美恵子・金森由美(2012).現代日本語書き言葉均衡コーパスにおける漢語名詞「影響」のコロケーションの特徴:修飾語および述語動詞との共起を中心に 大学教育,9,78-85.(CiNii Articles「現代日本語書き言葉均衡コーパス」で知る)
- 柏野和佳子・奥村学(2012).和語や漢語のカタカナ表記:『現代日本語書き言葉均衡コーパス』の書籍における使用実態 計量国語学,4,153-161.(CiNii Articles「現代日本語書き言葉均衡コーパス」で知る)
- 金城克哉(2011).「現代日本語書き言葉均衡コーパス」(BCCWJ)を利用した「くらい」・「ぐらい」の研究 言語文化研究紀要,20,17-38.(CiNii Articles「現代日本語書き言葉均衡コーパス」で知る)
- 冨土池優美(2011).『現代日本語書き言葉均衡コーパス』における長単位の構成要素について 日本語の研究,2,104.(CiNii Articles「現代日本語書き言葉均衡コーパス」で知る)
- 黄慧(2011).現代日本語におけるオノマトペの「スル動詞化」について:現代日本語書き言葉均衡コーパスBCCWJを用いた調査を基に 言語・地域文化研究,17,77-94.(CiNii Articles「現代日本語書き言葉均衡コーパス」で知る)
- 村田年・山崎誠(2011).「手」の慣用句を指標とした文章ジャンルの判別:現代日本語書き言葉均衡コーパスを用いて 日本語と日本語教育,39,75-88.(CiNii Articles「現代日本語書き言葉均衡コーパス」で知る)
- 中溝朋子・坂井美恵子・金森由美・大岩幸太郎(2011).漢語名詞「進歩」と「向上」のコロケーションの異同について 大学教育,8,88-95.(CiNii Articles「現代日本語書き言葉均衡コーパス」で知る)
- 山崎誠(2011).文末表現の分布と文体:「現代日本語書き言葉均衡コーパス」を利用して Japio year book,280-283.(CiNii Articles「現代日本語書き言葉均衡コーパス」で知る)
- 李在鎬(2011).大規模テストの読解問題作成過程へのコーパス利用の可能性 日本語教育,84-98.[PDF](CiNii Articles「現代日本語書き言葉均衡コーパス」で知る)
- 柏野和佳子・奥村学(2010).国語辞典に「古い」と注記される語の現代書き言葉における使用傾向の調査 情報処理学会研究報告.CH,4,1-6.(CiNii Articles「現代日本語書き言葉均衡コーパス」で知る)
- 河内昭浩(2010).語彙を豊かにする作文指導:「コーパス」を活用した実践と今後の教材開発の可能性について 全国大学国語教育学会発表要旨集,119,186-189.(CiNii Articles「現代日本語書き言葉均衡コーパス」で知る)
- 西部みちる・小林正行・大島一(2010).メディア別外字表現の実態:『現代日本語書き言葉均衡コーパス』収録サンプルより ことば工学研究会,35-42.(CiNii Articles「現代日本語書き言葉均衡コーパス」で知る)
- 宮内佐夜香(2010).通時的変化を背景とした接続助詞ガとケレド類の機能についての調査:『現代日本語書き言葉均衡コーパス』を資料として 都大論究,47,1-15.(CiNii Articles「現代日本語書き言葉均衡コーパス」で知る)
- 宮内佐夜香(2010).丁寧体文内における従属句の文体と接続助詞について:『現代日本語書き言葉均衡コーパス』を資料として 日本語の研究,2,129.(CiNii Articles「現代日本語書き言葉均衡コーパス」で知る)
- 小木曽智信(2010).『現代日本語書き言葉均衡コーパス』における可能表現のバリエーション 日本語の研究,2,128.(CiNii Articles「現代日本語書き言葉均衡コーパス」で知る)
- 佐野大樹(2010).ブログにおける評価情報の分類と体系化:アプレイザル理論を用いて 電子情報通信学会技術研究報告.NLC, 言語理解とコミュニケーション,390,37-42.(CiNii Articles「現代日本語書き言葉均衡コーパス」で知る)
- 黄慧(2010).オノマトペの基本語彙に関する一考察:『現代日本語書き言葉均衡コーパス(2009モニター公開版)』を用いて 東京外国語大学日本研究教育年報,17-39.(CiNii Articles「現代日本語書き言葉均衡コーパス」で知る)
- 鄭惠先・小池真理・舩橋瑞貴(2009).『現代日本語書き言葉均衡コーパス』に見られる「~てならない」「~てたまらない」「~てしかたない」「~てしようがない」の使い分け:日本語学習者に対する指導への応用 北海道大学留学生センター紀要,13,4-21.(CiNii Articles「現代日本語書き言葉均衡コーパス」で知る)
- 宮内佐夜香・小木曽智信・小椋秀樹・小磯花絵(2009).『現代日本語書き言葉均衡コーパス』に現れる接続表現形式のジャンル別比較 日本語の研究,4,119-120.(CiNii Articles「現代日本語書き言葉均衡コーパス」で知る)
- 丸山岳彦(2009).作文の文体情報:『現代日本語書き言葉均衡コーパス』から見えるもの 日本語教育,140,26-36.(CiNii Articles「現代日本語書き言葉均衡コーパス」で知る)
- 柏野和佳子(2008).書籍の文章の多様性をとらえる観点付与の設計:『現代日本語書き言葉均衡コーパス』の収録文章を対象に ことば工学研究会:人工知能学会第2種研究会ことば工学研究会資料,3011-22.(CiNii Articles「現代日本語書き言葉均衡コーパス」で知る)
- 奥村学・白井清昭(2008).現代日本語書き言葉均衡コーパスを用いた意味解析:語義の自動特定、新語義の発見 言語,37(8),66-73.(CiNii Articles「現代日本語書き言葉均衡コーパス」で知る)
- 山崎誠・丸山岳彦・山口昌也・小椋秀樹・森本祥子・柏野和佳子・佐野大樹・高田智和・間淵洋子・北村雅則・小木曽智信・小磯花絵・冨士池優美・小沼悦・田中牧郎・前川喜久雄(2008).現代日本語書き言葉均衡コーパスの設計と検索デモンストレーション 日本語の研究,4(2),128-129.(CiNii Articles「現代日本語書き言葉均衡コーパス」で知る)
[2019.12.25]IRなどについての文献メモ 文献一覧を更新、内容をアップ<内部質保証、institutional effectiveness(IE)>
- Ayuk, P. T., & Jacobs, G. J. (2018). Developing a measure for student perspectives on institutional effectiveness in higher education. SA Journal of Industrial Psychology, 44(1), 1-12.[PDF](IEの概要を説明、学生の視点からIEに内在する要素を検討、学生のアウトカムをレビューを行い南アフリカの高等教育の文脈におけるIEの4つの指標を検討する;institutional effectiveness (IE) の概要を説明、学生の観点からIEの要素を検討、南アフリカの高等教育の文脈;Google Scholar「"institutional effectiveness"」で知る)
- Hwang, Y. (2019). Adoption of big data in higher education for better institutional effectiveness. American Journal of Creative Education, 2(1), 31-44.[PDF](高等教育システムのIEにビッグデータを用いるための概念モデルを検証する、モデルは主なステークホルダー(機関/教員/学生)の関係を扱う;Google Scholar「"institutional effectiveness"」で知る)
- Hanna, S. G. (2018). Faculty Perception of Organizational Culture and Institutional Effectiveness in Florida Colleges (Doctoral dissertation, Barry University).(全ての高等教育機関はIEを通じて認証評価機関やステークホルダーに説明責任を果たすことが求められている、各機関は組織管理やコンプライアンスに独自の文化を持っている、フロリダカレッジシステムにおいて教員(フルタイム/パートタイム)がIEにどのような認識を持っているかを定量的分析手法で検証、IE;Google Scholar「"institutional effectiveness"」で知る)
- Moye, J. N. (2019). A machine learning, artificial intelligence approach to institutional effectiveness in higher education. Bingley, UK: Emerald Group Publishing.(機関のパフォーマンスについて測定・評価・センスメインキングをするための実用的・効果的・体系的アプローチを提示する、アプローチにはカリキュラム/学習/インストラクション/支援サービス/プログラミングの実行可能性や環境スキャニングのパフォーマンスを測定・評価する手立てを含む;Google Scholar「"institutional effectiveness"」で知る)
- Laskin, M., & Zoe, L. (2017). Information literacy and institutional effectiveness: A longitudinal analysis of performance indicators of student success. CUNY Academic Works.[PDF](学生の成功に関する指標(リテンション率/卒業率/各種テストの合格率/GPA/取得単位)に潜在的に影響する要因を検討、都市部コミュニティカレッジの2,000人近くの学生を5年に渡り追跡調査、情報リテラシーのプログラムに参加した学生が全てのカテゴリーで成功する傾向が見られた;Google Scholar「"institutional effectiveness"」で知る)
- Nhung, P. T. T. (2018). Improving the Vietnamese Accreditation in Light of the SACSCOC's Institutional Effectiveness Standards. VNU Journal of Science: Education Research, 34(3).[PDF](ベトナムの高等教育のアクレディテーションの基準に米国のIEを実装できるかを検討、IEのプロセス(戦略的計画-計画と評価-業務計画)と評価サイクル(プログラムの学習成果-カリキュラムマップ-評価手法-データ収集-改善活動)の枠組みを用いた;Google Scholar「"institutional effectiveness"」で知る)
- Horn, A. S., Horner, O. G., & Lee, G. (2019). Measuring the effectiveness of two-year colleges: A comparison of raw and value-added performance indicators. Studies in Higher Education, 44(1), 151-169.(予測された卒業率と実際の卒業率の差を調べることでIEを評価することが多い、しかしその方法に信頼性・妥当性があるかについてはほとんど知られていない、そこで残差の分析で検証(対象は米国コミュニティカレッジ875校);Google Scholar「"institutional effectiveness"」で知る)
- Rizvi, S. A., & Jacobsen, T. E. (2017). Assessing the effectiveness of learning opportunities: Improving course availability through demand balancing. Journal of Academic Administration in Higher Education, 13(2), 49-56.[PDF](4年間での卒業率は高等教育聞機関の主要な指標となっている、しかし4年制のプログラムにおいて4年間で卒業する学生は30%未満であり低さの要因を検証する必要がある、高校生が大学で学ぶ準備ができていないことがよく議論されるがその準備の貧弱さは大学側がコントロールできない、大学がコントロールできるものとしてコースの履修可能性の重要性を指摘する;Google Scholar「"institutional effectiveness"」で知る)
- Gill, N. R.(2017). Empowering transformation through structure: Assessing effectiveness on the organizational placement of institutional researchers. All Theses And Dissertations, 117. [PDF](IR担当者の成功を促進させる要因について検証、調査によって中心的なリーダーとの近さ/監督者の強力な支援/行動の共有などの重要性が示された;Google Scholar「"institutional effectiveness"」で知る)
- Knight, W., & Tweedell, C. (2017). A national profile of vice presidents for institutional effectiveness. Association for Higher Education Effectiveness.[PDF](米国のIE担当副学長の役割/責任/知識・スキル/制度などを検討;Association for Higher Education Effectiveness(AHEE)の助成による調査、電話インタビューなどを実施;Google Scholar「"institutional effectiveness"」で知る)
[2019.12.25]IRなどについての文献メモ 文献一覧を更新<プレゼンテーション>
- 伊藤壮哉・山田篤志・菅野真功・小林稔(2019).プレゼンテーション支援を目的とした聴衆のうなずき誘発手法の検討 ワークショップ2019論文集,2019,39-44.[PDF]※2021年11月07日からダウンロード可能(CiNii Articles「プレゼンテーション」で知る)
- 北村雅則(2019).スマートフォンを用いた相互評価によるプレゼンテーションスキルの改善 日本教育工学会研究報告集,19(4),163-168.(CiNii Articles「プレゼンテーション」で知る)
- 中北美千子・山田真理・田中真理(2019).プレゼンテーション実技科目における「トレイト別フローチャート」を利用したピアフィードバックの試み 名古屋外国語大学論集,5,419-436.(CiNii Articles「プレゼンテーション」で知る)
- 加野まきみ・ピーター,ゴーベル(2019).プレゼンテーション授業における学習者相互評価モバイルアプリ使用とそれに対する学生の意識について 京都産業大学総合学術研究所所報,14, 47-61.[PDF](CiNii Articles「プレゼンテーション」で知る)
- 奥切恵(2019).日本人大学生による英語プレゼンテーションとアイコンタクト 聖心女子大学論叢,133,53-70.[PDF](CiNii Articles「プレゼンテーション」で知る)
- 徳久弘樹・大野直紀・中村聡史(2019).自身のみが聴取可能な音楽によるプレゼンテーション支援手法の提案 電子情報通信学会技術研究報告,119(38),45-50.(CiNii Articles「プレゼンテーション」で知る)
- 佐瀬竜一・松浦佳代・小倉久美子・松澤亜希子・八反田希望(2019).座談会 プレゼンテーションの準備を授業にどう活かすか:「プレゼンテーションを学ぶワークショップ」に参加して 看護教育,60(5),376-381.[PDF](CiNii Articles「プレゼンテーション」で知る)
- 佐瀬竜一(2019).教育や実践を豊かにするプレゼンテーション:「プレゼンテーションを学ぶワークショップ」の概要 看護教育,60(5),368-374.[PDF](CiNii Articles「プレゼンテーション」で知る)
- 八幡紕芦史(2019).プレゼンテーション力で授業を変える方法 看護教育,60(5),361-366.[PDF](CiNii Articles「プレゼンテーション」で知る)
- 吉澤みどり(2019).プレゼンテーション 地域保健,50(3),46-50.(CiNii Articles「プレゼンテーション」で知る)
- 正木幸子・横山宏・佐藤教子・中谷陽仁(2019).大学におけるプレゼンテーション教育手法の総合的検討 大阪商業大学論集,15(1),391-413.[PDF](CiNii Articles「プレゼンテーション」で知る)
- 稲葉みどり(2019).異文化探求の授業におけるグループ発表を自己評価する:振り返りによる学びの構築をめざして 愛知教育大学教職キャリアセンター紀要,4,69-76.(CiNii Articles「プレゼンテーション」で知る)
- 小林輝美(2019).自己の映像を利用した英語プレゼンテーション改善:映像撮影者の有無による自己評価の比較 日本教育工学会研究報告集,19(1),163-170.(CiNii Articles「プレゼンテーション」で知る)
- 小林真(2019).視覚障害者とプレゼンテーション技術 電子情報通信学会技術研究報告,118(491),95-98.(CiNii Articles「プレゼンテーション」で知る)
- 常山隆光(2019).英語で表現する力を高める指導の工夫:プレゼンテーションの活動を通して 研究紀要,123,125-136.(CiNii Articles「プレゼンテーション」で知る)
- 小里千寿(2019).プレゼンテーションにおけるコミュニケーション能力醸成についての一考察:社会人基礎力を指標とした能力の伸びとそのきっかけ 金沢学院短期大学紀要:学葉,17,1-11.(CiNii Articles「プレゼンテーション」で知る)
- 中嶋克成(2019).弱視シミュレーションを用いた主体的・協働的学びの実践:教養ゼミ「プレゼンテーション合同発表会」を通じて 徳山大学総合研究所紀要,41,93-100.(CiNii Articles「プレゼンテーション」で知る)
- 周康・兼松祥央・鶴田直也・近藤邦雄・三上浩司(2019).提示音と誘導点を用いたプレゼンテーション時の視線矯正VRシステム 映像情報メディア学会技術報告,43(9),85-88.(CiNii Articles「プレゼンテーション」で知る)
- Lai, W. L., Nilep, C, Weeks, M., Baumert, N., & Todayama, K. (2019). Implementing a logical thinking approach for education in research writing and presentation. 名古屋高等教育研究,19,267-293.[PDF](CiNii Articles「プレゼンテーション」で知る)
- 中馬成子・北島洋子・丸上輝剛・瀬山由美子(2019).基礎看護学における看護過程演習のグループワークによる主体的な学習態度の変化と看護過程の習得状況 奈良学園大学紀要,10,89-97.[PDF](CiNii Articles「プレゼンテーション」で知る)
- 戸羽俊介・橋本浩二(2019).効果的な遠隔プレゼンテーションの実現に向けた全方位視聴システム 第81回全国大会講演論文集,2019(1),237-238.[PDF](CiNii Articles「プレゼンテーション」で知る)
- 若山昇・立野貴之・河村一樹・飯箸泰宏(2019).大学生の非認知的能力の向上:「日常のなぜ」をクリティカルに探究する試み 帝京大学高等教育開発センターフォーラム,6,43-63.(CiNii Articles「プレゼンテーション」で知る)
- 小薬哲哉(2019).iPadを活用した英語ポスタープレゼンテーション:ICT支援英語アクティブラーニングの実践報告 サイバーメディア・フォーラム,19,19-24.[PDF](CiNii Articles「プレゼンテーション」で知る)
- 田原毅(2019).アクティブラーニング型授業におけるプレゼンテーション活動の実践 YASEELE,23,1-14.(CiNii Articles「プレゼンテーション」で知る)
- 山本恭子(2019).ルーブリックを活用した学生プレゼンテーションの教育効果 研究年報,26,7-18.(CiNii Articles「プレゼンテーション」で知る)
- 八木悠太朗・岡田将吾・塩原翔太・杉村聡太(2019).ビジネスプレゼンテーションにおける言語・非言語的能力の自動推定 人工知能学会全国大会論文集,JSAI2019,4F2OS11a02-4F2OS11a02.[PDF](CiNii Articles「プレゼンテーション」で知る)
- 柏原昭博・石野達也・後藤充裕(2019).プレゼンテーション動作を診断・再構成する講義代行ロボット 人工知能学会全国大会論文集,JSAI2019,1P3OS2104-1P3OS2104.[PDF](CiNii Articles「プレゼンテーション」で知る)
- 桐山聰・矢部玲子(2019).学生との協働によるプレゼンテーション評価ノートの開発 情報教育,1,33-35.[PDF](CiNii Articles「プレゼンテーション」で知る)
- 齋麻子(2019).プレゼンテーションスキル向上のための試み2:自主探究と直結した国語教育 八戸工業高等専門学校紀要,53,7-12.[PDF](CiNii Articles「プレゼンテーション」で知る)
- 佐藤賢一(2019).質問駆動型授業ハテナソンの生命科学教育への導入:京都産業大学総合生命科学部生命システム学科専門科目「腫瘍細胞生物学」における設計、実践、ならびに成果 高等教育フォーラム,9,71-85.[PDF](CiNii Articles「プレゼンテーション」で知る)
- 松岡みさ子(2018).プレゼンテーション力向上のためのスマートフォン効果的活用法:利便性を自己省察に活かして 大妻女子大学紀要.社会情報系,社会情報学研究,27,89-97.[PDF](CiNii Articles「プレゼンテーション」で知る)
- 堀越泉・田村恭久(2018).プレゼンテーション相互評価における学習者とティーチングアシスタントの評価行動の比較 日本教育工学会研究報告集,18(5),37-44.(CiNii Articles「プレゼンテーション」で知る)
- 天野由貴・隅谷孝洋・長登康・稲垣知宏(2018).「大学教育入門」における反転授業の実践:講義動画視聴記録とオンラインテスト受験記録の分析 大学ICT推進協議会年次大会論文集,2018.[PDF](CiNii Articles「プレゼンテーション」で知る)
- 難波功士(2018).プレゼンテーションの力が求められる時代に 児童心理,72(11),1163-1169.(CiNii Articles「プレゼンテーション」で知る)
- 松本華歩・栗原一貴(2018).Toolification of Gamesを活用したプレゼンテーション中の立ち位置移動トレーニングの提案 エンタテインメントコンピューティングシンポジウム2018論文集,2018,189-194.[PDF](CiNii Articles「プレゼンテーション」で知る)
- 林奈緒子(2018).シラバス変更によるプレゼンテーション授業の改善について:シラバス変更後に実施したアンケート調査をもとに 越谷情報センター年報,3,2-16.[PDF](CiNii Articles「プレゼンテーション」で知る)
- 前田和昭(2018).Webを活用したプレゼンテーションソフトウェアに関する検討 産業経済探究,1,43-55.(CiNii Articles「プレゼンテーション」で知る)
- 佐藤剛(2018).聞き手を意識したプレゼンテーションの指導実践:「話し手」と「聞き手」の相乗効果を得る 弘前大学教養教育開発実践ジャーナル,2,61-73.[PDF](CiNii Articles「プレゼンテーション」で知る)
- 佐野香織(2018).プレゼンテーション活動における評価項目 学習者自己作成の試み:学習プロセスに自律的評価活動を組み込む実践事例 早稲田日本語教育実践研究,6,109-110.[PDF](CiNii Articles「プレゼンテーション」で知る)
- 柏原昭博・稲澤佳祐(2018).先進的学習科学と工学研究会,82,91-96.(CiNii Articles「プレゼンテーション」で知る)
- 後藤充裕・石野達也・稲澤佳祐・松村成宗・布引純史・柏原昭博(2018).聴衆のプレゼンテーション理解を促進するロボットの非言語動作の検証 先進的学習科学と工学研究会,82,13-18.(CiNii Articles「プレゼンテーション」で知る)
- 上野亮・飯島泰裕(2018).電子図書館を活用したプレゼン教育に関する研究 第80回全国大会講演論文集,2018(1),479-480.[PDF](CiNii Articles「プレゼンテーション」で知る)
- 五十嵐真人(2018).アカデミックライティング・アカデミックプレゼンテーション実施報告 調査資料,254,79-89.(CiNii Articles「プレゼンテーション」で知る)
- 大塚誠也(2018).状況対応力を養成する対照的なプレゼンテーション:「商品紹介」と「研究発表」 早稲田大学国語教育研究,38,72-81.(CiNii Articles「プレゼンテーション」で知る)
- 大山真司・山崎俊彦・相澤清晴(2018).プレゼンテーションスライドのデザインに対するCNNを用いた客観的フィードバックの生成 電子情報通信学会技術研究報告,117(432),223-228.(CiNii Articles「プレゼンテーション」で知る)
- 森本敦司・笹原康孝(2018).「プレゼンテーション演習」受講生に対するアンケート調査報告 常磐短期大学研究紀要,46,115-126.(CiNii Articles「プレゼンテーション」で知る)
- 橋本はる美・堀井千夏・栢木紀哉(2018).反転授業による情報リテラシー教育の実践と評価 経営情報研究:摂南大学経営学部論集,25(1・2),43-54.[PDF](CiNii Articles「プレゼンテーション」で知る)
- 笠巻知子(2018).学生の「プレゼンテーション力」は,評価者としての学生の評価力に影響を及ぼすか? Language education & technology,55,97-122.(CiNii Articles「プレゼンテーション」で知る)
- 山本恭子・上野真由美(2018).ルーブリックを活用したプレゼンテーション評価シートの設計 研究年報,25,43-53.(CiNii Articles「プレゼンテーション」で知る)
- 矢野香(2018).自己評価の介入によるプレゼンテーションスキル向上:モニタリング訓練とモデリング訓練導入による他者評価との一致 応用心理学研究,44(1),34-50.[PDF](CiNii Articles「プレゼンテーション」で知る)
- 田中裕実(2018).ICTを活用した主体的な英語プレゼンテーション活動の実践 中部地区英語教育学会紀要,47,229-236.[PDF](CiNii Articles「プレゼンテーション」で知る)
- 福田昇(2018).学習単元のまとめで行うプレゼンテーション活動でピア評価が与える学習効果 全国英語教育学会紀要,29,257-272.[PDF](CiNii Articles「プレゼンテーション」で知る)
- 滝麻衣(2018).プレゼンテーションに向けた授業での効果的な協働学習を目指して 国際教養大学専門職大学院グローバル・コミュニケーション実践研究科日本語教育実践領域実習報告論文集,9,117.(CiNii Articles「プレゼンテーション」で知る)
- 趙新博・由井薗隆也・宗森純(2018).初心者向けプレゼンテーション練習支援システムPRESENCEの開発と評価 電気学会論文誌.C,138(10),1269-1277.[PDF](CiNii Articles「プレゼンテーション」で知る)
- 嶋津章仁・日永田智絵・長井隆行・中村友昭・武田祐樹・原豪紀・中川修・前田強(2018).系列変換モデルを用いたプレゼンテーション動作の生成 人工知能学会全国大会論文集,JSAI2018,2G103.[PDF](CiNii Articles「プレゼンテーション」で知る)
- 中野美香(2018).大学におけるプレゼンテーションの学びとは:「プレゼンテーション基礎」の受講者の分析を通して 基幹教育紀要,4,7-22.[PDF](CiNii Articles「プレゼンテーション」で知る)
- 松原悠・斎藤未夏・石津朋之・大山貴稔・佐藤まみ子・新村麻実・野村港二(2017).筑波大学中央図書館ラーニング・コモンズにおける大学院共通科目「ザ・プレゼンテーション」の実施 大学図書館研究,107,1-11.[PDF](CiNii Articles「プレゼンテーション」で知る)
- 小山義徳(2017).学生の情報収集,パワーポイント作成,プレゼンテーションスキルの向上を目的としたパワーポイント・ディベートの実践 千葉大学教育学部研究紀要,66(1),317-320.[PDF(CiNii Articles「プレゼンテーション」で知る)
- 石野達也・後藤充裕・柏原昭博(2017).代講を目的としたロボットによるプレゼンテーション 先進的学習科学と工学研究会,81,26-29.(CiNii Articles「プレゼンテーション」で知る)
- 北林茉莉代(2017).グループプレゼンテーションを中心とした授業実践報告:「TED紹介」から「レポート執筆」まで 大正大学教育開発推進センター年報,2,16-22.(CiNii Articles「プレゼンテーション」で知る)
- 田中佐代子・小林麻己人・三輪佳宏(2017).研究者のためのビジュアルデザイン:「ビジュアルデザインハンドブック」の有用性 科学技術コミュニケーション,21,41-57.[PDF](CiNii Articles「プレゼンテーション」で知る)
- 和上順子(2017).アクティブ・ラーニングにおける効果的なプレゼンテーションスキル 広島文教グローバル,1,63-75.[PDF](CiNii Articles「プレゼンテーション」で知る)
- 下野正代(2017).ICTを活用した教育プレゼンテーション能力の育成:「教育の方法と技術」「教科の指導法」「アクティブ・ラーニング」 情報学研究,26,1-13.[PDF](CiNii Articles「プレゼンテーション」で知る)
- 髙橋雅子・杉本美穂・飛田美穂・山方純子(2017).プレゼンテーション活動におけるルーブリックの作成と活用:公平な評価と学習者への指標の明示化を目指して 早稲田日本語教育実践研究,5,189-190.[PDF](CiNii Articles「プレゼンテーション」で知る)
- 小野瀬泰祐・松浦友紀・米谷雄介・永岡慶三(2017).ニコニコ動画を用いた自己評価と他者評価の一致度の提案とプレゼンテーション改善との関連性 電子情報通信学会技術研究報告,116(517),19-24.(CiNii Articles「プレゼンテーション」で知る)
- 坂井敬子・山本好比古・山本隆太・須藤智(2017).地域課題を題材とした初年次科目「プレゼンテーション入門」の実践報告:静岡大学新設の地域創造学環における試み 静岡大学教育研究,13,83-88.[PDF](CiNii Articles「プレゼンテーション」で知る)
- 倉田伸・藤木卓・室田真男(2017).モバイル端末でプレゼンテーションの相互評価を実現するビデオプレゼンテーション評価システムの開発と実践 日本教育工学会研究報告集,17(1),553-556.(CiNii Articles「プレゼンテーション」で知る)
- 森玲奈(2017).大学生の参画意識を促す講義と評価のデザイン:プレゼンテーション教育の事例に着眼して 日本教育工学会研究報告集,17(1),399-402.(CiNii Articles「プレゼンテーション」で知る)
- 徳永悠作・小尻智子(2017).プレゼンテーションスキル育成のためのコンテンツ印象診断システム 日本教育工学会研究報告集,17(1),69-76.(CiNii Articles「プレゼンテーション」で知る)
- 山鹿貴史(2017).八洲学園大学におけるプレゼンテーション教育の実践:eラーニングとその課題 八洲学園大学紀要,13,21-26.[PDF](CiNii Articles「プレゼンテーション」で知る)
- 大曽根匡(2017).情報リテラシ教育におけるプレゼンテーションとディベート 専修大学情報科学研究所所報,89,27-30.[PDF](CiNii Articles「プレゼンテーション」で知る)
- 中島昭・小谷侑・菅沼由唯・長崎弘・原田信広・吉田友昭・稲垣秀人・土田邦博・山口央輝・近藤一直・宮地栄一・飯塚成志・池本和久・石原悟・大熊真人・金子葉子・河合房夫(2017).プレゼンテーション評価シートの導入による学生発表会の改善 医学教育,48(5),323-325.[PDF](CiNii Articles「プレゼンテーション」で知る)
- 上山輝(2017).デザイン教育の視点からみる一般学生のプレゼンテーションポスター制作と評価 美術教育学研究,49(1),121-128.[PDF](CiNii Articles「プレゼンテーション」で知る)
- 森本康裕(2017).伝わるプレゼンテーションのありかた「ポイントを絞って文字数を減らせ」 日本臨床麻酔学会誌,37(1),116-120.[PDF](CiNii Articles「プレゼンテーション」で知る)
- 讃岐美智義(2017).そのプレゼンテーションのゴールはなにか? 日本臨床麻酔学会誌,37(1),125-130.[PDF](CiNii Articles「プレゼンテーション」で知る)
- 上嶋浩順(2017).伝えるプレゼンテーションに必要な3つの要素 日本臨床麻酔学会誌,37(1),131-135.[PDF](CiNii Articles「プレゼンテーション」で知る)
- 山下祐一郎・中島平(2016).プレゼンテーション型アクティブラーニングの実践に関する検討:教員養成課程の学生を対象とした予備実験 教育情報学研究,15,1-7.[PDF](CiNii Articles「プレゼンテーション」で知る)
- 横山宏(2017).プレゼンテーション能力の教育手法:基礎・基本に特化した教育手法の概観 情報文化学会誌,23(2),67-70.(CiNii Articles「プレゼンテーション」で知る)
[2019.12.18]IRなどについての文献メモ 文献一覧を更新、内容をアップ<内部質保証、institutional effectiveness(IE)>
- Vroeijenstijn, A. I. (1995). Improvement and accountability: Navigating between Scylla and Charybdis. Guide for external quality assessment in higher education. Bristol, PA: Taylor and Francis.(ガイドによって高等教育機関向けの外部品質評価(EQA)システムの設計についてアドバイスと推奨事項を提供;Google Scholar「Defining quality(Harvey & Green, 1993)の引用論文検索」で知る)
- Lagrosen, S., Seyyed‐Hashemi, R., & Leitner, M. (2004). Examination of the dimensions of quality in higher education. Quality Assurance in Education, 12(2), 61-69.(高等教育の質を構成する次元を検証、一般的なサービスの品質と比較、詳細なインタビューの結果を基にしてアンケート調査を実施(オーストリアとスウェーデンの学生448名が対象)、因子分析で高等教育の質の次元を定義;Google Scholar「Defining quality(Harvey & Green, 1993)の引用論文検索」で知る)
- Voss, R., Gruber, T., & Szmigin, I. (2007). Service quality in higher education: The role of student expectations. Journal of Business Research, 60(9), 949-959.[PDF](学生が教員に求める資質をインタビューと質問紙で検証、知識・熱意・親しみやすさなどを求めている;Google Scholar「Defining quality(Harvey & Green, 1993)の引用論文検索」で知る)
- Srikanthan, G., & Dalrymple, J. (2003). Developing alternative perspectives for quality in higher education. International Journal of Educational Managementh, 17(3), 126-136.(高等教育の質についての議論が工業分野の質を対象にしている、高等教育の分野において90年代以前には品質管理(QC)の手法が導入されたが表面的だった、90年代以降は品質マネジメント(QM)の手法が好まれるようになった、現在は管理主義に陥っている、学問の自由と大学の運営についての伝統的価値を維持できるようにQMを教育のプロセスに適応させるべき;Google Scholar「Defining quality(Harvey & Green, 1993)の引用論文検索」で知る)
- Tam, M. (2001). Measuring quality and performance in higher education. Quality in Higher Education, 7(1), 47-54.(高等教育の質についての考え方を分析、質を測定する様々なモデルを検証、'production model'(インプットとアウトプットの直接的な関係)/'value-added approach'(高等教育を受ける前後の利益)/'total quality experience approach'(大学での学習経験全体を捉える);Google Scholar「Defining quality(Harvey & Green, 1993)の引用論文検索」で知る)
- Harvey, L., & Stensaker, B. (2008). Quality culture: Understandings, boundaries and linkages. European Journal of Education, 43(4), 427-442.[PDF](「質の文化」は高等教育で当たり前の概念となっている、質の文化が質/質の改善/質保証とどのように関係するか理論的アプローチで検証する;Google Scholar「Defining quality(Harvey & Green, 1993)の引用論文検索」で知る)
- Houston, D. (2008). Rethinking quality and improvement in higher education. Quality Assurance in Education, 16(1), 61-79.(高等教育の質に対する主要な概念とアプローチを批判的にレビューする、質についての活動の焦点を説明責任・管理から改善に移すアプローチを提案;Google Scholar「Defining quality(Harvey & Green, 1993)の引用論文検索」で知る)
- Venkatraman, S. (2007). A framework for implementing TQM in higher education programs. Quality Assurance in Education, 15(1), 92-112.(高等教育にTQMのフレームワークを提供する、TQMの考え方や工業/高等教育への適応に関する文献の調査により理論的・実践的背景を提供、7つの手順のコース評価プロセスによる実践的なガイドラインを提供;Google Scholar「Defining quality(Harvey & Green, 1993)の引用論文検索」で知る)
- Harvey, L. (2005). A history and critique of quality evaluation in the UK. Quality Assurance in Education, 13(4), 263-276.(1980年代中頃から質のシステムが出現し高等教育政策の主要な関心事になっていった歴史を描く、英国の質管理システムは変容する学習と教授に関与することができなかった;Google Scholar「Defining quality(Harvey & Green, 1993)の引用論文検索」で知る)
- Rhoades, G., & Sporn, B. (2002). Quality assurance in Europe and the US: Professional and political economic framing of higher education policy. Higher Education, 43(3), 355-390.([米国と欧州の2国間]と[欧州内とくにドイツとオーストリア]における質保証のモデルと実践についての研究、世界的な普及と地域による違いを検証;Google Scholar「Defining quality(Harvey & Green, 1993)の引用論文検索」で知る)
- Mishra, S. (2007). Quality assurance in higher education: An introduction. India: National Assessment and Accreditation Council.[PDF](インドにおけるCommonwealth of Learning(COL)の3か年計画(2006-2009年)の主要な取り組みのひとつに教育部門の質保証がある、近年National Assessment and Accreditation Council(NAAC)は質保証システムの全てのレベルでの人材育成を行った;Google Scholar「Defining quality(Harvey & Green, 1993)の引用論文検索」で知る)※参考:「インドの高等教育の質保証が加速か―UGCが認証評価機関の増加へ乗り出す」(大学改革支援・学位授与機構評価事業部国際課「QA UPDATES」、2018年10月10日)
- Harvey, L. (2002). Evaluation for what? Teaching in Higher Education, 7(3), 245-263.[PDF](外部評価による質のモニタリングについて外部機関・用いられる手法・評価する理由を検討、外部評価は現状を正当化するだけで学習の本質について検証していない、また方法論に気を取られ学習理論の進展などを考慮できていない、外部評価機関は説明責任・コンプライアンス志向から学習の改善を問うアプローチに移行する必要がある;Google Scholar「Defining quality(Harvey & Green, 1993)の引用論文検索」で知る)
- Harvey, L. (1998). An assessment of past and current approaches to quality in higher education. Australian Journal of Education, 42(3), 237-255.(Google Scholar「Defining quality(高等教育分野での「質」とは何であるかがほとんど検討されていない、そのため質のモニタリングについて手法の理論的根拠が検討されていない、質のモニタリングは改善よりも説明責任が強調されている;Harvey & Green, 1993)の引用論文検索」で知る)
- Srikanthan, G., & Dalrymple, J. F. (2007). A conceptual overview of a holistic model for quality in higher education. International Journal of Educational Management, 21(3), 173-193.(高等教育の質についての議論を包括的に扱えるフレームワークを提供、マネージメントの様々なアプローチの統合を試みる;Google Scholar「Defining quality(Harvey & Green, 1993)の引用論文検索」で知る)
- Van Kemenade, E., Pupius, M., & Hardjono, T. W. (2008). More value to defining quality. Quality in Higher education, 14(2), 175-185.(教育の質には様々な定義がある、Garvin(1984)の5つのアプローチ(the transcendental approach, the product‐oriented approach, the customer‐oriented approach, the manufacturing‐oriented approach and the value‐for‐money approach)、Harvey and Green(1993)の5つの概念(exceptional, perfection (or consistency), fitness for purpose, value for money and transformative)、高等教育における近年の質の議論を説明するためには新たな定義が必要、4つの構成要素から成る質の概念(object, standard, subject and values)について記述する、4つの価値システム(control, continuous improvement, commitment and breakthrough)によって近年の質のマネジメントについての説明が可能となる;Google Scholar「Defining quality(Harvey & Green, 1993)の引用論文検索」で知る)
- Harvey, L. (1995). Beyond tqm. Quality in Higher Education, 1(2), 123-146.[PDF](TQMを高等教育の文脈に適用することについて検討、適用ができないことを分析するのではなく適用可能な面があることを示す;Google Scholar「Defining quality(Harvey & Green, 1993)の引用論文検索」で知る)
- Stensaker, B. R. (2008). Outcomes of quality assurance: A discussion of knowledge, methodology and validity. Quality in Higher Education, 14(1), 3-13.(質保証の枠組みにおける組織変革について議論;Google Scholar「Defining quality(Harvey & Green, 1993)の引用論文検索」で知る)
- Stensaker, B. (2007). Quality as fashion: Exploring the translation of a management idea into higher education. In Quality assurance in higher education (pp. 99-118). Dordrecht: Springer.[PDF](質の概念は過去20年で最も支配的で影響のある'meta-idea'のひとつ、高等教育において質の概念が用いられるようになった理由を解説;Google Scholar「Defining quality(Harvey & Green, 1993)の引用論文検索」で知る)
- Cameron, K. S. & Whetten, D. A. (1996). Organizational effectiveness and quality: The second generation. In Smart, J. C. (Ed.). Higher education: Handbook of theory and research, vol. XI(pp.265–306). New York: Agathon Press.(米国において質の概念はeffectivenessの代わりに機関レベルの主要な要素になった;Stensaker(2007)"Quality as fashion"で知る)
- Rowley, J. (1996). Measuring quality in higher education. Quality in Higher Education, 2(3), 237-255.(サービスの分野で「質」を測定する場合は「サービスの質とは何か」「何を測ろうとしているのか」「質の測定とそれに続く改善はどのような関係があるのか」などを意識することが重要、教育やサービスの分野に適用される質の測定についての文脈を検討する(理論と実践をレビューする)、教育とサービスの分野はお互いに貢献できる一方でそれぞれに固有の議論がある;Google Scholar「Defining quality(Harvey & Green, 1993)の引用論文検索」で知る)
- Pratasavitskaya, H., & Stensaker, B. R. (2010). Quality management in higher education: towards a better understanding of an emerging field. Quality in Higher Education, 16(1), 37-50.(高等教育研究において品質管理がどのように理解されているかについて分析する、1995–2008年のQuality in Higher Education誌を使用、中心概念を特定して品質管理の研究分野で共通して検討されていることがあるかを検証する;Google Scholar「Defining quality(Harvey & Green, 1993)の引用論文検索」で知る)
- Gvaramadze, I. (2008). From quality assurance to quality enhancement in the European Higher Education Area. European Journal of Education, 43(4), 443-455.(欧州高等教育圏での質向上を促進する方法や大学の質の文化への影響を分析、機関レベル/プログラムレベルの質向上アプローチの両方について議論、質の文化に関する現在のアプローチは質保証から文脈の質向上に焦点を移してきている;Google Scholar「Defining quality(Harvey & Green, 1993)の引用論文検索」で知る)
- Schindler, L., Puls-Elvidge, S., Welzant, H., & Crawford, L. (2015). Definitions of quality in higher education: A synthesis of the literature. Higher Learning Research Communications, 5(3), 3-13.[PDF](高等教育における質の定義について先行研究を統合する、多様な地域の異なる種類の大学に適用できる普遍的な質の定義を定めるためにはより多くの研究が必要、研究の中で質保証とアクレディテーションの関係が曖昧;Google Scholar「Defining quality(Harvey & Green, 1993)の引用論文検索」で知る)
- Boyle, P., & Bowden, J. A. (1997). Educational quality assurance in universities: An enhanced model. Assessment & Evaluation in Higher Education, 22(2), 111-121.(過去10年ほどで高等教育に関連する様々な分野での質保証の文献が急増した、多くの機関で質保証のアプローチは発展しているものの断片的/体系的でない/計画性に乏しく統合されていないアプローチが今でも一般的、質保証と高等教育の文化に関する文献から主要なアイデアを抽出して教育の質保証のモデルを提唱する;Google Scholar「Defining quality(Harvey & Green, 1993)の引用論文検索」で知る)
- Craft, A. (Ed.). (2018). International developments in assuring quality in higher education (Vol. 6). London: Routledge.(1993年にカナダで開催された国際会議(高等教育質保証機関の国際的ネットワーク;International Network for Quality Assurance Agencies in Higher Education (INQAAHE) )の論文集;Google Scholar「Defining quality(Harvey & Green, 1993)の引用論文検索」で知る)
- Elassy, N. (2015). The concepts of quality, quality assurance and quality enhancement. Quality Assurance in Education, 23(3), 250-261.(高等教育における質/質保証/質向上の概念に関する様々な定義を批判的な視点でレビュー、質保証と質向上は連続体の一部として扱うべき、また両者はともに高等教育における進行中のプロセスにとって必要;Google Scholar「Defining quality(Harvey & Green, 1993)の引用論文検索」で知る)
- Sakthivel, P. B., & Raju, R. (2006). Conceptualizing total quality management in engineering education and developing a TQM educational excellence model. Total Quality Management & Business Excellence, 17(7), 913-934.(TQMは産業や企業に限定されたものではない、米国や英国などの先進国において高等教育の分野でうまく適用されている、先行文献のレビューによりモデルを提案;Google Scholar「Defining quality(Harvey & Green, 1993)の引用論文検索」で知る)
- Westerheijden, D. F. (1999). Where are the quantum jumps in quality assurance? Higher Education, 38(2), 233-254.(欧州における教育の質保証に関する過去10年の文献をレビュー、実践から理論までを扱う、理論面で近年飛躍的な発展があったことを示す:Google Scholar「Defining quality(Harvey & Green, 1993)の引用論文検索」で知る)
- Westerheijden, D. F. (2007). States and Europe and quality of higher education. In Westerheijden, D. F., Stensaker, B., & Rosa, M. J. Quality assurance in higher education (pp. 73-95). Dordrecht: Springer.(質保証がマクロ/メゾ/ミクロレベルでの高等教育のパフォーマンスにどのように影響を与えたかを検証、新古典派経済学の理論に基づいて考察、外部の関係者(質保証機関/省庁/超国家機関など)の考える質の概念によって高等教育機関のパフォーマンスが決まる;Google Scholar「Defining quality(Harvey & Green, 1993)の引用論文検索」で知る)
- Ryan, T. (2015). Quality assurance in higher education: A review of literature. Higher Learning Research Communications, 5(4).[PDF](質保証の文献レビュー、グローバルな高等教育における質保証のメカニズムとしてアクレディテーションについて概観する、学生参加に焦点を絞って質保証の実践の効果をレビューする、質保証には統一された定義・モデルがなく共通の枠組みが必要、学生が高等教育の中心で時間と資金を投資していると考えると学生の関与によって質保証プロセスは改善する;Google Scholar「Defining quality(Harvey & Green, 1993)の引用論文検索」で知る)
- Teeroovengadum, V., Kamalanabhan, T. J., & Seebaluck, A. K. (2016). Measuring service quality in higher education: Development of a hierarchical model (HESQUAL). Quality Assurance in Education, 24(2), 244-258.(高等教育のサービスの質を測定するための階層モデルを開発して実証的にテストする、定性的手法と文献レビューによって53の属性から成るサービスの質の概念モデルを開発、定量的手法(因子分析)で階層モデルを評価、最終的なモデルの構成要素はadministrative quality, physical environment quality, core educational quality, support facilities quality and transformative qualityであった;Google Scholar「Defining quality(Harvey & Green, 1993)の引用論文検索」で知る)
[2019.12.11]IRなどについての文献メモ 文献一覧を更新<内部質保証、institutional effectiveness(IE)>
- Sutherland, D. (2017). Institutional Effectiveness Assessment 2016-17 Annual Report.[PDF](Google Scholar「"institutional effectiveness"」で知る)
- Ayuk, P. T., & Jacobs, G. J. (2018). Developing a measure for student perspectives on institutional effectiveness in higher education. SA Journal of Industrial Psychology, 44(1), 1-12.[PDF](institutional effectiveness (IE) の概要を説明、学生の観点からIEの要素を検討、南アフリカの高等教育の文脈;Google Scholar「"institutional effectiveness"」で知る)
- Temple, P. (2018). Space, place and institutional effectiveness in higher education. Policy reviews in higher education, 2(2), 133-150.(Google Scholar「"institutional effectiveness"」で知る)
- Hwang, Y. (2019). Adoption of big data in higher education for better institutional effectiveness. American Journal of Creative Education, 2(1), 31-44.[PDF](Google Scholar「"institutional effectiveness"」で知る)
- Hanna, S. G. (2018). Faculty Perception of Organizational Culture and Institutional Effectiveness in Florida Colleges (Doctoral dissertation, Barry University).(Google Scholar「"institutional effectiveness"」で知る)
- Moye, J. N. (2019). A machine learning, artificial intelligence approach to institutional effectiveness in higher education. Bingley, UK: Emerald Group Publishing.(Google Scholar「"institutional effectiveness"」で知る)
- Smieszek, M. (2019). Evaluating institutional effectiveness: the case of the Arctic Council. The Polar Journal, 1-24.(Google Scholar「"institutional effectiveness"」で知る)
- Laskin, M., & Zoe, L. (2017). Information literacy and institutional effectiveness: A longitudinal analysis of performance indicators of student success. CUNY Academic Works.[PDF](Google Scholar「"institutional effectiveness"」で知る)
- Nhung, P. T. T. (2018). Improving the Vietnamese Accreditation in Light of the SACSCOC's Institutional Effectiveness Standards. VNU Journal of Science: Education Research, 34(3).[PDF](Google Scholar「"institutional effectiveness"」で知る)
- Horn, A. S., Horner, O. G., & Lee, G. (2019). Measuring the effectiveness of two-year colleges: A comparison of raw and value-added performance indicators. Studies in Higher Education, 44(1), 151-169.(Google Scholar「"institutional effectiveness"」で知る)
- Rizvi, S. A., & Jacobsen, T. E. (2017). Assessing the effectiveness of learning opportunities: Improving course availability through demand balancing. Journal of Academic Administration in Higher Education, 13(2), 49-56.[PDF](Google Scholar「"institutional effectiveness"」で知る)
- Gill, N. R.(2017). Empowering transformation through structure: Assessing effectiveness on the organizational placement of institutional researchers. All Theses And Dissertations, 117. [PDF](Google Scholar「"institutional effectiveness"」で知る)
- Knight, W., & Tweedell, C. (2017). A national profile of vice presidents for institutional effectiveness. Association for Higher Education Effectiveness.[PDF](Google Scholar「"institutional effectiveness"」で知る)
- Romich, R. J. (2018). Faculty Perceptions of Institutional Effectiveness Practices and Measures. Unpublished doctoral dissertation, North Carolina State University, Raleigh, NC.[PDF](Google Scholar「"institutional effectiveness"」で知る)
[2019.12.9]IRなどについての文献メモ 内容をアップ
[2019.12.7]IRなどについての文献メモ 文献一覧を更新<内部質保証>
- Harvey, L., & Green, D.(1993). Defining quality. Assessment & Evaluation in Higher Education, 18(1), 9-26.(高等教育における質の概念を5つに分類(非凡さ・完全性(整合性)・目的適合性・資金に見合う価値・変容)、後続の多くの研究で参照されている;林(2018)「内部質保証システムの概念と要素」で知る)
- The Danish Evaluation Institute.(2003). Quality procedures in European Higher Education: An ENQA survey. European Network for Quality Assurance in Higher Education.[PDF](欧州各国の質保証機関を対象にした調査、2003年に実施、プログラム単位の外部質保証に焦点を置いていた(プログラム単位の質保証を実施:83%、機関単位の質保証を実施:53%);林(2018)「内部質保証システムの概念と要素」で知る)
- Grifoll, J., Hopbach, A., Kekalainen, H., Lugano, N., Rozsnyai, C., & Shopov, T. (2012). Quality procedures in the European Higher Education Area and beyond - Visions for the future: Third ENQA survey. European Network for Quality Assurance in Higher Education.[PDF](欧州各国の質保証機関を対象にした調査、2012年に実施、外部質保証が機関単位にシフト(プログラム単位の質保証を実施:84%、機関単位の質保証を実施:72%);林(2018)「内部質保証システムの概念と要素」で知る)
- Sursock, A.(2012). Quality assurance and the European transformational agenda. In A. Curaj, P. Scott, L. Vlasceanu, & L. Wilson(Eds.), European higher education at the crossroads: Between the Bologna Process. 247-265. Dordrecht: Springer.(欧州では機関としてのアイデンティティが弱くプログラム中心で質保証が形成されてきた;林(2018)「内部質保証システムの概念と要素」で知る)
[2019.12.3]IRなどについての文献メモ 文献一覧を更新<内部質保証>
[2019.12.3]IRなどについての文献メモ 文献一覧を更新<専門職>
- 二宮祐・小島佐恵子・児島功和・小山治・浜島幸司(2019).大学における新しい専門職のキャリアと働き方:聞き取り調査の結果から 大学評価・学位研究,20,1-25.[PDF](「第三の領域」で働く新しい専門職のキャリアと職務に関する意識についての聞き取り調査、対象はファカルティ・デベロッパー(3名)、キャリア支援・教育担当者(3名)、IR担当者(3名)、URA(2名)、産官学コーディネート担当者(3名);大学評価・学位研究バックナンバーで知る)
[2019.11.7]IRなどについての文献メモ 文献一覧を更新<IR、質保証、高等教育>
- 山岸直司(2014).米国高等教育における学習成果アセスメント:背景・論理・政治プロセス 博士論文(東京大学)(Twitter(@high190さん)で知る)
- 藤原僚平・齋藤渉・上畠洋佑(2019).大学への調査の実態把握に関するパイロット分析:A大学における調査負担可視化の試み 大学評価とIR,11,3-14.[PDF]
- 大森不二雄(2006).教育の質保証と戦略的経営:教授システム学専攻の試み アルカディア学報,254.(Twitter(@high190さん)で知る)
- 坂本健成(2019).アセスメント・ポリシー策定に向けて:愛媛大学・北海道大学・関西国際大学の事例から 流通科学研究,19(1),89-101.[PDF](Twitter(@daigaku23さん)で知る)
- 加藤諭(2019).大学アーカイブズの成立と展開:公文書管理と国立大学 吉川弘文館(Twitter(@nekonoizumiさん)で知る)
- 住吉廣行(2019).今、取り組むべき優先課題を見極めるためのIR Between,287,32-33.[PDF]
- 高等教育のあり方研究会教育プログラム評価のあり方に関する調査研究部会(2019).教育プログラム評価ハンドブック 大学基準協会(大阪市立大学第27回教育改革シンポジウムの鳥居朋子先生(立命館大学)ご講演で知る)
- Muller, Jerry Z.松本裕(訳)(2019).測りすぎ:なぜパフォーマンス評価は失敗するのか? みすず書房(教学マネジメント特別委員会(第7回)会議議事録で知る)
- 秦由美子(2014).イギリスの大学:対位線の転位による質的転換 東信堂(四天王寺大学図書館書架で知る)
- Sanderson, M.安原義仁(訳)(2003).イギリスの大学改革:1809-1914 玉川大学出版部(Amazon.co.jp「内部質保証」で知る)
- 旺文社(編)(2019) .2020年用:大学の真の実力:情報公開BOOK 旺文社
- 小林信一(2019).基礎から学び直す大学制度 法政大学教育研究,10,80-94.(広島大学高等教育研究センターからのお知らせで知る)
- 村田直樹(2017).英国における高等教育質保証制度に関する研究 放送大学審査学位論文(博士)(Google「"英国の大学の質保証システムと学習成果アセスメント"」で知る)[PDF]
- 深堀聰子(2012).国立教育政策研究所プロジェクト研究(研究代表者:深堀聰子)研究成果報告書 学習成果アセスメントのインパクトに関する総合的研究[PDF]
- 大森不二雄(2012).英国の大学の質保証システムと学習成果アセスメント 国立教育政策研究所プロジェクト研究(研究代表者:深堀聰子)研究成果報告書 学習成果アセスメントのインパクトに関する総合的研究,72-105.(Google「"UK Quality Code for Higher Education"」で知る)[PDF]
[2019.11.7]IRなどについての文献メモ 文献一覧を更新<言語学>
[2019.11.7]IRなどについての文献メモ 文献一覧を更新<学習心理学、その他>
[2019.11.6]IRなどについての文献メモ 文献一覧を更新<データリテラシー>
- 溝上智恵子・大学図書館研究グループ(2019).データリテラシーの論点整理 図書館界,71(2),129-134.[PDF]
[2019.11.6]IRなどについての文献メモ 内容をアップ
- 大森不二雄(2014).教学マネジメントをめぐる日・英の政策動向:「経営」は「質保証」をもたらすか 高等教育研究,17,9-30.[PDF][内容](Google「"UK Quality Code for Higher Education"」で知る)
[2019.11.6]IRなどについての文献メモ 文献一覧を更新<高等教育>
- 大森不二雄(2014).教学マネジメントをめぐる日・英の政策動向:「経営」は「質保証」をもたらすか 高等教育研究,17,9-30.[PDF](Google「"UK Quality Code for Higher Education"」で知る)
- 大森不二雄(2012).英国における大学経営と経営人材の職能開発:変革のマネジメントとリーダーシップ 名古屋高等教育研究,12,67-93.[PDF](CiNii Articles「大森不二雄」で知る)
- 大森不二雄(2015).貿易交渉に見る高等教育のグローバル化:政治経済の論理と我が国の課題 RIHE,130,59-85.(CiNii Articles「大森不二雄」で知る)
- 大森不二雄(2019).集権的な統制から法の支配への転換が大学の変革を促す:自由と多様性で活性化する高等教育システムの再設計を 大学マネジメント,15(6),10-23.(CiNii Articles「大森不二雄」で知る)
- 大森不二雄(2018).英国の大学授業料・ローン制度の成功から学ぶ教訓:高等教育の無償化論に潜む落とし穴 大学マネジメント,13(12),24-34.(CiNii Articles「大森不二雄」で知る)
- 大森不二雄(2018).SDレポート 第1回大学教育イノベーションフォーラム「SD義務化と大学の未来:全教職員の能力開発を組織開発につなげるために」について 大学職員論叢,6,221-224.(CiNii Articles「大森不二雄」で知る)
- 大森不二雄・斉藤準(2018).米国STEM教育におけるDBER (discipline-based education research)の勃興:日本の大学教育への示唆を求めて 東北大学高度教養教育・学生支援機構紀要,4,239-246.[PDF](CiNii Articles「大森不二雄」で知る)
- 大森不二雄・高田英一・岡田有司(2017).教育の「質保証」を学生の「学習」に連結させるための課題:大学の内部質保証観と学生の学習観への合理的選択理論からのアプローチ 東北大学高度教養教育・学生支援機構紀要,3,75-88.[PDF](CiNii Articles「大森不二雄」で知る)
- 大森不二雄・高橋潔(2018).高等教育研究と経営学理論の対話から見えてくる新視点:革新的な大学組織の在り方を探索する学際的研究の試み 東北大学高度教養教育・学生支援機構紀要 ,4,227-237.(CiNii Articles「大森不二雄」で知る)
- 渡辺雄貴・大森不二雄(2012).学習成果と授業設計をリンクするシラバス作成に関する研究 日本教育工学会研究報告集,2012(1),153-159.(CiNii Articles「大森不二雄」で知る)
- 渡辺雄貴・大森不二雄・永井正洋(2014).学習成果に基づく授業設計の視点から見たシラバスの内容分析 大学評価研究,13,113-122.(CiNii Articles「大森不二雄」で知る)
[2019.11.3]大学に関わる情報メモ 内容をアップ
[2019.10.30]大学に関わる情報メモ 内容をアップ
[2019.9.24]IRなどについての文献メモ 文献一覧を更新<質保証、IR>
- 山田勉(2019).学生参加による高等教育の質保証:「欧州高等教育圏における質保証の基準とガイドライン」に関する批判的考察に基づいて(要旨) 博士論文(京都大学)[PDF](Google Scholar「質保証」で知る)
- 田中正弘(2018).日本の大学における学生参画:質保証への参画を中心として 大学研究 (45),17-30.[PDF](Google Scholar「質保証」で知る)
- 沖裕貴(2019).日本のFDの現状と課題 名古屋高等教育研究,19,17-21.[PDF](Google Scholar「質保証」で知る)
- 葛城浩一(2019).ボーダーフリー大学における学士課程教育の質保証の実現可能性:学部系統による教育の質保証の実態の差異 香川大学教育研究 (16),71-84.[PDF](Google Scholar「質保証」で知る)
- 吉本圭一・坂巻文彩(2019).大学における学修成果と質保証のための卒業生調査:九州大学教育学部卒業生調査にみる職業統合的学習 大学院教育学研究紀要 (21),45-72.[PDF](Google Scholar「質保証」で知る)
- 杉原亨(2019).高等教育の質保証に関する枠組み及び政策的動向への視点 関東学院大学高等教育研究・開発センター年報,3,17-24.[PDF](Google Scholar「質保証」で知る)
- 嶌田敏行(2019).データーを活かした教育改善 茨城大学全学教育機構論集.大学教育研究,2,99-102.[PDF](Google Scholar「質保証」で知る)
- 早田幸政(2018).ASEAN地域における高等教育質保証連携と「資格枠組み(QF)」の構築・運用の現段階:今、日本の高等教育質保証に何が求められているか 大学評価研究,17,39-59.(Google Scholar「質保証」で知る)
- 吉田美喜夫(2018).大学の質保証と学習方法の改革 大学評価研究,17,1-5.(CiNii Articles「特集テーマ 大学評価の国際的通用性」で知る)
- 鈴木典比古(2018).国際化に向かう大学教育とその認証評価:視覚的分析の試み 大学評価研究,17,11-15.(CiNii Articles「特集テーマ 大学評価の国際的通用性」で知る)
- 前田早苗(2018).アメリカのアクレディテーションをめぐる近年の状況:高等教育法改正案を中心に 大学評価研究,17,17-24.(CiNii Articles「特集テーマ 大学評価の国際的通用性」で知る)
- 堀井祐介(2018).ヨーロッパにおける大学評価の最新の動向 大学評価研究,17,25-31.(CiNii Articles「特集テーマ 大学評価の国際的通用性」で知る)
- 黄福涛(2018).中国の大学評価の新動向 大学評価研究,17,33-38.(CiNii Articles「特集テーマ 大学評価の国際的通用性」で知る)
- 奈良信雄(2018).医学教育の国際的な評価の動向 大学評価研究,17,61-66.(CiNii Articles「特集テーマ 大学評価の国際的通用性」で知る)
- 小澤孝一郎(2018).薬学教育の国際的な評価の動向 大学評価研究,17,67-75.(CiNii Articles「特集テーマ 大学評価の国際的通用性」で知る)
- 深堀聰子(2018).工学教育領域の国際的な評価の動向 大学評価研究,17,77-89.(CiNii Articles「特集テーマ 大学評価の国際的通用性」で知る)
- 古井貞熙(2018).TTICにおける適格認定プロセス 大学評価研究,17,91-96.(CiNii Articles「特集テーマ 大学評価の国際的通用性」で知る)
- 河野宏和(2018).国際認証取得に向けた視点 大学評価研究,17,97-104.(CiNii Articles「特集テーマ 大学評価の国際的通用性」で知る)
- 原和世(2018).質保証機関の国際連携(台湾評鑑協会との共同認証プロジェクトが目指すもの) 大学評価研究,17,105-110.(CiNii Articles「特集テーマ 大学評価の国際的通用性」で知る)
- 深堀聰子(2019).日本版ディプロマ・サプリメントが明かす日本高等教育質保証システムの課題 工学教育,67(1),1_22-1_27.(Google Scholar「質保証」で知る)
- 前田早苗(2019).高等教育の質保証システムの課題と展望:第3期認証評価を中心に 工学教育,67(1),1_16-1_21.(Google Scholar「質保証」で知る)
- 中井俊樹(2018).大学におけるインスティチューショナル・リサーチ (IR) に関する論点の整理 薬学教育,2.※ページ番号なし[PDF](Google Scholar「質保証」で知る)
- 岡田聡志(2018).医学教育におけるInstitutional Researchの分野別評価と内部質保証への関わり:機関レベルと専門分野レベルのIR機能と関連性 薬学教育,2.※ページ番号なし[PDF](Google Scholar「質保証」で知る)
- 鈴木匡・安原智久(2018).「事前学習・実務実習のアウトカムを測る」序文 薬学教育,2.※ページ番号なし[PDF](『薬学教育』バックナンバーで知る)
- 小森浩二・安原智久・曾根知道・河野武幸(2018).事前学習と実務実習の総合的評価の確立に向けて 薬学教育,2.※ページ番号なし[PDF](『薬学教育』バックナンバーで知る)
- 安原智久・隠岐英之・串畑太郎・曾根知道(2018).薬局実務実習におけるルーブリックを用いたパフォーマンス評価 薬学教育,2.※ページ番号なし[PDF](『薬学教育』バックナンバーで知る)
- 鈴木小夜・中村智徳(2018).病院実習で行うパフォーマンス評価 薬学教育,2.※ページ番号なし[PDF](『薬学教育』バックナンバーで知る)
- 山田勉(2018).薬学教育評価・第2サイクルの課題 薬学教育,2.※ページ番号なし[PDF](『薬学教育』バックナンバーで知る)
- 平田收正(2018).平成28年度第三者評価の結果と薬学教育の今後のあり方 薬学教育,2.※ページ番号なし[PDF](『薬学教育』バックナンバーで知る)
- 長谷川洋一・小澤光一郎・中村明弘(2018).第2サイクル評価基準案:アウトカムと質保証 薬学教育,2.※ページ番号なし[PDF](『薬学教育』バックナンバーで知る)
- 尾﨑惠一(2018).大阪薬科大学におけるFD活動の新しい取り組み 薬学教育,2.※ページ番号なし[PDF](『薬学教育』バックナンバーで知る)
- 小佐野博史(2018).薬学部に求められるFD活動 薬学教育,2.※ページ番号なし[PDF](『薬学教育』バックナンバーで知る)
- 井上誠・脇屋義文・古野忠秀・茂木眞希雄(2018).FDワークショップの振り返りからみえてきたこと 薬学教育,2.※ページ番号なし[PDF](『薬学教育』バックナンバーで知る)
- 松岡一郎(2018).薬学教育の枠組みを「知る」ことからFD活動を考える 薬学教育,2.※ページ番号なし[PDF](『薬学教育』バックナンバーで知る)
- 小嶋英二朗・石津隆・上敷領淳・松田幸久(2018).薬学部での教学IRの試み1 薬学教育,2.※ページ番号なし[PDF](『薬学教育』バックナンバーで知る)
- 大津史子(2018).薬学部での教学IRの試み2 薬学教育,2.※ページ番号なし[PDF](『薬学教育』バックナンバーで知る)
- 工藤一彦(2018).教育の質保証枠組に基づく学修成果の社会への提示法 工学教育研究講演会講演論文集,2018,500-501.[PDF](Google Scholar「質保証」で知る)
- 市坪誠・中村成芳・黒田恭平・山田宏・油谷英明・山口隆司(2018).ジェネリックスキルの国別・思考力別評価 工学教育研究講演会講演論文集,2018,498-499.[PDF](Google Scholar「質保証」で知る)
[2019.9.24]大学に関わる情報メモ 内容をアップ
[2019.9.13]大学に関わる情報メモ 内容をアップ
[2019.9.9]大学に関わる情報メモ 内容をアップ
[2019.9.6]大学に関わる情報メモ 内容をアップ
[2019.8.29]「過去の「お知らせ」」、「IRなどについての文献メモ」、「これまでの発表・競争的研究資金など」に追加
- 研修会講師「データと経験による「継続的な改善活動」:単科大学の長所を活かしたIR」(三重県立看護大学FD/SD研修会)※講師依頼
[2019.8.26]IRなどについての文献メモ 文献一覧を更新<高等教育、大学改革>
- 天野郁夫(2013).大学改革を問い直す 慶應義塾大学出版会(Amazon.co.jp「大学改革」で知る)
- 藤本夕衣・古川雄嗣・渡邉浩一・井上義和・児島功和・坂本尚志・佐藤真一郎・杉本舞・高野秀晴・二宮祐・藤田尚志・堀川宏・宮野公樹(2017).反「大学改革」論:若手からの問題提起 ナカニシヤ出版(Amazon.co.jp「公立大学」で知る)
- 松本美奈(2019).異見交論:崖っぷちの大学を語る 先端教育機構事業構想大学院大学出版部(Amazon.co.jp「大学改革」で知る)
- 小川正人・岩永雅也(編著)(2015).日本の教育改革 放送大学教育振興会(Amazon.co.jp「大学改革」で知る)
- 水戸英則(編著)(2014).今、なぜ「大学改革」か?:私立大学の戦略的経営の必要性 丸善プラネット(Amazon.co.jp「大学改革」で知る)
- 羽田貴史(2019).大学の組織とガバナンス 東信堂(Amazon.co.jp「大学改革」で知る)
- 山口裕之(2017).「大学改革」という病:学問の自由・財政基盤・競争主義から検証する 明石書店(Amazon.co.jp「大学改革」で知る)
- 坂野慎二・藤田晃之(編著)(2015).海外の教育改革 放送大学教育振興会(Amazon.co.jp「大学改革」で知る)
- 篠田道夫・教育学術新聞編集部(2014).大学マネジメント改革:改革の現場-ミドルのリーダーシップ ぎょうせい(Amazon.co.jp「大学改革」で知る)
- 金子忠史(1994).変革期のアメリカ教育 東信堂(Amazon.co.jp「大学改革」で知る)
- 今村令子(1990).永遠の「双子の目標」:多文化共生の社会と教育 東信堂(Amazon.co.jp「大学改革」で知る)
- OECD教育調査団(編著)深代惇郎(訳)(2001).日本の教育政策 日本図書センター(Amazon.co.jp「大学改革」で知る)
- 経済協力開発機構(著)弓削俊彦(訳)(2002).未来の学校教育 技術経済研究所(Amazon.co.jp「大学改革」で知る)
- 日本教育経営学会・学校改善研究委員会(編)(1990).学校改善に関する理論的・実証的研究 ぎょうせい(Amazon.co.jp「大学改革」で知る)
- OECD(編著)森利枝(訳)(2019).日本の大学改革:OECD高等教育政策レビュー:日本 明石書店(Amazon.co.jp「大学改革」で知る)
- 佐々木毅・成田憲彦・藤嶋亮・飯尾潤・池本大輔・安井宏樹・後房雄・野中尚人・廣瀬淳子(2015).21世紀デモクラシーの課題:意思決定構造の比較分析 吉田書店(Amazon.co.jp「大学改革」で知る)
- 城山英明・細野助博(編著)(2002).中央省庁の政策形成過程:その持続と変容 中央大学出版部(Amazon.co.jp「大学改革」で知る)
- 中田雅敏(2014).教育改革のゆくえ 新典社(Amazon.co.jp「大学改革」で知る)
- 乾彰夫(1990).日本の教育と企業社会:一元的能力主義と現代の教育=社会構造 大月書店(Amazon.co.jp「大学改革」で知る)
- 飯尾潤(2007).日本の統治構造:官僚内閣制から議院内閣制へ 中央公論新社(Amazon.co.jp「大学改革」で知る)
- 城山英明・細野助博(編著)(2002).中央省庁の政策形成過程:その持続と変容 中央大学出版部(Amazon.co.jp「大学改革」で知る)
- 城山英明・鈴木寛・細野助博(編著)(1999).中央省庁の政策形成過程:日本官僚制の解剖 中央大学出版部(Amazon.co.jp「大学改革」で知る)
- 貝塚茂樹(2018).戦後日本教育史 放送大学教育振興会(Amazon.co.jp「大学改革」で知る)
- 岩田龍子(1988).学歴主義の発展構造 日本評論社(Amazon.co.jp「大学改革」で知る)
- Dore, R. P.松居弘道(訳)(2008).学歴社会新しい文明病 岩波書店(Amazon.co.jp「大学改革」で知る)
- 大田堯(編著)(1978).戦後日本教育史 岩波書店(Amazon.co.jp「大学改革」で知る)
- Ravitch, D.末藤美津子(訳)(2011).教育による社会的正義の実現:アメリカの挑戦(1945~1980) 東信堂(Amazon.co.jp「大学改革」で知る)
- 松尾知明(2010).アメリカの現代教育改革:スタンダードとアカウンタビリティの光と影 東信堂(Amazon.co.jp「大学改革」で知る)
- 天野郁夫(2009).大学の誕生(上):帝国大学の時代 中央公論新社(Amazon.co.jp「大学改革」で知る)
- 天野郁夫(2009).大学の誕生(下):大学への挑戦 中央公論新社(Amazon.co.jp「大学改革」で知る)
- 天野郁夫(2004).大学改革:秩序の崩壊と再編 東京大学出版会(Amazon.co.jp「大学改革」で知る)
- 天野郁夫(2003).日本の高等教育システム:変革と創造 東京大学出版会(Amazon.co.jp「大学改革」で知る)
- 天野郁夫(2006).大学改革の社会学 玉川大学出版部(Amazon.co.jp「大学改革」で知る)
- 天野郁夫(2001).大学改革のゆくえ:模倣から創造へ 玉川大学出版部(Amazon.co.jp「大学改革」で知る)
- 山上浩二郎(2013).検証大学改革:混迷の先を診る 岩波書店(Amazon.co.jp「大学改革」で知る)
- Rudolph, F.阿部美哉・阿部温子(訳)(2003).アメリカ大学史 玉川大学出版部(Amazon.co.jp「大学改革」で知る)
- 安原義仁・大塚豊・羽田貴史(編著)(2008).大学と社会 放送大学教育振興会(Amazon.co.jp「大学改革」で知る)
- 飯尾潤(2019).現代日本の政治 放送大学教育振興会(Amazon.co.jp「大学改革」で知る)
- 飯尾潤(2013).現代日本の政策体系:政策の模倣から創造へ 筑摩書房(Amazon.co.jp「大学改革」で知る)
- 村井実(全訳解説)(1979).アメリカ教育使節団報告書 講談社(Amazon.co.jp「大学改革」で知る)
- Verger, J.大高順雄(訳)(1991).中世の大学 みすず書房(Amazon.co.jp「大学改革」で知る)
- Le Goff, J.柏木英彦・三上朝造(訳)(1977).中世の知識人:アベラールからエラスムスへ 岩波書店(Amazon.co.jp「大学改革」で知る)
- Haskins, C. H.青木靖三・三浦常司(訳)(2009).大学の起源 八坂書房(Amazon.co.jp「大学改革」で知る)
- 天野郁夫(2017).帝国大学:近代日本のエリート育成装置 中央公論新社(Amazon.co.jp「大学改革」で知る)
- 天野郁夫(2019).新制大学の時代:日本的高等教育像の模索 名古屋大学出版会(Amazon.co.jp「大学改革」で知る)
- 天野郁夫(1992).大学:挑戦の時代 東京大学出版会(Amazon.co.jp「大学改革」で知る)
- 天野郁夫(2000).学長:大学改革への挑戦 玉川大学出版部(Amazon.co.jp「大学改革」で知る)
- 宇佐見忠雄(2006).現代アメリカのコミュニティ・カレッジ:その実像と変革の軌跡 東信堂(Amazon.co.jp「大学改革」で知る)
- 難波功士(2014).「就活」の社会史:大学は出たけれど・・・ 祥伝社(Amazon.co.jp「大学改革」で知る)
- 斎藤貴男(2016).機会不平等 岩波書店(Amazon.co.jp「大学改革」で知る)
- 細井克彦(2018).岐路に立つ日本の大学:新自由主義大学改革とその超克の方向 合同出版(Amazon.co.jp「大学改革」で知る)
- 潮木守一(2004).世界の大学危機:新しい大学像を求めて 中央公論新社(Amazon.co.jp「大学改革」で知る)
- 潮木守一(1993).アメリカの大学 講談社(Amazon.co.jp「大学改革」で知る)
- 廣田照幸・石川健治・橋本伸也・山口二郎(2016).学問の自由と大学の危機 岩波書店(Amazon.co.jp「大学改革」で知る)
- 高柳信一(1983).学問の自由 岩波書店(Amazon.co.jp「大学改革」で知る)
- 天野郁夫(2008).国立大学・法人化の行方:自立と格差のはざまで 東信堂(Amazon.co.jp「大学改革」で知る)
- 斬馬剣禅(1988).東西両京の大学:東京帝大と京都帝大 講談社(Amazon.co.jp「大学改革」で知る)
- 松岡亮二(2019).教育格差:階層・地域・学歴 筑摩書房(Amazon.co.jp「大学改革」で知る)
- Charle, C., & Verger, J.岡山茂, 谷口清彦(訳)(2009).大学の歴史 白水社(Amazon.co.jp「大学改革」で知る)
- 長野公則(2019).アメリカの大学の豊かさと強さのメカニズム:基本財産 (エンダウメント) の歴史、運用と教育へのインパクト 東信堂(Amazon.co.jp「大学改革」で知る)
- 小林雅之(2008).進学格差:深刻化する教育費負担 筑摩書房(Amazon.co.jp「大学改革」で知る)
[2019.8.26]IRなどについての文献メモ 文献一覧を更新<初年次教育>
- 世界思想社編集部(編)(2015).大学生学びのハンドブック:勉強法がよくわかる! 世界思想社(Amazon.co.jpレコメンド機能で知る)
- 稲垣忠(編)(2019).教育の方法と技術:主体的・対話的で深い学びをつくるインストラクショナルデザイン 北大路書房(Amazon.co.jpレコメンド機能で知る)
- 鈴木克明・美馬のゆり(編著)(2018).学習設計マニュアル:「おとな」になるためのインストラクショナルデザイン 北大路書房(Amazon.co.jpレコメンド機能で知る)
- 稲垣忠・鈴木克明(編著)(2015).授業設計マニュアル:教師のためのインストラクショナルデザイン 北大路書房(Amazon.co.jpレコメンド機能で知る)
- 佐藤智明・矢島彰・山本明志(編)(2014).大学学びのことはじめ:初年次セミナーワークブック ナカニシヤ出版(Amazon.co.jpレコメンド機能で知る)
- 佐藤望(編著)・湯川武・横山千晶・近藤明彦(著)(2012).大学生のための知的技法入門 慶應義塾大学出版会(Amazon.co.jpレコメンド機能で知る)
- 学習技術研究会(編著)(2019).知へのステップ:大学生からのスタディ・スキルズ くろしお出版(Amazon.co.jpレコメンド機能で知る)
- 日本高等教育開発協会・ベネッセ教育総合研究所(編)(2016).大学生の主体的学びを促すカリキュラム・デザイン:アクティブ・ラーニングの組織的展開にむけて ナカニシヤ出版(Amazon.co.jpレコメンド機能で知る)
- 初年次教育テキスト編集委員会(編)(2014).フレッシュマンセミナーテキスト:大学新入生のための学び方ワークブック 東京電機大学出版局(Amazon.co.jpレコメンド機能で知る)
- 世界思想社編集部(編)(2014).大学新入生ハンドブック:大学生活これだけは知っておきたい! 世界思想社(Amazon.co.jpレコメンド機能で知る)
- 世界思想社編集部(編)(2018).大学生学びのハンドブック:勉強法がよくわかる! 世界思想社(Amazon.co.jpレコメンド機能で知る)
- Upcraft, M. L., Gardner, J. N., & Barefoot, B. O.山田礼子(監訳)(2007).初年次教育ハンドブック:学生を「成功」に導くために 丸善(Amazon.co.jpレコメンド機能で知る)
- 川廷宗之・川野辺裕幸・岩井洋(編)(2011).プレステップ基礎ゼミ 弘文堂(Amazon.co.jpレコメンド機能で知る)
- 中澤務・森貴史・本村康哲(編)(2007).知のナヴィゲーター:情報と知識の海:現代を航海するための くろしお出版(Amazon.co.jpレコメンド機能で知る)
- 北尾謙治・朝尾幸次郎・石川慎一郎・石川有香・KitaoS. Kathleen・実松克義・島谷浩・西納春雄・野澤和典・早坂慶子(2005).広げる知の世界:大学でのまなびのレッスン ひつじ書房(Amazon.co.jpレコメンド機能で知る)
- 藤田哲也(編著)(2006).大学基礎講座:充実した大学生活をおくるために 北大路書房(Amazon.co.jpレコメンド機能で知る)
- 佐渡島紗織・坂本麻裕子・大野真澄(編著)(2015).レポート・論文をさらによくする「書き直し」ガイド:大学生・大学院生のための自己点検法29 大修館書店(Amazon.co.jpレコメンド機能で知る)
- 渡辺哲司(2010).「書くのが苦手」をみきわめる:大学新入生の文章表現力向上をめざして 学術出版会(Amazon.co.jpレコメンド機能で知る)
- 佐渡島紗織・太田裕子(編)(2013).文章チュータリングの理念と実践:早稲田大学ライティング・センターでの取り組み ひつじ書房(Amazon.co.jpレコメンド機能で知る)
- 戸田山和久(2012).論文の教室:レポートから卒論まで NHK出版(Amazon.co.jpレコメンド機能で知る)
- 木下是雄(1994).レポートの組み立て方 筑摩書房(Amazon.co.jpレコメンド機能で知る)
- 関西地区FD連絡協議会・京都大学高等教育研究開発推進センター(編)(2013).思考し表現する学生を育てるライティング指導のヒント ミネルヴァ書房(Amazon.co.jpレコメンド機能で知る)
- 村岡貴子・因京子・仁科喜久子(2013).論文作成のための文章力向上プログラム:アカデミック・ライティングの核心をつかむ 大阪大学出版会(Amazon.co.jpレコメンド機能で知る)
- 溝上慎一・藤田哲也(編)(2005).心理学者、大学教育への挑戦 ナカニシヤ出版(Amazon.co.jpレコメンド機能で知る)
- 山田剛史・林創(2011).大学生のためのリサーチリテラシー入門:研究のための8つの力 ミネルヴァ書房(Amazon.co.jpレコメンド機能で知る)
- Rychen, D. S., & Salganik, L. H.(編著)立田慶裕・今西幸藏・岩崎久美子・猿田祐嗣・名取一好・野村和・平沢安政(2006).キー・コンピテンシー:国際標準の学力をめざして 明石書店(Amazon.co.jpレコメンド機能で知る)
- 田中耕治(編著)(2008).新しい学力テストを読み解く:PISA/TIMSS/全国学力・学習状況調査/教育課程実施状況調査の分析とその課題 日本標準(Amazon.co.jpレコメンド機能で知る)
- 東京大学学校教育高度化センター(編)(2009).基礎学力を問う:21世紀日本の教育への展望 東京大学出版会(Amazon.co.jpレコメンド機能で知る)
- 佐藤学・澤野由紀子・北村友人(編著)(2009).揺れる世界の学力マップ 明石書店(Amazon.co.jpレコメンド機能で知る)
[2019.8.26]IRなどについての文献メモ 文献一覧を更新<公立大学>
- 吉川卓治(2010).公立大学の誕生:近代日本の大学と地域 名古屋大学出版会(Amazon.co.jp「公立大学」で知る)
- 内田穣吉(1983).公立大学:その現状と展望 日本評論社(Amazon.co.jp「公立大学」で知る)
- 高崎経済大学附属産業研究所(編)(2010).地方公立大学の未来 日本経済評論社(Amazon.co.jp「公立大学」で知る)
- 高橋寛人(2009).20世紀日本の公立大学:地域はなぜ大学を必要とするか 日本図書センター(Amazon.co.jp「公立大学」で知る)
- 関一研究会(編集・校訂)(1986).関一日記:大正・昭和初期の大阪市政 東京大学出版会(Amazon.co.jp「公立大学」で知る)
- 村田鈴子(編著)(1994).公立大学に関する研究:地域社会志向とユニバーサリズム 多賀出版(Amazon.co.jp「公立大学」で知る)
- 高橋寛人(編著)(2004).公設民営大学設立事情 東信堂(Amazon.co.jp「公立大学」で知る)
[2019.8.26]IRなどについての文献メモ 文献一覧を更新<言語学>
- 風間喜代三・上野善道・松村一登・町田健(2004).言語学 東京大学出版会(Amazon.co.jp「言語学」で知る)
- Vygotskiĭ, L. S.柴田義松(訳)(2001).思考と言語 新読書社(Amazon.co.jp「ヴィゴツキー」で知る)
- 中村和夫(2004).ヴィゴーツキー心理学:完全読本:「最近接発達の領域」と「内言」の概念を読み解く 新読書社(Amazon.co.jp「ヴィゴツキー」で知る)
- 柴田義松(2006).ヴィゴツキー入門 子どもの未来社(Amazon.co.jp「ヴィゴツキー」で知る)
- Godfrey-Smith, P.夏目大(訳)(2018).タコの心身問題:頭足類から考える意識の起源 みすず書房(Amazon.co.jpレコメンド機能で知る)
- Saussure, F.町田健(訳)(2016).新訳ソシュール一般言語学講義 研究社(Amazon.co.jp「ソシュール」で知る)
- Saussure, F.小林英夫(訳)(1972).一般言語学講義 岩波書店(Amazon.co.jp「ソシュール」で知る)
- 町田健(2004).ソシュールと言語学:コトバはなぜ通じるのか 講談社(Amazon.co.jp「ソシュール」で知る)
- 楠見孝(編)(2010).思考と言語 北大路書房(Amazon.co.jp「言語学」で知る)
- 丸山圭三郎(2008).言葉とは何か 筑摩書房(Amazon.co.jp「言語学」で知る)
- Sapir, E.安藤貞雄(訳)(1998).言語:ことばの研究序説 岩波書店(Amazon.co.jp「言語学」で知る)
- 丸山圭三郎(2012).ソシュールを読む 講談社(Amazon.co.jp「ソシュール」で知る)
- 加賀野井秀一(1995).20世紀言語学入門:現代思想の原点 講談社(Amazon.co.jp「言語学」で知る)
- 庵功雄(2012).新しい日本語学入門:ことばのしくみを考える スリーエーネットワーク(Amazon.co.jp「言語学」で知る)
- 庵功雄(2013).日本語教育・日本語学の「次の一手」 くろしお出版(Amazon.co.jp「言語学」で知る)
- 益岡隆志(編著)(2011).はじめて学ぶ日本語学:ことばの奥深さを知る15章 ミネルヴァ書房(Amazon.co.jp「言語学」で知る)
- 小島剛一(2012).再構築した日本語文法 ひつじ書房(Amazon.co.jp「言語学」で知る)
- 滝浦真人(編著)(2018).新しい言語学:心理と社会から見る人間の学 放送大学教育振興会(Amazon.co.jp「言語学」で知る)
- 丸山圭三郎(1987).言葉と無意識 講談社(Amazon.co.jp「言語学」で知る)
- 白畑知彦・須田孝司・鈴木一徳・平川眞規子・近藤隆子・横田秀樹・松村昌紀・奥脇奈津美・中川右也・尾島司郎(2019).言語習得研究の応用可能性:理論から指導・脳科学へ くろしお出版(Amazon.co.jp「言語習得」で知る)
- 児玉一宏・野澤元(2009).言語習得と用法基盤モデル:認知言語習得論のアプローチ 研究社(Amazon.co.jp「言語習得」で知る)
[2019.8.26]IRなどについての文献メモ 文献一覧を更新<大学職員>
- 寺崎昌男・立教学院職員研究会(編著)(2016).21世紀の大学:職員の希望とリテラシー 東信堂(Amazon.co.jp「大学職員」で知る)
- 岩田雅明(2016).戦略的大学職員養成ハンドブック:経営参画できる"職員力" ぎょうせい(Amazon.co.jp「大学職員」で知る)
[2019.8.26]IRなどについての文献メモ 文献一覧を更新<FD>
- 佐藤浩章(編著)(2017).講義法 玉川大学出版部(Amazon.co.jpレコメンド機能で知る)
- 京都大学高等教育教授システム開発センター(編)(2002).大学授業研究の構想:過去から未来へ 東信堂(Amazon.co.jpレコメンド機能で知る)
- Davis, B. G., Wood, L., & Wilson, R.香取草之助(監訳)(1995).授業をどうする!:カリフォルニア大学バークレー校の授業改善のためのアイデア集 東海大学出版会(Amazon.co.jpレコメンド機能で知る)
[2019.8.26]IRなどについての文献メモ 文献一覧を更新<マインドマップ>
- 矢嶋美由希(2015).実践!ふだん使いのマインドマップ CCCメディアハウス(Amazon.co.jp「マインドマップ」で知る)
- 矢嶋美由希(2012).ふだん使いのマインドマップ:描くだけで毎日がハッピーになる 阪急コミュニケーションズ(Amazon.co.jp「マインドマップ」で知る)
[2019.8.26]IRなどについての文献メモ 文献一覧を更新<テキストマイニング、IR>
- 牛澤賢二(2018).やってみようテキストマイニング:自由回答アンケートの分析に挑戦! 朝倉書店(Amazon.co.jpレコメンド機能で知る)
- 小林雄一郎(2019).ことばのデータサイエンス 朝倉書店(Amazon.co.jpレコメンド機能で知る)
- 中谷宇吉郎(1956).科学の方法 岩波書店(Amazon.co.jpレコメンド機能で知る)
[2019.8.23]「過去の「お知らせ」」、「IRなどについての文献メモ」、「これまでの発表・競争的研究資金など」に追加
- 口頭発表「オーソライズされた「学修成果の評価方針」の内容と広がり:公表資料の網羅的な調査による検証」(大学評価・IR担当者集会2019)
[2019.8.14]「これまでの発表・競争的研究資金など」に追加
- 講師「ICT実践活用」(平成31年度免許状更新講習)
- 講師「情報教育」(平成31年度免許状更新講習)
[2019.7.25]「過去の「お知らせ」」、「これまでの発表・競争的研究資金など」に追加
- オブザーバー「学びロボ Osaka & Tokyo 2019」
[2019.7.17]ホーム「お知らせ」欄に追加
- 口頭発表「オーソライズされた「学修成果の評価方針」の内容と広がり:公表資料の網羅的な調査による検証」(大学評価・IR担当者集会2019IR実務担当者セッション)を掲載
- オブザーバー「学びロボ Osaka & Tokyo 2019」を掲載
[2019.7.12]「これまでの発表・競争的研究資金など」に追加
- 大学見学会模擬授業(ドローンとMakeblockを使った高校生・高校教諭向けプログラミング教育体験、四天王寺大学、2019年7月10・11日)
[2019.6.2]「過去の「お知らせ」」、「IRなどについての文献メモ」、「これまでの発表・競争的研究資金など」に追加
- ポスター発表"What is the roll of full-time institutional research staff in Japan?"(2019 AIR Forum)
[2019.5.12]「過去の「お知らせ」」、「IRなどについての文献メモ」、「これまでの発表・競争的研究資金など」に追加
- ポスター発表「継続的改善プロセスの定着に向けたデータの整備・蓄積:四天王寺大学の事例」(関西地区FD連絡協議会第12回総会ポスターセッション)
[2019.5.8]IRなどについての文献メモ 文献一覧を更新<institutional effectiveness>
- Bresciani, M. J. (2006). Outcomes-based academic and co-curricular program review: A compilation of institutional good practices. Sterling, Va.: Stylus.(Google Scholar「"institutional effectiveness"」で知る)
[2019.5.8]ホーム「お知らせ」欄に追加
- ポスター発表「継続的改善プロセスの定着に向けたデータの整備・蓄積:四天王寺大学の事例」(関西地区FD連絡協議会第12回総会ポスターセッション)を掲載
[2019.4.25]ホーム「お知らせ」欄に追加
- ポスター発表"What is the roll of full-time institutional research staff in Japan?"(2019 AIR Forum)発表日時を追記
[2019.4.14]IRなどについての文献メモ 文献一覧を更新<建学の精神>
- 菅真城(2008).国立大学に建学の精神はあるのか?:広島大学、大阪大学の場合 広島大学文書館紀要,10,1-22.[PDF](Google Scholar「国立大学 建学の精神」で知る)
- 木村正則(2017).私立大学における「建学の精神」の役割 教養・外国語教育センター紀要.外国語編 8(1),71-82.[PDF](CiNii Articles「私立大学 建学の精神」で知る)
[2019.4.14]「これまでの発表・競争的研究資金など」に追加
- 外部資金「大学ベンチマークの理論に関する基礎的研究」(平成30年度公募型共同利用「重点テーマ2:IRのための学術文献データ分析と統計的モデル研究の深化」(統計数理研究所))
[2019.4.12]大学に関わる情報メモ 内容をアップ
[2019.4.10]IRなどについての文献メモ 文献一覧を更新<高等教育学>
- 羽田貴史(2019).高等教育研究の制度化と大学教育研究センター 名古屋高等教育研究,19,5-16.[PDF](名古屋高等教育研究バックナンバーで知る)
- 沖裕貴(2019).日本のFDの現状と課題 名古屋高等教育研究,19,17-32.[PDF](名古屋高等教育研究バックナンバーで知る)
- 近田政博(2019).高等教育関連センターの機構化が意味するもの:名古屋大学と神戸大学の比較考察 名古屋高等教育研究,19,33-48.[PDF](名古屋高等教育研究バックナンバーで知る)
- 中井俊樹(2019).高等教育学を専門とする教員は何をすべきなのか 名古屋高等教育研究,19,49-59.[PDF](名古屋高等教育研究バックナンバーで知る)
- 池田輝政(2019).成長するティップス先生の過去、現在、未来 名古屋高等教育研究,19,61-76.[PDF](名古屋高等教育研究バックナンバーで知る)
- 夏目達也(2019).高等教育センターの研究活動を考える:名古屋大学高等教育研究センターの15年間 名古屋高等教育研究,19,77-95.[PDF](名古屋高等教育研究バックナンバーで知る)
- 中島英博(2019).高校教員から見た大学による高校訪問 名古屋高等教育研究,19,99-114.[PDF](名古屋高等教育研究バックナンバーで知る)
- 森朋子・松下佳代(2019).深い学びに寄与するグループ活動のデザイン:思考と活動の乖離を乗り越えるために 名古屋高等教育研究,19,141-152.[PDF](名古屋高等教育研究バックナンバーで知る)
- 村澤昌崇・中尾走・松宮慎治(2019).大学の研究生産とガバナンス 名古屋高等教育研究,19,153-169.[PDF](名古屋高等教育研究バックナンバーで知る)
- 両角亜希子(2019).学長のリーダーシップとその能力養成 名古屋高等教育研究,19,171-197.[PDF](名古屋高等教育研究バックナンバーで知る)
[2019.4.10]IRなどについての文献メモ 文献一覧を更新<大学職員>
[2019.4.9]IRなどについての文献メモ 文献一覧を更新<統計>
[2019.4.8]IRなどについての文献メモ 文献一覧を更新<IR>
[2019.4.5]ホーム「お知らせ」欄に追加
- 平成31年度科学研究費助成事業(学術研究助成基金助成金)基盤研究(C)(一般)「IRの専門性活用と大学の文脈の相互構造に関する研究」採択を掲載
[2019.3.29]「過去の「お知らせ」」、「IRなどについての文献メモ」、「これまでの発表・競争的研究資金など」に追加
- 橋本智也(2019).学修時間の増加・確保に向けた組織的な取り組みの支援 大学行政管理学会2015年度若手研究奨励成果発表,1-5.
[2019.3.27]IRなどについての文献メモ 文献一覧を更新<IR、クラスター分析>
- 宗方比佐子(2004).女子学生に対するキャリア開発支援の試み(1)」:クラスター分析による職業意識の分類 金城学院大学論集. 人文科学編,1,166-177.[PDF](クラスター分析→学科別に割合比較、カイ二乗検定;Google Scholar「>クラスター分析 学生 学科別」で知る)
- 前田一男・宮下佳子・佐藤良・油井原均・長谷川慶子・大島宏(2008).大学生の教育観・教職観の形成過程に関する追跡調査研究:1995年調査と2006年調査の比較から 立教大学教育学科研究年報,51,79-123.[PDF](クラスター分析→性別・学科別の割合比較;Google Scholar「>クラスター分析 学生 学科別」で知る)
[2019.3.27]IRなどについての文献メモ 文献一覧を更新<統計>
- 石村貞夫・加藤千恵子・劉晨・石村友二郎(2013).SPSSによるカテゴリカルデータ分析の手順 東京図書(Amazon.co.jpレコメンド機能で知る)
- 石村貞夫・石村光資郎(2016).SPSSによる多変量データ解析の手順 東京図書(Amazon.co.jpレコメンド機能で知る)
- 石村光資郎(著)・石村貞夫(監修)(2018).SPSSによるアンケート調査のための統計処理 東京図書(Amazon.co.jpレコメンド機能で知る)
- 村瀬洋一・高田洋・廣瀬毅士(編)(2007).SPSSによる多変量解析 オーム社(Amazon.co.jpレコメンド機能で知る)
- 内田治(2014).SPSSによるノンパラメトリック検定 オーム社(Amazon.co.jpレコメンド機能で知る)
- 藤井良宜(著)・金明哲(監修)(2010).カテゴリカルデータ解析 共立出版(Amazon.co.jpレコメンド機能で知る)
- 中室牧子・津川友介(2017).「原因と結果」の経済学:データから真実を見抜く思考法 ダイヤモンド社(Amazon.co.jpレコメンド機能で知る)
- Morin, P.堀江慧・陣内佑・田中康隆(訳)(2018).みんなのデータ構造 ラムダノート(Twitter(@DINDIN92さん)で知る)
- Salsburg, D.竹内惠行・熊谷悦生(訳)(2006).統計学を拓いた異才たち:経験則から科学へ進展した一世紀 日本経済新聞社(Amazon.co.jpレコメンド機能で知る)
[2019.3.27]IRなどについての文献メモ 文献一覧を更新<高等教育>
- 小入羽秀敬(2019).私立学校政策の展開と地方財政:私学助成をめぐる政府間関係 吉田書店(Twitter(@skrnmrさん)で知る)
- 青木栄一・川上泰彦(2019).教育の行政・政治・経営 放送大学教育振興会(Amazon.co.jpレコメンド機能で知る)
[2019.3.27]IRなどについての文献メモ 文献一覧を更新<デザイン>
- 加藤健郎・佐藤弘喜・佐藤浩一郎(編著)(2018).デザイン科学概論:多空間デザインモデルの理論と実践 慶應義塾大学出版会(Amazon.co.jpレコメンド機能で知る)
[2019.3.25]「過去の「お知らせ」」、「IRなどについての文献メモ」、「これまでの発表・競争的研究資金など」に追加
- 橋本智也・白石哲也(2019).大学におけるIRの実態に関するアンケートの調査報告:自由記述に見られた困難・活動内容 大学評価とIR,10,16-28.[PDF]
[2019.3.19]IRなどについての文献メモ 文献一覧を更新、内容をアップ<統計>
- 村尾博(2004).リッカート型項目データの回帰への使用と通常最小2乗推定量 青森公立大学経営経済学研究,9(2),63-79.[概要][PDF](Google「重回帰分析 リッカート site:ac.jp」で知る)
[2019.3.14]IRなどについての文献メモ 内容をアップ
- 岡田有司・鳥居朋子・宮浦崇・青山佳世・松村初・中野正也・吉岡路(2011).大学生における学習スタイルの違いと学習成果 立命館高等教育研究,11,167-182.[概要][PDF](Google Scholar「学習時間 意欲 大学」で知る、Google「site:ac.jp GPA 重回帰分析」で知る)
[2019.3.9]ホーム「お知らせ」欄に追加
- 口頭発表「大学ベンチマークの理論に関する基礎的研究」(平成30年度共同利用重点型研究「IRのための学術文献データ分析と統計的モデル研究の深化」成果報告会)を掲載
[2019.3.9]「過去の「お知らせ」」、「IRなどについての文献メモ」、「これまでの発表・競争的研究資金など」に追加
- 口頭発表「アセスメント・ポリシーを運用している大学への訪問調査結果について(中間報告)」(継続的改善のためのIR/IEセミナー2019)
[2019.2.26]IRなどについての文献メモ 文献一覧を更新<統計>
- 永田靖(2016).統計的方法の考え方を学ぶ:統計的センスを磨く3つの視点 日科技連出版社(researchmap「永田靖」で知る)
[2019.2.25]IRなどについての文献メモ 内容をアップ
- 永田靖(1998).多重比較法の実際 応用統計学,27(2),93-108.[PDF][概要](Google「Steel-Dwass サンプルサイズ」で知る)
[2019.2.25]IRなどについての文献メモ 文献一覧を更新<統計>
- 永田靖(1998).多重比較法の実際 応用統計学,27(2),93-108.[PDF][概要](Google「Steel-Dwass サンプルサイズ」で知る)
- 久力洋(2017).多重比較を正しく使うために:Dunnett型多重比較を事例として 3.正規分布などの特定の分布が仮定できない場合 第2期医薬安全性研究会第20回定例会資料,1-29.[PDF](Google「Steel-Dwass サンプルサイズ」で知る)
[2019.2.24]大学に関わる情報メモ 内容をアップ
[2019.2.11]IRなどについての文献メモ 文献一覧を更新<テキストマイニング>
[2019.2.11]IRなどについての文献メモ 文献一覧を更新<高等教育>
- 橋本鉱市(2014).高等教育の政策過程 玉川大学出版部(Amazon.co.jp「高等教育」で知る)
- 瀧澤博三(2016).高等教育政策と私学 悠光堂(Amazon.co.jp「高等教育」で知る)
- 天野郁夫(2013).高等教育の時代(上):戦間期日本の大学 中央公論新社(Amazon.co.jp「高等教育」で知る)
- 天野郁夫(2013).高等教育の時代(下):大衆化大学の原像 中央公論新社(Amazon.co.jp「高等教育」で知る)
- 天野郁夫(2016).新制大学の誕生(上):大衆高等教育への道 名古屋大学出版会(Amazon.co.jp「高等教育」で知る)
- 天野郁夫(2016).新制大学の誕生(下):大衆高等教育への道 名古屋大学出版会(Amazon.co.jp「高等教育」で知る)
- 山内乾史(編)(2015).学修支援と高等教育の質保証I 学文社(Amazon.co.jp「高等教育」で知る)
- 山内乾史・武寛子(編)(2015).学修支援と高等教育の質保証II 学文社(Amazon.co.jp「高等教育」で知る)
- 日本高等教育学会(編)(2017).高等教育研究のニューフロンティア 玉川大学出版部(Amazon.co.jp「高等教育」で知る)
[2019.1.31]ホーム「お知らせ」欄に追加
- ポスター発表"What is the roll of full-time institutional research staff in Japan?"(2019 AIR Forum)を掲載
- 口頭発表「アセスメント・ポリシーを運用している大学への訪問調査結果について(中間報告)」(継続的改善のためのIR/IEセミナー2019)を掲載
[2019.1.31]大学に関わる情報メモ 内容をアップ
[2018.12.26]大学に関わる情報メモ 内容をアップ
[2018.12.19]「過去の「お知らせ」」、「IRなどについての文献メモ」、「これまでの発表・競争的研究資金など」に追加
- 白石哲也・橋本智也(2018).大学におけるIRの実態に関するアンケート調査報告:アンケートの基礎集計 大学評価とIR,9,62-77.[PDF]
[2018.12.13]IRなどについての文献メモ 文献一覧を更新<言語学>
- 寺村秀夫(1982).日本語のシンタクスと意味:第1巻 くろしお出版
- 寺村秀夫(1984).日本語のシンタクスと意味:第2巻 くろしお出版
- 寺村秀夫(1991).日本語のシンタクスと意味:第3巻 くろしお出版
- 早瀬尚子(編著)吉村あき子・谷口一美・小松原哲太・井上逸兵・多々良直弘(2018).言語の認知とコミュニケーション:意味論・語用論、認知言語学、社会言語学 開拓社(Amazon.co.jpレコメンド機能で知る)
[2018.12.13]IRなどについての文献メモ 文献一覧を更新<言語発達>
- 岩立志津夫・小椋たみ子(編)(2017).よくわかる言語発達 ミネルヴァ書房
- 広瀬友紀(2017).ちいさい言語学者の冒険:子どもに学ぶことばの秘密 岩波書店(Twitter(@hamakado_mamikoさん)で知る)
- 小山正(2018).言語発達 ナカニシヤ出版(Amazon.co.jp「言語発達」で知る)
- 遊佐典昭(編著)杉崎鉱司・小野創・藤田耕司・田中伸一・池内正幸・谷明信・尾崎久男・米倉綽(2018).言語の獲得・進化・変化:心理言語学、進化言語学、歴史言語学 開拓社(Twitter(@editechさん)で知る)
- 小椋たみ子・小山正・水野久美(2015).乳幼児期のことばの発達とその遅れ:保育・発達を学ぶ人のための基礎知識 ミネルヴァ書房(Amazon.co.jp「言語発達」で知る)
- 石田宏代・石坂郁代(編)(2016).言語聴覚士のための言語発達障害学 医歯薬出版(Amazon.co.jp「言語発達」で知る)
- 臨床発達心理士認定運営機構(監修)秦野悦子・高橋登(編)(2017).言語発達とその支援 ミネルヴァ書房(Amazon.co.jp「言語発達」で知る)
[2018.12.13]IRなどについての文献メモ 文献一覧を更新<資料作成、フォント>
- MdN編集部(編)(2018).MdN EXTRA Vol. 5 絶対フォント感を身につける。 エムディエヌコーポレーション(Amazon.co.jpレコメンド機能で知る)
- 山本高史(2018).伝わるしくみ マガジンハウス(Amazon.co.jpレコメンド機能で知る)
- 写真植字機研究所石井茂吉伝記編纂委員会(1969).石井茂吉と写真植字機 写真植字機研究所石井茂吉伝記編纂委員会(Amazon.co.jp「石井茂吉」で知る)
[2018.12.13]IRなどについての文献メモ 文献一覧を更新<学生支援>
- 東田直樹(2014).跳びはねる思考:会話のできない自閉症の僕が考えていること イースト・プレス(Amazon.co.jp「東田直樹」で知る)
- 東田直樹(2016).自閉症の僕が跳びはねる理由 KADOKAWA(Amazon.co.jp「東田直樹」で知る)
- 東田直樹(2016).自閉症の僕が跳びはねる理由 (2) KADOKAWA(Amazon.co.jp「東田直樹」で知る)
[2018.12.13]IRなどについての文献メモ 文献一覧を更新<プログラミング教育>
- 阿部和広・豊福晋平・芳賀高洋(監修)(2018).小学校の先生のための Why!?プログラミング 授業活用ガイド 日経BP社(Amazon.co.jpレコメンド機能で知る)
- 石原淳也・阿部和広(監修)(2018).Scratchで楽しく学ぶ アート&サイエンス 日経BP社(Amazon.co.jpレコメンド機能で知る)
- 赤堀侃司(2018).プログラミング教育の考え方とすぐに使える教材集 ジャムハウス(Amazon.co.jp「プログラミング教育」で知る)
- 小林祐紀・兼宗進・白井詩沙香・臼井英成(編著・監修)(2018).これで大丈夫!小学校プログラミングの授業:3+αの授業パターンを意識する 翔泳社(Amazon.co.jp「プログラミング教育」で知る)
[2018.12.13]IRなどについての文献メモ 文献一覧を更新<質的研究>
- 御厨貴(編)(2007).オーラル・ヒストリー入門 岩波書店
[2018.12.13]IRなどについての文献メモ 文献一覧を更新<辞書学>
- 安田敏朗(2018).大槻文彦『言海』:辞書と日本の近代 慶應義塾大学出版会(Amazon.co.jp「大槻文彦」で知る)
- 今野真二(2018).『日本国語大辞典』をよむ 三省堂
- 沖森卓也(編)木村一・山本真吾・陳力衛・木村義之(2008).図説 日本の辞書 おうふう(Amazon.co.jpレコメンド機能で知る)
- 増井元(2013).辞書の仕事 岩波書店(Amazon.co.jpレコメンド機能で知る)
- 倉島節尚(2002).辞書と日本語:国語辞典を解剖する 光文社
- 見坊豪紀(1990).日本語の用例採集法 南雲堂(倉島(2002)『辞書と日本語』で知る)
- 飯間浩明(2013).辞書に載る言葉はどこから探してくるのか?:ワードハンティングの現場から ディスカヴァー・トゥエンティワン(Amazon.co.jpレコメンド機能で知る)
[2018.12.13]IRなどについての文献メモ 文献一覧を更新<マーケットデザイン>
- 坂井豊貴(2010).マーケットデザイン入門:オークションとマッチングの経済学 ミネルヴァ書房(Amazon.co.jp「マーケットデザイン」で知る)
- 坂井豊貴(2013).マーケットデザイン:最先端の実用的な経済学 筑摩書房(Amazon.co.jp「マーケットデザイン」で知る)
- 川越敏司(2015).マーケット・デザイン オークションとマッチングの経済学 講談社(Amazon.co.jp「マーケットデザイン」で知る)
- ロス,A.E.櫻井祐子(訳)(2018).Who gets what:マッチメイキングとマーケットデザインの経済学 日本経済新聞出版社(Amazon.co.jp「マーケットデザイン」で知る)
[2018.12.10]IRなどについての文献メモ 文献一覧を更新<IR>
- 荒木俊博・藤原僚平・上畠洋佑(2018).日本版コモン・データ・セット(CDS)実現に向けた予備的研究:大学を対象にした調査の質問項目の分析を通して 大学評価とIR,9,50-61.[PDF](大学評価コンソーシアムメーリングリストで知る)
- 吉本圭一(2007).卒業生を通した「教育の成果」の点検・評価方法の研究 大学評価・学位研究,5,75-107.[PDF](Google「卒業生調査 卒後」で知る)
- 東京大学大学経営・政策コース(編)(2018).大学経営・政策入門 東信堂(Twitter(@ish3173さん)で知る)
- 丸山剛史・橋本啓・石井和也・桑島英理佳・小柏香穂理・竹井沙織(2018).学修到達度可視化システムの開発に関する基礎研究:学生及び教員を対象としたアンケート調査を通して 宇都宮大学教育学部教育実践紀要,5,373-376.[PDF](Twitter(@daigaku23さん)で知る)
- 大津史子(2018)薬学部での教学IRの試み2:名城大学薬学部での取り組み 薬学教育,2,1-5.[PDF]((Twitter(@daigaku23さん)で知る)
[2018.12.10]IRなどについての文献メモ 文献一覧を更新<言語学、日本語学、音声学、語用論>
- 山東功(2016).書評論文 斉木美知世・鷲尾龍一著『国語学史の近代と現代:研究史の空白を埋める試み』 日本語文法,16(1),112-119.(Google「斉木美知世」で知る)
- 榎木久薫(2016).通時的変化として見たサ行子音とザ行子音 地域学論集 鳥取大学地域学部紀要,12(3),211-219.[PDF](Google Scholar「サ行子音の歴史」で知る)
- 小倉肇(1998).サ行子音の歴史 国語学,195,71-58.[PDF](Google「サ行 音声学」で知る)
- 服部隆(2017).明治期における日本語文法研究史 ひつじ書房(安田(2018)『大槻文彦『言海』:辞書と日本の近代』で知る)
- 斉木美知世・鷲尾龍一(2012).日本文法の系譜学 :国語学史と言語学史の接点 開拓社(安田(2018)『大槻文彦『言海』:辞書と日本の近代』で知る)
- 井之口有一(1982).明治以後の漢字政策 日本学術振興会(安田(2018)『大槻文彦『言海』:辞書と日本の近代』で知る)
- 磯野英治・上仲淳(2014).日本語学習者の接触場面におけるターン交替時の発話の語用論的特徴 大阪大学国際教育交流センター研究論集,18,31-39.[PDF](Google Scholar「語用論」で知る)
[2018.12.10]IRなどについての文献メモ 文献一覧を更新<音声認識、会話>
- 河原達也(2018).音声認識技術の変遷と展望 自動認識,31(10),55-58.(CiNii Articles「音声認識」で知る)
- 渡部晋治・堀貴明(2018).音声言語理解のための音声認識 電子情報通信学会誌,101(9),885-890.(CiNii Articles「音声認識」で知る)
- 中野幹生(2018).音声言語理解技術の概要と今後の展望 電子情報通信学会誌,101(9),875-879.(CiNii Articles「音声認識」で知る)
- 河原達也(2018).音声認識技術の変遷と最先端:深層学習によるEnd-to-Endモデル 日本音響学会誌,74(7),381-386.(CiNii Articles「音声認識」で知る)
- 駒谷和範(2018).音声認識技術を使った人と機械との対話 生産と技術,70(4),19-25.(CiNii Articles「音声認識」で知る)
- 河原達也・荒木章子(2018).会議録作成を支援するICT 電子情報通信学会誌,101(5),486-491.(CiNii Articles「音声認識」で知る)
- 高木正則・河合直樹・大信田侑里・鈴木雅実・木村寛明(2018).発話に含まれる特性語の出現頻度に基づいた協調学習時の貢献度推定手法の提案と評価 情報処理学会論文誌教育とコンピュータ(TCE),4(1),70-82.(CiNii Articles「音声認識」で知る)
- 李晃伸(2018).汎用大語彙音声認識ソフトウェア入門 システム/制御/情報,62(2),50-56.[PDF](CiNii Articles「音声認識」で知る)
- 宮部真衣・四方朱子・久保圭・荒牧英治(2018).音声認識を用いた言語能力自動測定システム"言秤"の構築 自然言語処理,25(1),33-56.[PDF](CiNii Articles「音声認識」で知る)
- 齊藤剛史(2017).サイレント音声認識の研究動向:読唇技術を中心として 電子情報通信学会技術研究報告,117(251),77-81.(CiNii Articles「音声認識」で知る)
- 能勢隆(2017).深層学習を利用した多様な音声の合成・認識・変換と応用 電子情報通信学会技術研究報告,117(160),3-8.(CiNii Articles「音声認識」で知る)
- 河野進・相原健郎(2017).グループ会話における発話意図の推定システム 情報処理学会論文誌,58(5),1113-1123.(CiNii Articles「音声認識」で知る)
- 佐藤庄衛(2017).音声認識技術の動向と字幕制作システムの地域局展開 NHK技研R&D,161,4-12.(CiNii Articles「音声認識」で知る)
- 下岡和也・徳久良子・吉村貴克・星野博之・渡部生聖(2017).音声対話ロボットのための傾聴システムの開発 自然言語処理,24(1),3-47.(CiNii Articles「音声認識」で知る)
- 磯健一(2017).音声認識におけるDeep Learningの活用 日本神経回路学会誌,24(1),27-38.(CiNii Articles「音声認識」で知る)
- 入部百合絵・北岡教英(2017).音声認識にむけた超高齢者音声のコーパス構築 日本音響学会誌,73(5),303-310.[PDF](CiNii Articles「音声認識」で知る)
- 石黒浩(2016).人工知能学会共同企画:人工知能とは何か? 情報処理,57(10),958-959.(CiNii Articles「音声認識」で知る)
- 久保陽太郎(2016).ニューラルネットワークによる音声認識の進展 人工知能,31(2),180-188.(CiNii Articles「音声認識」で知る)
- 吉川雄一郎・石黒浩(2016).複数体のロボットによる音声認識なし対話の可能性 電子情報通信学会通信ソサイエティマガジン,10(3),179-183.[PDF](CiNii Articles「音声認識」で知る)
- 河原達也・原田達也(2016).音声認識・画像認識における機械学習の最近の動向 システム/制御/情報,60(3),113-119.[PDF](CiNii Articles「音声認識」で知る)
- 河原達也(2015).音声認識技術の展開 電子情報通信学会技術研究報告,115(388),111-116.(CiNii Articles「音声認識」で知る)
- 中川聖一(2015).音声処理技術がヒトの能力を超える日 電子情報通信学会技術研究報告,115(346),25-30.(CiNii Articles「音声認識」で知る)
- 中谷智広(2015).音声音響信号処理の国際会議参加報告:IEEE ICASSP 2015 情報処理,56(9),932-933.(CiNii Articles「音声認識」で知る)
- 河原達也(2015).音声認識技術 電子情報通信学会誌,98(8),710-717.(CiNii Articles「音声認識」で知る)
- 中村哲(2015).音声翻訳技術概観 電子情報通信学会誌,98(8),702-709.(CiNii Articles「音声認識」で知る)
- 南條浩輝・西崎博光(2015).初等教育における授業音声の収集と音声認識の基礎的検討 情報処理学会研究報告.SLP,音声言語情報処理,2015-SLP-106(2),1-7.(CiNii Articles「音声認識」で知る)
- 山崎史生・芋野美紗子・土屋誠司・渡部広一(2015).会話システムにおける質問文の回答予測による音声認識補正システム 電子情報通信学会技術研究報告,114(481),29-34.(CiNii Articles「音声認識」で知る)
- 藤江真也(2015).イラストで学ぶ音声認識,荒木雅弘著,講談社,2015年,A5判,185頁,定価2,600円(税別) 日本音響学会誌,71(10),554.[PDF](CiNii Articles「音声認識」で知る)
- 荒木雅弘(2015).イラストで学ぶ音声認識 講談社(藤江真也(2015)の書評で知る)
- 西光雅弘・堀智織(2015).現在の音声認識にできること・できないこと 日本音響学会誌,71(3),158-163.[PDF](CiNii Articles「音声認識」で知る)
- 荒木章子・堀貴明・中谷智広(2014).会話シーン分析の複数人自由会話音声認識における音声強調 電子情報通信学会技術研究報告,114(274),9-14.(CiNii Articles「音声認識」で知る)
- 南角吉彦(2014).統計的機械学習問題としての音声研究 電子情報通信学会技術研究報告,114(151),25-30.(CiNii Articles「音声認識」で知る)
- 河原達也(2014).実用化進む音声認識 システムの構成要素を概観 日経エレクトロニクス,1135,88-95.(CiNii Articles「音声認識・対話技術の基礎と応用」で知る)
- 河原達也(2014).音声認識に新潮流 ビッグデータやDNNを活用 日経エレクトロニクス,1136,82-87.(CiNii Articles「音声認識・対話技術の基礎と応用」で知る)
- 河原達也(2014).音声認識・対話のアプリケーション:成功の鍵は必然性や自然性 日経エレクトロニクス,1137,68-74.(CiNii Articles「音声認識」で知る)
- 河原達也(2014).話し言葉をテキスト化するシステム 会議録の作成や字幕付与への展開 日経エレクトロニクス,1138,92-97.(CiNii Articles「音声認識・対話技術の基礎と応用」で知る)
- 河原達也(2014).音声対話システムの実際 Siriはどのように成功したか 日経エレクトロニクス,1139,86-93.(CiNii Articles「音声認識・対話技術の基礎と応用」で知る)
- 久保陽太郎(2014).音声認識における深層学習の活用とその進展 電子情報通信学会技術研究報告,114(52),39-44.(CiNii Articles「音声認識」で知る)
- 河原達也(2014).音声認識の方法論に関する考察:世代交代に向けて 情報処理学会研究報告.SLP,音声言語情報処理,2014-SLP-100(3),1-5.(CiNii Articles「音声認識」で知る)
- 篠田浩一・堀貴明・堀智織・篠崎隆宏(2014).「音声認識」は今後こうなる! 研究報告音声言語情報処理(SLP),2014-SLP-100(2),1-6.(CiNii Articles「音声認識」で知る)
- 久保陽太郎(2014).音声認識のための深層学習 人工知能,29(1),62-71.[PDF](CiNii Articles「音声認識」で知る)
- 荒木雅弘(2017).フリーソフトでつくる音声認識システム:パターン認識・機械学習の初歩から対話システムまで 森北出版(Amazon.co.jp「音声認識」で知る)
[2018.12.10]IRなどについての文献メモ 文献一覧を更新<プログラミング教育>
- 内田早紀子・松村敦(2018).日常の活動を題材とした小学生向けプログラミング的思考育成ツールの開発 研究報告コンピュータと教育(CE),2018-CE-147(9),1-5.[PDF](Google Scholar「プログラミング教育」で知る)
- 安影亜紀・新地辰朗(2018).教員研修による小学校プログラミング教育の実践・促進に関わる自信の変容 日本科学教育学会研究会研究報告,33(2),43-46.[PDF](Googleアラート「プログラミング教育」で知る)
- 小野功一郎(2018).「Society5.0」に向けた小学校におけるプログラミング教育の提言:ドローンフライトをプログラミングする 日本デジタル教科書学会発表予稿集,7,89-90.[PDF](Google Scholar「プログラミング教育」で知る)
- 伊東史子・長谷川春生(2018).プログラミングを取り入れた総合的な学習の時間に関する研究:小学校第6学年「わたしたちのくらしとコンピュータ」の授業実践を通して 日本デジタル教科書学会発表予稿集,7,87-88.[PDF](Google Scholar「プログラミング教育」で知る)
- 嶋田賢太郎・長谷川春生(2018).プログラミング教材を取り入れた体育科の学習に関する研究:小学校第5学年「ホップ・ステップ・ダンス!」の授業実践を通して 日本デジタル教科書学会発表予稿集,7,85-86.[PDF](Google Scholar「プログラミング教育」で知る)
- 北野彩佳・坂田陽子(2018).幼児の絵本内容理解にデジタルデバイスの画面サイズが及ぼす影響 日本デジタル教科書学会発表予稿集,7,69-70.[PDF](Google Scholar「プログラミング教育」で知る)
- 山田秀哉・小野田千明(2018).小学校2年生におけるプログラミング教育の実践報告 日本デジタル教科書学会発表予稿集,7,61-62.[PDF](Google Scholar「プログラミング教育」で知る)
- 白石利夫(2018).肢体不自由特別支援学校におけるタブレット端末の活用 日本デジタル教科書学会発表予稿集,7,35-36.[PDF](Google Scholar「プログラミング教育」で知る)
- 岡花和樹・村上元良・細辻浩介・堀優作・森真樹・竹中章勝(2018).プログラミング的思考とアナログ的操作を融合した算数授業の研究 日本デジタル教科書学会発表予稿集,7,29-30.[PDF](Google Scholar「プログラミング教育」で知る)
- 三井一希・佐藤和紀・萩原丈博・竹内慎一・堀田龍也(2018). 日本デジタル教科書学会発表予稿集,7,27-28.[PDF](Google Scholar「プログラミング教育」で知る)
- 松田孝(2018).低学年プログラミング教育の必然性とその実際:Cutlery Appsの活用を通して 日本デジタル教科書学会発表予稿集,7,25-26.[PDF](Google Scholar「プログラミング教育」で知る)
- 手塚明美・長谷川春生(2018).フローチャートを作成する活動を取り入れた小学校家庭科の単元開発 日本デジタル教科書学会発表予稿集,7,15-16.[PDF](Google Scholar「プログラミング教育」で知る)
- 佐藤和紀・礒川祐地・萩原丈博・竹内慎一・堀田龍也(2018).IoTブロックを活用したプログラミング教育の授業実践構想に関する分類 日本デジタル教科書学会発表予稿集,7,5-6.[PDF](Google Scholar「プログラミング教育」で知る)
- 木村了士・臼井英成・小林祐紀(2018).小学校第5学年算数科におけるプログラミング教育の授業開発:ドリトルを用いた正多角形の作図の指導 日本デジタル教科書学会発表予稿集,7,3-4.[PDF](Google Scholar「プログラミング教育」で知る)
- 岩山直樹・伊藤一成・長谷川春生(2018)生活とつながるプログラミング教育の授業開発:5年「よりよい生活を送るために〜人型ピクトグラムで情報を伝えよう〜」の実践を通して 日本デジタル教科書学会発表予稿集,7,1-2.[PDF](Google Scholar「プログラミング教育」で知る)
- 山本利一・山内悠(2018).初等教育における特別な教科「道徳」で取り組むプログラミング学習の提案 教育情報研究,34(1),17-25.[PDF](Google Scholar「プログラミング教育」で知る)
- 菊池貴大・鈴木研二・岩波正浩・松原真理(2018).小学生のためのロボット教材を用いたプログラミング学習 宇都宮大学教育学部教育実践総合センター紀要,36,249-256.[PDF](宇都宮大学学術リポジトリで知る)
- 平間啓太郎・菊地智美・菊池貴大・松原真理(2018).小学生を対象にしたロボットを用いたプログラミング教室 宇都宮大学教育学部教育実践総合センター紀要,37,141-148.[PDF](宇都宮大学学術リポジトリで知る)
- 小林毅・小泉拓也・松原真理(2018).大学生を対象としたプログラミングの授業実践 宇都宮大学教育学部教育実践紀要,2,441-444.[PDF](宇都宮大学学術リポジトリで知る)
- 藤沼航・坂本弘志・松原真理(2018).小学校3年生を対象にしたプログラミングの授業実践 宇都宮大学教育学部教育実践紀要,3,441-444.[PDF](宇都宮大学学術リポジトリで知る)
- 戸田富士夫・坂本弘志・松原真理(2018).義務教育におけるプログラミングの授業の提案 宇都宮大学教育学部教育実践紀要,4,83-88.[PDF](宇都宮大学学術リポジトリで知る)
- 日向野歩・岡田倫明・坂本弘志・松原真理(2018).小学校におけるロボットを用いた授業実践 宇都宮大学教育学部教育実践紀要,5,487-490.[PDF](宇都宮大学学術リポジトリで知る)
- 岡田倫明・上岡惇一・戸田富士夫・松原真理(2018).教育学部学生を対象としたプログラミングの授業実践 宇都宮大学教育学部教育実践紀要,5,479-482.[PDF](宇都宮大学学術リポジトリで知る)
- 鹿江宏明(2018).小学校教員養成におけるプログラミング教育に関する研究(1):教育版LEGO MINDSTORMを用いた授業実践例 比治山大学紀要,24,111-119.[PDF](Google Scholar「プログラミング教育」で知る)
[2018.12.10]IRなどについての文献メモ 文献一覧を更新<アセスメント、評価>
- サスキー,L.齋藤聖子(訳)(2015).学生の学びを測る:アセスメント・ガイドブック 玉川大学出版部(大学評価コンソーシアムメーリングリストで知る)
- ウォルワード,B.山﨑めぐみ・安野舞子・関田一彦(訳)(2013).大学教育アセスメント入門:学習成果を評価するための実践ガイド ナカニシヤ出版(大学評価コンソーシアムメーリングリストで知る)
- バーンバウム,R.高橋靖直(訳)(1992).大学経営とリーダーシップ 玉川大学出版部(大学評価コンソーシアムメーリングリストで知る)
[2018.12.10]IRなどについての文献メモ 文献一覧を更新<統計>
- 佐原奈々美・中村俊彦・逢沢峰昭・大久保達弘(2018).日本中部亜高山帯林の伐採後に成立した落葉広葉樹優占林の実生の発生・定着におけるコケ群落の役割 日本森林学会誌,100(4),102-109.[PDF]([Steel-Dwassの方法を用いた多重比較検定]の記載例、図あり、和文;Google Scholar「"Steel-Dwass"」で知る)
- 岡崎千聖・逢沢峰昭・森嶋佳織・福沢朋子・大久保達弘(2018).群馬県のナラ枯れを起こしたカシノナガキクイムシは在来か近年移入の個体群か:遺伝解析に基づく検証 日本森林学会誌,100(4),116-123.[PDF]([Steel-Dwassの方法を用いた多重比較検定]の記載例、和文;Google Scholar「"Steel-Dwass"」で知る)
[2018.12.10]IRなどについての文献メモ 文献一覧を更新<ティーチング・ポートフォリオ>
- 皆本晃弥(2016).ティーチング・ポートフォリオによる教育業績評価 医学教育,47(2),89-96.[PDF](Google「ティーチングポートフォリオ」で知る)
- 大学評価・学位授与機構(2014).ティーチング・ポートフォリオの定着・普及に向けた取り組み:効果検証・質保証・広がり 大学評価・学位授与機構評価研究部[PDF](Google「ティーチングポートフォリオ」で知る)
[2018.11.3]「過去の「お知らせ」」、「IRなどについての文献メモ」、「これまでの発表・競争的研究資金など」に追加
- 口頭発表「志願者・合格者・入学者の動向を把握する」(平成30年度IR実務担当者連絡会)を掲載
[2018.8.29]「過去の「お知らせ」」、「IRなどについての文献メモ」、「これまでの発表・競争的研究資金など」に追加
- ポスター発表「評価・IR担当者に必要な知識・スキルを考える」(SPODフォーラム2018)を掲載
[2018.8.24]「ホーム」、「これまでの発表・競争的研究資金など」に追加
- 研究助成「大学IRの充実に資する研究または実践活動(平成30年度)」(一般財団法人大学IR総研)採択結果を掲載
[2018.8.24]「過去の「お知らせ」」に追加
- スタッフ担当「内部質保証に向けたIRや調査機能の育成、評価・IRの実践・課題共有セッション、IR実務担当者セッション」(大学評価・IR担当者集会2018)を掲載
[2018.8.24]IRなどについての文献メモ 文献一覧を更新<政策評価>
- 米国行政学会・行政経営センター(原著)・谷口敏彦(訳)・村岡政明(編)(2001).行政評価の世界標準モデル:戦略計画と業績測定 東京法令出版
- 佐々木亮(2003).政策評価トレーニング・ブック:7つの論争と7つの提案 多賀出版
- 龍慶昭・佐々木亮(2009).大学の戦略的マネジメント:経営戦略の導入とアメリカの大学の事例 多賀出版(Amazon.co.jp「政策評価トレーニング・ブック」で知る)
- 国際協力機構企画・評価部評価監理室(編著)(2004).プロジェクト評価の実践的手法/考え方と使い方 国際協力出版会
[2018.8.24]「過去の「お知らせ」」、「IRなどについての文献メモ」、「これまでの発表・競争的研究資金など」に追加
- 口頭発表「IR実態調査の概要(総集編)」(大学評価・IR担当者集会2018)を掲載
[2018.8.24]「ホーム」「これまでの発表・競争的研究資金など」に追加
[2018.8.21]IRなどについての文献メモ 文献一覧を更新<統計>
- 南風原朝和・平井洋子・杉澤武俊(2009).心理統計学ワークブック:理解の確認と深化のために 有斐閣(Amazon.co.jp「心理学 ワークブック」で知る)
[2018.8.21]IRなどについての文献メモ 文献一覧を更新<インテリジェンス>
- 小林良樹(2014).インテリジェンスの基礎理論 立花書房(四天王寺大学図書館書架で知る)
- Lowenthal, M. M.茂田宏(訳)(2011).インテリジェンス:機密から政策へ 慶應義塾大学出版会(小林良樹(2014)『インテリジェンスの基礎理論』で知る)
- 北岡元(2008).仕事に役立つインテリジェンス PHP研究所(Amazon.co.jp「インテリジェンス 北岡元」で知る)
- 北岡元(2009).ビジネス・インテリジェンス:未来を予想するシナリオ分析の技法 東洋経済新報社(Amazon.co.jp「インテリジェンス 北岡元」で知る)
- 北岡元(2009).インテリジェンス入門:利益を実現する知識の創造 慶應義塾大学出版会(Amazon.co.jp「インテリジェンス 北岡元」で知る)
- 情報史研究会(編)(2008).名著で学ぶインテリジェンス 日本経済新聞出版社(Amazon.co.jp「インテリジェンス 北岡元」で知る)
[2018.8.8]サイト全体 常時SSL化
[2018.8.8]「これまでの発表・競争的研究資金など」に追加
- 講師「ICT実践活用」(平成30年度免許状更新講習)
- 講師「情報教育」(平成30年度免許状更新講習)
[2018.8.2]IRなどについての文献メモ 文献一覧を更新<IR>
- 岩田康之(2018).教員養成系大学における教学改善とIR:HATOプロジェクトの取り組みから 情報の科学と技術,68(3),105-110.[PDF](Google Scholar「キャリア意識 調査 大学」で知る)
- 山田礼子(2010).大学教育の成果測定:学生調査の可能性と課題 クオリティ・エデュケーション,3,15-32.[PDF](Google「就職 "直接評価" "間接評価"」で知る)
- 春原淑雄(2007).教育学部生の教師効力感に関する研究:尺度の作成と教育実習にともなう変化 日本教師教育学会年報,16,98-108.(「平成27年度HATOプロジェクト「教学IRシンポジウム」資料」で知る)
- 松井寿貢(2016).IR(Institutional Research)組織の設置:私立大学等改革総合支援事業への対応 私学経営,496,21-31.(沖(2017)「私立大学経営におけるIR(Institutional Research)の意義と課題」で知る)
- 沖清豪(2017).私立大学経営におけるIR(Institutional Research)の意義と課題 日本教育経営学会紀要,59,26-35.[PDF](Google Scholar「私立大学等総合改革支援事業」で知る)
- 岩崎保道・鈴木弘道(2017).IR組織の動向 関西大学高等教育研究,8,93-101.[PDF](Google Scholar「私立大学等総合改革支援事業」で知る)
- 姉川恭子(2017).ベンチマークを通じて明らかにする早稲田大学の学生調査の課題 早稲田教育評論,31(1),73-83.[PDF](早稲田大学で実施されている学生関連の各種調査を整理、「学生生活調査」に関して調査自体の課題を抽出;Google Scholar「"学生生活調査"」で知る)
- 濱名篤・川嶋太津夫・山田礼子・小笠原正明(2013).大学改革を成功に導くキーワード 30:「大学冬の時代」 を生き抜くために 学事出版株式会社(山形大学において3つのポリシーに用いることのできる動詞等の一覧を整理する際に参照;浅野(2017)「3つのポリシーの体系化に向けたIRによる支援」で知る)
- 宮本淳・出口寿久・伊藤一馬・川西奈津美・河野未幸・鈴木里奈・細川敏幸.(2018).教職員協働による教学に関するIR(Institutional Research)勉強会 高等教育ジャーナル:高等教育と生涯学習,25,49-54.[PDF](「」で知る)
- 武藤英幸(2018).国立大学入試担当課職員の汎用性と専門性:法人化と高大接続改革に伴う職能開発 名古屋高等教育研究 ,18,71-86.[PDF](Google Scholarアラート「インスティテューショナル・リサーチ」で知る)
- 浅野茂(2017).<高等教育の動向>米国におけるIR/IEの最新動向と日本への示唆 京都大学高等教育研究,23,97-108.[PDF](Google Scholarアラート「"institutional research"」で知る)
- 山田剛史(2018).大学教育の質的転換と学生エンゲージメント 名古屋高等教育研究,18,155-176.[PDF](Google Scholarアラート「"institutional research"」で知る)
[2018.8.2]IRなどについての文献メモ 文献一覧を更新<3つのポリシー、アセスメント・ポリシー>
- 沖裕貴・宮浦崇・井上史子(2011).一貫性構築のための3つのポリシー(DP・CP・AP)の策定方法:各大学の事例をもとに 教育情報研究,26(3),17-30.[PDF](使用可能な動詞等の一覧を山形大で整理する際に参照;浅野(2017)「3つのポリシーの体系化に向けたIRによる支援」で知る)
- 池田輝政・野口真弓・佐々木幾美(2014).学位授与方針から設計するカリキュラム・マッピングの提案と実践 大学・学校づくり研究.6,29-40.[PDF](浅野(2017)「3つのポリシーの体系化に向けたIRによる支援」で知る)
- 松下佳代(2016).学生に求められる能力とその評価 学士課程教育機構研究誌,5,49-62.[PDF](Google Scholar「アセスメントポリシー」で知る)
- 野村浩(2018).アセスメントポリシー策定にむけた看護学科の取り組み Bulletin of Toyohashi Sozo University,22,45-57.[PDF](Google Scholar「アセスメントポリシー」で知る)
- 細川敏幸・山田邦雅・宮本淳(2018).アセスメント・ポリシーの考え方:アセスメント・ポリシー研究会報告 高等教育ジャーナル:高等教育と生涯学習,25,69-73.[PDF](Twitter(@high190さん)で知る
[2018.8.2]IRなどについての文献メモ 文献一覧を更新<学習成果>
- 松下佳代(2012).パフォーマンス評価による学習の質の評価:学習評価の構図の分析にもとづいて 京都大学高等教育研究,18,75-114.[PDF](松下(2016)「学生に求められる能力とその評価」で知る)
[2018.8.2]IRなどについての文献メモ 文献一覧を更新<学生生活調査>
- 津富宏・小針進・斉藤麻友佳(2017)静岡県立大学生は, 安心して大学生活を送り, 勉学に励むことができているか:県大生の経済状況に関する調査結果 国際関係・比較文化研究,16(1),31-70.[PDF](奨学金・アルバイト状況の調査、設問記載あり;Google Scholar「"学生生活調査"」で知る)
- 岩田弘三(2018).大学における中退の実態とその防止に向けた取り組み:大学へのヒアリング調査をもとにした事例分析 武蔵野大学教養教育リサーチセンター紀要,8,15-26.>[PDF](Google Scholar「"学生生活調査"」で知る)
[2018.8.2]IRなどについての文献メモ 文献一覧を更新<中途退学>
- 古曵牧人・川邉讓・岩熊史朗・高岸百合子(2017)心理学部における中途退学の要因の検討 駿河台大学論叢,54,73-83.[PDF](Google Scholar「GPA 中途退学」で知る)
[2018.8.2]IRなどについての文献メモ 文献一覧を更新<学力>
- 大作勝・南部広孝(2006).AO入試における調査書の扱いについて 大学入試研究ジャーナル,16,65-70.[PDF](Google Scholar「評定平均 学力 相関」で知る)
[2018.8.2]IRなどについての文献メモ 文献一覧を更新<初年次教育>
- 山田剛史(2007).学生の視点を踏まえた初年次教育の展開:多様化を見据えた教育改革の組織化に向けて 島根大学生涯学習教育研究センター研究紀要,5,15-29.[PDF](Google Scholar「初年次教育」で知る)
- 石倉健二・高島恭子・原田奈津子・山岸利次(2008).ユニバーサル段階の大学における初年次教育の現状と課題 長崎国際大学論叢,8,167-177.[PDF](「初年次教育」がいかなるものであるかを国内外の動向をレビューしつつ検討;Google Scholar「初年次教育」で知る)
- 藤田哲也(2006).初年次教育の目的と実際 リメディアル教育研究,1(1),1-9.[PDF](Google Scholar「初年次教育」で知る)
[2018.8.2]IRなどについての文献メモ 文献一覧を更新<統計>
- 金谷英俊・磯谷悠子・牧勝弘・天野成昭(2018).心理統計のためのSPSS操作マニュアル:t検定と分散分析 ナカニシヤ出版(Google「ナカニシヤ出版 心理統計」で知る)
[2018.8.2]IRなどについての文献メモ 文献一覧を更新<私立大学等総合改革支援事業>
- 佐藤雄一(2014).私立大学等改革総合支援事業について 大学評価研究,13,69-77.[PDF](前文部科学省 高等教育局 私学部 私学助成課 課長補佐が執筆(肩書は執筆当時)、見解は個人的なものである旨の記載あり;Google Scholar「私立大学等総合改革支援事業」で知る))
[2018.8.2]IRなどについての文献メモ 文献一覧を更新<キャリア教育>
- 髙橋南海子(2018).大学生の就職活動に関する実証的研究の動向と課題 明星大学明星教育センター研究紀要,8,1-15.[PDF](Google Scholar「大学 就職 アンケート」で知る)
- 坂柳恒夫(1996).大学生のキャリア成熟に関する研究:キャリア・レディネス尺度(CRS)の信頼性と妥当性の検討 愛知教育大学教科教育センター研究報告,20,9-18.[PDF](職業キャリア成熟/人生キャリア成熟の観点で関心性・自律性・計画性を測定する尺度を作成;髙橋(2018)「大学生の就職活動に関する実証的研究の動向と課題」で知る)
- 下村英雄・堀洋道(1994).大学生の職業選択における情報収集行動の検討 筑波大学心理学研究,16,209-220.[PDF](若林他(1983)の下位次元を再検討、「明瞭性」・「関与」・「非選択性」の3つに集約;髙橋(2018)「大学生の就職活動に関する実証的研究の動向と課題」で知る)
- 杉本英晴(2008).大学生における 「就職しないこと」 イメージの構造と進路未決定:テキストマイニングを用いた検討 名古屋大学大学院教育発達科学研究科紀要 心理発達科学,55,77-89.[PDF](「就職イメージ尺度」を作成;杉本・速水(2012)「大学生における仮想的有能感と就職イメージおよび時間的展望」で知る)
- 種市康太郎・志村直子(2005).企業内定と社会的スキルおよび就職活動の関連の検討 産業ストレス研究,13(1),61.(就職活動を経験した人に生じる変化、知識や実務的な能力の獲得とその知識や能力を活用した結果として生じる態度や行動の変化;髙橋(2018)「大学生の就職活動に関する実証的研究の動向と課題」で知る)
- 柿澤寿信・田澤実・梅崎修(2013).SNSは就職活動の効果的ツールか?:就職活動生に対するアンケート調査結果の分析 キャリアデザイン研究,9,181-189.(SNSの使用状況が大学生の就職意識や就職活動への取り組み状況に与える影響を検討;髙橋(2018)「大学生の就職活動に関する実証的研究の動向と課題」で知る)
- 関口倫紀(2012).大学生のアルバイト選択とコミットメントおよび就職活動目標:中核的自己評価と職務特性の役割を中心に 経営行動科学,25(2),129-140.(アルバイトが就職活動に及ぼす影響を検討;髙橋(2018)「大学生の就職活動に関する実証的研究の動向と課題」で知る)
- 杉村和美(2001).関係性の観点から見た女子青年のアイデンティティ探求:2年間の変化とその要因 発達心理学研究,12(2),87-98.[PDF](就職活動を経験した人に生じる変化、それまで意識してこなかった重要な他者との関係の再認識や再構築;髙橋(2018)「大学生の就職活動に関する実証的研究の動向と課題」で知る)
- 梅村祐子・金井篤子(2006).就職活動における理想と現実の統合過程に関する探索的研究 経営行動科学,19(2),151-162.[PDF](大学生は就職活動中に理想自己と現実自己とのギャップ、理想自己と現実状況とのギャップに直面する、現実状況がすり合わされて統合される;髙橋(2018)「大学生の就職活動に関する実証的研究の動向と課題」で知る)
- 浦上昌則(1996).女子短大生の職業選択過程についての研究 教育心理学研究,44(2),195-203.[PDF](就職活動を経験した人に生じる変化、自己概念および職業的自己概念の明確化、縦断研究(就職活動終了後に自己概念を調査);髙橋(2018)「大学生の就職活動に関する実証的研究の動向と課題」で知る)
- 北見由奈・茂木俊彦・森和代(2009).大学生の就職活動ストレスに関する研究:評価尺度の作成と精神的健康に及ぼす影響 学校メンタルヘルス,12(1),43-50.(ソーシャルスキルの高低と就職活動ストレス・精神的健康との関連を検討、就労目標が定まっていないことが精神的健康に悪影響を及ぼす;髙橋(2018)「大学生の就職活動に関する実証的研究の動向と課題」で知る)
- 北見由奈・森和代(2010).大学生の就職活動ストレスおよび精神的健康とソーシャルスキルとの関連性の検討 ストレス科学研究,25,37-45.[PDF](就活ストレス:①就労目標不確定、②時間的制約、③採用未決、④他者比較の因子を抽出、精神的健康との関連を検討;髙橋(2018)「大学生の就職活動に関する実証的研究の動向と課題」で知る)
- 下村英雄・木村周(1997).大学生の就職活動ストレスとソーシャルサポートの検討 進路指導研究,18(1),9-16.[PDF](就職活動におけるストレス尺度を開発、①物理・身体的ストレス、企業関連ストレス、③適正・興味関連ストレスから構成される;髙橋(2018)「大学生の就職活動に関する実証的研究の動向と課題」で知る)
- 松田侑子・永作稔・新井邦二郎(2010).大学生の就職活動不安が就職活動に及ぼす影響:コーピングに注目して 心理学研究,80(6),512-519.[PDF](髙橋(2018)「大学生の就職活動に関する実証的研究の動向と課題」で知る)
- 藤井義久(1999).女子学生における就職不安に関する研究 心理学研究,70(5),417-420.[PDF](就職不安の定義「職業決定および就職活動段階において生じる心配や戸惑い、ならびに就職決定後における将来に対する否定的な見通しや絶望感」、就職不安は抑うつを悪化;髙橋(2018)「大学生の就職活動に関する実証的研究の動向と課題」で知る)
- 浦上昌則(1995).女子短期大学生の進路選択に対する自己効力と職業不決断:Taylor & Betz (1983) の追試的検討. 進路指導研究,16,40-45.[PDF](Taylor and Betz(1983)の「進路選択自己効力尺度」を基に日本で尺度を開発;髙橋(2018)「大学生の就職活動に関する実証的研究の動向と課題」で知る)
- 富永美佐子(2000).女子大学生の進路選択過程における自己効力 進路指導研究,20(1),21-31.[PDF](aylor & Betz(1983)の「進路選択自己効力尺度」(①目標選択、②自己認識、③職業情報の収集、④将来設計、⑤課題解決の5領域)を基に日本で尺度を開発;髙橋(2018)「大学生の就職活動に関する実証的研究の動向と課題」で知る)
- 安達智子(2001).大学生の進路発達過程 教育心理学研究,49(3),326-336.[PDF](Taylor and Betz(1983)の「進路選択自己効力尺度」(①目標選択、②自己認識、③職業情報の収集、④将来設計、⑤課題解決の5領域)を基に日本で尺度を開発;髙橋(2018)「大学生の就職活動に関する実証的研究の動向と課題」で知る)
- 輕部雄輝・佐藤純・杉江征(2015).大学生の就職活動維持過程尺度の作成 教育心理学研究,63(4),386-400.[PDF](就職活動は2つの過程を持つ、就活当初:現在志向的行動、継続に伴って追加:未来思考的行動;髙橋(2018)「大学生の就職活動に関する実証的研究の動向と課題」で知る)
- 輕部雄輝・佐藤純・杉江征(2014).大学生の就職活動維持過程モデルの検討:不採用経験に着目して 筑波大学心理学研究,48,71-85.[PDF](大学生の就職活動は企業からの内定獲得および就職達成に向けての不採用経験を乗り越えていく過程;髙橋(2018)「大学生の就職活動に関する実証的研究の動向と課題」で知る)
- 西村圭子・種市康太郎(2011).大学生の進路決定における心理的プロセスに関する記述的研究 (1) 心理学研究:健康心理学専攻・臨床心理学専攻,1,46-60.[PDF](就活期間を開始期・活動期・終結期に区分、各期のポジティブ・ネガティブの感情と認識;髙橋(2018)「大学生の就職活動に関する実証的研究の動向と課題」で知る)
- 若松養亮(2012).大学生におけるキャリア選択の遅延:そのメカニズムと支援 風間書房(「自己内省」・「情報収集」・「外的活動」の3側面で大学生の進路探索行動を捉えて進路未決定との関連を検討、未決定者は決定者よりも進路探索行動が少ない;髙橋(2018)「大学生の就職活動に関する実証的研究の動向と課題」で知る)
- 矢崎裕美子・斎藤和志(2014).就職活動中の情報探索行動および入社前研修が内定獲得後の就職不安低減に及ぼす効果 実験社会心理学研究,53(2),131-140.[PDF](自己探索と環境探索がともにキャリア・パースペクティブの変化に有効;髙橋(2018)「大学生の就職活動に関する実証的研究の動向と課題」で知る)
- 安達智子(2008).女子学生のキャリア意識:就業動機,キャリア探索との関連 心理学研究,79(1),27-34.[PDF](自己探索と環境探索によって就業動機や進路探索に対する自己効力が増す;髙橋(2018)「大学生の就職活動に関する実証的研究の動向と課題」で知る)
- 下村英雄(1996).大学生の職業選択における情報探索方略:職業的意思決定理論によるアプローチ 教育心理学研究,44(2),145-155.[PDF](進路選択を行う過程を学習することが学生の意思決定に対する理解を促す;髙橋(2018)「大学生の就職活動に関する実証的研究の動向と課題」で知る)
- 杉本英晴・速水敏彦(2012).大学生における仮想的有能感と就職イメージおよび時間的展望 発達心理学研究,23(2),224-232.[PDF](大学生の就職イメージには「規範的」「希望的」「自立的」「拘束的」の4側面がある;髙橋(2018)「大学生の就職活動に関する実証的研究の動向と課題」で知る)
- 坂柳恒夫(1990).進路指導におけるキャリア発達の理論.知教育大学研究報告 教育科学,39,141-155.[PDF](「職業キャリア成熟」と「人生キャリア成熟」の観点で「関心性」・「自律性」・「計画性」を測定する尺度を作成、大学生版・成人版がある;髙橋(2018)「大学生の就職活動に関する実証的研究の動向と課題」で知る)
- 下村英雄・堀洋道(1994).大学生の職業選択における情報収集行動の検討 筑波大学心理学研究,16,209-220.(若林他(1983)の下位次元を再検討、「明瞭性」・「関与」・「非選択性」の3つに集約;髙橋(2018)「大学生の就職活動に関する実証的研究の動向と課題」で知る)
- 若林滿(1983).職業レディネスと職業選択の構造 Bulletin of The Faculty of Education,30,63-98.[PDF](職業レディネス尺度を作成、職業選択への興味・選択範囲の限定性・選択の現実性・選択の主体性・自己知識の客観性を設定;髙橋(2018)「大学生の就職活動に関する実証的研究の動向と課題」で知る)
- 亀野淳(2017).大学生のジェネリックスキルと成績や就職との関連に関する実証的研究:北海道大学生に対する調査結果を事例として 高等教育ジャーナル:高等教育と生涯学習,24,137-144.[PDF](Google Scholar「大学 就職 アンケート」で知る)
- 田澤実・佐藤一磨・梅崎修(2017).大学生における学内サポート資源の活用と就職活動プロセス:大学内の組織間の連携に注目して 大学教育研究ジャーナル,14,29-36.[PDF](Google Scholar「大学 就職 アンケート」で知る)
[2018.8.2]IRなどについての文献メモ 文献一覧を更新<資料作成>
- 阿久津洋巳・近藤雄希(2010).文字の読みやすさ2:読みやすさと読みの速さの比較 日本官能評価学会誌,14(1-2),26-33.[PDF](CiNii Articles「文字の読みやすさ」で知る)
- 阿久津洋巳(2009).文字の読みやすさ1:文字の大きさと読みやすさの評価 日本官能評価学会誌,14(1-2),26-33.[PDF](Google「フォントサイズ 9ポイント 読みやすさ」で知る)
[2018.8.2]IRなどについての文献メモ 文献一覧を更新<プログラミング教育>
- 飯塚昂大・原田泰(2018).小学生を対象としたプロジェクション・プレイのワークショップ デザイン学研究,218-219.[PDF](Googleアラート「プログラミング教育」で知る)
- 荒木貴之・板垣翔大・齋藤玲・佐藤和紀・堀田龍也(2018).プログラミング教育の経験に対する学習者の振り返りの分析 教育システム情報学会誌,35(2), 233-238.[PDF](Google Scholarアラート「プログラミング教育」で知る)
- 兼宗進(2018).新教育課程でのプログラミング教育とプログラミング環境の研究 教育システム情報学会誌,35(2),104-110.[PDF](Google Scholarアラート「プログラミング教育」で知る)
- 田代高章・宮川洋一・馬場智子(2018).教育課程改革における「主体的・対話的で深い学び」の位置づけと課題 岩手大学教育学部附属教育実践総合センター研究紀要,17,115−132.[PDF](Googleアラート「プログラミング教育」で知る)
- 小池翔太(2018).小学校第 3 学年の総合的な学習の時間におけるプログラミング教育のカリキュラム開発の試み 教育におけるゲーミフィケーションに関する実践的研究,3,23-32.[PDF](Googleアラート「プログラミング教育」で知る)
- 黒田昌克・森山潤(2018).小学校段階におけるプログラミング教育に対する教員の意識と意義形成要因の検討 教育メディア研究,24(2),43-54.[PDF](Googleアラート「プログラミング教育」で知る)
[2018.8.1]「ホーム」に追加
- ポスター発表「評価・IR担当者に必要な知識・スキルを考える」(SPODフォーラム2018)を掲載
- スタッフ担当「内部質保証に向けたIRや調査機能の育成、評価・IRの実践・課題共有セッション、IR実務担当者セッション」(大学評価・IR担当者集会2018)を掲載
[2018.8.1]「これまでの発表・競争的研究資金など」に追加
- 運営協力者「大学評価コンソーシアム」を掲載
- 情報誌編集委員「大学評価コンソーシアム」を掲載
[2018.8.1]「過去の「お知らせ」」、「IRなどについての文献メモ」、「これまでの発表・競争的研究資金など」に追加
- 研究ノート「国立大学及び私立大学におけるIR組織の形成」(『関西大学高等教育研究』第9号)を掲載
- ポスター発表"What sort of personnel are shouldering the responsibility of IR in Japan?"(2018 AIR Forum)を掲載
- 口頭発表「事例報告(四天王寺大学)」(大学評価及びIRにおける実践知と共通知に関する研究会)を掲載
- 口頭発表「日本のIR組織における「3つの知性」の実態と課題」(日本高等教育学会第21回大会)を掲載
- 口頭発表「日本の大学はIRにどのくらいの人的資源を投入しているか」(大学教育学会第40回大会)を掲載
- 口頭発表「国立大学及び私立大学におけるIR組織の形成」(第24回大学教育研究フォーラム)を掲載
- 研究助成「平成29年度公益財団法人文教協会調査研究助成」を掲載
- 研究助成「平成30年度公募型共同利用「重点テーマ2:学術文献データ分析の新たな統計科学的アプローチ」」(統計数理研究所)採択結果を掲載
- 研究助成「平成29年度公募型共同利用「重点テーマ2:学術文献データ分析の新たな統計科学的アプローチ」」(統計数理研究所)を掲載
- 研究助成「平成29年度「教育の活性化 学長奨励金」」(四天王寺大学)を掲載
- 講演「授業アンケートを教育改善サイクルに活用するための工夫」(第8回C-Learningセミナー)を掲載
- 審査員「学びロボ in Osaka 2018」を掲載
[2018.8.1]「「私立大学職員によるIR文献メモ」メルマガバックナンバー」を廃止
- 「「私立大学職員によるIR文献メモ」メルマガバックナンバー」を廃止
[2018.3.15]ホーム「お知らせ」欄に追加
- ポスター発表"What sort of personnel are shouldering the responsibility of IR in Japan?"(2018 AIR Forum)の日時を掲載
- 口頭発表「日本の大学はIRにどのくらいの人的資源を投入しているか」(大学教育学会第40回大会)を掲載
[2018.3.8]「過去の「お知らせ」」、「IRなどについての文献メモ」、「これまでの発表・競争的研究資金など」に追加
- 研修会講師「IRの事例を通して考える継続的な改善活動」(大阪薬科大学IR研修会)※講師依頼
[2018.3.3]「過去の「お知らせ」」、「IRなどについての文献メモ」、「これまでの発表・競争的研究資金など」に追加
- 事例報告、ファシリテーター・パネリスト「日本型IRの課題とその解決に向けたセッション」(継続的改善のためのIR/IEセミナー2018)
[2018.2.24]IRなどについての文献メモ 文献一覧を更新、内容をアップ<IR>
- 越中康治・高田淑子・木下英俊・安藤明伸・高橋潔・田幡憲一・岡正明・石澤公明(2015).テキストマイニングによる授業評価アンケートの分析:共起ネットワークによる自由記述の可視化の試み 宮城教育大学情報処理センター研究紀要:COMMUE,22,67-74.[概要][PDF](Google Scholar「自由記述 テキストマイニング」で知る)
[2018.2.13]IRなどについての文献メモ 文献一覧を更新<IR>
- Terenzini, P. T. (1993). On the nature of institutional research and the knowledge and skills it requires. Research in higher education, 34(1), pp.1-10.
- Terenzini, P. T. (1999). On the nature of institutional research and the knowledge and skills it requires. New directions for institutional research, 1999(104), pp.21-29.(Terenzini(1993)の同タイトル論文の再録)
- Terenzini, P. T. (2013). "On the nature of institutional research and the knowledge and skills it requires" revisited: Plus ça change... ? Research in higher education, 54(2), pp.137-148.
[2018.2.11]IRなどについての文献メモ 文献一覧を更新<ベンチマーク>
- Achtemeier, S. D., & Simpson, R. D. (2005). Practical considerations when using benchmarking for accountability in higher education. Innovative higher education, 30(2), pp.117–128.(小林他(2011)『大学ベンチマークによる大学評価の実証的研究』で知る)
- コトラー,P.&アンドリーセン,A.R.新日本監査法人公会計本部(訳)(2005).非営利組織のマーケティング戦略 第一法規(Amazon.co.jp「非営利組織 マーケティング」で知る)
- コトラー,P.&リー,N.スカイライトコンサルティング(訳)(2007).社会が変わるマーケティング:民間企業の知恵を公共サービスに活かす 英治出版(Amazon.co.jpレコメンド機能で知る)
- 井田正明(2005).米国における高等教育情報収集の事例 大学評価・学位研究,3,69-73.[PDF](Google Scholar「ipeds 米国」で知る)
- 山崎慎一(2008).Common Data Setに見るアメリカの大学情報の質保証,情報管理,51(3),207-219.[PDF](Google Scholar「common data set 米国」で知る)
- 大野賢一・藤原宏司・嶌田敏行・浅野茂・関隆宏・小湊卓夫(2015).大学の意思決定支援を目的とした指標の策定に関する検討 日本高等教育学会第18回大会口頭発表資料(大学ベンチマーク研究会(2017年12月)で知る)
- 山野真裕・鳥谷真佐子(2014).大学の研究戦略支援業務を支える研究力分析ツール カレントアウェアネス,322,2-4.[PDF](Google「"web of science" scopus 研究力」で知る)
[2017.8.17]ホーム「お知らせ」欄に追加
- ポスター発表"What sort of personnel are shouldering the responsibility of IR in Japan?"(2018 AIR Forum)を掲載
- 事例報告、ファシリテーター・パネリスト「日本型IRの課題とその解決に向けたセッション」(継続的改善のためのIR/IEセミナー2018)
[2018.2.11]「過去の「お知らせ」」、「IRなどについての文献メモ」、「これまでの発表・競争的研究資金など」に追加
- 口頭発表「大学ベンチマークの理論に関する基礎的研究」(平成29年度公募型共同利用「学術文献データ分析の新たな統計科学的アプローチ」成果報告会vol.1)
[2018.1.17]「過去の「お知らせ」」、「IRなどについての文献メモ」、「これまでの発表・競争的研究資金など」に追加
- 口頭発表「ベンチマークの基礎となる文献レビュー」(大学ベンチマーク研究会)
[2017.12.15]ホーム「お知らせ」欄に追加
- 口頭発表「ベンチマークの基礎となる文献レビュー」(ベンチマーク研究会)を掲載
[2017.12.15]「過去の「お知らせ」」、「IRなどについての文献メモ」、「これまでの発表・競争的研究資金など」に追加
- 口頭発表「小学校の教科の中でプログラミング教育をどのように実施するか:学生の発見と困難」(情報処理学会「第142回CE・第23回CLE合同研究発表会」)
[2017.12.6]ホーム「お知らせ」欄に追加
- 研修会講師(近畿地方の私立大学様、2018年3月実施で調整中)を掲載
[2017.11.17]ホーム「お知らせ」欄に追加
- 口頭発表「小学校の教科の中でプログラミング教育をどのように実施するか:学生の発見と困難」(情報処理学会「第142回CE・第23回CLE合同研究発表会」)を掲載
[2017.11.17]ホーム「お知らせ」欄、「これまでの発表・競争的研究資金など」に追加
- 平成29年度「教育の活性化 学長奨励金」(四天王寺大学)を掲載
[2017.11.12]ホーム「お知らせ」欄を変更
- 「お菓子で学べるプログラミング「グリコード(GLICODE®)」親子体験会」(学びのプロジェクト「ハルカス大学」による体験プログラム、学生さんとともに運営協力で参加)を掲載
[2017.9.18]IRなどについての文献メモ 文献一覧を更新<プログラミング教育>
- 山本利一・鈴木航平・岳野公人・鹿野利春(2017).初等教育におけるタブレットを活用したプログラミング学習の提案 教育情報研究,33(1),41-48.[PDF](Googleアラート「プログラミング教育」で知る)
[2017.9.10「これまでの発表・競争的研究資金など」に追加
- 学内研修会「今年度冬学期に向けた中途退学対策:過去の中途退学者の欠席状況から見えること」(口頭発表、平成29年度教職員合同研修会、四天王寺大学)を掲載
[2017.9.1]「これまでの発表・競争的研究資金など」に追加
- 「京都光華女子大学において財団法人大学基準協会の大学評価(認証評価)受審業務に従事(『平成27年度点検・評価報告書』の各章・根拠資料の取りまとめ、第10章「内部質保証」執筆、2015年度)」を掲載
[2017.8.27]「過去の「お知らせ」」、「これまでの発表・競争的研究資金など」に追加
- 研修会講師「大学職員の得意分野から「実現可能なIR」を考える」(平成29年度共同プログラム「高等教育機関教職員のための人材育成プログラム」)を掲載※講師依頼
[2017.8.20]「過去の「お知らせ」」、「これまでの発表・競争的研究資金など」に追加
- 「ロボットを使ってプログラミングの基礎を体験!」(あべの天王寺サマーキャンパス2017、学生さんとともに体験プログラムの運営協力で参加)を掲載
[2017.8.20]「過去の「お知らせ」」、「IRなどについての文献メモ」、「これまでの発表・競争的研究資金など」に追加
- 「大学からの中途退学に関する日本の研究は蓄積・統合されているか:2015年までの文献を用いた検証」(第6回大学情報・機関調査研究集会論文集)を掲載
[2017.8.18]IRなどについての文献メモ 文献一覧を更新<研究動向把握、計量書誌学>
- 野々山和宏(2013).研究動向把握のための分析方法に関する覚書:学際的領域の研究動向把握に向けて 弓削商船高等専門学校紀要,35,22-35.[PDF](Google「cinii 収録論文数 "年代別"」で知る)
[2017.8.18]ホーム「お知らせ」欄を変更
- 「ロボットを使ってプログラミングの基礎を体験!」(あべの天王寺サマーキャンパス2017、学生さんとともに体験プログラムの運営協力で参加)を掲載
[2017.8.10]IRなどについての文献メモ 文献一覧を更新<プログラミング>
- Sweigart, A.相川愛三(訳)(2017).退屈なことはPythonにやらせよう:ノンプログラマーにもできる自動化処理プログラミング オライリージャパン(ブックファーストで知る)
[2017.8.9]ホーム
[2017.8.9]IRなどについての文献メモ 文献一覧を更新<IR、CIP>
- 藤原宏司(2017).米国における教育プログラムの分類コード(CIP)について 大学評価とIR,8,33-43.[PDF](大学評価コンソーシアムからの案内で知る)
[2017.8.8]IRなどについての文献メモ 文献一覧を更新<大学評価>
- 関隆宏(2017).初めて評価を担当される方へ(前編) 大学評価とIR,8,15-32.[概要][PDF](大学評価コンソーシアムからの案内で知る)
[2017.8.6]IRなどについての文献メモ 文献一覧を更新<専門的職員>
- 吉武博通(2017).大学組織のマネジメントと人材育成 情報の科学と技術,67(8),400-404.[PDF](大学において専門性の高い職員がより一層求められるようになりつつある、専門的職員の先駆けともいえる図書館職員の育成はどうあるべきを検討;Google Scholarアラート「インスティテューショナル・リサーチ」で知る)
[2017.8.2]IRなどについての文献メモ 文献一覧を更新<プログラミング教育>
- 原田康徳(2017).プログラミングの社会への浸透 サービソロジー,4(2),38-41.[PDF](Googleアラート「プログラミング教育」で知る)
上松恵理子(2017).最新のテクノロジーを活用した教育方法の現状 サービソロジー,4(2),6-9.[PDF](Googleアラート「プログラミング教育」で知る)
[2017.7.31]IRなどについての文献メモ 文献一覧を更新、内容をアップ<プログラミング教育>
- 岡崎善弘・大角茂之・倉住友恵・三島知剛・阿部和広(2017).プログラミングの体験形式がプログラミング学習の動機づけに与える効果 日本教育工学会論文誌,早期公開,1-7.[PDF](小学生が対象、①講義型と②協同型は有意に上昇、③個別型は上昇しないことが示唆された;Googleアラート「プログラミング教育」で知る)
[2017.7.27]IRなどについての文献メモ 文献一覧を更新<アンケート調査>
- ナフリック,K.C.村井瑞枝(訳)(2017).Google流資料作成術 日本実業出版社(Amazon.co.jpレコメンド機能で知る)
[2017.7.27]IRなどについての文献メモ 文献一覧を更新<資料作成>
- 朝野煕彦(編著)(2011).アンケート調査入門:失敗しない顧客情報の読み方・まとめ方 東京図書(Amazon.co.jpレコメンド機能で知る)
- 酒井隆(2012).図解アンケート調査と統計解析がわかる本:調査設計から調査票の作成、実査、集計、分析技術まで 日本能率協会マネジメントセンター(Amazon.co.jpレコメンド機能で知る)
- 酒井隆(2012).アンケート調査の進め方 日本経済新聞出版社(Amazon.co.jpレコメンド機能で知る)
- 柏木吉基(2016).統計学に頼らないデータ分析「超」入門 ポイントは「データの見方」と「目的・仮説思考」にあり! SBクリエイティブ(Amazon.co.jpレコメンド機能で知る)
- 深沢真太郎(2013).数学女子智香が教える仕事で数字を使うって、こういうことです 日本実業出版社(Amazon.co.jpレコメンド機能で知る)
[2017.7.26]IRなどについての文献メモ 文献一覧を更新、内容をアップ<プログラミング教育>
- 江本理恵(2017).教学IR情報を活用した学習支援室の試み 日本教育工学会研究報告集,JSET17-3,151-154.(岩手大学ではデータを活用した学修支援を中期目標に掲げている、体制整備・図書館の学修支援室の強化について計画・実施内容・成果を報告、平成27年度にデータベース(DataSpider)と分析ツール(ClikView)などを導入した、平成28年度からポートフォリオシステムを稼働させている(学生は1週間の時間の使い方・学習経験・学位授与の方針に対する自己評価などを学期末に回答(江本,2016)、8割を超える学生が回答)、データベースに格納している他のデータ:学務情報システムの全てのデータ(取得単位・成績など)・入試システムの全てのデータ(入試形態・入試の成績など)・奨学金の受給状況・図書館の利用状況など、退学理由に成績を挙げている学生が多い学部を重点的に支援、当該学部の学生の傾向についてデータを用いて分析した、当該学部の教務委員会・学生委員会と協議して役割分担を明確にした上で学修支援室の新たな取り組みを企画した、結果:来室数はそれほど増えなかったが学部との協力関係ができつつある、今後の課題:①中期目標に掲げている「学習支援室における大学院生の活用」、②外国の学校等を卒業して入学してくる学生への支援、③教学IRの活用とそのシステム化(担当教職員が交代しても確実に支援できる体制を整える);日本教育工学会からの冊子配布で知る)
[2017.7.26]IRなどについての文献メモ 文献一覧を更新、内容をアップ<プログラミング教育>
- 太田雅之・笠井俊信(2017).中学校技術科におけるScratchを用いた授業実践と評価 日本教育工学会研究報告集,JSET17-3,169-176.(中学校の技術科の授業でプログラミング教育を行った、目的はプログラミング教育の基礎習得と協調活動の経験であった、Scratchと知識構成型ジグソー法を用いるとともに授業時数を短縮した、ほとんどの生徒が①分岐を含むプログラミングを作成した、②いつもの授業より多く発言した、③協力して作品を制作できた;日本教育工学会からの冊子配布で知る)
- 小原裕二・神部順子・八木徹・山口敏和・玉田和恵・松田稔樹(2017).プログラミング教育を通じた問題解決力育成のための指導法開発にむけての事前調査 日本教育工学会研究報告集,JSET17-3,1-6.(高校までのプログラミング教育の成果を分析するために大学生にアンケート調査を行った、対象:入学したばかりの2017年度1年生464名、結果:現行のプログラミング教育ではアルゴリズム的思考・論理的思考・プログラミング的思考は身についていなかった;日本教育工学会からの冊子配布で知る)
[2017.7.26]IRなどについての文献メモ 文献一覧を更新、内容をアップ6<eポートフォリオ>
- 佐藤隼明・北澤武・今井慎一・森本康彦(2017).ショーケース・ポートフォリオを用いた教職実践演習における大学4年間の振り返りの実践 日本教育工学会研究報告集,JSET17-3,33-38.(大学4年生の教職実践演習(4年間の学びの振り返りが求められる)でショーケース・ポートフォリオを用いた実践事例を紹介、質問紙で評価を行った、結果(母平均を中央値(4)とするt検定を行い27項目中24項目に有意差あり、4つの可能性が示唆された):①「学習成果物選択」ベストワークを選択することで4年間の学びの振り返りを促進して自分の成長を実感するようになる可能性、②「振り返りのコメント」4年間の学びを振り返ってコメントを加えることで蓄積された学習記録を活かして次の学びにつなげようと考える可能性、③「ショーケース・ポートフォリオの閲覧」仲間の内容を閲覧することで自身の学びを別の視点から考えるようになる可能性、④「ショーケース・ポートフォリオ作成全体」ショーケース・ポートフォリオ作成の活動全体を通して自ら興味・責任を持って真剣に取り組む・自身の成長や変容を感じる・これからどのようにすればよいかを考える可能性;日本教育工学会からの冊子配布で知る)
[2017.7.24]「過去の「お知らせ」」、「これまでの発表・競争的研究資金など」に追加
- セミナー運営委員「平成29年度第1回継続的改善のためのIR/IEセミナー」を掲載
[2017.7.24]IRなどについての文献メモ 文献一覧を更新<プログラミング教育>
- 平井聡一郎・福田晴一(監修)松田孝・吉田潤子・原田康徳・久木田寛直・赤石先生・利根川裕太・國領二郎・デビドソン,S.(2017).小学校の「プログラミング授業」実況中継:教科別:2020年から必修のプログラミング教育はこうなる 技術評論者(Twitter(@akaishi_Teacherさん)で知る)
- マルティネス,S.L.,ステージャー,G.酒匂寛(訳)(2015).作ることで学ぶ:makerを育てる新しい教育のメソッド オライリー・ジャパン(Twitter(@abee2さん)で知る)
- Bell, T., Witten, I. H., Fellows, M.兼宗進(監訳)(2007).コンピュータを使わない情報教育:アンプラグドコンピュータサイエンス イーテキスト研究所(Amazon.co.jpレコメンド機能で知る)
- 阿部和広(2013).小学生からはじめるわくわくプログラミング 日経BP社(阿部一晴先生/京都光華女子大学からの紹介で知る)
- 阿部和広(監修)・倉本大資(2016).小学生からはじめるわくわくプログラミング2 日経BP社(Amazon.co.jpレコメンド機能で知る)
- 黒上晴夫・堀田龍也(2017).プログラミング教育導入の前に知っておきたい思考のアイディア 小学館(Amazon.co.jpレコメンド機能で知る)
[2017.7.24]IRなどについての文献メモ 文献一覧を更新<文章作成>
[2017.7.20]IRなどについての文献メモ 文献一覧を更新<人工知能>
- 小野田博一(2017).人工知能はいかにして強くなるのか?:対戦型AIで学ぶ基本のしくみ 講談社(ブックファーストで知る)
- 西垣通(2017).ビッグデータと人工知能:可能性と罠を見極める 中央公論新社(ブックファーストで知る)
[2017.7.20]IRなどについての文献メモ 文献一覧を更新<脳科学>
- 理化学研究所脳科学総合研究センター(編)(2016).つながる脳科学:「心のしくみ」に迫る脳研究の最前線 講談社(ブックファーストで知る)
[2017.7.20]IRなどについての文献メモ 文献一覧を更新<学生支援、自閉症>
- シルバーマン,S.正高信男・入口真夕子(訳)(2017).自閉症の世界:多様性に満ちた内面の真実 講談社(ブックファーストで知る)
[2017.7.18]ホーム「お知らせ」欄、「過去の「お知らせ」」を変更
- 文部科学省「大学教育改革の実態の把握及び分析等に関する調査研究」調査報告書の事例調査(京都光華女子大学)を掲載
[2017.7.17]IRなどについての文献メモ 文献一覧を更新<情報処理>
[2017.7.15]「過去の「お知らせ」」、「IRなどについての文献メモ」、「これまでの発表・競争的研究資金など」に追加
- 口頭発表「データを可視化するときの実務内容:BIツール(TableauとExcel)による違いに着目して1(Excel編)」(平成29年度第2回IR実務担当者連絡会)を掲載
- 口頭発表"A data-driven approach to dropout prevention: Kyoto Koka Women's University case"(DSIR2017)を掲載
[2017.7.10]IRなどについての文献メモ 文献一覧を更新<プログラミング教育>
- 鹿野利春(2017).学習指導要領の改訂と共通教科情報科 情報処理,58(7),626-629.[PDF](Googleアラート「プログラミング教育」で知る)
[2017.7.7]ホーム「お知らせ」欄を変更
- 口頭発表「大学からの中途退学に関する日本の研究は蓄積・統合されているか:2015年までの文献を用いた検証」(第6回MJIR)を掲載
[2017.7.1]「過去の「お知らせ」」、「IRなどについての文献メモ」、「これまでの発表・競争的研究資金など」に追加
- 口頭発表「大学ベンチマークの理論に関する基礎的研究」(平成29年度公募型共同利用「学術文献データ分析の新たな統計科学的アプローチ」キックオフ、発表者:白石哲也/清泉女子大学)を掲載
- 研修会講師「既存業務から始めるIR」(IR(インスティテューショナル・リサーチ)に関する学習会)を掲載※講師依頼
[2017.6.30]IRなどについての文献メモ 文献一覧を更新<論文作成>
- 大塚昭義(2003).学術論文のより良い書き方:これだけは知っておきたい! 日本放射線技術學會雜誌,59(10),1218-1221.[PDF]
[2017.6.26]ホーム「お知らせ」欄を変更
- 研修会講師「既存業務から始めるIR」(IR(インスティテューショナル・リサーチ)に関する学習会)を掲載※講師依頼
[2017.6.25]IRなどについての文献メモ 文献一覧を更新<institutional effectiveness(IE)>
- Nichols, J. O. (1995). A practitioner's handbook for institutional effectiveness and student outcomes assessment implementation. New York: Agathon Press.(Google Scholar「"institutional effectiveness"」で知る)
- Nichols, J. O. (1989). Institutional effectiveness and outcomes assessment implementation on campus: A practitioner's handbook. New York: Agathon Press.(Amazon.co.jp「A practitioner's handbook for institutional effectiveness」で知る)
- Welsh, J. F., & Metcalf, J. (2003). Faculty and administrative support for institutional effectiveness activities: A bridge across the chasm? The journal of higher education, 74(4), 445-468.[Abstract](Google Scholar「"institutional effectiveness"」で知る)
- Jenkins, D. (2007). Institutional effectiveness and student success: A study of high-and low-impact community colleges. Community college journal of research and practice, 31(12), 945-962.[Abstract](Google Scholar「"institutional effectiveness"」で知る)
- Hockaday, J., & Friga, J. J. (1989). Assessment of institutional effectiveness: A practical model for small colleges. Community college review, 17(3), 28-33.[Abstract](Google Scholar「"institutional effectiveness"」で知る)
- Middaugh, M. F. (2010). Planning and assessment in higher education: Demonstrating institutional effectiveness. San Francisco: Jossey-Bass.(Google Scholar「"institutional effectiveness"」で知る)
- Gray, J., Goldstein, H., & Thomas, S. (2001). Predicting the future: the role of past performance in determining trends in institutional effectiveness at A level. British educational research journal, 27(4), 391-405.[Abstract](Google Scholar「"institutional effectiveness"」で知る)
- Ewell, P. T. (2011). Accountability and institutional effectiveness in the community college. Directions for community colleges, 2011(153), 23-36.[Abstract](Google Scholar「"institutional effectiveness"」で知る)
- Nichols, J. O., & Nichols, K. W. (2000). The departmental guide and record book for student outcomes assessment and institutional effectiveness 3rd edition. New York: Agathon Press.[Abstract](Google Scholar「"institutional effectiveness"」で知る)
- Welsh, J. F., & Metcalf, J. (2003). Cultivating faculty support for institutional effectiveness activities: Benchmarking best practices. Assessment & Evaluation in Higher Education, 28(1), 33-45.[Abstract](Google Scholar「"institutional effectiveness"」で知る)
- Keeling, R. P., Wall, A. F., Underhile, R., & Dungy, G. J. (2008). Assessment reconsidered: Institutional effectiveness for student success. Washington, DC: NASPA.(Google Scholar「"institutional effectiveness"」で知る)
- Dodd, A. H. (2004). Accreditation as a catalyst for institutional effectiveness. New directions for institutional research, 2004(123), 13-25.[Abstract](Google Scholar「"institutional effectiveness"」で知る)
- Skolits, G. J., & Graybeal, S. (2007). Community college institutional effectiveness: Perspectives of campus stakeholders. College Review, 34(4), 302-323.[Abstract](Google Scholar「"institutional effectiveness"」で知る)
- Kim, M. M. (2001). Institutional effectiveness of women-only colleges: Cultivating students' desire to influence social conditions. The Journal of Higher Education, 72(3), 287-321.[Abstract]Google Scholar「"institutional effectiveness"」で知る)
- Head, R. B. (Ed.)(2011). Institutional effectiveness: New directions for community colleges, 153.[Table of Contents](Amazon.co.jp「institutional effectiveness」で知る)
- Ewell, P., & Lisensky, R. P. (1988). Assessing institutional effectiveness: Redirecting the self-study process. Consortium for the Advancement of Private Higher Education.(Amazon.co.jp「institutional effectiveness」で知る)
- Fincher, C. (Ed.)(1989). Assessing institutional effectiveness: Issues, methods, and management. Athens: The University of Georgia.(Amazon.co.jp「institutional effectiveness」で知る)
- Katsinas, S. G. & Lacey, V. A. (1989). Community colleges and economic development: Models of institutional effectiveness. Alexandria, VA: American Association of Community and Junior Colleges Publications.[PDF](Amazon.co.jp「institutional effectiveness」で知る)
[2017.6.25]IRなどについての文献メモ 文献一覧を更新<プログラミング教育>
- 津田真理子・本吉達郎(2017).視覚障がい者を対象に含めたタンジブルなプログラミングツールに対する学習要素の拡張 北陸信越支部総会・講演会講演論文集[PDF](Googleアラート「プログラミング教育」で知る)
[2017.6.25]IRなどについての文献メモ 文献一覧を更新、内容をアップ<コンピテンシー>
- 西あゆみ・加藤真紀(2017).複数の学術領域におけるコンピテンス概念把握の試み Working Paper Series, WP2017-01, 1-24.[PDF][概要](Googleアラート「言語学」で知る)
[2017.6.25]IRなどについての文献メモ 文献一覧を更新<言語学>
- 鍋島弘治朗・中野阿佐子(2017).シミリとメタファーの境界:シミリを導入する表現の分類に関する一考察 Kansai Linguistic Society: Proceedings of the annual meeting of the Kansai Linguistic Society: KLS, 37, 121-132.[PDF](Googleアラート「言語学」で知る)
[2017.6.23]ホーム「お知らせ」欄を変更
- セミナー運営委員「平成29年度第1回継続的改善のためのIR/IEセミナー」を掲載
[2017.6.23]IRなどについての文献メモ 文献一覧を更新<資料作成>
- 桐山岳寛(2017).説明がなくても伝わる:図解の教科書 かんき出版(ブックファーストで知る)
[2017.6.23]IRなどについての文献メモ 文献一覧を更新<仕事術>
- ナップ,J.,ゼラツキー,J.&コウィッツ,B.櫻井祐子(訳)(2017).SPRINT最速仕事術:あらゆる仕事がうまくいく最も合理的な方法 ダイヤモンド社(ブックファーストで知る)
[2017.6.23]IRなどについての文献メモ 文献一覧を更新<Excel>
- 藤井直弥・大山啓介(2017).Excel最強の教科書:完全版:すぐに使えて、一生役立つ「成果を生み出す」超エクセル仕事術 SBクリエイティブ(ブックファーストで知る)
[2017.6.19]ホーム「お知らせ」欄を変更
- 口頭発表「データを可視化するときの実務内容:BIツール(TableauとExcel)による違いに着目して」(平成29年度第2回IR実務担当者連絡会)を掲載
- 口頭発表"A data-driven approach to dropout prevention: Kyoto Koka Women's University case"(DSIR2017)発表時間を変更(9:00-10:45→8:30-10:40)
[2017.6.19]IRなどについての文献メモ 文献一覧を更新<IR、ベンチマーク>
- 荒木俊博・上畠洋佑(2017).職員IR(SIR)フォーラム実践報告 大学評価とIR,8,3-14.[PDF](大学評価コンソーシアムからの案内で知る)
- Dunn, D. S., McCarthy, M. A., Baker, S. C., Halonen, J. S., & Maki, P. (2010). Using quality benchmarks for assessing and developing undergraduate programs. San Francisco: Jossey-Bass.(Google Scholar「benchmark」で知る)
- Tarango, J. & Machin-Mastromatteo, J. (2010). The role of information professionals in the knowledge economy: Skills, profile and a model for supporting scientific production and communication Cambridge, Mass: Chandos Publishing.(Google Scholar「benchmark」で知る)
[2017.6.19]IRなどについての文献メモ 文献一覧を更新<言語学>
[2017.6.19]IRなどについての文献メモ 文献一覧を更新<プログラミング教育>
- 萩原克幸(2017).小学校におけるロボットプログラミングの実践について 三重大学教育学部研究紀要. 自然科学・人文科学・社会科学・教育科学・教育実践,68,307-315.[PDF](Googleアラート「プログラミング教育」で知る)
- 石田保輝・宮崎修一(2017).アルゴリズム図鑑 絵で見てわかる26のアルゴリズム 翔泳社(Twitter(@editechさん)で知る)
[2017.6.19]IRなどについての文献メモ 文献一覧を更新<ガバナンス>
- 高等教育における組織・ガバナンス研究会(監修)野村朋絵・村澤昌崇(編)(2017).大学における教学ガバナンスとその効果に関する調査研究 広島大学高等教育研究開発センター[PDF](広島大学高等教育研究開発センター新着情報通知サービスで知る)
[2017.6.19]IRなどについての文献メモ 文献一覧を更新<入試募集>
- 雨森聡(2016).入試広報戦略のありようについて:入試広報の効果検証を中心に 大学入試研究ジャーナル,26,111-116.[PDF](Cinii Articles「雨森聡」で知る)
- 雨森聡(2015).不本意入学の学修への影響:これまでの不本意入学は本当に不本意なのか 大学入試研究ジャーナル,25,111-116.[PDF](Cinii Articles「雨森聡」で知る)
[2017.6.14]ホーム「お知らせ」欄を変更
- 口頭発表"A data-driven approach to dropout prevention: Kyoto Koka Women's University case"(DSIR2017)発表時間を掲載
- 口頭発表「平成29年度公募型共同利用「学術文献データ分析の新たな統計科学的アプローチ」キックオフ」を掲載
[2017.6.13]「過去の「お知らせ」」、「IRなどについての文献メモ」、「これまでの発表・競争的研究資金など」に追加
- 口頭発表「大学規模別に見たIR活動の類型化:実践事例報告を用いて」(大学教育学会第39回大会)を掲載
[2017.6.3]「過去の「お知らせ」」、「IRなどについての文献メモ」、「これまでの発表・競争的研究資金など」に追加
- ポスター発表"Feasible ways to benchmark with inadequate database systems"(2017 AIR Forum)を掲載
[2017.5.17]IRなどについての文献メモ 文献一覧を更新<英語>
- 内藤由美子(2013).ネイティブに誤解なく、きちんと伝わる 英文メールの基本 KADOKAWA(Amazon.co.jp「内藤由美子」で知る)
- 内藤由美子(2017).日本人のための英文ライティング即効薬 KADOKAWA(Amazon.co.jpレコメンド機能で知る)
[2017.5.16]IRなどについての文献メモ 文献一覧を更新<政策>
[2017.5.16]IRなどについての文献メモ 文献一覧を更新<SPSS、統計>
[2017.5.16]IRなどについての文献メモ 文献一覧を更新<私立大学>
[2017.5.11]ホーム「お知らせ」欄を変更
- 口頭発表"A data-driven approach to dropout prevention: Kyoto Koka Women's University case"(DSIR2017)タイトルを掲載
[2017.5.6]ホーム「お知らせ」欄を変更
- ポスター発表"Feasible ways to benchmark with inadequate database systems"(2017 AIR Forum)発表時間を掲載
[2017.5.6]IRなどについての文献メモ 文献一覧を更新<文部科学省>
[2017.4.28]IRなどについての文献メモ 文献一覧を更新<アクティブ・ラーニング>
[2017.4.27]IRなどについての文献メモ 文献一覧を更新<アクティブ・ラーニング>
- 栗田佳代子・日本教育研究イノベーションセンター(2017).インタラクティブ・ティーチング:アクティブ・ラーニングを促す授業づくり 河合出版(ASAGAOメーリングリストで知る)
[2017.4.25]ホーム「お知らせ」欄を変更
- 口頭発表「大学規模別に見たIR活動の類型化:実践事例報告を用いて」(大学教育学会第39回大会)発表時間を掲載
[2017.4.24]IRなどについての文献メモ 文献一覧を更新<統計、ロジスティック回帰分析>
- 内田治(2016).SPSSによるロジスティック回帰分析 オーム社(Amazon.co.jp「ロジスティック回帰分析」で知る)
[2017.4.16]IRなどについての文献メモ 文献一覧を更新<教育工学>
[2017.4.16]IRなどについての文献メモ 文献一覧を更新<教育工学>
- 坂元昻・岡本敏雄・永野和男(編著)(2012).教育工学とはどんな学問か ミネルヴァ書房(Amazon.co.jp「教育工学」で知る)
- 清水康敬・中山実・向後千春(編著)(2012).教育工学研究の方法 ミネルヴァ書房(日本教育工学会サイト「出版物のご案内 教育工学選書」で知る)
- 矢野米雄・平嶋宗(編著)(2012).教育工学とシステム開発 ミネルヴァ書房(日本教育工学会サイト「出版物のご案内 教育工学選書」で知る)
- 西之園晴夫・生田孝至・小柳和喜雄(編著)(2012).教育工学における教育実践研究 ミネルヴァ書房(日本教育工学会サイト「出版物のご案内 教育工学選書」で知る)
- 水越敏行・吉崎静夫・木原俊行・田口真奈(2012).授業研究と教育工学 ミネルヴァ書房(日本教育工学会サイト「出版物のご案内 教育工学選書」で知る)
- 近藤勲・黒上晴夫・堀田龍也・野中陽一(2015).教育メディアの開発と活用 ミネルヴァ書房(日本教育工学会サイト「出版物のご案内 教育工学選書」で知る)
- 永岡慶三・植野真臣・山内祐平(編著)(2012).教育工学における学習評価 ミネルヴァ書房(日本教育工学会サイト「出版物のご案内 教育工学選書」で知る)
- 赤倉貴子・柏原昭博(編著)(2016).eラーニング・eテスティング ミネルヴァ書房(日本教育工学会サイト「出版物のご案内 教育工学選書」で知る)
- 森本康彦・永田智子・小川賀代・山川修(編著)(2017).教育分野におけるeポートフォリオ ミネルヴァ書房(日本教育工学会サイト「出版物のご案内 教育工学選書」で知る)
- 藤本徹・森田裕介(編著)(2017).ゲームと教育・学習 ミネルヴァ書房(日本教育工学会サイト「出版物のご案内 教育工学選書」で知る)
- 加藤浩・望月俊男(編著)(2016).協調学習とCSCL ミネルヴァ書房(日本教育工学会サイト「出版物のご案内 教育工学選書」で知る)
- 大島純・益川弘如(編著)(2016).学びのデザイン:学習科学 ミネルヴァ書房(日本教育工学会サイト「出版物のご案内 教育工学選書」で知る)
- 山内祐平・山田政寛(編著)(2016).インフォーマル学習 ミネルヴァ書房(日本教育工学会サイト「出版物のご案内 教育工学選書」で知る)
- 木原俊行・島田希・寺嶋浩介(編著)(2016).教育工学的アプローチによる教師教育:学び続ける教師を育てる・支える ミネルヴァ書房(日本教育工学会サイト「出版物のご案内 教育工学選書」で知る)
- 小柳和喜雄(編著)(2017).Lesson study ミネルヴァ書房(日本教育工学会サイト「出版物のご案内 教育工学選書」で知る)
- 吉崎静夫・村川雅弘(編著)(2016).教育実践論文としての教育工学研究のまとめ方 ミネルヴァ書房(日本教育工学会サイト「出版物のご案内 教育工学選書」で知る)
- 松田岳士・根本淳子・鈴木克明(編著)(2017).大学授業改善とインストラクショナルデザイン ミネルヴァ書房(日本教育工学会サイト「出版物のご案内 教育工学選書」で知る)
- 鈴木克明・中山実(編著)(2016).職業人教育と教育工学 ミネルヴァ書房(日本教育工学会サイト「出版物のご案内 教育工学選書」で知る)
[2017.4.16]IRなどについての文献メモ 文献一覧を更新<アセスメント>
- Middaugh, M. F. (2010). Planning and assessment in higher education: Demonstrating institutional effectiveness. San Francisco: Jossey-Bass.(Amazon.com「institutional research」で知る)
- Suskie, L. A. (2009). Assessing student learning: A common sense guide 2nd edition. San Francisco: Jossey-Bass.(Amazon.comレコメンド機能で知る)
- サスキー,L.A.齋藤聖子(訳)(2015).学生の学びを測る:アセスメント・ガイドブック 玉川大学出版部(CiNii Books「Assessing Student Learning: A Common Sense Guide」で知る)
- Banta, T. W., & Palomba, C. A. (2015). Assessment essentials: Planning, implementing, and improving assessment in higher education. San Francisco: Jossey-Bass.(Amazon.comレコメンド機能で知る)
- Barbara, E. W. (2010). Assessment clear and simple: A practical guide for institutions, departments, and general education. San Francisco: Jossey-Bass.(Amazon.comレコメンド機能で知る)
- バーバラ,W.山崎めぐみ・安野舞子・関田一彦(訳)(2013).大学教育アセスメント入門:学習成果を評価するための実践ガイド ナカニシヤ出版(CiNii Books「Assessment Clear and Simple」で知る)
- Banta, T. W., Jones, E. A., & Black, K. E. (2009). Designing effective assessment: Principles and profiles of good practice. San Francisco: Jossey-Bass.(Amazon.comレコメンド機能で知る)
- Driscoll, A., & Wood, S. (2007). Developing outcomes-based assessment for learner-centered education: A faculty introduction. Sterling, VA: Stylus.(Amazon.comレコメンド機能で知る)
- Angelo, T. A., & Cross, K. P. (1993). Classroom assessment techniques: A handbook for college teachers 2nd edition. San Francisco: Jossey-Bass Publishers.(Amazon.comレコメンド機能で知る)
- Dannelle, S. S., & Antonia, L. (2013). Introduction to rubrics: An assessment tool to save grading time, convey effective feedback, and promote student learning 2nd edition. Sterling: Stylus.(Amazon.comレコメンド機能で知る)
- ダネル,S.,&アントニア,L.井上敏憲・俣野秀典(訳)(2014).大学教員のためのルーブリック評価入門 玉川大学出版部(CiNii Books「Introduction to rubrics」で知る)
- Kuh, G. D., Ikenberry, S. O., Jankowski, N. A., Cain, T. R., Ewell, P. T., Hutchings, P., & Kinzie, J. (2015). Using evidence of student learning to improve higher education. San Francisco, CA: Jossey-Bass.(Amazon.comレコメンド機能で知る)
[2017.4.15]IRなどについての文献メモ 文献一覧を更新<ACCESS>
- 谷尻かおり(2008).ACCESSクエリの達人ガイド:集計&データ整理の極意 技術評論社(Amazon.co.jp「クエリ」で知る)
[2017.4.15]IRなどについての文献メモ 文献一覧を更新<IR>
[2017.4.9]「これまでの発表・競争的研究資金など」に追加
- 外部資金「IR活動の実践知の体系化に関する研究:大学の規模の観点から」(平成29年度公益財団法人文教協会調査研究助成)
[2017.4.8]ホーム「お知らせ」欄、「これまでの発表・競争的研究資金など」に追加
- 外部資金「大学ベンチマークの理論に関する基礎的研究」(平成29年度公募型共同利用「重点テーマ2:学術文献データ分析の新たな統計科学的アプローチ」(統計数理研究所))
[2017.4.3]IRなどについての文献メモ 文献一覧を更新<IR、3つのポリシー、教育の質保証>
[2017.4.3]IRなどについての文献メモ 文献一覧を更新<高大接続、大学入学希望者学力テスト(仮称)、>
[2017.4.1]「過去の「お知らせ」」、「これまでの発表・競争的研究資金など」に追加
- 平成28年度大学改革支援制度(京都光華女子大学学長裁量経費)「学内の既存データと学科の要望を組み合わせた入学初期段階と経時的変化の分析(IR)」を掲載
- ポスター発表「学習行動調査データを用いた女子大学ベンチマーク」(大学教育改革フォーラムin東海2017)を掲載
[2017.4.1]ホーム
- サイト名、ロゴを変更(変更前:私立大学職員によるInstitutional Research(IR)文献メモ、変更後:Institutional Research(IR)文献メモ)
- 「このサイトの紹介」欄へのページ内リンクを追加
- 「このサイトの紹介」欄の記載を変更
[2017.3.25]IRなどについての文献メモ 文献一覧を更新<IR、ベンチマーク>
- 関東地区IR研究会(監修) 松田岳士・森雅生・相生芳晴・姉川恭子(編)(2017).大学IRスタンダード指標集:教育質保証から財務まで 玉川大学出版部(松田岳士先生(首都大学東京)からのご恵贈で知る、白石哲也さん(清泉女子大学)からの情報提供で知る)
[2017.3.23]ホーム「お知らせ」欄を変更
- 研修会講師「大学職員の得意分野から「実現可能なIR」を考える」(平成29年度共同プログラム「高等教育機関教職員のための人材育成プログラム」)を掲載※講師依頼
[2017.3.22]「過去の「お知らせ」」、「これまでの発表・競争的研究資金など」に追加
- 企画・話題提供「小規模大学におけるIR」(第23回大学教育研究フォーラム参加者企画セッション)を掲載
- 口頭発表「ディプロマ・ポリシーとカリキュラム・ポリシーのつながりをデータに基づいて検証する」(第23回大学教育研究フォーラム個人研究発表)を掲載
- 口頭発表「女子大学ベンチマークの試み」(第23回大学教育研究フォーラム個人研究発表)を掲載
[2017.3.15]IRなどについての文献メモ 文献一覧を更新<統計>
- 郡山彬・和泉澤正隆(1997).統計・確率のしくみ 日本実業出版社
- 長谷川勝也(2000).イラスト・図解確率・統計のしくみがわかる本:わからなかったことがよくわかる、確率・統計入門 技術評論社(Amazon.co.jpレコメンド機能で知る)
[2017.3.14]ホーム「お知らせ」欄を変更
- 口頭発表「大学規模別に見たIR活動の類型化:実践事例報告を用いて」(大学教育学会第39回大会)を掲載
[2017.3.14]IRなどについての文献メモ 文献一覧を更新<学習支援>
[2017.3.14]IRなどについての文献メモ 文献一覧を更新<戦略>
- 齋藤孝(監修)(2016).こども孫子の兵法:強くしなやかなこころを育てる! 日本図書センター(Amazon.co.jpレコメンド機能で知る)
[2017.3.12]ホーム「お知らせ」欄を変更
- 口頭発表"On practical institutional research for small-scale private universities: To encourage at-risk students"(DSIR2017)を掲載
[2017.3.9]IRなどについての文献メモ 文献一覧を更新<IR、ベンチマーク>
- 関東地区IR研究会(監修) 松田岳士・森雅生・相生芳晴・姉川恭子(編)(2017).大学IRスタンダード指標集:教育質保証から財務まで 玉川大学出版部(白石哲也さん(清泉女子大学)からの情報提供で知る)
[2017.3.9]IRなどについての文献メモ 文献一覧を更新<戦略>
- 稲垣栄洋(2002).雑草の成功戦略:逆境を生きぬく知恵 NTT出版(「SWITCHインタビュー達人達」で知る)
- 稲垣栄洋(2016).面白くて眠れなくなる植物学 PHPエディターズ・グループ(CiNii Books「稲垣栄洋」で知る)
- 稲垣栄洋(2016).植物はなぜ動かないのか:弱くて強い植物のはなし 筑摩書房(CiNii Books「稲垣栄洋」で知る)
- 稲垣栄洋(2016).オスとメスはどちらが得か? 祥伝社(CiNii Books「稲垣栄洋」で知る)
- 稲垣栄洋(2015).なぜ仏像はハスの花の上に座っているのか:仏教と植物の切っても切れない66の関係 幻冬舎(CiNii Books「稲垣栄洋」で知る)
- 稲垣栄洋(2015).たたかう植物:仁義なき生存戦略 筑摩書房(CiNii Books「稲垣栄洋」で知る)
- 稲垣栄洋(2015).身近な花の知られざる生態 PHPエディターズ・グループ(CiNii Books「稲垣栄洋」で知る)
- 稲垣栄洋(2014).弱者の戦略 新潮社(CiNii Books「稲垣栄洋」で知る)
- 稲垣栄洋(2013).植物の不思議な生き方 朝日新聞出版(CiNii Books「稲垣栄洋」で知る)
- 稲垣栄洋(2013).雑草に学ぶ「ルデラル」な生き方:小さく、速く、多様に、しなやかに 亜紀書房(CiNii Books「稲垣栄洋」で知る)
- 稲垣栄洋(2012).雑草は踏まれても諦めない:逆境を生き抜くための成功戦略 中央公論新社(CiNii Books「稲垣栄洋」で知る)
[2017.3.4]ホーム「お知らせ」欄を変更
- ポスター発表「学習行動調査データを用いた女子大学ベンチマーク」(大学教育改革フォーラムin東海2017)を掲載
[2017.3.1]「過去の「お知らせ」」、「これまでの発表・競争的研究資金など」に追加
- 研修会講師「講義:京都光華女子大学のIR実践事例」、「講義:IR入門のためのQ&A」、「演習:IR入門のためのグループ討論」(平成28年度第2回IR初級人材研修会(パイロット事業))を掲載※講師依頼
[2017.2.22]IRなどについての文献メモ 文献一覧を更新<アカデミックスキル>
[2017.2.22]IRなどについての文献メモ 文献一覧を更新<リサーチクエスチョン>
[2017.2.20]IRなどについての文献メモ 文献一覧を更新<中途退学、リテンション>
- 千島雄太・水野雅之(2015).入学前の大学生活への期待と入学後の現実が大学適応に及ぼす影響:文系学部の新入生を対象として 教育心理学研究,63,228-241.[PDF](はてなブックマークで知る)
[2017.2.20]IRなどについての文献メモ 文献一覧を更新<内部質保証、認証評価>
- 工藤潤(2017).第3期認証評価における大学評価について:大学基準協会が目指す内部質保証 大学時報,372,98-105.[PDF]
[2017.2.20]ホーム「お知らせ」欄を変更
- 企画・話題提供「小規模大学におけるIR」(第23回大学教育研究フォーラム参加者企画セッション)発表時間を掲載
- 口頭発表「ディプロマ・ポリシーとカリキュラム・ポリシーのつながりをデータに基づいて検証する」(第23回大学教育研究フォーラム個人研究発表)発表時間を掲載
- 口頭発表「女子大学ベンチマークの試み」(第23回大学教育研究フォーラム個人研究発表)発表時間を掲載
[2017.2.7]IRなどについての文献メモ 文献一覧を更新<教育>
- 大村はま(2006).日本の教師に伝えたいこと 筑摩書房(ブログ「ならずものになろう」(@s_locarnoさん)の記事で知る)
- 大村はま(1973).教えるということ 共文社(Amazon.co.jp「大村はま」で知る)
- 大村はま(1996).新編 教えるということ 筑摩書房(Amazon.co.jp「大村はま」で知る)
- 大村はま(2012).大村はまの日本語教室:日本語を育てる 風濤社(Amazon.co.jp「大村はま」で知る)
[2017.2.6]IRなどについての文献メモ 文献一覧を更新<統計>
[2017.2.4]IRなどについての文献メモ 内容をアップ
- 山田礼子(2016).日本のIRの現段階 IDE:現代の高等教育,586,11-16.[概要](副学長の記事執筆で知る)
- 小林雅之・劉文君(2016).日本型IRの構築のために IDE:現代の高等教育,586,17-22.[概要](副学長の記事執筆で知る)
- 細川敏幸(2016).IRネットワークの活動 IDE:現代の高等教育,586,23-28.[概要](副学長の記事執筆で知る)
- 小湊卓夫(2016).IR実務者の現状と課題 IDE:現代の高等教育,586,29-32.[概要](副学長の記事執筆で知る)
- 佛淵孝夫(2016).佐賀大学のIR IDE:現代の高等教育,586,33-36.[概要](副学長の記事執筆で知る)
[2017.1.31]IRなどについての文献メモ 内容をアップ
- 金子元久(2016).IRを育てる IDE:現代の高等教育,586,4-11.[概要](副学長の記事執筆で知る)
[2017.1.31]IRなどについての文献メモ 文献一覧を更新<IR>
- 金子元久(2016).IRを育てる IDE:現代の高等教育,586,4-11.(副学長の記事執筆で知る)
- 山田礼子(2016).日本のIRの現段階 IDE:現代の高等教育,586,11-16.(副学長の記事執筆で知る)
- 小林雅之・劉文君(2016).日本型IRの構築のために IDE:現代の高等教育,586,17-22.(副学長の記事執筆で知る)
- 細川敏幸(2016).IRネットワークの活動 IDE:現代の高等教育,586,23-28.(副学長の記事執筆で知る)
- 小湊卓夫(2016).IR実務者の現状と課題 IDE:現代の高等教育,586,29-32.(副学長の記事執筆で知る)
- 佛淵孝夫(2016).佐賀大学のIR IDE:現代の高等教育,586,33-36.(副学長の記事執筆で知る)
- 水野豊(2016).京都光華女子大学のIR:建学の精神の具現化をめざして IDE:現代の高等教育,586,37-40.(副学長の記事執筆で知る)
- 吉田文・山岸直司・姉川恭子(2016).早稲田大学における分散型IR IDE:現代の高等教育,586,41-45.(副学長の記事執筆で知る)
- 高田英一(2016).IRの目的と取組:九州大学の事例を踏まえて IDE:現代の高等教育,586,46-49.(副学長の記事執筆で知る)
- 遠藤翼(2016).IR政策の動向 IDE:現代の高等教育,586,50-54.(副学長の記事執筆で知る)
- 森利枝(2016).米国のIRとAIR IDE:現代の高等教育,586,55-60.(副学長の記事執筆で知る)
- 劉献君・苑復傑(2016).中国のIR IDE:現代の高等教育,586,61-67.(副学長の記事執筆で知る)
[2017.1.30]ホーム「お知らせ」欄を変更
- 研修会講師「講義:京都光華女子大学のIR実践事例」、「講義:IR入門のためのQ&A」、「演習:IR入門のためのグループ討論」(平成28年度第2回IR初級人材研修会(パイロット事業))を掲載
[2017.1.25]IRなどについての文献メモ 文献一覧を更新<発想法>
- 読書猿(2017).アイデア大全:創造力とブレイクスルーを生み出す42のツール フォレスト出版(Amazon.co.jpレコメンド機能で知る)
[2017.1.25]IRなどについての文献メモ 文献一覧を更新<言語学>
- 工藤真由美・八亀裕美(2008).複数の日本語:方言からはじめる言語学 講談社(Amazon.co.jpレコメンド機能で知る)
[2017.1.23]「過去の「お知らせ」」、「これまでの発表・競争的研究資金など」に追加
- 平成28年度継続的改善のためのIR/IEセミナー運営委員
[2017.1.16]ホーム「お知らせ」欄を変更
- 企画・話題提供「小規模大学におけるIR」(第23回大学教育研究フォーラム)を掲載
- ポスター発表"Feasible ways to benchmark with inadequate database systems"(2017 AIR Forum)
- 外部資金「IR活動の実践知の体系化に関する研究:大学の規模の観点から」(平成29年度公益財団法人文教協会調査研究助成)
[2017.1.4]IRなどについての文献メモ 文献一覧を更新<高等教育政策>
[2017.1.4]IRなどについての文献メモ 文献一覧を更新、内容をアップ<国立大学第3期中期目標>
- 藤井都百(2016).国立大学第3期中期目標期間の中期計画に含まれる指標の種類と特性,大学評価とIR,7,3-10.[PDF][概要](大学評価コンソーシアムからの案内で知る)
- 嶌田敏行(2016).学生調査の際に学籍番号を取得することに関する小考察,大学評価とIR,7,11-16.[PDF][概要](大学評価コンソーシアムからの案内で知る)
[2017.1.2]IRなどについての文献メモ 文献一覧を更新<意思決定>
- ギルボア,I.川越敏司・佐々木俊一郎(訳)(2012).意思決定理論入門 NTT出版(Amazon.co.jp「意思決定」で知る)
- 籠屋邦夫(1997).意思決定の理論と技法:未来の可能性を最大化する ダイヤモンド社(Amazon.co.jp「意思決定」で知る)
- ベイザーマン,M.H.&ムーア,D.A.長瀬勝彦(訳)(2011).行動意思決定論:バイアスの罠 白桃書房 (Amazon.co.jp「意思決定」で知る)
- ロベルト,M.A.スカイライトコンサルティング(訳)(2006).決断の本質:プロセス志向の意思決定マネジメント 英治出版(Amazon.co.jp「意思決定」で知る)
- 田坂広志(2003).意思決定12の心得:仕事を成長の糧とするために PHP研究所(Amazon.co.jp「意思決定」で知る)
- 印南一路(1997).すぐれた意思決定:判断と選択の心理学 中央公論社(Amazon.co.jp「意思決定」で知る)
- 中島一(2009).意思決定入門:第2版 日本経済新聞出版社(Amazon.co.jp「意思決定」で知る)
- 長瀬勝彦(2008).意思決定のマネジメント 東洋経済新報社(Amazon.co.jp「意思決定」で知る)
- 松原望(2001).意思決定の基礎:改訂版 朝倉書店(Amazon.co.jp「意思決定」で知る)
- カーネマン,D. 村井章子(訳)(2012).ファスト&スロー (上):あなたの意思はどのように決まるか? 早川書房(Amazon.co.jp「意思決定」で知る)
- カーネマン,D. 村井章子(訳)(2012).ファスト&スロー (下):あなたの意思はどのように決まるか? 早川書房(Amazon.co.jp「意思決定」で知る)
- ソフトバンクアカデミア特別講義(編)(2011).孫正義:リーダーのための意思決定の極意 光文社(Amazon.co.jp「意思決定」で知る)
- 印南一路(2014).意思決定トレーニング 筑摩書房(Amazon.co.jp「意思決定」で知る)
- 本田直之(2009).意思決定力 ダイヤモンド社(Amazon.co.jp「意思決定」で知る)
- 冨田和成(2016).鬼速PDCA クロスメディア・パブリッシング (Amazon.co.jp「意思決定」で知る)
[2017.1.2]IRなどについての文献メモ 文献一覧を更新<言語学>
- 鈴木孝夫(1973).ことばと文化 岩波書店(Amazon.co.jp「鈴木孝夫」で知る)
- 鈴木孝夫(1990).日本語と外国語 岩波書店(Amazon.co.jp「鈴木孝夫」で知る)
- 鈴木孝夫(1996).教養としての言語学 岩波書店(Amazon.co.jp「鈴木孝夫」で知る)
- 鈴木孝夫(1999).日本人はなぜ英語ができないか 岩波書店(Amazon.co.jp「鈴木孝夫」で知る)
- 鈴木孝夫(2009).日本語教のすすめ 新潮社(Amazon.co.jp「鈴木孝夫」で知る)
[2016.12.22]IRなどについての文献メモ 文献一覧を更新<研修>
- 中原淳(編著)(2015).人事よ、ススメ!:先進的な企業の「学び」を描く「ラーニングイノベーション論」の12講 碩学舎(Amazon.co.jp「中原淳」で知る)
- 中原淳(2014).駆け出しマネジャーの成長論:7つの挑戦課題を「科学」する 中央公論新社(Amazon.co.jpレコメンド機能で知る)
- 中原淳(2014).研修開発入門:会社で「教える」、競争優位を「つくる」 ダイヤモンド社(Amazon.co.jpレコメンド機能で知る)
- 中原淳(2012).経営学習論:人材育成を科学する 東京大学出版会(Amazon.co.jpレコメンド機能で知る)
- 中原淳(編著)(2012).職場学習の探究:企業人の成長を考える実証研究 生産性出版(Amazon.co.jpレコメンド機能で知る)
- 中原淳(2010).職場学習論:仕事の学びを科学する 東京大学出版会(Amazon.co.jpレコメンド機能で知る)
- 鈴木克明(2015).研修設計マニュアル:人材育成のためのインストラクショナルデザイン 北大路書房(Amazon.co.jpレコメンド機能で知る)
- 永谷研一(2015).人材育成担当者のための絶対に行動定着させる技術 ProFuture(Amazon.co.jpレコメンド機能で知る)
- 本間浩輔・中原淳(2016).会社の中はジレンマだらけ:現場マネジャー「決断」のトレーニング 光文社(Amazon.co.jpレコメンド機能で知る)
[2016.12.22]IRなどについての文献メモ 文献一覧を更新<動画>
- 瀬川陣市(2014).ショートムービー作りでおぼえる動画撮影の教科書 秀和システム(Amazon.co.jp「動画作成」で知る)
- 家子史穂・千崎達也(2015).仕事に使える動画術:成功例に学ぶYouTube活用とオリジナル動画作成法 翔泳社(Amazon.co.jpレコメンド機能で知る)
- 新井一樹(編著)(2016).いきなり効果があがるPR動画の作り方:自分で作れる、シナリオが決め手 言視舎(Amazon.co.jpレコメンド機能で知る)
- 渡川修一・小西イサオ(2016).1人でできる!3日で完成!事例で学ぶ1分間PR動画ラクラク作成ハンドブック:今日から役立つ入門書!プロが教えるノウハウ満載 ペンコム(Amazon.co.jpレコメンド機能で知る)
[2016.12.15]IRなどについての文献メモ 文献一覧を更新<デザイン>
- カイシトモヤ(2016).たのしごとデザイン論:クリエイターが幸福に仕事をするための50の方法論。 エムディエヌコーポレーション(京都精華大学購買部で知る)
- ウィリアムズ,C.小竹由加里(訳)(2014).かたちの理由:自然のもの、人工のもの。何がかたちを決め、変えるのか ビー・エヌ・エヌ新社(京都精華大学購買部で知る)
[2016.12.15]「過去の「お知らせ」」、「IRなどについての文献メモ」、「これまでの発表・競争的研究資金など」に追加
- 口頭発表「IR研修のための動画コンテンツ:全体構想に基づいた試作版、ユーザー評価の報告」(平成28年度第3回IR実務担当者連絡会)を掲載
- 口頭発表「図書館データを活用した女子大学ベンチマークの試行から見えてくるもの:利点と課題」(平成28年度第3回IR実務担当者連絡会)を掲載
[2016.12.09]ホーム「お知らせ」欄を変更
- セミナー運営委員「平成28年度継続的改善のためのIR/IEセミナー」を掲載
[2016.12.07]IRなどについての文献メモ 文献一覧を更新<IR>
[2016.12.07]IRなどについての文献メモ 文献一覧を更新<中途退学、リテンション>
[2016.12.07]IRなどについての文献メモ 文献一覧を更新、内容をアップ<IR>
- 劉文君(2016).日本におけるIRの機能:IR組織の設置との関連に着目して 大学研究,42,65-76.[PDF][概要](Google Scholarアラート「"institutional research"」で知る)
[2016.12.07]IRなどについての文献メモ 文献一覧を更新、内容をアップ<大学職員、SD>
- 加藤毅(2016).大学職員の職務特性と育成環境 大学研究,42,27-48.[PDF][概要](Google Scholarアラート「"institutional research"」で知る)
[2016.12.1]「過去の「お知らせ」」、「IRなどについての文献メモ」、「これまでの発表・競争的研究資金など」に追加
- 研修会講師「講義:IR入門のためのQ&A」、「演習:IR入門のためのグループ討論」(平成28年度第1回IR初級人材研修会(パイロット事業))を掲載※講師依頼
[2016.11.28]IRなどについての文献メモ 文献一覧を更新<デザイン、書体>
- 張秀民・大内田貞郎・豊島正之・鈴木広光・小宮山博史・宮坂弥代生・佐賀一郎・劉賢国・孫明遠・内田明・小形克宏(2009).活字印刷の文化史:きりしたん版・古活字版から新常用漢字表まで 勉誠出版(小宮山博史(2009)『日本語活字ものがたり』で知る)
- 松田行正(2013).和的:日本のかたちを読む NTT出版(Google「美華書館」で知る)
- 日本新聞協会(1959).新聞活字字体統一に関する資料(小宮山博史(2009)『日本語活字ものがたり』で知る)
[2016.11.25]ホーム「お知らせ」欄を変更
- 口頭発表「ディプロマ・ポリシーとカリキュラム・ポリシーのつながりをデータに基づいて検証する」(第23回大学教育研究フォーラム)を掲載
- 口頭発表「女子大学ベンチマークの試み」(第23回大学教育研究フォーラム)を掲載
[2016.11.18]ホーム「お知らせ」欄を変更
- 口頭発表「IR研修のための動画コンテンツ:全体構想に基づいた試作版、ユーザー評価の報告」(平成28年度第3回IR実務担当者連絡会)を掲載
- 口頭発表「図書館データを活用した女子大学ベンチマークの試行から見えてくるもの:利点と課題」(平成28年度第3回IR実務担当者連絡会)を掲載
[2016.11.16]ホーム「お知らせ」欄を変更
- 研修会講師「講義:IR入門のためのQ&A」、「演習:IR入門のためのグループ討論」(平成28年度第1回IR初級人材研修会(パイロット事業))を掲載
[2016.11.16]IRなどについての文献メモ 文献一覧を更新<デザイン、書体>
- 小宮山博史(2009).日本語活字ものがたり:草創期の人と書体 誠文堂新光社(雪朱里+グラフィック社編集部(編)(2015)で知る)
- 小宮山博史・小池和夫・府川充男(2001).真性活字中毒者読本:版面考証/活字書体史遊覧 柏書房(Amazon.co.jpレコメンド機能で知る)
- 印刷史研究会(編)(2000).本と活字の歴史事典 柏書房(Amazon.co.jpレコメンド機能で知る)
- 小林章(2005).欧文書体:その背景と使い方 美術出版社(Amazon.co.jpレコメンド機能で知る)
- 小林章(2008).欧文書体2:定番書体と演出法 美術出版社(Amazon.co.jpレコメンド機能で知る)
[2016.11.05]IRなどについての文献メモ 文献一覧を更新、内容をアップ<FD、組織>
- 中井俊樹・齋藤芳子(2007).大学教育の質を総合的に向上させる研修教材の評価 メディア教育研究,4(1),31-40.[PDF][概要](CiNii Articles「大学 構成員 意識」で知る)
[2016.10.31]「過去の「お知らせ」」、「IRなどについての文献メモ」、「これまでの発表・競争的研究資金など」に追加
- 会義講師「大学価値の向上を目指したIRの試みとICTシステムの構築」(平成28年度教育改革事務部門管理者会義)を掲載※講演依頼
[2016.10.30]IRなどについての文献メモ 文献一覧を更新<デザイン>
- デザインノート編集部(編)(2016).デザインノート:最新デザインの表現と思考のプロセスを追う(No.69:文字。:文字の達人の仕事を徹底研究) 誠文堂新光社(Amazon.co.jpレコメンド機能で知る)
- デザインノート編集部(編)(2016).デザインノート:最新デザインの表現と思考のプロセスを追う(No.67:色の模様と和のデザイン) 誠文堂新光社(Amazon.co.jpレコメンド機能で知る)
- デザインノート編集部(編)(2016).デザインノート:最新デザインの表現と思考のプロセスを追う(No.68:最新のクリエイションの現場と仕事の人脈) 誠文堂新光社(誠文堂新光社『デザインノート』バックナンバーで知る)
- デザインノート編集部(編)(2015).デザインノート:最新デザインの表現と思考のプロセスを追う(No.64:ロゴ&マークは、やっぱり楽しい。) 誠文堂新光社(誠文堂新光社『デザインノート』バックナンバーで知る)
- デザインノート編集部(編)(2015).デザインノート:最新デザインの表現と思考のプロセスを追う(No.63:もっとも新しいデザインの教科書) 誠文堂新光社(誠文堂新光社『デザインノート』バックナンバーで知る)
- デザインノート編集部(編)(2015).デザインノート:最新デザインの表現と思考のプロセスを追う(No.62:デザインで攻略するプレゼンテーション術) 誠文堂新光社(誠文堂新光社『デザインノート』バックナンバーで知る)
- デザインノート編集部(編)(2015).デザインノート:最新デザインの表現と思考のプロセスを追う(No.60:デザイナー60人が魅せる小型グラフィックス) 誠文堂新光社(誠文堂新光社『デザインノート』バックナンバーで知る)
- デザインノート編集部(編)(2014).デザインノート:最新デザインの表現と思考のプロセスを追う(No.57:トップADから学ぶ「色」の使い方選び方) 誠文堂新光社(誠文堂新光社『デザインノート』バックナンバーで知る)
- デザインノート編集部(編)(2014).デザインノート:最新デザインの表現と思考のプロセスを追う(No.56:「模様」のデザイン) 誠文堂新光社(誠文堂新光社『デザインノート』バックナンバーで知る)
- デザインノート編集部(編)(2013).デザインノート:最新デザインの表現と思考のプロセスを追う(No.49:Typography 文字を学び文字を極める) 誠文堂新光社(誠文堂新光社『デザインノート』バックナンバーで知る)
- デザインノート編集部(編)(2013).デザインノート:最新デザインの表現と思考のプロセスを追う(No.47:「触れる」グラフィックデザイン) 誠文堂新光社(誠文堂新光社『デザインノート』バックナンバーで知る)
- デザインノート編集部(編)(2012).デザインノート:最新デザインの表現と思考のプロセスを追う(No.46:「手描き」活用術) 誠文堂新光社(誠文堂新光社『デザインノート』バックナンバーで知る)
- デザインノート編集部(編)(2012).デザインノート:最新デザインの表現と思考のプロセスを追う(No.43:グラフィックデザインの教科書) 誠文堂新光社(誠文堂新光社『デザインノート』バックナンバーで知る)
- デザインノート編集部(編)(2012).デザインノート:最新デザインの表現と思考のプロセスを追う(No.42:博報堂のデザイン) 誠文堂新光社(誠文堂新光社『デザインノート』バックナンバーで知る)
- デザインノート編集部(編)(2011).デザインノート:最新デザインの表現と思考のプロセスを追う(No.41:「色」で伝えるデザイン) 誠文堂新光社(誠文堂新光社『デザインノート』バックナンバーで知る)
- デザインノート編集部(編)(2011).デザインノート:最新デザインの表現と思考のプロセスを追う(No.38:デザインを極める文字と文字組) 誠文堂新光社(誠文堂新光社『デザインノート』バックナンバーで知る)
- デザインノート編集部(編)(2011).デザインノート:最新デザインの表現と思考のプロセスを追う(No.36:キャラクターデザイン活用術!!) 誠文堂新光社(誠文堂新光社『デザインノート』バックナンバーで知る)
- デザインノート編集部(編)(2010).デザインノート:最新デザインの表現と思考のプロセスを追う(No.31:「手書き」から創るデザイン) 誠文堂新光社(誠文堂新光社『デザインノート』バックナンバーで知る)
- デザインノート編集部(編)(2008).デザインノート:最新デザインの表現と思考のプロセスを追う(No.25:タイポグラフィ2009) 誠文堂新光社(誠文堂新光社『デザインノート』バックナンバーで知る)
- デザインノート編集部(編)(2008).デザインノート:最新デザインの表現と思考のプロセスを追う(No.22:デザインとコピー) 誠文堂新光社(誠文堂新光社『デザインノート』バックナンバーで知る)
- デザインノート編集部(編)(2008).デザインノート:最新デザインの表現と思考のプロセスを追う(No.17:トップアートディレクターの表現力が冴えるポスターデザイン) 誠文堂新光社(誠文堂新光社『デザインノート』バックナンバーで知る)
- デザインノート編集部(編)(2007).デザインノート:最新デザインの表現と思考のプロセスを追う(No.13:LOGO TYPOGRAPHY) 誠文堂新光社(誠文堂新光社『デザインノート』バックナンバーで知る)
- デザインノート編集部(編)(2006).デザインノート:最新デザインの表現と思考のプロセスを追う(No.9:プレゼンテーションを支える立体デザインディレクション) 誠文堂新光社(誠文堂新光社『デザインノート』バックナンバーで知る)
- デザインノート編集部(編)(2005).デザインノート:最新デザインの表現と思考のプロセスを追う(No.2:アートディレクターが魅せる文字・ロゴ・フォント) 誠文堂新光社(誠文堂新光社『デザインノート』バックナンバーで知る)
[2016.10.30]IRなどについての文献メモ 文献一覧を更新<デザイン、書体>
- MdN編集部(編)(2015).月刊MdN(2015年7月号 特集:絶対フォント感を身につける) エムディエヌコーポレーション(id:rororororoさんのブログ記事「デザイナーが仕事で使い倒してるフリー日本語フォント12選」で知る)
- MdN編集部(編)(2016).月刊MdN(2016年11月号 特集:絶対フォント感を身につける。2) エムディエヌコーポレーション(Amazon.co.jpレコメンド機能で知る)
- MdN編集部(編)(2014).月刊MdN(2014年12月号 特集:漫画デザインのタイポグラフィ表現論) エムディエヌコーポレーション(Amazon.co.jpレコメンド機能で知る)
- +DESIGNING編集部(2016).+DESIGNING VOLUME 42(特集:基礎力UP&実力UP!実践文字組み講座) マイナビ出版(Amazon.co.jpレコメンド機能で知る)
- 鳥海修(2016).文字を作る仕事 晶文社(Amazon.co.jpレコメンド機能で知る)
- 大崎善治(2010).タイポグラフィの基本ルール:プロに学ぶ、一生枯れない永久不滅テクニック SBクリエイティブ(Amazon.co.jpレコメンド機能で知る)
- 雪朱里+グラフィック社編集部(編)(2015).もじ部:書体デザイナーに聞く デザインの背景・フォント選びと使い方のコツ グラフィック社(Amazon.co.jpレコメンド機能で知る)
- 雪朱里(2010).文字をつくる:9人の書体デザイナー 誠文堂新光社(Amazon.co.jpレコメンド機能で知る)
- 正木香子(2013).文字の食卓 本の雑誌社(Amazon.co.jpレコメンド機能で知る)
- カイシトモヤ(2014).How to Design:いちばん面白いデザインの教科書 エムディエヌコーポレーション(Amazon.co.jpレコメンド機能で知る)
- ヴィクショナリー(編)(2015).モノトーン・デザイン:単色使いが効果的な世界のグラフィック・コレクション グラフィック社(Amazon.co.jpレコメンド機能で知る)
- 永原康史(2016).インフォグラフィックスの潮流:情報と図解の近代史 誠文堂新光社(Amazon.co.jpレコメンド機能で知る)
- 佐藤浩二・田中雄一郎・小野圭介(2016).ロゴデザインの現場:事例で学ぶデザイン技法としてのブランディング エムディエヌコーポレーション(Amazon.co.jpレコメンド機能で知る)
- リンクアップ・グラフィック社編集部(編)(2016).実用的なチラシデザイン:ペラ1枚に落としこむ情報整理のアイデア集 グラフィック社(Amazon.co.jpレコメンド機能で知る)
- PIE BOOKS(編)(2016).数字で伝える広告デザイン パイインターナショナル(Amazon.co.jpレコメンド機能で知る)
- 水口克夫(2015).アートディレクションの「型」。:デザインを伝わるものにする30のルール 誠文堂新光社(Amazon.co.jpレコメンド機能で知る)
[2016.10.23]「過去の「お知らせ」」、「IRなどについての文献メモ」、「これまでの発表・競争的研究資金など」に追加
- 口頭発表「事例の文脈を理解するための観点:中途退学防止に関するIR活動を事例として」(平成28年度第2回IR実務担当者連絡会)
- 分科会講師「「IR活動を学内で進めていくための実現可能な方法」を考える」(2016年度第14回SDフォーラム分科会D)※講師依頼
[2016.10.13]IRなどについての文献メモ 文献一覧を更新<大学評価>
- 生和秀敏(編)(2016).大学評価の体系化 東信堂(大学基準協会からの会員校向け出版物送付で知る)
- 小林雅之(2003).海外の大学情報データベースと日本の可能性 大学評価,3,51-64.(Google「"organization * database" ipeds」で知る)
[2016.10.12]IRなどについての文献メモ 文献一覧を更新<IT>
[2016.10.11]IRなどについての文献メモ 文献一覧を更新<資料作成、イラスト>
[2016.10.03]IRなどについての文献メモ 文献一覧を更新<科研費>
[2016.09.30]IRなどについての文献メモ 文献一覧を更新<学習時間、単位制度>
- Noda, A. (2016). How do credit hours assure the quality of higher education? Time-based vs. competency-based debate. CEAFJP discussion paper series, 16-05, 1-18.[PDF](Google「"study hours" "outside * classes"」で知る)
[2016.09.28]ホーム「お知らせ」欄を変更
- 口頭発表「事例の文脈を理解するための観点:中途退学防止に関するIR活動を事例として」(平成28年度第2回IR実務担当者連絡会)を掲載
- 会義講師「大学価値の向上を目指したIRの試みとICTシステムの構築」(平成28年度教育改革事務部門管理者会義)を掲載※講演依頼
[2016.09.24]IRなどについての文献メモ 文献一覧を更新<職業教育、学位>
- 大学改革支援・学位授与機構(2016).高等教育における職業教育と学位:アメリカ・イギリス・フランス・ドイツ・中国・韓国・日本の7か国比較研究報告(大学評価・学位授与機構研究報告 第2号) 大学改革支援・学位授与機構[PDF](Twitter(@high190さん)で知る)
[2016.09.16]IRなどについての文献メモ 文献一覧を更新<事例、抽象化>
- Ishikawa, T., & Terano, T. (1996). Analogy by abstraction: Case retrieval and adaptation for inventive design expert systems. Expert systems with applications, 10(3-4), 351-356.[Abstract](Google Scholar「abstraction case」で知る)
- Winters, N., & Mor, Y. (2009). Dealing with abstraction: Case study generalisation as a method for eliciting design patterns. Computers in human behavior, 25(5), 1079–1088.[Abstract](Google Scholar「abstraction case」で知る)
- Bergmann, R., & Wilke, W. (2005). On the role of abstraction in case-based reasoning. Advances in case-based reasoning, 1168, 28-43.[Abstract](Google Scholar「abstraction case」で知る)
- 吉浦裕(1992).事例ベース推論 電氣學會雜誌,112(12),989-992.[PDF](Google Scholar「事例ベース推論」で知る)
- 仲谷善雄(2002).事例ベース推論の動向 人工知能学会誌,17(1),28-33.[PDF](Cinii Articles「事例ベース推論」で知る)
- 工藤与志文(2013).ルール学習における知識表象の不十分な抽象化とその問題 教育心理学研究,61(3),239-250.[PDF](Google Scholar「知識 抽象化」で知る)
- LeFevre, J-N., & Dixon, P. (2009). Do written instructions need examples? Cognition and instruction, 3, 10-30.[Abstract](何らかの情報を与えられて学習を行う場合は一般的な教示や原理に関する情報よりもより特殊性を帯びた「事例」に関する情報に頼る傾向がある、それを帰納的推論の領域で報告;工藤(2013)「ルール学習における知識表象の不十分な抽象化とその問題」で知る)
- Ross, B. H.; & Kilbane, M. C. (1997). Effects of principle explanation and superficial similarity on analogical mapping in problem solving. Journal of experimental psychology: Learning, memory, and cognition, 23(2), 427-440.[Abstract](何らかの情報を与えられて学習を行う場合は一般的な教示や原理に関する情報よりもより特殊性を帯びた「事例」に関する情報に頼る傾向がある、それをアナロジーの領域で報告;工藤(2013)「ルール学習における知識表象の不十分な抽象化とその問題」で知る)
- 藤田敦(2005).複数事例の提示が概念の般化可能性に及ぼす影響:気圧の力学的性質に関する概念受容学習過程 教育心理学研究,53(1),122-132.[PDF](複数事例の提示が概念の頒価可能性を促進するという効果の背景を検証した、提示事例数の増加に伴って概念の適用範囲に影響する要因が[提示事例と般化問題の表面的な類似性]から[因果的、関係構造的な類似性]へと移行する、学校で科学的概念の教育が概念受容学習の手続きで行われる場合には多様な事例を準備することが望ましいのは言うまでもない、ただし効率性を考えると概念受容学習の過程で[学習者が最低限経験すべきことが何であるか]を明確にする必要がある;Google Scholar「転移 抽象化」で知る)
- 工藤与志文(2003).概念受容学習における知識の一般化可能性に及ぼす教示情報解釈の影響:「事例にもとづく帰納学習」の可能性の検討 教育心理学研究,51(3),281-287.[PDF] (事例からの帰納によって概念を発見していくという学習過程ではなく教授者から予め提示される科学的概念に関する説明を学習者が受け容れることで成立するという「概念受容学習」の過程がある;藤田(2005)「複数事例の提示が概念の般化可能性に及ぼす影響」で知る)
- 麻柄啓一(1990).科学的概念の発達 丸野俊一(編)新・児童心理学講座:概念と知識の発達 pp.155-197.(「特定の事例に対してだけしか外延が広がっていないとすれば、学習者の概念は十分な発達をとげているとはいえない」;藤田(2005)「複数事例の提示が概念の般化可能性に及ぼす影響」で知る)
- 松原仁(1992).推論技術の観点からみた事例に基づく推論 人工知能学会誌,7(4),567-575.[PDF](Cinii Articles「<特集>「事例ベース推論」」で知る)
- 小林重信 (1992).事例ベース推論の現状と展望 人工知能学会誌,7(4),559-566.[PDF](Cinii Articles「<特集>「事例ベース推論」」で知る)
- 戸沢義夫(1992).特集「事例ベース推論」にあたって 人工知能学会誌,7(4),558.[PDF](Cinii Articles「<特集>「事例ベース推論」」で知る)
[2016.09.08]IRなどについての文献メモ 文献一覧を更新<卒業後>
- Coughlin, M. A., Laguilles, J. S., Kelly, H. A., & Walters, A. M. (2016). Postgraduate outcomes in American higher education. New directions for institutional research, 2016(169), 11-23.[Abstract](New Directions for Institutional Researchのcontent alertで知る)
- Laguilles, J. S. (2016). Collecting and using postgraduate outcomes data at a private college. New directions for institutional research, 2016(169), 25–36.[Abstract](New Directions for Institutional Researchのcontent alertで知る)
- Kelly, H. A., & Walters, A. M. (2016). First-destination outcomes at a public research university: Aligning our survey with a set of standards. New directions for institutional research, 2016(169), 37-50.[Abstract](New Directions for Institutional Researchのcontent alertで知る)
- Rowen, C. (2016). So much more than salary: Outcomes research in the liberal arts. New directions for institutional research, 2016(169), 51–60.[Abstract](New Directions for Institutional Researchのcontent alertで知る)
- Guthrie, L. A. (2016). Community colleges: Preparing students for diverse careers. New directions for institutional research, 2016(169), 61–72.[Abstract](New Directions for Institutional Researchのcontent alertで知る)
- Powers, K., & MacPherson, D. (2016). Leading gainful employment metric reporting. New directions for institutional research, 2016(169), 73–86.[Abstract](New Directions for Institutional Researchのcontent alertで知る)
- Troutman, D. R., & Shedd, J. M. (2016). Using state workforce data to examine postgraduation outcomes. New directions for institutional research, 2016(169), 87–102.[Abstract](New Directions for Institutional Researchのcontent alertで知る)
[2016.08.28]「過去の「お知らせ」」、「IRなどについての文献メモ」、「これまでの発表・競争的研究資金など」に追加
- ポスター発表「ディプロマポリシーを根拠に基づいて見直す:単位配分・成績評価・履修登録データを用いた検証作業」(高等教育質保証学会第6回大会)
[2016.08.28]「過去の「お知らせ」」、「これまでの発表・競争的研究資金など」に追加
- 大学評価担当者集会2016分科会「評価・IRの実践・課題共有セッション」私立大学班ファシリテーター
[2016.08.24]IRなどについての文献メモ 文献一覧を更新<統計、相関>
- 谷岡一郎(2000).「社会調査」のウソ:リサーチ・リテラシーのすすめ 文藝春秋(Google「相関 因果関係 site:ac.jp」で知る)
- 谷岡一郎(2007).データはウソをつく:科学的な社会調査の方法 筑摩書房(Amazon.co.jp「社会調査のうそ」で知る)
- ジョエル,B.林大(訳)(2002).統計はこうしてウソをつく:だまされないための統計学入門 白揚社(Amazon.co.jp「社会調査のうそ」で知る)
- ジョエル,B.林大(訳)(2007).統計という名のウソ:数字の正体,データのたくらみ 白揚社(Amazon.co.jp「社会調査のうそ」で知る)
[2016.08.20]IRなどについての文献メモ 内容をアップ
- 日本私立大学協会(編)(1998).米国の大学経営戦略:マーケティング手法に学ぶ 学法文化センター出版部[概要](Twitter(@yochipumiさん)で知る)
- 阿部彩(2014).子どもの貧困II:解決策を考える 岩波書店[概要](Amazon.co.jp「貧困 教育」で知る)
- 阿部彩(2008).子どもの貧困:日本の不公平を考える 岩波書店[概要](Amazon.co.jp「貧困 教育」で知る)
- 三谷宏治(2009).発想の視点力:いまは見えないものを見つけ出す 日本実業出版社[概要](Amazon.co.jpレコメンド機能で知る)
[2016.08.20]IRなどについての文献メモ 文献一覧を更新<発想法>
- 三谷宏治(2009).発想の視点力:いまは見えないものを見つけ出す 日本実業出版社(Amazon.co.jpレコメンド機能で知る)
[2016.08.19]ホーム「お知らせ」欄を変更
- 大学評価担当者集会2016でのスタッフ(ファシリテーター)担当を掲載
[2016.08.17]IRなどについての文献メモ 文献一覧を更新<中途退学、リテンション>
- Clotfelter, C. T. (1991). Patterns of enrollment and completion. In C. T. Clotfelter, R. G. Ehrenberg, M. Getz, & J. J. Siegfeied Economic challenges in higher education. Chicago: University of Chicago Press. pp.28-58.[PDF](Google「"Persistence to Degree"」で知る)
[2016.08.10]大学に関わる情報メモ 内容をアップ
[2016.08.10]大学に関わる情報メモ 内容をアップ
[2016.08.08]「過去の「お知らせ」」、「IRなどについての文献メモ」、「これまでの発表・競争的研究資金など」に追加
- 口頭発表「女子大学ベンチマークの構築プロセス:図書館の学習支援を比較対象とした試行」(平成28年度第1回IR実務担当者連絡会)
[2016.08.08]「これまでの発表・競争的研究資金など」に追加
- 大学評価コンソーシアム次期幹事選定会議委員(2016年)
[2016.08.08]ホーム「お知らせ」欄を変更
- 分科会事例報告「「IR活動を学内で進めていくための実現可能な方法」を考える」(2016年度第14回SDフォーラム)を掲載※話題提供依頼
[2016.08.05]IRなどについての文献メモ 文献一覧を更新<科研費>
[2016.08.05]「これまでの発表・競争的研究資金など」に追加
- 大学評価コンソーシアム『大学評価とIR』査読者(2015年)を掲載
[2016.08.05]IRなどについての文献メモ 文献一覧を更新<ベンチマーク>
- 山田礼子(2012).学士課程教育の質保証へむけて:学生調査と初年次教育からみえてきたもの 東信堂(京都光華女子大学図書館蔵書検索「初年次教育」で知る)(学修行動調査などの教育に関するデータは財務データなどと異なり多くの大学が共通して使用できるだけでなく教育の効果のベンチマーク(評価指標)として利用することが可能;山田(2013)「学生の特性を把握する間接評価」で知る)
- 池田輝政・神保啓子・中井俊樹・青山佳代(2006).FDを持続的に革新するベンチマーキング手法の事始め 大学論集,37,115-130.[PDF](『大学論集』バックナンバーで知る)(いわゆるグッドプラクティスにあたる大学と当該大学を比較することをベンチマークと呼ぶ場合がある;小林・片山・劉(2011)「大学ベンチマークによる大学評価の実証的研究」知る)
- 小林雅之・片山英治・劉文君(2011).大学ベンチマークによる大学評価の実証的研究 東京大学大学総合教育研究センター[PDF](日本のIRについての先行研究レビュー、IRの定義について初期にはデータ収集・分析という点が強調されたが現在は戦略計画の策定や大学の変化を促進する役割など定義が広がっている、ベンチマークは様々な意味で用いられている、どのような意味で用いられているか十分注意する必要がある;小林・浅野(2011)で知る)
- Levy, G. D., & Valcik, N. A. (2004). Benchmarking in institutional research. New directions for higher education, 156.(Amazon.co.jp「institutional research」で知る)(Amazon.co.jp「ベンチマーク」で知る)(Amazon.co.jp「benchmarking in higher education an international review」で知る)
- Alstete, J. W. (1996). Benchmarking in higher education: Adapting best practices to improve quality. Washington, D.C.: Graduate School of Education and Human Development, the George Washington University.(Amazon.co.jp「benchmarking in higher education an international review」で知る)
- Smith, H., Armstrong, M., & Brown, A. (1999). Benchmarking and threshold standards in higher education. London: Kogan Page.(Amazon.co.jp「benchmarking in higher education an international review」で知る)
[2016.08.03]IRなどについての文献メモ 文献一覧を更新<政策評価>
- 龍慶昭・佐々木亮(2004).「政策評価」の理論と技法 多賀出版(Amazon.co.jp「政策評価」で知る)
- 山谷清志(2011).政策評価 ミネルヴァ書房(Amazon.co.jp「政策評価」で知る)
- 山谷清志(2016).政策評価の理論とその展開:政府のアカウンタビリティ 晃洋書房(Amazon.co.jp「政策評価」で知る)
- エプスタイン,M.J.,&ユーザス,K.鵜尾雅隆(訳)(2015).社会的インパクトとは何か:社会変革のための投資・評価・事業戦略ガイド 英治出版(Amazon.co.jp「政策評価」で知る)
- 小長谷一之・前川知史(編)(2012).経済効果入門:地域活性化・企画立案・政策評価のツール 日本評論社(Amazon.co.jp「政策評価」で知る)
- レヴィン,H.,&マキューアン,P.赤林英夫(訳)(2009).教育の費用効果分析:学校・生徒の教育データを使った政策の評価と立案 日本評論社(Amazon.co.jp「政策評価」で知る)
- 今井照(1999).わかりやすい自治体の政策評価 学陽書房(Amazon.co.jp「政策評価」で知る)
[2016.08.01]ホーム「お知らせ」欄を変更
- ポスター発表「ディプロマポリシーを根拠に基づいて見直す:単位配分・成績評価・履修登録データを用いた検証作業」(高等教育質保証学会第6回大会)を掲載
[2016.08.01]IRなどについての文献メモ 内容をアップ
- 『文部科学教育通信』誌の連載「大学IRの今」(上畠洋佑他、2016年2~8月、全13回、企画者:上畠洋佑先生/金沢大学)[概要]
[2016.08.01]「私立大学職員によるIR文献メモ」メルマガ バックナンバーを更新
[2016.07.30]IRなどについての文献メモ 文献一覧を更新<IR、連載「大学IRの今」>
- 上畠洋佑(2016).日本のIRと大学組織 文部科学教育通信,381,24-25.(連載のイントロダクションの位置づけ;上畠(2016)「Institutional "RE" Search」のまとめを参考に記載)
- 岩野摩耶(2016).科研費(奨励研究)による職員の研究①:英国大学における学内外のデータ収集について 文部科学教育通信,382,26-27.(英国の高等教育統計局(HESA)の役割(収集されたデータを政府や助成団体等に提供するとともに大学・一般にも提供する)と同様のものが日本にも必要;上畠(2016)「Institutional "RE" Search」のまとめを参考に記載))
- 岩野摩耶(2016).科研費(奨励研究)による職員のIR研究②:日本におけるIRデータ収集の3つの課題 文部科学教育通信,383,26-27.(入試・広報を担当する大学職員へのアンケート調査結果を報告、部署をまたがる情報を得ること・学内の情報を一元化することを望んでいた;上畠(2016)「Institutional "RE" Search」のまとめを参考に記載)
- 林英明(2016).教学IRに関わる私大職員の視点から:立教大学 教学IR部会の事例報告 文部科学教育通信,384,26-27.(立教大学の全学委員会型IRの事例を紹介;上畠(2016)「Institutional "RE" Search」のまとめを参考に記載)
- 荒木俊博(2016).私立大学等改革総合支援事業からみるIR 文部科学教育通信,385,24-25.(補助金を獲得するための手段が目的化しているのではないかと指摘;上畠(2016)「Institutional "RE" Search」のまとめを参考に記載)
- 橋本智也(2016).学内データの利用について同意を得る:具体的な進め方の提案 文部科学教育通信,386,24-25.(IR担当者のソフトスキル(組織内コミュニケーション構築など)の習得方法を記載;上畠(2016)「Institutional "RE" Search」のまとめを参考に記載)
- 松宮慎治(2016).私立大学等改革総合支援事業によるIRの「流行」とその問題点 文部科学教育通信,387,26-27.(私立大学等改革総合支援事業によってIRが普及すると期待したが本質を伴わない流行に留まっていると指摘;上畠(2016)「Institutional "RE" Search」のまとめを参考に記載)
- 栗原郁太(2016).玉川大学における教学IRの取り組み 文部科学教育通信,388,26-27.(玉川大学の協調分散型方式IRの事例紹介;上畠(2016)「Institutional "RE" Search」のまとめを参考に記載)
- 長山琢磨(2016).大学ポートレートの活用とIRのこれから 文部科学教育通信,389,30-31.(大学ポートレートの現状と課題についてデータを用いて論じている;上畠(2016)「Institutional "RE" Search」のまとめを参考に記載)
- 小島理絵(2016).私立大学経営から見たIR 文部科学教育通信,390,30-31.(「各大学の経営課題との明確な結びつきが見えない形で学生実態調査などが行われ、それをIRと呼んでいる」と指摘;上畠(2016)「Institutional "RE" Search」のまとめを参考に記載)
- 杉原亨(2016).地方短期大学におけるIR:卒業生調査の実践より 文部科学教育通信,391,26-27.(短期大学のIRの現状と実践経験を紹介;上畠(2016)「Institutional "RE" Search」のまとめを参考に記載)
- 岩野摩耶(2016).科研費(奨励研究)による職員のIR研究③:日本のIR担当者を対象にしたインタビュー調査 文部科学教育通信,392,26-27.(日本の4大学(国立1・私立3)の教職員へのインタビュー調査結果を報告、日本のIRは試行錯誤の段階;上畠(2016)「Institutional "RE" Search」のまとめを参考に記載)
- 上畠洋佑(2016).Institutional "RE" Search 文部科学教育通信,393,30-31.(連載の各記事を「調査研究」・「課題考察」・「IRerの実践知」・「事例紹介」に整理、IR担当者には大学内の限られた資源を効率的・効果的に活用する役割が期待されている)
[2016.07.25]IRなどについての文献メモ 文献一覧を更新<単位制度>
- 仲井邦佳(2016).大学の単位制度と学年暦:「1単位=45時間」と「1科目=1350分説(15週論)」 立命館産業社会論集,51(4),1-11.[PDF](はてなブックマークで知る)
[2016.07.21]IRなどについての文献メモ 文献一覧を更新<貧困、教育機会>
- 西澤晃彦(2015).貧困と社会 放送大学教育振興会(放送大学教育振興会テキスト検索「貧困」で知る)
- 岡田昭人(2013).教育の機会均等 学文社(Amazon.co.jp「教育機会」で知る)
- 日本教育行政学会研究推進委員会(編)(2013).教育機会格差と教育行政 福村出版(Amazon.co.jp「教育機会」で知る)
- 社会政策学会(編)(2007).格差社会への視座:貧困と教育機会 社会政策学会本部事務局(Amazon.co.jp「貧困 教育」で知る)
- 小林雅之(2009).大学進学の機会:均等化政策の検証 東京大学出版会(Amazon.co.jp「教育機会」で知る)
- 杉村宏(監修)(2012).戦後日本貧困問題基本文献集 第1期 日本図書センター[各巻構成](京都光華女子大学図書館蔵書検索「貧困と社会」で知る)
- 杉村宏(監修)(2013).戦後日本貧困問題基本文献集 第2期 日本図書センター[各巻構成](京都光華女子大学図書館蔵書検索「貧困と社会」で知る)
- 伊ケ崎暁生(編)(1978).教育基本法文献選集3 教育の機会均等:第3条 学陽書房(Amazon.co.jp「教育機会」で知る)
- 小林雅之(2008).進学格差:深刻化する教育費負担 筑摩書房(Amazon.co.jp「教育機会」で知る)
- 金子元久・小林雅之(1996).教育・経済・社会 放送大学教育振興会(CiNii Books「小林雅之」で知る)
- 阿部彩(2008).子どもの貧困:日本の不公平を考える 岩波新書(Amazon.co.jp「貧困 教育」で知る)
- 阿部彩(2008).子どもの貧困II:解決策を考える 岩波新書(Amazon.co.jp「貧困 教育」で知る)
- 保坂渉・池谷孝司(2012).ルポ 子どもの貧困連鎖 教育現場のSOSを追って 光文社(Amazon.co.jp「貧困 教育」で知る)
- 藤田孝典(2016).貧困世代:社会の監獄に閉じ込められた若者たち 講談社(Amazon.co.jp「貧困 教育」で知る)
[2016.07.19]IRなどについての文献メモ 文献一覧を更新<戦略>
- 孫子 金谷治(訳注)(2000).孫子 岩波文庫(Amazon.co.jpレコメンド機能で知る)
[2016.07.19]IRなどについての文献メモ 内容をアップ
- 小湊卓夫(2016).IR活動に関するガイドラインの日米比較と今後の展望,大学評価とIR,6,21-31.[概要][PDF](大学評価コンソーシアムからの案内で知る)
[2016.07.19]IRなどについての文献メモ 文献一覧を更新<IR>
- 小湊卓夫(2016).IR活動に関するガイドラインの日米比較と今後の展望,大学評価とIR,6,21-31.[PDF](大学評価コンソーシアムからの案内で知る)
[2016.07.15]ホーム「お知らせ」欄を変更
- 口頭発表「女子大学ベンチマークの構築プロセス:図書館の学習支援を比較対象とした試行」(平成28年度第1回IR実務担当者連絡会)を掲載
- 口頭発表「組織的な早期の中途退学防止策:累積欠席コマ数の週次レポートで個別状況と全体傾向を共有する」(初年次教育学会第9回大会)を掲載
[2016.07.08]大学に関わる情報メモ 内容をアップ
[2016.07.05]IRなどについての文献メモ 内容をアップ
- 山本幸一(2016).設立初期のIRオフィスにおける意思決定支援の効果的運用に係る検討:明治大学におけるファクトブックの作成を通じて 大学評価とIR,6,12-20.[概要][PDF](大学評価コンソーシアムからの案内で知る)
[2016.07.05]IRなどについての文献メモ 文献一覧を更新<IR、ファクトブック>
- 山本幸一(2016).設立初期のIRオフィスにおける意思決定支援の効果的運用に係る検討:明治大学におけるファクトブックの作成を通じて 大学評価とIR,6,12-20.[PDF](大学評価コンソーシアムからの案内で知る)
[2016.06.27]IRなどについての文献メモ 文献一覧を更新<ベンチマーク>
- Hubbell, L. W. L., Massa, R. J., & Lapovsky, L. (2002). Using benchmarking to influence tuition and fee decisions. New directions for higher education, 118, 39-63.(ベンチマークの対象校があまりに多くなると強み・弱みが明確にならない場合がある;小林(2014)「大学ランキングと大学ベンチマークの試み」で知る)
- 小林雅之(2014).大学ランキングと大学ベンチマークの試み 東京大学(編)大学におけるIR(インスティテューショナル・リサーチ)の現状と在り方に関する調査研究報告書 pp.102-109.[PDF]
[2016.06.24]IRなどについての文献メモ 内容をアップ
- 藤原宏司(2016).BIツールを用いた学内データの動的可視化について 大学評価とIR,6,3-11.[PDF][概要](大学評価コンソーシアムからの案内で知る)
- 河尻直己(2016).機能要件の粒度:要件の詳細度を考える 日経systems,276,102-105.[概要](Cinii Articles「粒度」で知る)
[2016.06.15]IRなどについての文献メモ 文献一覧を更新<IR、BIツール>
- 藤原宏司(2016).BIツールを用いた学内データの動的可視化について 大学評価とIR,6,3-11.[PDF](大学評価コンソーシアムからの案内で知る)
[2016.06.14]IRなどについての文献メモ 文献一覧を更新<IR>
- Dee, J. R., & Heineman, W. A. (2016). Understanding the organizational context of academic program development. New directions for institutional research, 168, 9-35.[Abstract](New Directions for Institutional Researchのcontent alertで知る)
- Hagedorn, L. S., & Kuznetsova, I. (2016). Developmental, remedial, and basic skills: Diverse programs and approaches at community colleges. New directions for institutional research, 168, 49–64.[Abstract](New Directions for Institutional Researchのcontent alertで知る)
- King, B. R. (2016). Making the connections across institutional types and academic programs: Recommendations for institutional research practice and future research. New directions for institutional research, 168, 101-105.[Abstract](New Directions for Institutional Researchのcontent alertで知る)
[2016.06.14]IRなどについての文献メモ 文献一覧を更新<要件定義>
- 河尻直己(2016).機能要件の粒度:要件の詳細度を考える 日経systems,276,102-105.(Cinii Articles「粒度」で知る)
- 細川泰秀(2016).要件定義の実態と対策:稼働日に定時帰りが目標 日経systems,271,94-97.(Cinii Articles「誰でも出来る要件定義」で知る)
- 岩佐洋司(2016).作成するドキュメントと事前準備:どこに責任があるのか 日経systems,272,96-99.(Cinii Articles「誰でも出来る要件定義」で知る)
- 岩佐洋司(2016).業務要件定義のポイント:業務要件定義の留意事項 日経systems,273,102-105.(Cinii Articles「誰でも出来る要件定義」で知る)
- 鳥谷部聡(2016).機能漏れや不整合のチェック法:モデル図で網羅的に検証 日経systems,274,104-107.(Cinii Articles「誰でも出来る要件定義」で知る)
- 鳥谷部聡(2016).非機能要件:8項目の品質特性を押さえる 日経systems,275,96-99.(Cinii Articles「誰でも出来る要件定義」で知る)
[2016.06.09]IRなどについての文献メモ 文献一覧を更新<IR>
- Swing, R. L., & Ross, L. E. (2016). A new vision for institutional research. Change, March-April 2016. [HTML]
- Swing, R. L., Jones, D., & Ross, L. E. (2016). The AIR national survey of institutional research offices. Association for Institutional Research, Tallahassee, Florida.[PDF]
[2016.06.08]大学に関わる情報メモ 内容をアップ
[2016.06.06]IRなどについての文献メモ 文献一覧を更新<FD>
[2016.06.06]「過去の「お知らせ」」、「これまでの発表・競争的研究資金など」に追加
- ポスター発表"A data-driven approach to dropout prevention in Japan"(2016 AIR Forum)
[2016.05.20]IRなどについての文献メモ 文献一覧を更新<ラーニングコモンズ>
- 小幡誉子(2016).大正大学における図書館外ラーニング・コモンズの効果と課題:アンケートによる比較調査の結果から 大学マネジメント,9(7),27-34.(Google Scholarアラート「ラーニングコモンズ」で知る)
- 竹内比呂也(2016).大学図書館の新しい姿 大学マネジメント,9(7),2-8.(CiNii Articles「特集 大学図書館の新しい姿」で知る)
- 小山憲司(2016).大学図書館の「あたらしいかたち」:ラーニング・コモンズをとおして見るあらたな役割と課題 大学マネジメント,9(7),9-15.(CiNii Articles「特集 大学図書館の新しい姿」で知る)
- 石田英敬(2016).東京大学「新図書館計画」:新しい知の拠点、アカデミック・コモンズとして 大学マネジメント,9(7),16-20.(CiNii Articles「特集 大学図書館の新しい姿」で知る)
- 米澤誠(2016).アクティブな教育と学習の場としてのラーニング・コモンズ考 大学マネジメント,9(7),21-26.(CiNii Articles「特集 大学図書館の新しい姿」で知る)
- 篠塚義弘(2016).仕事とわたし(15)偶然という必然(縁を大切に) 大学マネジメント,9(7),36-39.(CiNii Articles「特集 大学図書館の新しい姿」で知る)
[2016.05.19]ホーム「お知らせ」欄、「これまでの発表・競争的研究資金など」に追加
- 平成28年度大学改革支援制度(京都光華女子大学学長裁量経費)「学内の既存データと学科の要望を組み合わせた入学初期段階と経時的変化の分析(IR)」を掲載
[2016.05.13]IRなどについての文献メモ 内容をアップ
- 岩崎保道・宮嶋恒二・蔭久孝政・福島謙吉・谷ノ内識(2016).中途退学の防止についての一考察 高知大学教育研究論集,20,49-60.[概要](宮嶋恒二さん(京都学園大学)からのご恵贈で知る)
[2016.05.13]IRなどについての文献メモ 文献一覧を更新<中途退学>
- 岩崎保道・宮嶋恒二・蔭久孝政・福島謙吉・谷ノ内識(2016).中途退学の防止についての一考察 高知大学教育研究論集,20,49-60.(宮嶋恒二さん(京都学園大学)からのご恵贈で知る)
[2016.05.11]IRなどについての文献メモ 文献一覧を更新<IR>
- 高田英一(2016).IRの大学経営への戦略的活用 岩崎保道(編著)大学の戦略的経営手法 大学教育出版 pp.28-43.(中元崇さん(京都大学)からのご恵贈で知る)
[2016.05.11]IRなどについての文献メモ 文献一覧を更新<大学経営>
- 岩崎保道(編著)(2016).大学の戦略的経営手法 大学教育出版(中元崇さん(京都大学)からのご恵贈で知る)
[2016.05.11]IRなどについての文献メモ 文献一覧を更新<アクティブラーニング、協調学習>
- 三宅なほみ・東京大学CoREF・河合塾(2016).協調学習とは:対話を通して理解を深めるアクティブラーニング型授業 北大路書房(はてなブックマークで知る)
[2016.05.02]IRなどについての文献メモ 内容をアップ
- 中島ゆり(2016).大学IR推進上の課題 長崎大学大学教育イノベーションセンター紀要,7,1-8.[PDF][概要](Google Scholarアラート「"institutional research"」で知る)
- 村田嘉弘(2014).大学IRについて 長崎大学 大学教育イノベーションセンター紀要,5,7-11.[PDF][概要](CiNii Articles「institutional research」で知る)(中島(2016)「大学IR推進上の課題」で知る)
- 石井英真(2015).教育実践の論理から「エビデンスに基づく教育」を問い直す:教育の標準化・市場化の中で 教育学研究,82(2),216-228.[概要](中島(2016)「大学IR推進上の課題」で知る)
[2016.05.02]IRなどについての文献メモ 文献一覧を更新<IR>
- 中島ゆり(2016).大学IR推進上の課題 長崎大学大学教育イノベーションセンター紀要,7,1-8.[PDF](Google Scholarアラート「"institutional research"」で知る)
- 村田嘉弘(2014).大学IRについて 長崎大学 大学教育イノベーションセンター紀要,5,7-11.[PDF](CiNii Articles「institutional research」で知る)(中島(2016)「大学IR推進上の課題」で知る)
- 石井英真(2015).教育実践の論理から「エビデンスに基づく教育」を問い直す:教育の標準化・市場化の中で 教育学研究,82(2),216-228.(中島(2016)「大学IR推進上の課題」で知る)
[2016.04.28]「過去の「お知らせ」」、「これまでの発表・競争的研究資金など」に追加
- 連載企画記事「学内データの利用について同意を得る:具体的な進め方の提案」(『文部科学教育通信』誌,386号,pp.24-25)
[2016.04.26]ホーム「お知らせ」欄を変更
- 連載企画記事(『文部科学教育通信』誌の「大学IRの今」)の掲載号・ページを追記
[2016.04.26]IRなどについての文献メモ 文献一覧を更新<IR>
- 橋本智也(2016).学内データの利用について同意を得る:具体的な進め方の提案 文部科学教育通信,386,24-25.
[2016.04.18]IRなどについての文献メモ 文献一覧を更新<学び>
[2016.04.14]IRなどについての文献メモ 文献一覧を更新<テキストマイニング>
- 小林祐司・寺田充伸・佐藤誠治(2012).テキストマイニングを活用したアンケートにおける自由回答の分析と生活環境評価 日本建築学会計画系論文集,77(671),85-93.[PDF](Google Scholar「テキストマイニング アンケート」で知る)
- 磯島昭代(2006).テキストマイニングを用いた米に関する消費者アンケートの解析 農業情報研究,15(1),49-60.[PDF](Google Scholar「テキストマイニング アンケート」で知る)
- 相川勇之・伊藤山彦・高山泰博・鈴木克志・今村誠(2003).概念抽出型テキストマイニングによるアンケート分析手法の提案 情報処理学会研究報告デジタルドキュメント(DD),2003(37(2002-DD-038)),1-6.[PDF](Google Scholar「テキストマイニング アンケート」で知る)
- 林田英雄・脇森浩志(2005).テキストマイニング技術とその応用 Unisys技報,24(4),401-441.[PDF](Google Scholar「テキストマイニング アンケート」で知る)
- 森田哲夫・入澤覚・長塩彩夏・野村和広・塚田伸也・大塚裕子・杉田浩(2012).自由記述データを用いたテキストマイニングによる都市のイメージ分析 土木学会論文集D3(土木計画学),68(5),I_315-I_323[PDF](Google Scholar「テキストマイニング アンケート」で知る)
- 武市祥司・ライニアソンリー・松石正克(2011).データマイニング手法を用いた学習到達度自己評価のアンケート分析 工学教育59(4),9-14.[PDF](Google Scholar「テキストマイニング アンケート」で知る)
- 石田基広(2012).社会調査における計量テキスト分析の手順と実際:アンケートの自由回答を中心に 石田基広・金明哲(編著) コーパスとテキストマイニング pp.119-128.(Google Scholar「テキストマイニング アンケート」で知る)
- 磯島昭代(2010).テキストマイニングによる農産物に対する消費者ニーズの把握 フードシステム研究,16(4),38-42.[PDF](Google Scholar「テキストマイニング アンケート」で知る)
- 永野峻祐・小根山裕之・大口敬・鹿田成則(2012).形態素解析を用いたアンケート調査自由記述欄の分析手法に関する研究:路面電車利用意識調査データを用いたケーススタディー 土木学会論文集D3(土木計画学),68(5),I_973-I_981.[PDF](Google Scholar「テキストマイニング アンケート」で知る)
- 竹内広宜,杉山喜昭,太田千景,山口高平(2010).マーケティングミックスとテキストマイニングを用いた市場分析支援 人工知能学会全国大会論文集,24,1-4.(Google Scholar「テキストマイニング アンケート」で知る)
- 中村陽人(2008).サービス品質の次元:テキストマイニングによる自由記述アンケートの定性分析 横浜国際社会科学研究,13(1・2),43-57.[PDF](Google Scholar「テキストマイニング アンケート」で知る)
- 坂井慎吾・直野公美・藤井美知子・古賀掲維・丹羽量久(2008).テキストマイニングによる授業開始時および授業中アンケートの分析 教育システム情報学会研究報告,22(6),23-28.(Google Scholar「テキストマイニング アンケート」で知る)
- 松河秀哉・齊藤貴浩(2011).データ・テキストマイニングを活用した授業評価アンケートフィードバックシステムの開発と評価 日本教育工学会論文誌,35(3),217-226.[PDF]Google Scholar「テキストマイニング アンケート」で知る)
- 佐々木邦明・丸石浩一(2011).テキストマイニングを用いたワークショップの討議内容の特徴把握と可視化に関する研究 都市計画論文集,46(3),1039-1044.[PDF](Google Scholar「テキストマイニング アンケート」で知る)
- 中島誠・長濱文与・中山留美子(2013).授業評価へのフィードバックを授業時間中に実施する効果 大学教育研究:三重大学授業研究交流誌,21,63-68.[PDF](Google Scholar「テキストマイニング アンケート」で知る)
- 釜賀誠一(2015).テキストマイニングを用いた授業評価の自由記述の分析と対策 尚絅大学研究紀要.A,人文・社会科学編,47,49-61.[PDF](Google Scholar>の引用元機能(「テキストマイニングを活用したアンケートにおける自由回答の分析と生活環境評価」)で知る)
[2016.04.12]IRなどについての文献メモ 文献一覧を更新<テキストマイニング、R>
- 石田基広(2008).Rによるテキストマイニング入門 森北出版(Amazon.co.jp「テキストマイニング」で知る)
- 石田基広・小林雄一郎(2013).Rで学ぶ日本語テキストマイニング ひつじ書房(Amazon.co.jp「テキストマイニング」で知る)
[2016.04.11]IRなどについての文献メモ 内容をアップ
- 嶌田敏行・藤原宏司・小湊卓夫(2016).日米における中規模大学のIR活動に関する事例研究 名古屋高等教育研究,16,287-304.[PDF][概要](Google Scholarアラート「インスティテューショナル・リサーチ」で知る)
[2016.04.11]IRなどについての文献メモ 文献一覧を更新<IR>
- 嶌田敏行・藤原宏司・小湊卓夫(2016).日米における中規模大学のIR活動に関する事例研究 名古屋高等教育研究,16,287-304.[PDF](Google Scholarアラート「インスティテューショナル・リサーチ」で知る)
[2016.04.11]「私立大学職員によるIR文献メモ」メルマガ バックナンバーを更新
[2016.04.02]「過去の「お知らせ」」に追加
- 平成27年度科学研究費助成事業(科学研究費補助金)(奨励研究)を掲載(期間終了)
- 大学行政管理学会2015年度若手研究奨励を掲載(期間終了)
[2016.03.30]IRなどについての文献メモ 文献一覧を更新<会議>
- 寺沢俊哉(2010).感動の会議!:リーダーが会議で「人を動かす」技術 ディスカヴァー・トゥエンティワン(Amazon.co.jpレコメンド機能で知る)
[2016.03.30]IRなどについての文献メモ 文献一覧を更新<アイデア、着想>
- 山口高弘(2015).アイデア・メーカー:今までにない発想を生み出しビジネスモデルを設計する教科書&問題集 東洋経済新報社(Amazon.co.jpレコメンド機能で知る)
- 三谷宏治(2015).発想力の全技法 PHP研究所(Amazon.co.jpレコメンド機能で知る)
- 三谷宏治(2015).シゴトの流れを整える PHP研究所(Amazon.co.jpレコメンド機能で知る)
[2016.03.30]IRなどについての文献メモ 文献一覧を更新<PDCA>
- 稲田将人(2016).PDCAプロフェッショナル:トヨタの現場×マッキンゼーの企画=最強の実践力 東洋経済新報社(Amazon.co.jp「PDCA」で知る)
[2016.03.30]IRなどについての文献メモ 文献一覧を更新<プランニング、事業計画>
- 佐藤尚之(2015).明日のプランニング:伝わらない時代の「伝わる」方法 講談社(Amazon.co.jp「プランニング」で知る)
- ウェイド,W. 野村恭彦(監訳)・関美和(訳)(2013).シナリオ・プランニング:未来を描き、創造する 英治出版(Amazon.co.jp「プランニング」で知る)
- シルバースタイン,D.,サミュエル,P.,デカーロ,N.野村恭彦(監訳)・関美和(訳)(2015).発想を事業化するイノベーション・ツールキット:機会の特定から実現性の証明まで 英治出版(Amazon.co.jp「プランニング」で知る)
- オスターワルダー,A.,ピニュール,Y.小山龍介(訳)(2012).ビジネスモデル・ジェネレーション:ビジネスモデル設計書:ビジョナリー、イノベーターと挑戦者のためのハンドブック 翔泳社(Amazon.co.jp「プランニング」で知る)
[2016.03.30]IRなどについての文献メモ 文献一覧を更新<数学>
- 安野光雅(1982).はじめてであうすうがくの絵本(1) 福音館書店
- 森毅・竹内啓(1973).数学の世界:それは現代人に何を意味するか 中央公論社(安野光雅(1982)『はじめてであうすうがくの絵本(1)』で知る)
- 遠山啓(1972).数学の学び方・教え方 岩波書店(安野光雅(1982)『はじめてであうすうがくの絵本(1)』で知る)
- 大栗博司(2015).数学の言葉で世界を見たら:父から娘に贈る数学 幻冬舎(Amazon.co.jpレコメンド機能で知る)
- 野崎昭弘(2008).離散数学「数え上げ理論」:「おみやげの配り方」から「Nクイーン問題」まで 講談社(Amazon.co.jpレコメンド機能で知る)
- 遠山啓(1980).無限と連続 岩波書店(Amazon.co.jpレコメンド機能で知る)
[2016.03.30]IRなどについての文献メモ 文献一覧を更新<ベンチマーク、競合分析>
- Levy, G. D., & Valcik, N. A.(Eds.) (2012). Benchmarking in institutional research. New directions for institutional research, 156.(Amazon.co.jp「ベンチマーク」で知る)
- 高梨智弘(2006).ベンチマーキング入門:ベストプラクティスの追求とナレッジマネジメントの実現 生産性出版(Amazon.co.jp「ベンチマーク」で知る)
- ワトソン,G.H.日本能率協会コンサルティング(監訳)(1994).ベンチマーキング入門:業績向上の新手法 日本能率協会マネジメントセンター(CiNii Books「ベンチマーキング入門」で知る)
- キャンプ,R.C.高梨智弘(監訳)(1996).ビジネス・プロセス・ベンチマーキング:ベスト・プラクティスの導入と実践 生産性出版(Amazon.co.jp「ベンチマーク」で知る)
- 高橋透(2015).勝ち抜く戦略実践のための 競合分析手法 中央経済社(Amazon.co.jp「ベンチマーク」で知る)
[2016.03.30]IRなどについての文献メモ 文献一覧を更新<初年次教育>
- Padgett, R. D.(Ed.) (2014). Emerging research and practices on first-year students. New directions for institutional research, 160.(Amazon.co.jpレコメンド機能で知る)
[2016.03.30]IRなどについての文献メモ 文献一覧を更新<データ分析>
- ダベンポート,T.H.&ハリス,J.G.村井章子(訳)(2008).分析力を武器とする企業:強さを支える新しい戦略の科学 日経BP社(Amazon.co.jpレコメンド機能で知る)
- ダベンポート,T.H.,ハリス,J.G.,&ロバート,M.村井章子(訳)(2008).分析力を駆使する企業:発展の五段階:分析で答を出す六つの問題 日経BP社(Amazon.co.jpレコメンド機能で知る)
- アナリティクスアソシエーション(2015).新しいアナリティクスの教科書:データと経営を結び付けるWeb解析の進化したステージ インプレス(Amazon.co.jpレコメンド機能で知る)
- 横内大介・青木義充(2014).現場ですぐ使える時系列データ分析:データサイエンティストのための基礎知識 技術評論社(Amazon.co.jpレコメンド機能で知る)
- 高橋威知郎(著)・日経ビッグデータ(編)(2015).ロジカルデータ分析:スピーディーに収益につなげる新手法 日経BP社(Amazon.co.jpレコメンド機能で知る)
- 高橋威知郎(2014).14のフレームワークで考えるデータ分析の教科書 かんき出版(Amazon.co.jpレコメンド機能で知る)
- Ray, J. M.(Ed.) (2014). Research data management: Practical strategies for information professionals. West Lafayette, Ind.: Purdue University Press.(Amazon.co.jpレコメンド機能で知る)
- Xu, Y. J.(Ed.) (2012). Refining the focus on faculty diversity in postsecondary institutions. New directions for institutional research, 155.(Amazon.co.jpレコメンド機能で知る)
- Griffin, K. A., & Museus, S. D.(Eds.) (2011). Using mixed methods to study intersectionality in higher education. New directions for institutional research, 151.(Amazon.co.jpレコメンド機能で知る)
- Kennedy-Phillips, L. C., Baldasare, A., & Christakis, M. N. (Eds.) (2015). Measuring cocurricular learning: the role of the IR office. New directions for institutional research, 164.(Amazon.co.jpレコメンド機能で知る)
- Calderone, A., & Webber, K. L.(Eds.) (2013). Global issues in institutional research. New directions for institutional research, 157.(Amazon.co.jpレコメンド機能で知る)
- Mullin, C. M., Bers, T., & Hagedorn, L. S.(Eds.) (2012). Data use in the community college. New directions for institutional research, 153.(Amazon.co.jpレコメンド機能で知る)
- Hu, S., & Li, S.(Eds.) (2012). Using typological approaches to understand college student experiences and outcomes. New directions for institutional research, assessment suppl. 2011.(Amazon.co.jpレコメンド機能で知る)
- Power, K., & Henderson, A. E.(Eds.) (2016). Burden or benefit: External data reporting. New directions for institutional research, 166.(Amazon.co.jpレコメンド機能で知る)
- Harper, S. R., & Museus, S. D.(Eds.) (2008). Using qualitative methods in institutional assessment. New directions for institutional research, 136.(Amazon.co.jpレコメンド機能で知る)
[2016.03.30]IRなどについての文献メモ 文献一覧を更新<中途退学、リテンション>
- Peltier, G. L., Laden, R., & Matranga, M. (2000). Student persistence in college: A review of research. Journal of college student retention: Research, theory & practice, 1(4), 357-375.(Google Scholar「review dropout|retention university|college」で知る)
- Trowler, V. (2010). Student engagement literature review. The higher education academy, 11, 1-15.[PDF](Google Scholarの引用元機能(「Student persistence in college: A review of research」)で知る)
- Reason, R. D. (2003). Student variables that predict retention: Recent research and new developments. Naspa journal, 40(4), 172-191.(Google Scholarの引用元機能(「Student persistence in college: A review of research」)で知る)
[2016.03.30]IRなどについての文献メモ 文献一覧を更新<ファクトブック>
- 関隆宏・今井博英・小田美奈子(2016).「新潟大学ファクトブック2015」の作成について,大学評価とIR,5,44-52.[PDF](大学評価コンソーシアムからの案内で知る)
[2016.03.30]ホーム「お知らせ」欄を変更
- ポスター発表"A data-driven approach to dropout prevention in Japan"(2016 AIR Forum)の日時を掲載
[2016.03.30]IRなどについての文献メモ 文献一覧を更新<授業アンケート>
- 荒木俊博(2016).履修者人数と授業アンケート結果の関連についての検討 大学評価とIR,5,36-43.[PDF](大学評価コンソーシアムからの案内で知る)
[2016.03.26]ホーム「お知らせ」欄を変更
- 連載企画記事(『文部科学教育通信』誌の「大学IRの今」)のタイトルを掲載
[2016.03.19]「過去の「お知らせ」」、「IRなどについての文献メモ」、「これまでの発表・競争的研究資金など」に追加
- 話題提供「教育改善に向けてデータをどのように共有できるのか」(第22回大学教育研究フォーラム<参加者企画セッション>)
- 口頭発表「データに基づく大学生の中途退学防止策:日米の制度差に着目して」(第22回大学教育研究フォーラム<個人研究発表>)
[2016.03.15]IRなどについての文献メモ 文献一覧を更新<中途退学、リテンション>
- 竹橋洋毅・藤田敦・杉本雅彦・藤本昌樹・近藤俊明(2016).退学者予測におけるGPAと欠席率の貢献度 大学評価とIR,5,28-35.[PDF](大学評価コンソーシアムからの案内で知る)
[2016.03.14]IRなどについての文献メモ 文献一覧を更新<アクティブラーニング>
- 大山牧子・田口真奈(2013). 大学におけるグループ学習の類型化:アクティブ・ラーニング型授業のコースデザインへの示唆 日本教育工学会論文誌,37(2),129-143.[PDF](グループ学習をデザインするための手がかりとなる枠組みを提示する、グループ学習の類型とプロセス分析を行う、実践事例を「事前作業の有無」と「事後作業の在り方」に着目して整理した⇒6類型:「(A)交流型」「(B)意見獲得型」「(C)課題解決型」「(D)主張交換型」「(E)理解深化型」「(F)集約型」、CとFで授業観察を行い学習プロセスを分析した⇒事前作業の有無は学生の既有知識と関連、事後作業の在り方はコースの学習能力目標の設定と関連;はてなブックマークで知る)
[2016.03.13]「過去の「お知らせ」」、「IRなどについての文献メモ」、「これまでの発表・競争的研究資金など」に追加
- ポスター発表「大学生の学習時間についての文献レビュー:量的側面を中心に」(大学教育改革フォーラムin東海2016)
[2016.03.13]IRなどについての文献メモ 文献一覧を更新<アクティブラーニング>
[2016.03.10]IRなどについての文献メモ 内容をアップ
- 大桑良彰(2000).宮崎医科大学における入試の追跡調査:入試成績と学内成績の関係 医学教育,31(3),181-193.[PDF][概要](CiNii Articles「退学」で知る)
[2016.03.10]IRなどについての文献メモ 文献一覧を更新<統計、入試、成績>
- 高木広文(1984).ナースのための統計学:データのとり方・生かし方 医学書院(入試成績と入学後の学内成績にあまり相関がないのは「打ち切りデータ」のため(仮に受験者全員が入学していれば正の相関が期待されるが、実際には合格点以上の入学者だけを対象にして相関を調べることになる);大桑良彰(2000)「宮崎医科大学における入試の追跡調査」で知る)
- 高木廣文(2009).ナースのための統計学 第2版 医学書院(CiNii Books「ナースのための統計学」で知る)
- 香川靖雄・青野修・横山英明・中野康平・高久史麿(1982).自治医科大学における入学試験より医師国家試験に至る学業成績の追跡調査 医学教育,13(1),55-63.[PDF](入試成績と入学後の学内成績にあまり相関がないのは「打ち切りデータ」のため(仮に受験者全員が入学していれば正の相関が期待されるが、実際には合格点以上の入学者だけを対象にして相関を調べることになる);大桑良彰(2000)「宮崎医科大学における入試の追跡調査」で知る)
- 金関毅(1989).共通1次発足より10年を経て:佐賀医科大学(推薦入学を含めて) 医学教育,20(2),87-90.[PDF](センター試験(以前の共通一次も含む)の合計点と入学後の学内成績に相関がなかったと報告;大桑良彰(2000)「宮崎医科大学における入試の追跡調査」で知る)
- 鈴木庄亮・青木繁伸・小川正行(1988).医学部入学者の、高校・医進・専門・国家試験における成績間の相互関連:とくに非順調進級者の予測可能性について 医学教育,19(1),33-40.[PDF](センター試験(以前の共通一次も含む)の合計点と入学後の学内成績に相関がなかったと報告;大桑良彰(2000)「宮崎医科大学における入試の追跡調査」で知る)
- 香川靖雄(1993).選抜方法改善の実施経験を踏まえて:学科試験 医学教育,24(2),73-76.[PDF](センター試験(以前の共通一次も含む)の合計点と入学後の学内成績に相関がなかったと報告、ただし入試方法が悪いのではなく合格者の入試データの分布が輪切りになって狭いためと指摘;大桑良彰(2000)「宮崎医科大学における入試の追跡調査」で知る)
- 橋本信也・桜井勇・堀原一・中川米造・尾島昭次・佐藤重房・高垣東一郎・牛場大蔵(1990).第8回入学者選抜に関する討議会報告 医学教育,21(4),275-282.[PDF](面接試験の入試区分は入学後の学内成績がよいと報告;大桑良彰(2000)「宮崎医科大学における入試の追跡調査」で知る)
- 原田規章・中本稔(1997).医学部における入学者選抜方法と入学後の経過について 山口大学における追跡調査から(2) 入学後の経過に及ぼす要因の多変量解析 医学教育,28(2),77-83.[PDF](入試選抜方法の改善に資することを目的として入学後の成績を追跡調査;CiNii Articles「退学」で知る)(面接試験の入試区分は入学後の学内成績がよいと報告;大桑良彰(2000)「宮崎医科大学における入試の追跡調査」で知る)
- 原田規章・中本稔(1997).医学部における入学者選抜方法と入学後の経過について 山口大学における追跡調査から(3) 留年・退学、国試合否に対する面接評価の意義 医学教育,28(3),167-171.[PDF](入試選抜方法の改善に資することを目的として入学後の成績を追跡調査;CiNii Articles「退学」で知る)(面接試験の入試区分は入学後の学内成績がよいと報告;大桑良彰(2000)「宮崎医科大学における入試の追跡調査」で知る)
[2016.03.09]IRなどについての文献メモ 内容をアップ
- 鎌田浩史・井上雄介(2016).教育達成モデルに基づく退学行動の研究:ディシジョンツリー分析による検討 大学評価とIR,5,23-27.[PDF][概要](大学評価コンソーシアムからの案内で知る)
[2016.03.09]IRなどについての文献メモ 文献一覧を更新<中途退学、リテンション>
- 鎌田浩史・井上雄介(2016).教育達成モデルに基づく退学行動の研究:ディシジョンツリー分析による検討,大学評価とIR,5,23-27.[PDF](大学評価コンソーシアムからの案内で知る)
[2016.03.09]IRなどについての文献メモ 内容をアップ
- 谷川恵美子・村由美子・萩中正二(2007).わが校における中途退学者の早期発見と学生指導について 日本歯科技工学会雑誌,28(1),83-85.[概要](CiNii Articles「退学」で知る)
- 原清治(2012).「つながり」の関係づくりを中心に置いた中途退学者ゼロを目指す取り組み 私学経営,450,18-29.[概要](CiNii Articles「退学」で知る)
- 原清治(2011).「縁(えにし)」コミュニティによる離脱者ゼロ計画 大学マネジメント,7(8),18-23.[概要](CiNii Articles「退学」で知る)
- 藤田長太郎(2011).メンタルヘルスケアによる中途退学防止:不登校がちな学生へのアウトリーチ型支援を実施して 大学マネジメント,7(8),13-17.[概要](CiNii Articles「退学防止」で知る)(CiNii Articles「退学」で知る)
- 松原達哉(1980).就学不適応学生の原因とその対応について:留年・退学問題の立場から 厚生補導,164,17-27.[概要](CiNii Articles「退学」で知る)
- 野辺地正之(1977).意欲減退学生の背景と対策 厚生補導,131,15-24.[概要](CiNii Articles「退学」で知る)
[2016.03.08]IRなどについての文献メモ 内容をアップ
- 谷村英洋(2010).大学の教員が想定している授業外学習の時間 大学教育学会誌,32(2),87-94.[概要](CiNii Articles「谷村英洋」で知る)
[2016.03.08]IRなどについての文献メモ 文献一覧を更新<学修時間、学習時間>
- 溝上慎一(研究代表者)(2009).単位制度の実質化を目指すカリキュラム評価方法の開発(科学研究費補助金研究成果報告書)[PDF](授業を通じた知識・技能の習得度合いが授業外学習時間によって左右されている;谷村(2010)「大学の教員が想定している授業外学習の時間」で知る)
- 鈴木鯛功・安岡高志(2007).単位修得に必要な学修時間についての調査:授業外学修時間を中心として 大学教育学会誌,29(2),159-164.(CiNii Articles「単位制度」で知る)(授業外学習時間を積極的に伸ばしていくための手段・要因についての分析、課題の量が学習時間を規定している;谷村(2010)「大学の教員が想定している授業外学習の時間」で知る)
- 金子元久・浦田広朗・大多田直樹・両角亜紀子(2008).大学生の学習参加の構造 日本高等教育学会第11回大会発表要旨集録,76-79.(学生参加型・双方向型の授業実践が授業外学習に対して正の効果を有すると指摘;谷村(2010)「大学の教員が想定している授業外学習の時間」で知る)
- 平尾智隆(2009).学習時間を決定する要因
- 谷村英洋(2009).大学生の学習時間分析:授業と学習時間の関連性 大学教育学会誌,31(1),128-135.(CiNii Articles「学習時間」で知る)(藤村(2013)「大規模学生調査から学習成果と学習時間の構造を掴む」で知る)(授業外学習時間を積極的に伸ばしていくための手段・要因についての分析;谷村(2010)「大学の教員が想定している授業外学習の時間」で知る)
- 蒋妍(2010).授業外学習を促す授業実践の研究 大学教育学会誌,32(1),134-140.(授業で出される課題が大学生の授業外学修時間に与える影響を検討、教員が課題を出すことは大学生の授業外学修時間を促す可能性、ビデオ観察・インビュー調査を用いた;畑野(2014)「大学生の主体的な学修態度の形成に関する実証的研究」で知る)(授業外学習時間を積極的に伸ばしていくための手段・要因についての分析;谷村(2010)「大学の教員が想定している授業外学習の時間」で知る)
- 両角亜希子(2010).大学生の学習行動の大学間比較:授業の効果に着目して 東京大学大学院教育学研究科紀要,49,191-206.[PDF](社会科学系6大学と工学系6大学の能動的学習や授業外学習時間を比較分析;藤村(2013)「大規模学生調査から学習成果と学習時間の構造を掴む」で知る)(授業外学習時間を積極的に伸ばしていくための手段・要因についての分析;谷村(2010)「大学の教員が想定している授業外学習の時間」で知る)
- 広島大学高等教育研究開発センター(編)(2004).FDの制度化に関する研究(2):2003年大学教員調査報告[大学教育改善の全国調査(教員篇)] 広島大学高等教育研究開発センター[PDF](一般教員を対象にして生活・勤務実態・意識・行動について調査、教員の授業実践・授業改善に注目している;谷村(2010)「大学の教員が想定している授業外学習の時間」で知る)
- 米澤彰純・佐藤香(編)(2008).大学教員のキャリア・ライフスタイルと都市・地域:「大学教員の生活実態に関する調査」から 広島大学高等教育研究開発センター[PDF](一般教員を対象にして生活・勤務実態・意識・行動について調査、谷村(2010)「大学の教員が想定している授業外学習の時間」で知る)
- 清水亮・橋本勝・松本美奈(編著)(2009).学生と変える大学教育:FDを楽しむという発想 ナカニシヤ出版(鮫島輝美先生(京都光華女子大学)からの紹介で知る)(大規模授業で学生参加型・双方向型授業を行う工夫を報告;谷村(2010)「大学の教員が想定している授業外学習の時間」で知る)
- 杉江修治・関田一彦・安永悟・三宅なほみ(2004).大学授業を活性化する方法 玉川大学出版部(大学教育での協調学習事例;鈴木(編著)(2009).『学びあいが生みだす書く力:大学におけるレポートライティング教育の試み』で知る)(大規模授業で学生参加型・双方向型授業を行う工夫を報告;谷村(2010)「大学の教員が想定している授業外学習の時間」で知る)
- 小笠原正明・西森敏之・瀬名波栄潤(編)(2006).TA (ティーチングアシスタント) 実践ガイドブック 玉川大学出版部(TAの数が増加する一方でトレーニングの制度化は進んでいない;谷村(2010)「大学の教員が想定している授業外学習の時間」で知る)
- 有本章(編著)(2008).変貌する日本の大学教授職 玉川大学出版部(90年代前半からの15年間で大学教員の担当授業科目数が増加、1科目に配分できる時間は減少傾向にある;谷村(2010)「大学の教員が想定している授業外学習の時間」で知る)
[2016.03.07]「私立大学職員によるIR文献メモ」メルマガ バックナンバーを更新
[2016.03.06]「過去の「お知らせ」」、「IRなどについての文献メモ」、「これまでの発表・競争的研究資金など」に追加
- ポスター発表「学科内での授業改善策の議論を促す仕組み作り:「授業アンケート結果に対する担当教員のコメント」の活用」(第21回FDフォーラム)
[2016.03.05]IRなどについての文献メモ 文献一覧を更新<IR>
- 佐賀大学インスティテューショナル・リサーチ室(編)(2015).大学マネジメントとIR:最適なKPIの設定を目指して 昭和堂
[2016.03.04]IRなどについての文献メモ 文献一覧を更新<学修時間、学習時間>
- 葛城浩一(2013).学修時間の確保は教育成果の獲得にどのような影響を与えるか:授業外学修時間と教育成果の獲得との関連性に着目して 大学教育学会誌,35(2),104-111.(葛城浩一(2014)「学修時間の増加・確保に意欲的な大学はどのような大学か」で知る)
[2016.03.04]IRなどについての文献メモ 内容をアップ
- 金子元久(2013).大学教育の再構築:学生を成長させる大学へ 玉川大学出版部(東京大学大学院教育学研究科総合教育科学専攻大学経営・政策コース「2015年度シラバス」で知る)(日本の学生の平均的学修時間は1日にほぼ4時間程度(授業時間が2.8時間、卒業論文が0.5時間、自主的な学修が0.9時間、残りはサークル活動やアルバイトなど);清水一彦(2014)「単位制度の再構築」で知る)
[2016.03.04]IRなどについての文献メモ 文献一覧を更新<研究力>
- 佐藤翔・上田真緒・木原絢・成宮詩織・林さやか・森田眞実(2016).日本の学協会誌掲載論文のオンライン入手環境 情報管理,12,908-918.[PDF]
[2016.03.04]IRなどについての文献メモ 内容をアップ
- 畑野快(2014).大学生の主体的な学修態度の形成に関する実証的研究 京都大学博士論文[PDF][概要](CiNii Articles「谷村英洋」で知る)
[2016.03.02]IRなどについての文献メモ 内容をアップ
- 細谷功(2014).具体と抽象:世界が変わって見える知性のしくみ dZERO(具体と抽象の関係は「N:1」、具体レベルと抽象レベルを階層化させて「つながった目標」にする、具体的な目標設定は5W1Hが表現されているので達成したかを判定することができる、抽象化するときは共通点を探す、抽象化と具体化はセットで機能する(それぞれに長所・短所がある);Amazon.co.jpレコメンド機能で知る)
[2016.03.01]IRなどについての文献メモ 文献一覧を更新<研究力>
- 阪彩香・伊神正貫(2015).研究論文に着目した日本の大学ベンチマーキング2015:大学の個性活かし、国全体としての水準を向上させるために 科学技術・学術政策研究所[PDF][論文ベンチマーキング調査専用ページ](はてなブックマークで知る)
[2016.02.29]IRなどについての文献メモ 文献一覧を更新<IR>
[2016.02.25]IRなどについての文献メモ 文献一覧を更新<資料作成、プレゼン>
[2016.02.24]ホーム「お知らせ」欄を変更
- ポスター発表「大学生の学習時間についての文献レビュー:量的側面を中心に」(大学教育改革フォーラムin東海2016)を掲載
[2016.02.24]「過去の「お知らせ」」、「IRなどについての文献メモ」、「これまでの発表・競争的研究資金など」に追加
- 口頭発表「日本におけるIRオフィス立ち上げ期の関心事:15大学・団体から訪問調査を受けた際の照会事項から見えること」(平成27年度第4回IR実務担当者連絡会)
[2016.02.24]IRなどについての文献メモ 文献一覧を更新<KPI>
[2016.02.24]IRなどについての文献メモ 文献一覧を更新<モデル>
- 近藤次郎(1976).数学モデル:現象の数式化 丸善
- Russell, S., & Norvig, P.古川康一(訳)(2008).エージェントアプローチ:人工知能 第2版 共立出版
[2016.02.24]IRなどについての文献メモ 文献一覧を更新<統計、数学>
- ポリア,P.柿内賢信(訳)(1975).いかにして問題をとくか 第11版 丸善(Amazon.co.jpレコメンド機能で知る)
- 竹内薫(2014).数学×思考=ざっくりと:いかにして問題をとくか 丸善出版(Amazon.co.jpレコメンド機能で知る)
- 神永正博(2014).直感を裏切る数学:「思い込み」にだまされない数学的思考法 講談社(Amazon.co.jpレコメンド機能で知る)
- 神永正博(2011).ウソを見破る統計学:退屈させない統計入門 講談社(Amazon.co.jpレコメンド機能で知る)
- 西成活裕(2014).とんでもなく役に立つ数学 KADOKAWA(Amazon.co.jpレコメンド機能で知る)
[2016.02.22]IRなどについての文献メモ 文献一覧を更新<統計>
[2016.02.20]IRなどについての文献メモ 文献一覧を更新<統計>
[2016.02.20]「過去の「お知らせ」」、「IRなどについての文献メモ」、「これまでの発表・競争的研究資金など」に追加
- セミナー講師「中途退学防止の知見を共有・蓄積する:米国の研究の発展期から得られる示唆」(ERMS研究会公開セミナーvol.2「エンロールメントとリテンションマネジメントのためのIR」)
[2016.02.17]IRなどについての文献メモ 文献一覧を更新<中途退学、リテンション>
- Kamens, D. H. (1971). The college "charter" and college size: Effects on occupational choice and college attrition. Sociology of education, 44(3), 270-296.(Berger et al.(2012)"Past to present: A histrical look at retention"で知る)
[2016.02.17]IRなどについての文献メモ 文献一覧を更新<品質管理>
- 宮村鐵夫(2011).プロセスの考え方によるマネジメント 新製品・技術の開発と信頼性工学:信頼性のコンセプトによるマネジメントの進め方 日科技連出版社 pp.117-157.(中央大学シラバス検索「品質管理 経」で知る)
[2016.02.15]IRなどについての文献メモ 文献一覧を更新<IR>
- 小湊卓夫・嶌田敏行(2016).IR その着実な一歩のために:最終回 IRオフィスのスタートアップに必要なこと Between,266,31-33.[PDF](IRオフィス設立に向けたチェックリストの掲載あり;Twitter(@23kugaさん)で知る)
[2016.02.15]IRなどについての文献メモ 文献一覧を更新<R(統計)>
- Wickham, H.石田基広・市川太祐・高柳慎一・福島真太朗(訳)(2016).R言語徹底解説 共立出版[目次](Twitter(@stattanさん)で知る)(「R言語徹底解説」入門(nakamichiさん)で知る)(『R言語徹底解説』(共立出版)をいただきました!(bicycle1885さん)で知る)
- 村井潤一郎(2013).はじめてのR:ごく初歩の操作から統計解析の導入まで 北大路書房(Amazon.co.jpレコメンド機能で知る)
- 山田剛史・杉澤武俊・村井潤一郎(2008).Rによるやさしい統計学 オーム社(Amazon.co.jpレコメンド機能で知る)
- 金明哲(2007).Rによるデータサイエンス:データ解析の基礎から最新手法まで 森北出版[HTML](Amazon.co.jpレコメンド機能で知る)
- Lander, J. P.高柳慎一・牧山幸史・簑田高志(訳)(2015).みんなのR:データ分析と統計解析の新しい教科書 マイナビ(Amazon.co.jpレコメンド機能で知る)
- 養成読本編集部(編)(2014).データサイエンティスト養成読本:R活用編 技術評論社(Amazon.co.jpレコメンド機能で知る)
- Chang, W.石井弓美子・河内崇・瀬戸山雅人・古畠敦(訳)(2013).Rグラフィックスクックブック:ggplot2によるグラフ作成のレシピ集 オライリー・ジャパン(Amazon.co.jpレコメンド機能で知る)
- 舟尾暢男(2009).The R Tips:データ解析環境Rの基本技・グラフィックス活用集 第2版 オーム社(Amazon.co.jpレコメンド機能で知る)
[2016.02.12]IRなどについての文献メモ 文献一覧を更新<品質管理>
[2016.02.10]IRなどについての文献メモ 文献一覧を更新<中途退学、リテンション>
- Knoell, D. M. (1966). A critical review of research on the college dropout. In L. A. Pervin, L. E. Reik, & W. Dalrymple (Eds.) The college dropout and the utilization of talent. Princeton, N.J.: Princeton University Press. pp.63-81.(Spady(1970)"Dropouts from higher education: An interdisciplinary review and synthesis"で知る)
[2016.02.09]IRなどについての文献メモ 文献一覧を更新<品質管理>
- 久米均(2005).品質管理 岩波書店(中央大学シラバス検索「品質工学\品質管理 精電応」で知る)
- 石川馨(1989).品質管理入門 第3版 日科技連出版社(中央大学シラバス検索「品質工学\品質管理 精電応」で知る)
- 中条武志・山田秀(編著)日本品質管理学会標準委員会(編)(2006).マネジメントシステムの審査・評価に携わる人のためのTQMの基本 日科技連出版社(中央大学シラバス検索「品質工学\品質管理 精電応」で知る)
- 谷津進・宮川雅巳(1988).品質管理 朝倉書店(中央大学シラバス検索「品質管理 経」で知る)
- 宮村鐵夫(2011).新製品・技術の開発と信頼性工学:信頼性のコンセプトによるマネジメントの進め方 日科技連出版社(中央大学シラバス検索「品質管理 経」で知る)
- 中尾政之(2005).失敗百選:41の原因から未来の失敗を予測する 森北出版株式会社(「品質管理に関する文献」(中村隆昭先生)で知る)
- 中尾政之(2010).続・失敗百選:リコールと事故を防ぐ60のポイント 森北出版株式会社(「品質管理に関する文献」(中村隆昭先生)で知る)
- 中尾政之(2016).続々・失敗百選:「違和感」を拾えば重大事故は防げる:原発事故と“まさか"の失敗学 森北出版株式会社(Amazon.co.jp「失敗百選」で知る)
[2016.02.09]ホーム「お知らせ」欄を変更
- 口頭発表「中途退学防止の知見を共有・蓄積する:米国の研究の発展期から得られる示唆」(ERMS研究会公開セミナーvol.2)を掲載
[2016.02.09]IRなどについての文献メモ 文献一覧を更新<単位制度>
- 三好登(2015).大学生の学習時間・学習意欲と学習成果との関係 大学教育学会誌,37(1),105-113.(CiNii Articles「単位制度」で知る)
- 清水一彦(2015).大学単位制度と能動的学修 教育制度学研究,22,167-172.(CiNii Articles「単位制度」で知る)
- ウルリッヒ,T.・吉川裕美子(訳)(2014).ボローニャ改革がドイツと欧州諸国の大学の学修プログラムに与えた影響:ボローニャ・プロセス10年間の改革努力の総括 大学評価・学位研究,16,1-25.[PDF](CiNii Articles「単位制度」で知る)
- 清水一彦(2014).単位制度の再構築 大学評価研究,13,39-49.[PDF](CiNii Articles「単位制度」で知る)
- 小山内優(2014).アクティブ・ラーニングに関する中央教育審議会答申と学士課程教育及び単位制度に関する課題 学士課程教育機構研究誌,3,51-64.(CiNii Articles「単位制度」で知る)
- 葛城浩一(2014).学修時間の増加・確保に意欲的な大学はどのような大学か 教育総合研究叢書,7,29-42.[PDF](CiNii Articles「単位制度」で知る)
- 田中正弘・森利枝(2014).ボローニャ・プロセスへの対応による新たな学位・単位制度の活用と課題:ドイツ・スイスにおける取組から 21世紀教育フォーラム,9,9-18.[PDF](CiNii Articles「単位制度」で知る)
- 清水一彦(2014).大学単位制度の実質化方策 教育制度学研究,21,97-107.(CiNii Articles「単位制度」で知る)
- 森利枝(2014).米国高等教育における教学マネジメントへの学外統制メカニズム:単位制度の運用を手がかりに 高等教育研究,17,31-44.(CiNii Articles「単位制度」で知る)
- 長尾佳代子・谷川裕稔(2013).高等教育における学習支援についての諸問題:歴史的視点にもとづいた検討 大学教育学会誌,35(2),71-74.(CiNii Articles「単位制度」で知る)
- 早田幸政(2013).「学習成果の測定・評価」と内部質保証:第2期認証評価を担うJUAAの課題と期待 大学評価研究,12,23-36.(CiNii Articles「単位制度」で知る)
- 沖裕貴・井上史子・林泰子(2012).日本の大学におけるルーブリック評価導入の方策と課題:客観的,厳格かつ公正な成績評価を目指して 年会論文集,28,166-169.(CiNii Articles「単位制度」で知る)
- 吉田博・金西計英(2012).学生の授業外学習を促進する授業:2年にわたる授業実践を通して 大学教育研究ジャーナル,9,1-10.[PDF](CiNii Articles「単位制度」で知る)
- 大塚雄作・森利枝・溝上慎一(2011).単位制度から見る教授学習・カリキュラム(<第17回大学教育研究フォーラムシンポジウム>全体討論) 京都大学高等教育研究,17,193-202.[PDF](CiNii Articles「単位制度」で知る)
- 伊藤浩行(2011).単位制度から見る教授学習・カリキュラム(<第17回大学教育研究フォーラムシンポジウム>報告4「工学系数学における新たな授業制度の試み:1週複数回授業、成績更新型履修制度、単元クレジット」) 京都大学高等教育研究,17,173-182.[PDF](CiNii Articles「単位制度」で知る)
- 森本剛(2011).単位制度から見る教授学習・カリキュラム(<第17回大学教育研究フォーラムシンポジウム>報告3「医学教育におけるモジュール制カリキュラムと履修制度」) 京都大学高等教育研究,17,162-172.[PDF](CiNii Articles「単位制度」で知る)
- 溝上慎一(2011).単位制度から見る教授学習・カリキュラム(<第17回大学教育研究フォーラムシンポジウム>報告2「大学生の授業外学習の実態と成長指標としての授業外学習」) 京都大学高等教育研究,17,150-161.[PDF](CiNii Articles「単位制度」で知る)
- 森利枝(2011).単位制度から見る教授学習・カリキュラム(<第17回大学教育研究フォーラムシンポジウム>報告1「単位制度の基盤と今日的課題:時間と成果」) 京都大学高等教育研究,17,140-149.[PDF](CiNii Articles「単位制度」で知る)
- 大塚雄作・松下佳代(2011).単位制度から見る教授学習・カリキュラム(<第17回大学教育研究フォーラムシンポジウム>シンポジウム「単位制度から見る教授学習・カリキュラム」) 京都大学高等教育研究,17,138-139.[PDF](CiNii Articles「単位制度」で知る)
- 中村章二(2011).単位制度の弾力化と質保証:授業運営制度上の課題 大学アドミニストレーション研究,1,67-80.[PDF](CiNii Articles「単位制度」で知る)
- 弓倉整(2010).単位制度と取得方法 日本医師会雑誌,139(6),1227-1230.(CiNii Articles「単位制度」で知る)
- 土持ゲーリー法一(2010).最終講義「大学教育の現状と課題:なぜ『単位制度の実質化』が問われるか」 21世紀教育フォーラム,5,1-10.[PDF](CiNii Articles「単位制度」で知る)
- 植田正暢(2009).福岡女学院大学短期大学部における学習時間増加のための取り組み:単位制度の実質化の視点から リメディアル教育研究,4(2),155-161.[PDF](CiNii Articles「単位制度」で知る)
- 西垣順子・矢部正之(2009).単位制度に関わる施策の導入状況と学生の学習への効果:国内大学質問紙調査報告 大阪市立大学大学教育,7,25-30.(CiNii Articles「単位制度」で知る)
- 溝上慎一・中間玲子・山田剛史(2009).学習タイプ(授業・授業外学習)による知識・技能の獲得差違 大学教育学会誌,31(1),112-119.(CiNii Articles「単位制度」で知る)
- 武村秀雄(2009).学士力向上と質保証のためのFD:単位制度・シラバス・成績評価を中心にして 桜美林シナジー,8,75-91.(CiNii Articles「単位制度」で知る)
- 舘昭(2008).大学教育の質保証のための教育システムづくり:単位制度と成績評価 大阪市立大学大学教育,5(2),65-77.(CiNii Articles「単位制度」で知る)
- 小笠原正明(2008).学士課程におけるカリキュラム開発と単位制度の実質化:北海道大学と東京農工大学における理系教育改革の経験から 大阪市立大学大学教育,5(2),53-64.(CiNii Articles「単位制度」で知る)
- 鈴木鯛功・安岡高志(2007).単位修得に必要な学修時間についての調査:授業外学修時間を中心として 大学教育学会誌,29(2),159-164.(CiNii Articles「単位制度」で知る)
- 舘昭(2006).改めて「大学制度とは何か」を問う(5)そもそも「単位制度」とは 単位は与えられない 与えられるのはクレジット:4年課程なら120単位,2年課程なら60単位を基準に カレッジマネジメント,24(5),30-34.(CiNii Articles「単位制度」で知る)
- 安岡高志(2006).単位制度と授業評価 青山スタンダード論集,1,131-173.[PDF](CiNii Articles「単位制度」で知る)
- 安岡高志(2005).単位制度から見た中央教育審議会答申 大学時報,54(302),94-99.(CiNii Articles「単位制度」で知る)
- 西垣順子(2005).単位制度実質化を実現するための教育システム 信州大学高等教育システムセンター紀要,1,83-92.[PDF](CiNii Articles「単位制度」で知る)
- 廣澤孝之(2004).「単位」制度の運用に関する現状と課題:大学教育における未完の改革を展望して 松山大学論集,16(2),95-114.(CiNii Articles「単位制度」で知る)
- 濱名篤(2001).大学教育学会2000年度課題研究集会シンポジウム(1)単位制度の運用:その効用と展望 大学設置基準改正後に単位制度はどこまで改善されたか 大学教育学会誌,23(2),105-109.(CiNii Articles「単位制度」で知る)
- 舘昭(2001).単位制度運用の前提となる個々の授業の充実とその方策 大学教育学会誌,23(1),10-12.(CiNii Articles「単位制度」で知る)
- 土持法一(2001).新制大学における「単位制度」の導入と展開の過程 大学論集,31,65-80.[PDF](CiNii Articles「単位制度」で知る)
- 仙波克也(2000).清水一彦著, 『日米の大学単位制度の比較史的研究』,風間書房,1998年,582頁 日本教育行政学会年報,26,263-266.[PDF](CiNii Articles「単位制度」で知る)
- 清水一彦(2000).大学単位制度の50年:1単位と124単位の原則規定の変遷 教育制度研究紀要,1,51-68.(CiNii Articles「単位制度」で知る)
- 清水一彦(2000).単位制度とカリキュラム編成 RIHE,60,56-70.[PDF](CiNii Articles「単位制度」で知る)
- 吉川裕美子(1999).ドイツ高等教育における単位制度導入の動向:学位制度と学修課程の検討から 学位研究,11,73-89.(CiNii Articles「単位制度」で知る)
- 小林哲也(1999).学習における学生の自己責任:イギリスの学士教育 大学教育学会誌,21(2),66-70.(CiNii Articles「単位制度」で知る)
- 讃岐和家(1999).単位制度の効果的な運用のための諸方策:上限設定制の導入を中心として 大学教育学会誌,21(1),57-60.(CiNii Articles「単位制度」で知る)
- 舘昭(1999).教育課程、カリキュラム、授業設計の基礎としての単位制度 大学教育学会誌,21(1),53-56.(CiNii Articles「単位制度」で知る)
- 舘昭(1999).清水一彦著『日米の大学単位制度の比較史的研究』 大学論集,29,273-275.(CiNii Articles「単位制度」で知る)
- 土持法一(1999).清水一彦著「日米の大学単位制度の比較史的研究」 比較教育学研究,1999(25),196-197.[PDF](CiNii Articles「単位制度」で知る)
- 渡辺勇一(1998).授業時間外の学習を促す講義法 大学教育研究年報,4,21-24.[PDF](CiNii Articles「単位制度」で知る)
- 斎藤陽一(1998).単位制の有効性をめぐって 大学教育研究年報,4,15.[PDF](CiNii Articles「単位制度」で知る)
- 舘昭(1998).単位制度と大学教育 大学教育研究年報,4,5-14.[PDF](CiNii Articles「単位制度」で知る)
- 清水一彦(1997).大学単位制度の確立の必要性 教育制度学研究,4,126-129.[PDF](CiNii Articles「単位制度」で知る)
- 清水一彦(1994).大学教育改革における単位制度運用の現状と課題 日本教育制度学会紀要,創刊号,115-136.[PDF](CiNii Articles「単位制度」で知る)
- 讃岐和家(1991).日米両国の四年制大学における単位制度の比較に関する研究 国際基督教大学学報.I-A,教育研究,33,1-24.[PDF](CiNii Articles「単位制度」で知る)
- 清水一彦(1990).わが国における大学の単位制度の基準に関する研究:「大学設置基準」(昭和31年)以降 日本教育行政学会年報,16,239-254.[PDF](CiNii Articles「単位制度」で知る)
- 清水一彦(1989).大学における単位制度の現状と課題 日本教育学会大會研究発表要項,48,135.[PDF](CiNii Articles「単位制度」で知る)
- 清水一彦(1989).大学の単位制度の基準に関する研究:「大学基準」(昭22)から「大学設置基準」(昭31)まで 大学研究,5,133-155.(CiNii Articles「単位制度」で知る)
- 広瀬孝文(1982).ヨーロッパ式単位制度による言語教育:言語活動における必要事項の決定 聖徳学園岐阜教育大学紀要,9,1-15.[PDF](CiNii Articles「単位制度」で知る)
- 福村哲夫(1980).単位制度における第2外国語の問題点 日本フランス語フランス文学会中部支部研究報告集,4,17-18.[PDF](CiNii Articles「単位制度」で知る)
- 逸見博昌(1971).単位制度、卒業制度、学位制度の現状と問題 教育と医学,19(9),18-24.(CiNii Articles「単位制度」で知る)
- 松尾恒雄(1966).入館者数と時間割の関係:単位制度の改訂に備えて 薬学図書館,11(4),86-91.[PDF](CiNii Articles「単位制度」で知る)
[2016.02.08]IRなどについての文献メモ 文献一覧を更新<IR>
- 小川勤(2013).インスティテューショナル・リサーチとアウトカム評価に関する研究:カレッジ・インパクト研究に基づく教学改善の新展開 大学教育,10,1-12.[PDF]
[2016.02.08]IRなどについての文献メモ 文献一覧を更新<認証評価>
- 関隆宏(2015).平成26年度大学機関別認証評価から見える新潟大学の課題 新潟大学高等教育研究,3,27-32.[PDF](CiNii Articles「認証評価」で知る)
- 内田智也(2015).国立大学法人岐阜大学における質保証の取組:新たな教育の質保証システム構築に向けて 岐阜大学教育推進・学生支援機構年報,1,104-117.[PDF](CiNii Articles「認証評価」で知る)
- 森雅生・大石哲也・高田英一(2015).大学評価とIR 研究報告教育学習支援情報システム(CLE),2015(3),1-5.[PDF](CiNii Articles「認証評価」で知る)
- 石井幸雄・浜田行弘・菅真城・松岡美佳(2013).大学における文書管理に関する基礎的研究II:問題点・課題の解決手法を中心に レコード・マネジメント:記録管理学会誌,65,109-133.[PDF](CiNii Articles「認証評価」で知る)
- 高森智嗣(2013).認証評価における「教育の成果」の記述内容分析:大学評価・学位授与機構を対象に 福島大学総合教育研究センター紀要,15,93-100.(CiNii Articles「認証評価」で知る)
- 工藤潤・松坂顕範(2013).第2期認証評価における大学評価の実践とその課題 大学評価研究,12,85-94.(CiNii Articles「認証評価」で知る)
- 佐藤東洋士(2013).大学連合組織の立場をふまえ、「大学評価」に関する一考察 大学評価研究,12,77-84.(CiNii Articles「認証評価」で知る)
- 奥野武俊・中田晃(2013).公立大学の特徴と認証評価に関する課題 大学評価研究,12,67-76.(CiNii Articles「認証評価」で知る)
- 宇川彰(2013).国立大学における認証評価:第1サイクルの経験と第2サイクルの課題 大学評価研究,12,59-66.(CiNii Articles「認証評価」で知る)
- 小原一仁(2013).第2期大学認証評価の実践と課題:玉川大学における内部質保証 大学評価研究,12,37-44.(CiNii Articles「認証評価」で知る)
- 早田幸政(2013).「学習成果の測定・評価」と内部質保証:第2期認証評価を担うJUAAの課題と期待 大学評価研究,12,23-36.(CiNii Articles「認証評価」で知る)
- 義本博司(2013).大学行政から見た認証評価の実践上の課題 大学評価研究,12,15-22.(CiNii Articles「認証評価」で知る)
- 金子元久(2013).認証評価の展望 大学評価研究,12,5-13.(CiNii Articles「認証評価」で知る)
- 工藤潤(2013).大学基準協会がめざす認証評価:内部質保証システムが構築するための条件 IDE:現代の高等教育,551,41-45.(CiNii Articles「認証評価」で知る)
- 鈴木賢次郎(2013).進化する大学機関別認証評価:第1サイクルの成果を踏まえて IDE:現代の高等教育,551,37-41.(CiNii Articles「認証評価」で知る)
- 板東久美子(2013).大学の設置認可と認証評価 IDE:現代の高等教育,551,4-11.(CiNii Articles「認証評価」で知る)
- 工藤潤(2012).学士課程教育と学士力の実質化:認証評価からみた現状と課題 大学教育学会誌,34(2),17-22.(CiNii Articles「認証評価」で知る)
- 納谷廣美(2012).自己点検・評価結果の改善・改革に向けた活用:明治大学の事例 現状と課題 大学評価研究,11,9-19.(CiNii Articles「認証評価」で知る)
- 赤井益久(2012).第2ステージを迎えた認証評価と教学経営 國學院大學教育開発推進機構紀要,3,1-22.(CiNii Articles「認証評価」で知る)
- 両角亜希子(2012).関西学院大学 認証評価と大学独自戦略の併存に向けて カレッジマネジメント,30(1),22-25.[PDF](CiNii Articles「認証評価」で知る)
- 川嶋太津夫(2012).進化する日本の認証評価制度 カレッジマネジメント,30(1),6-13.[PDF](CiNii Articles「認証評価」で知る)
- 木田竜太郎(2012).高等教育質保証と日本の課題:大学認証評価「完成年」の実状をめぐって 早稲田大学教育学会紀要,14,121-128.(CiNii Articles「認証評価」で知る)
- 早田幸政(2011).特集 大学の認証評価の課題と展望 内外教育,6110,6-9.(CiNii Articles「認証評価」で知る)
- 秦敬治(2011).日本の国立大学におけるIRの現状と課題に関する考察 大学評価研究,10,29-36.(CiNii Articles「認証評価」で知る)
- 矢田俊文(2011).わが国の大学評価システムの成果と課題 大学評価研究,10,3-7.(CiNii Articles「認証評価」で知る)
- 瀧澤博三(2011).認証評価の新段階 IDE:現代の高等教育,533,35-39.(CiNii Articles「認証評価」で知る)
- 納谷廣美(2011).新時代を迎えて:これからの認証評価制度について IDE:現代の高等教育,533,22-27.(CiNii Articles「認証評価」で知る)
- 早田幸政・齊藤貴浩(2011).学生の学習成果と大学における内部質保証体制の検証に係る認証評価の方向性に関する考察 大阪大学大学教育実践センター紀要,7,19-28.[PDF](CiNii Articles「認証評価」で知る)
- 赤井益久(2011).大学教育の質保証と教学監査 國學院大學教育開発推進機構紀要,2,1-16.(CiNii Articles「認証評価」で知る)
- 青野透(2011).大学を教育改革へと動かす法制度:認証評価・授業研究・障害学生支援 季刊教育法,168,94-99.(CiNii Articles「認証評価」で知る)
- 渋井進・野田文香・田中弥生・野澤庸則(2011).自己評価書と評価結果報告書の関係から見た大学機関別認証評価の分析 大学評価・学位研究,12,117-138.[PDF](CiNii Articles「認証評価」で知る)
- 高倉翔(2011).第二期の認証評価:自己点検・評価の実質化を IDE:現代の高等教育,528,52-56.(CiNii Articles「認証評価」で知る)
- 戸澤幾子(2011).高等教育の評価制度をめぐって:機関別認証評価制度と国立大学法人評価制度を中心に レファレンス,61(1),7-28.(CiNii Articles「認証評価」で知る)
- 奥川義尚(2011).大学教育の質の保証に関する一考察 (その2):2年制大学の認証評価を中心として Problemata mundi,20,1-11.(CiNii Articles「認証評価」で知る)
- 山田勉(2010).大学基準協会 認証評価説明会:「達成度評価と水準評価」 上武大学教育研究センター年報,2(2008),25-32.(CiNii Articles「認証評価」で知る)
- 関隆宏(2010).認証評価から見える国立大学法人における教育成果の検証の現状:平成19・20年度の大学評価・学位授与機構による大学機関別認証評価の自己評価書から 大学評価研究,9,81-90.(CiNii Articles「認証評価」で知る)
- 川崎友嗣(2010).認証評価における評価者の位置、あり方、課題について 大学評価研究,9,73-79.(CiNii Articles「認証評価」で知る)
- 串本剛(2010).質問紙調査から見る認証評価制度と大学教育改革:実績と期待 大学評価研究,9,61-71.(CiNii Articles「認証評価」で知る)
- 関口正司(2010).改善につながる評価をめざして:九州大学における認証評価への取組 大学評価研究,9,51-60.(CiNii Articles「認証評価」で知る)
- 森利枝(2010).米国における高等教育機関・アクレディテーション団体・連邦政府の関係について 大学評価研究,9,41-49.(CiNii Articles「認証評価」で知る)
- 小方直幸(2010).卒業生調査を用いた大学の教育成果の評価 大学評価研究,9,29-39.(CiNii Articles「認証評価」で知る)
- 工藤潤(2010).大学基準協会が実施する新大学評価システム:内部質保証システムの構築の重要性 大学評価研究,9,17-27.(CiNii Articles「認証評価」で知る)
- 生和秀敏(2010).認証評価の新展開 大学評価研究,9,9-16.(CiNii Articles「認証評価」で知る)
- 伊藤昇(2010).私立大学職員の新しい業務像を求めて 第3章 今日的な職員業務:自己点検・評価業務を含む認証評価業務と大学ブランド戦略にかかわる業務 私学経営,427,36-58.(CiNii Articles「認証評価」で知る)
- 高森智嗣(2010).第三者評価に基づく大学の改善に関する研究:認証評価における指摘事項の分析を中心に 大学教育学会誌,32(1),94-99.[PDF](CiNii Articles「認証評価」で知る)
- 齊藤貴浩・望月太郎・早田幸政(2010).教育成果に関する評価指標の大学評価での扱いに関する考察:大学を対象とする認証評価機関への調査を中心として 大阪大学大学教育実践センター紀要,6,9-26.[PDF](CiNii Articles「認証評価」で知る)
- 山田勉(2010).大学認証評価の現状と課題:大学基準協会での3年間の経験から 大学行政研究,5,203-210.[PDF](CiNii Articles「認証評価」で知る)
- 村上孝弘(2010).認証評価と「事務組織」 大学行政管理学会誌,3,125-132.(CiNii Articles「認証評価」で知る)
- 林透(2010).高等教育質保証システムの揺らぎ:認証評価制度導入期を中心に 大学行政管理学会誌,4,93-101.(CiNii Articles「認証評価」で知る)
- 関隆宏(2010).新潟大学における認証評価・法人評価の受審とその後 大学探究,3,15-23.[PDF](CiNii Articles「認証評価」で知る)
- 前田早苗(2009).大学の質保証における認証評価が果たすべき役割について 大学評価研究,4,53-63.(CiNii Articles「認証評価」で知る)
- 荻上紘一(2009).認証評価制度の問題点とこれからの改革の方向 大学評価研究,8,43-51.(CiNii Articles「認証評価」で知る)
- 河田悌一(2009).自己点検・評価体制の見直し:関西大学の場合 大学評価研究,8,3-8.(CiNii Articles「認証評価」で知る)
- 中道眞(2009).書評 早田幸政・船戸高樹編『よくわかる大学の認証評価:大学機関別認証評価篇』エイデル研究所(2007年1月):「第1章 大学の認証評価とは何か」を中心に (世界の中の日本,日本の中の世界:大学評価システムの国際比較と「評価文化」に関する総合研究) 龍谷大学国際社会文化研究所紀要,11,29-34.(CiNii Articles「認証評価」で知る)
- 関隆宏(2009).大学機関別認証評価を通じて得られた新潟大学の課題 大学教育研究年報,14,47-53.(CiNii Articles「認証評価」で知る)
- 金性希・林隆之・齊藤貴浩(2009).認証評価による大学等の改善効果の創出構造:大学等に対する認証評価の検証アンケート結果の比較分析を中心に 大学評価・学位研究,9,19-42.[PDF](CiNii Articles「認証評価」で知る)
- 伊藤昇(2009).認証評価制度と国立大学法人評価制度における大学の改善・改革:自己点検・評価の高度化と「大学評価文化」の定着を目指して 大学行政研究,4,187-235.[PDF](CiNii Articles「認証評価」で知る)
- 関根秀和(2008).短期大学の認証評価:自己組織性の形成を支援する IDE:現代の高等教育,504,59-62.(CiNii Articles「認証評価」で知る)
- 原野幸康(2008).日本高等教育評価機構の現状と課題 IDE:現代の高等教育,504,53-59.(CiNii Articles「認証評価」で知る)
- 長田豊臣(2008).大学基準協会の大学評価:課題と改革方向 IDE:現代の高等教育,504,48-52.(CiNii Articles「認証評価」で知る)
- 木村孟(2008).大学評価・学位授与機構の認証評価 IDE:現代の高等教育,504,42-47.(CiNii Articles「認証評価」で知る)
- 土屋俊(2008).機関別認証評価に参加して IDE:現代の高等教育,504,40-42.(CiNii Articles「認証評価」で知る)
- 圓月勝博(2008).エビデンスとメソッド IDE:現代の高等教育,504,37-39.(CiNii Articles「認証評価」で知る)
- 羽田積男(2008).認証評価の折り返し点に立って IDE:現代の高等教育,504,34-37.(CiNii Articles「認証評価」で知る)
- 久保猛志(2008).2機関の評価を受けて:金沢工業大学 IDE:現代の高等教育,504,31-34.(CiNii Articles「認証評価」で知る)
- 後藤俊夫(2008).認証評価の意義:中部大学 IDE:現代の高等教育,504,27-30.(CiNii Articles「認証評価」で知る)
- 藤沢謙一郎(2008).評価を受けて:信州大学 IDE:現代の高等教育,504,23-27.(CiNii Articles「認証評価」で知る)
- 古関彰一(2008).評価を受けて:獨協大学 IDE:現代の高等教育,504,19-22.(CiNii Articles「認証評価」で知る)
- 潮江宏三(2008).評価を受けて:京都市立芸術大学 IDE:現代の高等教育,504,15-19.(CiNii Articles「認証評価」で知る)
- 村岡啓一(2008).評価を受けて:一橋大学法科大学院 IDE:現代の高等教育,504,11-14.(CiNii Articles「認証評価」で知る)
- 天野郁夫(2008).認証評価の現段階 IDE:現代の高等教育,504,4-11.(CiNii Articles「認証評価」で知る)
- 関根秀和(2008).短期大学基準協会 短期「大学」としての大学文化の形成を支援する カレッジマネジメント,26(3),20-23.(CiNii Articles「認証評価」で知る)
- 原野幸康(2008).日本高等教育評価機構 急増期に向け評価システムの改善・精緻化が不可欠 カレッジマネジメント,26(3),16-19.(CiNii Articles「認証評価」で知る)
- 工藤潤(2008).大学基準協会:大学の内部質保証システムの構築が基盤 カレッジマネジメント,26(3),12-15.(CiNii Articles「認証評価」で知る)
- 川口昭彦(2008).大学評価・学位授与機構:目的・目標の明確化と学外への情報発信強化を カレッジマネジメント,26(3),8-11.(CiNii Articles「認証評価」で知る)
- (2008).大学の4割が評価を終える カレッジマネジメント,26(3),5-7.(CiNii Articles「認証評価」で知る)
- 安岡高志(2008).認証評価制度の問題点と将来の方向性:コンプライアンス主義に陥るな 大学時報,57(319),92-95.(CiNii Articles「認証評価」で知る)
- 川本明人(2008).認証評価結果による大学教育の質向上:広島修道大学の改革 大学時報,57(319),88-91.(CiNii Articles「認証評価」で知る)
- 山中博心(2008).認証評価を大学改革に生かすために 大学時報,57(319),84-87.(CiNii Articles「認証評価」で知る)
- 坂本和一(2008).認証評価結果を生かした大学改革:立命館大学の取り組み 大学時報,57(319),78-83.(CiNii Articles「認証評価」で知る)
- 鈴木典比古(2008).大学改革を励ます効果的な認証評価 大学時報,57(319),74-77.(CiNii Articles「認証評価」で知る)
- 沖裕貴(2007).観点別教育目標から考えるカリキュラム・ポリシーの構造:理念・目標、ディプロマ・ポリシー、シラバスとの関連において 立命館高等教育研究,7,61-74.(CiNii Articles「認証評価」で知る)
- 中留武昭・岡田佳子(2007).大学「学士課程」におけるカリキュラムマネジメントの理論と実際:認証評価機関にみるカリキュラムマネジメントの要因分析の吟味:大学評価・学位授与機構におけるケース 季刊教育法,152,58-69.(CiNii Articles「認証評価」で知る)
- 横山恵子(2007).日本型評価国家における私立セクターの特性:機関別認証評価の私立大学への影響に関する研究 大学論集,38,143-158.[PDF](CiNii Articles「認証評価」で知る)
- 羽田貴史(2007).第1章 行政改革における評価の動向と認証評価 COE研究シリーズ,28,1-23.(CiNii Articles「認証評価」で知る)
- 前角和宏(2007).認証評価制度の現状と課題:大学はどう生かすことができるのか 神戸海星女子学院大学研究紀要,46,213-227.[PDF](CiNii Articles「認証評価」で知る)
- 中留武昭・岡田佳子(2006).大学「学士課程」におけるカリキュラムマネジメントの理論と実際 認証評価機関にみるカリキュラムマネジメントの要因分析の吟味:大学基準協会におけるケース 季刊教育法,151,68-77.(CiNii Articles「認証評価」で知る)
- 伊藤敏弘(2006).日本高等教育評価機構における認証評価の実施とその特徴 大学教育学会誌,28(2),28-32.(CiNii Articles「認証評価」で知る)
- 川口昭彦(2006).独立行政法人大学評価・学位授与機構が実施する大学機関別認証評価について 大学教育学会誌,28(2),22-27.(CiNii Articles「認証評価」で知る)
- 関根秀和(2006).評価文化の形成に向けて:短期大学基準協会の場合 大学教育学会誌,28(2),17-21.(CiNii Articles「認証評価」で知る)
- 山岸駿介(2006).第三者評価をだれが育てるのか:評価一年目に考えたこと 短期大学教育,62,58-63.(CiNii Articles「認証評価」で知る)
- 山内昭人(2006).(財)短期大学基準協会の認証評価、一年目を終えて 短期大学教育,62,53-57.(CiNii Articles「認証評価」で知る)
- 関口正司(2006).認証評価の機会を九州大学ならではの教育の質的向上に活かす 大学教育,12,1-6.(CiNii Articles「認証評価」で知る)
- 山崎その(2006).認証評価と自己改善:大学の視点からみた課題 大学行政管理学会誌,10,87-99.(CiNii Articles「認証評価」で知る)
- 奈良哲(2005).認証評価制度の概要 京都大学高等教育研究,11,105-109.[PDF](CiNii Articles「認証評価」で知る)
- 久保猛志(2005).日本高等教育評価機構の試行評価を受けて IDE:現代の高等教育,476,57-60.(CiNii Articles「認証評価」で知る)
- 角紀代恵(2005).大学基準協会の認証評価を受けて IDE:現代の高等教育,476,53-57.(CiNii Articles「認証評価」で知る)
- 関根秀和(2005).評価文化の形成に向けて IDE:現代の高等教育,476,33-38.(CiNii Articles「認証評価」で知る)
- 伊藤敏弘(2005).日本高等教育評価機構の認証評価システム IDE:現代の高等教育,476,27-32.(CiNii Articles「認証評価」で知る)
- 木村孟(2005).大学評価・学位授与機構による認証評価 IDE:現代の高等教育,476,19-27.(CiNii Articles「認証評価」で知る)
- 前田早苗(2005).大学基準協会が目指す質保証 IDE:現代の高等教育,476,12-19.(CiNii Articles「認証評価」で知る)
- 舘昭(2005).動き出した認証評価と今後の課題 IDE:現代の高等教育,476,5-12.(CiNii Articles「認証評価」で知る)
- 安岡高志(2005).自己点検・評価や認証評価に必要な評価者養成 大学教育学会誌,27(2),129-134.(CiNii Articles「認証評価」で知る)
- 文部科学省高等教育局高等教育企画課(2005).認証評価制度について 文部科学時報,1548,50-59.(CiNii Articles「認証評価」で知る)
- 鈴木典比古(2005).自己点検・評価の構造と活動:認証評価にどう臨むか 大学評価研究,4,65-72.(CiNii Articles「認証評価」で知る)
- 山本淳司(2005).認証評価制度の実態と職員の専門化・高度化 大学行政管理学会誌,9,105-118.(CiNii Articles「認証評価」で知る)
- 山崎その(2005).認証評価制度の現状と課題 大学行政管理学会誌,9,91-104.(CiNii Articles「認証評価」で知る)
- 山内昭人(2004).短期大学基準協会 IDE:現代の高等教育,464,31-35.(CiNii Articles「認証評価」で知る)
- 伊藤敏弘(2004).日本私立大学評価機構 IDE:現代の高等教育,464,28-31.(CiNii Articles「認証評価」で知る)
- 澤田進(2004).財団法人大学基準協会 IDE:現代の高等教育,464,23-27.(CiNii Articles「認証評価」で知る)
- 木村孟(2004).大学評価・学位授与機構 IDE:現代の高等教育,464,18-22.(CiNii Articles「認証評価」で知る)
- 舘昭(2004).大学の評価と質の保証:「認証評価」制度の意義と課題 IDE:現代の高等教育,464,10-18.(CiNii Articles「認証評価」で知る)
- 合田隆史(2004).認証評価の仕組み IDE:現代の高等教育,464,5-10.(CiNii Articles「認証評価」で知る)
- 清水一彦(2004).なぜ今日本に認証評価が必要か:認証評価機関設立をめぐって 短期大学教育,60,58-63.(CiNii Articles「認証評価」で知る)
[2016.02.05]IRなどについての文献メモ 文献一覧を更新<論文執筆、英語>
- 上出洋介(2014).国際誌エディターが教えるアクセプトされる論文の書きかた 丸善出版(Amazon.co.jpレコメンド機能で知る)
- 和田朋子(2013).はじめての英語論文 引ける・使えるパターン表現&文例集 増補改訂版 すばる舎(Amazon.co.jpレコメンド機能で知る)
- Glasman-Dea, H. (2010). Science research writing for non-native speakers of English. London, UK: Imperial College Press.(Amazon.co.jpレコメンド機能で知る)
- Wallwork, A. (2011). English for writing research papers. New York: Springer.(Amazon.co.jpレコメンド機能で知る)
- Wallwork, A. (2010). English for presentations at international conferences. New York: Springer.(Amazon.co.jpレコメンド機能で知る)
- 原田豊太郎(2004).間違いだらけの英語科学論文:失敗例から学ぶ正しい英文表現 講談社(Amazon.co.jpレコメンド機能で知る)
- 原田豊太郎(2002).理系のための英語論文執筆ガイド:ネイティブとの発想のズレはどこか? 講談社(Amazon.co.jpレコメンド機能で知る)
- 杉原厚吉(1994).理科系のための英文作法:文章をなめらかにつなぐ四つの法則 中央公論社(Amazon.co.jpレコメンド機能で知る)
- 上松正朗(2006).英語:抄録・口頭発表・論文作成虎の巻:忙しい若手ドクターのために 南江堂(Amazon.co.jpレコメンド機能で知る)
[2016.02.05]IRなどについての文献メモ 文献一覧を更新<科研費>
- 岡田益男(2015).採択される科研費申請ノウハウ:審査から見た申請書のポイント 第2版 アグネ技術センター(Amazon.co.jpレコメンド機能で知る)
- 児島将康(編)(2015).科研費獲得の方法とコツ:実例とポイントでわかる申請書の書き方と応募戦略 改訂第4版 羊土社(Amazon.co.jpレコメンド機能で知る)
[2016.02.05]IRなどについての文献メモ 文献一覧を更新<文章作成>
- 結城浩(2013).数学文章作法 基礎編 筑摩書房(Twitter(@aokikenichiさん)で知る)
- 結城浩(2014).数学文章作法 推敲編 筑摩書房(Twitter(@aokikenichiさん)で知る)
- 鈴木哲也・高瀬桃子(2015).学術書を書く 京都大学学術出版会(Amazon.co.jpレコメンド機能で知る)
- 吉岡友治(2015).シカゴ・スタイルに学ぶ論理的に考え、書く技術:世界で通用する20の普遍的メソッド 草思社(Amazon.co.jpレコメンド機能で知る)
- 吉岡友治(2013).いい文章には型がある PHP研究所(Amazon.co.jpレコメンド機能で知る)
- 吉岡友治(2014).その言葉だと何も言っていないのと同じです!:「自分の考え」を論理的に伝える技術 日本実業出版社(Amazon.co.jpレコメンド機能で知る)
- 近藤勝重(2015).必ず書ける「3つが基本」の文章術 幻冬舎(Amazon.co.jpレコメンド機能で知る)
- 安藤智子(2015).言いたいことが伝わる 上手な文章の書き方 秀和システム(Amazon.co.jpレコメンド機能で知る)
[2016.02.05]IRなどについての文献メモ 文献一覧を更新<資料作成、プレゼン>
- 渡部欣忍(2014).あなたのプレゼン誰も聞いてませんよ!:シンプルに伝える魔法のテクニック 南江堂(Amazon.co.jpレコメンド機能で知る)
- 天野暢子(2015).テレビに学ぶ 中学生にもわかるように伝える技術 ディスカヴァー・トゥエンティワン(Amazon.co.jpレコメンド機能で知る)
- 天野暢子(2010).プレゼンはテレビに学べ! ディスカヴァー・トゥエンティワン(Amazon.co.jpレコメンド機能で知る)
[2016.02.04]IRなどについての文献メモ 文献一覧を更新<思考法>
- 岸良裕司・きしらまゆこ(2014).考える力をつける3つの道具:かんたんスッキリ問題解決! ダイヤモンド社(Amazon.co.jpレコメンド機能で知る)
- 太田薫正(2014).思考を広げるまとめる深める技術 KADOKAWA(Amazon.co.jpレコメンド機能で知る)
- 細谷功(2014).具体と抽象:世界が変わって見える知性のしくみ dZERO(Amazon.co.jpレコメンド機能で知る)
[2016.02.04]IRなどについての文献メモ 文献一覧を更新<課題解決>
- 村上悟(2008).問題解決を「見える化」する本 中経出版(Amazon.co.jpレコメンド機能で知る)
[2016.02.04]IRなどについての文献メモ 文献一覧を更新<会議>
- 杉野幹人(2013).会社を変える会議の力 講談社(Amazon.co.jpレコメンド機能で知る)
[2016.02.04]IRなどについての文献メモ 文献一覧を更新<文章作成>
- 樋口裕一(2011).文章力の鍛え方 中経出版(Amazon.co.jpレコメンド機能で知る)
[2016.02.04]IRなどについての文献メモ 文献一覧を更新<高大接続>
[2016.02.04]IRなどについての文献メモ 文献一覧を更新<IR>
- 小原一仁・大山篤之(2015).私立大学のスリム化はなにをもたらすか ニッセイ基礎研究所報,59,101-115.[PDF](Twitter(@high190さん)で知る)
- 小原一仁・大山篤之(2013).大学入試はどう管理されるべきか EMの現状:大学入試合格者数決定手法の一提案 ニッセイ基礎研レポート,2013-10-18,1-15.[PDF](ニッセイ基礎研所報(小原・大山,2015)の「関連レポート」で知る)
- 森雅生(2016).大学経営の鍵となるIR ECO-FORUM,31(2),10-19.[PDF](Twitter(@high190さん)で知る)
- 両角亜紀子(2016).18歳人口減少と私学経営・政策の課題 ECO-FORUM,31(2),3-9.[PDF](ECO-FORUMの目次で知る)
[2016.02.01]IRなどについての文献メモ 内容をアップ
- 荒木宏子・安田宏樹(2016).大学4年生の正社員内定要因に関する実正分析 経済分析,190,1-24.[PDF](大学4年生の正社員内定者の特徴を明らかにして効果的な就職支援の在り方を考察、正社員内定の要因がジョブサーチ活動そのもの(活動開始時期・応募先の選定基準など)か個人の特性(学力や人的資本など)のどちらにあるのかを検証、サンプルを学部別(文系・理系)・大学区分(偏差値・国公私立)・男女別に分けて検証、使用したデータ:『大学生のキャリア展望と就職活動に関する実態調査』(労働政策研究・研修機構が2015年10月に実施)の個票データ、結果(一定の効果が期待できるもの)・・・文系:就職活動の開始時期の適切な誘導、文系私立中高位・国公立・理系私立高位:就職応募先の選定についてのアドバイス、文系私立低位・公立:学力促進、理系については課外活動(アルバイト)への熱心な取り組みが悪影響を及ぼす傾向、考察:特性に応じた政策立案が重要;はてなブックマークで知る)
[2016.02.01]IRなどについての文献メモ 文献一覧を更新<IR>
- 荒木宏子・安田宏樹(2016).大学4年生の正社員内定要因に関する実正分析 経済分析,190,1-24.[PDF](はてなブックマークで知る)
[2016.02.01]IRなどについての文献メモ 文献一覧を更新<統計>
- 河本薫(2013).会社を変える分析の力 講談社(Amazon.co.jpレコメンド機能で知る)
- 酒巻隆治・里洋平(2014).ビジネス活用事例で学ぶデータサイエンス入門 SBクリエイティブ(Amazon.co.jpレコメンド機能で知る)
- 工藤卓哉・保科学世(2013).データサイエンス超入門:ビジネスで役立つ「統計学」の本当の活かし方 日経BP社(Amazon.co.jpレコメンド機能で知る)
- 工藤卓哉(2013).これからデータ分析を始めたい人のための本 PHPエディターズ・グループ(Amazon.co.jpレコメンド機能で知る)
- 齋藤健太(2013).問題解決のためのデータ分析 クロスメディア・パブリッシング(Amazon.co.jpレコメンド機能で知る)
- 末吉正成・末吉美喜(2014).Excelビジネス統計分析 第2版 翔泳社(Amazon.co.jpレコメンド機能で知る)
[2016.02.01]IRなどについての文献メモ 文献一覧を更新<デザイン、資料作成>
- 森重湧太(2016).一生使える 見やすい資料のデザイン入門 インプレス(Amazon.co.jpレコメンド機能で知る)
[2016.01.29]ホーム「お知らせ」欄を変更
- 話題提供「教育改善に向けてデータをどのように共有できるのか」(第22回大学教育研究フォーラム<参加者企画セッション>)の企画者・話題提供者・指定討論者・司会者を掲載
[2016.01.28]IRなどについての文献メモ 内容をアップ
- 藤原宏司(2016).学業を中断する学生の予測モデル構築について,大学評価とIR,5,8-22.[PDF](「学業中断のおそれがある学生」を判別予測するデータマイニングモデルの具体例を紹介、学業中断の定義(3つの条件)、米国の短期大学では在籍継続率(学生の自大学における学業の継続状況を示す指標)よりも学業継続・修了率が使われている、学業継続・修了率を「学生成功率(Student Success Rate)」と呼ぶ大学もある(学生が学業を中断していない状態を学生にとっての「成功」と捉えている)、学業継続・修了率の改善を目的としたプロジェクト(IR室が予測モデルにより「学業中断のおそれがある」学生を判別予測→学生部が介入プログラム実施)において著者が担当した予測モデルを構築・選択・適用したプロセスを紹介、予測変数(予測に用いる変数)の解説、10種類の予測モデル(決定木・ナイーブベイズ分類器・k近傍法・ ニューラルネットワーク・サポートベクターマシン・バギング・ブースティング・ランダムフォレスト・ロジスティック回帰分析・プロビット回帰分析、投入された学生データを計算し2値の結果を判別予測する)を候補とした、決定木の分析結果を例示(決定ルールの可視化が容易で分析結果も理解しやすい、結果を用いた学内の議論が活発になることが期待できる)、予測精度を重視する場合は複数の予測モデルで検証することが望ましい、サンプル数が少ないためホールドアウト検証で各モデルの予測精度を推定した(1,000より大きいなど十分なサンプル数がある場合は交差検証が一般的に推奨される)、感度が一番高いニューラルネットワークを採用した、予測と実際の結果は近いものであった、学生部が[入学の翌学期]に介入プログラムを試みたが学生は[入学学期の中盤]までに学業中断を決めていた、そのためモデルによる検出を[入学の翌学期開始直後(理想は開始前)]に行うことになった、モデルを再構築したが予測精度が下がった([入学学期の成績](予測モデルにとって大変重要な変数)を欠くモデルでは判別予測が困難)、パイロットプロジェクトの大幅な見直しが必要となりベイジアンネットワーク(変数間の因果関係を探索的に視覚化する手法)を用いて介入プログラム対象の学生を抽出した(別稿で報告)、本稿で報告した2値の結果を判別予測するモデルの構築は日本の大学においても十分に実践可能と思われる(中途退学者、就職成功者、資格試験合格など)、日常的なIR業務は学内外へのレポーティングであり本稿で報告した予測モデルの構築は稀;大学評価コンソーシアムからの案内で知る)
[2016.01.28]IRなどについての文献メモ 文献一覧を更新<IR>
- 藤原宏司(2016).学業を中断する学生の予測モデル構築について,大学評価とIR,5,8-22.[PDF](大学評価コンソーシアムからの案内で知る)
[2016.01.28]IRなどについての文献メモ 文献一覧を更新<論文執筆、英語>
- エディテージ、熊沢美穂子 (訳)(2016).英文校正会社が教える 英語論文のミス100 ジャパンタイムズ(Amazon.co.jpレコメンド機能で知る)
[2016.01.26]IRなどについての文献メモ 文献一覧を更新<図書館>
- 飯野勝則(2016).図書館を変える!:ウェブスケールディスカバリー入門 出版ニュース社(はてなブックマークで知る)
[2016.01.26]IRなどについての文献メモ 文献一覧を更新<研究データ、オープンサイエンス>
- 武田英明・村山泰啓・中島律子(2015).研究データへのDOI登録実験 情報管理,58(10),763-770.[PDF](はてなブックマークで知る)
[2016.01.25]「私立大学職員によるIR文献メモ」メルマガ バックナンバーを更新
[2016.01.21]ホーム「お知らせ」欄を変更
- 口頭発表「日本におけるIRオフィス立ち上げ期の関心事:15大学・団体から訪問調査を受けた際の照会事項から見えること」(平成27年度第4回IR実務担当者連絡会)を掲載
- ポスター発表「学科内での授業改善策の議論を促す仕組み作り:「授業アンケート結果に対する担当教員のコメント」の活用」(第21回FDフォーラム)を掲載
[2016.01.13]IRなどについての文献メモ 文献一覧を更新<中途退学、リテンション>
- 全国大学保健管理協会(編)(1990).創立25周年記念特集号 全国大学保健管理協会(全国各大学の退学者問題対応の経緯、1960年代には疾病・傷害による退学多い、そのため各大学の関心は疾病・傷害による退学・除籍者の実態調査と予防・対応に向けられていた、橋本注:尾崎(1991)には「学生生活適応困難学生の早期発見」とあるが本誌には記載見当たらず、「研究会集会資料」の講演一覧・テーマ一覧を踏まえた言及か;尾崎(1991)「長崎総合科学大学における退学状況について(1)」で知る)
- 沢田丞司(1979).学生と休学、退学 藤土圭三(編著)現代学生の精神衛生:若者指導のためのハンドブック 北大路書房 pp. 83-98.(全国の国公私立大学を対象にした休学・退学の実態調査が文部省によって1969年に報告された、各大学からの報告を見ると私立大学では退学が増加する傾向が推測される、退学の一般的な背景要因:①学生の主体的要因・②大学環境要因・③社会環境要因(3つが重複して複雑に影響し合うことが多い);尾崎(1991)「長崎総合科学大学における退学状況について(1)」で知る)
- 中島潤子(1990).大学における休・退学、留年学生に関する調査:第12報 大学精神衛生研究会報告書,12,40-59.(国立大学48校・私立大学4校の退学状況について報告、国立大学では1983年度1.15%(橋本注:図2-1の線グラフか(値の記載なし))→1990年度1.3%(橋本注:値の記載あり)に増加、割合としては大きく増加していないものの入学者数は増えているため絶対数が増加;尾崎(1991)「長崎総合科学大学における退学状況について(1)」で知る)
- 安藤延男(1982).大学生の不適応に関する文献総説 安藤延男・園田五郎(編)大学生の原級残留に関する研究と対策:九州大学教養部での10年間の歩み 九州大学教養部学生指導教官室 pp. 11-25.(大学生の不適応または適応異常についての研究を分類:①大学生の学業不振・②心理的障害による不適応の予防・③入学者選抜・④その他;尾崎(1991)「長崎総合科学大学における退学状況について(1)」で知る)
- 小林哲朗(2000).大学・学部への満足感 小林哲郎・高石恭子・杉原保史(編著)大学生がカウンセリングを求めるとき:こころのキャンパスガイド ミネルヴァ書房 pp. 56-72.(不本意入学には4つの型がある:①第一志望不合格型・②合格優先型(「受かる大学」に入学)・③就職優先型(興味・適正よりも資格取得など就職の有利さを優先)・④家庭の事情型(通学圏内・安い学費など経済的・地理的事情を優先)、入学後の不本意間についても多様な要因を指摘(授業がおもしろくない・履修登録を失敗した・単位が取れそうにない・教員への違和感など);山田(2006)「大学新入生における適応感の検討」で知る)
[2016.01.12]IRなどについての文献メモ 文献一覧を更新<資料作成>
- 吉澤準特(2014).外資系コンサルが実践する資料作成の基本:パワーポイント、ワード、エクセルを使い分けて「伝える」→「動かす」王道70 日本能率協会マネジメントセンター(デアウィ株式会社さんのブログ記事「【厳選】プレゼンのコツを掴むために読んでおきたい6冊の本。」で知る)
- 前田鎌利(2015).社内プレゼンの資料作成術 ダイヤモンド社(Amazon.co.jpレコメンド機能で知る)
- 西脇資哲(2015).プレゼンは「目線」で決まる ダイヤモンド社(Amazon.co.jpレコメンド機能で知る)
- 柏木吉基(2015).それちょっと、数字で説明してくれる?と言われて困らないできる人のデータ・統計術 SBクリエイティブ(Amazon.co.jpレコメンド機能で知る)
- 柏木吉基(2015).日産で学んだ世界で活躍するためのデータ分析の教科書:誰が見てもわかる「データ」で、筋の通った「ストーリー」を作る 日経BP社(Amazon.co.jpレコメンド機能で知る)
- 中川邦夫(2010).ドキュメント・コミュニケーションの全体観:提案書、報告書、会議資料の“質"と“制作スピード"を上げるメカニズム(上巻)原則と手順 コンテンツ・ファクトリー コンテンツ・ファクトリー(Amazon.co.jpレコメンド機能で知る)
- 中川邦夫(2010).ドキュメント・コミュニケーションの全体観:提案書、報告書、会議資料の“質"と“制作スピード"を上げるメカニズム(下巻)技法と試合運び コンテンツ・ファクトリー コンテンツ・ファクトリー(Amazon.co.jpレコメンド機能で知る)
[2016.01.10]ホーム「お知らせ」欄を変更
- ポスター発表"A data-driven approach to dropout prevention in Japan"(2016 AIR Forum)を掲載
[2016.01.09]「過去の「お知らせ」」、「IRなどについての文献メモ」、「これまでの発表・競争的研究資金など」に追加
- 口頭発表「大学からの中途退学についての文献レビュー:日本の雑誌論文を中心に」(平成27年度第3回IR実務担当者連絡会)
[2016.01.07]IRなどについての文献メモ 文献一覧を更新<統計>
[2016.01.06]IRなどについての文献メモ 文献一覧を更新<中途退学、リテンション>
- 全国大学保健管理協会(編)(1964).第1回全国大学保健管理研究集会報告書 全国大学保健管理協会(1970年代以降になると疾病や傷害が原因でない当時としては理由がはっきりしない退学が見られるようになった、留年・休学と並んで学生の大学環境への適応の問題として注目され始めた;尾崎(1991)「長崎総合科学大学における退学状況について(1)」で知る)
- 全国大学生協共済生活協同組合連合会(2014).ANNUAL REPORT 2013 全国大学生協共済生活協同組合連合会[PDF](藤本昌(2014)「学生の疾病・傷害の保障に関する考察」で知る)
- 加野芳正・葛城浩一(編)(2011).学生による学生支援活動の現状と課題 広島大学高等教育研究開発センター[PDF](川﨑他(2014)「大学における寄り添い型学生支援体制の構築」で知る)
- 旺文社教育情報センター(2007).17 年度私立大中途退学状況:私立大の17年度中退者5万5,500人、中退率2.9%! 教育情報(平成19(2007)年度5月24日)[PDF](日本私立学校振興・共済事業団による「学校法人基礎調査」を解説;姉川(2014)「大学の学習・生活環境と退学率の要因分析」で知る)
- Robbins, S. B., Lauver, K., Le, H., Davis, D., & Langley, R. (2004). Do psychosocial and study skill factors predict college outcomes? A meta-analysis. Psychological bulletin, 130(2), 261-288.[Abstract](姉川(2014)「大学の学習・生活環境と退学率の要因分析」で知る)
- Lotkowski, V. A., Robbins, S. B., & Noeth, R. J. (2004). The role of academic and non-academic factors in improving college retention. ACT policy report, 130(2), 1-31.[PDF](Robbins et al.(2004)の主な結果をまとめている;姉川(2014)「大学の学習・生活環境と退学率の要因分析」で知る)
- Weissberg, N. C., & Owen, D. R. (2005). Do psychosocial and study skill factors predict college outcomes? Comment on Robbins et al.(2004). Psychological bulletin, 131(3), 407-409.[Abstract](Google Scholar「Do psychosocial and study skill factors predict college outcomes?」で知る)
- Ishitani, T. T., & DesJardins, S. L. (2002). A longitudinal investigation of dropout from college in the United States. Journal of college student retention: Research, theory & practice, 4(2), 173-201.[Abstract](国や大学から学資援助(奨学金)を受けることができた学生はそうでない学生と比べて退学率が有意に下がっている;姉川(2014)「大学の学習・生活環境と退学率の要因分析」で知る)
- Ishitani, T. T., & DesJardins, S. L. (2002). A longitudinal investigation of dropout from college in the United States. AIR 2002 Forum paper. Paper presented at the Annual Meeting of the Association for Institutional Research (42nd, Toronto, Ontario, Canada, June 2-5, 2002)[PDF](Google Scholar「A longitudinal investigation of dropout from college in the United States」で知る)
- 矢野眞和(2007).大学は本人のためだけでなく、社会のために役立っている 日本労働研究雑誌,49(4),59-61.[PDF](矢野(2005)『工学教育のレリバンス』の内容を紹介、大学での学習経験と仕事の関係についてアンケート調査、大学時代の科目や読書などの熱心さと所得の関係を分析、大学時代の熱心さよりも職場の経験・学習が所得上昇に効果があるという結果(重回帰分析を用いた)、ただし間接的な経路(大学時代の熱心さ)が現在の知識能力などに大きなプラス効果をもたらしていると指摘;姉川(2014)「大学の学習・生活環境と退学率の要因分析」で知る)
- 矢野眞和(研究代表者)(2005).工学教育のレリバンス 文部科学省科学研究費補助金基盤研究(B)研究成果報告書(研究課題番号:14310118)(矢野眞和(2007)「大学は本人のためだけでなく、社会のために役立っている」で知る」)
- Cragg, K. M. (2009). Influencing the probability for graduation at four-year institutions: A multi-model analysis. Research in higher education, 50(4), 394-413.[Abstract](「図書貸出数」や「学生に対する教員比率」の変数が保持率(大学に留まる学生の割合)に正の効果;姉川(2014)「大学の学習・生活環境と退学率の要因分析」で知る)
- Weiner, S. (2009). The contribution of the library to the reputation of a university. The journal of academic librarianship, 35(1), 3–13.[Abstract](「図書貸出数」や「学生に対する教員比率」の変数が保持率(大学に留まる学生の割合)に正の効果、図書館の質が学生の大学生活の満足度・評価に影響を及ぼす;姉川(2014)「大学の学習・生活環境と退学率の要因分析」で知る)
- 船戸高樹(2007).深刻化する退学者問題:全学的な取組みが求められる(上) アルカディア学報,288.[HTML](岩崎(2015)「大学における休・退学防止の検討」で知る)
- 船戸高樹(2007).深刻化する退学者問題:エンロールメント・マネジメントの必要性(下) アルカディア学報,289.[HTML](Google「深刻化する退学者問題」で知る)
- 日本中退予防研究所(編著)(2011).中退予防戦略 Newvery(消極的理由の中退は「辞めたいと思う前の予防が必要であり、かつ予防することが十分に可能な中退」;岩崎(2015)「大学における休・退学防止の検討」で知る)
- 田部井世志子・生田カツエ(編)(2014).学生サポート大作戦:寄りそう学生支援 九州大学出版会(北九州市立大学の「早期支援システム」を紹介;岩崎(2015)「大学における休・退学防止の検討」で知る)
- 内田千代子(2010).21年間の調査からみた大学生の自殺の特徴と危険因子:予防への手がかりを探る 精神神經學雜誌,112(6),543-560.[Abstract](休学・退学・留年学生の中に自殺その他の精神疾患を認めることは希ではない;内田(2010)「休学・退学の変化」で知る)
- 谷原弘之(2004).校内の組織づくりと効果的な運用 平松清志(編著)現場に生きるスクールカウンセリング:子ども・教師・保護者への対応と援助 金剛出版 pp.73-91.([1週間のうち3日以上理由のない欠席があった生徒の情報]によりスクールカウンセラーが危機介入を行うシステム;谷原(2012)「退学予防を目的とした「3日以上の理由のない欠席者の報告システム」の効果」で知る)
[2016.01.06]IRなどについての文献メモ 文献一覧を更新<IR>
[2016.01.06]IRなどについての文献メモ 内容をアップ
- 山口直範・頭師由里(2012).能動的な学生相談体制の試み 奈良佐保短期大学研究紀要,20,101-107.[PDF](学生相談室員が学生の訪問を待つのではなく能動的に学生に働きかけた、取り組み内容:①カウンセラー1名→3名(個性が異なるため学生は相性の良いカウンセラーを選択できる、カウンセラー間の連携・セカンドオピニオン)、②相談受付時間を拡大(昼休みを含むようにした)、③カウンセラーが学内巡回(積極的な声かけ、とくに講義後に教室に残って1人で昼食をとっている学生には必ず声かけ、相談室内だけで学生の姿を知ろうとしない)、④「なんでも相談コーナー」を開設(学生が多く集まるオープンスペースにパーテーション・机・椅子を配置、ざわざわ相談室に行かなくても気軽に相談できる、学生にカウンセラーの顔を覚えてもらう)、⑤相談室を移転・受付方法を変更(「なんでも相談コーナー」の上の階(コーナーから個室に速やかに移行できる)、事前予約必要→必要なし)、取り組みの結果:①相談件数が増加した、②退学者が減少した、③休学者は大きな変化が見られなかった;CiNii Articles「退学」で知る)
- 今野克幸・白石悟・細川和彦・井田直人・福原朗子・木内伸洋(2013).授業時間割の改善や初年度教育の充実等による修学支援と退学者減少対策 工学教育研究講演会講演論文集,25(61),650-651.[PDF](学内の退学率が高いため①時間割の改善(学年ごとに必修と選択を交互に配置⇒必修を落としても翌年度に上級学年の必修と重ならない、木曜日の午後を共通の空きコマに設定⇒補講・天候に左右される演習の補習措置が容易になった)と②初年次教育の充実など(グループワーク・フィードワークの機会を増やす⇒目的意識向上・友だち作り、再学習室の設置)を行った、その結果退学者減少となった、分析内容:入試区分別の退学率(学力試験を課さない区分で高い)・1年生前期の単位取得数別の退学率(単位数が少ないと高くなる、この時期の指導強化が必要)、退学・除籍率×入学後経過年数のグラフ(入学年度ごとに線グラフで表示)の掲載あり;CiNii Articles「退学」で知る)
- 浜崎央・片庭美咲・松本美奈・柴田幸一・住吉廣行・山本由紀(2013).初年次の退学率減少につながる入学前教育:教職協働によるIRの成果 地域総合研究,14(1),57-66.[PDF](入学前教育を充実させた年度の前後で退学率が変化したかを検証、入学前教育を始めた年から退学率・入学初年度の退学者数が減少、退学者数の経年変化のグラフ掲載あり;CiNii Articles「退学」で知る)
- 藤本昌(2014).学生の疾病・傷害の保障に関する考察:実務者からみる現行制度の現状と課題 保険学雑誌,2014(627),627_129-627_148.[PDF](学生の休学・退学の原因となる身体疾患・精神障害の状況を整理(内田(2013)「大学における休・退学、留年学生に関する調査 第34報告」の数値を使用)、身体疾患と精神障害がもたらす結果を整理(①死亡、②後遺障害、③入院・手術、④通院、全国大学生協共済生活協同組合連合会(2014)「ANNUAL REPORT 2013」の数値を使用);CiNii Articles「退学」で知る)
- 川﨑孝明・中嶋弘二・川嶋健太郎・川口惠子(2014).大学における寄り添い型学生支援体制の構築:中途退学防止の観点からの実践的アプローチ 尚絅大学研究紀要. A, 人文・社会科学編,46,75-89.[PDF](コミュニケーションが苦手な学生・意欲が減退している学生などへの対応が担任任せになっていた⇒退学の意思を示す以前の段階で学生が抱える問題を発見し早期介入するためにチームアプローチによる学生支援体制を構築(学科内で「退学防止対策班」を組織)、学生支援に関する研究動向を整理、寄り添い型支援をめぐる政策を整理、学科内の具体的取り組みを紹介(退学防止対策班(チームによる対応)、対応事例(匿名)の詳述)、事例に共通すること:健康状態の悪化によって結果的に不登校状態になっている(不登校学生の最初のサインは体調不良を訴えること)⇒日頃の体調把握は退学防止の観点から重要、保健室内で同じ境遇の学生同士のつながりが生じた(ピアカウンセリング)、関係機関(高校・医療機関等)と連携した;CiNii Articles「退学」で知る)
- 姉川恭子(2014).大学の学習・生活環境と退学率の要因分析 経済論究,149,1-16.[PDF](中途退学に関連した各種調査を整理・・・「大学の実力」(読売新聞):全国の国公私立大学の退学率は2008年調査7.7%→2010年調査8.2%(増加の傾向)、「学校法人基礎調査(2006年)」(日本私立学校振興・共済事業団):中途退学の背景には経済的理由だけではなく「学生のニーズと大学側が提供する学部教育の内容に隔たりがある」点もある)、「学校基本調査(各年版)」(文部科学省):4年制大学の入学者数から4年後の卒業者数を引いた数値を時系列で追うと1990年度入学生は約2万5000人→2005年度入学生は約5万人(絶対数が大きく増加、1991年の大学設置基準の大綱化による大学数・入学者数の増加が背景にある)、大学の中途退学の現状や高等教育に対する学生の満足度について分析した先行研究を概観(それらが主にどのような要因と相関しているかについての特徴を整理)、学びの環境の整備・拡充が中途退学の抑制にどのような効果を与えうるかを検証した(「大学の実力」と「日本の大学ランキング」の各年版データから作成したデータを使用、先行研究で扱われている変数に注目)、仮説①学生の入学時点の学力が高い大学ほど退学率は低い(偏差値を使用、退学率・標準修業年限卒業率との関係を検証)、仮説②学生の学習意欲が高い大学ほど退学率は低い(学生1人あたりの図書貸出数を使用、意欲の高い学生が多ければ他の学生も啓発されると想定、図書館の質を高めるなどの大学の取り組みが学習意欲に影響を及ぼすサイクルを想定)、仮説③学習環境に優れた大学ほど退学率は低い([学生100人あたりの教員数]と[学生支援スコア]を使用)、仮説④生活支援の手厚い大学ほど退学率は低い(生活支援スコアを使用)、結果と考察・・・仮説①・②・③の一部が成り立つ、「偏差値」(入学前の学力)が退学率に少なからぬ影響をもたらしていることが示唆された、ただし[大学が提供する学習環境が退学率の抑制に影響を与えている可能性]が重要、とくに「図書貸出数」・「学生に対する教員比率」が退学率の抑制に影響をもたらす可能性が示された点が重要(学習環境の強化が重要、それらの変数は「学ぶきっかけ」がどれだけ存在しているかと関連、学ぶ楽しさを経験することことそが個々の生活満足度・教育満足度を高める→大学全体での中途退学の低下につながりうる、[退学する学生は入学時点の学力によって既に決まっている]という考え方が安直であることを示している(同じ偏差値でも学習環境を整備している/していない大学間で退学率・卒業率に差が生じうる))、仮説④では優位な相関が見られなかったが先行研究では[効果的な「生活支援」や「学生支援」は学生の学習意欲を高め退学率の縮小に大きな効果がある]と実証している、Robbins et al.(2004)のnon-academic factorsは厳密には「入学後の学習環境要因(learning environment factors)」と解釈することが妥当(学習習慣や学習時間などアカデミックな部分と関連する変数が含まれているため);CiNii Articles「退学」で知る)
- 船戸高樹(2007).深刻化する退学者問題:全学的な取組みが求められる(上) アルカディア学報,288.[PDF](退学防止の取り組み(少人数ゼミやクラス担任制など)が退学者減少に結びついていない、担当者に任せるだけで全学的な取り組みになっていないことが原因、退学防止策:①理事会が中心となって全学的に取り組む体制とシステムを構築する、②現在取り組んでいる退学防止策について点検・評価して改善策を検討する、③「退学願」が出てきてからでは遅いため兆候(欠席が多くなる・成績が低下するなど)をできる限り早くつかむ、④個別のケースごとに退学理由を詳細に調査・分析する、⑤分析結果を基にして対応策を打ち出す、⑥「できない」理由を探すのではなく「どうしたらできるか」という観点で取り組む;岩崎(2015)「大学における休・退学防止の検討」で知る)
- Robbins, S. B., Lauver, K., Le, H., Davis, D., & Langley, R. (2004). Do psychosocial and study skill factors predict college outcomes? A meta-analysis. Psychological bulletin, 130(2), 261-288.[Abstract](米国の中途退学の先行研究をメタ分析して統計的に統合、中途退学者の割合よりも保持率(college retention rate、主に入学して1年以内に当該大学に残っている割合)に着目して要因分析を行う、中途退学と家族の社会経済ステータスに相関が見られる(親の所得・学歴が高い学生は中途退学をしにくい傾向)①academic factors(入学前の成績など)・②non-academic factors(学内の活動状況や大学の学習環境など)・③other factors(学生の世帯所得や両親の学歴など)が保持率に与える影響を検証、大学入学時あるいは入学以前の本人の能力(大学1年次のGPAやACTの成績など)が一定の府の効果をもたらす傾向、学習のプロセスに影響を与えるファクター(大学に入ってからの学習意欲・学習に対する自信・勉強する習慣・学問上の目標など)が入学前後の成績以上に保持率と負の相関を持つ;姉川(2014)「大学の学習・生活環境と退学率の要因分析」で知る)
- 内田千代子(2010).休学・退学の変化 精神科,17(4),330-338.(全国の国立大学を対象にした休学・退学・留年についての調査を参考にして休学・退学・留年の変化と最近の大学生の精神保健を考察、休学・退学・留年率の経年推移・・・休学・退学・留年率は調査を始めた1978年頃から上昇曲線を描いてきた、しかし2000年前後から変化(1989年の時点で休学率が退学率を上回る傾向に変化、つまり大学に籍を置いたまま大学を利用する学生が増えた)、男子が女子に比べて休学・退学・留年率全て高い状態が現在まで続いている(進学率の違い・男性優位社会での就職の不利な条件を考慮した女子の努力などが考えられる)、理系の男子の退学率が高いことは一貫して変わらない、文系の休学率が高いことは一環して変わらない、休学・退学・留年率の最近の変化・・・休学率:1995年頃から急増傾向→2001年度から横ばい状態→2004年度から減少傾向(とくに男子)、退学率:1994年頃から急増傾向→2000年度にやや減少→その後横ばいから減少傾向、留年率:<男子>1990年度から急増傾向→2003年度から連続減少・<女子>2001年度から横ばい傾向(休学率と留年率は男女差が縮小しているが男女で理由がことなるため女子が従来の男子に近づいたということではない)、最近数年間の男子の[休学率・留年率の低下傾向]と[退学率の横ばい傾向]は進学率の上昇とは同調していない、休学・退学の理由・・・積極的/消極的:本人の主観とは関係がない、大学教育路線上に残るか離れるか、休学・退学理由の経年変化・・・<休学>1988年頃から留学・司法試験の勉強などの「積極的理由」が多くなっている→1989~1996年度は「積極的理由」が「消極的理由」の2倍弱(1989年度から休学率が退学率を上回るようになったのは「積極的理由」が増えたため、1988~1992年度はバブルで海外留学などが多くなった時期)→1997年度以降は「積極的理由」と「消極的理由」が同程度(最近の数年間は「積極的理由」での休学率が下がっている、1998年頃から[主に経済的要因による環境の理由]が増加、国立大学は休学中に学費を払う必要がないため不況により休学して一時的に働く学生が増加したことが考えられる、最近の数年間はやや減少)、<退学>「消極的理由」が昔から一貫して多い(最近は「消極的理由」の割合が高くなっている、休学と同様に1999年頃から経済的理由が増えたが最近やや減少傾向)、休学・退学ともに「積極的理由」「消極的理由」を問わず「進路に関する理由」が増えている(学生の進路の多様化)、10年前と変わらないこと:休学・退学ともに男子が多い・理系が多い、休学では「積極的理由」で女子が多い・文系が多い;CiNii Articles「退学」で知る)
- 中島潤子(1995).スチューデント・アパシーの行方:大学精神衛生研究会の「休・退学、留年学生に関する調査」から 大学と学生,357,11-16.(大学精神衛生研究会について紹介、「休・退学、留年学生調査」は2つの調査方法で構成される:①統計調査(国立大学を中心に55大学、対象は約35万人になった)、②実態調査(死亡については55大学全てが参加、休学・退学・留年は有志の大学のみ(例年10大学ほど))、死亡原因:戦前は「自殺」が第1位だったが研究会が統計を取り始めてからは減少傾向(昭和54年~平成5年度で第1位になった年度は4回、最近は微妙に増加傾向)、休学における海外留学などの急増について解説、ステューデントアパシーの傾向について解説(ステューデントアパシーが多様化);CiNii Articles「退学」で知る)
[2016.01.06]IRなどについての文献メモ 文献一覧を更新<適応感>
- 谷島弘仁(2005).大学生における大学への適応に関する検討 人間科学研究,27,19-27.[PDF](様々な理由で大学になじめない学生が増えている;野波他(2006)「初年次生の大学生活への適応に関する調査報告(1)」で知る)
[2016.01.06]IRなどについての文献メモ 文献一覧を更新<業務計画>
- 原尚美(2011).「事業計画書」のつくり方:51の質問に答えるだけですぐできる 日本実業出版社(Amazon.co.jp「計画」で知る)
- 秦充洋(2015).成功する事業計画書のつくり方 ナツメ社(Amazon.co.jp「計画」で知る)
- 井口嘉則(著)・飛高翔(作画)(2013).マンガでやさしくわかる事業計画書 日本能率協会マネジメントセンター(Amazon.co.jp「計画」で知る)
- 加納治郎(1963).計画の科学 経済往来社(Amazon.co.jp「計画」で知る)
- 川原慎也(2012).これだけ!PDCA:必ず結果を出すリーダーのマネジメント4ステップ すばる舎リンケージ(Amazon.co.jp「計画」で知る)
- 上石幸拓(2013).成功する計画の立て方・進め方:やさしいプロジェクト・プランニング 日科技連出版社(Amazon.co.jp「計画」で知る)
- 浦正樹(2013).「実行」に効く計画の技術 翔泳社(Amazon.co.jp「計画」で知る)
- 加藤昭吉(2007).「計画力」を強くする:あなたの計画はなぜ挫折するか 講談社(Amazon.co.jp「計画」で知る)
- サービス産業生産性協議会(編).優れたサービスのしくみ:理念をかたちにする「仕事の基準」のつくりかた 生産性出版(Amazon.co.jp「計画」で知る)
- 本道純一(2009).すべての「見える化」実現ワークブック:可視化経営システムづくりのノウハウ 実務教育出版(Amazon.co.jp「計画」で知る)
- 山本政樹(2015).ビジネスプロセスの教科書:アイデアを「実行力」に転換する方法 東洋経済新報社(Amazon.co.jp「計画」で知る)
[2016.01.05]IRなどについての文献メモ 文献一覧を更新<適応感>
- 大久保智生(2005).青年の学校への適応感とその規定要因:青年用適応感尺度の作成と学校別の検討 教育心理学研究,53(3),307-319.[PDF](学校の適応感を構成する要因(中学生から大学生まで共通):①居心地の良さの感覚・②課題・目的の存在・③信頼感・受容感・④劣等感の無さ、大学での適応感は高校時代の学校への適応感に大きく影響される;山田(2006)「大学新入生における適応感の検討」で知る)
[2016.01.05]IRなどについての文献メモ 文献一覧を更新<中途退学、リテンション>
- 深沢孝克・大宮司信(1992).作業療法学科における退学者について 北海道大学医療技術短期大学部作業療法学科(編)10周年記念誌 北海道大学医療技術短期大学部作業療法学科 pp.57-59.(上野他(1994)「北海道大学医療技術短期大学部作業療法学科における学生異動の実態」で知る)
- Hirsch, S. J., & Keniston, K. (1970). Psychosocial issues in talented college dropouts. Psychiatry, 33(1), 1-20.[Abstract](中途退学の肯定的な面を指摘、大学中退者の心理特性として父親に対する同一化における強い葛藤・困難な状況から回避する傾向などを挙げている;森田(1996)「大学中途退学者のアイデンティティ形成に関する研究」で知る)
- Timmons, F. R. (1978). Freshman withdrawal from college: A positive step toward identity formation? A follow-up study. Journal of youth and adolescence, 7(2), 159-173.[Abstract](中途退学の肯定的な面を指摘;森田(1996)「大学中途退学者のアイデンティティ形成に関する研究」で知る)
[2016.01.05]IRなどについての文献メモ 内容をアップ
- 藤原宏司(2016).「スピンドクターとしてのIR」に関する一考察 大学評価とIR,5,3-7.[PDF](Volkwein(1999)の4つの役割・機能(情報精通者・政策分析者・スピンドクター・研究者)はIRの一般的な業務内容を適切に表しているものの「スピンドクターとしてのIR」については疑問の余地あり、現在の米国のIRにはスピンドクターとしての中心的な役割は存在しない可能性が高い(大学におけるスピンドクターとは学内に対して「大学の良いイメージ」を作り上げることを業務としている人達と捉えることができる)、著者が勤務するミネソタ州立大学機構ベミジ州立大学およびノースウェスト技術短期大学においてスピンドクターの役割はIR室ではなく広報室が担っている、「学生の入学・履修状況に関するニュースリリース」の事例を通して「スピンドクターとしてのIR」などについて考察、IR室がまとめたデータを広報室が取捨選択して「大学の良いイメージ」に上手くスピンさせて学内外に発信した事例を紹介、IR室はデータの解釈を行わず解釈は受け手に任せるべき(IR室が時と場合によってデータや解釈を使い分けると経営陣が混乱、IRに対する信頼が低下)、AIRUM(AIRの地方支部)の年次大会において他大学のIR関係者に尋ねても広報室がスピンドクターの役割を担当しているとの回答があった、学内主要関係者へのレポート提出の方法について紹介あり(エグゼクティブサマリー(メール冒頭)+表のみの4ページのレポート)、IR室では学内レポートのほとんどにエグゼクティブサマリーを付けている;大学評価コンソーシアムからの案内で知る)
- 窪内節子(2009).大学退学とその防止に繋がるこれからの新入生への学生相談的アプローチのあり方 山梨英和大学紀要,8,9-17.[PDF](読売新聞「大学の実力」でとくに入学から1年での退学率の高さが明らかになった、学生相談担当者や学生部関係者が行ってきたこと・・・主に退学率改善のため:居場所作り・メンタルサポート・人間関係作り・生活支援・経済的支援、学力向上のため:担任制・少人数制・習熟度別クラス編成・個別学習指導・添削指導など、しかしそれらは大学側が必要と考えて提供しているものであって実際に学生が求めているかは不明、そこで大学新入生を対象とした退学防止に関するこれまでの心理学的研究の知見を基に[新入生のニーズに則した学生相談的アプローチとしての在り方]を検討、大学退学者に関する心理学的な研究はほとんど行われてこなかった(個々の大学における事例的研究を除く)、理由は大学退学率が問題になったのが最近であるため・退学者の実態調査が困難であるためなど、大学退学に関する研究は①臨床心理学的・精神医学的アプローチ(大学生活への不適応の改善を目的とした事例研究、蓄積はあるが退学に焦点を当てた研究はほとんどない)と②社会心理学的・社会学的アプローチの2つに大別できる、「大学退学に対する大学環境要因の影響力の分析」(丸山,1984)は②の最初の論文と考えられる、「学生の休学・退学について」(西村・中村,2000)は休学・退学を減少させるために精神障害ではない理由から大学不適応に陥る学生への支援が重要としている、小塩ら(2007a、2007b)はUPI(University Personality Inventory)得点から大学退学者の特徴を検討し身体的な症状に着目する視点を示した(多くの大学で行われている新入生への退学防止プログラムは大学適応に関するもので進退問題への援助に関するものは少ない)、「大学のカウンセリング・サービスに対する学生のニーズとその構造」(金沢・山賀,1998)は学生が学生相談室でどのような事柄を相談したいかを調査⇒従来から論じられている心理的・情緒的事柄への援助が必要+開発的・教育的援助のニーズも必要(1年生の段階でのガイダンス・サービスなど進路に関する援助が求められている)、「大学新入生における適応感の検討」(山田,2006)は入学直後からの欠席と大学違和感により意欲減退感が大学不適応→休学・退学へと繋がる可能性を示唆、森田・岡本(2006)と森田(2006)は学生相談室員による大学新入生向けの大学適応促進のための講義(正規授業)を検討し早期に大学不適応新入生への援助が必要と言及、先行研究から見えてくること:退学や休学に繋がる大学不適応は特別なものではない、大学が学生の状態や動向に注目したシステムやきめ細かい学生援助を提供することが求められている、著者が考える大学新入生に対する学生相談的アプローチ:①学生相談担当者が正規授業の中で出前授業を実施、②大学入学以前から新入生援助を開始、③[入学後できるだけ早期に授業欠席者や成績不良者を発見するシステム]を構築、④成熟促進のためのグループワーを実施;CiNii Articles「退学」で知る)
- 伊藤武彦・井上孝代(1999).留学生の中途退学者の全国調査 学生相談研究,20(1),38-48.[PDF](外国人留学生を対象にして日本の大学からの中途退学者の実態を調査、411高等教育機関に質問紙を送付、115大学380人の学部・大学院の中退事例が寄せられた、学部生の中途退学は経済的理由・不適応の理由が多い、大学院生の中途退学は日本の大学院のシステムの構造的問題点によって説明される事例が多い;CiNii Articles「退学」で知る)
- 林田雅希・鷺池トミ子・湯川幸一(2000).新入生健診結果と休・退学、留年および卒業との関連性 全国大学メンタルヘルス研究会報告書,22,81-83.[PDF](長崎大学の事例、精神科医による入学時の面接・入学時の性格検査(MPI)・休退学などの調査資料の関連性を検討、入学4年後に卒業しなかった学生について休学・退学・留年のいずれであるかを確認、MPIからみた性格傾向の差ではなく医師面接の判断が卒業・退学と関連することが示唆された;CiNii Articles「退学」で知る)
- 柳澤健・新田收・笠井久隆・猫田泰敏・飯田恭子・菊池恵美子・長田久雄・福士政広・齋藤秀敏・福田賢一(2000).東京都立医療技術短期大学生の入学・在学時成績と医療系国家試験合否との関係 東京保健科学学会誌,2(4),276-281.[PDF](入学・在学時成績と医療系国家試験合否との関係を統計学的に6つに分けて分析、そのうちの1つ入学選抜方法(一般入試・選抜入試)と退学・除籍者数では推薦入学の方が退学・除籍者が多い傾向が見られた、対象者:平成2~7年度入学の全学生1,132名(卒業者数:1,105名、退学・除籍者数:27名);CiNii Articles「退学」で知る)
- 河野銀子(2003).大学大衆化時代における'First-Generation'の位相 山形大學紀要. 教育科學,13(2),33-49(127-143).[PDF](アメリカの大学におけるFirst-Generationについての調査研究を解説、日本におけるFirst-Generationについての調査結果を報告(1大学の事例)、First-Generation学生に見られたこと(抜粋):大学からの離脱につながりやすい傾向が見受けられた(退学を考えたことが多い・勉学面での悩みを抱えている・大学での出来事を両親に話せないなど)、調査対象は低レベルではない学生であったにも関わらず大学からの離脱傾向を潜在的に持っているという結果は日本の高等教育機関においてもFirst-Generation学生の問題が顕在化しつつあると見た方がよいかもしれない;CiNii Articles「退学」で知る)
- 宮田正和・飯田一惠・濱崎麻由美(2004).教員養成大学における休学・退学理由の現状について 心身医学,44(7),520.[PDF](休学・退学の理由の大半は「一身上の都合」であるが実際には種々の理由があると考えられる、福岡教育大学における平成13年度の休学・退学届けの理由(「一身上の都合」が最も多かった)を再検討・再分類した、結果(抜粋)・・・休学:経済的理由が多かった、退学:志望・進路変更が半分以上を占めていた、考察:「一身上の都合」を鵜呑みにせず内容の十分な検討が必要など;CiNii Articles「退学」で知る)
- 大谷晃也(2005).文科系学生の数学の基礎学力と退学率、就職率 研究論集,82,191-197.[PDF](1学期の数学のテスト成績によって退学率・就職率に差が出たかを検証(対象:著者の数学の授業を受けた1大学の学生、1992・1993年度の296名+1996年度・1997年度の526名)、数学の基礎学力が低い学生は大学の授業についていけず退学者が多くなる・SPIなどで足切りをされて就職率が下がると推測、結果・・・退学率・就職率:数学の成績が悪いほど悪かった;CiNii Articles「退学」で知る)
- 馬込武志・尾崎剛志(2008). 学生の退学要因と退学回避の方策について:卒業時アンケートを参考にして 湊川短期大学紀要,44,69-74.[PDF](大学等の退学を扱った研究をレビュー⇒[入学前に持っていた学生生活のイメージ]と[実際の学生生活]のギャップを埋める+キャリアガイダンス(卒業後の将来設計を含む)を入学前後に行う+学生と教員の相互作用を強化するなど、湊川短期大学生活福祉専攻の学生に対して行っている卒業時アンケートの結果に基づき学生がどのように退学願望を乗り越えているのかを検討+退学を回避するためにどのような学生支援をすべきかを検討⇒学生と親の関係の重要性が明らかになった(従来の退学研究ではあまり取り上げられていない)、入学決定時に親が学生とどのような関わり合いを持つかが学生生活の安定度に影響を及ぼしていた、学校-学生-親のつながりを築くことが重要;CiNii Articles「退学」で知る)
- 村上嘉津子(2007).変革期の大学と学生、学生相談担当者の視点:退学勧告制度と関係性の醸成 京都大学カウンセリングセンター紀要,36,17-27.[PDF](日本で退学勧告制度が話題になったのは1998年の大学審議会答申「21世紀の大学像と今後の改革方策について」で「厳格な成績評価」の例としてGPAが取り上げられてから;CiNii Articles「退学」で知る)
[2016.01.05]IRなどについての文献メモ 文献一覧を更新<IR>
- 藤原宏司(2016).「スピンドクターとしてのIR」に関する一考察 大学評価とIR,5,3-7.[PDF](大学評価コンソーシアムからの案内で知る)
[2016.01.05]IRなどについての文献メモ 文献一覧を更新<中途退学、リテンション、Tinto>
- Tinto, V. (2006). Research and practice of student retention: What next? Journal of college student retention: Research, theory & practice, 8(1), 1-19.[PDF]
- Tinto, V. (2014). Tinto's south africa lectures. Journal of student affairs in africa, 2(2), 5-28.[PDF]("Selected publications of Vincent Tinto"を含む;Google Scholar「著者:"Vincent Tinto"」で知る)
- Davidson, C., & Wilson, K. (2013). Reassessing Tinto's concepts of social and academic integration in student retention. Journal of college student retention: Research, theory & practice, 15(3), 329-346.[Abstract](Journal of college student retention: Research, theory & practiceのサイト内検索「Tinto」で知る)
- Metz, G. W. (2004). Challenge and changes to Tinto's persistence theory: A historical review. Journal of college student retention: Research, theory & practice, 6(2), 191-207.[Abstract](Journal of college student retention: Research, theory & practiceのサイト内検索「Tinto」で知る)
- Longwell-Grice, R., & Longwell-Grice, H. (2008). Testing Tinto: How do retention theories work for first-generation, working-class students? Journal of college student retention: Research, theory & practice, 9(4), 407-420.[Abstract](Journal of college student retention: Research, theory & practiceのサイト内検索「Tinto」で知る)
- Tucker, J. E. (1999). Tinto's model and successful college transitions. Journal of college student retention: Research, theory & practice, 1(2), 163-175.[Abstract](Journal of college student retention: Research, theory & practiceのサイト内検索「Tinto」で知る)
- Karp, M. M., Hughes K. L., & O'Gara, L. (2010). An exploration of Tinto's integration framework for community college students. Journal of college student retention: Research, theory & practice, 12(1), 69-86.[Abstract](Journal of college student retention: Research, theory & practiceのサイト内検索「Tinto」で知る)
- Nora, M. (2001). The depiction of significant others in Tinto's "rites of passage": A reconceptualization of the influence of family and community in the persistence process. Journal of college student retention: Research, theory & practice, 3(1), 41-56.[Abstract](Journal of college student retention: Research, theory & practiceのサイト内検索「Tinto」で知る)
[2016.01.04]IRなどについての文献メモ 文献一覧を更新<比較教育学>
- 山内乾史(2011).比較教育学とはどのような学問か:高等教育研究からの視点 日本比較教育学会(編)比較教育学とはどのような学問か 比較教育学研究,42,159-168.(Amazon.co.jp「比較教育学」で知る)
[2016.01.04]IRなどについての文献メモ 内容をアップ
- 浅野茂(2015).「IRの4つの顔」から見える日本の大学のIR像 大学評価とIR,4,43-50.[PDF](「大学評価担当者集会2015」のワークショップについての事例報告、ワークショップの構成:Volkwein(1999)が提示する「IRの4つの顔(または立ち振る舞い)」を用いて①概念・考え方を解説・②大学評価への活かし方を解説・③参加者間で業務に照らして議論、IRの4つの顔:①情報精通者としてのIR・②政策分析者としてのIR・③スピンドクターとしてのIR・④学者・研究者としてのIR、グループワークの結果(参加者が付箋に[従事している]または[今後従事したい]評価やIRの業務を記入):情報精通者(Volkwein(1999)で重要な位置付け)>政策分析者>スピンドクター>学者・研究者、ワークショップの結果を見ると日本でも「情報精通者としてのIR」が重要(Volkwein(1999)は米国のIRを前提にした枠組み)、参加者の回答を見ると「情報精通者としてのIR」を担っているというよりは今後担っていく上での課題と捉えている;大学評価コンソーシアムからの案内で知る)
[2016.01.04]IRなどについての文献メモ 文献一覧を更新<IR>
- 藤井律子(2015).広島文教女子大学における教学IR活動の展望 広島文教女子大学高等教育研究,1,5-14.[PDF](IRの歴史、日本の教学IRの現状、広島文教女子大学の教学IRの状況、今後の課題と展望(データ一元化の必要性・統合的データ管理システムの整備など);Twitter(@ikthrさん)で知る)
[2015.12.31]IRなどについての文献メモ 内容をアップ
- 佐藤仁(2015).IR人材に求められる力量からIR組織に求められる知性へ:テレンジーニ(Patrick T. Terenzini)による3つの知性論の再検討 大学評価とIR,4,35-42.[PDF](テレンジーニの「3つの知性」の内容を概説・・・上位の層には下位の層の知性が必要、1層:専門的/分析的知性、第2層:問題に関する知性、第3層:文脈に関する知性、2013年論文の概説・・・第1層:現在でも通用・基礎的、テクノロジーの発展によって調査目的よりもツールに価値を見出してしまう可能性、第2層:主要な問題領域に変化はない、ただしトピックが多様化(アカウンタビリティのための評価、非伝統的学生、研究生産性分析など)、第3層:「文脈」の意味をより広範に捉える必要がある(勤務大学だけではなく高等教育の外的環境の変化)、日本の文脈を踏まえた3つの知性の解釈・・・IR担当者ではなくIR組織に帰属するものと理解することが必要、3つの知性は直線的な関係にないという点をきちんと理解する必要がある(第1層がなければ第2層がないという階層的な図式を日本においても順守することは現実的ではない、米国の文脈だからこそ階層的)、組織として「どこが欠けているのか」を常に問いながら組織的な知性も高めていくことが日本のIRにおいては重要、[借用対象である国・地域の教育事情の正確な理解]と[自国の現状の理解]を踏まえた上で借用対象を解釈して実践を考える必要がある;大学評価コンソーシアムからの案内で知る)
[2015.12.31]IRなどについての文献メモ 文献一覧を更新<比較教育学、教育借用>
- Takayama, K. (2014). Global "diffusion," banal nationalism, and the politics of policy legitimation: A genealogical study of "zest for living" in Japanese education policy discourse. In P. Alasuutari, & A. Qadir(Eds.) National policy-making: Domestication of global trends. Abingdon, Oxon, UK: Routledge. pp.129-146.(教育借用について書かれた文献;佐藤(2015)「IR人材に求められる力量からIR組織に求められる知性へ」で知る)
- 田中正弘(2005).教育借用の理論:最新研究の動向 人間研究,41,29-39.[PDF](CiNii Articles「教育借用」で知る)
- 長島啓記(編著)(2014).基礎から学ぶ比較教育学 学文社(比較教育学の歴史・理論・方法についての章あり;Amazon.co.jp「教育借用」で知る)
- 日本比較教育学会(編)(2011).比較教育学とはどのような学問か 比較教育学研究,42.(Amazon.co.jp「比較教育学」で知る)
- 沖原豊・小沢周三(1991).比較教育学研究の回顧と展望 比較教育学研究,17,155-166.[PDF](Amazon.co.jp「比較教育学」で知る)
- 佐々木毅(1991).比較教育学研究の回顧と展望:日本 比較教育学研究,17,208-219.[PDF](CiNii Articles「比較教育学研究の回顧と展望」で知る)
- 北村友人(2005).比較教育学と開発研究の関わり 比較教育学研究,31,241-252.[PDF](Google Scholar「比較教育学」で知る)
- 北村友人(2011).政策科学としての比較教育学:教育開発研究における方法論の展開 教育學研究,78(4),361-373.[PDF](Google Scholar「比較教育学」で知る)
[2015.12.30]IRなどについての文献メモ 文献一覧を更新<IR>
- 佐藤仁(2015).IR人材に求められる力量からIR組織に求められる知性へ:テレンジーニ(Patrick T. Terenzini)による3つの知性論の再検討,大学評価とIR,4,35-42.[PDF][概要](大学評価コンソーシアムからの案内で知る)
- 浅野茂(2015).「IRの4つの顔」から見える日本の大学のIR像,大学評価とIR,4,43-50.[PDF](大学評価コンソーシアムからの案内で知る)
[2015.12.28]IRなどについての文献メモ 文献一覧を更新<IR>
- 末次剛健志(2015).第3期中期目標期間の計画策定や評価対応に向けたIR業務の在り方の検討 大学評価とIR,4,26-34.[PDF](佐賀大学における第3期中期目標・中期計画に関するこれまでの検討状況、IR業務として今後対応することになる中期目標・中期計画に関連する進捗管理や自己点検・評価業務の支援の在り方;大学評価コンソーシアムからの案内で知る)
-
[2015.12.26]IRなどについての文献メモ 文献一覧を更新<中途退学、リテンション>
- Knoell, D. M. (1960). Institutional research on retention and withdrawal. In H. T. Sprauge(Ed.), Research on college students. Boulder: Western Interstate Commission for Higher Education.(中途退学関連の文献を4つに分類、①調査(census studies、大学内・間の退学・転学・リテンション率を記述する)・②事後の分析(autopsy studies、退学した学生の自己申告による理由を通した分析)・③個々の事例(case studies、入学時点でリスクありと判断された学生の長期追跡調査)・④予測(prediction studies、入学時点の要素を使って大学での成功を予測);Spady(1970)"Dropouts from higher education: An interdisciplinary review and synthesis"で知る)
- Marsh, L. M. (1966). College dropout: A review. The personnel and guidance journal, 44(5), 475–481.[Abstract](中途退学関連の文献を3つに分類、①理論(philosophical and theoretical studies、退学を防ぐべきものとして対策を勧める)・②記述(descriptive studies、退学者の特徴を記述、学生生活の様子・退学理由)・③予測(predictive studies、Knoell(1960)の分類「予測」と同様);Spady(1970)"Dropouts from higher education: An interdisciplinary review and synthesis"で知る)
[2015.12.25]IRなどについての文献メモ 内容をアップ
- 白井靖敏(2015).学生の学修行動に関する間接評価 名古屋女子大学紀要.家政・自然編,人文・社会編,61,143-152.[PDF](ある学科の2・3年生を対象に1日の平均生活時間(授業、予習・復習、自主学習、アルバイト、サークル活動など)などを無記名式アンケートで調査した(有効回答数:98名)、結果:勉強していない(全国的な調査結果との差異はほとんどなし)、考察:単にキャップ制を強化して大学設置基準21条に沿った改善をしても効果が小さい、むしろ各授業において学生の自主的な学習を促すきめ細かい授業改善が必要(調査項目の「勉強していない理由」より);Google Scholarの引用元機能(谷村・金子(2009)「学習時間の日米比較」)で知る)
- 畑野快(2014).大学生の主体的な学修態度の形成に関する実証的研究 京都大学博士論文[PDF](大学生の授業外学修時間を増加する取り組みが大学に推奨される機運が高まりつつある、しかし主体的な学修態度という質的な側面については十分に議論されていない、そこで大学生の主体的な学修態度を適切かつ明確に定義・測定、その形成を促す心理的要因を明らかにする、これまでの授業外学修時間と学修成果の関係を検討した実証的研究に対する疑問:①授業外学修時間は学修成果に寄与しているものの影響力は極めて小さい(標準偏回帰係数の値が非常に小さい)・学修時間の測定は単純に拘束時間(量的側面)の測定に留まっている可能性、②学修時間に着目するだけでは質的側面を明らかにすることはできない可能性;CiNii Articles「谷村英洋」で知る)
[2015.12.25]IRなどについての文献メモ 文献一覧を更新<学習時間、学修時間>
- 谷村英洋・金子元久(2009).学習時間の日米比較 IDE:現代の高等教育,515,61-65.(中山(2013)「アクティブ・ラーナーを育てる能動的学修の推進におけるPBL教育の意義と導入の工夫」で知る)
- 白井靖敏(2015).学生の学修行動に関する間接評価 名古屋女子大学紀要.家政・自然編,人文・社会編,61,143-152.[PDF][概要](Google Scholarの引用機能(谷村・金子(2009)「学習時間の日米比較」)で知る)
- 谷村英洋(2013).休暇中の大学生 IDE:現代の高等教育,553,60-66.(CiNii Articles「谷村英洋」で知る)
- 谷村英洋(2010).大学の教員が想定している授業外学習の時間 大学教育学会誌,32(2),87-94.(CiNii Articles「谷村英洋」で知る)
- 畑野快(2014).大学生の主体的な学修態度の形成に関する実証的研究 京都大学博士論文[PDF][概要](CiNii Articles「谷村英洋」で知る)
- 東京大学大学院教育学研究科大学経営・政策研究センター(2008).全国大学生調査第1次報告書[PDF](2007年に全国127大学288学部44,950名を調査、1日あたり4.6時間、そのほとんどが授業に出席する時間で占められている(授業出席時間(卒業論文に関わる時間含む):3.6時間、授業関連学修時間1.0時間);畑野(2014)「大学生の主体的な学修態度の形成に関する実証的研究」で知る)
- Astin, A. W. (1984). Student involvement: A developmental theory for higher education. Journal of college student personnel, 25(4), 297-308.[PDF](学修時間の長さと成績などの学修成果との間に正の関連を示す結果;畑野(2014)「大学生の主体的な学修態度の形成に関する実証的研究」で知る)
- Brint, S., & Cantwell, A. M. (2010). Undergraduate time use and academic outcomes: Results from the University of California Undergraduate Experience Survey 2006. Teachers College Record, 112(9), 2441-2470.[PDF](学修時間の長さと成績などの学修成果との間に正の関連を示す結果;畑野(2014)「大学生の主体的な学修態度の形成に関する実証的研究」で知る)
- Brint, S., Cantwell, A. M., & Hanneman, R. A. (2008). The two cultures of undergraduate academic engagement. Research in Higher Education, 49(5), 383-402.(学修時間の長さと成績などの学修成果との間に正の関連を示す結果;畑野(2014)「大学生の主体的な学修態度の形成に関する実証的研究」で知る)
- 西垣順子(2008).初年次学生の「質」に関する調査報告:学生による質評価と成績評価、自主学習との関連 大阪市立大学大学教育,6(1),1-8.[PDF](授業外学習の時間が長い学生ほど評定が高い、分析対象は1年生のみ;谷村英洋(2011)「大学生の学習時間と学習成果」で知る)(学修時間と汎用的技能の関連を示す結果(アメリカと類似)、大学生2,720名を対象とした質問紙調査、1週間あたりの勉強や宿題にかける時間と汎用的技能の獲得感との関係を検討、週6時間以上の学生はそうでない学生よりも汎用的技能の獲得感が高かった;畑野(2014)「大学生の主体的な学修態度の形成に関する実証的研究」で知る)
- 金子元久(2012).大学教育と学生の成長 名古屋高等教育研究,12,211-236.[PDF](Google Scholar「学習時間 意欲 大学」で知る)(授業外学修時間と汎用的能力の関係を重回帰分析で検討した、獲得感に寄与する可能性、東京大学大学院教育学研究科大学経営・政策研究センターによる全国大学生調査のデータを使用;畑野(2014)「大学生の主体的な学修態度の形成に関する実証的研究」で知る)
- 小方直幸(2008).学生のエンゲージメントと大学教育のアウトカム 高等教育研究,11,45-64.(大学教育のアウトカムを重視する傾向が強まっている;山田・森(2008)で知る)(授業外学習の合計時間が汎用的技能および学問的知識の獲得に有意な影響を与えている;谷村英洋(2011)「大学生の学習時間と学習成果」で知る)(桜美林大学シラバス検索で知る[桜美林大学大学院大学アドミニストレーション研究科の提供科目])(①入学前の学習・学修習慣・②教育プログラムの特性が学生のエンゲージメント(授業外学習時間)を支えている可能性、授業外学修時間が学修成果を予測する可能性、重回帰分析・パス解析を用いて検討、東京大学大学院教育学研究科大学経営・政策研究センターによる全国大学生調査のデータを使用;畑野(2014)「大学生の主体的な学修態度の形成に関する実証的研究」で知る)
- 山田礼子(2009).アセスメントの理論と実践 山田礼子(編著)大学教育を科学する:学生の教育評価の国際比較 東信堂 pp.13-38.(学修時間と汎用的技能の関連について実証的に検討、機関の環境(学年・専門分野)は学生の関与(努力の質(学修時間)・努力の量など・経験・適応)に正の影響を与える、学生の関与は学修成果に正の影響を与える影響、重回帰分析を用いた、2005~2006年に国公私立大学8校の大学生3,961名からの回答を使用;畑野(2014)「大学生の主体的な学修態度の形成に関する実証的研究」で知る)
- 溝上慎一・中間玲子・山田剛史・森朋子(2009).学習タイプ(授業・授業外学習)による知識・技能の獲得差違 大学教育学会誌,31(1),112-119.(学修内容と卒業後のキャリアが直結する学部系統は比較的高い汎用的技能を持っている、大学教育改革は[正課・正課外を含むトータルな視点]や[学生の成長・発達という視点]から捉えていく必要がある、またその研究・実践を蓄積していく必要がある;山田・森(2008)で知る)(生活時間(学習・友人との交際・アルバイト・サークルなど)を基準に高群・低群に分類、それに基づき大学生を8つのタイプに分類、授業内学修・授業外学修に加えて交際やアルバイトなど様々な活動に時間を費やす学生タイプは汎用的技能(コミュニケーション能力・起業能力など)の獲得感が高い;畑野(2014)「大学生の主体的な学修態度の形成に関する実証的研究」で知る)
- 山田剛史・森朋子(2010).Evidenceに基づく初年次教育プログラムの構築:モデル授業の効果検証を踏まえて 初年次教育学会誌,2(1),56-63.(沖・岡田(編著)(2011).『データによる大学教育の自己改善:インスティテューショナル・リサーチの過去・現在・展望』で知る)([授業内・外学修=正課内活動]・[アルバイトやサークルなど=正課外活動]とした上で費やした時間から学生タイプを作成、正課内だけでなく正課外活動に時間を費やす学生タイプは汎用的技能の獲得感が高い;畑野(2014)「大学生の主体的な学修態度の形成に関する実証的研究」で知る)
- 蒋妍(2010).授業外学習を促す授業実践の研究 大学教育学会誌,32(1),134-140.(授業で出される課題が大学生の授業外学修時間に与える影響を検討、教員が課題を出すことは大学生の授業外学修時間を促す可能性、ビデオ観察・インビュー調査を用いた;畑野(2014)「大学生の主体的な学修態度の形成に関する実証的研究」で知る)
- 吉田博・戸川聡・金西計英(2011).大学の授業における学生が授業外学習を行う要因 日本教育工学会論文誌,35(Suppl.),153-156.[PDF](CiNii Articles「学習時間」で知る)(大学生が授業外学修を行う動機について尋ねた、その記述を分類、結果:授業外学修時間を促す要因として①授業内容のレベル・②課題・③教材・資料・④学生同士の関係構築・⑤学生が主体的に取り組む授業設計が見出された;畑野(2014)「大学生の主体的な学修態度の形成に関する実証的研究」で知る)
- 清水一彦(1998).日米の大学単位制度の比較史的研究 風間書房(学修時間はあくまで学修に費やした時間を表しているにすぎない、その測定からは学習にどのように取り組んだのかという学修態度は明らかにならない;畑野(2014)「大学生の主体的な学修態度の形成に関する実証的研究」で知る)
- 森利枝(2011).単位制度から見る教授学習・カリキュラム 京都大学高等教育研究,17,140-149.[PDF](アメリカでは時間で学修成果を測定することへの限界が指摘されている、単位制度とは異なった評価システムを構築することの重要性が指摘されている;畑野(2014)「大学生の主体的な学修態度の形成に関する実証的研究」で知る)
[2015.12.25]IRなどについての文献メモ 文献一覧を更新<アクティブラーニング>
- 中山留美子(2013).アクティブ・ラーナーを育てる能動的学修の推進におけるPBL教育の意義と導入の工夫 21世紀教育フォーラム,8,13-21.[PDF](弘前大学のFDワークショップの講演内容を基に「アクティブ・ラーニング(能動的学修)」推進のためのPBL教育の導入について論じる、心理学的な視点からの説明を行う、PBL教育を導入する際の困難や具体的な工夫を紹介;Google Scholar「学修時間」で知る)
[2015.12.24]IRなどについての文献メモ 内容をアップ
- 濱中淳子(代表)(2013).大衆化する大学:学生の多様化をどうみるか 岩波書店(「大衆化した大学」を捉えるための3つの論点:①大衆化の担い手・②葛藤の源泉([多様化する学生から突きつけられる改革への要求]と[保守的な大学内部])・③「エリート段階の教育」のゆくえ(日本において何を「エリート段階の教育」と見なすか)、学生論でしばしば取り上げられる事情は部分的現象・事実誤認、各年代の特徴:<1960年代まで>教育機会の拡大で学習行動や家計収入などにおいてエリート的というべき学生層の諸特性が融解・<1990年代以降>再拡大期(ユニバーサル段階への移行期)で学生層に多様な側面、大学進学率の上昇により直ちに学生の学力水準の低下がもたらされているとは言えない(学力上・中・下位層別の進学率の変化を検証)、すぐに役立つことを求めるため従来型の大学教育観・学生観から見ると「学ぶ意欲・関心の低下」と映る;Amazon.co.jp「学生 多様化」で知る)
[2015.12.24]ホーム「お知らせ」欄を変更
- 連載企画記事(『文部科学教育通信』誌の「大学IRの今」)の予定を掲載
[2015.12.24]IRなどについての文献メモ 文献一覧を更新<IR、留年、GPA>
- 嶌田敏行(2015).留年してしまう学生の効率的・効果的な検出方法についての検討 大学評価とIR,4,18-25.[PDF](数量的なデータから「留年しそうな学生」を検出、学生のGPAを連続的に点検する方式が一定程度有効、現象にのみ着目し一概に留年を否定しない;大学評価コンソーシアムからの案内で知る)
[2015.12.24]IRなどについての文献メモ 内容をアップ
- 神田悟(2015).単科大学で実践できるIR(Institutional Research)とは 2015年度SDゼミナールレポート集,50-56.(単科大学(京都薬科大学)でのIR活動の特徴・長所:教務課が単独で活動できる範囲だったのでスピーディーにデータ分析ができた、トップダウンが徹底しやすい(総合大学では学部間の調整が必要)、別々の部署(教務課と学生課)で管理されたデータを集約しやすい、IR実践のポイント:目的・役割・手順を明確にする・・・活動範囲を認証評価活動の支援に絞る、データ集約体制を構築するために各部署に1名ずつIR委員を任命(それぞれが自部署のデータを持ち寄る)、事例校でのIRの定義「報告のためのデータを一元管理すること」、集めるデータの範囲は大学基準協会が指定する評価項目(データ項目の選定で迷わないというメリット)、活動目的はデータ収集であり調査・分析には踏み込まない(高度な専門知識は不要)、定型業務の延長として推進する(抵抗感・負担感を減らす);大学コンソーシアム京都からの出版物送付で知る)
[2015.12.22]IRなどについての文献メモ 文献一覧を更新<IR>
- 大学基準協会(編)(2015).大学評価論の体系化に関する調査研究報告書 大学基準協会(大学基準協会からの出版物送付で知る)
[2015.12.22]IRなどについての文献メモ 文献一覧を更新<IR>
- 神田悟(2015).単科大学で実践できるIR(Institutional Research)とは 2015年度SDゼミナールレポート集,50-56.[概要](大学コンソーシアム京都からの出版物送付で知る)
[2015.12.22]「私立大学職員によるIR文献メモ」メルマガ バックナンバーを更新
[2015.12.19]IRなどについての文献メモ 文献一覧を更新<IR、学生調査>
- 今尾真(2015).『第14回学生生活実態調査』から読み解く現代学生像 大学時報,365,16-21.[PDF](はてなブックマークで知る)
- 日本私立大学連盟学生委員会(編)日本私立大学連盟(監修)(2015).私立大学学生生活白書2015 日本私立大学連盟[PDF](進学目的はこれまでの3回の調査(2006、2010、2014)で「大学卒の学歴が必要」が常に1位、収入は「家族などからの援助」が減少し「アルバイト・定職収入」が増加、大学生活で「友人との交際」が低下+正課外活動の参加目的で「友人を得る」・「学生生活を楽しむ」が大きく減少→孤立化が進んでいる、相談相手は友人が減少・家族が増加・大学(教職員・相談室)の利用は低い;今尾真(2015)「『第14回学生生活実態調査』から読み解く現代学生像」で知る)
[2015.12.17]IRなどについての文献メモ 文献一覧を更新<統計>
[2015.12.17]IRなどについての文献メモ 文献一覧を更新<IR>
- 小湊卓夫・嶌田敏行(2015).IR その着実な一歩のために:第2回 担当者に求められるのは高度な分析力か? Between,262,25-27.[PDF]
- 小湊卓夫・嶌田敏行(2015).IR その着実な一歩のために:<鈴鹿医療科学大学>第3回 確実な一歩を踏み出した"データで議論する"しくみ Between,263,25-27.[PDF]
- 小湊卓夫・嶌田敏行(2015).IR その着実な一歩のために:第4回 創価大学 トップの意思決定を支える目的遂行型の組織編成がカギ Between,264,25-27.[PDF]
- 小湊卓夫・嶌田敏行(2015).IR その着実な一歩のために:第5回 琉球大学 多方面から意思決定をサポートできる「包括的IR」の構築をめざす Between,265,27-29.[PDF]
- 伊多波良雄・山﨑その・宮嶋恒二(2015).「第2回大学経営効率化」に関するアンケート調査結果 Discussion Paper Series,2015-02.[PDF](大学経営効率化研究会からの案内メールで知る)
[2015.12.16]IRなどについての文献メモ 内容をアップ
- Cooper, H. (2003). Editorial. Psychological bulletin, 129, 3-9.[内容](シルヴィア(2015)『できる研究者の論文生産術』で知る)
[2015.12.16]IRなどについての文献メモ 文献一覧を更新<文献レビュー書き方>
- Cooper, H. M. (1982). Scientific guidelines for conducting integrative research reviews. Review of educational research, 52(2), 291-302.[
[2015.12.15]IRなどについての文献メモ 文献一覧を更新<中途退学、リテンション>
- 小林志津子・小山弘・新保卓郎(2008).日本の医学部及び医学系大学院に学ぶ女性の出産時休暇の現況 医学教育,39(3),183-186.[PDF](CiNii Articles「退学」で知る)
[2015.12.14]「私立大学職員によるIR文献メモ」メルマガ バックナンバーを更新
[2015.12.11]「過去の「お知らせ」」に追加
- 西九州大学短期大学部「平成26年度未来経営戦略推進経費(教学改革推進のためのシステム構築・職員育成)」(日本私立学校振興・共済事業団、平成26~28年度)平成27年度外部評価[取り組みの概略(PDF)]
-
[2015.12.11]「過去の「お知らせ」」、「IRなどについての文献メモ」、「これまでの発表・競争的研究資金など」に追加
- 橋本智也(2015).授業アンケートを教育改善サイクルに活用する:回答率を向上させ、学生から建設的な意見を得るための工夫 大学評価とIR,4,3-17.[PDF]
[2015.12.10]IRなどについての文献メモ 文献一覧を更新<IR>
- 鎌田浩史(2015).学士課程教育におけるジェネリックスキルに関する考察:関東学院大学の2014年度新入生を対象に 関東学院大学高等教育研究・開発センター年報,1,7-17.
- 杉原亨・奈良堂史(2015).体育会学生の学習動機とキャリア形成に関する一考察 関東学院大学高等教育研究・開発センター年報,1,19-29.
[2015.12.08]IRなどについての文献メモ 文献一覧を更新<組織論>
- バーナード,C.I.山本安次郎・田杉競・飯野春樹(訳)(1986).経営者の役割 ダイヤモンド社(組織が生成・存続していくために必要な要素、協働意思・共通目的・コミュニケーション;佐々木圭吾(2013)『みんなの経営学:使える実戦教養講座』で知る)
- 森下伸也・君塚大学・宮本孝二(1998).パラドックスの社会学 新曜社(「意図せざる結果」、ある意図や目的をもってとられた行動が生じさせた予想外の思いもよらなかった事態や結末;佐々木圭吾(2013)『みんなの経営学:使える実戦教養講座』で知る)
[2015.12.05]IRなどについての文献メモ 文献一覧を更新<SD>
- 加藤毅(2015).大学職員の人材形成プロセスとSD 大学研究,41,17-27.[PDF](今後求められる大学マネジメント人材に必要とされる高度なスキルや知識を習得するための学習プロセス、大学職員に特化した議論から一旦離れて一般的な大卒総合職の人材形成プロセスの研究を援用;Google Scholarアラート「インスティテューショナル・リサーチ」で知る)
[2015.12.04]IRなどについての文献メモ 文献一覧を更新<中途退学、リテンション>
- 奥村武久・河原啓・長井勇(1985).大学の精神衛生の分野に於ける関心の推移:全国大学保健管理研究集会報告書に見られる論題に限定して 神戸大学保健管理センター年報,10,57-65.[PDF](CiNii Articles「退学」で知る)
- 中村真・松田英子(2013).大学生の学校適応に影響する要因の検討 江戸川大学紀要,23,151-160.[PDF](CiNii Articles「退学」で知る)
- ブラウンホワード,W.(1950).何故中途退学するか エデュケーション・ダイジェスト,1(5),34-36.(CiNii Articles「退学」で知る)
- 藤林益三(1950).私立学校退学処分の法律上の性質とその効力の判定(民事々件):判例研究 判例タイムズ,1(4),31-33.(CiNii Articles「退学」で知る)
- 長崎文次(1952).退学処分について 信濃教育,786,13-17.(CiNii Articles「退学」で知る)
- 青木宗也(1953).会社附属学校の退学処分の効力と雇傭関係の有無 季刊労働法,9,91-97.(CiNii Articles「退学」で知る)
- 林修三(1954).退学処分と裁判所の審判権 時の法令,151,36-39.(CiNii Articles「退学」で知る)
- 大友成彦(1955).退学の真因 声,936,(不明).(CiNii Articles「退学」で知る)
- 大西芳雄(1955).公立大学生の退学処分 民商法雑誌,31(6),(不明).(CiNii Articles「退学」で知る)
- 竹中昭彦(1957).退学の理由 文芸首都,26(10),4-17.(CiNii Articles「退学」で知る)
- 成田頼明(1964).私立大学学生の在学関係とその退学処分の要件:昭和女子大事件(1) 法律のひろば,17(2),26-29.(CiNii Articles「退学」で知る)
- 成田頼明(1964).私立大学学生の在学関係とその退学処分の要件(2) 法律のひろば,17(3),23-27.(CiNii Articles「退学」で知る)
- 関口研日磨(1967).入学・退学・卒業:米国の州立大学と私立大学 大学資料,23,8-13.(CiNii Articles「退学」で知る)
- 和田英夫(1967).私立大学学生の退学処分問題:昭和女子大事件第一・二審判決を顧みて 判例時報,480,83-92.(CiNii Articles「退学」で知る)
- 宮口明義(1970).本学、四ケ年間における運動クラブ、一般学生の体力、運動能力の実態調査及び疾病、休学、退学の現状 金沢経済大学論集,4(1),87-112,表2枚.(CiNii Articles「退学」で知る)
- 松田明(1971).いつか来た道を嘆く防大退学者 潮,147,270-276.(CiNii Articles「退学」で知る)
- 土川隆史(1974).意欲減退学生について 厚生補導,95,7-13.(CiNii Articles「退学」で知る)
- 石村善治(1974).私立大学における思想・信条の自由と退学処分:昭和女子大事件(最判昭和49.7.19) 季刊教育法,14,86-95.(CiNii Articles「退学」で知る)
- 兼子仁(1974).私立大学が学生の政治活動を理由として退学処分を行なうことの可否:昭和女子大事件上告審判決(最判昭和49.7.19) 判例時報,756,140-144.(CiNii Articles「退学」で知る)
- 東条武治(1975).1.私立大学における学生の政治的活動に対する規制の合理性 2.学生の退学処分と学長の裁量権 3.私立大学の学生に対する退学処分の効力が是認された事例(最判昭和49.7.19) 民商法雑誌,72(6),1028-1043.(CiNii Articles「退学」で知る)
- 鶴光代(1976).休学・退学者にみられる不適応について 福岡教育大学紀要 第4分冊 教職科編,25,89-95,表1枚.(CiNii Articles「退学」で知る)
- 権藤与志夫(1977).留年と中途退学に関する統計的研究:ユネスコ・「再構成コーホート法」を中心に 教育と医学,25(3),248-256.(CiNii Articles「退学」で知る)
- 野辺地正之(1977).意欲減退学生の背景と対策 厚生補導,131,15-24.(CiNii Articles「退学」で知る)
- 坪根治広・田中洋(1978).高専における修学指導に関する一考察:留年退学について 工業教育,26(1),27-34.[PDF](CiNii Articles「退学」で知る)
- 大石真(1978).私立大学における学生の政治的活動に対する規制の合理性及び学生の退学処分と学長の裁量権(最判昭和49.7.19) 法学,42(1),118-122.(CiNii Articles「退学」で知る)
- 松原達哉(1980).就学不適応学生の原因とその対応について:留年・退学問題の立場から 厚生補導,164,17-27.(CiNii Articles「退学」で知る)
- 丸山文裕(1984).大学退学に対する大学環境要因の影響力の分析 教育社会学研究,39,140-153.[PDF](CiNii Articles「退学」で知る)
- 中村純五(1986).宮崎大学における休・退学、留年実態調査:昭和50~58年度 宮崎大学保健管理紀要,3,87-91.(CiNii Articles「退学」で知る)
- Pascarella, E. T., Terenzini P. T., & Wolfle, L. M.(1987).大学へのオリエンテーションと新入学生の学業継続・退学決定 広島工業大学研究紀要,21(25),39-52.(CiNii Articles「退学」で知る)
- 嶋崎素吉・上月英樹・山口直美(1989).大学生の不適応に関する精神医学的検討:筑波大学における休、退学学生の調査唐 筑波の環境研究,12,15-21.(CiNii Articles「退学」で知る)
- Gilbert, S. N., & Gomme, I. M.加沢恒雄(訳)(1990).自発的退学による大学の学生数減少に関する将来の方向 広島工業大学研究紀要,24,93-101.(CiNii Articles「退学」で知る)
- 伊藤勝志(1991).学生の退学状況及び精神健康調査の報告 人文論究,51,11-25.(CiNii Articles「退学」で知る)
- 原田啓次・宮脇幸治郎・伊藤詣二・片山登揚・新井宏忠・柴茂(1991).府立高専における留年・退学者に関する調査 大阪府立工業高等専門学校研究紀要,25,109-115.[PDF](CiNii Articles「退学」で知る)
- 尾崎節子(1991).長崎総合科学大学における退学状況について(1) 長崎総合科学大学紀要,32(2),317-332.[PDF](CiNii Articles「退学」で知る)
- 中島潤子・大学精神衛生研究会共同研究グル-プ(1993).大学における休・退学、留年学生に関する調査 第15報 大学精神衛生研究会報告書,15,33-46.(CiNii Articles「退学」で知る)
- 中島潤子(1994).大学における休・退学、留年学生に関する調査 第16報 大学精神衛生研究会報告書,16,21-31.(CiNii Articles「退学」で知る)
- 上野武治・深澤孝克・真木誠・大宮司信・末永義圓・丸谷隆明・村田和香・河野仁志・吉田直樹・八田達夫(1994).北海道大学医療技術短期大学部作業療法学科における学生異動の実態:開設以来10年間の入学者の留年・休学・退学を中心に 北海道大学医療技術短期大学部紀要,7,61-71.[PDF](CiNii Articles「退学」で知る)
- 中島潤子(1995).大学における休・退学、留学生に関する調査 第17報 全国大学メンタルヘルス研究会報告書,17,15-30.(CiNii Articles「退学」で知る)
- 中島潤子(1995).スチューデント・アパシーの行方:大学精神衛生研究会の「休・退学、留年学生に関する調査」から 大学と学生,357,11-16.(CiNii Articles「退学」で知る)
- 中島潤子・野村正文(1996).大学における休・退学、留年学生に関する調査 第18報 全国大学メンタルヘルス研究会報告書,18,99-117.(CiNii Articles「退学」で知る)
- 田原弘幸・井口茂・鶴崎俊哉・沖田実・中野裕之・千住秀明・穐山富太郎・加藤克知・松坂誠應(1996).長崎大学医療技術短期大学部理学療法学科における学生異動の実態:開設以来10年間の退学・休学・留年を中心に 長崎大学医療技術短期大学部紀要,9,15-21.[PDF](CiNii Articles「退学」で知る)
- 井上孝代・土屋順一・谷和明(1996).国費学部留学生の退学とその要因:「国費学部留学生に関する調査報告」(1995)をふまえての一考察 東京外国語大学留学生日本語教育センター論集,22,193-208.(CiNii Articles「退学」で知る)
- 森田裕司(1996).大学中途退学者のアイデンティティ形成に関する研究 広島経済大学研究論集,19(1),71-98.[PDF](CiNii Articles「退学」で知る)
- 原田規章・中本稔(1997).医学部における入学者選抜方法と入学後の経過について 山口大学における追跡調査から(1) 入学形態と入学後成績、進級、国試合否との関連 医学教育,28(1),35-40.[PDF](入試選抜方法の改善に資することを目的として入学後の成績を追跡調査;CiNii Articles「退学」で知る)
- 原田規章・中本稔(1997).医学部における入学者選抜方法と入学後の経過について 山口大学における追跡調査から(2) 入学後の経過に及ぼす要因の多変量解析 医学教育,28(2),77-83.[PDF](入試選抜方法の改善に資することを目的として入学後の成績を追跡調査;CiNii Articles「退学」で知る)(面接試験の入試区分は入学後の学内成績がよいと報告;大桑良彰(2000)「宮崎医科大学における入試の追跡調査」で知る)
- 原田規章・中本稔(1997).医学部における入学者選抜方法と入学後の経過について 山口大学における追跡調査から(3) 留年・退学、国試合否に対する面接評価の意義 医学教育,28(3),167-171.[PDF](入試選抜方法の改善に資することを目的として入学後の成績を追跡調査;CiNii Articles「退学」で知る)(面接試験の入試区分は入学後の学内成績がよいと報告;大桑良彰(2000)「宮崎医科大学における入試の追跡調査」で知る)
- 中島潤子・野村正文(1997).大学における休・退学、留年学生に関する調査 第19報 全国大学メンタルヘルス研究会報告書,19,5-16.(CiNii Articles「退学」で知る)
- 高橋順一(1997).旭川高専における中途退学者の状況調査:より良い旭川高専を目指して 旭川工業高等専門学校研究報文,34,181-197.(CiNii Articles「退学」で知る)
- 徳村烝(1997).学校における信教の自由の保障の問題:「エホバの証人」派生徒信者の原級留置処分及び退学処分事件の裁判の分析 教育学論叢,4,1-17.(CiNii Articles「退学」で知る)
- 菊地直子・丸山富雄(1997).体育大学における退学者の特徴に関する予備的研究 仙台大学紀要,28(2),135-144.[PDF](一般に体育大学は具体的な目的を持った学生が入学することが予想される、体育大学の退学者の特徴について入学時から退学に至るまでの変容を考察、調査票(郵送法)を用いた、回答率が低く予備的研究としての扱い(137名に対して有効回答率・数は18.2%の25名);CiNii Articles「退学」で知る)
- 河野銀子(1997).大学におけるスループットの検討:退学者のインタビューを中心として 山形大学教育実践研究,6,71-82.(CiNii Articles「退学」で知る)
- 山川昇・武田拓(1998).本校〔仙台電波工業高等専門学校〕の中途退学者の現状分析とその課題:過去10年間の調査結果より 仙台電波工業高等専門学校研究紀要,28,7-13.(CiNii Articles「退学」で知る)
- 中島潤子・野村正文(1998).大学における休・退学、留年学生に関する調査 第20報 全国大学メンタルヘルス研究会報告書,20,7-17.(CiNii Articles「退学」で知る)
- 三村泰臣(1998).退学に関する実態と分析 広島工業大学研究紀要,32,303-307.(CiNii Articles「退学」で知る)
- 立花隆(1998).明治四年、東大医学部は学生の八割を退学させた 私の東大論6 文芸春秋,76(9),262-276.(CiNii Articles「退学」で知る)
- 内田千代子・野村正文・中島潤子(1999).大学における休・退学、留年学生に関する調査 第21報 全国大学メンタルヘルス研究会報告書,21,12-20.(CiNii Articles「退学」で知る)
- 奥平康照(1999).イギリスの退学処分問題と教育改革 人間関係学部紀要,4,143-156.(CiNii Articles「退学」で知る)
- 伊藤武彦・井上孝代(1999).留学生の中途退学者の全国調査 学生相談研究,20(1),38-48.[PDF](CiNii Articles「退学」で知る)
- 村上敦(1999).GPA・退学勧告・学習支援 大学資料,143,125-128.(CiNii Articles「退学」で知る)
- 内田千代子・中島潤子・野村正文(2000).大学における休・退学、留年学生に関する調査 第22報(2) 大学別資料一覧を主にして 全国大学メンタルヘルス研究会報告書,22,21-30.(CiNii Articles「退学」で知る)
- 林田雅希・鷺池トミ子・湯川幸一(2000).新入生健診結果と休・退学、留年および卒業との関連性 全国大学メンタルヘルス研究会報告書,22,81-83.[PDF](CiNii Articles「退学」で知る)
- 福田真也(2000).大学生の引きこもりと心身症(大学生のメンタルヘルスと心身症) 心身医学,40(3),199-205.[PDF](CiNii Articles「退学」で知る)
- 柳澤健・新田收・笠井久隆・猫田泰敏・飯田恭子・菊池恵美子・長田久雄・福士政広・齋藤秀敏・福田賢一(2000).東京都立医療技術短期大学生の入学・在学時成績と医療系国家試験合否との関係 東京保健科学学会誌,2(4),276-281.[PDF](CiNii Articles「退学」で知る)
- 大桑良彰(2000).宮崎医科大学における入試の追跡調査:入試成績と学内成績の関係 医学教育,31(3),181-193.[PDF](CiNii Articles「退学」で知る)
- 西村優紀美・中村剛(2000).学生の休・退学について 学園の臨床研究,1,7-12.[PDF](CiNii Articles「退学」で知る)
- 内田千代子・中島潤子・野村正文(2001).大学生における休・退学、留年学生に関する調査 第23報(その1) 全国大学メンタルヘルス研究会報告書,23,12-25.(CiNii Articles「退学」で知る)
- 内田千代子(2001).大学における休・退学、留年学生に関する調査 第22報(その1) Campus Health,37(2),121-126.(CiNii Articles「退学」で知る)
- 牧野幸志(2001).大学生の不登校に関する基礎的研究(1):大学生の不登校と退学希望の理由の探索 高松大学紀要,36,79-91.[PDF](CiNii Articles「退学」で知る)
- 若林佳史(2002).多義的な名称を冠した学部を退学する学生の特徴:大妻女子大学社会情報学部を事例として(その1) 入学から退学までの期間、退学の理由、入学試験を受けた理由 大妻女子大学紀要. 社会情報系, 社会情報学研究,11,187-204.(CiNii Articles「退学」で知る)
- 若林佳史(2002).多義的な名称を冠した学部を退学する学生の特徴:大妻女子大学社会情報学部を事例として(その2) 入学時のSCTに記された将来像に見る6タイプ 大妻女子大学紀要. 社会情報系, 社会情報学研究,11,205-217.(CiNii Articles「退学」で知る)
- 内田千代子(2002).大学における休・退学、留学学生に関する調査(24の1) 全国大学メンタルヘルス研究会報告書,24,11-25.(CiNii Articles「退学」で知る)
- 中村美代子(2002).入学時THI (東大式健康調査) 結果における退学者の特質 Campus Health,38(2),499-502.(CiNii Articles「退学」で知る)
- 原千恵子・杉浦ゆり・平尾良雄・秋元弘子・佐藤美加子(2002).本学学生の心身の健康調査について 山野研究紀要,10,77-86.[PDF](CiNii Articles「退学」で知る)
- 林田雅希・鷺池トミ子・湯川幸一・石井伸子(2002).新入生健診結果と休・退学留年および卒業との関連性(II研究業績) 長崎大学保健管理センター年報,12,127-129.[PDF](CiNii Articles「退学」で知る)
- 伊藤洋(2002).なぜ早期退学を勧告するのか:大学を真の学びの場にするために 科学,72(4),387-389.(CiNii Articles「退学」で知る)
- 大渕恵理・藤原俊郎・中山孝・中村浩(2002).留年、退学した学生の分析(教育・管理) 理学療法学,29(2),215.[PDF](留年・退学した理由ごとに高校成績・高校欠席数/入学試験成績の平均値を求めた、8年間の留年者12名と退学者7名が対象;CiNii Articles「退学」で知る)
- 川村雄介(2002).大学の常識 社会の非常識(57) 少なくない家計理由の退学者 彼らを留める公的資金導入を 週刊ダイヤモンド,90(22),63.(CiNii Articles「退学」で知る)
- 鈴木要(2002).社会人を対象とした建築教育:就学者が抱えている退学因子 日本建築学会技術報告集,15,355-358.[PDF](CiNii Articles「退学」で知る)
- 鈴木成文・曽根彰(2002).社会人を対象とした建築教育:就学者が抱えている退学因子、鈴木 要、355 日本建築学会技術報告集,15,418.[PDF](CiNii Articles「退学」で知る)
- 堤文生・橋元隆・高橋精一郎・石橋敏郎(2003).TEG(東大式エゴグラム)による性格分析:入学時性格と年次成績との関連 日本理学療法学術大会,2002,783-783.[PDF](CiNii Articles「退学」で知る)
- 塗師恵子・冨山博・佐藤聰夫(2003).UPIによる休学・退学者の心理的傾向 北海道自動車短期大学研究紀要,28,61-63.(CiNii Articles「退学」で知る)
- 内田千代子(2003).大学における休・退学、留年学生に関する調査(第25報・その1)〔含 質疑応答〕 全国大学メンタルヘルス研究会報告書,25,55-66,71.(CiNii Articles「退学」で知る)
- 安宅勝弘・齋藤憲司・影山任佐(2003).大学院における休学・退学・留年学生の調査(第1報)〔含 質疑応答〕 全国大学メンタルヘルス研究会報告書,25,67-71.(CiNii Articles「退学」で知る)
- 内田千代子(2003).大学における休・退学、留年学生について:調査をもとに 大学と学生,460,25-33.(CiNii Articles「退学」で知る)
- 河野銀子(2003).大学大衆化時代における'First-Generation'の位相 山形大學紀要. 教育科學,13(2),33-49(127-143).[PDF](CiNii Articles「退学」で知る)
- 石川雅健(2003).UPI(精神健康調査)からみた現代女子短大生のパーソナリティ 東海女子大学紀要,22,75-79.[PDF](CiNii Articles「退学」で知る)
- 斉藤泰雄(2003).留年・中途退学問題への取り組み:日本の歴史的経験 国際教育協力論集,6(1),43-53.[PDF](CiNii Articles「退学」で知る)
- 内田千代子(2004).「大学における休・退学、留年学生に関する調査」第23、24、25報(その2) 休・退学理由についての実態調査 全国大学メンタルヘルス研究会報告書,26,33-45.(CiNii Articles「退学」で知る)
- 安宅勝弘・齋藤憲司・影山任佐(2004).大学院における休学・退学・留年学生に関する調査 第2報 全国大学メンタルヘルス研究会報告書,26,46-51.(CiNii Articles「退学」で知る)
- 一宮厚(2004).入学時アンケートの結果と留年 休学 退学の関連について Campus Health,41(1),177.(CiNii Articles「退学」で知る)
- 澤村信英(2004).世界の動き 留年、中途退学の克服が課題に:苦悩するケニアの教育 内外教育,5464,2-4.(CiNii Articles「退学」で知る)
- 宮田正和・飯田一惠・濱崎麻由美(2004).教員養成大学における休学・退学理由の現状について 心身医学,44(7),520.[PDF](CiNii Articles「退学」で知る)
- 安宅勝弘(2004).事例紹介 大学院における休学・退学・留年学生に関する調査について:平成14年度集計結果から 大学と学生,5,34-41.(CiNii Articles「退学」で知る)
- 一宮厚・福盛英明・馬場園明(2004).大学生の入学時の精神状態と留年・休学・退学との関連について:対人緊張は大学生の就学を阻害する 精神医学,46(11),1185-1192.(CiNii Articles「退学」で知る)
- 内田千代子(2005).大学における休・退学、留年学生に関する調査(第26報) 全国大学メンタルヘルス研究会報告書,27,83-101.(CiNii Articles「退学」で知る)
- 安宅勝弘・齋藤憲司・影山任佐(2005).大学院における休学・退学・留年学生に関する調査:平成15年度調査結果から 全国大学メンタルヘルス研究会報告書,27,102-107.(CiNii Articles「退学」で知る)
- 片瀬一男(2005).退学者動向・調査報告(1)教養学部の場合 意欲があって大学を去る者、意欲を失ってやめる者:二つの不幸な退学理由へのブール代数アプローチ 東北学院大学教育研究所報告集,5,43-69.[PDF](CiNii Articles「退学」で知る)
- 篠崎俊子・山口快生(2005).福岡女子大学学生の入学時におけるCornell Medical lndex実態調査:過去37年間-昭和43年度~平成16年度 文芸と思想,69,205-252.[PDF](CiNii Articles「退学」で知る)
- 大谷晃也(2005).文科系学生の数学の基礎学力と退学率、就職率 研究論集,82,191-197.[PDF](CiNii Articles「退学」で知る)
- 宮城徹(2005).日本政府奨学金学部留学生の中途退学率、退学理由から見えてくるもの:オセアニア地域からの留学生の場合を中心にして オセアニア教育研究,11,53-65.[PDF](CiNii Articles「退学」で知る)
- 相澤直子・佐藤いづみ・鈴木悦子・加藤恵・松崎こづえ・石田清子(2006).進路・修学上の悩みを抱える女子学生へのサポート:カウンセラーから見た退学学生 研究紀要. 短期大学部,39,35-41.(CiNii Articles「退学」で知る)
- 堤文生(2006).東大式エゴグラム(TEG)による性格分析:オーバーラップ・エゴグラムの活用 日本理学療法学術大会,2005,G0935-G0935.[PDF](CiNii Articles「退学」で知る)
- 内田千代子(2006).大学における休・退学、留年学生に関する調査 第27報 全国大学メンタルヘルス研究会報告書,28,13-25.(CiNii Articles「退学」で知る)
- 安宅勝弘・齋藤憲司・影山任佐(2006).大学院における休学・退学・留年学生に関する調査:平成16年度調査結果から 全国大学メンタルヘルス研究会報告書,28,26-29.(CiNii Articles「退学」で知る)
- 野原隆彦(2006).症例研究 ゲームにはまって引きこもり退学を余儀なくされたT君 全国大学メンタルヘルス研究会報告書,28,82-85.(CiNii Articles「退学」で知る)
- 岡伊織・山崖俊子・佐々木由利子(2006).大学生精神医学的チェックリスト(UPI)における津田塾大学生の28年間にわたる変化 学生相談研究,26(3),233-242.(CiNii Articles「退学」で知る)
- 黒田登美雄・岡崎威生(2006).琉球大学における入学者選抜試験の追跡調査:入学試験の成績と休学者・除籍者・退学者の関係について 大学入試研究ジャーナル,16,165-172.(CiNii Articles「退学」で知る)
- 山田ゆかり(2006).大学新入生における適応感の検討 名古屋文理大学紀要,6,29-36.[PDF](CiNii Articles「退学」で知る)
- 淨住護雄(2006).学生の大学入学の経緯、学生生活意識と蓄積的疲労徴候の関連についての研究 学校保健研究,48(3),229-244.[PDF](CiNii Articles「退学」で知る)
- 小坂守孝(2007).大学生のインターネット・携帯電話利用に関するストレッサーと、ハーディネス・ストレス反応との関係 北方圏生活福祉研究所年報,13,33-42.[PDF](CiNii Articles「退学」で知る)
- 内田千代子(2007).大学における休・退学、留年学生に関する調査 第28報 全国大学メンタルヘルス研究会報告書,29,86-108.(CiNii Articles「退学」で知る)
- 安宅勝弘・斎藤憲司・佐藤武(2007).大学院における休学・退学・留年学生に関する調査:平成17年度調査結果から 全国大学メンタルヘルス研究会報告書,29,109-115.(CiNii Articles「退学」で知る)
- 相馬泰栄・中澤孝敏・植木一範(2007).本学歯科技工士学科における学生の異動実態:休・退学および留年の実態と今後の課題について 明倫歯科保健技工学雑誌,10(1),119.[PDF](CiNii Articles「退学」で知る)
- 谷野幸子・成瀬優知・四間丁千枝・桑守美千代・松井三枝・松井祥子・井上博(2007).医薬系大学における入学時MMPIの適応予測性の検討:退学との関連で 学園の臨床研究, 6,11-17.[PDF](CiNii Articles「退学」で知る)
- 村上嘉津子(2007).変革期の大学と学生、学生相談担当者の視点:退学勧告制度と関係性の醸成 京都大学カウンセリングセンター紀要,36,17-27.[PDF](CiNii Articles「退学」で知る)
- 吉澤隆志(2007).内田クレペリン検査と定期試験成績および留年・退学者との関係について:入学後から2年間の追跡調査 理学療法学,34(2),578.[PDF](CiNii Articles「退学」で知る)
- 南正信・矢花光・岩田裕美・船越利代子・長島緑(2007).福祉系短期大学生の進路選択過程における自己効力感と大学選択動機との関連 紀要,35,91-96.[PDF](CiNii Articles「退学」で知る)
- 谷川恵美子・村由美子・萩中正二(2007).わが校における中途退学者の早期発見と学生指導について 日本歯科技工学会雑誌,28(1),83-85.(CiNii Articles「退学」で知る)
- 小塩真司・願興寺礼子・桐山雅子(2007).大学退学者の入学時における悩みの特徴 日本教育心理学会総会発表論文集,49,293.[PDF](CiNii Articles「退学」で知る)
- 小塩真司・願興寺礼子・桐山雅子(2007).大学退学者におけるUPI得点の特徴 学生相談研究,28(2),134-142.(CiNii Articles「退学」で知る)
- 木ノ瀬朋子・江口昌克・西村香(2007).退学者における入学時UPIの特徴 明海大学教養論文集,19,12-17.(CiNii Articles「退学」で知る)
- 馬込武志・尾崎剛志(2008).学生の退学要因と退学回避の方策について:卒業時アンケートを参考にして 湊川短期大学紀要,44,69-74.[PDF](CiNii Articles「退学」で知る)
- 濱田輝一・福留英明・山本広伸(2008).ゆとり教育を受けた、私立大学学生の学習と特性:アパシー傾向、自立度、学習スタイル 日本理学療法学術大会,2007,G0413-G0413.[PDF](CiNii Articles「退学」で知る)
- 内田千代子(2008).大学における休・退学、留年学生に関する調査 第29報 全国大学メンタルヘルス研究会報告書,30,70-85.[PDF](CiNii Articles「退学」で知る)
- 安宅勝弘・影山任佐・齋藤憲司(2008).大学院における休学・退学・留年学生に関する調査:平成18年度調査結果および平成14~18年度5年間のデータから 全国大学メンタルヘルス研究会報告書,30,86-94.(CiNii Articles「退学」で知る)
- 藤村博恵・峯馨・畠中佳織・大森智美・佐野有理香・藤澤和歌子(2008).妊娠先行型結婚で出産を経験した学生の妊娠期の心理・社会的特徴 母性衛生,48(4),428-436.[PDF](CiNii Articles「退学」で知る)
- 中村三緒子(2008).大卒女性のライフコース分化の規定要因 日本女子大学大学院人間社会研究科紀要,14,43-56.[PDF](CiNii Articles「退学」で知る)
- 吉澤隆志・藤沢しげ子(2008).内田クレペリン検査と留年・退学者との関係:入学後から2年間の追跡調査 理学療法科学,23(2),275-278.[PDF](CiNii Articles「退学」で知る)
- 米倉明(2008).法科大学院雑記帳(46)答案から見える退学候補者 戸籍時報,635,37-47.(CiNii Articles「退学」で知る)
- 窪内節子(2009).大学退学とその防止に繋がるこれからの新入生への学生相談的アプローチのあり方 山梨英和大学紀要,8,9-17.[PDF](CiNii Articles「退学」で知る)
- 鍛治致(2009).新設大学における退学・休学・留年:多変量解析による要因分析 研究紀要,7(1),153-163.(CiNii Articles「退学」で知る)
- 上村智彦(2009).全入時代の教育の質の保証 工学教育,57(1),51-56.[PDF](CiNii Articles「退学」で知る)
- 出村由利子・山本正司・佐藤美紀(2009).退学の危機を脱した体験から学ぶ学生指導のあり方 和泉短期大学研究紀要,29,37-48.(CiNii Articles「退学」で知る)
- 三池大和・大橋修・一山幸子(2009).学生のストレスに関する心理学的研究(2) 社会福祉学科紀要,6(1),25-28.(CiNii Articles「退学」で知る)
- 亀島信也・宇惠弘・最上多美子(2009).認知学習理論を応用した大学生の学力向上プログラム 関西福祉科学大学紀要,12,179-183.[PDF](CiNii Articles「退学」で知る)
- 松田美登子(2009).「メンタルヘルス調査」を退学者対策に繋げるための予備的研究:学生相談室におけるドロップアウト危機の事例を中心に 学生相談研究,30(2),136-147.(CiNii Articles「退学」で知る)
- 堤文生(2010).理学療法学科学生の不安要因について 日本理学療法学術大会,2009,G4P2324-G4P2324.[PDF](CiNii Articles「退学」で知る)
- 松井洋・中村真・田中裕(2010).大学生の大学適応に関する研究 川村学園女子大学研究紀要,21(1),121-133.(CiNii Articles「退学」で知る)
- 三宅仁・大岡美穂・若月トシ(2010).小規模理系単科大学における独法化前後の休退学の実態 全国大学メンタルヘルス研究会報告書,32,7-79.(CiNii Articles「退学」で知る)
- 内田千代子(2010).大学における休・退学、留年学生に関する調査 第31報 全国大学メンタルヘルス研究会報告書,32,80-94.(CiNii Articles「退学」で知る)
- 安宅勝弘・影山任佐・齋藤憲司(2010).大学院における休学・退学・留年学生に関する調査:平成20年度調査結果を中心に 全国大学メンタルヘルス研究会報告書,32,95-101.(CiNii Articles「退学」で知る)
- 井奈波良一・吉安裕樹・堀貴光・堀内聖剛・清水三矢・広瀬万宝子・井上眞人・植木啓文(2010).医学生の退学願望と睡眠時間、メンタルヘルス不調およびメランコリー親和型性格との関係 日本職業・災害医学会会誌,58(1),19-23.[PDF](CiNii Articles「退学」で知る)
- 三池大和(2010).学生のストレスに関する心理学的研究(3)社会福祉学科19、20年度及び21年度生 社会福祉学科紀要,7(1),26-29.(CiNii Articles「退学」で知る)
- 矢島一永(2010).大学の活性化に向けた課題:上武大学の退学者問題について考える 上武大学教育研究センター年報:大学の質の向上を目指して,2(2008),52-53.[PDF](CiNii Articles「退学」で知る)
- 鍛治致(2010).新設大学における退学・休学・留年:多変量解析による要因分析 日本教育社会学会大会発表要旨集録,62,392-393.[PDF](CiNii Articles「退学」で知る)
- 内田千代子(2010).休学・退学の変化 精神科,17(4),330-338.(CiNii Articles「退学」で知る)
- 野波侑里・近藤伸彦・玉本拓郎(2011).初年次生の大学生活への適応に関する調査報告(1) 大手前大学論集,12,227-243.[PDF](大学適応に困難が生じる主な原因:①学力面における適応困難、②人間関係におけるコミュニケーション能力不足、学生の実態を把握するために基礎的データを収集(年間4回のアンケート)、4つの指標を利用した:①ソーシャルスキル、②自尊心、③大学生活(姿勢)、④大学生活(実際);CiNii Articles「退学」で知る)
- 堤文生(2011).理学療法学科学生の不安要因について(第2報):1年間の追跡調査 日本理学療法学術大会,2010,GbPI1481-GbPI1481.[PDF](CiNii Articles「退学」で知る)
- 内田千代子(2011).大学における休・退学、留年学生に関する調査 第32報 全国大学メンタルヘルス研究会報告書:学生支援合同フォーラム,33,42-59.(CiNii Articles「退学」で知る)
- 安宅勝弘・影山任佐・斎藤憲司(2011).大学院における休学・退学・留年学生に関する調査:平成21年度調査結果を中心に 全国大学メンタルヘルス研究会報告書:学生支援合同フォーラム,33,60-66.(CiNii Articles「退学」で知る)
- 井奈波良一・井上眞人・広瀬万宝子・植木啓文(2011).男子医学生の退学願望とメランコリー親和型性格、メンタルヘルス不調および睡眠時間との関係 日本職業・災害医学会会誌,59(1),49-52.[PDF](CiNii Articles「退学」で知る)
- 杉山雅宏(2011).「中途退学の原因」因子と「心理的支援」因子の因果関係に関する検討 人間文化研究所紀要,5,11-22.[PDF](CiNii Articles「退学」で知る)
- 大坪檀(2011).学生の中途退学→離学生問題 その取り組み方:静岡産業大学のケース 大学マネジメント,7(8),8-12.(CiNii Articles「退学」で知る)
- 藤田長太郎(2011).メンタルヘルスケアによる中途退学防止:不登校がちな学生へのアウトリーチ型支援を実施して 大学マネジメント,7(8),13-17.(CiNii Articles「退学」で知る)
- 原清治(2011).「縁(えにし)」コミュニティによる離脱者ゼロ計画 大学マネジメント,7(8),18-23.(CiNii Articles「退学」で知る)
- 山本繁(2011).「中退予防」が大学存続の命運分ける:大学の教育情報公開の時代 大学マネジメント,7(8),24-28.(CiNii Articles「退学」で知る)
- 高橋恵子・田名場美雪・阿部緑・工藤誓子・高梨信吾(2012).ストレスと健康:大学新入生の生活習慣からみた疲労感およびストレス反応 弘前大学保健管理概要,33,42134.[PDF](CiNii Articles「退学」で知る)
- 松井洋・田中裕・中村真(2012).大学生の大学適応に関する研究(3) 川村学園女子大学研究紀要,23(1),117-129.(CiNii Articles「退学」で知る)
- 髙橋稔(2012).退学の予防に向けた取組と課題 教育研究,30,34-57.(CiNii Articles「退学」で知る)
- 安宅勝弘・齋藤憲司・粥川裕平(2012).大学における休学・退学・留年学生に関する調査:平成22年度調査結果を中心に 全国大学メンタルヘルス研究会報告書:学生支援合同フォーラム,34,20-27.(CiNii Articles「退学」で知る)
- 山口直範・頭師由里(2012).能動的な学生相談体制の試み 奈良佐保短期大学研究紀要,20,101-107.[PDF](CiNii Articles「退学」で知る)
- 原清治(2012).「つながり」の関係づくりを中心に置いた中途退学者ゼロを目指す取り組み 私学経営,450,18-29.(CiNii Articles「退学」で知る)
- 中山智佳・菊本東陽(2013).理学療法学生の進学動機や職業同一性との関連およびその変化 日本理学療法学術大会,2012,48102100-48102100.[PDF](CiNii Articles「退学」で知る)
- 杉山雅宏(2013).中途退学者の語りに関する分析研究 社会福祉科学研究,2,49-57.(CiNii Articles「退学」で知る)
- 加藤かすみ・中田佳代子・飛田昌子(2013).看護師養成所3年課程の休学・退学と学生への支援の実態 中国四国地区国立病院附属看護学校紀要,9,142-151.(CiNii Articles「退学」で知る)
- 丸谷俊之・安宅勝弘・齋藤憲司(2013).大学院における休学・退学・留年学生に関する調査:平成23年度調査結果を中心に 全国大学メンタルヘルス研究会報告書:学生支援合同フォーラム,35,11-20.(CiNii Articles「退学」で知る)
- 内田千代子(2013).大学における休・退学、留年学生に関する調査 第34報 全国大学メンタルヘルス研究会報告書:学生支援合同フォーラム,35,36-51.(CiNii Articles「退学」で知る)
- 内田千代子(2013).大学は今(第18回)大学生の休学・退学・留年に関する問題(1)国立大学の調査から 週刊教育資料,1240,28-29.(CiNii Articles「退学」で知る)
- 内田千代子(2013).大学は今(第19回)大学生の休学・退学・留年に関する問題(2)国立大学の調査から 週刊教育資料,1242,28-29.(CiNii Articles「退学」で知る)
- 姉川恭子(2013).私立大学等経常費補助金と大学の学習・生活環境の動向に関する考察 大学職員論叢,1,101-107.(CiNii Articles「退学」で知る)
- 内田千代子(2013).大学は今(第20回)大学生の休学・退学・留年に関する問題(3)国立大学の調査から 週刊教育資料,1244,28-29.(CiNii Articles「退学」で知る)
- 内田千代子(2013).大学は今(第21回)大学生の休学・退学・留年に関する問題(4)国立大学の調査から 週刊教育資料,1246,28-29.(CiNii Articles「退学」で知る)
- 清水一(2013).大学の偏差値と退学率・就職率に関する予備的分析:社会科学系学部のケース 大阪経大論集,64(1),57-70.[PDF](high190さんの記事「読売新聞「大学の実力2013」を活用した偏差値・退学率・就職率を分析した論文が興味深い」で知る)(CiNii Articles「退学」で知る)
- 今野克幸・白石悟・細川和彦・井田直人・福原朗子・木内伸洋(2013).授業時間割の改善や初年度教育の充実等による修学支援と退学者減少対策 工学教育研究講演会講演論文集,25(61),650-651.[PDF](CiNii Articles「退学」で知る)
- 浜崎央・片庭美咲・松本美奈・柴田幸一・住吉廣行・山本由紀(2013).初年次の退学率減少につながる入学前教育:教職協働によるIRの成果 地域総合研究,14,57-66.[PDF](CiNii Articles「退学」で知る)
- 西田斉二・田丸佳希・宮嶋愛弓・杉原勝美・川上永子・松下太・銀山章代・上田任克(2014).リハビリテーション医療系大学生における学業および大学生活適応尺度の作成 四條畷学園大学リハビリテーション学部紀要,10,25-29.[PDF](CiNii Articles「退学」で知る)
- 藤本昌(2014).学生の疾病・傷害の保障に関する考察:実務者からみる現行制度の現状と課題 保険学雑誌,2014(627),627_129-627_148.[PDF](CiNii Articles「退学」で知る)
- 丸谷俊之・安宅勝弘・齋藤憲司(2014).大学院における休学・退学・留年学生に関する調査:平成24年度調査結果を中心に 全国大学メンタルヘルス研究会報告書:学生支援合同フォーラム,36,16-25.(CiNii Articles「退学」で知る)
- 三浦淳・布施泰子・苗村育郎(2014).大学における休・退学、留年学生に関する調査(第35報)平成24年度集計結果 全国大学メンタルヘルス研究会報告書:学生支援合同フォーラム,36,26-31.(CiNii Articles「退学」で知る)
- 志田秀史(2014).日米の中途退学調査の比較検討:アメリカの全国中途退学予防センター調査を手がかりに 総合人間科学,2,131-148.(CiNii Articles「退学」で知る)
- 舟橋啓臣・小川由美子(2014).高等教育現場における諸問題:特に中途退学について考える 愛知医療学院短期大学紀要,5,97-101.[PDF](CiNii Articles「退学」で知る)
- 後閑裕志・大谷真(2014).出席状況把握システムの解析 第76回全国大会講演論文集,2014(1),851-853.[PDF](出欠データを用いた退学/留年憂慮者の抽出方法を提案、分析内容:[曜日・時限・履修数・履修人数・授業回数]×欠席率;CiNii Articles「退学」で知る)
- 川崎孝明・中嶋弘二・川嶋健太郎・川口惠子(2014).大学における寄り添い型学生支援体制の構築:中途退学防止の観点からの実践的アプローチ 尚絅大学研究紀要. A, 人文・社会科学編,46,75-89.[PDF](CiNii Articles「退学」で知る)
- 伊藤宏隆・伊藤圭佑・舟橋健司・山本大介・齋藤彰一・松尾啓志・内匠逸(2014).学生の修学データを用いた要注意学生の傾向分析 研究報告教育学習支援情報システム(CLE),2014(8),1-8.[PDF](CiNii Articles「退学」で知る)
- 姉川恭子(2014).大学の学習・生活環境と退学率の要因分析 経済論究,149,1-16.[PDF](CiNii Articles「退学」で知る)
- 松本美奈(2014).「入試方法別の退学率」が語るのは IDE:現代の高等教育,566,60-63.(CiNii Articles「退学」で知る)
- 文部科学省(2015).学生の中途退学や休学等の状況について〔抜粋〕 私学経営,479,86-92.(CiNii Articles「退学」で知る)
- 岩崎保道(2015).大学における休・退学防止の検討:学内組織連携型の学生支援策に注目して 関西大学高等教育研究,6,81-86.[PDF](休学・退学を扱った調査の整理、休学・退学防止のための対策を行っている事例紹介;CiNii Articles「退学」で知る)
- 飯田満希子・松浦智美・小川由美子(2015).全学を挙げた学生支援に向けて:中途退学・留年問題への危機感を通して 愛知医療学院短期大学紀要,6,30-41.[PDF](CiNii Articles「退学」で知る)
- 舟橋啓臣・小川由美子(2015).中途退学防止に向けたIRの活用 愛知医療学院短期大学紀要,6,57-63.[PDF](CiNii Articles「退学」で知る)
- 中村真・松田英子(2015).大学への帰属意識が大学不適応に及ぼす影響:出席率、GPA を用いた分析 江戸川大学紀要,25,135-144.[PDF](CiNii Articles「退学」で知る)
- 玉田和恵・神部順子・八木徹・重藤暁・松村豊子・古里靖彦(2015).個に応じたキャリア教育を実現するためのファカルティ・ディベロップメントの取り組み(7):不登校・退学者の防止と基礎学力の徹底向上目指して 江戸川大学紀要,25,.[PDF](不登校・退学者を防止するために学科で行っている初年次教育について紹介、基礎学力の向上・学業にどう取り組むかという支援を中心に紹介;CiNii Articles「退学」で知る)
- 住谷圭子・甘佐京子・松本行弘・山下真裕子(2015).看護専門学校生の学業継続に影響する要因 人間看護学研究,13,43-49.[PDF](CiNii Articles「退学」で知る)
- 重歩美(2015).教育困難校からの中途退学をめぐる問題 臨床心理学研究,53(1),41-57.(CiNii Articles「退学」で知る)
- (不明)(1953).退学処分の法的性格:行政判例 教育委員会月報,5,43-51.(CiNii Articles「退学」で知る)
- (不明)(1953).退学処分に対する行政訴訟 判例時報,3,3-10.(CiNii Articles「退学」で知る)
- (不明)(1973).東海大学退学処分事件(大学・学生をめぐる最近の判例)(東京地裁48.5.30) 厚生補導,85,65-73.(CiNii Articles「退学」で知る)
- (不明)(1993).<Q&A>学生の休学、退学について 大学と学生,337,58-59.(休学・退学の制度・手続きについて説明;CiNii Articles「退学」で知る)
- (不明)(1998).[5]休・退学、留年者の実態調査 保健管理センター概要,8,79-85.[PDF](CiNii Articles「退学」で知る)
- (不明)(1998).[7]休・退学、留年者の実態調査 保健管理センター概要,9,103-108.[PDF](CiNii Articles「退学」で知る)
- (不明)(1999).[6]休・退学、留年者の実態調査 保健管理センター概要,10,106-115.[PDF](CiNii Articles「退学」で知る)
- (不明)(2000).三重大医学部セクハラ退学学生が入学した有名国立大学の困惑 週刊朝日,105(20),32-34.(CiNii Articles「退学」で知る)
- (不明)(2001).[6]休・退学・留年者の実態調査 保健管理センター概要,11,124-133.[PDF](CiNii Articles「退学」で知る)
- (不明)(2002).[6]休・退学、留年者の実態調査 長崎大学保健管理センター年報,12,115-121.[PDF](CiNii Articles「退学」で知る)
- (不明)(2004).現状 ドロップアウトはどの程度深刻なのか:国立より私立、短大は退学率10%を超える カレッジマネジメント,22(3),4-13.(CiNii Articles「退学」で知る)
- (不明)(2004).国立大学の現状:女子より男子、文系より理系が深刻 カレッジマネジメント,22(3),5-8.(CiNii Articles「退学」で知る)
- (不明)(2004).私立大学の現状とその対応策:「進路変更」「意欲の低下」が主要因 カレッジマネジメント,22(3),8-11.(CiNii Articles「退学」で知る)
- (不明)(2005).[7]休・退学、留年者の実態調査 長崎大学保健管理センター年報,15,118-119.[PDF](CiNii Articles「退学」で知る)
[2015.12.03]IRなどについての文献メモ 文献一覧を更新<中途退学、リテンション>
- 松田英子・日浅美由紀・鈴木秀生・中村真・高澤則美(2014).江戸川大学生のメンタルヘルスに関する調査報告 江戸川大学紀要,24,39-47.[PDF](CiNii Articles「中退」で知る)
- 小野直広(1968).青年期のパースナリティと行動:正常・非行・学校中退者等のMMPIパターン(Hathaway、S.R.& Monachesi、E.D;Adolescent Personality and Behavior:MMPI patterns of normal、delinquent、and other outcomes、1963) 犯罪心理学研究,5(2),36-39.(CiNii Articles「中退」で知る)
- 朝岡幸彦(1992).高校・大学の中退問題と進路指導 日本教育社会学会大会発表要旨集録,44,96-97.[PDF](CiNii Articles「中退」で知る)
- 河内敬子(1997).シリーズ私の実践/新たな自己へ中退から学ぶ(3) 月刊社会教育,41(7),82-86.(CiNii Articles「中退」で知る)
- 河地敬子(1997).シリーズ私の実践:新たな自己へ:中退から学ぶ-3完-編集長への手紙〔含 返信〕 月刊社会教育,41(8),89-91.(CiNii Articles「中退」で知る)
- 奥井礼喜(1998).平成の「勤め人道」言志録(16)中退する2.5%の子たちは人生のエリート エルダー,20(4),58-59.(CiNii Articles「中退」で知る)
- 五十嵐敦(1998).進路選択あるいは中退 現代のエスプリ,372,65-72.(CiNii Articles「中退」で知る)
- 金口恭久(1998).アメリカの教育事情(16)アメリカの教育の現状と課題 その2:ドラッグと中退の現状と問題 学校経営,43(10),74-78.(CiNii Articles「中退」で知る)
- 橋本鉱市(1999).アメリカにおける学外学位授与機関(その3)チャーターオーク州立大学の卒業生・中退者の意識と動態 学位研究,11,91-105.[PDF](CiNii Articles「中退」で知る)
- 笠木恵司(2000).短大卒・専門学校卒・中退者のための学歴改造計画 ダイヤモンド・エグゼクティブ,37(8),35-37.(CiNii Articles「中退」で知る)
- 中田信哉(2001).大学の風景(9)除籍、中退そして留年 物流logistics,12(8),60-63.(CiNii Articles「中退」で知る)
- 佐藤太郎(2001).大学 「失業中退」の悲惨:親が倒産・リストラで。慶応・国士舘は緊急融資 AERA,56,8-11.(CiNii Articles「中退」で知る)
- 池田英二(2003).大学生き残りの王道:私語、居眠り、途中退場なしの教室を如何にして実現するか 日本産業経済学会産業経済研究,3,1-15.(CiNii Articles「中退」で知る)
- 佐藤龍子(2005).国立大学法人の中期目標・中期計画にみるキャリア教育と就職・学生支援 社会科学,75,53-73.[PDF](CiNii Articles「中退」で知る)
- 長谷綾子・藤村尚子・井上治美・高木総平・田中チカ子・永田俊代・中村博文・兼久志津子・吉田恵子・河野順子・山田俊介(2007).過去6年間のUPI調査結果からみた新入生の心理的健康と中退者の特徴について:来談しない・できないハイリスク者のサポートを考える 松山東雲女子大学人文学部紀要,15,61-78.(CiNii Articles「中退」で知る)
- 福井有希・岩下真由美・有園博子(2009).人生の浮沈曲線にみる留学・中退経験者の心理的変遷 発達心理臨床研究,15,109-119.(CiNii Articles「中退」で知る)
- 澤田晃宏(2009).GW明け中退防ぐ信じられない大学の対策 AERA,23,32-34.(CiNii Articles「中退」で知る)
- 文部科学省高等教育局(2009).キーワードで見る最新高等教育事情(第37回)各大学等の授業料滞納や中退等の状況について 週刊教育資料,1075,30-31.(CiNii Articles「中退」で知る)
- 日本中退予防研究所(2010).日本中退予防研究所の問題意識と大学・短大・専門学校における中退の現状及び、中退を予防するために高校でできること 月刊生徒指導,40(8),36-39.(CiNii Articles「中退」で知る)
- 山本繁(2010).就職戦線にも立てない 大学中退者8万人の悲惨 週刊東洋経済,6293,78-79.(CiNii Articles「中退」で知る)
- 斉藤美香・飯田昭人・川崎直樹(2011).学生相談における多層的支援:居場所づくりの試み 北翔大学北方圏学術情報センター年報,3,143-149.[PDF](CiNii Articles「中退」で知る)
- 山本繁(2011).「中退予防」が大学存続の命運分ける:大学の教育情報公開の時代 大学マネジメント,7(8),24-28.[PDF](CiNii Articles「中退」で知る)
- 山内祐平(2011).ラーニングコモンズと学習支援 情報の科学と技術,61(12),478-482.[PDF](CiNii Articles「中退」で知る)
- 白川はるひ(2012).中退予防策に向けた本学学生の簡易調査 戸板女子短期大学研究年報,55,69-73.[PDF](CiNii Articles「中退」で知る)
- 山本繁(2012).学生の中退防止 IDE:現代の高等教育,546,30-36.(CiNii Articles「中退」で知る)
- 朴澤泰男(2012).学校基本調査にみる中退と留年 IDE:現代の高等教育,546,64-67.(CiNii Articles「中退」で知る)
- 山本繁(2013).高等教育研究会 学習交流会 学生の中退防止に向けた今後の取り組み課題 大学職員ジャーナル,17,10-19.(CiNii Articles「中退」で知る)
- 見城悌治(2013).戦前期における東京高等工芸学校(現千葉大学工学部)の留学生とその動向 国際教育,6,29-54.[PDF](CiNii Articles「中退」で知る)
- 山本繁(2013).中退予防のための教学IR 大学時報,350,46-51.[PDF](CiNii Articles「中退」で知る)
- 濱名篤(2013).大学中退のとらえ方:マクロな視点から 大学教育学会誌,35(1),12-16.(CiNii Articles「中退」で知る)
- 鈴木典比古(2013).中退問題をとらえる新しい視座 大学教育学会誌,35(1),17-19.(CiNii Articles「中退」で知る)
- 山本繁(2013).学生の中退とは何か:そのメカニズムと理由、対策実施上の課題 大学教育学会誌,35(1),20-24.(CiNii Articles「中退」で知る)
- 肥後功一(2013).島根大学における教育の質保証をめぐって 大学教育学会誌,35(1),25-28.(CiNii Articles「中退」で知る)
- 森朋子・吉田香奈(2013).開催校企画シンポジウムを司会して 大学教育学会誌,35(1),29-31.(CiNii Articles「中退」で知る)
- 西田斉二・田丸佳希・宮嶋愛弓・杉原勝美・川上永子・松下太・銀山章代・上田任克(2014).リハビリテーション医療系大学生における学業および大学生活適応尺度の作成 四條畷学園大学リハビリテーション学部紀要,10,25-29.[PDF](CiNii Articles「中退」で知る)
- 鈴木大介(2014).スーツに革靴、朝8時スタート、自分名義のケータイNG…大学中退者や就活敗退組も。年収1千万~2千万円はザラ オレオレ詐欺に就く若者 週刊朝日,119(12),43-45.(CiNii Articles「中退」で知る)
- 辰巳哲子(2015).大学中退後のキャリアに影響する大学入学以前の経験 Works review:リクルートワークス研究所研究報告,10,6-15.[PDF](CiNii Articles「中退」で知る)
- 野村昌二・竹下郁子(2015).娘が父に綴った16枚の中退決意:いま、そこにある「教育格差」 AERA,22,25-27.(CiNii Articles「中退」で知る)
- 重歩美(2015).教育困難校からの中途退学をめぐる問題 臨床心理学研究,53(1),41-57.(CiNii Articles「中退」で知る)
- 山本繁(2015).理事長インタビュー NPO法人NEWVERY 山本繁(やまもとしげる)理事長 中退・進路未決定・離職を予防し若者が社会的弱者に転落するのを防ぐ 文部科学教育通信,371,8-15.(CiNii Articles「中退」で知る)
- (不明)(1962).アメリカにおける学校中退とその対策:海外だより 家庭裁判月報,14(5),252-254.(CiNii Articles「中退」で知る)
- (不明)(1999).短大・専門学校卒業者&大学中退者のための学士号取得ルート 徹底研究 ダイヤモンド・エグゼクティブ,36(10),56-58.(CiNii Articles「中退」で知る)
- (不明)(2008).2008年就労条件総合調査(その2)退職給付制度の内容と支給実態 勤続35年以上の定年退職金:大学卒2、281万円、高校卒1、929万円 適格年金の移行先は中退共が17.2%、見直し内容未定が26.6% 賃金事情,2555,12-17.(CiNii Articles「中退」で知る)
- (不明)(2011).年間7.3万人!学生を手厚くサポートする中退しない・させない大学 週刊東洋経済,6356,70-72.(CiNii Articles「中退」で知る)
- (不明)(2014).大学中退、2割が「経済的理由」:5年前より6ポイント増加:文科省調査 内外教育,6366,9.(CiNii Articles「中退」で知る)
- (不明)(2014).大学等を中退した学生は7万9千人 そのうち2割が「経済的理由」:文部科学省が「学生の中途退学」状況を調査 国内動向:過激各派の諸動向・教育・労働問題に関する専門情報誌,1309,22-24.(CiNii Articles「中退」で知る)
[2015.12.02]ホーム「お知らせ」欄を変更
- 口頭発表「大学からの中途退学についての文献レビュー:日本の雑誌論文を中心に」(平成27年度第3回IR実務担当者連絡会)を掲載
[2015.12.01]IRなどについての文献メモ 文献一覧を更新<高等教育、フランス>
- 坂本尚志(2012).バカロレア哲学試験は何を評価しているか?:受験対策参考書からの考察 京都大学高等教育研究,18,53-63.[PDF](フランスの教育制度の特徴の1つがリセ最終学年の哲学教育とバカロレアの哲学試験、高校で哲学を学んだフランス人すべてが哲学的思考を身につけていると考えることは誤り、平凡な生徒や「落ちこぼれ」の学習も確実に哲学教育の一部、いかなる要素がバカロレア哲学試験において重視されているかを参考書の分析によって理解することを試みる、哲学試験もいわば「暗記科目」としての側面を持っており、決して単に「高次の学力」(細尾、2008)や「思考の練磨と思慮深い判断力の形成」(綾井、2008)を問うだけではない;Google「フランス バカロレア」で知る)
- 細尾萌子(2008).バカロレア試験制度 フランス教育学会(編)フランス教育の伝統と革新 大学教育出版 pp.152-160.(坂本(2012)「バカロレア哲学試験は何を評価しているか」で知る)
- 綾井桜子(2008).後期中等教育 フランス教育学会(編)フランス教育の伝統と革新 大学教育出版 pp.112-120.(坂本(2012)「バカロレア哲学試験は何を評価しているか」で知る)
[2015.11.30]IRなどについての文献メモ 文献一覧を更新<中途退学、リテンション>
- 労働政策研究・研修機構(編)(2015).大学等中退者の就労と意識に関する研究 労働政策研究・研修機構[PDF]
- 労働政策研究・研修機構(編)(2012).大都市の若者の就業行動と意識の展開:「第3回若者のワークスタイル調査」から 労働政策研究・研修機構[PDF](高校・高等教育機関からの中途退学者の就業形態について記載あり)
[2015.11.30]IRなどについての文献メモ 文献一覧を更新<中途退学、リテンション、フランス>
- Bédard, D., & Béchard, J.-P. (2009). Comprendre le monde des étudiants. In Bédard, D., & Béchard, J.-P.(Eds.) Innover dans l'enseignement supérieur. Paris: Presses universitaires de France. pp.61-76.(学生の属性分析などIRについての記載あり;Google Scholar「"recherche institutionnelle"」で知る)
[2015.11.27]IRなどについての文献メモ 文献一覧を更新<学生による授業評価、授業アンケート、教員評価>
- 米谷淳(2007).学生による授業評価についての実践的研究 大学評価・学位研究,5,121-134.[PDF](Google「授業アンケート 実施率 文部科学省」で知る)(授業評価は授業改善だけでなく教員評価にも用いられる;Google Scholar「授業アンケート|授業評価 "教員評価"」で知る)
[2015.11.26]IRなどについての文献メモ 文献一覧を更新<中途退学、リテンション>
- Berger, J. B., Ramírez, G. B., & Lyonsm, S. (2012). Past to present: A histrical look at retention. In A. Seidman(Ed.) College student retention: Formula for student success second edition. Lanham, ML: Rowman & Littlefield Publishing Group. pp.7-34.
- Spady, W. G. (1970). Dropouts from higher education: An interdisciplinary review and synthesis. Interchange, 1(1), 64-85.[Abstract](Berger et al. (2012). Past to present: A histrical look at retention.で知る)
- Spady, W. G. (1971). Dropouts from higher education: Toward an empirical model. Interchange, 2(3), 38-62.[Abstract](Berger et al. (2012). Past to present: A histrical look at retention.で知る)
[2015.11.26]IRなどについての文献メモ 文献一覧を更新<学習支援>
- 清水栄子(2015).アカデミック・アドバイジング:日本の大学へのアメリカの示唆 東信堂(大学行政管理学会会員向け案内メールで知る)
[2015.11.20]「これまでの発表・競争的研究資金など」に追加
- 西九州大学短期大学部「平成26年度未来経営戦略推進経費(教学改革推進のためのシステム構築・職員育成)」(日本私立学校振興・共済事業団、平成26~28年度)平成27年度外部評価
[2015.11.18]IRなどについての文献メモ 文献一覧を更新<単位制度>
[2015.11.18]ホーム「お知らせ」欄を変更
- 話題提供「教育改善に向けてデータをどのように共有できるのか」(第22回大学教育研究フォーラム<参加者企画セッション>)を掲載
[2015.11.17]IRなどについての文献メモ 文献一覧を更新<組織論>
- 高橋正泰・磯山優・山口善昭・文智彦(1998).経営組織論の基礎 中央経済社(明治大学経営学部シラバスで知る)
- 加藤茂夫(編著)(2002).ニューリーダーの組織論:企業のダイナミズムを引き出す 泉文堂(明治大学経営学部シラバスで知る)
- 馬塲杉夫・蔡芢錫・福原康司・伊藤真一・奥村経世・矢澤清明(2015).マネジメントの航海図:個人と組織の複眼的な経営管理 中央経済社(明治大学経営学部シラバスで知る)
- 大月博司・高橋正泰(編著)(2003).経営組織 学文社(明治大学経営学部シラバスで知る)
- 高橋正泰(2006).組織シンボリズム:メタファーの組織論 同文舘出版(明治大学経営学部シラバスで知る)
- 楠木建(2010).ストーリーとしての競争戦略:優れた戦略の条件 東洋経済新報社(専修大学大学院シラバス検索で知る)
- 沼上幹(2000).行為の経営学:経営学における意図せざる結果の探究 白桃書房(専修大学大学院シラバス検索で知る)
- Aldrich, H.若林直樹・高瀬武典・岸田民樹・坂野友昭・稲垣京輔(訳)(2007).組織進化論:企業のライフサイクルを探る 東洋経済新報社(専修大学大学院シラバス検索で知る)
- Daft, R. L.高木晴夫(訳)(2002).組織の経営学:戦略と意思決定を支える ダイヤモンド社(専修大学大学院シラバス検索で知る)
- 佐々木圭吾(2013).みんなの経営学:使える実戦教養講座 日本経済新聞出版社(東京理科大学大学院イノベーション研究科技術経営専攻シラバスで知る)
[2015.11.16]「私立大学職員によるIR文献メモ」メルマガ バックナンバーを更新
[2015.11.16]IRなどについての文献メモ 文献一覧を更新<高等教育、フランス>
- 夏目達也(2012).フランスにおける学士課程改革と学習成果アセスメント 深堀聰子(研究代表者)学習成果アセスメントのインパクトに関する総合的研究 国立教育政策研究所 pp.36-53.[PDF](Google Scholar「フランス 退学」で知る)
- 大学評価・学位授与機構(編)(2012).諸外国の高等教育分野における質保証システムの概要:フランス 大学評価・学位授与機構[PDF](Google Scholar「フランス 退学」で知る)
- 大場淳・夏目達也(2010).フランスの大学・学位制度 学位と大学,1,93-159.[PDF](Google Scholar「フランス 退学」で知る)
- 柴田治呂(2008).フランスの大学改革 科学技術振興機構研究開発戦略センター[PDF](「現状では入学した学生の50%は最初の1年で授業についていけず、進学できないという極めて深刻な状況に陥っている」、「毎年9万人の学生が学位を取得することなく、大学を退学する」、「その理由は、バカロレア保持者は無試験で大学に入学できるという制度により、大量の学生がしっかりした考えを持たず、大学に入学するためである」;Google Scholar「フランス 退学」で知る)
- 科学技術振興機構研究開発戦略センター海外動向ユニット(2015).科学技術・イノベーション動向報告:フランス編:2014年度版 科学技術振興機構研究開発戦略センター[PDF](Google Scholar「フランス 退学」で知る)
- 大場淳(2011).高等教育の市場化と政府統制:近年のフランスの大学改革を巡って 大学論集,42,19-35.(CiNii Articles「フランスの大学改革」で知る)
- 大場淳(2010).フランスの大学改革:サルコジ=フィヨン政権下での改革を中心に 大学論集,41,59-77.(CiNii Articles「フランスの大学改革」で知る)
- 大場淳(2009).フランスの大学改革 大学マネジメント,5(4),6-10.(CiNii Articles「フランスの大学改革」で知る)
- 服部憲児(2006).フランスの大学改革における大学評価の活用:ヴェルサイユ大学およびCNE(全国大学評価委員会)に対する訪問調査を中心に 大阪教育大学紀要.IV,教育科学,54(2),125-139.(CiNii Articles「フランスの大学改革」で知る)
- 富安瑛躬(1979).フランスの大学改革とその現状について レファレンス,29(10),25-40.(CiNii Articles「フランスの大学改革」で知る)
- 大場淳(2005).フランス:フランスのバカロレアと高等教育の質保証に関する一考察 COE研究シリーズ,16,69-94.[PDF](CiNii Articles「フランスの大学改革」で知る)
- 藤井佐知子(2000).高校教育改革における知の再構築と市民性育成:フランスの試み 比較教育学研究,26,41-53.[PDF](CiNii Articles「フランスの大学改革」で知る)
- 大場淳(2004).フランスの大学における「学力低下」問題とその対応 広島大学大学院教育学研究科紀要.第三部,教育人間科学関連領域,52,371-380.[PDF](CiNii Articles「フランスの大学改革」で知る)
[2015.11.16]「過去の「お知らせ」」、「IRなどについての文献メモ」、「これまでの発表・競争的研究資金など」に追加
- ワークショップ講師「大学改革における職員とIR:京都光華女子大学の事例」(大学改革研究会2015年度第5回ワークショップ)
[2015.11.12]IRなどについての文献メモ 文献一覧を更新<高等教育>
- 佐々木享(1984).大学入試制度 大月書店(広島大学シラバスで知る[広島大学大学院教育学研究科高等教育開発専攻/教育人間科学専攻提供の科目])
- 矢野真和(2011).「習慣病」になったニッポンの大学:18歳主義・卒業主義・親負担主義からの解放 日本図書センター(広島大学シラバスで知る[広島大学大学院教育学研究科高等教育開発専攻/教育人間科学専攻提供の科目])
- 天野郁夫(2013).大学改革を問い直す 慶應義塾大学出版会(広島大学シラバスで知る[広島大学大学院教育学研究科高等教育開発専攻/教育人間科学専攻提供の科目])
- 土戸敏彦(1999).冒険する教育哲学:「子ども」と「大人」のあいだ 勁草書房(広島大学シラバスで知る[広島大学大学院教育学研究科高等教育開発専攻/教育人間科学専攻提供の科目])
- 井上俊・上野千鶴子・大澤真幸・見田宗介・吉見俊哉(編)(1996).こどもと教育の社会学 岩波書店(広島大学シラバスで知る[広島大学大学院教育学研究科高等教育開発専攻/教育人間科学専攻提供の科目])
- 越智貢(編)(2005).岩波応用倫理学講義6:教育 岩波書店(広島大学シラバスで知る[広島大学大学院教育学研究科高等教育開発専攻/教育人間科学専攻提供の科目])
-
- 小笠原道雄・伴野昌弘・渡邉満・渡邉隆信(2006).教職概論 福村出版(広島大学シラバスで知る[広島大学大学院教育学研究科高等教育開発専攻/教育人間科学専攻提供の科目])
- 沼上幹(2004).組織デザイン 日本経済新聞社(広島大学シラバスで知る[広島大学大学院教育学研究科高等教育開発専攻/教育人間科学専攻提供の科目])
- 山本眞一(2012).大学事務職員のための高等教育システム論:より良い大学経営専門職となるために 東信堂(広島大学シラバスで知る[広島大学大学院教育学研究科高等教育開発専攻/教育人間科学専攻提供の科目])
- Lewis-Beck, M. S.(1980). Applied regression: An introduction. Beverly Hills, Calif.: Sage Publications.(広島大学シラバスで知る[広島大学大学院教育学研究科高等教育開発専攻/教育人間科学専攻提供の科目])
- Lewis-Beck, M. S.(1995). Data analysis: An introduction. Beverly Hills, Calif.: Sage Publications.(広島大学シラバスで知る[広島大学大学院教育学研究科高等教育開発専攻/教育人間科学専攻提供の科目])
- 高根正昭(1979).創造の方法学 講談社(広島大学シラバスで知る[広島大学大学院教育学研究科高等教育開発専攻/教育人間科学専攻提供の科目])
- 竹内洋・徳岡秀雄(編)(1995).教育現象の社会学 世界思想社(広島大学シラバスで知る[広島大学大学院教育学研究科高等教育開発専攻/教育人間科学専攻提供の科目])
- Flick, U.小田博志・山本則子・春日常・宮地尚子(訳)(2011).質的研究入門:「人間の科学」のための方法論 春秋社(広島大学シラバスで知る[広島大学大学院教育学研究科高等教育開発専攻/教育人間科学専攻提供の科目])
- 山田潤(2002).「不登校」だれが、なにを語ってきたか 現代思想,30(5),233-247.(広島大学シラバスで知る[広島大学大学院教育学研究科高等教育開発専攻/教育人間科学専攻提供の科目])
- 丸山恭司(2002).教育という悲劇、教育における他者:教育のコロニアリズムを超えて 近代教育フォーラム,11,1-12.(広島大学シラバスで知る[広島大学大学院教育学研究科高等教育開発専攻/教育人間科学専攻提供の科目])
- 白川俊之(2011).現代高校生の教育期待とジェンダー:高校タイプと教育段階の相互作用を中心に 教育社会学研究,89,49-69.[PDF](広島大学シラバスで知る[広島大学大学院教育学研究科高等教育開発専攻/教育人間科学専攻提供の科目])
- 荒牧草平(2003).現代都市高校におけるカリキュラム・トラッキング 教育社会学研究,73,25-42.[PDF](広島大学シラバスで知る[広島大学大学院教育学研究科高等教育開発専攻/教育人間科学専攻提供の科目])
- 有海拓巳(2011).地方/中央都市部の進学校生徒の学習・進学意欲:学習環境と達成動機の質的差異に着目して 教育社会学研究,88,185-205.[PDF](広島大学シラバスで知る[広島大学大学院教育学研究科高等教育開発専攻/教育人間科学専攻提供の科目])
- 朴澤泰男(2012).大学進学率の地域格差の再検討:男子の大学教育投資の都道府県別便益に着目して 教育社会学研究,91,51-71.[PDF](広島大学シラバスで知る[広島大学大学院教育学研究科高等教育開発専攻/教育人間科学専攻提供の科目])
- 吉原惠子(1998).異なる競争を生み出す入試システム:高校から大学への接続に見るジェンダー分化 教育社会学研究,62,43-67.[PDF](広島大学シラバスで知る[広島大学大学院教育学研究科高等教育開発専攻/教育人間科学専攻提供の科目])
- 中西祐子(1993).ジェンダー・トラック:性役割観に基づく進路分化メカニズムに関する考察 教育社会学研究,53,131-154.[PDF](広島大学シラバスで知る[広島大学大学院教育学研究科高等教育開発専攻/教育人間科学専攻提供の科目])
- 矢野眞和・濱中淳子(2006).なぜ、大学に進学しないのか:顕在的需要と潜在的需要の決定要因 教育社会学研究,79,85-104.[PDF](広島大学シラバスで知る[広島大学大学院教育学研究科高等教育開発専攻/教育人間科学専攻提供の科目])
- 藤村正司(2009).大学進学における所得格差と高等教育政策の可能性 教育社会学研究,85,27-48.[PDF](広島大学シラバスで知る[広島大学大学院教育学研究科高等教育開発専攻/教育人間科学専攻提供の科目])
- 丸山文裕(1981).大学生の就職企業選択に関する一考察 教育社会学研究,36,101-111.[PDF](広島大学シラバスで知る[広島大学大学院教育学研究科高等教育開発専攻/教育人間科学専攻提供の科目])
- 潮木守一(2008).大学進学率上昇をもたらしたのは何なのか:計量分析と経験知の間で 教育社会学研究,83,5-22.[PDF](広島大学シラバスで知る[広島大学大学院教育学研究科高等教育開発専攻/教育人間科学専攻提供の科目])
- 上山浩次郎(2011).大学進学率の都道府県間格差の要因構造とその変容:多母集団パス解析による4時点比較 教育社会学研究,88,207-227.[PDF](広島大学シラバスで知る[広島大学大学院教育学研究科高等教育開発専攻/教育人間科学専攻提供の科目])
[2015.11.09]IRなどについての文献メモ 文献一覧を更新<高等教育>
- 山岸直司(2008).データに見る大学職員 IDE:現代の高等教育,499,66-69.(桜美林大学シラバス検索で知る[桜美林大学大学院大学アドミニストレーション研究科の提供科目])
- 舘昭(2008).大学職員論 IDE:現代の高等教育,499,60-66.(桜美林大学シラバス検索で知る[桜美林大学大学院大学アドミニストレーション研究科の提供科目])
- 久保公人(2008).大学の人事政策 IDE:現代の高等教育,499,55-60.(桜美林大学シラバス検索で知る[桜美林大学大学院大学アドミニストレーション研究科の提供科目])
- 篠田道夫(2008).私立大学の職員像 IDE:現代の高等教育,499,49-55.(桜美林大学シラバス検索で知る[桜美林大学大学院大学アドミニストレーション研究科の提供科目])
- 横田利久(2008).大学行政管理学会と職員 IDE:現代の高等教育,499,44-49.(桜美林大学シラバス検索で知る[桜美林大学大学院大学アドミニストレーション研究科の提供科目])
- 里見朋香(2008).「体験的」大学職員論 IDE:現代の高等教育,499,40-43.(桜美林大学シラバス検索で知る[桜美林大学大学院大学アドミニストレーション研究科の提供科目])
- 村田直樹(2008).横浜国大職員塾の試み IDE:現代の高等教育,499,36-40.(桜美林大学シラバス検索で知る[桜美林大学大学院大学アドミニストレーション研究科の提供科目])
- 藤田幸男(2008).職員の育成:私大連の試み IDE:現代の高等教育,499,31-35.(桜美林大学シラバス検索で知る[桜美林大学大学院大学アドミニストレーション研究科の提供科目])
- 本間政雄(2008).マネジメントの課題と新たな職員像 IDE:現代の高等教育,499,25-30.(桜美林大学シラバス検索で知る[桜美林大学大学院大学アドミニストレーション研究科の提供科目])
- 上杉道世(2008).トータルプランで職員を変える IDE:現代の高等教育,499,20-25.(桜美林大学シラバス検索で知る[桜美林大学大学院大学アドミニストレーション研究科の提供科目])
- 清成忠男(2008).私学経営と職員 IDE:現代の高等教育,499,15-20.(桜美林大学シラバス検索で知る[桜美林大学大学院大学アドミニストレーション研究科の提供科目])
- 山本眞一(2008).これからの大学職員 IDE:現代の高等教育,499,11-15.(桜美林大学シラバス検索で知る[桜美林大学大学院大学アドミニストレーション研究科の提供科目])
- 金子元久(2008).大学職員の展望 IDE:現代の高等教育,499,4-10.(桜美林大学シラバス検索で知る[桜美林大学大学院大学アドミニストレーション研究科の提供科目])
- 八木沼圭司(2003).「大学経営管理職員」主導型改革の実践:SDからADへ 大学と学生,465,35-42.(桜美林大学シラバス検索で知る[桜美林大学大学院大学アドミニストレーション研究科の提供科目])
- 篠田道夫(2003).日本福祉大学におけるSDの取組について 大学と学生,465,28-34.(桜美林大学シラバス検索で知る[桜美林大学大学院大学アドミニストレーション研究科の提供科目])
- 佐賀啓男(2003).メディアを用いる教員の効果的FD支援について 大学と学生,465,22-27.(桜美林大学シラバス検索で知る[桜美林大学大学院大学アドミニストレーション研究科の提供科目])
- 岡村純(2003).学生の教育環境づくりとFD活動:学生も利用可能なFD教材を中心に 大学と学生,465,15-21.(桜美林大学シラバス検索で知る[桜美林大学大学院大学アドミニストレーション研究科の提供科目])
- 孫福弘(2003).SDの理論と実践:アドミニストレーターの開発・育成を中心に 大学と学生,465,7-14.(桜美林大学シラバス検索で知る[桜美林大学大学院大学アドミニストレーション研究科の提供科目])
- 高橋真義(2002).運動としてのSD-FMICS IDE:現代の高等教育,439,55-60.(桜美林大学シラバス検索で知る[桜美林大学大学院大学アドミニストレーション研究科の提供科目])
- 大橋敏子(2002).国際交流の専門職 IDE:現代の高等教育,439,50-55.(桜美林大学シラバス検索で知る[桜美林大学大学院大学アドミニストレーション研究科の提供科目])
- 村松君雄(2002).国立大学のSD IDE:現代の高等教育,439,45-50.(桜美林大学シラバス検索で知る[桜美林大学大学院大学アドミニストレーション研究科の提供科目])
- 河原崎福治(2002).職員組織による研究サポート IDE:現代の高等教育,439,40-45.(桜美林大学シラバス検索で知る[桜美林大学大学院大学アドミニストレーション研究科の提供科目])
- 小出秀文(2002).私立大学協会の職員研修事業:直接実施の「全国研修会」を中心に IDE:現代の高等教育,439,35-40.(桜美林大学シラバス検索で知る[桜美林大学大学院大学アドミニストレーション研究科の提供科目])
- 吉田信正(2002).私立大学連盟の職員研修事業 IDE:現代の高等教育,439,29-34.(桜美林大学シラバス検索で知る[桜美林大学大学院大学アドミニストレーション研究科の提供科目])
- 孫福弘(2002).経験的SD論 IDE:現代の高等教育,439,24-29.(桜美林大学シラバス検索で知る[桜美林大学大学院大学アドミニストレーション研究科の提供科目])
- 佐藤東洋士(2002).大学院でのSDの可能性 IDE:現代の高等教育,439,18-24.(桜美林大学シラバス検索で知る[桜美林大学大学院大学アドミニストレーション研究科の提供科目])
- 山本眞一(2002).なぜいまSDなのか IDE:現代の高等教育,439,13-18.(桜美林大学シラバス検索で知る[桜美林大学大学院大学アドミニストレーション研究科の提供科目])
- 舘昭(2002).SDの課題:プロフェッショナル時代の教員外職員能力開発 IDE:現代の高等教育,439,5-13.(桜美林大学シラバス検索で知る[桜美林大学大学院大学アドミニストレーション研究科の提供科目])
- 本間政雄(2003).米国の大学の管理運営と事務職員の養成 大学時報,52(288),70-75.(桜美林大学シラバス検索で知る[桜美林大学大学院大学アドミニストレーション研究科の提供科目])
- 武村秀雄(2003).専門知識を有する大学職員の養成:大学アドミニストレーション専攻 大学時報,52(288),64-69.(桜美林大学シラバス検索で知る[桜美林大学大学院大学アドミニストレーション研究科の提供科目])
- 今泉博之(2003).今後の大学職員研修に求められるもの 大学時報,52(288),58-63.(桜美林大学シラバス検索で知る[桜美林大学大学院大学アドミニストレーション研究科の提供科目])
- 西澤勇(2003).医科系大学における教職協働の取り組み 大学時報,52(288),54-57.(桜美林大学シラバス検索で知る[桜美林大学大学院大学アドミニストレーション研究科の提供科目])
- 石黒敦子(2003).試行錯誤する国外研修制度 大学時報,52(288),48-53.(桜美林大学シラバス検索で知る[桜美林大学大学院大学アドミニストレーション研究科の提供科目])
- 石渡朝男(2003).能力開発型人事制度導入による組織改革 大学時報,52(288),42-47.(桜美林大学シラバス検索で知る[桜美林大学大学院大学アドミニストレーション研究科の提供科目])
- 阿曽沼一成(2003).今日の大学職員の役割 大学時報,52(288),36-41.(桜美林大学シラバス検索で知る[桜美林大学大学院大学アドミニストレーション研究科の提供科目])
- 高野二郎(2003).新しい大学の創造と職員の役割 大学時報,52(288),32-35.(桜美林大学シラバス検索で知る[桜美林大学大学院大学アドミニストレーション研究科の提供科目])
- 武村秀雄(2005).大学院の職員能力開発プログラム:桜美林大学の専攻例 IDE:現代の高等教育,469,59-64.(桜美林大学シラバス検索で知る[桜美林大学大学院大学アドミニストレーション研究科の提供科目])
- 篠田道夫(2005).日本福祉大学事務局改革の歩みと挑戦:『大学職員論』での提起とその背景 IDE:現代の高等教育,469,54-59.(桜美林大学シラバス検索で知る[桜美林大学大学院大学アドミニストレーション研究科の提供科目])
- 井原徹(2005).職員組織改革の視点:早稲田大学での経験をふまえて IDE:現代の高等教育,469,49-54.(桜美林大学シラバス検索で知る[桜美林大学大学院大学アドミニストレーション研究科の提供科目])
- 原邦夫(2005).大学行政管理学会の役割について IDE:現代の高等教育,469,44-49.(桜美林大学シラバス検索で知る[桜美林大学大学院大学アドミニストレーション研究科の提供科目])
- 瀧澤博三(2005).私立大学職員に期待されること IDE:現代の高等教育,469,40-44.(桜美林大学シラバス検索で知る[桜美林大学大学院大学アドミニストレーション研究科の提供科目])
- 椿弘次(2005).日本私立大学連盟の職員研修事業:大学間競争をこえて IDE:現代の高等教育,469,36-40.(桜美林大学シラバス検索で知る[桜美林大学大学院大学アドミニストレーション研究科の提供科目])
- 天野郁夫(2005).国立大学財務・経営センターの研修事業 IDE:現代の高等教育,469,32-36.(桜美林大学シラバス検索で知る[桜美林大学大学院大学アドミニストレーション研究科の提供科目])
- 本間政雄(2005).国立大学法人職員への期待 IDE:現代の高等教育,469,27-31.(桜美林大学シラバス検索で知る[桜美林大学大学院大学アドミニストレーション研究科の提供科目])
- 南学(2005).公立大学(法人)職員への期待 IDE:現代の高等教育,469,22-27.(桜美林大学シラバス検索で知る[桜美林大学大学院大学アドミニストレーション研究科の提供科目])
- 山本眞一(2005).大学職員の高度化の必要性 IDE:現代の高等教育,469,18-22.(桜美林大学シラバス検索で知る[桜美林大学大学院大学アドミニストレーション研究科の提供科目])
- 金子元久(2005).大学のスタッフディベロップメント:必要性と可能性 IDE:現代の高等教育,469,11-17.(桜美林大学シラバス検索で知る[桜美林大学大学院大学アドミニストレーション研究科の提供科目])
- 大江淳良(2005).大学職員の能力開発の視点 IDE:現代の高等教育,469,5-11.(桜美林大学シラバス検索で知る[桜美林大学大学院大学アドミニストレーション研究科の提供科目])
- 大谷忠彦・米田達郎(2011).米国派遣による職員能力開発:福岡工業大学における事例 IDE:現代の高等教育,535,57-61.(桜美林大学シラバス検索で知る[桜美林大学大学院大学アドミニストレーション研究科の提供科目])
- 福岡正藏(2011).SD事業の試行的実践:大学コンソーシアム京都 IDE:現代の高等教育,535,52-57.(桜美林大学シラバス検索で知る[桜美林大学大学院大学アドミニストレーション研究科の提供科目])
- 大坪檀(2011).共鳴・共感できる理念とミッションが職員を育てる:静岡産業大学 IDE:現代の高等教育,535,47-51.(桜美林大学シラバス検索で知る[桜美林大学大学院大学アドミニストレーション研究科の提供科目])
- 伊藤昇(2011).大学アドミニストレーター養成プログラム:立命館大学大学行政研究・研修センター IDE:現代の高等教育,535,42-46.(桜美林大学シラバス検索で知る[桜美林大学大学院大学アドミニストレーション研究科の提供科目])
- 池田輝政(2011).教育職員の成長プログラムづくり:名城大学大学・学校づくり研究科 IDE:現代の高等教育,535,37-42.(桜美林大学シラバス検索で知る[桜美林大学大学院大学アドミニストレーション研究科の提供科目])
- 伊藤彰浩(2011).高等教育マネジメント分野の現状:名古屋大学大学院 IDE:現代の高等教育,535,33-36.(桜美林大学シラバス検索で知る[桜美林大学大学院大学アドミニストレーション研究科の提供科目])
- 稲永由紀(2011).大学マネジメント人材の養成をめざして:筑波大学大学研究センター IDE:現代の高等教育,535,29-33.(桜美林大学シラバス検索で知る[桜美林大学大学院大学アドミニストレーション研究科の提供科目])
- 両角亜希子(2011).大学経営・政策コースの取り組み:東京大学 IDE:現代の高等教育,535,24-28.(桜美林大学シラバス検索で知る[桜美林大学大学院大学アドミニストレーション研究科の提供科目])
- 舘昭(2011).大学職員の「大学アドミニストレーター」への成長:桜美林大学大学院の取り組み IDE:現代の高等教育,535,20-24.(桜美林大学シラバス検索で知る[桜美林大学大学院大学アドミニストレーション研究科の提供科目])
- 大島英穂(2011).実践を通した職員の成長 IDE:現代の高等教育,535,15-20.(桜美林大学シラバス検索で知る[桜美林大学大学院大学アドミニストレーション研究科の提供科目])
- 加藤毅(2011).成長する職員が大学を動かす IDE:現代の高等教育,535,10-14.(桜美林大学シラバス検索で知る[桜美林大学大学院大学アドミニストレーション研究科の提供科目])
- 上杉道世(2011).大学職員は成長する IDE:現代の高等教育,535,4-9.(桜美林大学シラバス検索で知る[桜美林大学大学院大学アドミニストレーション研究科の提供科目])
- 大橋敏子(2002).国際交流の専門職 IDE:現代の高等教育,439,50-55.(桜美林大学シラバス検索で知る[桜美林大学大学院大学アドミニストレーション研究科の提供科目])
- 村松君雄(2002).国立大学のSD IDE:現代の高等教育,439,45-50.(桜美林大学シラバス検索で知る[桜美林大学大学院大学アドミニストレーション研究科の提供科目])
- 河原崎福治(2002).職員組織による研究サポート IDE:現代の高等教育,439,40-45.(桜美林大学シラバス検索で知る[桜美林大学大学院大学アドミニストレーション研究科の提供科目])
- 孫福弘(2002).経験的SD論 IDE:現代の高等教育,439,24-29.(桜美林大学シラバス検索で知る[桜美林大学大学院大学アドミニストレーション研究科の提供科目])
- Watson, D.大崎仁(訳)(2010).高等教育マネジメントのMBA(経営修士) IDE:現代の高等教育,523,50-57.(桜美林大学シラバス検索で知る[桜美林大学大学院大学アドミニストレーション研究科の提供科目])
- 両角亜希子(2010).職員の将来像と育成の課題・職員調査から IDE:現代の高等教育,523,45-49.(桜美林大学シラバス検索で知る[桜美林大学大学院大学アドミニストレーション研究科の提供科目])
- 川本幸彦(2010).国立大学の職員育成・兵庫教育大学を事例に IDE:現代の高等教育,523,40-45.(桜美林大学シラバス検索で知る[桜美林大学大学院大学アドミニストレーション研究科の提供科目])
- 谷口邦生(2010).「教職協働」を担う職員の育成・早稲田大学 IDE:現代の高等教育,523,35-39.(桜美林大学シラバス検索で知る[桜美林大学大学院大学アドミニストレーション研究科の提供科目])
- 鈴木敏之(2010).「行動シナリオ」と職員養成の課題・東京大学 IDE:現代の高等教育,523,30-35.(桜美林大学シラバス検索で知る[桜美林大学大学院大学アドミニストレーション研究科の提供科目])
- 大工原孝(2010).大学の事務組織と職員 IDE:現代の高等教育,523,25-29.(桜美林大学シラバス検索で知る[桜美林大学大学院大学アドミニストレーション研究科の提供科目])
- 山本清(2010).大学職員の能力開発 IDE:現代の高等教育,523,20-24.(桜美林大学シラバス検索で知る[桜美林大学大学院大学アドミニストレーション研究科の提供科目])
- 上杉道世(2010).変化する国立大学の事務組織 IDE:現代の高等教育,523,14-19.(桜美林大学シラバス検索で知る[桜美林大学大学院大学アドミニストレーション研究科の提供科目])
- 柴田洋三郎(2010).大学職員への期待 IDE:現代の高等教育,523,10-14.(桜美林大学シラバス検索で知る[桜美林大学大学院大学アドミニストレーション研究科の提供科目])
- 加藤毅(2010).大学職員のプロフェッショナル化に向けて IDE:現代の高等教育,523,4-10.(桜美林大学シラバス検索で知る[桜美林大学大学院大学アドミニストレーション研究科の提供科目])
- 鈴木克夫(2013).金成隆一著『ルポMOOC革命 無料オンライン授業の衝撃』 日本通信教育学会研究論集,92-96.(桜美林大学シラバス検索で知る[桜美林大学大学院大学アドミニストレーション研究科の提供科目])
- 鈴木克夫(2012).通信教育制度研究の視点と視野 日本教育社会学会大会発表要旨集録,64,230-231.(桜美林大学シラバス検索で知る[桜美林大学大学院大学アドミニストレーション研究科の提供科目])
- 鈴木克夫(2012).構造改革特区832全国展開の是非を問う 日本通信教育学会研究論集,77-83.(桜美林大学シラバス検索で知る[桜美林大学大学院大学アドミニストレーション研究科の提供科目])
- 鈴木克夫(2010).大学通信教育と「特修生」:「開かれた大学」の入学資格に潜むもの 桜美林論考.心理・教育学研究,1,87-110.(桜美林大学シラバス検索で知る[桜美林大学大学院大学アドミニストレーション研究科の提供科目])
- 鈴木克夫(2010).通信教育研究の回顧と展望:本学会『集録』の分析から 日本通信教育学会研究論集,4-15.(桜美林大学シラバス検索で知る[桜美林大学大学院大学アドミニストレーション研究科の提供科目])
- 鈴木克夫(2009).通信制大学院の現状と課題:社会人の再教育機関としての実態を中心に 桜美林高等教育研究,1,43-57.(桜美林大学シラバス検索で知る[桜美林大学大学院大学アドミニストレーション研究科の提供科目])
- 鈴木克夫(2009).サイバー大学本人確認問題考:構造改革特区832という桎梏 桜美林シナジー,8,27-46.(桜美林大学シラバス検索で知る[桜美林大学大学院大学アドミニストレーション研究科の提供科目])
- 石原朗子・鈴木克夫(2008).通信制大学院における学習状況について:2007年度学生実態調査から 日本教育社会学会大会発表要旨集録,60,207-208.(桜美林大学シラバス検索で知る[桜美林大学大学院大学アドミニストレーション研究科の提供科目])
- 鈴木克夫(2008).大学通信教育と社会人学生 IDE現代の高等教育,502,30-35.(桜美林大学シラバス検索で知る[桜美林大学大学院大学アドミニストレーション研究科の提供科目])
- 鈴木克夫(2006).八洲学園大学と星槎大学:新しい大学像を掲げる「通信制のみの2大学」 カレッジマネジメント,24(3),56-63.(桜美林大学シラバス検索で知る[桜美林大学大学院大学アドミニストレーション研究科の提供科目])
- 鈴木克夫(2004).通信教育と遠隔教育の関係を整理する:構造改革特区でさらに多様化するその設置形態 カレッジマネジメント,22(4),13-19.(桜美林大学シラバス検索で知る[桜美林大学大学院大学アドミニストレーション研究科の提供科目])
- 白石克己・川田隆雄・関口英里・鈴木克夫・武内雅俊(2002).大学導入教育における三つの異なるメディアの比較研究:自立学習支援教材『読む・書く・問う』の印刷教材版・CD-ROM 版・ビデオ版を使って 日本教育工学会大会講演論文集,18,829-830.(桜美林大学シラバス検索で知る[桜美林大学大学院大学アドミニストレーション研究科の提供科目])
- 鈴木克夫(2002).大学通信教育と「スクーリング」 大学時報,51(287),88-91.(桜美林大学シラバス検索で知る[桜美林大学大学院大学アドミニストレーション研究科の提供科目])
- 鈴木克夫(2002).通信教育とeラーニング IDE:現代の高等教育,440,38-42.(桜美林大学シラバス検索で知る[桜美林大学大学院大学アドミニストレーション研究科の提供科目])
- 鈴木克夫(2002).高等教育機関間の「異動」を自由に 週刊教育資料,748,46.(桜美林大学シラバス検索で知る[桜美林大学大学院大学アドミニストレーション研究科の提供科目])
- 鈴木克夫・南学・吉田文(2002).大学教育の可能性を探る:通信教育とEラーニングでここまでは出来る カレッジマネジメント,20(1),52-59.(桜美林大学シラバス検索で知る[桜美林大学大学院大学アドミニストレーション研究科の提供科目])
- 鈴木克夫(2002).人間総合科学大学 研究報告,31,310-312.(桜美林大学シラバス検索で知る[桜美林大学大学院大学アドミニストレーション研究科の提供科目])
- 鈴木克夫(2002).高等教育機関における編入学制度の考察 日本生涯教育学会論集,23,53-60.(桜美林大学シラバス検索で知る[桜美林大学大学院大学アドミニストレーション研究科の提供科目])
- 鈴木克夫(2001).「読む・書く・問う」の指導:自立学習型遠隔教育の実践 研究報告,22,26-34.(桜美林大学シラバス検索で知る[桜美林大学大学院大学アドミニストレーション研究科の提供科目])
- 鈴木克夫(2000).e-教材は専門家の共同作業なしに作れない:「通学制」と「通信制」の区別をどうつける カレッジマネジメント,18(5),46-48.(桜美林大学シラバス検索で知る[桜美林大学大学院大学アドミニストレーション研究科の提供科目])
- 鈴木克夫(1999).二つの遠隔教育:通信教育から遠隔教育への概念的連続性と不連続性について メディア教育研究,3,1-12.(桜美林大学シラバス検索で知る[桜美林大学大学院大学アドミニストレーション研究科の提供科目])
- 鈴木克夫(1998).「通信制大学院」の制度化について:大学審議会答申の背景とその意味 メディア教育研究,1,39-56.(桜美林大学シラバス検索で知る[桜美林大学大学院大学アドミニストレーション研究科の提供科目])
- 市川昭午(1990).政策志向の社会諸科学 教育社会学研究,47,95-100.[PDF](桜美林大学シラバス検索で知る[桜美林大学大学院大学アドミニストレーション研究科の提供科目])
- 上山浩次郎(2011).大学進学率の都道府県間格差の要因構造とその変容:多母集団パス解析による4時点比較 教育社会学研究,88,207-227.[PDF](桜美林大学シラバス検索で知る[桜美林大学大学院大学アドミニストレーション研究科の提供科目])
- 上山浩次郎(2012).高等教育進学率における地域間格差の再検証 現代社会学研究,25,21-36.[PDF](桜美林大学シラバス検索で知る[桜美林大学大学院大学アドミニストレーション研究科の提供科目])
- 上山浩次郎(2012).大学収容率からみた教育機会の地域間格差 北海道大学大学院教育学研究院紀要,115,1-15.[PDF](桜美林大学シラバス検索で知る[桜美林大学大学院大学アドミニストレーション研究科の提供科目])
- 上山浩次郎(2014).進路行動と地域移動:1990年代以降における関東での大学進学移動に注目して 北海道大学大学院教育学研究院紀要,120,111-135.[PDF](桜美林大学シラバス検索で知る[桜美林大学大学院大学アドミニストレーション研究科の提供科目])
- 潮木守一(2008).大学進学率上昇をもたらしたのは何なのか:計量分析と経験知の間で 教育社会学研究,83,5-22.[PDF](桜美林大学シラバス検索で知る[桜美林大学大学院大学アドミニストレーション研究科の提供科目])
- 浦田広朗(2009).大学の変容:供給構造と資金配分の変動がもたらしたもの 高等教育研究,12,29-48.(桜美林大学シラバス検索で知る[桜美林大学大学院大学アドミニストレーション研究科の提供科目])
- 大井方子(2013).進学率の地域格差に関する研究 社会科学論集:高知短期大学研究報告,102,21-40.(桜美林大学シラバス検索で知る[桜美林大学大学院大学アドミニストレーション研究科の提供科目])
- 金子元久(1986).高等教育進学率の時系列分析 大学論集,16,41-64.[PDF](桜美林大学シラバス検索で知る[桜美林大学大学院大学アドミニストレーション研究科の提供科目])
- 金子元久(1990).政策科学としての教育社会学 教育社会学研究,47,21-36.[PDF](桜美林大学シラバス検索で知る[桜美林大学大学院大学アドミニストレーション研究科の提供科目])
- 南学(2003).自治体の高等教育政策 IDE:現代の高等教育,451,12-16.(桜美林大学シラバス検索で知る[桜美林大学大学院大学アドミニストレーション研究科の提供科目])
- 南学(2005).公立大学(法人)職員への期待 IDE:現代の高等教育,469,22-27.(桜美林大学シラバス検索で知る[桜美林大学大学院大学アドミニストレーション研究科の提供科目])
- 鎌田積(2007).公立大学の動向:データを中心に IDE:現代の高等教育,488,55-62.(桜美林大学シラバス検索で知る[桜美林大学大学院大学アドミニストレーション研究科の提供科目])
- 高橋寛人(2007).公設民営大学の設立経緯にみる地域と大学 IDE:現代の高等教育,488,50-55.(桜美林大学シラバス検索で知る[桜美林大学大学院大学アドミニストレーション研究科の提供科目])
- 岡村甫(2007).公設民営大学の現状 IDE:現代の高等教育,488,48-50.(桜美林大学シラバス検索で知る[桜美林大学大学院大学アドミニストレーション研究科の提供科目])
- 新富康央(2007).国立大学と自治体:「民学官」連携への展望と課題 IDE:現代の高等教育,488,44-47.(桜美林大学シラバス検索で知る[桜美林大学大学院大学アドミニストレーション研究科の提供科目])
- 常本秀幸(2007).地方国立大学と自治体等との連携:北見工業大学の場合 IDE:現代の高等教育,488,40-44.(桜美林大学シラバス検索で知る[桜美林大学大学院大学アドミニストレーション研究科の提供科目])
- 黒木登志夫(2007).国立大学と公立大学の連携:岐阜大学と岐阜薬科大学の場合 IDE:現代の高等教育,488,36-40.(桜美林大学シラバス検索で知る[桜美林大学大学院大学アドミニストレーション研究科の提供科目])
- 曽我直弘(2007).大学の地域密着型活動と自治体 IDE:現代の高等教育,488,32-35.(桜美林大学シラバス検索で知る[桜美林大学大学院大学アドミニストレーション研究科の提供科目])
- 草間朋子(2007).地域医療と公立大学 IDE:現代の高等教育,488,28-32.(桜美林大学シラバス検索で知る[桜美林大学大学院大学アドミニストレーション研究科の提供科目])
- 角山茂章(2007).地域振興と会津大学 IDE:現代の高等教育,488,24-27.(桜美林大学シラバス検索で知る[桜美林大学大学院大学アドミニストレーション研究科の提供科目])
- 矢田俊文(2007).公立大学の法人化 IDE:現代の高等教育,488,18-24.(桜美林大学シラバス検索で知る[桜美林大学大学院大学アドミニストレーション研究科の提供科目])
- 中岡司(2007).公立大学改革 IDE:現代の高等教育,488,14-18.(桜美林大学シラバス検索で知る[桜美林大学大学院大学アドミニストレーション研究科の提供科目])
- 森正夫(2007).公立大学論 IDE:現代の高等教育,488,9-14.(桜美林大学シラバス検索で知る[桜美林大学大学院大学アドミニストレーション研究科の提供科目])
- 宇野重昭(2007).公立大学の現状と課題:「公共」の立場の確立をめざして IDE:現代の高等教育,488,4-8.(桜美林大学シラバス検索で知る[桜美林大学大学院大学アドミニストレーション研究科の提供科目])
- 南学(2008).エクステンションを軸とした大学の地域貢献の可能性 大学財務経営研究,5,229-236.(桜美林大学シラバス検索で知る[桜美林大学大学院大学アドミニストレーション研究科の提供科目])
- 千葉吉裕(2009).学生募集の課題 IDE:現代の高等教育,514,63-67.(桜美林大学シラバス検索で知る[桜美林大学大学院大学アドミニストレーション研究科の提供科目])
- 石塚公康(2009).「付属校」戦略の展開 IDE:現代の高等教育,514,58-63.(桜美林大学シラバス検索で知る[桜美林大学大学院大学アドミニストレーション研究科の提供科目])
- 大江淳良(2009).私立大学のガバナンス IDE:現代の高等教育,514,52-58.(桜美林大学シラバス検索で知る[桜美林大学大学院大学アドミニストレーション研究科の提供科目])
- 西井泰彦(2009).私学経営の危機 IDE:現代の高等教育,514,45-52.(桜美林大学シラバス検索で知る[桜美林大学大学院大学アドミニストレーション研究科の提供科目])
- 藤田幸男(2009).私学財政の問題と進路 IDE:現代の高等教育,514,39-45.(桜美林大学シラバス検索で知る[桜美林大学大学院大学アドミニストレーション研究科の提供科目])
- 河村潤子(2009).私学行政の課題 IDE:現代の高等教育,514,34-39.(桜美林大学シラバス検索で知る[桜美林大学大学院大学アドミニストレーション研究科の提供科目])
- 市川太一(2009).人口減少時代の地方私立大学:その戦略と課題 IDE:現代の高等教育,514,30-33.(桜美林大学シラバス検索で知る[桜美林大学大学院大学アドミニストレーション研究科の提供科目])
- 井原徹(2009).中小規模私大の課題と戦略 IDE:現代の高等教育,514,25-29.(桜美林大学シラバス検索で知る[桜美林大学大学院大学アドミニストレーション研究科の提供科目])
- 大沼淳(2009).私立大学の変遷と針路 IDE:現代の高等教育,514,17-25.(桜美林大学シラバス検索で知る[桜美林大学大学院大学アドミニストレーション研究科の提供科目])
- 白井克彦(2009).私立大学の課題と進むべき道 IDE:現代の高等教育,514,10-17.(桜美林大学シラバス検索で知る[桜美林大学大学院大学アドミニストレーション研究科の提供科目])
- 舘昭(2009).私立大学の現状と課題 IDE:現代の高等教育,514,4-10.(桜美林大学シラバス検索で知る[桜美林大学大学院大学アドミニストレーション研究科の提供科目])
- 影山光太郎(2007).学生の発明と職務発明 パテント,60(9),45-53.(桜美林大学シラバス検索で知る[桜美林大学大学院大学アドミニストレーション研究科の提供科目])
- 松村直樹・平尾元彦・松尾俊彦(2004).学生パーソナリティと就職活動特性:呉大学生調査に基づく実証分析 呉大学ネットワーク社会研究センター研究年報,4,41-53.(桜美林大学シラバス検索で知る[桜美林大学大学院大学アドミニストレーション研究科の提供科目])
- 米澤彰純(2011).アジアにおける高等教育の国際連携と日本:イニシアティブの多極化とその行方 比較教育学研究,43,75-87.(桜美林大学シラバス検索で知る[桜美林大学大学院大学アドミニストレーション研究科の提供科目])
- 南部広孝(2011).香港におけるトランスナショナル高等教育の展開 比較教育学研究,43,62-74.(桜美林大学シラバス検索で知る[桜美林大学大学院大学アドミニストレーション研究科の提供科目])
- Sugimura, M.(2011).Diversification of International Student Mobility and Transnational Programs in Asian Higher Education 比較教育学研究,43,45-61.(桜美林大学シラバス検索で知る[桜美林大学大学院大学アドミニストレーション研究科の提供科目])
- 杉本和弘(2011).豪州大学によるトランスナショナル教育の展開と質保証 比較教育学研究,43,30-44.(桜美林大学シラバス検索で知る[桜美林大学大学院大学アドミニストレーション研究科の提供科目])
- 秦由美子(2011).連合王国における国境を越える教育:現状と課題 比較教育学研究,43,16-29.(桜美林大学シラバス検索で知る[桜美林大学大学院大学アドミニストレーション研究科の提供科目])
- 杉本均(2011).トランスナショナル高等教育:新たな留学概念の登場 比較教育学研究,43,42078.(桜美林大学シラバス検索で知る[桜美林大学大学院大学アドミニストレーション研究科の提供科目])
- 榊原康貴(2014).大学通信教育とオープンエデュケーション 大学マネジメント,10(7),34-40.(桜美林大学シラバス検索で知る[桜美林大学大学院大学アドミニストレーション研究科の提供科目])
- 福原美三(2014).JMOOCの可能性 大学マネジメント,10(7),29-33.(桜美林大学シラバス検索で知る[桜美林大学大学院大学アドミニストレーション研究科の提供科目])
- 堀真寿美・小野成志(2014).ポストMOOCと日本の大学経営 大学マネジメント,10(7),22-28.(桜美林大学シラバス検索で知る[桜美林大学大学院大学アドミニストレーション研究科の提供科目])
- 重田勝介(2014).MOOCが高等教育に与えるインパクト 大学マネジメント,10(7),2-10.(桜美林大学シラバス検索で知る[桜美林大学大学院大学アドミニストレーション研究科の提供科目])
- 船守美穂(2014).MOOCと21世紀大学改革の相互作用 大学マネジメント,10(7),11-21.[PDF](桜美林大学シラバス検索で知る[桜美林大学大学院大学アドミニストレーション研究科の提供科目])
- 山内祐平・能地泰代・松本恵(2014).「オンライン学習+対面型授業」の教育効果 カレッジマネジメント,32(2),12-15.(桜美林大学シラバス検索で知る[桜美林大学大学院大学アドミニストレーション研究科の提供科目])
- 飯吉透(2014).オープンエデュケーションの進展と高等教育の質保証の課題:MOOCの台頭を巡って カレッジマネジメント,32(2),6-11.(桜美林大学シラバス検索で知る[桜美林大学大学院大学アドミニストレーション研究科の提供科目])
- 木村健太(2014).やってみたJMOOC:事務職員による受講体験記 大学時報,63(358),52-57.(桜美林大学シラバス検索で知る[桜美林大学大学院大学アドミニストレーション研究科の提供科目])
- 矢野桂司(2014).JMOOCの準備段階における課題と期待 大学時報,63(358),48-51.(桜美林大学シラバス検索で知る[桜美林大学大学院大学アドミニストレーション研究科の提供科目])
- 白尾隆太郎(2014).美術大学の実技課題をメディア授業化する 大学時報,63(358),44-47.(桜美林大学シラバス検索で知る[桜美林大学大学院大学アドミニストレーション研究科の提供科目])
- 田中秀穂(2014).社会人学生市場の開拓とJMOOC:芝浦工業大学専門職大学院工学マネジメント研究科の取り組み 大学時報,63(358),38-43.(桜美林大学シラバス検索で知る[桜美林大学大学院大学アドミニストレーション研究科の提供科目])
- 福原美三(2014).内外のMOOCの経緯と現状及び将来展望 大学時報,63(358),30-37.(桜美林大学シラバス検索で知る[桜美林大学大学院大学アドミニストレーション研究科の提供科目])
- 白井克彦・吉見俊哉・美馬のゆり(2014).世界で広まるMOOC(Massive Open Online Course):わが国の高等教育への展開 大学時報,63(358),14-29.(桜美林大学シラバス検索で知る[桜美林大学大学院大学アドミニストレーション研究科の提供科目])
- 小島佳子(2014).海外大学最新事情:フランス高等教育におけるデジタル化計画 IDE:現代の高等教育,564,70-74.(桜美林大学シラバス検索で知る[桜美林大学大学院大学アドミニストレーション研究科の提供科目])
- 飯吉透(2014).ICT利用とアメリカ高等教育の進展:その潮流と意義 IDE:現代の高等教育,564,62-66.(桜美林大学シラバス検索で知る[桜美林大学大学院大学アドミニストレーション研究科の提供科目])
- 白井克彦(2014).ICTと大学 IDE:現代の高等教育,564,54-61.(桜美林大学シラバス検索で知る[桜美林大学大学院大学アドミニストレーション研究科の提供科目])
- 阿部一晴(2014).京都光華女子大学のEM:実現基盤としてのポータルシステム IDE:現代の高等教育,564,50-54.(桜美林大学シラバス検索で知る[桜美林大学大学院大学アドミニストレーション研究科の提供科目])
- 鞆大輔(2014).近畿大学におけるSNS活用事例 IDE:現代の高等教育,564,45-49.(桜美林大学シラバス検索で知る[桜美林大学大学院大学アドミニストレーション研究科の提供科目])
- 肥後功一(2014).島根大学における教学IRの展開:WILL BEと反転授業 IDE:現代の高等教育,564,39-45.(桜美林大学シラバス検索で知る[桜美林大学大学院大学アドミニストレーション研究科の提供科目])
- 村田嘉弘(2014).長崎大学の主体的学修とICT IDE:現代の高等教育,564,34-39.(桜美林大学シラバス検索で知る[桜美林大学大学院大学アドミニストレーション研究科の提供科目])
- 美濃導彦(2014).京都大学のICT戦略:教育支援環境を中心に IDE:現代の高等教育,564,29-34.(桜美林大学シラバス検索で知る[桜美林大学大学院大学アドミニストレーション研究科の提供科目])
- 村山斉・荒優・藤本徹(2014).東京大学のMOOC配信の取り組み IDE:現代の高等教育,564,22-29.(桜美林大学シラバス検索で知る[桜美林大学大学院大学アドミニストレーション研究科の提供科目])
- 福原美三(2014).JMOOCの可能性 IDE:現代の高等教育,564,17-21.(桜美林大学シラバス検索で知る[桜美林大学大学院大学アドミニストレーション研究科の提供科目])
- 吉田文(2014).ICTは日本の大学教育を変えるのか IDE:現代の高等教育,564,10-16.(桜美林大学シラバス検索で知る[桜美林大学大学院大学アドミニストレーション研究科の提供科目])
- 安浦寛人(2014).大学の教育改革とICT IDE:現代の高等教育,564,4-9.(桜美林大学シラバス検索で知る[桜美林大学大学院大学アドミニストレーション研究科の提供科目])
- 川本皓嗣(2014).JMOOC講座「俳句:十七字の世界」を担当して 大学教育と情報,2014(3),11-13.(桜美林大学シラバス検索で知る[桜美林大学大学院大学アドミニストレーション研究科の提供科目])
- 福原美三(2014).JMOOCを理解するために 大学教育と情報,2014(3),2-10.(桜美林大学シラバス検索で知る[桜美林大学大学院大学アドミニストレーション研究科の提供科目])
- 山田礼子(2003).大学院改革の動向:専門職大学院の整備と拡充 教育學研究,70(2),148-164.[PDF](桜美林大学シラバス検索で知る[桜美林大学大学院大学アドミニストレーション研究科の提供科目])
- 山田礼子(2004).プロフェッショナル化する社会と人材:経営人材のプロフェッショナル化と教育 高等教育研究,7,23-47.(桜美林大学シラバス検索で知る[桜美林大学大学院大学アドミニストレーション研究科の提供科目])
- 本田由紀(2001).社会人教育の現状と課題:修士課程を中心に 高等教育研究,4,93-112.(桜美林大学シラバス検索で知る[桜美林大学大学院大学アドミニストレーション研究科の提供科目])
- 芝田政之(2010).イギリスの奨学金制度:イングランドの授業料・奨学金・ローン制度を中心に IDE:現代の高等教育,520,54-58.(桜美林大学シラバス検索で知る[桜美林大学大学院大学アドミニストレーション研究科の提供科目])
- 犬塚典子(2010).アメリカの学生支援:学資ローンと債務 IDE:現代の高等教育,520,48-53.(桜美林大学シラバス検索で知る[桜美林大学大学院大学アドミニストレーション研究科の提供科目])
- 両角亜希子(2010).大学生の経済環境と学習・生活 IDE:現代の高等教育,520,41-47.(桜美林大学シラバス検索で知る[桜美林大学大学院大学アドミニストレーション研究科の提供科目])
- 斉藤鉄生(2010).私立大学の学内奨学金 IDE:現代の高等教育,520,36-41.(桜美林大学シラバス検索で知る[桜美林大学大学院大学アドミニストレーション研究科の提供科目])
- 加藤毅(2010).学生生活調査と奨学金政策 IDE:現代の高等教育,520,29-35.(桜美林大学シラバス検索で知る[桜美林大学大学院大学アドミニストレーション研究科の提供科目])
- 梶山千里(2010).奨学金の現状と課題 IDE:現代の高等教育,520,24-29.(桜美林大学シラバス検索で知る[桜美林大学大学院大学アドミニストレーション研究科の提供科目])
- 小林雅之(2010).学費と奨学金 IDE:現代の高等教育,520,18-23.(桜美林大学シラバス検索で知る[桜美林大学大学院大学アドミニストレーション研究科の提供科目])
- 小塩隆士(2010).教育費負担の経済学 IDE:現代の高等教育,520,12-18.(桜美林大学シラバス検索で知る[桜美林大学大学院大学アドミニストレーション研究科の提供科目])
- 矢野眞和(2010).教育費政策のこれから:「日本的大衆大学」という習慣病を考える IDE:現代の高等教育,520,4-12.(桜美林大学シラバス検索で知る[桜美林大学大学院大学アドミニストレーション研究科の提供科目])
- 韓民(2007).中国の高等教育費政策 IDE:現代の高等教育,492,66-72.(桜美林大学シラバス検索で知る[桜美林大学大学院大学アドミニストレーション研究科の提供科目])
- 小山竜司(2007).アメリカの高等教育政策と学生支援 IDE:現代の高等教育,492,60-66.(桜美林大学シラバス検索で知る[桜美林大学大学院大学アドミニストレーション研究科の提供科目])
- 芝田政之(2007).イギリスの学費政策 IDE:現代の高等教育,492,53-59.(桜美林大学シラバス検索で知る[桜美林大学大学院大学アドミニストレーション研究科の提供科目])
- 村田直樹(2007).高等教育と財政政策 IDE:現代の高等教育,492,48-52.(桜美林大学シラバス検索で知る[桜美林大学大学院大学アドミニストレーション研究科の提供科目])
- 両角亜希子(2007).高等教育費負担の国際比較 IDE:現代の高等教育,492,42-47.(桜美林大学シラバス検索で知る[桜美林大学大学院大学アドミニストレーション研究科の提供科目])
- 小林雅之(2007).高等教育費の負担と教育機会 IDE:現代の高等教育,492,36-42.(桜美林大学シラバス検索で知る[桜美林大学大学院大学アドミニストレーション研究科の提供科目])
- 奥島孝康(2007).私立大学の費用負担 IDE:現代の高等教育,492,32-35.(桜美林大学シラバス検索で知る[桜美林大学大学院大学アドミニストレーション研究科の提供科目])
- 長田豊臣(2007).高等教育の費用負担と制度改革 IDE:現代の高等教育,492,28-32.(桜美林大学シラバス検索で知る[桜美林大学大学院大学アドミニストレーション研究科の提供科目])
- 小塩隆士(2007).高等教育費負担と経済学 IDE:現代の高等教育,492,22-28.(桜美林大学シラバス検索で知る[桜美林大学大学院大学アドミニストレーション研究科の提供科目])
- 金子元久(2007).高等教育財政の課題:質を支える財政へ IDE:現代の高等教育,492,16-21.(桜美林大学シラバス検索で知る[桜美林大学大学院大学アドミニストレーション研究科の提供科目])
- 矢野眞和(2007).誰が教育費を負担すべきか:教育費の社会学 IDE:現代の高等教育,492,10-16.(桜美林大学シラバス検索で知る[桜美林大学大学院大学アドミニストレーション研究科の提供科目])
- 鳥居泰彦(2007).高等教育費負担の新時代を拓く IDE:現代の高等教育,492,4-10.(桜美林大学シラバス検索で知る[桜美林大学大学院大学アドミニストレーション研究科の提供科目])
- 義本博司(2013).高等教育費政策の課題 IDE:現代の高等教育,555,59-65.(桜美林大学シラバス検索で知る[桜美林大学大学院大学アドミニストレーション研究科の提供科目])
- 水田健輔(2013).国立大学収支の現状 IDE:現代の高等教育,555,53-59.(桜美林大学シラバス検索で知る[桜美林大学大学院大学アドミニストレーション研究科の提供科目])
- 浦田広朗(2013).私立大学の資金収支 IDE:現代の高等教育,555,47-53.(桜美林大学シラバス検索で知る[桜美林大学大学院大学アドミニストレーション研究科の提供科目])
- 井原徹(2013).私立大学と外部資金 IDE:現代の高等教育,555,42-47.(桜美林大学シラバス検索で知る[桜美林大学大学院大学アドミニストレーション研究科の提供科目])
- 松本洋一郎(2013).研究大学と外部資金 IDE:現代の高等教育,555,37-42.(桜美林大学シラバス検索で知る[桜美林大学大学院大学アドミニストレーション研究科の提供科目])
- 上山隆大(2013).誰が研究費を負担するのか IDE:現代の高等教育,555,31-36.(桜美林大学シラバス検索で知る[桜美林大学大学院大学アドミニストレーション研究科の提供科目])
- 宮田由紀夫(2013).アメリカにおける経済格差と大学進学 IDE:現代の高等教育,555,25-30.(桜美林大学シラバス検索で知る[桜美林大学大学院大学アドミニストレーション研究科の提供科目])
- 広井良典(2013).「人生前半の社会保障」と高等教育費 IDE:現代の高等教育,555,19-24.(桜美林大学シラバス検索で知る[桜美林大学大学院大学アドミニストレーション研究科の提供科目])
- 小林雅之(2013).国際的に見た教育費負担 IDE:現代の高等教育,555,13-19.(桜美林大学シラバス検索で知る[桜美林大学大学院大学アドミニストレーション研究科の提供科目])
- 矢野眞和(2013).大学は誰のためにあるのか IDE:現代の高等教育,555,4-12.(桜美林大学シラバス検索で知る[桜美林大学大学院大学アドミニストレーション研究科の提供科目])
- 浦田広朗(1998).私立大学学納金の規定要因分析 教育社会学研究,63,119-136.[PDF](桜美林大学シラバス検索で知る[桜美林大学大学院大学アドミニストレーション研究科の提供科目])
- 小林雅之・吉田香奈・劉文君(2012).『奨学金制度に関する学長調査』結果報告 カレッジマネジメント,30(6),6-21.[PDF](桜美林大学シラバス検索で知る[桜美林大学大学院大学アドミニストレーション研究科の提供科目])
- 小林雅之(2007).高等教育の経済分析 高等教育研究,10,63-81.(桜美林大学シラバス検索で知る[桜美林大学大学院大学アドミニストレーション研究科の提供科目])
- 小林雅之(2007).高等教育機会の格差と是正政策 教育社会学研究,80,101-125.[PDF](桜美林大学シラバス検索で知る[桜美林大学大学院大学アドミニストレーション研究科の提供科目])
- 小林雅之(2010).今後の学生への経済的支援のあり方:諸外国と比較して 大学と学生,88,6-13.(桜美林大学シラバス検索で知る[桜美林大学大学院大学アドミニストレーション研究科の提供科目])
- 吉田文(2008).大学生研究の位相 高等教育研究,11,127-142.(桜美林大学シラバス検索で知る[桜美林大学大学院大学アドミニストレーション研究科の提供科目])
- 濱中義隆(2008).「学生の流動化」と進路形成:現状と可能性 高等教育研究,11,107-126.(桜美林大学シラバス検索で知る[桜美林大学大学院大学アドミニストレーション研究科の提供科目])
- 小杉礼子(2008).大学生の進路選択と就職活動 高等教育研究,11,85-105.(桜美林大学シラバス検索で知る[桜美林大学大学院大学アドミニストレーション研究科の提供科目])
- 望月由起(2008).高等教育大衆化時代における大学生のキャリア意識:入学難易度によるキャリア成熟の差異に着目して 高等教育研究,11,65-84.(桜美林大学シラバス検索で知る[桜美林大学大学院大学アドミニストレーション研究科の提供科目])
- 小方直幸(2008).学生のエンゲージメントと大学教育のアウトカム 高等教育研究,11,45-64.(桜美林大学シラバス検索で知る[桜美林大学大学院大学アドミニストレーション研究科の提供科目])
- 大前敦巳(2008).大学進学者の文化資本形成 高等教育研究,11,25-44.(桜美林大学シラバス検索で知る[桜美林大学大学院大学アドミニストレーション研究科の提供科目])
- 武内清(2008).学生文化の実態と大学教育 高等教育研究,11,7-23.(桜美林大学シラバス検索で知る[桜美林大学大学院大学アドミニストレーション研究科の提供科目])
- 井下千以子(2009).大学職員のキャリア発達と学生支援業務:"学びのコミュニティ"の構築を目指して 桜美林シナジー,8,1-13.(桜美林大学シラバス検索で知る[桜美林大学大学院大学アドミニストレーション研究科の提供科目])
[2015.11.09]「私立大学職員によるIR文献メモ」メルマガ バックナンバーを更新
[2015.11.09]全ページでSNSボタン廃止
[2015.11.06]IRなどについての文献メモ 文献一覧を更新<高大接続答申>
- 荒瀬克己(2015).高校教育の質保障の観点から答申をどのように受けとめるか 月刊高校教育,48(2),34-37.(CiNii Articles「高大接続答申」で知る)
- 渡辺敦司(2015).中教審で何が議論され、何が議論されなかったのか 月刊高校教育,48(2),38-41.(CiNii Articles「特集中教審・高校教育部会/高大接続部会の議論を総括する」で知る)
- 及川良一(2015).高校基礎学力テストの「選抜ツール」化を懸念する 月刊高校教育,48(2),30-33.(CiNii Articles「特集中教審・高校教育部会/高大接続部会の議論を総括する」で知る)
- 無藤隆(2015).高校教育・大学教育・入学者選抜の抜本的改革を目指す 月刊高校教育,48(2),26-29.(CiNii Articles「特集中教審・高校教育部会/高大接続部会の議論を総括する」で知る)
- 安彦忠彦(2015).高校は「受験準備教育」からの脱却を 月刊高校教育,48(2),22-25.(CiNii Articles「特集中教審・高校教育部会/高大接続部会の議論を総括する」で知る)
[2015.11.06]IRなどについての文献メモ 内容をアップ
- 橋村勝明(2015).GPAのチューニングについて:アセスメントポリシーの確立のために 広島文教女子大学高等教育研究,1,15-23.[PDF](成績評価が教員個人に委ねられている状況では評価感の違いが科目GPA の違いとなって現れる(評価に関わる一定の方針が確立し得ない、学生の能力以上/以下の評価となってしまう)、「卒業研究」(各学科の専門課程のキャップストーン)の科目GPAを学科間で比較⇒差が1.5を上回った⇒大学としてひとつのディプロマポリシーを定めているのでLG(Letter Grade)1段階以上の差は疑問、全学共通の「卒業研究」の評価のためのルーブリックを作成して評価を実施することにした(科目をグループ化、1つの成績評価方針に基づき厳格かつ公正に成績評価)、課程の部分からのチューニング:カリキュラムマップ作成⇒科目のグループ化⇒関連科目内で教員の評価観がチューニングされる、課程を通じた全体からチューニング:高大接続答申で大学は高校の学力3要素を総合するとしている、その「総合した学力」はプログラムとしての課程を通じて養成される(科目によっては知識技能を重要視するものがあってもよい)、どの科目が学力三要素のどの部分を重要視するのかをカリキュラムマネジメントを通じて明確化しておけばよい;Twitter(@high190さん)で知る)
[2015.11.06]IRなどについての文献メモ 文献一覧を更新<成績評価、GPA、ディプロマポリシー、アセスメントポリシー、カリキュラムマネジメント、高大連携接続答申>
- 橋村勝明(2015).GPAのチューニングについて:アセスメントポリシーの確立のために 広島文教女子大学高等教育研究,1,15-23.[PDF][概要](Twitter(@high190さん)で知る)
- 橋村勝明(2013).カリキュラムマネジメントの方法と実践:広島文教女子大学における取組を通して 広島文教女子大学紀要,48,1-11.[PDF](橋村(2015)「GPAのチューニングについて」で知る)
[2015.11.05]IRなどについての文献メモ 文献一覧を更新<高等教育>
- 荒井克弘(2007).高等教育研究の新たな課題 高等教育研究の課題 高等教育研究,10,179-191.(CiNii Articles「特集 高等教育研究の10年」で知る)
- Ulrich, T.吉本圭一(訳)(2007).海外からの視点 外から見た日本の高等教育研究 高等教育研究,10,165-177.(CiNii Articles「特集 高等教育研究の10年」で知る)
- 塚原修一(2007).大学改革と政策過程 高等教育研究,10,151-163.(CiNii Articles「特集 高等教育研究の10年」で知る)
- 濱名篤(2007).大学評価の研究と実践の10年 高等教育研究,10,129-150.CiNii Articles「特集 高等教育研究の10年」で知る)
- 大塚雄作(2007).高等教育の個別的実践と普遍的理論化の狭間で:大学評価・FD実践の体験を通して 高等教育研究,10,111-127.(CiNii Articles「特集 高等教育研究の10年」で知る)
- 中村高康(2007).高等教育研究と社会学的想像力:高等教育社会学における理論と方法の今日的課題 高等教育研究,10,97-109.(CiNii Articles「特集 高等教育研究の10年」で知る)
- 丸山文裕(2007).高等教育における財政と経営管理の研究 高等教育研究,10,83-95.(CiNii Articles「特集 高等教育研究の10年」で知る)
- 小林雅之(2007).高等教育の経済分析 高等教育研究,10,63-81.(CiNii Articles「特集 高等教育研究の10年」で知る)
- 川嶋太津夫(2007).高等教育研究における比較研究の成果と課題:紀要掲載論文を中心にして 高等教育研究,10,51-61.(CiNii Articles「特集 高等教育研究の10年」で知る)
- 羽田貴史・大塚豊・安原義仁(2007).大学史・高等教育史研究の10年 高等教育研究,10,31-50.(CiNii Articles「特集 高等教育研究の10年」で知る)
- 橋本鉱市(2007).高等教育学会の10年:組織編成と知識形成 高等教育研究,10,7-29.(CiNii Articles「特集 高等教育研究の10年」で知る)
[2015.11.03]IRなどについての文献メモ 文献一覧を更新<高等教育>
- Boyer, E. L.喜多村和之・舘昭・伊藤彰浩(1996).アメリカの大学・カレッジ:大学教育改革への提言 改訂版 玉川大学出版部(CiNii Books「アメリカの大学・カレッジ」で知る)
[2015.11.03]IRなどについての文献メモ 文献一覧を更新<大学職員、大学院>
- 高野篤子(2010).ラウンドテーブル 大学職員の能力開発と採用:大学院課程での学び 大学教育学会誌,32(2),66-69.(CiNii Articles「大学職員の能力開発」で知る)
[2015.11.02]IRなどについての文献メモ 文献一覧を更新<統計>
[2015.11.02]「私立大学職員によるIR文献メモ」メルマガ バックナンバーを更新
[2015.11.02]IRなどについての文献メモ 文献一覧を更新<高等教育>
- Altbach, P. G., & Selvaratnam, V(編)馬越徹・大塚豊(監訳)(1993).アジアの大学:従属から自立へ 玉川大学出版部(東京大学大学院教育学研究科総合教育科学専攻大学経営・政策コース「2015年度シラバス」で知る)
- Altbach, P. G.馬越徹(訳)(1994).比較高等教育論:「知」の世界システムと大学 玉川大学出版部(東京大学大学院教育学研究科総合教育科学専攻大学経営・政策コース「2015年度シラバス」で知る)
- Barr, M. J., & McClellan, G. S.(2011). Budgets and financial management in higher education. San Francisco: Jossey-Bass.(東京大学大学院教育学研究科総合教育科学専攻大学経営・政策コース「2015年度シラバス」で知る)
- Birnbaum, R.高橋靖直(訳)(1992).大学経営とリーダーシップ 玉川大学出版部(東京大学大学院教育学研究科総合教育科学専攻大学経営・政策コース「2015年度シラバス」で知る)
- Bok, D. C.宮田由紀夫(訳)(2004).商業化する大学 玉川大学出版部(東京大学大学院教育学研究科総合教育科学専攻大学経営・政策コース「2015年度シラバス」で知る)
- Flexner, A.坂本辰朗・羽田積男・渡辺かよ子・犬塚典子(訳)(2005).大学論:アメリカ・イギリス・ドイツ 玉川大学出版部(東京大学大学院教育学研究科総合教育科学専攻大学経営・政策コース「2015年度シラバス」で知る)
- Fichte J. G., Steffens, H., & Humboldt, W. F. von 梅根悟(訳)(1970).大学の理念と構想 明治図書出版(東京大学大学院教育学研究科総合教育科学専攻大学経営・政策コース「2015年度シラバス」で知る)
- Führ, C.天野正治・木戸裕・長島啓記(訳)(1996).ドイツの学校と大学 玉川大学出版部(東京大学大学院教育学研究科総合教育科学専攻大学経営・政策コース「2015年度シラバス」で知る)
- Humboldt, W. F. von(著)Menze, C.(編)Luhmer, K.・小笠原道雄・江島正子(訳)(1989).人間形成と言語 以文社(東京大学大学院教育学研究科総合教育科学専攻大学経営・政策コース「2015年度シラバス」で知る)
- Keller, G.堀江未来(監訳)(2013).無名大学を優良大学にする力:ある大学の変革物語 学文社(東京大学大学院教育学研究科総合教育科学専攻大学経営・政策コース「2015年度シラバス」で知る)
- マックス・プランク教育研究所研究者グループ 天野正治・木戸裕・長島啓記(監訳)(2006).ドイツの教育のすべて 東信堂(東京大学大学院教育学研究科総合教育科学専攻大学経営・政策コース「2015年度シラバス」で知る)
- NewmanJ. H.(著)Milward, P.(編)田中秀人(訳)(1983).大学で何を学ぶか 大修館書店(東京大学大学院教育学研究科総合教育科学専攻大学経営・政策コース「2015年度シラバス」で知る)
- Ortéga y Gassét J.井上正(訳)(1996).大学の使命 玉川大学出版部(東京大学大学院教育学研究科総合教育科学専攻大学経営・政策コース「2015年度シラバス」で知る)
- Pelikan, J. J.田口孝夫(訳)(1996).大学とは何か 法政大学出版局(東京大学大学院教育学研究科総合教育科学専攻大学経営・政策コース「2015年度シラバス」で知る)
- Sanderson, M.安原義仁(訳)(2003).イギリスの大学改革:1809-1914 玉川大学出版部(東京大学大学院教育学研究科総合教育科学専攻大学経営・政策コース「2015年度シラバス」で知る)
- Schelling, F. W. J. von 勝田守一(訳)(1957).学問論 岩波書店(東京大学大学院教育学研究科総合教育科学専攻大学経営・政策コース「2015年度シラバス」で知る)
- Schleiermacher, F.梅根悟・梅根栄一(訳)(1961).国家権力と教育:大学論・教育学講義序説 明治図書出版(東京大学大学院教育学研究科総合教育科学専攻大学経営・政策コース「2015年度シラバス」で知る)
- Tight, M. (2012). Researching higher education. Maidenhead, UK: Society for Research into Higher Education & Open University Press.(東京大学大学院教育学研究科総合教育科学専攻大学経営・政策コース「2015年度シラバス」で知る)
- Walliman, N.(2011). Research methods:The basics. London, UK: Routledge.(東京大学大学院教育学研究科総合教育科学専攻大学経営・政策コース「2015年度シラバス」で知る)
- 安原義仁・大塚豊・羽田貴史(2008).大学と社会 放送大学教育振興会(東京大学大学院教育学研究科総合教育科学専攻大学経営・政策コース「2015年度シラバス」で知る)
- 伊東俊太郎(2006).十二世紀ルネサンス 講談社(東京大学大学院教育学研究科総合教育科学専攻大学経営・政策コース「2015年度シラバス」で知る)
- 横尾壮英(1999).大学の誕生と変貌:ヨーロッパ大学史断章 東信堂(東京大学大学院教育学研究科総合教育科学専攻大学経営・政策コース「2015年度シラバス」で知る)
- 加藤淳子・境家史郎・山本健太郎(2014).政治学の方法 有斐閣(東京大学大学院教育学研究科総合教育科学専攻大学経営・政策コース「2015年度シラバス」で知る)
- 金子元久(2013).大学教育の再構築:学生を成長させる大学へ 玉川大学出版部(東京大学大学院教育学研究科総合教育科学専攻大学経営・政策コース「2015年度シラバス」で知る)
- 国立大学財務・経営センター(2004).国立大学法人経営ハンドブック 国立大学財務・経営センター(東京大学大学院教育学研究科総合教育科学専攻大学経営・政策コース「2015年度シラバス」で知る)
- 篠田道夫・教育学術新聞編集部(2014).大学マネジメント改革:改革の現場-ミドルのリーダーシップ ぎょうせい(東京大学大学院教育学研究科総合教育科学専攻大学経営・政策コース「2015年度シラバス」で知る)
- 大塚豊(2007).中国大学入試研究:変貌する国家の人材選抜 東信堂(東京大学大学院教育学研究科総合教育科学専攻大学経営・政策コース「2015年度シラバス」で知る)
- 谷聖美(2006).アメリカの大学:ガヴァナンスから教育現場まで ミネルヴァ書房(東京大学大学院教育学研究科総合教育科学専攻大学経営・政策コース「2015年度シラバス」で知る)
- 中山茂(1988).アメリカ大学への旅:その歴史と現状 リクルート出版(東京大学大学院教育学研究科総合教育科学専攻大学経営・政策コース「2015年度シラバス」で知る)
- 潮木守一(2008).フンボルト理念の終焉?:現代大学の新次元 東信堂(東京大学大学院教育学研究科総合教育科学専攻大学経営・政策コース「2015年度シラバス」で知る)
- 田村正紀(2006).リサーチ・デザイン:経営知識創造の基本技術 白桃書房(東京大学大学院教育学研究科総合教育科学専攻大学経営・政策コース「2015年度シラバス」で知る)
- 金子元久(2013).大学教育の再構築:学生を成長させる大学へ 玉川大学出版部(東京大学大学院教育学研究科総合教育科学専攻大学経営・政策コース「2015年度シラバス」で知る)
- 木戸裕(2011).ボローニャ・プロセスと高等教育の質保証:ドイツの大学をめぐる状況を中心に 広島大学高等教育研究開発センター(編)大学教育質保証の国際比較 pp.25-65.[PDF](東京大学大学院教育学研究科総合教育科学専攻大学経営・政策コース「2015年度シラバス」で知る)
- 大塚豊(1983).戦時下中国における欧米系大学 阿部洋(編)日中教育文化交流と摩擦 第一書房 pp.376-402.(東京大学大学院教育学研究科総合教育科学専攻大学経営・政策コース「2015年度シラバス」で知る)
- 福留東土(2014).比較高等教育研究の回顧と展望 大学論集,46,139-169.[PDF](東京大学大学院教育学研究科総合教育科学専攻大学経営・政策コース「2015年度シラバス」で知る)
- 山崎博敏(1985).高等教育システムの組織社会学的分析視角:B.クラークを中心に 大学論集,14,111-132.[PDF](東京大学大学院教育学研究科総合教育科学専攻大学経営・政策コース「2015年度シラバス」で知る)
- 安原義仁(2005).イギリスの大学における学士学位の構造と内容:近代オックスフォードの古典学優等学士学位を中心に 高等教育研究,8,95-120.(東京大学大学院教育学研究科総合教育科学専攻大学経営・政策コース「2015年度シラバス」で知る)
- 木戸裕(2011).ボローニャ・プロセスとドイツの大学改革 ドイツ研究,45,113-125.(東京大学大学院教育学研究科総合教育科学専攻大学経営・政策コース「2015年度シラバス」で知る)
- 木戸裕(2014).ヨーロッパ統合をめざした高等教育の国際的連携:ボローニャ・プロセスを中心にして 比較教育学研究,48,116-130.(東京大学大学院教育学研究科総合教育科学専攻大学経営・政策コース「2015年度シラバス」で知る)
- 天野郁夫(2009).日本高等教育システムの構造変動:トロウ理論による比較高等教育論的考察 教育學研究,76(2),172-184.[PDF](東京大学大学院教育学研究科総合教育科学専攻大学経営・政策コース「2015年度シラバス」で知る)
[2015.10.31]IRなどについての文献メモ 文献一覧を更新<統計>
[2015.10.30]大学に関わる情報メモ 内容をアップ
[2015.10.27]ホーム「お知らせ」欄を変更
- 口頭発表「データに基づく大学生の中途退学防止策:日米の制度差に着目して」(第22回大学教育研究フォーラム<個人研究発表>)を掲載
[2015.10.25]「私立大学職員によるIR文献メモ」メルマガ バックナンバーを更新
[2015.10.22]IRなどについての文献メモ 内容をアップ
- 森下孟(2013).論文キーワードのテキストマイニングによる米国ポートフォリオ研究動向の量的分析 信州大学教育学部研究論集,6,115-128.[PDF](ポートフォリオ研究論文について論文キーワードをテキストマイニング手法で構造的・機械的に分析・分類した、米国教育省教育資源情報センターの教育関連文献情報データベースを用いた、手順:「Portfolio」を含むものを抽出→年代別に分類してキーワードを抽出→IBM SPSS Text Analysis for Surveys英語版(同義語・反義語の独自辞書に基づき自動的にカテゴリ分類ができる)を用いてキーワード群をカテゴリ分類→IBM SPSS Statistics 18を用いて年代別カテゴリ分類結果を因子分析、結果の示し方:キーワードを持つ論文数の経年変化を線グラフ表示、抽出した総論文数、最も古い論文、急増した時期(広く注目され始めた時期)、論文数の変化(黎明期・発展期・最盛期・減衰期・安定期)、年代別(差異・共通)、対象の変化(個人から組織);Google Scholar「テキストマイニング "研究動向"」で知る)
[2015.10.22]IRなどについての文献メモ 文献一覧を更新<テキストマイニング>
- 陳漢雄・劉野・大保信夫(1997).データマイニングのキーワード検索に対する応用 情報処理学会研究報告.DBS,データベースシステム研究会報告,113,227-232.(CiNii Articles「データマイニング キーワード」で知る)
- 新美礼彦(2003).カオス文献情報からのデータマイニングによる研究動向調査 電子情報通信学会技術研究報告.AI,人工知能と知識処理 102(615),59-64.[PDF](CiNii Articles「データマイニング キーワード」で知る)
- 那須川哲哉・河野浩之・有村博紀(2001).テキストマイニング基盤技術 人工知能学会誌,16(2),201-211.[PDF](CiNii Articles「データマイニング キーワード」で知る)
- 市村由美・長谷川隆明・渡部勇・佐藤光弘(2001).テキストマイニング:事例紹介 人工知能学会誌,16(2),192-200.[PDF](CiNii Articles「データマイニング キーワード」で知る)
- 豊田裕貴(2003).テキストマイニングによるドキュメントデータの分析 情報の科学と技術,53(1),22-27.(テキストマイニングの基本的な処理をデータの数値化と分析とに分けて解説;CiNii Articles「データマイニング キーワード」で知る)
- 渡部勇(2003).テキストマイニングの技術と応用 情報の科学と技術,53(1),28-33.[PDF](テキストマイニングは文書を個別に調べてもわからない文書群全体に内在する知識を発見することを目的としている、要素技術と応用分野の両面からテキストマイニングについて解説;CiNii Articles「データマイニング キーワード」で知る)
- 新美礼彦・五十嵐睦・小西修(2005).書誌情報データベースからの多次元データ分析による研究動向分析 電子情報通信学会技術研究報告.NLP,非線形問題,105(206),57-62.[PDF](論文に含まれている特定のキーワードや時系列データを用いてOLAPによる多次元データ分析による頻度分析を行った、そこからカオス研究分野・研究動向の調査を行った;CiNii Articles「データマイニング キーワード」で知る)
- 沼尾雅之・清水周一・木村雅彦(1995).要因分析のためのデータマイニング 全国大会講演論文集 第51回(データベース),195-196.[PDF](データマイニングの手法として知られているものを大別:①クラス分類型・②クラスタ分割型・③演繹データベース検索型・④視覚化型、③は扱えるデータのサイズ・柔軟なパターン・解の完全性などの点で優れている;CiNii Articles「データマイニング キーワード」で知る)
- 林靖人・中嶋聞多.(2009).地域ブランド研究における研究領域構造の分析:論文書誌情報データベースを活用した定量分析の試み 人文科学論集人間情報学科編,43,87-109.[PDF](地域ブランド研究における研究領域構造の定性的・定量的分析を行った、定量的分析では論文書誌情報データベースより論文タイトルや論文雑誌名を抽出した、具体的にはテキスト・マイニングを用いて地域ブランド研究の論文タイトルに含まれる「キーワード」と「雑誌名」の対応分析を行い、研究領域間の関係性や研究領域間に共通する視点・独自の研究視点の有無について分析を行った;Google Scholar「テキストマイニング "研究動向"」で知る)
- 武田浩一・浦本直彦・松澤裕史・猪口明博・村上明子(2003).文献データベースからの生医学インフォマティクス 生体の科学,54(5),443-448.(ライフサイエンス分野におけるテキストマイニングの研究動向について情報抽出技術を中心に概説する、;Google Scholar「テキストマイニング "研究動向"」で知る)
- 森下孟(2013).論文キーワードのテキストマイニングによる米国ポートフォリオ研究動向の量的分析 信州大学教育学部研究論集,6,115-128.[PDF][概要](Google Scholar「テキストマイニング "研究動向"」で知る)
- 小田切康彦(2014).政策系大学における研究動向:論文タイトルを用いたテキストマイニングから 徳島大学社会科学研究,28,61-82.[PDF](論文数・性別・ページ数について時系列に集計して傾向を分析、論文タイトルの語句の傾向を分析(フリーソフト「KH Coder」を用いた)、結果の示し方:総論文数、論文数の経年変化、ピーク・減少時期、全期間・年代ごとの語句出現回数、自己組織化マップ(Self-Organizing Maps; SOM)による語句の分類;Google Scholar「テキストマイニング "研究動向"」で知る)
- いとうたけひこ(2013).テキストマイニングの看護研究における活用 漢語研究,46(5),475-484.(テキストマイニングの研究は①質的/量的研究に単純に分けられない「コウモリ的性格」を持っている、②探索的研究・仮説検証的研究・仮説生成的研究のすべてに有効、③質的研究や量的研究と併用することでミックス法の研究法の一部としても使える、テキストマイニング研究の限界・注意点・今後の課題について指摘;Google Scholar「テキストマイニング "研究動向"」で知る)
- 華山宣胤・山本樹・山崎航(2010).データマイニング手法を用いた研究動向分析手法の一考察 全国大会講演論文集 第72回(ソフトウェア科学・工学),261-262.[PDF](単にキーワード間の関連を見るだけではなく学術論文に特有の文法ルールに注目した解析を提案、各論文を内容に従って比較・分類する点に特徴がある;Google Scholar「テキストマイニング "研究動向"」で知る)
- 青木仕・青木きよ子(2009).わが国のアスベスト研究の分析:文献中のシソーラス用語とタイトル中のフリータームの解析 順天堂医学,55(4),478-486.[PDF](トレンドサーチ2008(社会情報サービス社)を使用してテキスト・マイニングを行った、結果の示し方:文献数の経年変化、タイトル中のフリータームのネットワーク図など;Google Scholar「テキストマイニング "研究動向"」で知る)
- 加藤千佳・城丸瑞恵(2010).医中誌データベースを用いた看護専門領域別実習に関する研究動向の分析 日本看護学会論文集 看護教育,41,138-141.(Google Scholar「テキストマイニング "研究動向"」で知る)
[2015.10.21]IRなどについての文献メモ 文献一覧を更新<文献レビュー書き方>
- Baumeister, R. F., & Leary, M. R. (1997). Writing narrative literature reviews. Review of general psychology, 1, 311-320.[PDF](シルヴィア(2015)『できる研究者の論文生産術』で知る)
- Bem, D. J. (1995). Writing a review article for Psychological Bulletin. Psychological bulletin, 118, 172-177.[HTML](シルヴィア(2015)『できる研究者の論文生産術』で知る)
- Cooper, H. (2003). Editorial. Psychological bulletin, 129, 3-9.(シルヴィア(2015)『できる研究者の論文生産術』で知る)
- Eisenberg, N. (2000). Writing a litterature review. In R. J. Sternberg (Ed.), Guide to publishing in psychology journals. Cambridge, England: Cambridge University Press. pp.17-34.(シルヴィア(2015)『できる研究者の論文生産術』で知る)
[2015.10.21]IRなどについての文献メモ 文献一覧を更新<文章作成>
- 酒井聡樹(2015).これから論文を書く若者のために:究極の大改訂版 共立出版(Amazon.co.jpレコメンド機能で知る)
- 酒井聡樹(2011).100ページの文章術:わかりやすい文章の書き方のすべてがここに 共立出版(Amazon.co.jpレコメンド機能で知る)
- シルヴィア,P.J.高橋さきの(訳)(2015).できる研究者の論文生産術:どうすれば「たくさん」書けるのか 講談社(Amazon.co.jpレコメンド機能で知る)
[2015.10.20]ホーム「お知らせ」欄を変更
- 口頭発表「大学改革における職員とIR:京都光華女子大学の事例」(大学改革研究会2015年度第5回ワークショップ)を掲載
[2015.10.20]「過去の「お知らせ」」、「IRなどについての文献メモ」、「これまでの発表・競争的研究資金など」に追加
- 口頭発表「IR実務担当者のための事例解説:中途退学防止についての文献レビューを意思決定支援につなげる方法」(平成27年度第2回IR実務担当者連絡会)
[2015.10.15]IRなどについての文献メモ 文献一覧を更新<意思決定>
- Mintzberg, H., Raisinghani, D., & Théorêt, A. (1976). The structure of "unstructured" decision processes. Administrative science quarterly, 21(2), 246-275.(意思決定とは何が問題かを認識して、それを解決するために必要な情報を集約し、その中で最善の選択肢を選んで行動を起こす過程;桑田・田尾(2010)『組織論:補訂版』で知る)
- 嶌田敏行・藤原宏司・浅野茂・大野賢一・関隆宏・小湊卓夫・土橋慶章・本田寛輔(2014).国立大学の評価・IR部署における業務の現状と今後の展開に関する一考察 日本高等教育学会第17回大会発表要旨集,46-47.(IR業務の定義、「学内の意思決定や判断の高度化を目的に、必要な時に、必要な情報を必要な人に提供する業務であり、およびそのためのデータの情報への加工」;藤原・大野(2015)「全学統合型データベースの必要性を考える」で知る)
[2015.10.15]IRなどについての文献メモ 文献一覧を更新<レビュー論文>
- 大木秀一・彦聖美(2013).研究方法論としての文献レビュー:英米の書籍による検討 石川看護雑誌,10,7-18.[PDF](CiNii Articles「レビュー論文」で知る)
- 村田和香(2013).研究論文の読み方(第2回)レビュー論文の読み方 作業療法ジャーナル,47(9),1028-1032.(CiNii Articles「レビュー論文」で知る)
[2015.10.13]IRなどについての文献メモ 内容をアップ
- 大場淳(2011).大学のガバナンス改革:組織文化とリーダーシップを巡って 名古屋高等教育研究,11,253-272.[PDF](ガバナンス改革は組織運営にかかる諸制度を変えれば済む話ではない、日本ではリーダーシップについて上意下達的側面が過度に強調された傾向が否めない、しかし大学では参加と合意形成を促す双方向的リーダーシップが必要、組織文化の変化をもたらすのは組織全体の学習;Google Scholar「"意思決定" 大学 組織」で知る)
[2015.10.13]IRなどについての文献メモ 文献一覧を更新<意思決定>
- 大場淳(2011).大学のガバナンス改革:組織文化とリーダーシップを巡って 名古屋高等教育研究,11,253-272.[PDF][概要](Google Scholar「組織 理解 納得 推進 大学」で知る)(Google Scholar「"意思決定" 大学 組織」で知る)
[2015.10.07]IRなどについての文献メモ 文献一覧を更新<質保証、評価>
[2015.10.04]IRなどについての文献メモ 文献一覧を更新<中途退学、リテンション>
- Dumbrigue, C., Moxley, D., & Najor-Durack, A. (2001). Keeping students in higher education: Successful practices and strategies for retention. London, UK: Routledge.(Amazon.co.jp「dropout higher education」で知る)
- Nora, A. (2004). Keeping Students in Higher Education: Successful Practices and Strategies for Retention (review). The review of higher education, 27(2), 287-288.[HTML](Google Scholar「Keeping students in higher education:successful practices & strategies for retention」で知る)
- Crosling, G., Thomas, L., & Heagney, M. (2008). Improving student retention in higher education: The role of teaching and learning. London, UK: Routledge.(Amazon.co.jp「dropout higher education」で知る)
- Cook, T., & Rushton, B. S. (2009). How to recruit and retain higher education students: A handbook of good practice. New York: Routledge.(Amazon.co.jp「dropout higher education」で知る)
- Seidman, A. (2005). College student retention: Formula for student success. Westport, CT: Praeger Publishers.(Amazon.co.jp「dropout higher education」で知る)
- Seidman, A. (2012). College student retention: Formula for student success second edition. Lanham, ML: Rowman & Littlefield Publishing Group.(Amazon.co.jp「dropout higher education」で知る)
- Tinto, V. (2012). Completing college: Rethinking institutional action. Chicago, IL: University of Chicago Press.(Amazon.co.jp「dropout higher education」で知る)
- Braxton, J. M., Doyle, W. R., Hartley III, H. V., Hirschy, A. S., Jones, W. A., & McLendon, M. K. (2014). Rethinking college student retention. San Francisco: Jossey-Bass.(Amazon.co.jp「dropout higher education」で知る)
- Primary Research Group. (2013). The survey of best practices in student retention 2013. New York: Primary Research Group.(Amazon.co.jp「dropout higher education」で知る)
- Primary Research Group. (2015). Survey of best practices in student retention 2015. New York: Primary Research Group.(Amazon.co.jp「the survey of best practices in student retention」で知る)
[2015.10.01]IRなどについての文献メモ 文献一覧を更新<授業アンケート、学生による授業評価>
- 松谷満・平井松午・佐竹昌之・桑折範彦(2005).全学共通教育の現状と課題:学生による授業評価アンケート調査の分析から 大学教育研究ジャーナル,2,13-25.(授業アンケートは外部評価に対する義務の履行という点が重視されて形だけの実施になっている;Google Scholar「授業アンケート|授業評価 活用」で知る)[PDF]
[2015.10.01]IRなどについての文献メモ 文献一覧を更新<アイデア、着想>
- 水野学(2012).アウトプットのスイッチ 朝日新聞出版(水野(2014)『センスは知識からはじまる』で知る)
- ブラウン,S.壁谷さくら(訳)(2015).描きながら考える力:The Doodle Revolution クロスメディア・パブリッシング(Amazon.co.jpレコメンド機能で知る)
[2015.10.01]IRなどについての文献メモ 文献一覧を更新<コピーライティング、資料作成>
- 小霜和也(2014).ここらで広告コピーの本当の話をします。 宣伝会議(Amazon.co.jpレコメンド機能で知る)
- 西任暁子(2012).「ひらがな」で話す技術 サンマーク出版(Amazon.co.jpレコメンド機能で知る)
- 小西利行(2014).伝わっているか? 宣伝会議(Amazon.co.jpレコメンド機能で知る)
[2015.09.28]IRなどについての文献メモ 文献一覧を更新<コピーライティング、資料作成>
- 鈴木康行(1982).名作コピー読本 誠文堂新光社(鈴木康之(2008)『名作コピーに学ぶ読ませる文章の書き方』で知る)
- 鈴木康之(1987).新・名作コピー読本 誠文堂新光社(Amazon.co.jpレコメンド機能で知る)
- 鈴木康之(2010).文章がうまくなるコピーライターの読書術 日本経済新聞出版社(Amazon.co.jpレコメンド機能で知る)
- 鈴木康之(2015).名作コピーの教え 日本経済新聞出版社(Amazon.co.jpレコメンド機能で知る)
[2015.09.21]IRなどについての文献メモ 文献一覧を更新<高等教育>
- 有本章(1994).大学改革の現在:社会学的考察 教育社会学研究,55,5-21.[PDF](大学改革の影響と課題、規制緩和や自由化が導入されても低成長時代であるのでとくに過去の実績や伝統を持つ機関が有利と見込まれる;Google Scholar「大学 "人的資源" 限られた」で知る)
[2015.09.21]IRなどについての文献メモ 内容をアップ<授業アンケート、学生による授業評価>
- 牧野幸志(2003).学生による授業評価の規定因の検討(3):記名式による調査が授業評価に与える影響 高松大学紀要,40,63-75.[PDF](「記名式の場合には、学生は自分の行なった授業評価がその後の自分への成績評価に影響を与えるのではないかという評価懸念をもってしまう。そのため、記名式の授業評価では、無記名式の場合に比べて、学生は好意的な評価を行なうと予想される。」(p.65)、分析結果:予想に反して、教員評価・授業内容評価・成績基準評価・授業準備評価の全てにおいて記名式と無記名式の評価が変わらなかった(=記名式の授業評価において、学生が評価懸念のために実際よりも高い授業評価を行なう傾向はみられなかった)、調査方法:短期大学の1年生を対象とした選択科目(「心理学」、講義形式)、受講生45名(全て女性)、<1回目>最終講義の終了後に記名式で実施、<2回目>試験日(翌週)の試験前に無記名で実施;Google Schlar「授業評価|授業アンケート 記名式」で知る)
[2015.09.21]IRなどについての文献メモ 文献一覧を更新<授業アンケート、学生による授業評価>
- 牧野幸志(2003).学生による授業評価の規定因の検討(3):記名式による調査が授業評価に与える影響 高松大学紀要,40,63-75.[PDF][概要](Google Schlar「授業評価|授業アンケート 記名式」で知る)
[2015.09.21]IRなどについての文献メモ 文献一覧を更新(デザイン、資料作成)
- アレフゼロ(2005).魅せるデザイン、語るレイアウト。:プロの実例から学ぶエディトリアルデザインの基礎 エムディエヌコーポレーション(筒井(2015)『なるほどデザイン>』で知る)
- 工藤強勝(監修)(2006).デザイン解体新書 ワークスコーポレーション(Amazon.co.jpレコメンド機能で知る)
- オブスキュアインク(2008).レイアウトデザインのルール:目を引くページにはワケがある。 ワークスコーポレーション(Amazon.co.jpレコメンド機能で知る)
- 鈴木康之(2008).名作コピーに学ぶ読ませる文章の書き方 日本経済新聞出版社(Amazon.co.jpレコメンド機能で知る)
- 水野学(2014).センスは知識からはじまる 朝日新聞出版(Amazon.co.jpレコメンド機能で知る)
- 水野学(2014).アイデアの接着剤 朝日新聞出版(Amazon.co.jpレコメンド機能で知る)
[2015.09.20]IRなどについての文献メモ 内容をアップ<授業アンケート、学生による授業評価>
- 松尾和枝・本田多美枝・江島仁子(2009).コンピュータによる授業評価システムに関する文献的考察 日本赤十字九州国際看護大学intramural research report,7,29-34.[PDF](日本における「コンピュータによる授業評価システムに関する研究」について文献調査、調査対象の期間は2002~2007年、<結果>文献数は年々増加、紙媒体の課題:タイムリーに活用できない・教員・学生の双方向のやりとりができない、システムが持つ機能の特徴:①即時性・双方向性の確保、②システムへの複数のアクセス方法、③自由記載データの分析、④出欠・成績・履修管理システムとの統合、⑤匿名性の確保;Google「授業アンケート|授業評価 web 紙 媒体」で知る)
- 渡部芳栄(2012).学生の主体的参加を促す取組みに関する一考察 福島大学総合教育研究センター紀要,12,19-26.[PDF](調査目的:「学生の主体的参加を促す取り組みの状況」を明らかにする、調査対象・方法:東北地域の学士課程を持つ48大学(国立7、公立9、私立32)に調査票を発送、87.5%(42大学)から回答、授業評価の実施形態についての結果:紙媒体38、WEB媒体6、その他0(複数回答可);Google「授業アンケート|授業評価 web 紙 媒体」で知る)
[2015.09.20]IRなどについての文献メモ 文献一覧を更新<授業アンケート、学生による授業評価>
- 松尾和枝・本田多美枝・江島仁子(2009).コンピュータによる授業評価システムに関する文献的考察 日本赤十字九州国際看護大学intramural research report,7,29-34.[PDF[概要](Google「授業アンケート|授業評価 web 紙 媒体」で知る)
- 鳥巣泰生・佐々木英洋(2004).リアルタイム授業評価システムを活用した授業改善 大手前大学社会文化学部論集,5,129-153.[PDF](パソコンと携帯電話で自由記述の量に有意差なし;松尾他(2009)「コンピュータによる授業評価システムに関する文献的考察」で知る)
- 鳥巣泰生・佐々木英洋(2005).リアルタイム授業評価システムを活用した授業改善(2) 大手前大学社会文化学部論集,6,287-315.[PDF](パソコンと携帯電話で自由記述の量に有意差なし;松尾他(2009)「コンピュータによる授業評価システムに関する文献的考察」で知る)
- 鳥巣泰生・佐々木英洋(2014).リアルタイム授業評価システムを活用した授業改善の変遷:導入から10年間の総括 大手前大学論集,15,301-318.(CiNii Article「鳥巣泰生」で知る)
- 渡部芳栄(2012).学生の主体的参加を促す取組みに関する一考察 福島大学総合教育研究センター紀要,12,19-26.[PDF][概要](Google「授業アンケート|授業評価 web 紙 媒体」で知る)
[2015.09.18]IRなどについての文献メモ 文献一覧を更新
- クリシュナ,G. 武舎るみ・武舎広幸(訳)(2015).さよなら、インタフェース:脱「画面」の思考法 ビー・エヌ・エヌ新社(Amazon.co.jpレコメンド機能で知る)
- 宇野雄(2014).フラットデザインで考える新しいUIデザインのセオリー 技術評論社(Amazon.co.jpレコメンド機能で知る)
- 佐藤好彦(2013).フラットデザインの基本ルール:Webクリエイティブ&アプリの新しい考え方。 インプレスジャパン(Amazon.co.jpレコメンド機能で知る)
- Weinschenk, S. 武舎広幸・武舎るみ・阿部和也(訳)(2012).インタフェースデザインの心理学:ウェブやアプリに新たな視点をもたらす100の指針 オライリー・ジャパン(Amazon.co.jpレコメンド機能で知る)
- 筒井美希(2015).なるほどデザイン エムディエヌコーポレーション(Amazon.co.jpレコメンド機能で知る)
- パイインターナショナル(2015).デザインの魂は細部に宿る パイインターナショナル(Amazon.co.jpレコメンド機能で知る)
- フレア(2015).なっとくレイアウト:感覚やセンスに頼らないデザインの基本を身につける エムディエヌコーポレーション(Amazon.co.jpレコメンド機能で知る)
- 坂本伸二(2015).デザイン入門教室:特別講義:確かな力を身に付けられる学び、考え、作る授業 SBクリエイティブ(Amazon.co.jpレコメンド機能で知る)
[2015.09.17]IRなどについての文献メモ 内容をアップ
- 三浦真琴(2012).進化する授業評価:リファインの試み 関西大学高等教育研究,3,13-30.[PDF](学生による授業評価に関連する答申・学校教育法の解説、「学生による授業評価はほとんどの大学で実施されるようにはなったが、その結果が授業改善に有機的に結びつけられているとは必ずしもいえない状況にあり、授業評価結果を授業改善に活用・反映させるための工夫を凝らし、装置を作ることなどが依然として大きな課題であることにかわりはない」(p.18)、結果の数値の読み取り方・設問設定の注意点、教員へのフィードバックに平均点を示す=平均点と自身の評価値を比較することを暗に求めている、しかしその比較にどれだけ意味があるかは考えられていない;Google Schlar「授業アンケート 学生による授業評価」で知る)
[2015.09.17]IRなどについての文献メモ 文献一覧を更新
- 三浦真琴(2012).進化する授業評価:リファインの試み 関西大学高等教育研究,3,13-30.[PDF][概要](Google Schlar「授業アンケート 学生による授業評価」で知る)
- 佐藤龍子・三浦真琴(2005).『学生による授業評価・授業アンケート』を評価する:111大学の授業評価の分析 大阪経済法科大学総合科学研究所年報,24,8-12.(Google Schlar「授業アンケート 学生による授業評価」で知る)
[2015.09.16]IRなどについての文献メモ 内容をアップ
- 林創・大塚雄作(2008).関西地区FD連絡協議会「授業評価ワークショップ」事前アンケートとその結果 京都大学高等教育研究開発推進センター 関西地区FD連絡協議会設立に向けて pp.133-171.[PDF](ワークショップの事前アンケートでの設問「貴学での授業評価に関わる課題として、どのようなものがあると思われますか?」の回答結果:回答の質や回答率、フィードバック、位置付け・活用など、ワークショップ参加希望校(者)の回答結果(関西地区の大学213校に送付、回答があったのは計76校(「参加する」54校63名・「参加しない」22校22名)で回収率35.7%、「参加しない」はほとんどが無回答であったので「参加する」の結果について記載);Google Schlar「アンケート インターネット|web 回答率|回収率 信頼性」で知る)
[2015.09.16]IRなどについての文献メモ 文献一覧を更新
- 本多則惠(2009).調査法が回答者を選ぶ?測定法(訪問・郵送・インターネット等)と無回答誤差の関係 石田浩・佐藤香・佐藤博樹・豊田義博・萩原牧子・萩原雅之・本多則惠・前田幸男・三輪哲 信頼できるインターネット調査法の確立に向けて SSJ Data Archive Research Paper Series,42,95-122.[PDF](Web調査によって得られたデータから留置調査データの再現が容易に可能であるのかどうかを検証;Google Schlar「アンケート インターネット|web 回答率|回収率 信頼性」で知る)
- 佐藤博樹(2009).インターネット調査の限界と有効性 石田浩・佐藤香・佐藤博樹・豊田義博・萩原牧子・萩原雅之・本多則惠・前田幸男・三輪哲 信頼できるインターネット調査法の確立に向けて SSJ Data Archive Research Paper Series,42,133-141.[PDF](Google Schlar「アンケート インターネット|web 回答率|回収率 信頼性」で知る)
- 林創・大塚雄作(2008).関西地区FD連絡協議会「授業評価ワークショップ」事前アンケートとその結果 京都大学高等教育研究開発推進センター 関西地区FD連絡協議会設立に向けて pp.133-171.[PDF][概要](Google Schlar「アンケート インターネット|web 回答率|回収率 信頼性」で知る)
- 本多則惠(2005).社会調査へのインターネット調査の導入をめぐる論点:比較実験調査の結果から 労働統計調査月報,57(2),12-20.[PDF](Google Schlar「アンケート インターネット|web 回答率|回収率 信頼性」で知る)
- 出口慎二(2009).インターネット調査の効用と課題 行動計量学,35(1),47-57.[PDF](Google Schlar「アンケート インターネット 回答率」で知る)
- 大隅昇(2002).インターネット調査の適用可能性と限界:データ科学の視点からの考察 行動計量学,29(1),20-44.[PDF](Google Schlar「アンケート インターネット 回答率」で知る)
[2015.09.12]「過去の「お知らせ」」、「IRなどについての文献メモ」、「これまでの発表・競争的研究資金など」に追加
- 勉強会講師「京都光華女子大学の休退学防止等に関するEMIRについて」(第8回EMIR勉強会)※講師依頼
[2015.09.07]「過去の「お知らせ」」、「IRなどについての文献メモ」、「これまでの発表・競争的研究資金など」に追加
- 口頭発表「成績評価データを教育の質保証に活用する:GP分布分析をFD活動につなげる仕組み」(大学行政管理学会第19回(2015年度)定期総会・研究集会)
[2015.09.04]「過去の「お知らせ」」、「IRなどについての文献メモ」、「これまでの発表・競争的研究資金など」に追加
- 口頭発表「基礎学力を把握する仕組みの開発:学科の要望と学内の既存データを組み合わせた教科内容の修得状況分析(IR)」(初年次教育学会第8回大会)
[2015.09.02]「過去の「お知らせ」」、「IRなどについての文献メモ」、「これまでの発表・競争的研究資金など」に追加
- 協議会講師「京都光華女子大学におけるEM」(平成27年度全国大学教育研究センター等協議会(筑波大学大学研究センター第57回公開研究会))※講師依頼
- シンポジウム講師「学びの成果をどう可視化し、組織的な教学改善を推進するか」(SPODフォーラム2015シンポジウム)※講師依頼
[2015.08.30]IRなどについての文献メモ 文献一覧を更新
- 澤田忠幸(2010).学生による授業評価の課題と展望 愛媛県立医療技術大学紀要,7(1),13-19.[PDF](Google「授業評価活用ハンドブック」で知る)
[2015.08.21]大学に関わる情報メモ 内容をアップ
[2015.08.21]IRなどについての文献メモ 文献一覧を更新
- 絹川正吉(1997).ICUにおけるGPA制度 一般教育学会誌,19(1),50-53.(GPAの算定方法には確固とした理論的背景があるわけではなく、たぶんに慣行的に定まったものとみられる;半田(2008)「機能するGPAとは何か」で知る)
- 諸星裕(2001).GPA制度、FTE、単位制:大学改革のためのツールとして 大学教育学会誌,23(1),13-17.(GPAの算定方法には確固とした理論的背景があるわけではなく、たぶんに慣行的に定まったものとみられる;半田(2008)「機能するGPAとは何か」で知る)
- 半田智久(2006).GPA制度に対する関心と導入の状況 静岡大学教育研究,2,1-9.[PDF](CiNii Articles「半田智久」で知る)(日本の308大学を対象にした調査で約3割が全学的な規模でGPAを運用;半田(2008)「機能するGPAとは何か」で知る)
[2015.08.20]IRなどについての文献メモ 文献一覧を更新
- 高間邦男(2008).組織を変える「仕掛け」 光文社(Amazon.co.jp「相対評価 絶対評価」で知る)
- 高間邦男(2005).学習する組織 現場に変化のタネをまく 光文社(Amazon.co.jpレコメンド機能で知る)
- 半田智久(2015).教学IR:お茶の水女子大学2013年度学生調査学内分析報告 高等教育と学生支援:お茶の水女子大学教育機構紀要,5,6-25.[PDF][概要](CiNii Articles「半田智久」で知る)
[2015.08.20]IRなどについての文献メモ 文献一覧を更新
- 八房智顯・王栄光・里信純・石井義裕(2015).広島工業大学における授業アンケートとGPAの相関分析 広島工業大学紀要.教育編,14.69-74.[PDF](様々な学力レベルの学生に授業方法を対応させていくため「授業アンケートの回答結果(4択)」と「回答者の成績(GPA)」を調査、対象講義の実施学年・講義種目は区別しない、<解析方法>①[平均回答値の大小]回答値は離散値(1・2・3・4)でGPAとの関係がわかりにくいため(図1)GPAを0.5で区切った上で「区間内の回答値の平均」を表示(図2)、②[回答値とGPAの相関係数](図3)、③[同年度の前期と後期の比較]同一集団の回答傾向の中で時間的に不変な要素を見出す→設問ごとの回答値とGPAの関連性の中から時間的変動要素を取り除く→学科ごとの特徴をより正確に見出す、横軸:前期の回答値とGPAの相関係数×縦軸:後期の同相関係数、それを設問ごと学科ごとにプロット(図4)、<解析結果と解釈>図4を使って設問ごとに相関関係を解釈、<回答傾向と問題点>①[全ての設問間の相関係数]前期・後期それぞれで調べた(学科を区別せず全学でまとめて算出)、横軸:前期の設問間の相関係数×縦軸:後期の同相関係数、前期と後期で設問間の相関係数は同程度だった(=経時変化は小さい)、②[設問間の相関係数]学習態度と各設問の関係、「意義・目的の理解」と「内容の理解」の関係、「教員の熱意」と「教え方の満足度」の関係、後半の設問で相関係数が高い(=同じような回答値が続いている)ことは「傾向が似ている」もしくは「回答疲れによる集中力低下」(表3、相関係数が高いほど濃い色で表示)、<GPAとの相関まとめ>[GPAが高いと強い傾向が見られたもの]出席状況や授業態度などで高い自己評価、教員の熱意・授業の理解、予復習に費やす時間が短くなる、[GPAが高いとやや傾向が見られたもの]授業内容への興味、後輩等に同授業を推薦、[GPAと関係が見出せなかったもの]教え方のわかりやすさ、教え方への満足;CiNii Articles「GPA」で知る)
- 半田智久(2015).教学IR:お茶の水女子大学2013年度学生調査学内分析報告 高等教育と学生支援:お茶の水女子大学教育機構紀要,5,6-25.[PDF](データを解釈する際の留意点:同じ条件での比較の重要性、標本数の違い、有意差のある集団を代表値でまとめてしまう、離散尺度の平均に連続量尺度を仮定して解釈、離散尺度の読み取り方(正規分布を仮定せずに分布パターンを比較→差異が偶然生じる確率を基に解釈);CiNii Articles「半田智久」で知る)
[2015.08.19]IRなどについての文献メモ 文献一覧を更新
- 後藤将之(2015).出席している、ということ:授業出席行動の社会心理学(1)GPA視点の場合 コミュニケーション紀要,26,71-86.(CiNii Articles「GPA」で知る)
- 尾崎徹・井上光(2015).GPAの適正な有効数字 広島工業大学紀要.教育編,14,23-28.[PDF](CiNii Articles「GPA」で知る)
- 八房智顯・王栄光・里信純・石井義裕(2015).広島工業大学における授業アンケートとGPAの相関分析 広島工業大学紀要.教育編,14.69-74.[PDF][概要](CiNii Articles「GPA」で知る)
[2015.08.19]ホーム「お知らせ」欄を変更
- 口頭発表「京都光華女子大学の休退学防止等に関するEMIRについて」(第8回EMIR勉強会)を掲載
[2015.08.18]IRなどについての文献メモ 内容をアップ
- 中村真・松田英子(2015).大学への帰属意識が大学不適応に及ぼす影響(2):出席率、GPAを用いた分析 江戸川大学紀要,25,135-144.[PDF](大学不適応に影響する要因の検討、一連の研究で用いた諸変数に「授業の出席率」と「GPA」(大学不適応を客観的に示す指標)を加えて検討した、結果:授業理解が困難であるほど大学への愛着が低いほど大学不適応感が大きくなる、友人関係の良好さは大学への愛着を介して間接的に大学不適応感の低さに影響する、大学不適応感は出席率およびGPAに負の影響を与えている、示唆されること:怠学・成績不振・留年・退学を予測する有効な指標である可能性;CiNii Articles「GPA 成績」で知る)
- 髙橋真樹・森雅博・細川正清(2015).学習成績に影響を及ぼす問題点抽出と、因果関係分析に基づいた問題解決の例 千葉科学大学紀要,8,39-50.[PDF](学習に関する問題点は複雑多岐にわたる、しかしそのすべてに均等に労力を割くのは賢明ではない(根本的あるいは本質的な問題に対して人的・物的資源を集中させることが重要)、実施内容と結果①:アンケートと因果関係分析シートを用いてGPAと相関がある問題を抽出した、成績不良者にみられる負の学習サイクルを可視化した、実施内容と結果②:そのサイクルの起始部に位置する問題に焦点を当てた勉強会を実施した、参加群と非参加群とでは薬学共用試験CBT体験受験の生物系薬学において得点率に有意差、示唆されること:問題点のすべてに対応しなくても改善・解決が可能;CiNii Articles「GPA 成績」で知る)
- 西丸良一(2014).大学生の学業成績・能力向上感と入試選抜方法の関連 評論・社会科学,111,141-155.[PDF](先行研究は選抜方法と入学後の学業成績の関連を検討することが多い、しかし学業成績のみで選抜方法の妥当性を判断するのは不十分、そこで学業成績以外に「能力向上感」の指標(学生の主観)も使用して入試選抜法の妥当性を検討した、能力向上感:①根拠を示し簡潔に書く、自分の考えや意見を伝える、③1つのことを複数の視点から考える、④文献・資料を読み解く、⑤文献・統計資料を探す、⑥数量的に分析する、⑦外国語のスキルに対する「向上した~低下した」(4段階)の回答を7で除す、結果:「一般・センター」に比べて「指定校・公募・AO」「内部推薦」「留学生・社会人・編入」のGPAが低いということはなかった、選抜方法によって能力向上感に大きな差は見られなかった、示唆されること:調査対象とした学部の入試選抜方法に大きな問題はない、GPAと能力向上感にほぼ関連がなかったことは問題(能力向上感が主観によることが要因か);CiNii Articles「GPA 成績」で知る)
- 桜井栄一(2014).本学学生の学業成績と各種条件の統計的解析 瀬木学園紀要,8,24-27.[PDF](愛知みずほ大学の学生を対象にした分析、実施内容・結果①:[高校評定平均と1~3年次それぞれのGPAの相関]入学年度2000~2011全体⇒有意水準5%の両側検定で有意だが相関係数rは1年次のみ0.21で弱い相関(2年次は0.18、3年次は0.16)、入学年次別⇒ほとんどの入学年度において各1~3年次で一定の相関関係あり(多くは0.4以上)だが2009年度(入学者数が底を打った年度)のみ相関なし)、結論・・・高校評定平均と入学後のGPAには一定の相関があることから入試判定材料とすることにそれなりの合理性がある(一方で2009年度のように全く相関が見られない場合もある)、実施内容・結果②:[GPAと学年進行]2013年度までの卒業生を対象にして1~4年次×1~4年次の各年次の相関を分析した、連続する年次(1・2年次など)は高い正の相関、学年が離れると相関が弱まるものの1・3年次でも高い相関(0.74)、4年次のみ他の年次と相関が低い(4年次の履修科目数が極端に少ないことに起因すると考えられる)、[1年次GPAをほぼ3分の1ずつ上・中・下群に分けて変化を検証]それぞれの群について1~2年次と2~3年次それぞれのペアでt検定(対応あり)、上・中・下位いずれの群でも有意水準5%で有意(下位群は2、3年次と上がるに従って上昇、中位・上位群は2年次に一旦下がる傾向)、結論・・・[1年次に成績がよい学生]2・3年次でも成績がよい、2・3年次の成績との関係について高校評定平均よりも1年次の成績の方が格段に高い相関、これらは初年次教育の重要性を示す根拠、[1年次に成績が比較的よくない学生]在学中に成績が上昇する傾向にある、よって学内の取り組みはそれなりに効果を上げている、実施内容・結果③:[GPAと履修登録科目数]履修登録科目が多いと各科目の学修が不十分になるという意見を検証(キャップ制導入前の意見)、相関関係が見られた(ただし因果関係(履修登録単位数を制限すれば成績が向上する)は不明);CiNii Articles「GPA 成績」で知る)
[2015.08.18]IRなどについての文献メモ 文献一覧を更新
- 中村真・松田英子(2015).大学への帰属意識が大学不適応に及ぼす影響(2):出席率、GPAを用いた分析 江戸川大学紀要,25,135-144.[PDF][概要](CiNii Articles「GPA 成績」で知る)
- 中村真・松田英子(2014).大学への帰属意識が大学不適応に及ぼす影響:帰属意識の媒介効果における性差および適応感を高める友人関係機能 江戸川大学紀要,24,13-19.[PDF](中村・松田(2015)「大学への帰属意識が大学不適応に及ぼす影響(2)」で知る)
- 中村真・松田英子(2013).大学生の学校適応に影響する要因の検討:大学不適応、大学満足、就学意欲に着目して 江戸川大学紀要,23,151-160.[PDF](中村・松田(2015)「大学への帰属意識が大学不適応に及ぼす影響(2)」で知る)
- 長根光男(2015).睡眠パターンと学業成績や心身状態は関連するか:夜間睡眠の質と量、日中の眠気と短時間睡眠の活用 千葉大学教育学部研究紀要,63,375-379.[PDF](CiNii Articles「GPA 成績」で知る)
- 髙橋真樹・森雅博・細川正清(2015).学習成績に影響を及ぼす問題点抽出と、因果関係分析に基づいた問題解決の例 千葉科学大学紀要,8,39-50.[PDF][概要](CiNii Articles「GPA 成績」で知る)
- 西丸良一(2014).大学生の学業成績・能力向上感と入試選抜方法の関連 評論・社会科学,111,141-155.[PDF][概要](CiNii Articles「GPA 成績」で知る)
- 桜井栄一(2014).本学学生の学業成績と各種条件の統計的解析 瀬木学園紀要,8,24-27.[PDF][概要](CiNii Articles「GPA 成績」で知る)
- 稲垣麻央・能上慎也(2014).科目難易度と個人成績を考慮したGPAと成績分布の関係について 電子情報通信学会技術研究報告.ET,教育工学,114(53),23-26.[PDF](CiNii Articles「GPA 成績」で知る)
- 高木明郎(2014).GPAを活用した学生支援の可能性 国際短期大学紀要,29,1-7.(CiNii Articles「GPA 成績」で知る)
- 山下仁司(2014).教育成果の測定のあり方をどのように考えるか:『大学生基礎力調査』のデータ実例で見る教育改善の方法 情報知識学会誌,24(4),404-413.(CiNii Articles「GPA 成績」で知る)
- 岸本健(2013). 学生の成績指数としてのGPAとその特性 国士舘大学理工学研究所報告,26,7-19.(CiNii Articles「GPA 成績」で知る)
- 中島寿宏・片桐康博・秋野禎見・土田邦彦・工藤雅之(2013).新入生の大学生活と学業成績:課外活動・生活習慣・運動習慣が学業成績に与える影響 工学教育研究講演会講演論文集,平成25年度(61),588-589.[PDF](CiNii Articles「GPA 成績」で知る)
- 神田健一(2012).GPA を用いた成績の調査分析(その1)入試の相違と課程の相違について (CiNii Articles「GPA 成績」で知る)
[2015.08.07]IRなどについての文献メモ 文献一覧を更新
- 橋本智也(2015).日々の業務の価値をデータで示す:IR活動の具体事例から応用できることを探る 京都外国語大学第2回IR・統計勉強会(口頭発表、京都外国語大学、2015年8月)
[2015.08.07]「過去の「お知らせ」」、「これまでの発表・競争的研究資金など」に追加
- 勉強会講師「日々の業務の価値をデータで示す:IR活動の具体事例から応用できることを探る」(京都外国語大学第2回IR・統計勉強会)※講師依頼
[2015.08.04]IRなどについての文献メモ 文献一覧を更新
- Menser, N. J. (2015). The perfect formula: Benchmarks that best predict retention in selective admissions programs. Unpublished doctoral dissertation, Western Kentucky University. [PDF](Google Scholar「"retention rates" withdrawal」で知る
[2015.08.04]「過去の「お知らせ」」、「これまでの発表・競争的研究資金など」に追加
- 口頭発表「IR実務担当者のための事例解説:授業アンケートの回答率を向上させ、学生から建設的な意見を得るための工夫」(平成27年度第1回IR実務担当者連絡会)
[2015.07.31]IRなどについての文献メモ 文献一覧を更新
- 苅谷剛彦(2012).アメリカの大学・ニッポンの大学:TA、シラバス、授業評価 中央公論新社(解説に宮田由紀夫先生によるアメリカの大学の近年の状況についての解説あり;Amazon.co.jpレコメンド機能で知る)
- 苅谷剛彦(2012).イギリスの大学・ニッポンの大学:カレッジ、チュートリアル、エリート教育 中央公論新社(苅谷剛彦(2012)『アメリカの大学・ニッポンの大学』で知る)
- 宮田由紀夫(2012).米国キャンパス「拝金」報告:これは日本のモデルなのか? 中央公論新社(苅谷剛彦(2012)『アメリカの大学・ニッポンの大学』で知る)
- デレック,B 宮田由紀夫(訳)(2015).アメリカの高等教育 玉川大学出版部[目次](Amazon.co.jp「宮田由紀夫」で知る)
[2015.07.29]IRなどについての文献メモ 内容をアップ
- 小島吉之(2010).用語解説 インテリジェンス・サイクル 情報史研究,2,165-168.[概要](CiNii Articles「インテリジェンスサークル」で知る)
[2015.07.29]IRなどについての文献メモ 文献一覧を更新
- 北岡元(2009).インテリジェンス入門:利益を実現する知識の創造 慶應義塾大学出版会(島吉之(2010)「用語解説 インテリジェンス・サイクル」で知る)
- 北岡元(2008).仕事に役立つインテリジェンス:問題解決のための情報分析入門 PHP研究所(Amazon.co.jpレコメンド機能で知る)
[2015.07.27]IRなどについての文献メモ 文献一覧を更新
- 北岡元(2007).情報学入門講座 いかに有効にインテリジェンス・サイクルを回すか ワールド・インテリジェンス,5,130-159.(CiNii Articles「インテリジェンスサークル」で知る)
- 小島吉之(2010).用語解説 インテリジェンス・サイクル 情報史研究,2,165-168.(CiNii Articles「インテリジェンスサークル」で知る)
[2015.07.25]IRなどについての文献メモ 文献一覧を更新
[2015.07.20]IRなどについての文献メモ 文献一覧を更新
- 早田幸政(編著)(2015).大学の質保証とは何か エイデル研究所
[2015.07.18]IRなどについての文献メモ 文献一覧を更新
[2015.07.12]IRなどについての文献メモ 文献一覧を更新
- 瀧澤博三(2006).「我が国の高等教育の将来像」答申について 私学高等教育研究所シリーズ,21,1-13.[PDF](Google「我が国の高等教育の将来像(答申)」で知る)
- 佐々木正峰(2006).「我が国の高等教育の将来像」答申を受けて 私学高等教育研究所シリーズ,21,17-28.[PDF](Google「我が国の高等教育の将来像(答申)」で知る)
- 金子元久(2006).中教審答申「我が国の高等教育の将来像について」:書かれた問題と書かれなかった問題 私学高等教育研究所シリーズ,21,31-44.[PDF](Google「我が国の高等教育の将来像(答申)」で知る)
- 文部科学省高等教育局高等教育企画課高等教育政策室(2005).中央教育審議会答申「我が国の高等教育の将来像」について:我が国の大学改革の潮流における位置づけ 文部科学時報,1550,52-61.(CiNii Articles「我が国の高等教育の将来像(答申)」で知る)
- 舘昭(2005).『我が国の高等教育の将来像』を読む:ユニバーサル・アクセスの実現に向けて 現代の高等教育,468,5-12.(Google「我が国の高等教育の将来像(答申)」、IDE現代の高等教育バックナンバー検索、CiNii Articles「「高等教育の将来像」の読み方」で知る)
- 佐々木毅(2005).『我が国の高等教育の将来像』において提起したこと 現代の高等教育,468,13-17.(Google「我が国の高等教育の将来像(答申)」、IDE現代の高等教育バックナンバー検索、CiNii Articles「「高等教育の将来像」の読み方」で知る)
- 石川明(2005).『我が国の高等教育の将来像』答申の基本的性格と位置づけ 現代の高等教育,468,18-23.(Google「我が国の高等教育の将来像(答申)」、IDE現代の高等教育バックナンバー検索、CiNii Articles「「高等教育の将来像」の読み方」で知る)
- 黒木登志夫(2005).地方国立大学の立場から(『高等教育の将来像』(中間報告)の読み方・考え方) 現代の高等教育,468,23-28.(Google「我が国の高等教育の将来像(答申)」、IDE現代の高等教育バックナンバー検索、CiNii Articles「「高等教育の将来像」の読み方」で知る)
- 金田章裕(2005).中間報告の読後感(『高等教育の将来像』(中間報告)の読み方・考え方) 現代の高等教育,468,28-32.(Google「我が国の高等教育の将来像(答申)」、IDE現代の高等教育バックナンバー検索、CiNii Articles「「高等教育の将来像」の読み方」で知る)
- 河田悌一(2005).私立大学からの一視点(『高等教育の将来像』(中間報告)の読み方・考え方) 現代の高等教育,468,32-36.(Google「我が国の高等教育の将来像(答申)」、IDE現代の高等教育バックナンバー検索、CiNii Articles「「高等教育の将来像」の読み方」で知る)
- ウィリアム,カリー(2005).将来像の実現のための緊急課題(『高等教育の将来像』(中間報告)の読み方・考え方) 現代の高等教育,468,37-40.(Google「我が国の高等教育の将来像(答申)」、IDE現代の高等教育バックナンバー検索、CiNii Articles「「高等教育の将来像」の読み方」で知る)
- 鷲山恭彦(2005).教員養成との関連で(『高等教育の将来像』(中間報告)の読み方・考え方) 現代の高等教育,468,41-45.(Google「我が国の高等教育の将来像(答申)」、IDE現代の高等教育バックナンバー検索、CiNii Articles「「高等教育の将来像」の読み方」で知る)
- 相澤益男(2005).高等教育政策の一大転換:計画と規制から将来像の提示へ(『高等教育の将来像』(中間報告)の読み方・考え方) 現代の高等教育,468,46-48.(Google「我が国の高等教育の将来像(答申)」、IDE現代の高等教育バックナンバー検索、CiNii Articles「「高等教育の将来像」の読み方」で知る)
- 丹保憲仁(2005).学習の体系と大学の構造(『高等教育の将来像』(中間報告)の読み方・考え方) 現代の高等教育,468,49-54.(Google「我が国の高等教育の将来像(答申)」、IDE現代の高等教育バックナンバー検索、CiNii Articles「「高等教育の将来像」の読み方」で知る)
- 森脇道子(2005).短期大学の将来像と方策の推進(『高等教育の将来像』(中間報告)の読み方・考え方) 現代の高等教育,468,54-57.(Google「我が国の高等教育の将来像(答申)」、IDE現代の高等教育バックナンバー検索、CiNii Articles「「高等教育の将来像」の読み方」で知る)
- 鈴木人司(2005).連合が考える高等教育の役割:大学分科会での発表意見を中心に(『高等教育の将来像』(中間報告)の読み方・考え方) 現代の高等教育,468,57-61.(Google「我が国の高等教育の将来像(答申)」、IDE現代の高等教育バックナンバー検索、CiNii Articles「「高等教育の将来像」の読み方」で知る)
- 横山晋一郎(2005).どこか"ズレ"ていませんか(『高等教育の将来像』(中間報告)の読み方・考え方) 現代の高等教育,468,61-65.(Google「我が国の高等教育の将来像(答申)」、IDE現代の高等教育バックナンバー検索、CiNii Articles「「高等教育の将来像」の読み方」で知る)
- 大蔵省印刷局(編)(1988).教育改革に関する答申:臨時教育審議会第一次~第四次(最終)答申 大蔵省印刷局(Google「臨教審答申:総集編」で知る)
[2015.07.11]IRなどについての文献メモ 文献一覧を更新
[2015.07.11]大学に関わる情報メモ 内容をアップ
[2015.07.08]IRなどについての文献メモ 文献一覧を更新
- Larson, B., Davis, M., English, D., & Purington, P. (2012). Visualizing data with Microsoft Power View. New York: McGraw-Hill/Osborne Media.(Amazon.com「power view」で知る)
- Clark, D. (2014). Beginning Power BI with Excel 2013: Self-service business intelligence using Power Pivot, Power View, Power Query, and Power Map. New York: Apress.(Amazon.com「power view」で知る)
[2015.07.07]IRなどについての文献メモ 文献一覧を更新
[2015.07.06]IRなどについての文献メモ 文献一覧を更新
[2015.07.06]大学に関わる情報メモ 内容をアップ
[2015.07.03]IRなどについての文献メモ 内容をアップ
- Reason, R. D. (2009). Student variables that predict retention: Recent research and new developments. NASPA journal, 46(3), 482-501.[PDF][概要](Google Scholar「diversity retention rates」で知る)
[2015.07.02]IRなどについての文献メモ 文献一覧を更新
- Reason, R. D. (2009). Student variables that predict retention: Recent research and new developments. NASPA journal, 46(3), 482-501.[PDF](大学生の人口統計学上の特性(性別・年齢・居住地域・所得・学歴・家族構成など)と在籍率の関係を扱った研究のレビュー、大学生がますます多様化してきているので[個々の学生について事前にわかっている情報]を在籍率の予測に使うという分析手法が必要になっている、在籍率を扱う文献の特徴:1990年以降の研究を中心に扱っている・高等教育における人口統計学上の特性の変化を強調している、分析に使われる比較的新しい変数(merit-index;[ある生徒の入学試験の点数(ACTやSATなど)]と[その生徒が通う高校の大学進学希望者全員の平均点]の関係を数値化したもの)を扱った研究のレビューも行う;Google Scholar「diversity retention rates」で知る)
- Reason, R. D. (2009). An examination of persistence research through the lens of a comprehensive conceptual framework. Journal of college student development, 50(6), 659-682.[Abstract](Google Scholarの引用元検索「Student variables that predict retention」で知る)
- Deil-Amen, P. (2011). Socio-academic integrative moments: Rethinking academic and social integration among two-year college students in career-related programs. The journal of higher education, 82(1), 54-91.[Abstract](Google Scholarの引用元検索「Student variables that predict retention」で知る)
- Wang, X. (2009). Baccalaureate attainment and college persistence of community college transfer students at four-year institutions. Research in Higher Education, 50(6), 570-588.[Abstract](Google Scholarの引用元検索「Student variables that predict retention」で知る)
- Torres, V. (2006). A mixed method study testing data-model fit of a retention model for Latino/a students at urban universities. Journal of college student development, 47(3), 299-318.[Abstract](Google Scholarの引用元検索「Student variables that predict retention」で知る)
- Kovacic, Z. (2010). Early prediction of student success: Mining students' enrolment data. Information systems and technology (Conference paper).[PDF](Google Scholarの引用元検索「Student variables that predict retention」で知る)
- Hopkins, T. H. (2008). Early identification of at-risk nursing students: A student support model. The Journal of nursing education, 47(6), 254-259.[Abstract](Google Scholarの引用元検索「Student variables that predict retention」で知る)
- Friedman, B. A. & Mandel, R. G. (2009). The prediction of college student academic performance and retention: Application of expectancy and goal setting theories. Journal of college student retention: Research, theory & practice, 11, 227-246.[Abstract](Google Scholarの引用元検索「Student variables that predict retention」で知る)
- Friedman, B. A. & Mandel, R. G. (2011). Motivation predictors of college student academic performance and retention. Journal of college student retention: Research, theory & practice, 13(1), 1-15.[Abstract](Google Scholarの引用元検索「Student variables that predict retention」で知る)
- Arredondo, M., & Knight, S. (2005). Estimating degree attainment rates of freshmen: A campus perspective. Journal of college student retention: Research, theory & practice, 7(1), 91-115.[Abstract](Google Scholarの引用元検索「Student variables that predict retention」で知る)
- Burgette, J. E. & Magun-Jackson, S. (2008). Freshman orientation, persistence, and achievement: A longitudinal analysis. Journal of college student retention: Research, theory & practice, 10(3), 235-263.[Abstract](Google Scholarの引用元検索「Student variables that predict retention」で知る)
- Campbell, C. M., & Mislevy, J. L. (2013). Student perceptions matter: Early signs of undergraduate student retention/attrition. Journal of college student retention: Research, theory & practice, 14(4), 467-493.[Abstract](Google Scholarの引用元検索「Student variables that predict retention」で知る)
- Gallard, A. J., Albritton, F., & Morgan, M. W. (2010). A comprehensive cost/benefit model: Developmental student success impact. Journal of developmental education, 34(1), 10-25.[PDF](Google Scholarの引用元検索「Student variables that predict retention」で知る)
- Wardley, L. J., Bélanger, C. H. & Leonard, V. M. (2013). Institutional commitment of traditional and non-traditional-aged students: A potential brand measurement? Journal of marketing for higher education, 23(1), 90-112.[Abstract](Google Scholarの引用元検索「Student variables that predict retention」で知る)
- Delaney, A. M. (2008). Typical institutional research studies on students: Perspective and examples. New directions for higher education, 141, 57-67.[Abstract](Google Scholarの引用元検索「Student variables that predict retention」で知る)
- Collins, M. L. (2010). Bridging the evidence gap in developmental education. Journal of developmental education, 34(1), 2-25.[Abstract](Google Scholarの引用元検索「Student variables that predict retention」で知る)
- Stewart, J., & Martinello, F. (2012). Are transfer students different? An examination of first-year grades and course withdrawals. Canadian journal of higher education, 42(1), 25-42.[Abstract](Google Scholarの引用元検索「Student variables that predict retention」で知る)
- Clounch, T. L. (2010). An exploration of how involvement in a freshman retention program relates to intention to complete an undergraduate degree. Unpublished doctoral dissertation, University of Kansas. [PDF](Google Scholarの引用元検索「Student variables that predict retention」で知る)
- Belloc, F., Maruotti, A. & Petrella, L.. (2011). How individual characteristics affect university students drop-out: A semiparametric mixed-effects model for an Italian case study. Studies in higher education, 38(10), 2225-2239.[Abstract](Google Scholarの引用元検索「Student variables that predict retention」で知る)
- Lehning, E. M. (2008). Impact of an extended orientation program on academic performance and retention. Unpublished doctoral dissertation, Kansas State University, Manhattan, KS.[PDF](Google Scholarの引用元検索「Student variables that predict retention」で知る)
- Ukpabi, C. V. (2005). Formulating a prediction model of retention rate in the University of North Carolina System. Unpublished doctoral dissertation, NC State University, Raleigh, NC.[PDF](Google Scholarの引用元検索「Student variables that predict retention」で知る)
- McEwan, B. (2013). Retention and resources: An exploration of how social network resources related to university commitment. Journal of college student retention: Research, theory & practice, 15(1), 113-128.[Abstract](Google Scholarの引用元検索「Student variables that predict retention」で知る)
- Mattern, K., Wyatt, J., & Shaw, E. (2013). College distance from home: Implications for student transfer behavior. Journal of the first-year experience & students in transition,, 25(1), 77-92.[ETS research report series, 2013(1), i-61.[PDF](Google Scholarの引用元検索「Student variables that predict retention」で知る)
- Emmons, M. (2012). The academic library impact on student persistence: Two models. Unpublished doctoral dissertation, University of New Mexico, Albuquerque, NM.[PDF](Google Scholarの引用元検索「Student variables that predict retention」で知る)
- Matthews、K. (2010). Causes and differences in retention of white, African American, and Hispanic students who progressed toward graduation after first year in college. Unpublished doctoral dissertation, Baylor University, Waco, TXd.[PDF](Google Scholarの引用元検索「Student variables that predict retention」で知る)
- Grillom M. C., & Leist, C. W. (2013). Academic support as a predictor of retention to graduation: New insights on the role of tutoring, learning assistance, and supplemental instruction. Journal of college student retention: Research, theory & practice, 15(3), 387-408.[Abstract](Google Scholarの引用元検索「Student variables that predict retention」で知る)
- Messina, J. A. (2011). A statistical analysis of the impact of participation in living-learning communities on academic performance and persistence. Unpublished doctoral dissertation, University of Akron, Akron, OH.[PDF](Google Scholarの引用元検索「Student variables that predict retention」で知る)
- Pan, W., & Bai, H. (2010). Testing and estimating direct and indirect effects of an intervention program on college student retention: A structural model. Enrollment management journal: Student access, finance, and success in higher education, 4(1), 10-26.[PDF](Google Scholarの引用元検索「Student variables that predict retention」で知る)
- Grefenstette, C. (2011). High school course patterns as related to university academic achievement and persistence. Unpublished doctoral dissertation, University of Houston, Houston, TX.[PDF](Google Scholarの引用元検索「Student variables that predict retention」で知る)
- Strahn-Koller, B. L. (2012). Academic transfer shock and social integration: A comparison of outcomes for traditional and nontraditional students transferring from 2-year to 4-year institutions. Unpublished doctoral dissertation, The University of Iowa, Iowa City, IA.[PDF](Google Scholarの引用元検索「Student variables that predict retention」で知る)
- Morgan, B. (2014). A Predictive Model of Canadian College Student Retention. Unpublished doctoral dissertation, University of Calgary, Calgary, Alberta, Canada.[PDF](Google Scholarの引用元検索「Student variables that predict retention」で知る)
- Chowdhury, L., & Nimmy, S. F. (2012). New dropout prediction for intelligent system. International journal of computer applications, 42(16), 26-31.[PDF](Google Scholarの引用元検索「Student variables that predict retention」で知る)
- Kim, J. (2015). Predictors of college retention and performance between regular and special admissions. Journal of student affairs research and practice, 52(1), 50-63i.[Abstract](Google Scholarの引用元検索「Student variables that predict retention」で知る)
- Artze-Vega, I. (2012). The relationship between student ratings and student retention. Unpublished doctoral dissertation, University of Miami, Coral Gables, FL.[PDF](Google Scholarの引用元検索「Student variables that predict retention」で知る)
- Alkan, N. (2014). Humor, loneliness and acceptance: Predictors of university drop-out intentions. Procedia: Social and behavioral sciences, 152(7), 1079–1086.[PDF](Google Scholarの引用元検索「Student variables that predict retention」で知る)
- Allen, J., Robbins, S. B., Casillas, A., & Oh, I. S. (2008). Third-year college retention and transfer: Effects of academic performance, motivation, and social connectedness. Research in Higher Education, 49(7), 647-664.[Abstract](Alkan(2014)"Humor, loneliness and acceptance"で知る)
- Asher, S. R., & Weeks, M. S. (2014). Loneliness and belongingness in the college years. In Robert J. C. & J. C. Bowker(Eds.) The handbook of solitude: Psychological perspectives on social isolation, social withdrawal, and being alone. Chichester, UK: Wiley Blackwell. pp.283-301.[
- Bray, N. J., Braxton, J. M., & Sullivan, A. S. (1999). The influence of stress-related coping strategies on college student departure decisions. Journal of college student development, 40(6), 645-657.[Abstract](Alkan(2014)"Humor, loneliness and acceptance"で知る)
- DeBerard, M. S., Spielmans, G. I., & Julka, D. C. (2004). Predictors of academic achievement and retention among college freshmen: A longitudinal study.College Student Journal, 38(1), 66-80.[Abstract](Alkan(2014)"Humor, loneliness and acceptance"で知る)
- Gerdes, H., & Mallinckrodt, B. (2011). Emotional, social, and academic adjustment of college students: A longitudinal study of retention. Journal of counseling & development, 72(3), 281-288.[Abstract](Alkan(2014)"Humor, loneliness and acceptance"で知る)
- Kuiper, N. A., & Martin, R. A. (1993). Humor and self-concept. Humor, 6(3), 251-270.[Abstract](Alkan(2014)"Humor, loneliness and acceptance"で知る)
- McGaha, V., & Fitzpatrick, J. (2005). Personal and social contributors to dropout risk for undergraduate students. College Student Journal, 39(2), 287-297.[Abstract](Alkan(2014)"Humor, loneliness and acceptance"で知る)
- Nicpon, M. F., Huser, L., Blanks, E. H., Sollenberger, S., Befort, C., & Kurpius, S. E. R. (2006). The relationship of loneliness and social support with college freshmen's academic performance and persistence. Journal of college student retention: Research, theory & practice, 8(3), 345-358.[Abstract](Alkan(2014)"Humor, loneliness and acceptance"で知る)
- Pritchard, M. E., & Wilson, G. S. (2003). Using emotional and social factors to predict student success. Journal of college student development, 44(1), 18-28.[Abstract](Alkan(2014)"Humor, loneliness and acceptance"で知る)
- Shields, N. (2008). Stress, active coping, and academic performance among persisting and nonpersisting college students. Journal of applied biobehavioral research, 6(2), 65-81.[Abstract](Alkan(2014)"Humor, loneliness and acceptance"で知る)
- Tinto, V. (2010). From theory to action: Exploring the institutional conditions for student retention. In J. C. Smart(Ed.) Higher education: Handbook of theory and research. New York: Springer. pp.51-89.[Abstract](Alkan(2014)"Humor, loneliness and acceptance"で知る)
- Tross, S. A., Harper, J. P., Osher, L. W., & Kneidinger, L. M. (2000). Not just the usual cast of characteristics: Using personality to predict college performance and retention. Journal of college student development, 41(3), 323-334.[Abstract](Alkan(2014)"Humor, loneliness and acceptance"で知る)
[2015.06.30]ホーム「お知らせ」欄を変更
- 口頭発表「IR実務担当者のための事例解説:授業アンケートの回答率を向上させ、学生から建設的な意見を得るための工夫」(平成27年度第1回IR実務担当者連絡会)を掲載
[2015.06.29]「私立大学職員によるIR文献メモ」メルマガ バックナンバーを更新
[2015.06.27]大学に関わる情報メモ 内容を修正
- 第6回EMIR勉強会
- 会場の記載が誤っていたため修正(誤:「大正大学(東京)」、正:「関西学院大学(兵庫)」)
[2015.06.26]IRなどについての文献メモ 文献一覧を更新
- 萩原剛・太田裕之・藤井聡(2006).アンケート調査回収率に関する実験研究:MM参加率の効果的向上方策についての基礎的検討 土木計画学研究・論文集,23,117-123.[PDF]
- 永原和夫・菅原良・松岡審爾・池田官司(2011).学生による授業評価に関する全国調査 北海道文教大学論集,12,157-172.[PDF](実施方法・アンケートの評価項目・統計データ集計方法・利活用について有効性がほとんど実証されていない、学生の声が着実に授業にフィードバックされる方法を開発する目的で全国の主要大学における学生による授業評価の実態を調査)
- 米谷淳(2007).学生による授業評価についての実践的研究 大学評価・学位研究,5,121-134.[PDF](Google「授業アンケート 実施率 文部科学省」で知る)
- 渡辺勇一(2003).学生による授業評価の平均値は後期に高くなる 大学教育研究年報,8,117-123.[PDF]
- 関内隆・縄田朋樹・葛生政則・ 北原良夫・板橋孝幸(2006).主要国立大学における「学生による授業評価」アンケートの分析 東北大学高等教育開発推進センター紀要,1,41-54.[PDF](アンケートの目的・実施方法・設問項目・結果の活用などを調査、調査対象は「全国大学教育研究センター等協議会」加盟の25大学など)
- 古宮昇(2003).学生による授業評価の、実施時期が評価におよぼす影響 大阪経大論集,54(2),407-411[PDF]()
[2015.06.22]IRなどについての文献メモ 文献一覧を更新
- Reason, R. D. (2009). Student variables that predict retention: Recent research and new developments. Journal of student affairs research and practice, 46(3), 850-869.[Abstract](Google Scholar「diversity retention rate」で知る)
- Seidman, A. (2005). Minority student retention: Resources for practitioners. New directions for institutional research, 125, 7-24.[Abstract](Google Scholar「diversity retention rate」で知る)
- Thayer, P. B. (2000). Retention of students from first generation and low income backgrounds. The journal of the Council for Opportunity in Education, 1-9.[PDF](Google Scholar「diversity retention rate」で知る)
[2015.06.16]IRなどについての文献メモ 文献一覧を更新
- ローム,D.住友進(訳)(2015).描いて、見せて、伝えるスゴい!プレゼン 講談社(Amazon.co.jpレコメンド機能で知る)
- 森井ユカ(2015).読みやすい文字と伝わるイラスト:描き方BOOK! KADOKAWA(Amazon.co.jpレコメンド機能で知る)
[2015.06.16]IRなどについての文献メモ 文献一覧を更新
- 苅谷剛彦・志水宏吉(編)(2004).学力の社会学:調査が示す学力の変化と学習の課題 岩波書店
- トロウ,M.天野郁夫・喜多村和之(訳)(1976).高学歴社会の大学:エリートからマスへ 東京大学出版会
[2015.06.12]ホーム ページ構成を変更
[2015.06.11]IRなどについての文献メモ 内容をアップ
- 浦坂純子・西村和雄・平田純一・八木匡(2013).大学入試制度の多様化に関する比較分析:労働市場における評価 RIETI Discussion Paper Series,3-J-019,1-10.[PDF][概要](Google Scholar「入試制度 多様化」で知る)
[2015.06.11]IRなどについての文献メモ 文献一覧を更新
- 苅谷剛彦(1995).大衆教育社会のゆくえ:学歴主義と平等神話の戦後史 中央公論社(一般選抜入学試験の意義について議論、日本の大学の一般入試は基本的に教科に関する筆記試験のみで選抜する方法を採っている、筆記試験で採用する教科は大学によって異なっており各大学が独自に作成する試験問題を解答させる形で実施している;浦坂他(2013)「大学入試制度の多様化に関する比較分析」で知る
[2015.06.10]IRなどについての文献メモ 文献一覧を更新
- 石井秀宗・椎名久美子・前田忠彦・柳井晴夫(2007). 大学教員における学生の学力低下意識に影響する諸要因についての検討 行動計量学,34(1),67-77.[PDF](学力低下を論ずる際にどのような立場の人はどういう側面の学力低下を議論するかを調査、性別・年齢・在職年数・設置形態・学部系統・担当学年の中では学部系統と設置形態の2つの属性が学力低下意識に相対的に強く影響していた、より年長の教員または私立の教員において基礎的能力の低下を懸念する傾向が強い、学部ごとの懸念事項・・・社会・体育・家政生活:基礎的能力の低下、理学:主体性(学習意欲)の低下、情報・経済・商・工・薬:基礎的能力と主体性(学習意欲)の両方の低下、属性や立場の違いからくる議論のすれ違いは学力低下論争に混乱をもたらしている;Goole Scholar「大学生 基礎学力 "従来の"」で知る)
- 濱中淳子(代表)(2013).大衆化する大学:学生の多様化をどうみるか 岩波書店(Amazon.co.jp「学生 多様化」で知る)
- 山内乾史(2013).大学生の学力形成支援 名古屋高等教育研究,13,165-176.[PDF](履修経歴の多様化(水平的多様化)と学力低下・拡散化(垂直的多様化)が―いずれの大学でも程度の差こそあれ―認められる、それらを入学後早期に整えることがことに共通教育と学部の初年次教育において重要な課題;Google Scholar「学生 学力 多様化 教育方法」で知る)
- 佐藤美津子(2011).大学入試の多様化と学力格差:4年制私立大学を中心にして 紀要,3,81-92.[PDF](4年制私立大学では2010 年度では定員割れが217校(38.1%)、AO・推薦入試による合格者数が一般入試による入学者数を上回っている、様々なAO・推薦入試方法で入学する学生が46%に拡大、基礎学力の把握無しに大学に入学してくる学生と一般入試で入学してくる学生との間に学力差が生じている;Google Scholar「学力 多様化 データ」で知る)
[2015.06.8]IRなどについての文献メモ 文献一覧を更新
[2015.06.05]IRなどについての文献メモ 文献一覧を更新
- 宮野公樹(2009).学生・研究者のための使える!PowerPointスライドデザイン:伝わるプレゼン1つの原理と3つの技術 化学同人(Amazon.co.jp「宮野公樹」で知る)
- 宮野公樹(2011).学生・研究者のための伝わる!学会ポスターのデザイン術:ポスター発表を成功に導くプレゼン手法 化学同人(Amazon.co.jp「宮野公樹」で知る)
- 宮野公樹(2015).研究を深める5つの問い:「科学」の転換期における研究者思考 講談社(Amazon.co.jp「宮野公樹」で知る)
[2015.06.05]IRなどについての文献メモ 文献一覧を更新
- 高橋威知郎・安宅和人・河本薫・吉田隆光・北川拓也・工藤卓哉・西山直樹・シバタアキラ(2015).データ活用実践教室:トップデータサイエンティストが教える 日経BP社(Amazon.co.jpレコメンド機能で知る)
[2015.06.04]IRなどについての文献メモ 文献一覧を更新
- Dennis, M. J. (1998). A practical guide to enrollment and retention management in higher education. Westport, Conn.:Bergin & Garvey.(Amazon.co.jp「enrollment management」で知る)
- Ingersoll, R. J. (1999). Enrollment management: Making it work. Phoenix, Ariz.: Oryx Press.(Amazon.co.jp「enrollment management」で知る)
- Dolence, M. G. (1996). Strategic enrollment management: Cases from the field. Washington, D.C.: American Association of Collegiate Registrars amd Admission Officers.(Amazon.co.jp「enrollment management」で知る)
- Ingersoll, D. Bontrager, B., & Ingersoll, R. (2012). Strategic enrollment management: Transforming higher education. Amazon Services International (Kindle).(Amazon.co.jp「enrollment management」で知る)
- Craig Westman, Penny Bouman (2005). AACRAO's basic guide to enrollment management. Washington, DC: American Association of Collegiate Registrars and Admissions Officers.(Amazon.co.jp「enrollment management」で知る)
- Hossler, D. (1984). Enrollment management an integrated approach. New York: College Entrance Examinaton Board.(Amazon.co.jp「enrollment management」で知る)
- Penn, G. (1999). Enrollment management for the 21st century: Institutional goals, accountability, and fiscal responsibility. Washington, DC: George Washington University.[PDF](Amazon.co.jp「enrollment management」で知る)
- Dixon, R. R.(Ed.) (1995). Making enrollment management work. San Francisco: Jossey-Bass Publishers.[Abstract](Amazon.co.jp「enrollment management」で知る)
- Coomes, M. D. (2000). The role student aid plays in enrollment management. San Francisco: Jossey-Bass Publishers.(Amazon.co.jp「enrollment management」で知る)[Abstract]
- Hossler, D. (1986). Creating effective enrollment management systems. New York: College Entrance Examination Board.[Abstract](Amazon.co.jp「enrollment management」で知る)
- Hossler, D. Bean, J. P. & associates (1990). The strategic management of college enrollments. San Francisco, Calif.: Jossey-Bass.[Abstract](Amazon.co.jp「enrollment management」で知る)
[2015.06.03]IRなどについての文献メモ 文献一覧を更新
- 大塚雄作(1994).理論と実践を結ぶ測定・評価に向けて 教育心理学年報,33,102-111.[PDF](21世紀COEプログラム東京大学大学院教育学研究科基礎学(編)(2006)『日本の教育と基礎学力:危機の構図と改革への展望』で知る)
[2015.06.03]IRなどについての文献メモ 文献一覧を更新
- 櫻田潤(2015).シンプル・ビジュアル・プレゼンテーション ブックウォーカー(Amazon.co.jpレコメンド機能で知る)
- ランド,P. 河村めぐみ(訳)(2014).ポール・ランドのデザイン思想 スペースシャワーネットワーク(櫻田(2015)『シンプル・ビジュアル・プレゼンテーション』で知る)
- ランド,P.(述)Kroeger, M. 三角和代(訳)(2008).ポール・ランド、デザインの授業 ビー・エヌ・エヌ新社(櫻田(2015)『シンプル・ビジュアル・プレゼンテーション』で知る)
- マエダ,J. 鬼澤忍(訳)(2008).シンプリシティの法則 東洋経済新報社(櫻田(2015)『シンプル・ビジュアル・プレゼンテーション』で知る)
- フィールド,S. 安藤紘平・加藤正人・小林美也子・山本俊亮(訳)(2009).映画を書くためにあなたがしなくてはならないこと フィルムアート社(櫻田(2015)『シンプル・ビジュアル・プレゼンテーション』で知る)
- 三木雄信(2015).世界のトップを10秒で納得させる資料の法則 東洋経済新報社(Amazon.co.jpレコメンド機能で知る)
- 大崎善治(2015).レイアウトの基本ルール:作例で学ぶ実践テクニック グラフィック社(Amazon.co.jpレコメンド機能で知る)
- 鈴木雅彦・鈴村嘉右(2015).データビジュアライゼーションのデザインパターン20:混沌から意味を見つける可視化の理論と導入 技術評論社(Amazon.co.jpレコメンド機能で知る)
- 加藤智也(2015).スライドデザインの心理学:一発で決まるプレゼン資料の作り方 翔泳社(Amazon.co.jpレコメンド機能で知る)
- レヴィット,S.&ダブナー,S. 櫻井祐子(訳)(2015).0ベース思考:どんな難問もシンプルに解決できる ダイヤモンド社(Amazon.co.jpレコメンド機能で知る)
- 石黒謙吾(2005).図解でユカイ ゴマブックス(Amazon.co.jpレコメンド機能で知る)
- カーツメディアワークス(編)(2014).インフォグラフィック・デザイン:わかりやすく情報を伝える図説のデザイン ビー・エヌ・エヌ新社(Amazon.co.jpレコメンド機能で知る)
[2015.06.03]ホーム「お知らせ」欄を変更
- 口頭発表「成績評価データを教育の質保証に活用する:GP分布分析をFD活動につなげる仕組み」(大学行政管理学会第19回(2015年度)定期総会・研究集会)を掲載
[2015.06.02]IRなどについての文献メモ 文献一覧を更新
- 濱名篤(2015).高大接続をめぐる課題と学生支援型IRの活用 初年次教育学会誌,7(1),76-84.
[2015.06.01]ホーム「お知らせ」欄を変更
- 平成27年度大学改革支援制度(京都光華女子大学学長裁量経費)「基礎学力を把握する仕組みの開発:学科の要望と学内の既存データを組み合わせた教科内容の修得状況分析(IR)」を掲載
- 「SPODフォーラム2015」講演依頼を掲載
- 「平成27年度全国大学教育研究センター等協議会」講演依頼を掲載
[2015.06.01]IRなどについての文献メモ 文献一覧を更新
- 関隆宏(2015).オレゴン大学IRオフィス訪問記 大学評価とIR,2,3-8.[PDF]
- 大野賢一・森藤郁美・細井由彦(2015).法人評価業務における鳥取大学の取組 大学評価とIR,2,9-16.[PDF]
- 藤原宏司(2015).政策立案・計画策定における米国IR室の役割 大学評価とIR,2,17-25.[PDF]
- 嶌田敏行・大野賢一・末次剛健志・藤原宏司(2015). IRオフィスを運用する際の留意点に関する考察 大学評価とIR,2,27-36.[PDF]
[2015.05.30]ホーム「お知らせ」欄を変更
- ポスター発表「基礎学力を把握する仕組みの開発:学科の要望と学内の既存データを組み合わせた教科内容の修得状況分析(IR)」(初年次教育学会第8回大会)を掲載
[2015.05.30]「過去の「お知らせ」」に追加
- ポスター発表"Bridging faculty members' expectations and students' actual studying hours"(2015 AIR Forum)
[2015.05.15]IRなどについての文献メモ 文献一覧を更新
- 藤村正司(2003).新潟大学教養教育GPデータにみる成績評価の分布 新潟大学大学教育開発研究センター,大学教育研究年報,8,139-145.[PDF](Google Scholar「"GP分布" 成績 大学」で知る)
[2015.05.10]IRなどについての文献メモ 文献一覧を更新
- 森雅生・大石哲也・高田英一(2015).教職員におけるIR技能の育成の現状と課題:「IR人材育成カリキュラム集中講習会」の成果の検証を中心に 大学職員論叢,3,81-90.(ブログ「松宮慎治の憂鬱」(松宮慎治さん)の記事「読了した文献(6)」で知る)
- 小湊卓夫・嶌田敏行(2015).IR その着実な一歩のために:「データ管理」と「IR」を隔てるもの Between,261,29-31.[PDF]
[2015.05.10]IRなどについての文献メモ 文献一覧を更新
- 細川和仁(2012).大学教育の質保証からみたGPA制度 秋田大学教養基礎教育研究年報,14,13-22.[PDF](GPA制度に関連した答申について記載、1988年大学審議会「21世紀の大学像と今後の改革方策について―競争的環境の中で個性が輝く大学―(答申):目標設定・評価基準を明示して厳格に(厳密に)評価する、2008年中央教育審議会「学士課程教育の構築に向けて(答申)」:成績評価に関して教員間の共通理解のもとで各授業科目の到達目標・成績評価基準を明確化しGPAなど客観的な評価システムを導入することを提起」;Google「厳格な成績評価?:教養部解体・GP分布・公正」で知る)
- 堤裕之・末田穂乃香・小寺亮(2015).紙媒体による運用を前提とした授業文書管理システムの構築とその汎用性 デジタルプラクティス,6(2),112-122.[PDF](CiNii Articles「成績評価 大学」で知る)
- 斎藤誠(2015)本学における成績評価の現状:教員アンケート調査結果の概要 東北学院大学教育研究所報告集,15,5-15.(CiNii Articles「成績評価 大学」で知る)
- 池上真人・新井英夫・西山文夫(2015)松山大学英語カリキュラムの現状と課題:習熟度別クラス制における成績評価方法 松山大学論集,26(6),227-245.[PDF](CiNii Articles「成績評価 大学」で知る)
- 田島貴裕(2014).初年次教育の理系実験に対する取組姿勢と成績評価の関連性:入試制度の観点から 日本教育工学会論文誌,38(Suppl.),1-4.[PDF](CiNii Articles「成績評価 大学」で知る)
- 伊藤宏隆・伊藤圭佑・舟橋健司・山本大介・齋藤彰一・松尾啓志・内匠逸(2014).学生の修学データを用いた要注意学生の傾向分析 研究報告教育学習支援情報システム(CLE),2014-CLE-13(8),1-8.[PDF](CiNii Articles「成績評価 大学」で知る)
- 川俣美砂子(2014)教育実習成績評価の分析:項目別評価から見る現場が求める保育者像 福岡女子短大紀要,80,1-11.(CiNii Articles「成績評価 大学」で知る)
[2015.05.08]IRなどについての文献メモ 文献一覧を更新
[2015.04.27]IRなどについての文献メモ 内容をアップ
[2015.04.25]IRなどについての文献メモ 文献一覧を更新
[2015.04.25]IRなどについての文献メモ 文献一覧を更新
[2015.04.21]IRなどについての文献メモ 文献一覧を更新
- 長谷川敦史(2015).大学図書館における「脱出ゲームとゲーミフィケーションの可能性 ふみくら:早稲田大学図書館報,87,2-4.[PDF](はてなブックマークインタレスト「図書館」で知る)
[2015.04.20]IRなどについての文献メモ 文献一覧を更新
- 武寛子(2015).日本におけるIR(インスティテューショナル・リサーチ)による大学教育の質保証:運用状況と制度的課題に関する比較分析 愛知教育大学教育創造開発機構紀要,5,113-122.[PDF]
[2015.04.19]IRなどについての文献メモ 文献一覧を更新
- 早坂清志・きたみあきこ(2015).EXCELグラフ作成[ビジテク]データを可視化するノウハウ 翔泳社(Amazon.co.jpレコメンド機能で知る)
- 日経情報ストラテジー(2014).データサイエンティストの仕事術 日経BP社(Amazon.co.jpレコメンド機能で知る)
[2015.04.17]IRなどについての文献メモ 文献一覧を更新
- 前野好太郎(2014).はじめようExcelでビッグデータ分析 リックテレコム(Amazon.co.jpレコメンド機能で知る)
- 小林孝嗣・できるシリーズ編集部(2014).ビッグデータ入門:分析から価値を引き出すデータサイエンスの時代へ:いま必要な知識が3時間で身につく インプレスジャパン(Amazon.co.jpレコメンド機能で知る)
- 末吉正成(著・監修)(2014).EXCELマーケティングリサーチ&データ分析:2013/2010/2007対応 翔泳社(Amazon.co.jpレコメンド機能で知る)
[2015.04.17]IRなどについての文献メモ 文献一覧を更新
- 21世紀COEプログラム東京大学大学院教育学研究科基礎学(編)(2006).日本の教育と基礎学力:危機の構図と改革への展望 明石書店(Amazon.co.jp「基礎学力」で知る)
[2015.04.14]IRなどについての文献メモ 文献一覧を更新
- 沖清豪(2015).全国私立大学IR調査結果について 私学高等教育研究所シリーズ,57,7-33.[PDF]
- 山田礼子(2015).ジェイ・サープ学生調査の新たな展開 私学高等教育研究所シリーズ,57,37-63.[PDF]
- 杉谷祐美子(2015).ジェイ・サープ学生調査から何がわかるか? 私学高等教育研究所シリーズ,57,67-94.[PDF]
- 木村拓也(2015).ジェイ・サープ学生調査データベースの活用方法 私学高等教育研究所シリーズ,57,97-123.[PDF]
- 森利枝(2015).質疑・討論 私学高等教育研究所シリーズ,57,127-134.[PDF]
- 木村拓也(2015).数値に何を語らせるのか?:IRの「日本化」と学生調査の「機能化」 私学高等教育研究所シリーズ,57,137-140.[PDF]
[2015.04.13]IRなどについての文献メモ 文献一覧を更新
- 細尾萌子(2014).フランスの中等教育における基礎学力論争:知識かコンピテンシーか 近畿大学教育論叢,26(1),17-46.[PDF](CiNii Articles「基礎学力」で知る)
- 宮下治・平岩史恵(2014).大学との連携を取り入れた高等学校理科授業の効果に関する実践研究 愛知教育大学教育創造開発機構紀要,4,1-7.[PDF](CiNii Articles「基礎学力」で知る)
- 坂井美穂・安田幸夫・吉村充功(2014).初年次における基礎学力講座(国語および数学) 日本文理大学紀要,42(1),29-34.(CiNii Articles「基礎学力」で知る)
- 岩田京子・酒見康廣・浦川安宏・大塚絵里子(2014).キャリア開発学科の初年次教育に関する基礎的研究:「スタディ・スキル」「スチューデント・スキル」「基礎学力」を視点として 中村学園大学・中村学園大学短期大学部研究紀要,46,189-198.[PDF](CiNii Articles「基礎学力」で知る)
- 八木澤圭(2014).基礎学力の向上を図るためのICT活用の継続に関する研究 教師養成研究紀要,5,147-159.(CiNii Articles「基礎学力」で知る)
- 岡田小夜子・甲斐荘正晃・玉木伸介・池頭純子(2014).学習成果の「視える化」と学生の「質の保証」を目的とした基礎教育の体系化 人間生活文化研究,2014(24),149-154.[PDF](CiNii Articles「基礎学力」で知る)
- 大島康裕(2014).崇城大学における入学者の数学の学力推移に関する考察:プレースメントテストの結果から 崇城大学紀要,39,39-44.[PDF](CiNii Articles「基礎学力」で知る)
- 柴田智世(2013).基礎学力の向上を目指した授業の試案的取り組み:実習記録及び指導案を作成するために 研究紀要,35,159-172.[PDF](CiNii Articles「基礎学力」で知る)
- 宮道力・三浦孝仁・坂入信也・中山芳一(2013).企業における採用活動の実態と新規学卒者に求める能力に関する実態調査報告 大学教育研究紀要,9,233-243.[PDF](CiNii Articles「基礎学力」で知る)
- 堤裕之・畔津憲司(2013).基礎学力以外の要因を考慮した期末試験スコアの回帰分析 リメディアル教育研究,8(1),139-146.[PDF](CiNii Articles「基礎学力」で知る)
- 野々村憲(2013).『基礎ゼミナール』を活用した授業計画と授業実践報告:学習成果到達度テストの分析結果を中心に 広島文化学園大学学芸学部紀要,3,63-68.[PDF](CiNii Articles「基礎学力」で知る)
- 前正七生・山岡節子(2013).実務者養成系短大における基礎学力に関する省察:初年度教育での文章力および計算力を中心に いわき短期大学研究紀要,46,47-61.(CiNii Articles「基礎学力」で知る)
- 水野貴敏・黒田潔・小林和彦・石川直弘・後藤信夫(2013).物理学基礎学力向上を目指した学習支援制度の進展(3) 玉川大学工学部紀要,48,75-84.[PDF](CiNii Articles「基礎学力」で知る)
- 藤木美江(2013).数学の基礎学力と確率・統計の理解度との関連性:担当科目における比較分析 四條畷学園大学リハビリテーション学部紀要,9,35-45.[PDF](CiNii Articles「基礎学力」で知る)
- 椿本弥生・大塚裕子・高橋理沙・美馬のゆり(2012).大学生を中心とした持続可能な学習支援組織の構築とピア・チュータリング実践 日本教育工学会論文誌,36(3),313-325.[PDF](CiNii Articles「基礎学力」で知る)
- 谷岡弘二・上野貴史・水谷隆(2012).本学入学生における基礎学力の相関関係に関する分析 大阪女子短期大学紀要,37,103-116.(CiNii Articles「基礎学力」で知る)
- 橋本美香・新見明子・黒田裕子(2012).日本語力向上のための初年次教育の実践:日本語教員と看護科教員の協働による下位クラスの学生に対する「文章表現」の取り組み 川崎医学会誌.一般教養篇,38,25-32.[PDF](CiNii Articles「基礎学力」で知る)
- 三原祥子(2012).「書く力」で"ステキな看護師"をつくろう 初年次から始められること(2)学生に教員の意図を正確に伝える:レポートにつなげるノート・テイキング 看護教育,53(5),416-420.(橋本他(2012)「日本語力向上のための初年次教育の実践」で知る)
- 三原祥子・松岡志帆・味木由佳(2012).「書く力」で"ステキな看護師"をつくろう 初年次から始められること(1)座談会「書く力」の適切な指導で"ステキな看護師"をつくる:私たちが連載で取り組むこと 看護教育,53(4),320-327.(CiNii Articles「初年次から始められること」で知る)
- 三原祥子(2012).「書く力」で"ステキな看護師"をつくろう 初年次から始められること(3)学習共同体を創り協働するために共有しておきたいポイント:評価規準とパラグラフを中心に 看護教育,53(6),510-514.(CiNii Articles「初年次から始められること」で知る)
- 味木由佳(2012).「書く力」で"ステキな看護師"をつくろう 初年次から始められること(4)その場で書く、リアクションペーパーの工夫と考察:普段の提出物で「書く力」のトレーニング 看護教育,53(7),608-611.(CiNii Articles「初年次から始められること」で知る)
- 味木由佳(2012).「書く力」で"ステキな看護師"をつくろう 初年次から始められること(5)持ち帰って参考文献なしで作成する提出物へのアドバイス:深く考えてまとめて「書く力」のトレーニング 看護教育,53(8),724-728.(CiNii Articles「初年次から始められること」で知る)
- 三原祥子(2012).「書く力」で"ステキな看護師"をつくろう 初年次から始められること(6)引用・参考文献を用いて作成するレポートへのアドバイス:書き方以前の問題に取り組む 看護教育,53(9),808-813.(CiNii Articles「初年次から始められること」で知る)
- 松岡志帆(2012).「書く力」で"ステキな看護師"をつくろう 初年次から始められること(7)実習レポートを書くためのアドバイス:「書く」ことで客観的視点と論理的思考のトレーニング 看護教育,53(10),896-901.(CiNii Articles「初年次から始められること」で知る)
- 三原祥子(2012).「書く力」で"ステキな看護師"をつくろう 初年次から始められること(8)レジュメおよび質疑応答の指導:相手が目の前にいることを「書く力」の指導に活かす 看護教育,53(11),980-984.(CiNii Articles「初年次から始められること」で知る)
- 松岡志帆(2012).「書く力」で"ステキな看護師"をつくろう 初年次から始められること(9)聞き手を意識した報告の仕方 看護教育,53(12),1062-1065.(CiNii Articles「初年次から始められること」で知る)
- 三原祥子(2013).「書く力」で"ステキな看護師"をつくろう 初年次から始められること(10)実用文(メール、手紙)の書き方の指導:読み手意識の涵養 看護教育,54(1),54-60.(CiNii Articles「初年次から始められること」で知る)
- 昧木由佳(2013).「書く力」で"ステキな看護師"をつくろう 初年次から始められること(11)ようこそ先輩!"書く力"をステキな看護師による講義で動機づける 看護教育,54(2),140-145.(CiNii Articles「初年次から始められること」で知る)
- 三原祥子(2013).「書く力」で"ステキな看護師"をつくろう 初年次から始められること(12)初年次看護学生の「書く力」を伸ばすために看護教員と看護学生の間のギャップを埋める 看護教育,54(3),234-238.(CiNii Articles「初年次から始められること」で知る)
- 佐藤政男・庄子昇・秋田昌彦・中山信子・三尾直樹(2011).大学生活への早期適応促進への「教育センター」の試み:基礎学力アップと定期試験への対応導入 徳島文理大学研究紀要,82,11-21.[PDF](CiNii Articles「基礎学力」で知る)
- 高橋琢理・高原健爾・池田和生・若松秀俊(2011).基礎数学科目での学習自己点検の実施による学習傾向の把握と学習習慣の形成 電気学会論文誌.A,基礎・材料・共通部門誌,131(8),622-627.[PDF](CiNii Articles「基礎学力」で知る)
- 飯塚育生・高見昭康・箕田充志・仲田知弘・渡邉修治・加藤健一・加藤聡・武邊勝道・鈴木純二(2011).ラーニング/ティーチングによる基礎学力向上を図る取組 工学教育,59(4),80-84.[PDF](CiNii Articles「基礎学力」で知る)
- 原田邦(2011).いつ物理学の学力が低下し始めたのか?:入学時における物理学の基礎学力の動向 東北薬科大学一般教育関係論集,24,117-128.[PDF](CiNii Articles「基礎学力」で知る)
- 竹内麻希子・矢野昌平・宮崎敏昌(2011).自律自習による基礎学力向上への取り組みについて:「電気電子理論演習2」導入の成果と評価 高専教育,34,119-124.[PDF](CiNii Articles「基礎学力」で知る)
- 甲田直喜(2011).リメディアル教育における文法項目の誤答調査と到達度目標 淑徳短期大学研究紀要,50,225-240.[PDF](CiNii Articles「基礎学力」で知る)
- 木村寛(2010).基礎学力の向上を目指す学習支援の在り方について(その1)数学支援の実情と問題点の改善 広島工業大学紀要 教育編,9,13-18.(CiNii Articles「基礎学力」で知る)
- 木村寛(2012).自ら学ぶ意欲を育てる学習支援の在り方について その2 広島工業大学紀要 教育編,11,67-72.[PDF](木村(2010)「基礎学力の向上を目指す学習支援の在り方について」で知る)
[2015.04.05]ホーム「お知らせ」欄を変更
- 平成27年度科学研究費助成事業(科学研究費補助金)(奨励研究)の採択結果を掲載
- 大学行政管理学会2015年度若手研究奨励の採択結果を掲載
[2015.04.05]IRなどについての文献メモ 文献一覧を更新
- 福島真司(2015).「総合的学生情報データ分析システム」の構築 山形大学におけるエンロールメント・マネジメントとインスティテューショナル・リサーチ 情報管理,58,2-11.[PDF](Twitter(@high190さん)で知る)
[2015.04.02]IRなどについての文献メモ 文献一覧を更新
- 船守美穂(2014).デジタル技術は高等教育のマス化問題を救えるか?:MOOCs,教育のビッグデータ,教学IRの模索 情報知識学会誌,24(4),424-436.[PDF](CiNii Articles「institutional research」で知る)
- 林隆之(2014).大学評価・質保証の新たな課題と組織的な情報分析 情報知識学会誌,24(4),370-380.(CiNii Articles「institutional research」で知る)
- 小林雅之・劉文君(2014).日本型IR構築に向けて カレッジマネジメント,32(6),6-13.[PDF](CiNii Articles「institutional research」で知る)
- 丸山和昭(2014).山形大学 入試対策等に端を発した大学マネジメント戦略 カレッジマネジメント,32(6),14-17.[PDF](CiNii Articles「institutional research」で知る)
- 杉本和弘(2014).京都光華女子大学 EMの実現をデータで支える活きたPDCAサイクル カレッジマネジメント,32(6),18-21.[PDF](CiNii Articles「institutional research」で知る)
- 吉田文(2014).日本福祉大学 分析と事業策定を分離した職員主体のIR カレッジマネジメント,32(6),22-25.[PDF](CiNii Articles「institutional research」で知る)
- 齊藤貴浩(2014).IR組織の新設事例【国立大学】<大阪大学未来戦略機構>機動的マネジメントを実現する未来戦略機構戦略企画室の取り組み カレッジマネジメント,32(6),26.[PDF](CiNii Articles「institutional research」で知る)
- 劉文君(2014).IR組織の新設事例 【私立大学】 <東洋大学IR室>IR室の設置と今後の展望について カレッジマネジメント,32(6),27.[PDF](CiNii Articles「institutional research」で知る)
- 高田英一・高森智嗣・森雅生(2014).IRにおけるデータ提供と活用支援のあり方について:九州大学版ファクトブック「Q-Fact」の取組の検証を基に 大学評価研究,13,101-111.(CiNii Articles「institutional research」で知る)
- 藤村直美・笠原義晃・伊東栄典・尾花昌浩・井上仁(2014).学生番号と異なる学内情報サービス専用ID付与 情報処理学会研究報告.IOT,[インターネットと運用技術]2014-IOT-26(1),1-6.[PDF](CiNii Articles「institutional research」で知る)
- 中島悠介(2014).アラブ首長国連邦における連邦立大学の内部質保証:UAE大学を事例として 京都大学大学院教育学研究科紀要,60,97-109.[PDF](CiNii Articles「institutional research」で知る)
- 村田嘉弘(2014).大学IRについて 長崎大学 大学教育イノベーションセンター紀要,5,7-11.[PDF](CiNii Articles「institutional research」で知る)
- 浜崎央・片庭美咲・柴田幸一・住吉廣行(2014).カリキュラム・ポリシーの成功度を評価する指標の開発:教職協働とInstitutional Researchの発展 松本大学研究紀要,12,77-85.[PDF](CiNii Articles「institutional research」で知る)
- 田中洋一・平塚紘一郎・入澤学・山川修(2014).学生意識調査フィードバックシステムの構築:Fレックスにおける教学IR 仁愛女子短期大学研究紀要,46,17-22,[PDF](CiNii Articles「institutional research」で知る)
- 桑原俊一(2014).IR(機関調査)と学修時間:社会のグローバル化のなかで 開発論集,93,25-48.[PDF](CiNii Articles「institutional research」で知る)
- 山内尚子・耳野健二・佐藤賢一(2014).京都産業大学における授業アンケートの成果と課題 高等教育フォーラム,4,105-109[PDF]CiNii Articles「institutional research」で知る)
- 松田岳士・石橋嘉一・中山実(2014).ルーブリックとLearning Analyticsを組み合わせたジェネリックスキル測定の試み 電子情報通信学会技術研究報告.ET,教育工学 113(377),31-35.[PDF](CiNii Articles「institutional research」で知る)
- 高橋哲也・星野聡孝・溝上慎一(2014).学生調査とeポートフォリオならびに成績情報の分析について:大阪府立大学の教学IR実践から 京都大学高等教育研究,20,1-15.(CiNii Articles「institutional research」で知る)
- 南俊朗(2014).図書館マーケティングから大学IR(機関研究)へ:図書館データ解析への期待 九州大学附属図書館研究開発室年報,8-17.(CiNii Articles「institutional research」で知る)
- 高田英一・森雅生・高森智嗣・桑野典子(2013).国立大学法人におけるIRの機能・データベース・組織のあり方について:IR担当理事に対するアンケート調査結果を中心に 大学評価研究,12,159-174.(CiNii Articles「institutional research」で知る)
- 安藤厚・細川敏幸・大沼明・山畑倫志・宮本淳・徳井美智代・山田邦雅・竹山幸作(2013).連携5大学「一年生・上級生調査2011年」の北海道大学を中心とした比較分析(報告):教学評価IRネットワーク推進のために 高等教育ジャーナル:高等教育と生涯学習,20(1),1-102.[PDF](CiNii Articles「institutional research」で知る)
- 小松川浩・佐藤眞久・望月雅光・山田礼子・穗屋下茂(2013).単位の実質化とICT活用:第8回全国大会ICT活用教育シンポジウムの記録 リメディアル教育研究,8(1),19-36.[PDF](CiNii Articles「institutional research」で知る)
[2015.03.19]IRなどについての文献メモ 文献一覧を更新
[2015.03.18]IRなどについての文献メモ 文献一覧を更新
- Webber, K. L. & Calderon, J. C.(Eds.)(2015). Institutional research and planning in higher education: Global contexts and themes. New York: Routledge.
[2015.03.13]ホーム「お知らせ」欄を変更
- 口頭発表「学生の主体的な活動を促すプロジェクト型授業の授業デザインシートの開発:ソーシャルアクションアプローチに着目して」(大学教育学会第37回大会)を掲載
[2015.03.13]「過去の「お知らせ」」に追加
- 口頭発表「内部質保証のために学修時間の質・量を向上させる仕組み:データに基づく検証システム(IR)と組織的な改善活動」(第21回大学教育研究フォーラム)
[2015.03.07]IRなどについての文献メモ 文献一覧を更新
- 橋本智也(2015).データの蓄積と組織的な活用(IR)による教育の質保証:学生の学修時間と成績・意欲の関係を検証する 情報処理学会研究報告 教育学習支援情報システム研究会報告,2015-CLE-15(1) pp.1-5.[PDF]
[2015.03.06]IRなどについての文献メモ 文献一覧を更新
- 成瀬尚志(2015).レポート評価において求められるオリジナリティと論題の設定について 長崎外大論叢第,18,99-107.(学部レベルのレポート評価においてどのような論題であればどのような能力が測れるか、論題を6つに類型化;Twitter(成瀬尚志先生)で知る)
[2015.03.05]IRなどについての文献メモ 文献一覧を更新
- 田中洋(編)(2014).ブランド戦略全書 有斐閣(Amazon.co.jp「ブランディング」で知る)
- 川上慎市郎・山口義宏著(2013).プラットフォームブランディング ソフトバンククリエイティ(Amazon.co.jp「ブランディング」で知る)
- 博報堂ブランドデザイン(2006).ブランドらしさのつくり方:五感ブランディングの実践 ダイヤモンド社(Amazon.co.jp「ブランディング」で知る)
- ジョン・ムーア 花塚恵(訳)(2014).スターバックスはなぜ値下げもテレビCMもしないのに強いブランドでいられるのか? ディスカヴァー・トゥエンティワン(Amazon.co.jp「ブランディング」で知る)
[2015.03.04]IRなどについての文献メモ 文献一覧を更新
- 成田秀夫・大島弥生・中村博幸(編)(2015).大学生の日本語リテラシーをいかに高めるか ひつじ書房[目次]
[2015.03.04]IRなどについての文献メモ 文献一覧を更新
- 日本生産性本部大学人事戦略クラスター結果(2012).大学 教職員の人事処遇制度に関するアンケート結果概要[PDF](IR実施状況について「実施している」19.0%・「検討中」50.0%・「実施しておらず、今後も予定はない」31.0%、実施していない理由について「IRを行うだけのノウハウがあるスタッフがいない」60.6%・「IRを行うだけの人員数がいない」42.4%、「現行の認証評価や自己点検で十分だと思われるから」30.3%;岩崎(2013)「IR(Institutional Research)の実施状況と特徴」で知る)
[2015.03.02]「過去の「お知らせ」」に追加
- ポスター発表「「京都光華のエンロールメント」の新たな展開:学修成果の可視化とアクティブラーナーの育成のための全学的な学修支援体制の整備」(第20回FDフォーラム)
[2015.02.26]IRなどについての文献メモ 文献一覧を更新
- 松下佳代(編著)(2015).ディープ・アクティブラーニング:大学授業を深化させるために 勁草書房
- 遠海友紀(研究代表者)(2014~2015年度).初年次教育において自律的な学習を促す授業デザインと評価 科学研究費補助金(若手研究(B)) 研究課題番号:20710312[HTML]
[2015.02.26]「過去の「お知らせ」」に追加
- ポスター発表「データに基づいた学生支援をどのように成長につなげるか:アクティブラーナー育成のための体制整備と学修成果の可視化」(京都外国語大学冬季専任教員研修会(学内FD))
[2015.02.24]IRなどについての文献メモ 文献一覧を更新
- 黄文哲(2014).設置別分析 東京大学(編)大学におけるIR(インスティテューショナル・リサーチ)の現状と在り方に関する調査研究報告書 pp.50-80.[PDF](「IRという語を含んだ名称の組織がある」と「IRという名称ではないが、IRを実施する組織がある」という2つの選択肢を合算すると、国立は40.9%、私立は24.7%、公立で10.2%であり、設置別に見ると大きな差が見られる)
[2015.02.23]IRなどについての文献メモ 文献一覧を更新
- 西村秀雄(2015).金沢工業大学における法人・教員・職員協働型IRシステム:現況と課題 学教育研究講演会講演論文集,平成26年度(62),102-103.[PDF](Twitter(@high190さん)で知る)
- 岩崎保道(2013).IR(Institutional Research)の実施状況と特徴:国立大学における取り組み状況に注目して 関西大学高等教育研究,4,19-27.[PDF](多くの国立大学でIRが導入されている背景、法人化によって事業成果を客観的に評価することが求められようになった;Google「IR 国立大学 推進 文部科学省」で知る)
[2015.02.20]IRなどについての文献メモ 文献一覧を更新
- 小林雅之(2014).大学におけるIRの課題と在り方 東京大学(編)大学におけるIR(インスティテューショナル・リサーチ)の現状と在り方に関する調査研究報告書 pp.110-115.[PDF](「日本の大学のケーススタディとアンケート調査により、日本の大学でもIR組織が全大学の4分の1で設置されており、かなり進展していることがわかった」、「IRを担当する全学レベルの組織を有する大学は4分の1にのぼっている」
[2015.02.20]IRなどについての文献メモ 文献一覧を更新
- 大森不二雄(2004).グローバル化が日本の大学に突き付ける課題:教育の質保証と戦略的経営 大学教育年報,7,50-55.[PDF](CiNii Articles「グローバル化 質保証」で知る)
- 大森不二雄(2004).WTO貿易交渉が迫る高等教育の市場開放:賽は投げられた、日本はこれにどう対処すべきか カレッジマネジメント,22(1),32-39.(大森(2004)「グローバル化が日本の大学に突き付ける課題」で知る)
- 深堀聰子(2013).大学教育の質保証:グローバル化による学力観と質概念の変化のなかで 日本教育社会学会大会発表要旨集録,65,375-376.[PDF](CiNii Articles「グローバル化 質保証」で知る)
[2015.02.19]IRなどについての文献メモ 文献一覧を更新
- 吉崎誠(2014).高等教育マネジメントを考える(2)大学の国際化・グローバル化 私学経営,475,34-46.(CiNii Articles「高等教育 グローバル化」で知る)
- 北垣郁雄(2014).国際化・グローバル化に関する高等教育文献の枠組と考察 大学論集,45,111-125.[PDF](CiNii Articles「高等教育 グローバル化」で知る)
- 亀山郁夫(2014).グローバル化時代の大学とガバナンス改革 IDE:現代の高等教育,557,64-69.(CiNii Articles「高等教育 グローバル化」で知る)
- 迫宏明・坂之上茂・吉門敬二・児玉英明・森脇可奈子(2013).グローバル化時代の高等教育制度に関する基礎的調査:教育情報の公表義務化及び学内文書の英文化推進を中心に 高等教育フォーラム,3,81-87.[PDF](CiNii Articles「高等教育 グローバル化」で知る)
- 佐藤禎一(2012).グローバル化の中の大学 IDE:現代の高等教育,540,4-10.(CiNii Articles「高等教育 グローバル化」で知る)
- 二宮皓(2012).高等教育におけるグローバル化の影響に関する研究:「まとめ」のためのフレームワーク 教育制度学研究,19,139-141.(CiNii Articles「高等教育 グローバル化」で知る)
- 山田礼子(2012).高等教育政策に見られる世界の共通点:グローバル化の影響を軸に 教育制度学研究,19,135-137.(CiNii Articles「高等教育 グローバル化」で知る)
- 和賀崇(2012).高等教育のグローバル化の影響に関する研究:短期高等教育を中心として 教育制度学研究,19,113-115.(CiNii Articles「高等教育 グローバル化」で知る)
- 嘉悦康太(2010).高等教育におけるグローバル・スタンダードと日本の私学助成 嘉悦大学研究論集52(2),41-76.(CiNii Articles「高等教育 グローバル化」で知る)
- 山本眞一(2010).わが国の大学にとってのグローバル化の意味 桜美林高等教育研究,2,19-30.(CiNii Articles「高等教育 グローバル化」で知る)
- Altbach, P. G.我妻鉄也(訳)(2010).高等教育におけるグローバリゼーションと国際化 桜美林高等教育研究,2,7-18.(CiNii Articles「高等教育 グローバル化」で知る)
[2015.02.19]IRなどについての文献メモ 文献一覧を更新
- 羽田貴史(2014).「大学のガバナンス:その特質を踏まえた組織運営の在り方を考える」へのコメント(大学のガバナンス:その特質を踏まえた組織運営の在り方を考える:第41回(2013年度)『研究員集会』の記録:討論) RIHE,128,153-156.[PDF](CiNii Articles「大学 委員会 組織」で知る)
- 島一則(2014).大学のガバナンス:セッション3:ディスカッションを司会して(大学のガバナンス:その特質を踏まえた組織運営の在り方を考える:第41回(2013年度)『研究員集会』の記録:討論) RIHE,128,157-159.[PDF](CiNii Articles「その特質を踏まえた組織運営の在り方を考える」で知る)
- 秦由美子(2014).第41回研究員集会:大学のガバナンス:その特質を踏まえた組織運営の在り方を考える:セッション2(大学のガバナンス:その特質を踏まえた組織運営の在り方を考える:第41回(2013年度)『研究員集会』の記録:討論) RIHE,128,147-151.[PDF](CiNii Articles「その特質を踏まえた組織運営の在り方を考える」で知る)
- 佐々木一也(2014).立教大学教養教育ガバナンス(大学のガバナンス:その特質を踏まえた組織運営の在り方を考える:第41回(2013年度)『研究員集会』の記録:討論) RIHE,128,127-145.[PDF](CiNii Articles「その特質を踏まえた組織運営の在り方を考える」で知る)
- 大森不二雄(2014).大学ガバナンスと教学マネジメント:首都大学東京の事例(大学のガバナンス:その特質を踏まえた組織運営の在り方を考える:第41回(2013年度)『研究員集会』の記録:討論) RIHE,128,113-125,.[PDF](CiNii Articles「その特質を踏まえた組織運営の在り方を考える」で知る)
- 堀井祐介(2014).金沢大学における組織改革:改革の概要およびその影響について(大学のガバナンス:その特質を踏まえた組織運営の在り方を考える:第41回(2013年度)『研究員集会』の記録:討論) RIHE,128,103-111.[PDF](CiNii Articles「その特質を踏まえた組織運営の在り方を考える」で知る)
- 大膳司(2014).第41回研究員集会の講演と報告を司会して(大学のガバナンス:その特質を踏まえた組織運営の在り方を考える:第41回(2013年度)『研究員集会』の記録:討論) RIHE,128,99-101.[PDF](CiNii Articles「その特質を踏まえた組織運営の在り方を考える」で知る)
- 大場淳(2014).大学ガバナンスの国際比較:研究の視点の整理(大学のガバナンス:その特質を踏まえた組織運営の在り方を考える:第41回(2013年度)『研究員集会』の記録:討論) RIHE,128,75-97.[PDF](CiNii Articles「その特質を踏まえた組織運営の在り方を考える」で知る)
- 村澤昌崇(2014).大学ガバナンスを考える:諸々の調査から(大学のガバナンス:その特質を踏まえた組織運営の在り方を考える:第41回(2013年度)『研究員集会』の記録:討論) RIHE,128,51-73.[PDF](CiNii Articles「その特質を踏まえた組織運営の在り方を考える」で知る)
- 水田健輔(2014).高等教育におけるガバナンス研究のフレームワーク(大学のガバナンス:その特質を踏まえた組織運営の在り方を考える:第41回(2013年度)『研究員集会』の記録:討論) RIHE,128,27-49.[PDF](CiNii Articles「その特質を踏まえた組織運営の在り方を考える」で知る)
- 山本眞一(2014).大学のガバナンスを巡る現状と課題(大学のガバナンス:その特質を踏まえた組織運営の在り方を考える:第41回(2013年度)『研究員集会』の記録:討論) RIHE,128,1-26.[PDF](CiNii Articles「その特質を踏まえた組織運営の在り方を考える」で知る)
[2015.02.18]IRなどについての文献メモ 文献一覧を更新
- 佐藤浩章(2012).日本におけるFD論の批判的検討 大学教育学会誌,34(1),80-88.(CiNii Articles「佐藤浩章」で知る)
- 佐藤浩章(2011).3つのポリシーの策定と一貫性構築によるカリキュラムの質保証 大学教育学会誌,33(2),30-35.(CiNii Articles「佐藤浩章」で知る)
- 川島啓二・加藤かおり・佐藤浩章・沖裕貴(2010).高等教育開発の課題と組織化 大学教育学会誌,32(2),43-46.(CiNii Articles「佐藤浩章」で知る)
- 佐藤浩章・長澤多代・中島英博・稲永由紀・川島啓二(2009).FDプログラムの体系化を目指したFDマップの開発 大学教育学会誌,31(1),136-144.(CiNii Articles「佐藤浩章」で知る)
[2015.02.18]IRなどについての文献メモ 文献一覧を更新
- 若松義人(2007).トヨタ式「改善」の進め方:最強の現場をつくり上げる! PHP研究所(Amazon.co.jp「組織 改善」で知る)
- 日本能率協会コンサルティング(2010).オフィスの業務改善がすぐできる本 日本能率協会マネジメントセンター(Amazon.co.jp「組織 改善」で知る)
- 白川克・榊巻亮(2013).業務改革の教科書:成功率9割のプロが教える全ノウハウ 日本経済新聞出版社 ((Amazon.co.jp「組織 改善」で知る)
- 松井忠三(2013).無印良品は、仕組みが9割 仕事はシンプルにやりなさい 角川書店(Amazon.co.jp「組織 改善」で知る)
[2015.02.17]IRなどについての文献メモ 文献一覧を更新
- 大嶽龍一・辻忠博・雨宮史卓(2014).全学的なFD等教育開発の効果的推進を見据えた教職員の意識と大学組織の在り方-FD等組織調査対象大学と日本大学との比較も踏まえて 日本大学FD研究,2,1-20.[PDF](CiNii Articles「教育改善 組織」で知る)
- 辻忠博・雨宮史卓・光澤浩・品田泰崇・大嶽龍一(2013).FD等教育開発推進関連組織に関する実態調査:調査対象大学の実態と課題 日本大学FD研究,1,53-67.[PDF](『日本大学FD研究』バックナンバー(創刊号:第1号)で知る)
- 田中岳(2011).ファカルティ・ディベロップメントと組織変革:2006年度から5年間の高等教育政策動向に学ぶ 大学教育,16,1-13.(CiNii Articles「教育改善 組織」で知る)[PDF]
- 長野剛(2011).大学の自己省察としてのファカルティ・ディベロップメント 大学教育,16,31-40.(CiNii Articles「教育改善 組織」で知る)[PDF]
- 辻高明(2011).大学教育改善とP2M:FD(FacultyDevelopment)を対象にして 研究発表大会予稿集,2011(春季),64-72.[PDF](CiNii Articles「教育改善 組織」で知る)
- 辻高明(2010).FDとプロジェクトマネジメント 研究発表大会予稿集,2010(春季),201-208.[PDF](CiNii Articles「辻高明」で知る)
- 山地弘起・岡田佳子(2009).教育改善を左右する学内関連組織間の情報流通 日本教育工学会研究報告集,2009(5),15-18.(CiNii Articles「教育改善 組織」で知る)
- 杉原真晃(2009).FDネットワークを評価する:FDネットワーク"つばさ"の一年を振り返って 山形大学高等教育研究年報:山形大学高等教育研究企画センター紀要,3,38-47.[PDF](CiNii Articles「教育改善 組織」で知る)
- 川島啓二(2009).早稲田大学大学史資料センター主催 第9回私立大学研究フォーラム報告 大学における教育改善のためのセンター組織の役割と機能 早稲田大学史記要,40,117-147.(CiNii Articles「教育改善 組織」で知る)
- 奥田雅信(2009).日常的な教育改善のための組織的な取り組み 大手前大学CELL教育論集,1,1-4[PDF]CiNii Articles「教育改善 組織」で知る)
- 岩部浩三(2008).山口大学における目標達成型教育改善プログラム組織的FDとカリキュラム 文部科学教育通信,195,20-22.(CiNii Articles「教育改善 組織」で知る)
- 木本尚美(2008).県立広島大学におけるFDの組織化と教育改善サイクルの構築 比治山高等教育研究,1,31-41.[PDF](CiNii Articles「教育改善 組織」で知る)
- 小田隆治(2007).クリニック型FDに関する一考察:山形大学のFD活動を通して 山形大学高等教育研究年報:山形大学高等教育研究企画センター紀要,1,66-75.[PDF](CiNii Articles「教育改善 組織」で知る)
- 小湊卓夫(2007).ファカルティ・ディベロップメントに見る大学教員の活動と可視化 関東学院大学経済経営研究所年報,29,1-11.[PDF](CiNii Articles「教育改善 組織」で知る)
- 曽我静男(2007).FDの組織化はどこまで可能か:大学教育改善のための実践例:大同工業大学 大学教育と情報,15(3),8-10.(CiNii Articles「教育改善 組織」で知る)
- 川嶋太津夫(2014).教育の組織化、教育課程の体系化・可視化による質保証:コース・ナンバリングの意味と意義 同志社大学学習支援・教育開発センター年報,5,51-76.[PDF](CiNii Articles「FD 組織」で知る)
- 山田剛史(2014).大学教員の教授・学習に関する認知・行動・成果の関連 大学教育学会誌,36(1),113-117.(CiNii Articles「FD 組織」で知る)
- 池田輝政(2014).FD課題への「学習する組織」理論の適用と知見に関するコメント 大学教育学会誌,36(1),109-112.(CiNii Articles「FD 組織」で知る)
- 山内尚子(2014).FDにおける「学習する組織」を推進する高等教育開発者(FD担当者)の役割 大学教育学会誌,36(1),104-108.(CiNii Articles「FD 組織」で知る)
- 井上史子(2014).組織的FD活動と「学習する組織」の構築 大学教育学会誌,36(1),100-103.(CiNii Articles「FD 組織」で知る)
- 雨宮史卓・大嶽龍一・後藤裕哉・辻忠博(2014).クラスター分析を用いたFD等教育開発推進に関する意識と組織の実態:全国国公私立230大学を対象としたアンケート調査結果に基づいて(第1報) 日本大学FD研究,2,31-47.[PDF](CiNii Articles「FD 組織」で知る)
- 田口真奈・半澤礼之・杉原真晃・村上正行(2012).若手FD担当者の業務に対する「やりがい」と「不安」:他部局との連携とキャリア展望の観点から 日本教育工学会論文誌,36(3),327-337.[PDF](CiNii Articles「FD 組織」で知る)
- 村上正行・山田政寛(2012).大学教育・FDに関する研究における教育工学の役割 日本教育工学会論文誌,36(3),181-192.[PDF](CiNii Articles「FD 組織」で知る)
- 岡部光明(2012).ファカルティ・ディベロップメント(FD)の理念と実践的提案 国際学研究,41,97-108.[PDF](CiNii Articles「FD 組織」で知る)
- 井上史子・土持ゲーリー法一・沖裕貴(2012).組織的な知識創造を目指したFDの検討 教育情報研究:日本教育情報学会学会誌,27(3),45-53.[PDF](CiNii Articles「FD 組織」で知る)
- 井上史子・土持ゲーリー法一・沖裕貴(2011).選択コースを取り入れたFDプログラムの開発:実践的FDプログラムの活用 年会論文集,27,186-189.[PDF](CiNii Articles「FD 組織」で知る)
- 小川勤・岩部浩三・岡田耕一(2011).成績分布共有システムを活用した組織的なFD活動の推進についての研究 年会論文集,27,66-69.[PDF](CiNii Articles「FD 組織」で知る)
- 山内尚子(2011).学習する大学の構築に向けて:山形大学の取組にみる実質的、組織的FD、SDのあり方 高等教育フォーラム,1,19-30.[PDF](CiNii Articles「FD 組織」で知る)
- 山田剛史(2010).大学教育センターからみたFD組織化の動向と課題 国立教育政策研究所紀要,139,21-35.[PDF](CiNii Articles「FD 組織」で知る)(授業アンケートについて「実際に出てくる意見としても授業評価アンケートの回収率が低いので何とかして欲しい、といったそれ自体問題でないわけではないが、そのようなテクニカルな話に終始しがち」)
- 井上史子・沖裕貴・林徳治(2009).実践的FDプログラムの開発:新任教員対象実践的FDプログラムモデルの提案 教育情報研究:日本教育情報学会学会誌(増刊),127-128.[PDF](CiNii Articles「FD 組織」で知る)
- 佐藤浩章(2009).組織的FDをどう進めるか? 教育情報研究:日本教育情報学会学会誌(増刊),43-47.[PDF](CiNii Articles「FD 組織」で知る)
[2015.02.17]IRなどについての文献メモ 文献一覧を更新
[2015.02.16]IRなどについての文献メモ 文献一覧を更新
- 土橋慶章・浅野茂(2015).評価・IR業務で収集した情報の効果的活用に係る一考察:神戸大学におけるデータ資料集の作成を通じて 大学評価とIR,1,5-14.[PDF]
- 末次剛健志(2015).佐賀大学におけるIRの展開:事務担当者の視点から 大学評価とIR,1,15-18.[PDF]
- 藤原宏司(2015).米国におけるIR履修証明プログラムについての一考察 大学評価とIR,1,19-30.[PDF]
- 嶌田敏行(2015).ファクトブック作成に向けた大学概要の活用について 大学評価とIR,1,31-38.[PDF]
- 藤原宏司・大野賢一(2015).全学統合型データベースの必要性を考える 大学評価とIR,1,39-47.[PDF](IR室の定義:「IR業務を(全学規模で)より効果的、効率的に行う部署」)
- 本田寛輔・浅野茂・嶌田敏行(2014).米国のインスティテューショナル・リサーチ(IR)業務の実態を整理する:説明責任、改善支援、通常業務、臨時業務の観点から 大学評価・学位研究,16,63-81.[PDF](ブログ「松宮慎治の憂鬱」(松宮慎治さん)の記事「読了した文献(4)」で知る)
- 佛淵孝夫(2015).大学版IRの導入と活用の実際 実業之日本社(実業之日本社サイトの記事「大学版IRの導入と活用の実際」で知る)
[2015.02.13]IRなどについての文献メモ 文献一覧を更新
- 夏目達也(2012).大学教育改革における大学執行部のリーダーシップの形成と発揮:国立大学副学長を中心に 名古屋高等教育研究,12,5-24.[PDF](CiNii Ariticles「特集 大学教育改革のためのリーダーシップの形成」で知る)
- 大塚雄作・夏目達也(2012).教育担当副学長のリーダーシップに関する調査の基礎的分析:国立大学教育担当副学長質問紙調査から 名古屋高等教育研究,12,25-51.[PDF](CiNii Ariticles「特集 大学教育改革のためのリーダーシップの形成」で知る)
- 島田次郎(2004).私立大学の「総長」制度について:中央大学における総長制の意義 中央大学経済研究所(大学執行部を直接に扱った数少ない研究、私立大学の総長制を対象としている;夏目達也(2012)「学教育改革における大学執行部のリーダーシップの形成と発揮」で知る)
- 島田次郎(2007).日本の大学総長制 中央大学出版部(大学執行部を直接に扱った数少ない研究、私立大学の総長制を対象としている;夏目達也(2012)「学教育改革における大学執行部のリーダーシップの形成と発揮」で知る)
- 吉武博通(2010).スタッフ・ディベロップメント(SD)の体系化と実践 カレッジマネジメント,161,50-53.[PDF](職員に求められる能力を高めるための望ましい研修のあり方;両角・小方(2011)「大学の経営と事務組織」で知る)
- 金子元久(2012).大学経営:課題・組織・人材 RIHE,118,1-18.[PDF]
- 両角亜希子(2012).大学経営人材としての職員の役割 RIHE,118,49-64.[PDF]
- 東京大学大学院教育学研究科大学経営・政策研究センター(2010).大学教育の現状と将来:全国大学教員調査[PDF](両角亜希子(2012)「大学経営人材としての職員の役割」で知る)
- 劉文君(2014).日本におけるIRの現状:全国大学アンケート調査から 東京大学 大学におけるIR(インスティテューショナル・リサーチ)の現状と在り方に関する調査研究(平成24-25年度文部科学省大学改革推進委託事業) pp.40-50.(IR組織の担当業務を尋ねた設問(複数回答可)で最も高い割合を占めているのは、国公私立全てにおいて「執行部への情報・分析の提供」(国公私立全体で65.6%))[PDF]
- 両角道代 (2012). 共同研究「市場原理と法」2011年度活動報告 明治学院大学法律科学研究所年報,28,261-270.[PDF](Google Scholar「市場原理とは」で知る)
- 大場淳(2008).大学職員の専門職化の国際的動向 大場淳(研究代表者)競争的環境下の大学における職員の専門職化に関する国際比較研究(科学研究費補助金最終報告書),3-10.(世界の高等教育制度において質保証の枠組みが発達する中で教員であることが多い管理運営責任者に学術的卓越性以上の能力が求められるようになった)[PDF]
- 山田礼子(2014).日本における質保証システムの構築としてのIRコンソーシアム 東京大学 大学におけるIR(インスティテューショナル・リサーチ)の現状と在り方に関する調査研究(平成24-25年度文部科学省大学改革推進委託事業) pp.93-101.(質保証を推進させるためにはIRを行うことが有効)[PDF]
- 里見朋香(2009).動く職員組織をつくる 京都大学高等教育研究,15,89-97.[PDF](人事異動による新しい後任者に対しては、円滑に業務の引き継ぎを行う必要がある)
- 佐竹秀雄(2006).文章を書く技術 ベレ出版(Google「"報告に必要な" ステップ」で知る)
[2015.02.13]IRなどについての文献メモ 文献一覧を更新
- 本田由紀(2009).教育の職業的意義:若者、学校、社会をつなぐ 筑摩書房(濱口(2013)『若者と労働』で知る)
[2015.02.13]IRなどについての文献メモ 文献一覧を更新
- 伊藤真(2010).伊藤真の法学入門:講義再現版 日本評論社(Amazon.co.jp「法学 入門」で知る)
[2015.02.12]IRなどについての文献メモ 文献一覧を更新
- 大学基準協会(編)(2009).内部質保証システムの構築:国内外大学の内部質保証システムの実態調査 大学基準協会(Google「内部質保証」で知る)
[2015.02.12]IRなどについての文献メモ 文献一覧を更新
- 山本眞一(2005).大学職員を巡る研究動向 大場淳(研究代表者)大学の戦略的経営のための職員の活用及び職能開発に関する研究(科学研究費助成事業(科学研究費補助金)研究成果報告書) pp.24-31.[PDF]
- 山本眞一(1998).大学の管理運営と事務職員:管理運営論への新たな視点 高等教育研究,1,163-179.(山本眞一(2005)「大学職員を巡る研究動向で知る」)
- 大場淳(2009).日本における大学職員専門職化 RIHE,105,13-23.[PDF]
- 大場淳(2007).大学の教員外職員 COE研究シリーズ,30,1-24.[PDF](大場淳(2009)「日本における大学職員専門職化」で知る)
[2015.02.12]IRなどについての文献メモ 文献一覧を更新
- 市川昭午(1983).教育サービスと行財政 ぎょうせい
- 市川昭午(2000).高等教育の変貌と財政 玉川大学出版部(Google「"教育サービスと行財政"」で知る)
- 近藤博之(1984).市川昭午著, 『教育サービスと行財政』, A5判, 364頁, 2500円, ぎょうせい 教育社会学研究,39,237-240.[PDF](Google「"教育サービスと行財政"」で知る)
[2015.02.09]IRなどについての文献メモ 文献一覧を更新
- 大場淳(2009).日本における高等教育の市場化 教育學研究,76(2),185-196.[PDF](Google「高等教育 市場化」で知る)
- 天野郁夫(2004).大学改革:秩序の崩壊と再編 東京大学出版会(高等教育の「市場化」=高等教育制度全般に市場原理を取り入れる;大場(2009)「日本における高等教育の市場化」で知る)
- 米澤彰純(2005).大学「評価」をめぐる日本の文脈 秦由美子(編著)新時代を切り拓く大学評価:日本とイギリス 東信堂 pp.105-126(日本で質保証が本格的に議論されるようになるのは21世紀に入ってから;大場(2009)「日本における高等教育の市場化」で知る)
- 福島一政(2007).大学職員のキャリアパスを考える:上 教育学術新聞,2263.[HTML]
- 福島一政(2007).大学職員のキャリアパスを考える:下 教育学術新聞,2264.[HTML]
[2015.02.06]IRなどについての文献メモ 文献一覧を更新
- 濱口桂一郎(2009).新しい労働社会:雇用システムの再構築へ 岩波書店(京都光華女子大学図書館蔵書検索「濱口桂一郎」で知る)
- 濱口桂一郎(2014).日本の雇用と中高年 筑摩書房(Amazon.co.jp「濱口桂一郎」で知る)
- 濱口桂一郎(2013).若者と労働:「入社」の仕組みから解きほぐす 中央公論新社(Amazon.co.jp「濱口桂一郎」で知る)
[2015.02.06]IRなどについての文献メモ 文献一覧を更新
- 橋本智也(2015).データの蓄積と組織的な活用(IR)による教育の質保証:学生の学修時間と成績・意欲の関係を検証する 情報処理学会研究報告 教育学習支援情報システム研究会報告,2015-CLE-15(1) pp.1-5.[PDF]
[2015.02.06]ホーム「お知らせ」欄を変更
- ポスター発表「IRの継続性を担保する仕組み:学内データの情報を文書化する「京都光華IR辞書」」(大学教育改革フォーラムin東海2015)を掲載
[2015.02.03]IRなどについての文献メモ 文献一覧を更新
- Clague, P. (2014). Why trade students withdraw from their courses: students' perspectives. An unpublished dissertation submitted in partial fulfilment of the requirements of the degree of Master of Education, Unitec Institute of Technology. [PDF](Google Scholar「withdraw retention」で知る)
[2015.02.03]IRなどについての文献メモ 文献一覧を更新
- 大場淳(研究代表者)(2008).競争的環境下の大学における職員の専門職化に関する国際比較研究(科学研究費補助金最終報告書)[PDF]
- 大場淳(2006).大学職員の過去・現在・未来 全大教時報,3(30),1-28.(大場(2008)『競争的環境下の大学における職員の専門職化に関する国際比較研究』で知る)[PDF]
- 大場淳(2005).欧州における学生の大学運営参加 大学行政管理学会誌,9,39-49.(大場(2008)『競争的環境下の大学における職員の専門職化に関する国際比較研究』で知る)
- 大場淳(2007).SD制度化の現状と課題 COE研究シリーズ,26,231-251.(大場(2008)『競争的環境下の大学における職員の専門職化に関する国際比較研究』で知る)[PDF]
- 大場淳(2008).欧州における学生参加:高等教育質保証への参加を中心に 大学と学生,50,7-13.(大場(2008)『競争的環境下の大学における職員の専門職化に関する国際比較研究』で知る)
- 小貫有紀子(2005).米国大学における学習支援職員の発展についての研究:ユニバーサル段階における職務の専門職分化 大学行政管理学会誌,9,23-28.(大場(2008)『競争的環境下の大学における職員の専門職化に関する国際比較研究』で知る)
- 小貫有紀子(2010).米国高等教育における学生担当職員の専門職能開発(PD)の体系化 高等教育研究,13,81-100.(CiNii Articles「小貫有紀子」で知る)
- 小貫有紀子(2009).学生支援の組織と業務の役割分担に関する一考察 RIHE,105,24-36.(CiNii Articles「小貫有紀子」で知る)[PDF]
- 小貫有紀子(2008).海外事例 米国学生支援における学生担当職の専門性と専門職団体 大学と学生,49,54-61.(CiNii Articles「小貫有紀子」で知る)
- 小貫有紀子(2007).大学職員の流動及び意思決定への参画に関する一考察:アンケート調査の結果から COE研究シリーズ,30,63-84.(CiNii Articles「小貫有紀子」で知る)
- 小貫有紀子(2007).米国高等教育における学生支援の概念モデルと学生担当職の役割に関する一考察 大学行政管理学会誌,11,31-38.(CiNii Articles「小貫有紀子」で知る)
- 大場淳(2007).SD制度化と質的保証 広島大学高等教育研究開発センター(編)21世紀型COEプログラム(平成14年度採択)研究教育拠点「21世紀型高等教育システム構築と質的保証」-COE最終報告書-第1部(下) 広島大学高等教育研究開発センター pp.31-45.[PDF](大場(2008)『競争的環境下の大学における職員の専門職化に関する国際比較研究』で知る)
- 大場淳(研究代表者)(2005).大学の戦略的経営のための職員の活用及び職能開発に関する研究(科学研究費助成事業(科学研究費補助金)研究成果報告書)(大場(2008)『競争的環境下の大学における職員の専門職化に関する国際比較研究』で知る)[PDF]
- 大場淳・山野井敦徳(編)(2003).大学職員研究序論 広島大学高等教育研究開発センター(大場(2005)『大学の戦略的経営のための職員の活用及び職能開発に関する研究』で知る)
- 大場淳(編)(2004).諸外国の大学職員 米国・英国編 広島大学高等教育研究開発センター(大場(2005)『大学の戦略的経営のための職員の活用及び職能開発に関する研究』で知る)
- 大場淳(2005).大学職員論 有本章・羽田貴史・山野井敦徳(編著)高等教育概論:大学の基礎を学ぶ ミネルヴァ書房 pp.92-115.(大場(2005)『大学の戦略的経営のための職員の活用及び職能開発に関する研究』で知る)
- 大場淳(2005).大学職員のキャリア形成 有本章・羽田貴史・山野井敦徳(編著)高等教育概論:大学の基礎を学ぶ ミネルヴァ書房 pp.248-253.(大場(2005)『大学の戦略的経営のための職員の活用及び職能開発に関する研究』で知る)
- 大場淳(編)(2005).諸外国の大学職員 フランス・ドイツ・中国・韓国編 広島大学高等教育研究開発センター(大場(2005)『大学の戦略的経営のための職員の活用及び職能開発に関する研究』で知る)
- 山崎慎一・林透(2014).ジョブディスクリプション分析によるアメリカの大学管理職に求められる知識・能力・経験の探索 大学アドミニストレーション研究,4,11-20.(CiNii Articles「大学職員」で知る)
- 山本眞一(2014).大学職員の役割に関する一考察:役員・教員・職員の意識の差を超えて 大学アドミニストレーション研究,4,1-9.(CiNii Articles「大学職員」で知る)
- 小田隆治(2014).大学間連携SD活動を通してみる教職員の職能開発へ向けた課題:書評(評者:澤登秀雄氏)へのリプライにかえて 大学職員論叢,2,119-125.(CiNii Articles「大学職員」で知る)
- 絹川正吉(2014).書評 清水亮・橋本勝編著『学生・職員と創る大学教育大学を変えるFDとSDの新発想』 大学職員論叢,2,111-117.(CiNii Articles「大学職員」で知る)
- 藤原将人(2014).書評 上杉道世著『大学職員は成長する:進化する大学 新段階のSD』大学職員論叢,2,105-109.(CiNii Articles「大学職員」で知る)
- 篠田道夫(2014).書評 山本眞一著『[新版]大学事務職員のための高等教育システム論:より良い大学経営専門職となるために』 大学職員論叢,2,99-103.(CiNii Articles「大学職員」で知る)
- 清水朗(2014).入試選抜への統計的手法活用の一考察:回帰直線による歩留り率予測 大学職員論叢,2,79-88.(CiNii Articles「大学職員」で知る)
- 高田英一・森雅生・桑野典子(2014).IR担当職員におけるIRの機能・人に関する意識の現状:国立大字職員に対するアンケート調査の結果を踏まえて 大学職員論叢,2,57-68.(CiNii Articles「大学職員」で知る)
- 江島広二・近藤倫明(2014).教学改革の推進と教職協働のあり方に関する考察:公立大学法人北九州市立大学の事例をとおして 大学職員論叢,2,47-55.(CiNii Articles「大学職員」で知る)
- 叶林(2014).中国における大学職員の動向 大学職員論叢,2,35-43.(CiNii Articles「大学職員」で知る)
- 大場淳(2014).フランスにおける大学職員:大学の自律性拡大と公務員制度の狭間で 大学職員論叢,2,25-34.(CiNii Articles「大学職員」で知る)
- 隅田英子(2014).英国の大学における大学職員の動向:グローバル競争激化時代の中での変容に関する一考察 大学職員論叢,2,13-24.(CiNii Articles「大学職員」で知る)
- 高野篤子(2014).アメリカにおける大学職員と職能開発の動向 大学職員論叢,2,5-12.(CiNii Articles「大学職員」で知る)
- 渡邉聡(2013).アメリカの大学職員とキャリアパス:さまざまな事例をもとに RIHE,123,89-99.[PDF](CiNii Articles「大学職員」で知る)
- 林透(2013).大学職員におけるロールモデルと専門性に関する一考察:国立大学法人を中心にして 大学職員論叢,1,69-77.(CiNii Articles「大学職員」で知る)
- 秦敬治(2013).大学職員論とは何か 大学職員の専門性と人事異動に関する考察 大学職員論叢,1,25-33.(CiNii Articles「大学職員」で知る)
- 羽田貴史(2013).大学職員論の課題 大学職員論叢,1,15-23.(CiNii Articles「大学職員」で知る)
- 山本眞一(2013).大学職員論のこれまでとこれから 大学職員論叢,1,5-13.(CiNii Articles「大学職員」で知る)
- 加藤毅(2013).大学院における大学職員養成プログラムの可能性 大学研究,39,19-29.[PDF](CiNii Articles「大学職員」で知る)
- 齋藤芳子(2013).大学における研究アドミニストレーション職の専門性と能力開発 名古屋高等教育研究,13,37-51.[PDF](CiNii Articles「大学職員」で知る)
- 夏目達也(2013).大学職員の主体性を尊重した職務遂行能力の形成:国立大学を中心に 名古屋高等教育研究,13,5-24.[PDF](CiNii Articles「大学職員」で知る)
- 小日向允(2013).大学職員は「経営管理」の専門家をめざせ 私学経営,455,17-23.(CiNii Articles「大学職員」で知る)
- 久志敦男・宮澤文玄(2013).諸外国における大学職員のキャリア開発とジョブローテーションに関する一考察 大学行政管理学会誌,17,45-53.(CiNii Articles「大学職員」で知る)
- 小室昌志(2012).私立大学職員の人事制度に関する一考察:評価制度を中心に 評論・社会科学,103,61-87.[PDF](CiNii Articles「大学職員」で知る)
- 伊藤彰浩(2010).高等教育研究としてのSD論:特集の趣旨をめぐって 高等教育研究,13,101-112.(ブログ「松宮慎治の憂鬱」(松宮慎治さん)の記事「読了した文献(1)」で知る)
- 寺崎昌男(2010).大学職員の能力開発(SD)への試論:プログラム化・カリキュラム編成の前提のために 高等教育研究,13,7-21.(ブログ「松宮慎治の憂鬱」(松宮慎治さん)の記事「読了した文献(1)」で知る)
- 大江淳良(2005).大学職員の能力開発の視点 現代の高等教育,469,5-11.(CiNii Articles「大学職員の能力開発」で知る)
- 金子元久(2005).大学のスタッフディベロップメント:必要性と可能性 現代の高等教育,469,11-17.(CiNii Articles「大学職員の能力開発」で知る)
- 山本眞一(2005).大学職員の高度化の必要性 現代の高等教育,469,18-22.(CiNii Articles「大学職員の能力開発」で知る)
- 南学(2005).公立大学(法人)職員への期待 現代の高等教育,469,22-27.(CiNii Articles「大学職員の能力開発」で知る)
- 本間政雄(2005).国立大学法人職員への期待 現代の高等教育,469,27-31.(CiNii Articles「大学職員の能力開発」で知る)
- 天野郁夫(2005).国立大学財務・経営センターの研修事業 現代の高等教育,469,32-36.(CiNii Articles「大学職員の能力開発」で知る)
- 椿弘次(2005).日本私立大学連盟の職員研修事業:大学間競争をこえて 現代の高等教育,469,36-40.(CiNii Articles「大学職員の能力開発」で知る)
- 瀧澤博三(2005).私立大学職員に期待されること 現代の高等教育,469,40-44.(CiNii Articles「大学職員の能力開発」で知る)
- 原邦夫(2005).大学行政管理学会の役割について 現代の高等教育,469,44-49.(CiNii Articles「大学職員の能力開発」で知る)
- 井原徹(2005).職員組織改革の視点:早稲田大学での経験をふまえて 現代の高等教育,469,49-54.(CiNii Articles「大学職員の能力開発」で知る)
- 篠田道夫(2005).日本福祉大学事務局改革の歩みと挑戦:『大学職員論』での提起とその背景 現代の高等教育,469,54-59.(CiNii Articles「大学職員の能力開発」で知る)
- 武村秀雄(2005).大学院の職員能力開発プログラム:桜美林大学の専攻例 現代の高等教育,469,59-64.(CiNii Articles「大学職員の能力開発」で知る)
- 羽田貴史(2010).高等教育研究と大学職員論の課題 高等教育研究,13,23-42.(ブログ「松宮慎治の憂鬱」(松宮慎治さん)の記事「読了した文献(1)」で知る)
- 福島一政(2010).大学のユニバーサル化とSD:大学職員の視点から 高等教育研究,13,43-60.(CiNii Articles「特集 スタッフ・ディベロップメント」で知る)
- 加藤毅(2010).スタッフ・ディベロップメント論のイノベーション 高等教育研究,13,61-79.(CiNii Articles「特集 スタッフ・ディベロップメント」で知る)
- 絹川正吉(2013).書評日本高等教育学会編『高等教育研究第13集特集スタッフ・ディベロップメント』 大学職員論叢,1,117-122.(CiNii Articles「特集 スタッフ・ディベロップメント」で知る)
- 山本眞一(2008).これからの大学職員 IDE,499,11-15.(ブログ「松宮慎治の憂鬱」(松宮慎治さん)の記事「読了した文献(1)」で知る)
- 山本眞一(2008).これからの大学職員:大学改革の中での新たな役割を考える 広島大学技術センター報告集,5,3-8.(CiNii Articles「これからの大学職員」で知る)
- 金子元久(2008).大学職員の展望 IDE,499,4-10.(CiNii Articles「これからの大学職員」で知る)
- 清成忠男(2008).私学経営と職員 IDE,499,15-20.(CiNii Articles「これからの大学職員」で知る)
- 上杉道世(2008).トータルプランで職員を変える IDE,499,20-25.(CiNii Articles「これからの大学職員」で知る)
- 本間政雄(2008).マネジメントの課題と新たな職員像 IDE,499,25-30.(CiNii Articles「これからの大学職員」で知る)
- 藤田幸男(2008).職員の育成:私大連の試み IDE,499,31-35.(CiNii Articles「これからの大学職員」で知る)
- 村田直樹(2008).横浜国大職員塾の試み IDE,499,36-40.(CiNii Articles「これからの大学職員」で知る)
- 里見朋香(2008).「体験的」大学職員論 IDE,499,40-43.(CiNii Articles「これからの大学職員」で知る)
- 横田利久(2008).大学行政管理学会と職員 IDE,499,44-49.(CiNii Articles「これからの大学職員」で知る)
- 篠田道夫(2008).私立大学の職員像 IDE,499,49-55.(CiNii Articles「これからの大学職員」で知る)
- 久保公人(2008).大学の人事政策 IDE,499,55-60.(CiNii Articles「これからの大学職員」で知る)
- 舘昭(2008).大学職員論 IDE,499,60-66.(CiNii Articles「これからの大学職員」で知る)
- 山岸直司(2008).データに見る大学職員 IDE,499,66-69.(CiNii Articles「これからの大学職員」で知る)
- 本間政雄(2008).これからの大学職員とは 大学時報,57(320),60-65.(CiNii Articles「これからの大学職員」で知る)
- 小澤芳明(2013).専門職員について考える:研究推進・支援職員としての経験に基づいて 大学マネジメント,9(1),2-11.(CiNii Articles「これからの大学職員」で知る)
- 永和田隆一(2013).私立大学における財務部職員の専門性とその役割 大学マネジメント,9(1),12-17.(CiNii Articles「これからの大学職員」で知る)
- 梅澤貴典(2013).高度情報化社会における大学図書館の役割と、職員の専門スキル向上策:FD・SD・大学経営・政策の視点からの改善案 大学マネジメント,9(1),18-25.(CiNii Articles「これからの大学職員」で知る)
- 佐間野有希子(2013).高等教育と大学職員コンピテンスの国際化:異文化コンピテンス発達モデルから学ぶSD開発へのヒント 大学マネジメント,9(1),26-31.(CiNii Articles「これからの大学職員」で知る)
- 福留(宮村)留理子(2004).大学職員の役割と能力形成:私立大学職員調査を手がかりとして 高等教育研究,7,157-176.(ブログ「松宮慎治の憂鬱」(松宮慎治さん)の記事「読了した文献(1)」で知る)
- 大場淳(2009).大学職員の専門職化の国際的動向 RIHE,105,1-12.(ブログ「松宮慎治の憂鬱」(松宮慎治さん)の記事「読了した文献(1)」で知る)[PDF]
- 中井俊樹(2014).教学マネジメントにおける大学職員の役割 高等教育研究,17,95-112.(ブログ「松宮慎治の憂鬱」(松宮慎治さん)の記事「読了した文献(2)」で知る)
- 井原徹(2001).巻頭言:「職員の役割論」に終焉を 大学行政管理学会誌,5,1-3.(ブログ「松宮慎治の憂鬱」(松宮慎治さん)の記事「読了した文献(2)」で知る)
- 加藤好郎(2001).専門職としての大学職員の必要性 大学行政管理学会誌,5,73-77.(ブログ「松宮慎治の憂鬱」(松宮慎治さん)の記事「読了した文献(2)」で知る)
- 水谷早人(2001).ワークショップ 大学職員のプロフェッショナル・スクールをデザインする 大学行政管理学会誌,5,87-91.(ブログ「松宮慎治の憂鬱」(松宮慎治さん)の記事「読了した文献(2)」で知る)
- 正木卓・水谷早人・塩原将行・南学・山崎敬夫・矢代誠・芦沢真五・孫福弘・上田千尋(2000).プロジェクト報告 大学行政専門職養成修士課程カリキュラムの展望について 大学行政管理学会誌,4,49-61.(ブログ「松宮慎治の憂鬱」(松宮慎治さん)の記事「読了した文献(2)」で知る)
- 福島一政(1997).大学職員改革論:大学は職員をどう位置づけるべきか 大学行政管理学会誌,1,37-42.(ブログ「松宮慎治の憂鬱」(松宮慎治さん)の記事「読了した文献(2)」で知る)
- 星野晶成(2012).国際交流担当職員の職能開発への自己点検とその一考察:教員・学生・職員の3者協働から生ずるSDの可能性 大学行政管理学会誌,16,85-94.(ブログ「松宮慎治の憂鬱」(松宮慎治さん)の記事「読了した文献(2)」で知る)
- 坪井啓太・伊藤博美(2009).職員による学生個別の履修指導--教職協働を観点とした提案 大学行政管理学会誌,13,195-202.(ブログ「松宮慎治の憂鬱」(松宮慎治さん)の記事「読了した文献(2)」で知る)
- 上西浩司・中井俊樹・齋藤芳子(2008).教務部門が求める教務担当職員像:教務部門事務責任者への全国調査結果 大学行政管理学会誌,12,179-186.(ブログ「松宮慎治の憂鬱」(松宮慎治さん)の記事「読了した文献(2)」で知る)
- 林一夫(2007).eラーニングなど教育におけるIT利用に関する教務系職員への期待 大学行政管理学会誌,11,47-53.(ブログ「松宮慎治の憂鬱」(松宮慎治さん)の記事「読了した文献(2)」で知る)
- 池田輝政・井原徹・本間政雄・吉武博通・吉田信正(2006).大学職員のアドミニストレーター養成における展望と課題 大学行政管理学会誌,10,23-45.(ブログ「松宮慎治の憂鬱」(松宮慎治さん)の記事「読了した文献(2)」で知る)
- 上田理子(2006).大学職員の人材育成と求められる知識・技能・能力への一考察 大学行政管理学会誌,10,199-204.(ブログ「松宮慎治の憂鬱」(松宮慎治さん)の記事「読了した文献(2)」で知る)
- 秦敬治(2006).大学職員の専門性を規定する要因に関する考察 大学行政管理学会誌,10,205-211.(ブログ「松宮慎治の憂鬱」(松宮慎治さん)の記事「読了した文献(2)」で知る)
- 武村秀雄(2003).大学アドミニストレーター養成の試み:桜美林大学の例:大学職員のためのMBA 大学教育学会誌,25(2),126-131.(ブログ「松宮慎治の憂鬱」(松宮慎治さん)の記事「読了した文献(2)」で知る)
- 林一夫(2006).事例研究 大学職員の今後のあり方・役割,取得すべき能力や知識技術:教務系職員を中心として 大学教育学会誌,28(2),101-107.(ブログ「松宮慎治の憂鬱」(松宮慎治さん)の記事「読了した文献(2)」で知る)
- 西田邦昭(2005).教学改革とマネジメントスタッフの役割:組織改革と人材育成 大学教育学会誌,27(1),40-45.(ブログ「松宮慎治の憂鬱」(松宮慎治さん)の記事「読了した文献(2)」で知る)
- 山本眞一(2005).大学の機能変化と職員の役割:教学支援と大学改革 大学教育学会誌,27(1),52-55.(ブログ「松宮慎治の憂鬱」(松宮慎治さん)の記事「読了した文献(2)」で知る)
- 関根秀和(2005).教学支援と大学改革:プロフェッショナル・ディベロップメントについて:指定討論者の視点から 大学教育学会誌,27(1),56-58.(ブログ「松宮慎治の憂鬱」(松宮慎治さん)の記事「読了した文献(2)」で知る)
- 大場淳(2014).大学職員論・教職協働論から見たカリキュラム・マネジメント実践 大学教育学会誌,36(1),53-58.(ブログ「松宮慎治の憂鬱」(松宮慎治さん)の記事「読了した文献(2)」で知る)
- 佐々木一也(2014).課題研究のまとめと教職協働によるカリキュラム・マネジメントの諸条件大学教育学会誌,36(1),48-52 .(ブログ「松宮慎治の憂鬱」(松宮慎治さん)の記事「読了した文献(2)」で知る)
- 佐々木一也(2013).職員から見た教養教育カリキュラム・マネジメント:作成・維持・検証 大学教育学会誌,35(2),53-56.(ブログ「松宮慎治の憂鬱」(松宮慎治さん)の記事「読了した文献(2)」で知る)
- 佐々木一也(2012).カリキュラム・マネジメントにおける教職協働 大学教育学会誌,34(2),116-119.(ブログ「松宮慎治の憂鬱」(松宮慎治さん)の記事「読了した文献(2)」で知る)
- 今田晶子(2011).教員と職員の協働の在り方と、大学における新たな業務:課題研究「SDの新たな地平:『大学人』能力開発に向けて」学会アンケート調査から 大学教育学会誌,33(1),61-65.(ブログ「松宮慎治の憂鬱」(松宮慎治さん)の記事「読了した文献(2)」で知る)
- 秦敬治(2011).カリキュラムに関する職員の関与とその可能性:「SDの新たな地平」学会アンケート調査から 大学教育学会誌,33(1),58-60.(ブログ「松宮慎治の憂鬱」(松宮慎治さん)の記事「読了した文献(2)」で知る)
- 清水栄子(2011).「SDの新たな地平:『大学人』能力開発に向けて」アンケート結果の概要について 大学教育学会誌,33(1),53-57.(ブログ「松宮慎治の憂鬱」(松宮慎治さん)の記事「読了した文献(2)」で知る)
- 佐々木一也(2009).教員が求める職員像:自律的に活動する大学を目指して 大学教育学会誌,31(2),75-78.(ブログ「松宮慎治の憂鬱」(松宮慎治さん)の記事「読了した文献(2)」で知る)
- 佐々木一也(2010).SDの新たな地平:「大学人」能力開発へ向けて:これまでの歩み 大学教育学会誌,32(1),67-71.(ブログ「松宮慎治の憂鬱」(松宮慎治さん)の記事「読了した文献(2)」で知る)
- 本郷優紀子(2008).学生の学びの支援と職員の教育参加 大学教育学会誌,30(2),39-43.(ブログ「松宮慎治の憂鬱」(松宮慎治さん)の記事「読了した文献(2)」で知る)
[2015.01.31]「過去の「お知らせ」」に追加
- 口頭発表「データの蓄積と組織的な活用(IR)による教育の質保証:学生の学修時間と成績・意欲の関係を検証する」(情報処理学会第15回教育学習支援研究発表会)
[2015.01.26]IRなどについての文献メモ 内容をアップ
- グローバルタスクフォース(2004).ポーター教授『競争の戦略』入門:ビジネスバイブル 総合法令出版[概要]京都光華女子大学図書館書架で知る)[詳細をローカルPCに保存]
[2015.01.23]IRなどについての文献メモ 文献一覧を更新
- 橋本智也(2015).IR実務担当者のための事例解説:質を伴った学修時間の増加・確保に向けた調査分析手法・実施体制 平成26年度第1回IR実務担当者連絡会
[2015.01.20]「過去の「お知らせ」」に追加
- 口頭発表「IR実務担当者のための事例解説:質を伴った学修時間の増加・確保に向けた調査分析手法・実施体制」(平成26年度第1回IR実務担当者連絡会)
[2015.01.16]ホーム「お知らせ」欄を変更
- ポスター発表"Bridging faculties' expectation and students' actual studying hours"(2015 AIR Forum)を掲載
[2015.01.15]IRなどについての文献メモ 文献一覧を更新
- 大膳司・有本章・黄福涛(2007).日本におけるFD活動の実態と今後の課題:時系列比較の結果から COE研究シリーズ,26,205-229.[PDF]
[2015.01.10]ホーム「お知らせ」欄を変更
- 口頭発表「IR実務担当者のための事例解説:質を伴った学修時間の増加・確保に向けた調査分析手法・実施体制」(平成26年度第1回IR実務担当者連絡会)を掲載
[2015.01.09]IRなどについての文献メモ 文献一覧を更新
- コトラー,K.&フォックス,F.A.水口健次(監訳)・柳澤健(訳)(1989).学校のマーケティング戦略 蒼林社出版(大坪檀(2009)「大学マーケティング(最終回)」で知る)
[2015.01.05]IRなどについての文献メモ 文献一覧を更新
- 大森不二雄(2012).大学教育と学修時間:中教審答申を批判的に読み解く アルカディア学報,494.[HTML](Google「質的転換答申 学修時間」で知る)
[2015.01.05]IRなどについての文献メモ 文献一覧を更新
[2014.12.19]ホーム「お知らせ」欄を変更
- 口頭発表「データの蓄積と組織的な活用(IR)による教育の質保証:学生の学修時間と成績・意欲の関係を検証する」(情報処理学会第15回教育学習支援研究発表会)を掲載
[2014.12.19]「過去の「お知らせ」」に追加
- 話題提供「学内でIRを進めるための3つの工夫」(IR関係者意見交換会)
[2014.12.17]大学に関わる情報メモ 内容をアップ
[2014.12.17]ホーム「お知らせ」欄を変更
- ポスター発表「『京都光華のエンロールメント』の新たな展開:学修成果の可視化とアクティブラーナーの育成のための全学的な学修支援体制の整備」(第20回FDフォーラム)を掲載
[2014.12.17]「過去の「お知らせ」」に追加
- ポスター発表「内部質保証のために学修時間の質・量を向上させる仕組み:データに基づく検証システム(IR)と組織的な改善活動の試行」(第19回情報知識学フォーラム)
[2014.12.16]IRなどについての文献メモ 文献一覧を更新
- 岡本真・森旭彦(2014).未来の図書館、はじめませんか? 青弓社[目次](『ACADEMIC RESOURCE GUIDE』No.515で知る)
[2014.12.15]IRなどについての文献メモ 文献一覧を更新
- 田尻慎太郎・白鳥成彦(2013).ビジネス系大学における学修履歴と活動データを用いた生存時間分析 日本教育社会学会大会発表要旨集録,65,120-121.[PDF](Twitter(@high190さん)で知る)
- 岡田有司・鳥居朋子・宮浦崇・青山佳世・松村初・中野正也・吉岡路(2011).大学生における学習スタイルの違いと学習成果 立命館高等教育研究,11,167-182.PDF](Google Scholar「学習時間 意欲 大学」で知る)
- 金子元久(2012).大学教育と学生の成長 名古屋高等教育研究,12,211-236.[PDF](Google Scholar「学習時間 意欲 大学」で知る)
[2014.12.15]IRなどについての文献メモ 文献一覧を更新
- 永田靖(2005).統計学のための数学入門30講 朝倉書店(西内(2014)『統計学が最強の学問である 実践編』で知る)
- 永田靖(1996).統計的方法のしくみ:正しく理解するための30の急所 日科技連出版社(西内(2014)『統計学が最強の学問である 実践編』で知る)
[2014.12.06]IRなどについての文献メモ 文献一覧を更新
- 橋本智也(2014).内部質保証のために学修時間の質・量を向上させる仕組み:データに基づく検証システム(IR)と組織的な改善活動の試行 第19回情報知識学フォーラム
[2014.12.04]IRなどについての文献メモ 内容をアップ
- 谷村英洋(2011).大学生の学習時間と学習成果 大学経営政策研究,1,71-84.[PDF][内容](Google Scholar「学習時間 学生」で知る)
[2014.12.04]IRなどについての文献メモ 文献一覧を更新
- キャンベル,C.G.&ベーカー,S.中嶋秀隆(訳)(2011).世界一わかりやすいプロジェクト・マネジメント 総合法令出版(Amazon.co.jp「プロジェクトマネジメント」で知る)
- 近藤哲生(2005).はじめてのプロジェクトマネジメント 日本経済新聞社(Amazon.co.jp「プロジェクトマネジメント」で知る)
- 白鳥美子(2014).大工の棟梁に学ぶプロジェクトマネジメント マイナビ(Amazon.co.jp「プロジェクトマネジメント」で知る)
- 能登原伸二(著)日経SYSTEMS(編)(2014).プロジェクトマネジメント現場マニュアル 日経BP社(Amazon.co.jp「プロジェクトマネジメント」で知る)
- 長尾清一(2003).先制型プロジェクト・マネジメント:なぜ、あなたのプロジェクトは失敗するのか ダイヤモンド・セールス編集企画(Amazon.co.jp「プロジェクトマネジメント」で知る)
- 冨永章(編著)日経コンピュータ(編)(2011).パーソナルプロジェクトマネジメント:PM術をONでもOFFでも徹底活用! 日経BP社(Amazon.co.jp「プロジェクトマネジメント」で知る)
- 岸良裕司(2011).最短で達成する全体最適のプロジェクトマネジメント 中経出版(Amazon.co.jp「プロジェクトマネジメント」で知る)
- Berkun, S.村上雅章(訳)(2006).アート・オブ・プロジェクトマネジメント:マイクロソフトで培われた実践手法 オライリー・ジャパン(Amazon.co.jp「プロジェクトマネジメント」で知る)
- Haugan, G. T.伊藤衡(監訳)(2005).実務で役立つWBS入門:Work breakdown structures 翔泳社(Amazon.co.jp「プロジェクトマネジメント」で知る)
- ミロセビッチ,D.PMI東京支部(監訳)(2007).プロジェクトマネジメント・ツールボックス 鹿島出版会(Amazon.co.jp「プロジェクトマネジメント」で知る)
- 岸良裕司(著)村上悟(監修)(2005).目標を突破する実践プロジェクトマネジメント:あなたのプロジェクトは必ず成功する 中経出版(Amazon.co.jp「プロジェクトマネジメント」で知る)
- 近藤哲生(2004).プロジェクトマネジメント:実用企業小説 日本経済新聞社(Amazon.co.jp「プロジェクトマネジメント」で知る)
- 峯本展夫(2007).プロジェクトマネジメント・プロフェッショナル:論理と知覚を磨く5つの極意 生産性出版(Amazon.co.jp「プロジェクトマネジメント」で知る)
- 長尾清一(2007).問題プロジェクトの火消し術:究極のプロジェクト・コントロール 日経BP社(Amazon.co.jp「プロジェクトマネジメント」で知る)
- ゴールドラット,E.M.三本木亮(訳)(2003).クリティカルチェーン:なぜ、プロジェクトは予定どおりに進まないのか? ダイヤモンド社(Amazon.co.jp「プロジェクトマネジメント」で知る)
[2014.11.25]IRなどについての文献メモ 文献一覧を更新
- 丸山文裕(1984).大学退学に対する大学環境要因の影響力の分析 教育社会学研究,39,140-153.[PDF](退学についてアメリカの先行研究レビュー、学校基本調査報告書のデータを使った日本の大学退学者の傾向分析、質問紙調査による退学に影響する環境要因の分析;Google「退学防止 事例 大学」で知る)
- 濱名篤(2013).大学中退のとらえ方:アメリカと日本を比較して 「平成25年度 学生生活にかかるリスクの把握と対応に関するセミナー 中途退学、休学、不登校の学生に対する取組」資料[PDF](Google「退学 アメリカ 経済的理由」で知る)
- 藤田長太郎(2011).メンタルヘルスケアによる中途退学防止:不登校がちな学生へのアウトリーチ型支援を実施して 大学マネジメント,7(8),13-17.(CiNii Articles「退学防止」で知る)
- 山田ゆかり(2006).大学新入生における適応感の検討 名古屋文理大学紀要,6,29-36.[PDF](意欲減退と大学生活不安の2つの側面から大学不適応感の実態を調査;川﨑他(2014)「大学における寄り添い型学生支援体制の構築」で知る)
- 森田裕司・岡本貞雄(2006).新入生対象の講義「キャンパスライフ実践論」の試み:学生生活全体のサポート 学生相談研究,26(3),185-197.(大学適応のためのプログラム実践の事例紹介;川﨑他(2014)「大学における寄り添い型学生支援体制の構築」で知る)
- 森田裕司(2004).新入生対象の講義「キャンパスライフ実践論」の試み 広島経済大学研究論集,27(3),67-72.[PDF](大学適応のためのプログラム実践の事例紹介;川﨑他(2014)「大学における寄り添い型学生支援体制の構築」で知る)
- 和田修(2011).大学キャンパスでおこなう、ひきこもり・不登校学生支援プログラム:復学までの過程 社会文化研究所紀要,68,129-146.[PDF](引きこもりや不登校経験をもつ大学生に関する支援プログラムや就労支援プログラムに関する研究;川﨑他(2014)「大学における寄り添い型学生支援体制の構築」で知る)
- 和田修(2012).大学と地域の連携でおこなう、ひきこもり・不登校学生への就労支援 教養研究,18(3),61-75.[PDF](引きこもりや不登校経験をもつ大学生に関する支援プログラムや就労支援プログラムに関する研究;川﨑他(2014)「大学における寄り添い型学生支援体制の構築」で知る)
- 桶谷文哲(2013).発達障がい学生支援における合理的配慮をめぐる現状と課題 学園の臨床研究,12,57-65.[PDF](発達障がいのある学生への大学支援に関する研究;川﨑他(2014)「大学における寄り添い型学生支援体制の構築」で知る)
- 桶谷文哲・西村優紀美(2013).発達障がいのある大学生への支援:修学支援から就職支援への展開 学園の臨床研究,12,45-52.[PDF](発達障がいのある学生への大学支援に関する研究;川﨑他(2014)「大学における寄り添い型学生支援体制の構築」で知る)
- 桶谷文哲・斎藤清二(2013).発達障がいのある大学生との個別面談:対話分析による検討 学園の臨床研究,12,67-76.[PDF](発達障がいのある学生への大学支援に関する研究;川﨑他(2014)「大学における寄り添い型学生支援体制の構築」で知る)
- 松田康子(2012).高等教育における障害学生支援と合理的配慮の検討:ひとりの障害学生への聴きとり調査を事例に 北海道大学大学院教育学研究院紀要,117,205-229.[PDF](発達障がいのある学生への大学支援に関する研究;川﨑他(2014)「大学における寄り添い型学生支援体制の構築」で知る)
- 三橋真人(2012).当事者と仲間の協働型による発達障害学生支援プロジェクト 健康科学大学紀要,8,45-63.[PDF](発達障がいのある学生への大学支援に関する研究;川﨑他(2014)「大学における寄り添い型学生支援体制の構築」で知る)
- 山崎安則・池田和彦・江玉睦美(2013).「高等教育機関における障害学生の受け入れと支援の在り方に関する特別研究」の研究成果 筑紫女学園大学・筑紫女学園大学短期大学部紀要,8,165-176.[PDF](聴覚障がい・視覚障がいのある学生への合理的配慮に基づく取組みに関する研究;川﨑他(2014)「大学における寄り添い型学生支援体制の構築」で知る)
[2014.11.20]ホーム「お知らせ」欄を変更
- ポスター発表「内部質保証のために学修時間の質・量を向上させる仕組み:データに基づく検証システム(IR)と組織的な改善活動の試行」(第19回情報知識学フォーラム)を掲載
[2014.11.18]IRなどについての文献メモ 内容をアップ
- 三好登(2013).大学生の学習成果に関する研究動向と今後の課題 大学論集,44,303-318.[PDF][概要](Google「大学生の学習時間と学習成果」で知る)
- 藤村正司(2013).大規模学生調査から学習成果と学習時間の構造を掴む:横断的・時系列的分析 大学論集,44,1-17.[PDF][概要](CiNii Articles「学習時間」で知る)(Google「大学生の学習時間と学習成果」で知る)
- 平尾智隆(2009).学習時間を決定する要因:学生生活状況調査データの分析 大学教育実践ジャーナル,7,9-16.[PDF][概要](CiNii Articles「学習時間」で知る)(谷村英洋(2011)「大学生の学習時間と学習成果」で知る)
[2014.11.17]IRなどについての文献メモ 文献一覧を更新
- 朴澤泰男(2009).一橋大学における学生の時間使用:「全国大学生調査」を用いた研究ノート 大学教育研究開発センター年報,2008,73-73-86.[PDF](Google Scholar「学習時間 学生」で知る)
- 谷村英洋(2010).大学生の学習時間と学習成果 大学経営政策研究,1,71-84.[PDF](Google Scholar「学習時間 学生」で知る)
- 三好登(2013).大学生の学習成果に関する研究動向と今後の課題 大学論集,44,303-318.[PDF][概要](Google「大学生の学習時間と学習成果」で知る)
- 三好登(2013).大学生の学習成果の規定要因に関する実証的研究:学習成果達成度タイプの観点からの検証 大学経営政策研究,4,93-105.[PDF](Cinii Articles「大学生の学習時間と学習成果」で知る)
- 藤村正司(2013).大規模学生調査から学習成果と学習時間の構造を掴む:横断的・時系列的分析 大学論集,44,1-17.[PDF][概要](CiNii Articles「学習時間」で知る)(Google「大学生の学習時間と学習成果」で知る)
- 金子元久(2009).大学教育の質的向上のメカニズム:「アウトカム志向」とその問題点 大学評価研究,8,17-29.(学生が経験している教育および学習の実態や成果を把握・分析し教育の改善をはかるためのひとつの手段として学生調査が有用;谷村英洋(2011)「大学生の学習時間と学習成果」で知る)
- 葛城浩一(2008).学習経験の量に対するカリキュラムの影響力:大学教育によって直接的に促される学習経験に着目して 広島大学大学院教育学研究科紀要 第三部 教育人間科学関連領域,57,133-140.[PDF](谷村英洋(2011)「大学生の学習時間と学習成果」で知る)
- 葛城浩一(2006).大学教育の成果としての性格・態度特性の変容 広島大学高等教育研究開発センター(編)学生からみた大学教育の質:授業評価からプログラム評価へ,55-70.[PDF](学習成果には学生のエンゲージメントである大学関連の学習時間が重要と指摘、分析には授業外学習時間のみを用いている;谷村英洋(2011)「大学生の学習時間と学習成果」で知る)
- 葛城浩一(2007).Fランク大学生の学習に対する志向性 大学教育学会誌,29(2),87-92.(大学の学習時間には高校生活の過ごし方と授業戦略が重要;谷村英洋(2011)「大学生の学習時間と学習成果」で知る)
- 平尾智隆(2009).学習時間を決定する要因:学生生活状況調査データの分析 大学教育実践ジャーナル,7,9-16.[PDF][概要](CiNii Articles「学習時間」で知る)(谷村英洋(2011)「大学生の学習時間と学習成果」で知る)
- 川澄岩雄 (2008).学習時間の確保 杏林大学研究報告 教養部門,25,21-27.(学生が学習時間を確保できない理由はカリキュラムの過負担と授業科目の配置が問題;平尾(2009)「学習時間を決定する要因」で知る)
- 野上俊一・丸野俊一(2008).学習目標や学習状態の違いに応じて大学生は学習活動をいかに調整するのか 日本教育工学会論文誌,32(1),1-11.[PDF](学習目標の違いにかかわらず学習状態の悪い項目群よりも良い項目群を多く学習する;平尾(2009)「学習時間を決定する要因」で知る)
- 矢根真二(2004).登録単位数と学習時間:成績評価へのペナルティと線型授業料の導入について 桃山学院大学総合研究所紀要,30(2),13-29.[PDF](学習時間に対する登録上限単位数の引き下げなどの制度改革の効果を理論的に検証、登録上限単位や成績評価へのペナルティ制度の導入が無条件に学習時間を上昇させるとは限らない、所定の大きさ以上のペナルティ制度や授業単位でなければ学習時間に影響を与えない;平尾(2009)「学習時間を決定する要因」で知る)
- 苅谷剛彦(2001).階層化日本と教育危機:不平等再生産から意欲格差社会 (インセンティブ・ディバイド) へ 有信堂高文社(高校生の学習時間を対象にした社会学的研究、学習時間が持つ文脈:学歴取得に向けた個人の関与の度合と費やされるエネルギー量(学習社会論の文脈)・競争のプレッシャー(受験教育批判の文脈)・学力の代理指標(学力論の文脈)、努力の指標として注目;平尾(2009)「学習時間を決定する要因」で知る)
- 小方直幸(2012).学生調査を用いた教育改善に向けた理論的フレームワークの構築 東北大学高等教育開発推進センター(編)教育・学習過程の検証と大学教育改革 東北大学出版会 pp.47-62.(藤村(2013)「大規模学生調査から学習成果と学習時間の構造を掴む」で知る)
- 谷村英洋(2009).大学生の学習時間分析:授業と学習時間の関連性 大学教育学会誌,31(1),128-135.(藤村(2013)「大規模学生調査から学習成果と学習時間の構造を掴む」で知る)
- 両角亜希子(2009).大学生の学習行動の大学間比較:授業の効果に着目して 東京大学大学院教育学研究科紀要,49,191-206.[PDF](社会科学系6大学と工学系6大学の能動的学習や授業外学習時間を比較分析;藤村(2013)「大規模学生調査から学習成果と学習時間の構造を掴む」で知る)
- 山内乾史(2004).現代大学教育論:学生・授業・実施組織 東信堂(アメリカのカレッジインパクト研究のレビュー;藤村(2013)「大規模学生調査から学習成果と学習時間の構造を掴む」で知る)
- 武内清(2008).学生文化の実態と大学教育 高等教育研究,11,7-23.(アメリカのカレッジインパクト研究のレビュー;藤村(2013)「大規模学生調査から学習成果と学習時間の構造を掴む」で知る)
- Pascarella, E. T., & Terenzini, P. T. (2005). How college affects students: A third decade of research. San Francisco: Jossey-Bass.(カレッジ・インパクト理論、「大学の効果は、キャンパスでの学術的、対人的、そして正課外の活動への個々人の努力と関与によって大きく規定される」;山田・森(2008)で知る)(アメリカのカレッジインパクト研究について2500あまりの論文をレビュー、教員中心のティーチングから学生志向のラーニングへ変化、学生の主体的な関わりなしには効果的な学習成果は得られない、大学教育は双方向的でホーリスティックな性格を持つ;藤村(2013)「大規模学生調査から学習成果と学習時間の構造を掴む」で知る)
- 土持ゲーリー法一(2006).戦後日本の高等教育改革政策:「教養教育」の構築 玉川大学出版部(京都光華女子大学図書館蔵書検索「教養教育」で知る)(単位制度と学習時間について教員によって想定授業外学習時間が異なる可能性に言及、「当然、講義の内容あるいは授業の進め方によって自学自修の『度合』は違ったはずである。それを杓子定規に一律にしたところに自学自修の精神を歪めた(p.215)」;三好登(2013)「大学生の学習成果に関する研究動向と今後の課題」で知る)
- 佐々木重雄(1957).新制度の大学教育と単位制度 大学基準協会(編)新制大学の諸問題:大学基準協会創立十年記念論文集,182-199.(単位制度と学習時間について教員によって想定授業外学習時間が異なる可能性に言及、「教室での学習と教室外での自習との時間比率をいかにとるかは、授業のやり方で変わってくるはずである。従って、授業科目ごとに担当教授が自己のやり方に照らして予測される自習時間を考慮して定めることが合理的なのではあるまいか」;三好登(2013)「大学生の学習成果に関する研究動向と今後の課題」で知る)
- Pace, R. (1990). The undergraduates: A report of their activities and progress in college in the 1980's. Los Angeles: Center for the Study of Evaluation.[PDF](授業への出席時間と授業外での学習時間の合計時間が長い学生ほど高成績、1980年代中盤に収集したデータを使用した分析、学習成果の規定要因として「努力の質」という概念を使用、学習時間はその指標の1つとして位置づけられている;谷村英洋(2011)「大学生の学習時間と学習成果」で知る)
- Brint, S., & Cantwell, A. M. (2008). Undergraduate time use and academic outcomes: Results from UCUES 2006. Berkeley: Center for Studies in Higher Education.[PDF](授業内外の合計学習時間が長い学生ほど成績がよい;谷村英洋(2011)「大学生の学習時間と学習成果」で知る)
- 西垣順子(2008).初年次学生の「質」に関する調査報告:学生による質評価と成績評価、自主学習との関連 大阪市立大学大学教育,6(1),1-8.[PDF](授業外学習の時間が長い学生ほど評定が高い、分析対象は1年生のみ;谷村英洋(2011)「大学生の学習時間と学習成果」で知る)
- 西垣順子・矢部正之(2008).成績評価の難易度と形成的評価が受講生の学習に与える影響:初年次学生と上回生での比較 大学教育学会誌,30(2),113-119.(単一の授業のための学習時間に着目、[評価が最も厳しい講義に向けた授業外学習時間]と[学習成果の評定]との関係を分析、1・2年生のを学年別に検討、2年生のみ有意差が見られた、とくに週1時間未満か1時間以上かで評定に差が生じていた;谷村英洋(2011)「大学生の学習時間と学習成果」で知る)
- 溝上慎一(2008).授業・授業外学習による学習タイプと汎用的技能との習得の関連 秦由美子(研究代表者)大学における学生の質に関する国際比較研究:教育の質保証・向上の観点から(科学研究費補助金最終報告書) p.13-22.[PDF](授業外学習に加えて授業に出席している時間も視野に入れて学習成果を検証、授業内外の学習時間によって学習タイプを作成、タイプ間で学習成果に有意な差があるかを検定、授業外学習を多く行っている学習タイプで学習成果が有意に高かった;谷村英洋(2011)「大学生の学習時間と学習成果」で知る)
- 溝上慎一(2009).授業・授業外学習による学習タイプと能力や知識の変化・大学教育満足度との関連性:単位制度の実質化を見据えて 山田礼子 (編)大学教育を科学する:学生の教育評価の国際比較 東信堂 pp.119-133.(授業外学習に加えて授業に出席している時間も視野に入れて学習成果を検証、授業外学習を[授業に関連する学習]と[授業に関連しない学習]に分類、授業内外の学習時間によって学習タイプを作成、タイプ間で学習成果に有意な差があるかを検定、授業外学習を多く行っている学習タイプで学習成果が有意に高かった、バランスのとれた授業・授業外学習の重要性を指摘、ただし授業に関連しない学習は明確な効果が見られなかった;谷村英洋(2011)「大学生の学習時間と学習成果」で知る)
- 村澤昌崇(2003).学生の力量形成における大学教育の効果 有本章(編)大学のカリキュラム 玉川大学出版部 pp.60-74.(大学での学習成果は経験した授業の特性や入学前の学習態度などに規定される;谷村英洋(2011)「大学生の学習時間と学習成果」で知る)
- 小方直幸(2008).学生のエンゲージメントと大学教育のアウトカム 高等教育研究,11,45-64.(大学教育のアウトカムを重視する傾向が強まっている;山田・森(2008)で知る)(授業外学習の合計時間が汎用的技能および学問的知識の獲得に有意な影響を与えている;谷村英洋(2011)「大学生の学習時間と学習成果」で知る)
[2014.11.17]IRなどについての文献メモ 文献一覧を更新
- 丸山文裕(2014).高等教育システム・経営研究のレビュー 大学論集,46,1-15.[PDF](『大学論集』バックナンバーで知る)
- 黄福涛(2014).大学カリキュラムに関する研究:回顧と展望 大学論集,46,17-29.[PDF](『大学論集』バックナンバーで知る)
- 大膳司(2014).高大接続に関する研究の展開:2006年から2013年まで 大学論集,46,31-53.[PDF](『大学論集』バックナンバーで知る)
- 大場淳(2014).大学職員研究の動向:大学職員論を中心として 大学論集,46,91-106.[PDF](『大学論集』バックナンバーで知る)
- 島一則(2014).高等教育財政・財務に関する研究の展開 大学論集,46,107-138.[PDF](『大学論集』バックナンバーで知る)
- 福留東土(2014).比較高等教育研究の回顧と展望 大学論集,46,139-169.[PDF](『大学論集』バックナンバーで知る)
- 村澤昌崇(2014).高等教育における評価の動向・課題 大学論集,46,171-189.[PDF](『大学論集』バックナンバーで知る)
- 小入羽秀敬(2014).私学政策・制度に関する研究 大学論集,46,191-204.[PDF](『大学論集』バックナンバーで知る)
- 大場淳(2014).フランスにおける大学ガバナンスの改革:大学の自由と責任に関する法律(LRU)の制定とその影響 大学論集,45,1-16.[PDF](『大学論集』バックナンバーで知る)
- 両角亜希子(2014).大学教員の意思決定参加に対する現状と将来像 大学論集,45,65-79.[PDF](『大学論集』バックナンバーで知る)
- 伊藤彰浩(2013).戦争と私立大学:戦時期・戦後改革期の私大財政を中心に 大学論集,44,97-113.[PDF](『大学論集』バックナンバーで知る)
- 橋本鉱市(2013).戦後日本における高等教育関連議員の構造分析 大学論集,44,163-178.[PDF](『大学論集』バックナンバーで知る)
- 川越明日香(2013).学生による授業評価の横断的・時系列的分析:1年次初等理科教育を事例として 大学論集,44,211-226.[PDF](『大学論集』バックナンバーで知る)
- 山本眞一(2012).高等教育研究と私:これまでの研究生活を振り返って 大学論集,43,34-44.[PDF](『大学論集』バックナンバーで知る)
- 北垣郁雄(2012).これまでの研究を振り返って:高等教育,教育工学、そして教育均衝 大学論集,43,67-82.[PDF](『大学論集』バックナンバーで知る)
- 黄福涛(2012).専門教育に関する歴史的・比較的研究:理念、制度、カリキュラムを中心に 大学論集,43,83-98.[PDF](『大学論集』バックナンバーで知る)
- 藤村正司(2012).なぜ女子の大学進学率は低いのか?:愛情とお金の間 大学論集,43,99-115.[PDF](『大学論集』バックナンバーで知る)
- 白川優治(2012).戦後日本における公的奨学金制度の制度的特性の形成過程:1965年までの政策課程の検証を中心に 大学論集,43,135-152.[PDF](『大学論集』バックナンバーで知る)
- 濱中淳子(2012).「大学教育の効用」再考:文系領域における学び習慣仮説の検証 大学論集,43,189-205.[PDF](『大学論集』バックナンバーで知る)
- 原田健太郎(2012).大学での知識の生産・整理・伝達に関する研究:日本における研究動向のレビュー 大学論集,43,239-254.[PDF](『大学論集』バックナンバーで知る)
- 吉川政夫・有沢孝治・川野辺裕幸・内田晴久(2012).構造化された授業評価アンケートの開発 大学論集,43,337-351.[PDF](『大学論集』バックナンバーで知る)
- 黄福涛(2011).コンピテンス教育に関する歴史的・比較的な研究:コンセプト、制度とカリキュラムに焦点をあてて 大学論集,42,1-18.[PDF](『大学論集』バックナンバーで知る)
- 大場淳(2011).高等教育の市場化と政府統制:近年のフランスの大学改革を巡って 大学論集,42,19-35.[PDF](『大学論集』バックナンバーで知る)
- 福留東土(2011).1980年代以降の米国における学士課程カリキュラムを巡る議論 大学論集,42,37-53.[PDF](『大学論集』バックナンバーで知る)
- 阿曽沼明裕(2011).米国における大学院の組織と運営:専門職学位と研究学位の対比から 大学論集,42,107-123.(『大学論集』バックナンバーで知る)
- 金子勉(2011).ドイツにおける近代大学理念の形成過程 大学論集,42,143-158.[PDF](『大学論集』バックナンバーで知る)
- 山田礼子(2011).大規模継続学生調査の可能性と課題 大学論集,42,245-263.[PDF](『大学論集』バックナンバーで知る)
- 山本眞一(2010).大学自治とオートノミー:法人化以降の国立大学運営の課題 大学論集,41,1-13.[PDF](『大学論集』バックナンバーで知る)
- 黄福涛(2010).アメリカにおけるliberal educationとgeneral educationについて:歴史的な考察および最近の動き 大学論集,41,27-42.[PDF](『大学論集』バックナンバーで知る)
- 小方直幸(2010).コンピテンス・アプローチ再考 大学論集,41,43-57.[PDF](『大学論集』バックナンバーで知る)
- 大場淳(2010).フランスの大学改革:サルコジ=フィヨン政権下での改革を中心に 大学論集,41,59-77.[PDF](『大学論集』バックナンバーで知る)
- 福留東土(2010).専門教育の視点からみた学士課程教育の構築 大学論集,41,109-127.[PDF](『大学論集』バックナンバーで知る)
- 有本章(2010).知識社会における大学院教育と学士課程教育の連結:その論点を考える 大学論集,41,185-202.[PDF](『大学論集』バックナンバーで知る)
- 杉本和弘(2010).オーストラリア高等教育のガバナンスと質保証:州政府の位置と機能 大学論集,41,251-269.[PDF](『大学論集』バックナンバーで知る)
- 堀田泰司(2010).ボローニャ宣言にみるエラスムスの経験の意義 大学論集,41,305-322.[PDF](『大学論集』バックナンバーで知る)
- 吉田香奈・柳浦猛(2010).米国テネシー州における高等教育財政とパフォーマンス・ファンディング 大学論集,41,323-341.[PDF](『大学論集』バックナンバーで知る)
- 清水栄子(2010).アメリカにおける学習助言(Academic Advising)の発展とその背景:実践主体とそれを支える組織を手がかりとして. 大学論集,41,361-375.[PDF](『大学論集』バックナンバーで知る)
- 高森智嗣(2010).大学における評価の活用に関する研究:自己点検・評価報告書の分析を中心に 大学論集,41,377-392.[PDF](『大学論集』バックナンバーで知る)
- Barton, B.(2010).Assessment of student learning outcomes: The quality enhancement plan. 大学論集,41,423-437.[PDF](『大学論集』バックナンバーで知る)
- 葛城浩一(2010).アウトカム指標のあり方を考える 大学論集,41,439-454.[PDF](『大学論集』バックナンバーで知る)
- 大場淳(2009).高等教育の市場化:平等と卓越の追求の狭間で:フランスにおける公役務概念の変化に着目して 大学論集,40,49-68.[PDF](『大学論集』バックナンバーで知る)
- 村澤昌崇(2009).高等教育における政策波及と機関の意思決定に関する研究序説:大学設置基準大綱化以降の自己点検・評価活動の波及に関するイベント・ヒストリー分析 大学論集,40,69-86.[PDF](『大学論集』バックナンバーで知る)
- 阿曽沼明裕(2009).米国研究大学における大学院管理 大学論集,40,107-126.[PDF](『大学論集』バックナンバーで知る)
- 鈴木敏之(2009).高等教育への公的投資について:教育振興基本計画の策定をめぐる論考 大学論集,40,127-144.[PDF](『大学論集』バックナンバーで知る)
- 濱中淳子(2009)<高等教育政策>の研究と<高等教育>の政策研究 大学論集,40,145-162.[PDF](『大学論集』バックナンバーで知る)
- 山田礼子(2009).学生の情緒的側面の充実と教育成果:CSS とJCSS 結果分析から 大学論集,40,181-198.[PDF](『大学論集』バックナンバーで知る)
- 立石慎治(2009).高等教育機関間の学生の移動:日米の編入学研究の動向と課題 大学論集,40,217-232.[PDF](『大学論集』バックナンバーで知る)
- カール・ノイマン 大膳司・渡邊隆(訳)(2009).大学における教育文化から学習文化への転換:大学教授学と大学改善のためのカリキュラム計画 大学論集,40,327-341.[PDF](『大学論集』バックナンバーで知る)
- 黄福涛(2008).大学カリキュラムの分析枠組み:カリキュラム研究の展開を手掛かりとして 大学論集,39,15-31.[PDF](『大学論集』バックナンバーで知る)
- 大場淳(2008).ボローニャ・プロセスとフランスにおける高等教育質保証:高等教育の市場化と大学の自律性拡大の中で 大学論集,39,33-54.[PDF](『大学論集』バックナンバーで知る)
- 有本章(2008).グローバル化時代における高等教育システムの構造と機能:その類似性に関する国際比較試論 大学論集,39,55-73.[PDF](『大学論集』バックナンバーで知る)
- 妹尾堅一郎(2008).実務家教員の必要性とその育成について:「実務知基盤型教員」を活用する大学教育へ 大学論集,39,109-128.[PDF](『大学論集』バックナンバーで知る)
- 西村和雄・浦坂純子・平田純一・八木匡(2008).企業による学力評価から見た人材確保と教育政策:日本の中小企業調査から見えるもの 大学論集,39,145-162.[PDF](『大学論集』バックナンバーで知る)
- 吉本圭一・立石和子(2008).大卒看護職の初期キャリアとコンピテンシー形成:看護師・関係者インタビューの分析 大学論集,39,223-240.[PDF](『大学論集』バックナンバーで知る)
- 大場淳(2007).フランスにおける国家予算制度改革と大学への影響:自律性拡大と評価制度整備に向けて 大学論集,38,103-124.[PDF](『大学論集』バックナンバーで知る)
- 黄福涛(2007).大学教育理念と学士課程カリキュラムの改革:歴史的・比較的視点から 大学論集,38,125-141.[PDF](『大学論集』バックナンバーで知る)
- 葛城浩一(2007).就職率の教育成果指標としての妥当性 大学論集,38,207-220.[PDF](『大学論集』バックナンバーで知る)
- 西村和雄・浦坂純子・平田純一・八木匡(2007).企業が求める人材と教育に関する実態調査 大学論集,38,239-255.[PDF](『大学論集』バックナンバーで知る)
- 松繁寿和・井川静恵(2007).絶対評価・相対評価が学生の学習行動に与える影響:大学の専門科目における実験 大学論集,38,277-292.[PDF](『大学論集』バックナンバーで知る)
- 大膳司(2007).戦後日本における大学入試の変遷に関する研究(I):臨時教育審議会(1984-1987年)以降を中心として 大学論集,38,337-351.[PDF](『大学論集』バックナンバーで知る)
- 山本清(2007).高等教育機関のアカウンタビリティとガバナンス:国立大学法人を中心にして 大学論集,38,369-380.[PDF](『大学論集』バックナンバーで知る)
- 山野井敦徳(2006).知識基盤社会における21世紀高等教育システムの理論的考察:大学の再構築分析に関する繰り込み理論の展開 大学論集,37,1-18.[PDF](『大学論集』バックナンバーで知る)
- 大場淳(2006).フランスにおける大学自治:2003年の高等教育機関自治法(大学改革法)案を巡って 大学論集,37,35-57.[PDF](『大学論集』バックナンバーで知る)
- 相原総一郎(2006).アメリカ大学教員のサラリー研究 大学論集,37,97-113.[PDF](『大学論集』バックナンバーで知る)
- 池田輝政・神保啓子・中井俊樹・青山佳代(2006).FDを持続的に革新するベンチマーキング手法の事始め 大学論集,37,115-130.[PDF](『大学論集』バックナンバーで知る)
- 橋本功・西山裕美子(2006).共通教育における受講者数と単位取得率の関係:適正受講者数算出に向けての基礎的研究 大学論集,37,183-194.[PDF](『大学論集』バックナンバーで知る)
- 串本剛(2006).大学教育におけるプログラム評価の現状と課題:教育成果を根拠とした形成的評価の確立を目指して 大学論集,37,263-276.[PDF](『大学論集』バックナンバーで知る)
- 有本章(2006).高等教育研究30年:高等教育研究の制度化の実現 大学論集,36,1-29.[PDF](『大学論集』バックナンバーで知る)
- 関正夫(2006).大学カリキュラム改革に関する研究の回顧と展望:学士課程教育を中心として 大学論集,36,31-67.[PDF](『大学論集』バックナンバーで知る)
- 有本章(2006).大学院教育に関する研究:回顧と展望 大学論集,36,83-105.[PDF](『大学論集』バックナンバーで知る)
- 大膳司(2006).高大接続に関する研究の展開 大学論集,36,127-148.[PDF](『大学論集』バックナンバーで知る)
- 伊藤彰浩(2006).近代日本の高等教育の歴史研究の展開 大学論集,36,149-168.[PDF](『大学論集』バックナンバーで知る)
- 小川佳万(2006).比較教育からみた高等教育研究の回顧と展望 大学論集,36,169-184.[PDF](『大学論集』バックナンバーで知る)
- 黄福涛(2006).高等教育の国際化に関する研究の回顧と展望 大学論集,36,211-220.[PDF](『大学論集』バックナンバーで知る)
- 金子元久(2006).政策と制度に関する研究の展開 大学論集,36,221-235.[PDF](『大学論集』バックナンバーで知る)
- 小方直幸(2006).大学教育と労働市場の研究:回顧と展望 大学論集,36,237-250.[PDF](『大学論集』バックナンバーで知る)
- 大場淳(2006).大学職員(SD)に関する研究の展開 大学論集,36,269-296.[PDF](『大学論集』バックナンバーで知る)
- 稲永由紀(2006).大学と地域社会に関する研究動向と課題 大学論集,36,297-313.[PDF](『大学論集』バックナンバーで知る)
- 米澤彰純(2006).高等教育の評価に関する研究の回顧と展望 大学論集,36,315-329.[PDF](『大学論集』バックナンバーで知る)
- 有本章(2005).高等教育研究40年の回顧 大学論集,35,59-86.[PDF](『大学論集』バックナンバーで知る)
- 羽田貴史(2005).国立大学法人制度論 大学論集,35,127-146.[PDF](『大学論集』バックナンバーで知る)
- 大膳司(2005).2022年度までの都道府県別大学進学者数の予測:これまでの予測モデルを参照して 大学論集,35,147-169.[PDF](『大学論集』バックナンバーで知る)
- 大場淳(2005).欧州高等教育圏創設とフランスの対応:新しい学位構造(LMD)の導入を巡って 大学論集,35,171-192.[PDF](『大学論集』バックナンバーで知る)
- 天野智水・南部広孝(2005).わが国の国立大学における学生による授業評価の展開 大学論集,35,229-243.[PDF](『大学論集』バックナンバーで知る)
- 羽田貴史(2004).企業的大学経営と集権的分権化 大学論集,34,21-40.[PDF](『大学論集』バックナンバーで知る)
- 大場淳(2004).フランスの大学における学生支援:進路指導並びに大学情報・進路指導センター(SCUIO)の活動を中心に 大学論集,34,41-61.[PDF](『大学論集』バックナンバーで知る)
- 藤村正司(2004).厳格な成績評価?:教養部解体・GP分布・公正 大学論集,34,177-193.[PDF](『大学論集』バックナンバーで知る)
- 山本清(2004).大学の管理・支援部門の経営管理について 大学論集,34,195-209.[PDF](『大学論集』バックナンバーで知る)
- 有本章(2003).高等教育の国際比較研究におけるトロウモデルと知識モデルの視点 大学論集,33,1-19.[PDF](『大学論集』バックナンバーで知る)
- 大場淳(2003).フランスの大学における管理運営の変遷と自律性の発展:日本の国立大学法人化とフランスの契約政策の比較考察 大学論集,33,37-56.[PDF](『大学論集』バックナンバーで知る)
- 黄福涛(2002).高等教育の国際化に関する研究の展開:比較的な視点 大学論集,32,29-41.[PDF](『大学論集』バックナンバーで知る)
- 小方直幸(2002).大学におけるプロフェッショナル養成:大学の知と現場の知の相克 大学論集,32,43-58.[PDF](『大学論集』バックナンバーで知る)
- 山崎博敏(2002).アメリカの州立大学における教育評価:大学・州・全国レベルでの機構 大学論集,32,131-146.[PDF](『大学論集』バックナンバーで知る)
- 山野井敦徳(2001).大学教員の公募制に関する研究:公募文書と採用者のマッチング分析を中心に 大学論集,31,17-33.[PDF](『大学論集』バックナンバーで知る)
- 土持法一(2001).新制大学における「単位制度」の導入と展開の過程 大学論集,31,65-80.[PDF](『大学論集』バックナンバーで知る)
- 山田礼子(2001).アメリカの高等教育機関における導入教育の意味:学生の変容との関連から 大学論集,31,129-144.[PDF](『大学論集』バックナンバーで知る)
- 椙山正弘(2000).女子大学研究論 大学論集,30,93-108.[PDF](『大学論集』バックナンバーで知る)
- 中井俊樹・馬越徹(2000).クラス規模が授業評価に与える影響に関する一考察:名古屋大学の事例分析 大学論集,30,109-123.[PDF](『大学論集』バックナンバーで知る)
- 土持ゲーリー法一(1997).憲法第89条と私立大学の助成問題に関する一考察 大学論集,26,149-167.[PDF](『大学論集』バックナンバーで知る)
- 浜野隆・牟田博光(1997).大学の授業評価にもとづく教育効果の分析 大学論集,26,169-187.[PDF](『大学論集』バックナンバーで知る)
- 牧野暢男(1997).コミュニティ・カレッジとアメリカ社会 大学論集,26,189-204.[PDF](『大学論集』バックナンバーで知る)
- 羽田貴史(1996).明治憲法体制成立期の帝国大学財政政策 大学論集,25,43-65.[PDF](『大学論集』バックナンバーで知る)
- 関正夫(1995).社会の変動と学問・教育等への影響:現代大学の本質的問題へのアプローチ 大学論集,24,1-31.[PDF](『大学論集』バックナンバーで知る)
- 天野郁夫(1995).高等教育システムの構造変動:計画モデルから市場モデルへ 大学論集,24,119-134.[PDF](『大学論集』バックナンバーで知る)
- 土持法一(1995).新制大学の成立経緯に関する一考察 大学論集,24,175-193.[PDF](『大学論集』バックナンバーで知る)
- 佐藤広志(1994)日本における最初の博士集団:明治20年代における学位取得者の特性 大学論集,23,117-133.(『大学論集』バックナンバーで知る)
- 伊藤虎丸(1994).大学設置基準の大綱化と私立大学:大学自治と一般教育との関連から 大学論集,23,153-170.(『大学論集』バックナンバーで知る)
- 尾形憲(1994).私大国庫助成運動30年をふりかえって 大学論集,23,171-189.[PDF](『大学論集』バックナンバーで知る)
- 羽田貴史(1994).国立大学財政制度研究序説 大学論集,23,231-247.[PDF](『大学論集』バックナンバーで知る)
- 小方直幸(1994).戦後大卒労働市場の構造変動 大学論集,23,329-344.[PDF](『大学論集』バックナンバーで知る)
- 喜多村和之(1993).大学研究の20年:大学はどこから来て、どこへ行くのか 大学論集,22,1-10.[PDF](『大学論集』バックナンバーで知る)
- 馬越徹(1993).比較高等教育研究の回顧と展望 大学論集,22,111-122.[PDF](『大学論集』バックナンバーで知る)
- 伊藤彰浩(1993).高等教育史研究の回顧と展望 大学論集,22,145-161.[PDF](『大学論集』バックナンバーで知る)
- 金子元久(1993).高等教育制度・政策の研究 大学論集,22,187-208.[PDF](『大学論集』バックナンバーで知る)
- 相原総一郎(1993).高等教育研究の特質:高等教育研究者の特性を中心に 大学論集,22,225-249.[PDF](『大学論集』バックナンバーで知る)
- 江淵一公(1992).ヨーロッパにおける大学の国際化の潮流:ERASMUS計画の動向を中心として 大学論集,21,31-64.[PDF](『大学論集』バックナンバーで知る)
- 伊藤彰浩(1992).五校昇格:大正期における官立大学昇格問題 大学論集,21,141-162.[PDF](『大学論集』バックナンバーで知る)
- 土持ゲーリー法一(1991).米国学術顧問団報告書と戦後日本の高等教育改革案:アダムス団長文書を中心に 大学論集,20,229-247.[PDF](『大学論集』バックナンバーで知る)
- 伊藤彰浩(1989).戦時期日本における「人的資源」政策:戦時動員と高等教育をめぐる政治過程 大学論集,18,127-148.[PDF](『大学論集』バックナンバーで知る)
- 土持ゲーリー法一(1989).占領下の教育改革:第一次米国対日教育使節団報告書と高等教育改革 大学論集,18,163-182.(『大学論集』バックナンバーで知る)
- 関正夫(1986).戦後日本の大学における教育研究組織の変遷:国立大学の場合 大学論集,16,1-24.[PDF](『大学論集』バックナンバーで知る)
- 喜多村和之(1986).一般教育はなぜ問題とされるのか:『一般教育研究委員会報告』(1951)をめぐる考察 大学論集,16,25-40p.[PDF](『大学論集』バックナンバーで知る)
- 丸山文裕(1986).教育の量的拡大のメカニズム:その理論と実証 大学論集,16,65-82.[PDF](『大学論集』バックナンバーで知る)
- 牧野暢男・上野真理子(1986).女子大生の就業意識の構造 大学論集,16,121-140.(『大学論集』バックナンバーで知る)
- 関正夫(1982).戦前期大学教育のカリキュラムに関する史的考察:帝国大学における法学・医学教育を中心として 大学論集,11,123-151.[PDF](『大学論集』バックナンバーで知る)
- 喜多村和之(1980).高等教育体制の段階移行論について:<トロウ・モデル>の再検討 大学論集,8,49-65.[PDF](『大学論集』バックナンバーで知る)
- 牧野暢男(1980).米国における公立大学の発展とその背景:その2:戦後から1960年代後半まで 大学論集,8,155-171.[PDF](『大学論集』バックナンバーで知る)
- 喜多村和之(1979).日本における「中等後教育」の制度的構 大学論集,7,21-39.[PDF](『大学論集』バックナンバーで知る)
- 関正夫(1978).戦前期における中等・高等教育の構造と入学者選抜 大学論集,6,135-173.[PDF](『大学論集』バックナンバーで知る)
- 横尾壮英(1977).学位制度の起源:ドクターを中心として 大学論集,5,1-21.(『大学論集』バックナンバーで知る)
- 喜多村和之(1978).Postsecondary Educationの概念について 大学論集,6,69-90.[PDF](『大学論集』バックナンバーで知る)
- トロウ,M.天野郁夫(訳)(1976).アメリカ高等教育の民主化 大学論集,4,110-125.(『大学論集』バックナンバーで知る)
- ペンペル,T.J.養祖京子(訳)(1975).日本における戦後高等教育拡大政策 大学論集,3,96-108.(『大学論集』バックナンバーで知る)
- カミングス,W.K.佐野正周(訳)(1975).日本の私立大学 大学論集,3,109-121.(『大学論集』バックナンバーで知る)
- 寺崎昌男(1973).「講座制」の歴史的研究序説:日本の場合(1) 大学論集,1,1-10.[PDF](『大学論集』バックナンバーで知る)
[2014.11.17]IRなどについての文献メモ 文献一覧を更新
- Cartmell, B. M. (2014). The relationship between freshman student retention and use of an online parent portal. Unpublished doctoral dissertation, The University of Tennessee at Chattanooga, Chattanooga, Tennessee.[PDF](Google Scholar「withdraw retention」で知る)
[2014.11.14]IRなどについての文献メモ 文献一覧を更新
- 姉川恭子(2014).大学の学習・生活環境と退学率の要因分析 経済論究,149,1-16.(CiNii Articles「退学」で知る)
- 川崎孝明・中嶋弘二・川嶋健太郎・川口惠子(2014).大学における寄り添い型学生支援体制の構築:中途退学防止の観点からの実践的アプローチ 尚絅大学研究紀要.A,人文・社会科学編,46,75-89.(CiNii Articles「退学」で知る)
- 志田秀史(2014). 日米の中途退学調査の比較検討:アメリカの全国中途退学予防センター調査を手がかりに 総合人間科学,2,131-148.(CiNii Articles「退学」で知る)
- 鈴木貴士・佐藤進・川尻達也・山口真史・吉道悦子・村田俊也・川田敬一・松本圭(2014). ストレス対処タイプ別のメンタルヘルスの特徴について KIT progress:工学教育研究,21,167-176.(CiNii Articles「退学」で知る)
- 今野克幸・白石悟・細川和彦・井田直人・福原朗子・木内伸洋(2014).授業時間割の改善や初年度教育の充実等による修学支援と退学者減少対策 工学教育研究講演会講演論文集 平成25年度,61,650-651.(CiNii Articles「退学」で知る)
- 内田千代子(2013).大学は今(第19回)大学生の休学・退学・留年に関する問題(1)国立大学の調査から 週刊教育資料,1240,28-29.(CiNii Articles「退学」で知る)
- 内田千代子(2013).大学は今(第19回)大学生の休学・退学・留年に関する問題(2)国立大学の調査から 週刊教育資料,1242,28-29.(CiNii Articles「退学」で知る)
- 内田千代子(2013).大学は今(第20回)大学生の休学・退学・留年に関する問題(3)国立大学の調査から 週刊教育資料,1244,28-29.(CiNii Articles「退学」で知る)
- 内田千代子(2013).大学は今(第21回)大学生の休学・退学・留年に関する問題(4)国立大学の調査から 週刊教育資料,1246,28-29.(CiNii Articles「退学」で知る)
- 内田千代子(2013).大学における休・退学、留年学生に関する調査(第34報) 全国大学メンタルヘルス研究会報告書:学生支援合同フォーラム,35,36-51.(CiNii Articles「退学」で知る)
- 藤原朝洋・富永ちはる・押味京子(2013).大学における休退学の現状・対策・課題の検討:37大学の現状と取組 九州共立大学研究紀要,4(1),11-18.[PDF](CiNii Articles「退学」で知る)(25の国公私立大学を対象にして休学・退学問題の対策を整理・・・①教員による対策:学習指導・履修指導・学生生活指導・学業不振者指導・3回欠席した学生への指導・少人数教育・休退学指導など、②学生相談機関による対策:休・退学希望者面談・カウンセリング・欠席がちの学生への連絡・保護者面談会での個別面接・復学支援・心の病の予防など、③その他の対策:学修支援アドバイザーの設置・出席管理システムでの出席管理・低GPA取得者支援・新入生歓迎会・復学支援昼食懇談会など、北九州市立大学の「早期支援システム」の紹介;岩崎(2015)「」で知る)
- 原清治(2012). 「つながり」の関係づくりを中心に置いた中途退学者ゼロを目指す取り組み 私学経営,450,18-29.(CiNii Articles「退学」で知る)
- 谷原弘之(2012).退学予防を目的とした「3日以上の理由のない欠席者の報告システム」の効果 医学と生物学,156(4),163-167.(CiNii Articles「退学」で知る)
- 山口直範・頭師由里(2012).能動的な学生相談体制の試み 研究紀要,20,101-107.[PDF](CiNii Articles「退学」で知る)
- Nicholas, B. A., & Steven, L. (2012). Trends and issues with the English assessment and class placement of first year students at Kyoei University: Department of international business management. 共栄大学研究論集,10,247-254.[PDF](CiNii Articles「退学」で知る)
- 松井洋・田中裕・中村真(2012).大学生の大学適応に関する研究(3) 川村学園女子大学研究紀要,23(1),117-129.(CiNii Articles「退学」で知る)
- 井奈波良一・井上眞人・広瀬万宝子・植木啓文(2011).男子医学生の退学願望とメランコリー親和型性格、メンタルヘルス不調および睡眠時間との関係 日本職業・災害医学会会誌,59(1),49-52.(CiNii Articles「退学」で知る)
- 内田千代子(2011).大学における休・退学、留年学生に関する調査(第32報) 全国大学メンタルヘルス研究会報告書:学生支援合同フォーラム,33,42-59.(CiNii Articles「退学」で知る)
- 内田千代子(2010).休学・退学の変化 精神科,17(4),330-338.(CiNii Articles「退学」で知る)
- 鍛治致(2010).新設大学における退学・休学・留年:多変量解析による要因分析 日本教育社会学会大会発表要旨集録,62,392-393.[PDF](CiNii Articles「退学」で知る)
- 内田千代子(2010).研究班発表 大学における休・退学、留年学生に関する調査(第31報) 全国大学メンタルヘルス研究会報告書,32,80-94.(CiNii Articles「退学」で知る)
- 三宅仁・大岡美穂・若月トシ(2010).小規模理系単科大学における独法化前後の休退学の実態 全国大学メンタルヘルス研究会報告書,32,7-79.(CiNii Articles「退学」で知る)
- 松井洋・中村真・田中裕(2010).大学生の大学適応に関する研究 川村学園女子大学研究紀要,21(1),121-133.(CiNii Articles「退学」で知る)
- 松田美登子(2009).「メンタルヘルス調査」を退学者対策に繋げるための予備的研究:学生相談室におけるドロップアウト危機の事例を中心に 学生相談研究,30(2),136-147.(CiNii Articles「退学」で知る)
- 出村由利子・山本正司・佐藤美紀(2009).退学の危機を脱した体験から学ぶ学生指導のあり方 和泉短期大学研究紀要,29,37-48.(CiNii Articles「退学」で知る)
- 竹山佳江(2009).大学生における休学・退学・復学 学生相談センター紀要,19,49-53.(CiNii Articles「退学」で知る)
- 鍛治致(2009).新設大学における退学・休学・留年:多変量解析による要因分析 研究紀要,7(1),153-163.(CiNii Articles「退学」で知る)
- 内田千代子(2008).大学における休・退学、留年学生に関する調査(第29報) 全国大学メンタルヘルス研究会報告書,30,70-85.(CiNii Articles「退学」で知る)
- 村澤昌崇(2008).大学中途退学の計量的分析:高等教育研究への計量分析の応用(その3)フリーソフトRを用いて 比治山高等教育研究,1,153-165.[PDF] (CiNii Articles「退学」で知る)
- 馬込武志・尾崎剛志(2008). 学生の退学要因と退学回避の方策について:卒業時アンケートを参考にして 湊川短期大学紀要,44,69-74.[PDF](CiNii Articles「退学」で知る)
- 木ノ瀬朋子・江口昌克・西村香・安齋順子・村上弘子・古俣万里子・鈴木洋州・山田多啓男(2007).退学者における入学時UPIの特徴 明海大学教養論文集,19,12-17.(CiNii Articles「退学」で知る)
- 小塩真司・願興寺礼子・桐山雅子(2007). 大学退学者におけるUPI得点の特徴 学生相談研究,28(2),134-142.(CiNii Articles「退学」で知る)
- 杉山雅宏(2007).中途退学予防のための心理的支援に関する調査研究 福祉心理学研究,4(1),15-25.(CiNii Articles「退学」で知る)
- 岡本英雄(2007).日本私立大学連盟WEBアンケート調査 留年、退学に関するアンケート調査結果報告 大学時報,56(312),86-91.(CiNii Articles「退学」で知る)
- 竹渕香織(2007).学生相談室利用事例からみる退学者の傾向と支援:退学者減少のための糸口を探る 聖学院大学総合研究所紀要,41,297-326.[PDF](CiNii Articles「退学」で知る)
[2014.11.14]IRなどについての文献メモ 内容をアップ
- 戈木クレイグヒル滋子(2006).グラウンデッド・セオリー・アプローチ:理論を生みだすまで 新曜社[概要](Google「グラウンデッドセオリー」で知る)
[2014.11.09]IRなどについての文献メモ 文献一覧を更新
- 広島大学高等教育研究開発センター(編)(2011).大学教育質保証の国際比較 広島大学高等教育研究開発センター[PDF](Google「内部質保証 外部質保証」で知る)
- 大場淳(2011).欧州における高等教育質保証の展開 広島大学高等教育研究開発センター(編)大学教育質保証の国際比較 広島大学高等教育研究開発センター pp.1-24.[PDF](「追求すべき質の内容は個々の国や大学、教育課程毎に定められるべきもの」;Google「内部質保証 外部質保証」で知る)
[2014.11.08]IRなどについての文献メモ 文献一覧を更新
- Peterson, M. W. (1985). Institutional research: An evolutionary perspective. New directions for higher education, 46, 5-15.(IRの定義:「高等教育機関の<教育的および経営的機能>と<情報に関する機能>を関連づける、重要な中継的部門」;青山(2006)「アメリカ州立大学におけるインスティテューショナル・リサーチの機能に関する考察」で知る)
- Saupe, J. L. (1990). The functions of institutional research. 2nd ed. Tallahassee, Florida: Association for Institutional Research. [PDF](IRの定義:「高等教育機関における計画策定、政策形成、ならびに意思決定支援のための研究を行う部門」;青山(2006)「アメリカ州立大学におけるインスティテューショナル・リサーチの機能に関する考察」で知る)
- Muffo, J. A. & McLaughlin, G. W.(Eds.)(1987). A primer on institutional research. Tallahassee, Florida: Association for Institutional Research.(IRの定義:「機関の計画策定、政策決定、意思決定を支援するような情報を提供すること」;小林・片山・劉(2011)「大学ベンチマークによる大学評価の実証的研究」で知る)
- 高瀬佳典・川口潔・山本修司・深尾嘉彦(2014).調査統計に基づく教学分野のIR(Institutional Research)の推進について 大学行政研究,9,17-33.[PDF](Google「"institutional research" 答申」で知る)
[2014.11.07]IRなどについての文献メモ 文献一覧を更新
- 青山佳代(2006).アメリカ州立大学におけるインスティテューショナル・リサーチの機能に関する考察 名古屋高等教育研究,6,113-130.[PDF](米国の大学におけるIRの状況;ブログ「よしなごと」(otani0083さん)の記事で知る)(IRはデータを収集し分析・解釈することで大学の計画策定・政策決定・意思決定を支援する機能を担っている、アメリカの歴史研究者たちが自大学の歴史的展開を研究したことがIRの始まり、1950~1970年代は学生数の増加により大学が成長・拡大した、1970年~1980年代後半はベトナム戦争を発端とした市民運動により学生が社会や大学に対して反発、大学は教育の質の分析に関心を示すようになった、1985年以降は大学が戦略的に経営計画を策定し始めデータが要求されるようになった、また教育の質の保証への関心が高まった、Volkwein(1999)の枠組み(4項目)を使って34の州立大学のIRを分類した、結果:枠組みに沿って4つの項目を持っていた、ただし項目を横断した機能が見られた;Google Scholar「"institutional research" 歴史」で知る)
- 山田礼子(2005).アメリカの大学における管理運営モデルの変遷 江原武一・杉本均(編)大学の管理運営改革 東信堂 pp.113-135.(アメリカのほとんどの大学にはIRオフィスが置かれている;小林・片山・劉(2011)「大学ベンチマークによる大学評価の実証的研究」で知る)
- 秋山卓也(2013).高等教育政策における内部質保証について 教育の内部質保証システム構築に関するセミナー資料[PDF][HTML(大会プログラム)](大学教育の質保証に係る近年の政策動向、中央教育審議会における内部質保証に関する議論(2008年の「学士課程教育の構築に向けて(答申)」で内部質保証体制の構築を提言);Google「質保証 政策」で知る)
- 鳥居朋子(2011).どうつくる?大学教育の質保証を支えるしくみ:教学領域のIR コトハジメ ニュースレター,16,1-3.[PDF](Google「質保証 政策」で知る)
[2014.11.06]IRなどについての文献メモ 文献一覧を更新
- 船守美穂(2011).日本型IR機能の課題と進化策:意思決定に役立つIRを考える IR機能の強化策―インフラと組織体制の実際(大学評価・情報シリーズ29)資料[PDF]
- 佐藤仁(2011).これまでの大学評価担当者集会における米国IRの議論 第5回大学評価担当者集会プレイベント(大学評価コンソーシアム主催、九州大学箱崎キャンパス、2011年9月15日)資料(既存の個人によるIR機能をどう組織的に行うか、機能を大学全体の活動に位置付けることができるのであればIR室は必要なものではない、組織的に行うためには組織間の調整と連携強化が必要;Google「"institutional research" 個人 依存」で知る)[PDF(PowerPoint資料)][PDF(書き起こし)]
- 田中岳(2008).教務系職員に期待されていた新たな業務 大場淳(研究代表者)競争的環境下の大学における職員の専門職化に関する国際比較研究(科学研究費補助金最終報告書) pp.32-40.(現在で言うところのFD・IRにつながる業務は教務系職員の専門職化だけでは対応できない、大学教育の改善を推進するという明確な目標を備えた組織の開発(その組織が要求する専門性に関して相応しい能力をもった人材の登用、人材の構成(チーム化))が必要;Google Scholar「"institutional research" 職員 重要」で知る)
- Hirsch, W. Z., & Weber, L. (2001). Governance in higher education:The university in a state of flux. London, UK: Economica.(ガバナンスには法令・明文化された規則・正式な議決などに基づく権限配分や権利・義務の設定等だけではなく多様な関係者間の黙示の合意に基礎を置く非公式な行動規範が含まれる、大学が適切に運営されるためには組織文化の理解が図られた上で当該組織文化と組織運営の一連の手順の間に調和が図られていなければならない;大場(2011)「大学のガバナンス改革:組織文化とリーダーシップを巡って」で知る)
- 大場淳(2011).大学のガバナンス改革:組織文化とリーダーシップを巡って 名古屋高等教育研究,11,253-272.[PDF](Google Scholar「組織 理解 納得 推進 大学」で知る)
- 木暮照正(2006).社会貢献・地域連携と大学:その論点整理 生涯学習教育研究センター年報,11,49-52.[PDF](大学の組織構成員は[大学が社会貢献・地域連携に取り組むことの必要性]は理解できても十分に納得して実践するのは難しい、そこで社会貢献・地域連携の必要性に関する理論的な枠組みの構築と多くの人が納得できるようなストーリーが重要になる;Google Scholar「組織 理解 納得 推進 大学」で知る)
- 上杉道世(2009).法人と運営組織の課題 IDE,511,49-55.(大学では露骨な権限行使よりも関係者の納得を重視した物事の進め方が歓迎されている、論理とデータに基づく[説得と納得によるリーダーシップ]は手間と時間はかかる、しかしいったん動き出せば大きな動きを作り出せる;大場(2011)「大学のガバナンス改革:組織文化とリーダーシップを巡って」で知る)
- 松塚ゆかり(2013).IRの組織基盤、実践、スキルミクス:一橋大学IRの事例から 名古屋高等教育研究,13,193-212.[PDF](日本の教学改善に関する取組事例;ブログ「よしなごと」(otani0083さん)の記事で知る)(新しい取組であるIRを行うためにはその活動が組織内で受容され得る環境あるいは条件がある程度整っていなければならない;Google Scholar「組織 理解 納得 推進 大学」で知る)
[2014.11.05]IRなどについての文献メモ 文献一覧を更新
- Campbell, C., & Rozsnyai, C. (2002). Quality assurance and the development of course programmes. Bucharest, Romania: UNESCO-CEPES.[PDF](質保証とは「高等教育の質を担保し、かつ発展するためのあらゆる政策、手順、行動を包含する包括的な用語」;大場(2009)「フランスにおける高等教育の質保証」で知る)
- Van Damme, D. (2002). Quality assurance in an international environment: National and international interests and tensions. In Council for Higher Education Accreditation International quality review: Values, opportunities, and issues. Washington, D.C.: Council for Higher Education Accreditation. pp.3-16.[PDF] (質保証の概念は国によって様々な文脈で用いられ多様な実践を包含する;大場(2009)「フランスにおける高等教育の質保証」で知る)
- Van Damme, D. (2004). Standards and indicators in institutional and programme accreditation in higher education: A conceptual framework and a proposal. In L. Vlasceanu, & L. C. Barrows(Eds.) Indicators for institutional and programme accreditation in higher/tertiary education. Bucharest: UNESCO-CEPES. pp.127-159.[PDF] (質保証は内部質保証と外部質保証に区分される;大場(2009)「フランスにおける高等教育の質保証」で知る)
- 大場淳(2009).フランスにおける高等教育の質保証 羽田貴史・米澤彰純・杉本和弘(編著)高等教育質保証の国際比較 東信堂 pp.177-195.
- 高森智嗣(2014).国立大学法人における大学評価実施体制の現状と課題:「評価室」を中心に 大学評価・学位研究,15,57-67.[PDF]
- 小林雅之・片山英治・劉文君(2011).大学ベンチマークによる大学評価の実証的研究 東京大学大学総合教育研究センター[PDF](日本のIRについての先行研究レビュー、IRの定義について初期にはデータ収集・分析という点が強調されたが現在は戦略計画の策定や大学の変化を促進する役割など定義が広がっている;小林・浅野(2011)で知る)
- 小林雅之・浅野茂(2011).調査の目標と概要 小林雅之(編)大学におけるIR(インスティテューショナル・リサーチ)の現状と在り方に関する調査研究 東京大学 pp.1-15.[PDF](IRの創設国であるアメリカにおいてさえIRには様々な定義・実践活動がある、そのことが日本の教育政策関係者や大学関係者間で共通の理解が得られていない原因となっている)
[2014.11.04]IRなどについての文献メモ 文献一覧を更新
- 橋本智也(2014).内部質保証にIRを活用する:退学要因分析を学生支援につなげる仕組み 第11回言語情報学会口頭発表資料
[2014.11.04]「過去の「お知らせ」」に追加
- 口頭発表「内部質保証にIRを活用する:退学要因分析を学生支援につなげる仕組み」(第11回言語情報学会)
[2014.11.01]IRなどについての文献メモ 文献一覧を更新
- カー,E.H.清水幾太郎(訳)(1962).歴史とは何か 岩波書店(Google「歴史を知る 現代」で知る)
[2014.11.01]IRなどについての文献メモ 文献一覧を更新
- 西内啓(2014).統計学が最強の学問である[実践編]:データ分析のための思想と方法 ダイヤモンド社(Amazon.co.jpレコメンド機能で知る)
[2014.11.01]IRなどについての文献メモ 文献一覧を更新
- 羽田貴史・加藤博和・保坂雅子(1999).中央教育審議会と大学改革 広島大学高等教育研究開発センター[PDF](1960年代に大学進学率が高まる一方で中央教育審議会での議論は4年制大学の規模拡大に慎重であった、第16回特別委員会第6回会議に配布された資料「秘231 大学の設置および組織・編成について」(1961年10月23日)で示された姿勢:大学院と大学の学部は「おおむね現状」を保つ、学生の増加は科学技術系に重点を置く、短期大学の規模を拡大する;羽田(2009)「日本における高等教育の質保証の歴史と課題」で知る)
- 羽田貴史(2009).日本における高等教育の質保証の歴史と課題 羽田貴史・米澤彰純・杉本和弘(編著)高等教育質保証の国際比較 東信堂 pp.21-57.
[2014.10.31]大学に関わる情報メモ 内容をアップ
[2014.10.31]IRなどについての文献メモ 内容をアップ
- 鳥居朋子(2009).教育制度研究情報 教育制度研究動向紹介 高等教育に関する研究動向:質保証システムに注目して 教育制度学研究,16,140-145.[概要](宮浦他(2011)で知る)
- 杉本和弘(研究代表者)(2013).大学における内部質保証システムの再構築と効果的運用に関する国際比較研究(科学研究費助成事業(科学研究費補助金)研究成果報告書)[PDF][概要](Google「質保証 国際比較」で知る)
[2014.10.31]IRなどについての文献メモ 文献一覧を更新
- 広島大学高等教育研究開発センター(編)(2003).21世紀型高等教育システム構築と質的保証 広島大学高等教育研究開発センター(広島大学高等教育研究開発センターサイト内「出版物・出版活動(COE研究シリーズ)」で知る)
- 広島大学高等教育研究開発センター(編)(2007).大学改革における評価制度の研究 広島大学高等教育研究開発センター[PDF](広島大学高等教育研究開発センターサイト内「出版物・出版活動(COE研究シリーズ)」で知る)
- 広島大学高等教育研究開発センター(編)(2007).21世紀型COEプログラム(平成14年度採択)研究教育拠点「21世紀型高等教育システム構築と質的保証」-COE最終報告書-第1部(上) 広島大学高等教育研究開発センター[PDF](広島大学高等教育研究開発センターサイト内「出版物・出版活動」で知る)
- 広島大学高等教育研究開発センター(編)(2007).21世紀型COEプログラム(平成14年度採択)研究教育拠点「21世紀型高等教育システム構築と質的保証」-COE最終報告書-第1部(下) 広島大学高等教育研究開発センター[PDF](広島大学高等教育研究開発センターサイト内「出版物・出版活動」で知る)
- 広島大学高等教育研究開発センター(編)(2007).21世紀型COEプログラム(平成14年度採択)研究教育拠点「21世紀型高等教育システム構築と質的保証」-COE最終報告書-第2部 広島大学高等教育研究開発センター[PDF](広島大学高等教育研究開発センターサイト内「出版物・出版活動」で知る)
- 小方直幸(2007).大学教育の質保証:教育の質保証から学習の質保証へ 広島大学高等教育研究開発センター(編)21世紀型COEプログラム(平成14年度採択)研究教育拠点「21世紀型高等教育システム構築と質的保証」-COE最終報告書-第1部(下) 広島大学高等教育研究開発センター pp.187-193.[PDF](質保証システムとしての学生調査の可能性について検討;鳥居(2009)「教育制度研究情報 教育制度研究動向紹介 高等教育に関する研究動向」で知る)
- 斎藤里美・杉山憲司(編著)(2009).大学教育と質保証:多様な視点から高等教育の未来を考える 明石書店[目次](Amazon.co.jp「質保証」で知る)(高等教育の質保証は3層(教育内容、教育機関、外部/第三者評価)に分かれる;鳥居(2009)「教育制度研究情報 教育制度研究動向紹介 高等教育に関する研究動向」で知る)
- 大学評価・学位授与機構内部質保証システムの構造・人材・知識基盤の開発に関する研究会(2013).教育の内部質保証システム構築に関するガイドライン(案)[PDF](杉本和弘(研究代表者)(2013)で知る)
- OECD(編著)森利枝(訳)(2009).日本の大学改革:OECD高等教育政策レビュー:日本 明石書店(日本の高等教育の質保証のかなりの部分が学外からの推進力や学外からの操縦によって成立している;杉本和弘(2013)で知る)
- 杉本和弘(2013).海外の大学における内部質保証システムについて:米・英・豪・欧州の動向から(教育の内部質保証システム構築に関するセミナー資料)[PDF]
- 高倉翔(2011).第二期の認証評価:自己点検・評価の実質化を IDE:現代の高等教育,528,52-56.(第二期認証評価における「内部質保証」への注目;杉本(2013)「海外の大学における内部質保証システムについて」で知る)
- 大学基準協会(2009).新大学認証評価システム ガイドブック:平成23年以降の大学認証評価システムの概要 大学基準協会[PDF](第二期認証評価における「内部質保証」への注目;杉本(2013)「海外の大学における内部質保証システムについて」で知る)
- 大学評価・学位授与機構(2011).大学機関別認証評価大学評価基準 大学評価・学位授与機構[PDF](第二期認証評価における「内部質保証」への注目;杉本(2013)「海外の大学における内部質保証システムについて」で知る)
[2014.10.30]IRなどについての文献メモ 内容をアップ
- 羽田貴史(2005).高等教育の質保証の構造と課題:質保証の諸概念とアクレディテーション 広島大学高等教育研究開発センター(編)高等教育の質的保証に関する国際比較研究 広島大学高等教育研究開発センター pp.1-13.[PDF][内容](舘(2010)で知る)
[2014.10.30]IRなどについての文献メモ 文献一覧を更新
- 広島大学高等教育研究開発センター(編)(2005).高等教育の質的保証に関する国際比較研究 広島大学高等教育研究開発センター[PDF]
- 羽田貴史(2005).日本の高等教育における質保証の歴史と課題 広島大学高等教育研究開発センター(編)高等教育の質的保証に関する国際比較研究 広島大学高等教育研究開発センター pp.15-39.[PDF](舘(2010)で知る)
- Schwarz, S., & Westerheijden, Don F. (2004). Preface In Stefanie Schwarz & Don F. Westerheijden(Eds.) Accreditation and evaluation in the European higher education area. Dordrecht: Springer. pp.ix-xii.(高等教育の質とは学生に対して提供する学位のための教育と研究そしてそれを支える運営と行政に関連する広範囲な概念)[PDF](羽田(2005)「日本の高等教育における質保証の歴史と課題」で知る)
- 喜多村和之(編)(2000).高等教育と政策評価 玉川大学出版部(Amazon.co.jp「行政評価 歴史」で知る)
[2014.10.30]IRなどについての文献メモ 文献一覧を更新
[2014.10.29]IRなどについての文献メモ 内容をアップ
- 舘昭(2010).ボローニャ・プロセスの意義に関する考察:ヨーロッパ高等教育圏形成プロセスの提起するもの 名古屋高等教育研究,10,161-180.[PDF][内容](CiNii Articles「舘昭」で知る)
[2014.10.29]IRなどについての文献メモ 文献一覧を更新
- リチャード,L.吉川裕美子(訳)(2005).講演録:ボローニャ宣言:ヨーロッパ高等教育の学位資格と質保証の構造への影響 大学評価・学位研究,3,75-90.[PDF](Google「ボローニャ宣言 質保証」で知る)
[2014.10.28]IRなどについての文献メモ 文献一覧を更新
- 高森智嗣(2014).日本におけるインスティテューショナル・リサーチへの認識に関する研究:国立大学法人に対するアンケート調査結果を中心に 大学探究,5,1-11.[PDF](Google Scholarアラート「インスティテューショナル・リサーチ」で知る)
[2014.10.28]IRなどについての文献メモ 内容をアップ
- 中島英博(2010).経営支援機能としての経営情報システムの必要性に関する実証分析:米国のインスティテューショナル・リサーチに注目して 高等教育研究,13,115-128.(沖・岡田(編著)(2011).『データによる大学教育の自己改善:インスティテューショナル・リサーチの過去・現在・展望』で知る)[内容]
[2014.10.28]大学に関わる情報メモ 内容をアップ
[2014.10.27]IRなどについての文献メモ 文献一覧を更新
- American Institutes for Research (2014). College persistence indicators research review. [PDF](Google Scholar「withdraw retention」で知る)
[2014.10.27]IRなどについての文献メモ 文献一覧を更新
- 羽田貴史・米澤彰純・杉本和弘(編著)(2009).高等教育質保証の国際比較 東信堂
- 鳥居朋子(2009).教育制度研究情報 教育制度研究動向紹介 高等教育に関する研究動向:質保証システムに注目して 教育制度学研究,16,140-145.(宮浦他(2011)で知る)
- 山田勉(2013).質保証は絵空事か:第2期認証評価実践上の課題 大学評価研究,12,45-58.[PDF](CiNii Articles「質保証制度」で知る)
- 川嶋太津夫(2012).進化する日本の認証評価制度 カレッジマネジメント,30(1),6-13.(CiNii Articles「質保証制度」で知る)
- 納谷廣美(2011).新時代を迎えて:これからの認証評価制度について IDE,533,22-27.(CiNii Articles「質保証制度」で知る)
- 林透(2010).高等教育質保証システムの揺らぎ:認証評価制度導入期を中心に 大学行政管理学会誌,14,93-101.(CiNii Articles「質保証制度」で知る)
- 荻上紘一(2009).認証評価制度の問題点とこれからの改革の方向 大学評価研究,8,43-51.(CiNii Articles「質保証制度」で知る)
- 伊藤昇(2009).認証評価制度と国立大学法人評価制度における大学の改善・改革:自己点検・評価の高度化と「大学評価文化」の定着を目指して 大学行政研究,4,187-235.(CiNii Articles「質保証制度」で知る)
- 安岡高志(2008).認証評価制度の問題点と将来の方向性:コンプライアンス主義に陥るな 大学時報,57(319),92-95.(CiNii Articles「質保証制度」で知る)
- 奈良哲(2005).認証評価制度の概要 京都大学高等教育研究,11,105-109.[PDF](CiNii Articles「質保証制度」で知る)
- 舘昭(2005).国際的通用力を持つ大学評価システムの構築:「認証評価」制度の意義と課題 大学評価・学位研究,3,3-19.(CiNii Articles「質保証制度」で知る)
- 文部科学省高等教育局高等教育企画課(2005).認証評価制度について 文部科学時報,1548,50-59.(CiNii Articles「質保証制度」で知る)
- 山崎その(2005).認証評価制度の現状と課題 大学行政管理学会誌,9,91-104.(CiNii Articles「質保証制度」で知る)
- 山本淳司(2005).認証評価制度の実態と職員の専門化・高度化 大学行政管理学会誌,9,105-118.(CiNii Articles「質保証制度」で知る)
- 舘昭(2004).大学の評価と質の保証:「認証評価」制度の意義と課題 現代の高等教育,464,10-18.(CiNii Articles「質保証制度」で知る)
- 早田幸政(2003).認証評価制度のインパクト:アメリカの「教育長官認証」の紹介を兼ねて 高等教育研究,6,105-129.(CiNii Articles「質保証制度」で知る)
- 林透(2014).高等教育における視学委員制度の研究:認証評価制度のルーツを探る 東信堂(CiNii Books「質保証制度」で知る)
- 斎藤里美・杉山憲司(編著)(2009).大学教育と質保証:多様な視点から高等教育の未来を考える 明石書店[目次](Amazon.co.jp「質保証」で知る)
- 舘昭(2011).質保証の国際動向:QFの世界的な展開と質保証 IDE,533,56-61.(CiNii Articles「舘昭」で知る)
- 舘昭(2011).「国際教育標準分類」(ISCED)の対象と構成について:日本の高等教育統計への示唆 桜美林高等教育研究,3,89-97.(CiNii Articles「舘昭」で知る)
- 舘昭(2010).「国際基準」からみた日本の大学統計情報の問題点:ISCEDと学校基本調査との比較から IDE ,522,42-47.(CiNii Articles「舘昭」で知る)
- 舘昭(2010).ボローニャ・プロセスの意義に関する考察:ヨーロッパ高等教育圏形成プロセスの提起するもの 名古屋高等教育研究,10,161-180.[PDF](CiNii Articles「舘昭」で知る)
- 舘昭(2010).ボローニャ・プロセスと欧州高等教育改革 IDE,518,44-51.(CiNii Articles「舘昭」で知る)
- 舘昭(2009).ボローニャ・プロセスと「大学院」:高等教育グローバル化の新機軸と学位システム IDE,512,45-51.(CiNii Articles「舘昭」で知る)
- 舘昭(2008).いまなぜ学士課程教育か:必要とされる学校観,教育観の転換 IDE,505,53-58.(CiNii Articles「舘昭」で知る)
- 舘昭(2008).変貌する短期高等教育:コミュニティ・カレッジとしての再生に向けて IDE,501,4-9.(CiNii Articles「舘昭」で知る)
- 舘昭(2008).大学教育の質保証のための教育システムづくり:単位制度と成績評価 大阪市立大学大学教育,5(2),65-77.(CiNii Articles「舘昭」で知る)
- 舘昭(2007).改めて「大学制度とは何か」を問う 東信堂(Google「改めて「大学制度とは何か」を問う」で知る)
- 大学基準協会(2009).新大学認証評価システム ガイドブック:平成23年以降の大学認証評価システムの概要 大学基準協会[PDF]
- 大学基準協会(2013).大学評価ハンドブック 2014(平成26)年度 申請大学用 大学基準協会[PDF]
[2014.10.26]IRなどについての文献メモ 文献一覧を更新
- 沖裕貴(2014).カリキュラムの整合性、体系性・系統性って何?:なぜ、カリキュラム・マップやツリーが必要なのか、どうして作ればいいのか ニュースレター,31,1-3.[PDF](Google「カリキュラムマップ 質保証」で知る)
- 沖裕貴(2007).観点別教育目標から考えるカリキュラム・ポリシーの構造:理念・目標、ディプロマ・ポリシー、シラバスとの関連において 立命館高等教育研究,7,61-74.[PDF](Google「カリキュラムマップ 質保証」で知る)
[2014.10.26]IRなどについての文献メモ 文献一覧を更新
[2014.10.22]ホーム「お知らせ」欄を変更
- 口頭発表「内部質保証のために学修時間の質・量を向上させる仕組み:データに基づく検証システム(IR)と組織的な改善活動」(第21回大学教育研究フォーラム)を掲載
[2014.10.20]IRなどについての文献メモ 文献一覧を更新
- 佐渡島紗織(2014).アカデミック・ライティング教育と情報リテラシー:《情報を再定義》し意見を構築できる学生を育てる 情報の科学と技術,64(1),22-28.[PDF](CiNii Articles「アカデミックライティング」で知る)
- 西垣順子(2011).大学におけるライティング教育をめぐる心理学研究の役割:アカデミックライティング教育の現状に対する批判的検討を踏まえて 心理科学,32(1),1-8.[PDF](CiNii Articles「アカデミックライティング」で知る)
- 佐渡島紗織(2011).日本におけるアカデミック・ライティングへの取り組み インターナショナルナーシング・レビュー,34(3),24-33.(CiNii Articles「アカデミックライティング」で知る)
- Skier, E. M.原田裕子(訳)(2011).アメリカにおけるアカデミック・ライティング教育 インターナショナルナーシング・レビュー,34(3),16-22.(CiNii Articles「アカデミックライティング」で知る)
- Swales, J. M., & Freak, C. B. (2012). Academic writing for graduate students: Essential tasks and skills. Ann Arbor, MI: University of Michigan Press.(Google Scholar「academic writing」で知る)
- Paltridge, B., Harbon, L., Hirsh, D., Shen, H., Stevenson, M., Phakiti, A., & Woodrow, L. (2009). Teaching academic writing: An itroduction for teachers of second language writers.Ann Arbor, MI: University of Michigan Press.(Google Scholar「academic writing」で知る)
- Paltridge, B. (2004). Academic writing. Language teaching, 37(2), 87-105.(Google Scholar「academic writing」で知る)
[2014.10.19]IRなどについての文献メモ 文献一覧を更新
- Hossler, D., Bontrager, B., & Associates (2014). Handbook of strategic enrollment management. San Francisco: Jossey-Bass. [Table of Contents](Google Scholarアラート「"institutional research"」で知る)
[2014.10.15]大学に関わる情報メモ 内容を修正
[2014.10.10]大学に関わる情報メモ 内容をアップ
[2014.10.10]IRなどについての文献メモ 文献一覧を更新
- 森藤大地・あんちべ(2014).エンジニアのためのデータ可視化「実践」入門:D3.jsによるWebの可視化 技術評論社
[2014.10.10]IRなどについての文献メモ 文献一覧を更新
[2014.10.10]IRなどについての文献メモ 文献一覧を更新
- Rickinson, B., & Rutherford, D. (1995). Increasing undergraduate student retention rates. British journal of guidance & counselling, 23(2), 161-172.[Abstract]([1年生の最初の学期における退学・在籍率]に影響する要因について質問紙を使って調査した、1年生の最初の学期に退学する恐れがある学生に対してカウンセリングが有効かも調査した;Google Scholar「"retention rates" withdrawal」で知る)
- Murtaugh, P. A., Burns, L. D., & Schuster, J. (1999). Predicting the retention of university students. Research in higher education, 40(3), 355-371.[Abstract](オレゴン州立大学の学生約9,000人(5年間)を対象にした在籍状況の分析、年齢が高くなるにつれて減員が大きくなっていた、高校のGPA・大学第1学期のGPAが高くなるにつれて減員が小さくなっていた、Freshman Orientation Courseの参加者は退学リスクが減少していると思われる;Google Scholar「"retention rates" withdrawal」で知る)
- Dunwoody, P. T., & Frank, M. L. (1995). Why students withdraw from classes. The journal of psychology, 129(5), 553-558.[Abstract](教員30名と学生151名が[考えられる退学理由として挙げられた15項目]を評価した、教員と学生では評価が異なっていた、学生よりも教員の方が[個人的理由による退学]を重要と評価した、その他の結果も含めて今回の結果から示唆されること:退学理由についてより多くの情報を教員にフィードバックすべきである;Google Scholar「"retention rates" withdrawal」で知る)
- Simpson, O. (2004). The impact on retention of interventions to support distance learning students. Open learning: The journal of open, distance and e-Learning, 19(1), 79-95.[Abstract](遠隔教育の学生を対象にした積極的な介入がどのように在籍状況に影響を与えるか、どのような学生を介入の対象にするか、どのようなメディアを使うか;Google Scholar「"retention rates" withdrawal」で知る)
- Smith, J. P., & Naylor, R. A. (2001). Dropping out of university: a statistical analysis of the probability of withdrawal for UK university students. Journal of the royal statistical society: Series a (Statistics in society), 164(2), 389-405.[Abstract](フルタイムの学生を調査して退学する可能性を見積もった、以下の2つの仮説を支持する証拠が得られた:1.退学せずに学期を終えられるかは学業の準備がどのくらいできているかが影響する、2.大学での「社会的統合」が重要;Google Scholar「"retention rates" withdrawal」で知る)
[2014.10.02]IRなどについての文献メモ 文献一覧を更新
- 金明秀(2008).エンロールメント・マネジメントと教育実践の融合:京都光華女子大学を事例として 京都光華女子大学研究紀要,46,251-296.[PDF]
- 金明秀(2009).日本におけるエンロールメント・マネジメントの展開(2)米国の課題と日本の可能性 私学経営,413,32-44.[PDF]
- 金明秀(2009).日本におけるエンロールメント・マネジメントの展開(3)京都光華女子大学における個別対応教育モデルとの融合実践 私学経営,414,34-45.[PDF]
- 山本嘉一郎(2013).エンロールメント・マネジメントを効果的に進めるためのIR について 京都光華女子大学研究紀要,51,89-98.[PDF]
- 山田剛史(2012).組織的活動の評価:大学評価・質保証文脈におけるIRの展開 京都大学高等教育研究開発推進センター(編)生成する大学教育学 ナカニシヤ出版 pp. 201-215.
[2014.10.02]IRなどについての文献メモ 文献一覧を更新
- 安西祐一郎(2012).主体的に学ぶ IDE:現代の高等教育,543,5-10.
- 佐々木雄太(2012).主体的な学びの回復のために IDE:現代の高等教育,543,11-16.
- 金子元久(2012).自律的学習への道 IDE:現代の高等教育,543,16-22.
- 舘昭(2012).「研究」を組み込んでこそ大学での学び:教育国際分類(ISCED)2011年版の示唆するもの IDE:現代の高等教育,543,
- 吉田文(2012)カリキュラムの体系化は可能か:学修時間の確保のために IDE:現代の高等教育,543,30-36.
- 猪口孝(2012).現代学生の学習:学生の勇気,教師のパワーアップが学生の学力向上の鍵である IDE:現代の高等教育,543,37-40.
- 小笠原正明(2012).主体的学びのパラドックス:理工系学士過程を中心に IDE:現代の高等教育,543,41-45.
- 居神浩(2012).学生の多様化に対応した学修支援 IDE:現代の高等教育,543,45-49.
- 島田博司(2012).主体的な学びを仕掛ける授業づくり:ライフスキルの育成 IDE:現代の高等教育,543,49-53.
- 山田礼子(2012).継続調査からみえてくる学生の現状:学修時間、ラーニング・アウトカムズを中心に IDE:現代の高等教育,543,57-64.
- 小方直幸(2012).大学教員の授業への構え IDE:現代の高等教育,543,64-70.
- 松本美奈(2012).学生は学習している IDE:現代の高等教育,543,53-56.
- 日本私立大学協会教育学術新聞(編)(2012).教授法が大学を変える2012年度版 日本私立大学協会[PDF]
- 日本私立大学協会教育学術新聞(編)(2013).教授法が大学を変える2013年度版 日本私立大学協会[PDF]
[2014.10.02]IRなどについての文献メモ 文献一覧を更新
- 根本啓一・高橋正道・林直樹・堀田竜士(2012).ワールドカフェ型のダイアログにおけるターンテイキング構造と参加者の理解度の関係性の分析 電子情報通信学会技術研究報告.LOIS,112(35),113-120.[PDF]
[2014.10.02]IRなどについての文献メモ 文献一覧を更新
- 所由紀(1999).会社経営にとって組織とは何か? 近代中小企業,34(8),7-13.
- 所由紀(1999).他社の組織図を研究しよう! 近代中小企業,34(8),14-23.
- 所由紀(1999).元気な会社〔(株)朝日ラバー〕の組織図に学ぼう! 近代中小企業,34(8),24-27.
[2014.10.01]IRなどについての文献メモ 文献一覧を更新
- 大工原孝(2012).IRとURA:新しい大学事務の展望 大学事務組織研究,3,61-77.
- 佛淵孝夫(2014).大学版IRについて:経営改善と改革のツールとして 大学行政管理学会誌,17,3-15.
[2014.10.01]IRなどについての文献メモ 文献一覧を更新
- 中村博幸(2007).接続教育と教育連携:高大接続と高大連携を中心に 人間学部研究報告,10,133-141.[PDF]
- 中條安芸子(2009).高大連携で問われる地域の教育力 情報研究,41,1-10.[PDF]
- 爲近勝(2004).高等学校学習指導要領を中心にみた教育の改善と高大連携 大学教育,10,155-168.
- 小棹理子・伊藤善隆・藤澤みどり・高橋可奈子・岩崎敏之・住谷勉・原満・三橋健彦・宮地妃佐子・石田英弥(2008).高大連携による接続教育プログラム開発の試み 湘北紀要,29,9-18.[PDF]
- 中條安芸子(2008).共同運営型の高大連携システムづくりに関する一考察:キャリア教育の視点から見た高校と大学との連携のあり方 情報研究,39,185-193.[PDF]
- 天野郁夫(2012).高校教育・入学者選抜・大学教育 IDE:現代の高等教育,539,4-13.
- 及川良一(2012).高校と大学との最適な関係 IDE:現代の高等教育,539,13-17.
- 千葉吉裕(2012).高校から見た大学進学 IDE:現代の高等教育,539,18-22.
- 耳塚寛明(2012).多様化の中の質保証:高校教育政策の新局面 IDE:現代の高等教育,539,23-27.
- 佐々木隆生(2012)高大接続テストの可能性 IDE:現代の高等教育,539,27-31.
- 川目俊哉(2012).学び方選びへのパラダイム転換 IDE:現代の高等教育,539,32-36.
- 松本美奈(2012).大学の情報は高校生に届いているか IDE:現代の高等教育,539,36-40.
- 太田光一(2012).推薦入試合格者のリメディアル教育 IDE:現代の高等教育,539,40-44.
- 井下理(2012).新入生の適応と適応支援 IDE:現代の高等教育,539,45-49.
- 濱名篤(2012).初年次教育の効果を考える:アメリカと日本の現状 IDE:現代の高等教育,539,50-55.
- 鈴木敏之(2012).秋季入学とギャップイヤー IDE:現代の高等教育,539,56-60.
- 花崎美紀・杉山裕司・花崎一夫・橋本功(2006).地域価値を高める双方向高大連携の試み 地域ブランド研究,2,145-168.[PDF]
[2014.09.29]「私立大学職員によるIR文献メモ」メルマガ バックナンバーを更新
[2014.09.27]IRなどについての文献メモ 文献一覧を更新
- 日本インダストリアルデザイナー協会(編)(2009).プロダクトデザイン:商品開発に関わるすべての人へ ワークスコーポレーション(黒須他(編)(2013)で知る)
- 黒須正明・堀部保弘・平沢尚毅・三樹弘之(2001).ISO13407がわかる本 オーム社(黒須他(編)(2013)で知る)
- ラプトン,E.,マカーティ,M.,マケイド,M.,&スミス,C.E.北村陽子(訳)(2012).なぜデザインが必要なのか:世界を変えるイノベーションの最前線 英治出版(Amazon.co.jp「プロダクトデザイン」で知る)
- 原研哉(2003).デザインのデザイン 岩波書店(Amazon.co.jp「プロダクトデザイン」で知る)
- サマラ,T.郷司陽子・戸崎順子(訳)(2004). グラフィックデザイナーのためのレイアウトデザインの法則 毎日コミュニケーションズ(Amazon.co.jp「プロダクトデザイン」で知る)
- IDSA,ハラー,L.,&チェリルC.D.(編)山田聡子・バベル(訳)(2005).アイデア&プロセスの法則プロダクトデザイン 毎日コミュニケーションズ(Amazon.co.jp「プロダクトデザイン」で知る)
[2014.09.27]IRなどについての文献メモ 文献一覧を更新
- オズボーン,A.F.上野一郎(訳)(1982).独創力を伸ばせ ダイヤモンド社(ラプトン(2012)で知る)
- デボノ,E.白井実(訳)(1971).水平思考の世界:電算機時代の創造的思考法 講談社(ラプトン(2012)で知る)
- コバーク,D.&バグナル,J.稲垣行一郎(訳)(1973).固定観念を打ち破ればどんな問題でも解決できる 産業能率大学出版部(ラプトン(2012)で知る)
- ケリー,T.&リットマン,J.鈴木主税・秀岡尚子(訳)(2002).発想する会社!:世界最高のデザイン・ファームIDEOに学ぶイノベーションの技法 早川書房(ラプトン(2012)で知る)
- Kimberly, E. バベル(訳)(2012).Balance in design:美しくみせるデザインの原則 ビー・エヌ・エヌ新社(ラプトン(2012)で知る)
[2014.09.24]IRなどについての文献メモ 内容をアップ
- 岡田聡志(2009).私立大学におけるInstitutional Researchの実態と意識-大学類型との関連性 大学教育学会誌,31(2),116-122.[内容]
[2014.09.18]「過去の「お知らせ」」に追加
- ポスター発表「正課とラーニングコモンズをつなぐ:学科の要望と学修支援内容の接続、IRの活用」(高等教育質保証学会第4回大会)
- 口頭発表「初年次教育の添削課題における「学習行動の改善を促す報告書」の開発:学生・教員の要望の組み入れとIRの活用」(初年次教育学会第7回大会)
- 口頭発表「どうすれば教職員の考えをインスティテューショナルリサーチ(IR)につなげられるか」(大学行政管理学会第18回(2014年度)定期総会・研究集会)
[2014.09.17]IRなどについての文献メモ 文献一覧を更新
- 宇野昇平・木村茂・國時誠・黒崎敏・戸恒浩人・鳥村鋼一・藤原佐知子・武藤智花・渡邊謙一郎(2014).腕のいいデザイナーが必ずやっている仕事のルール125 エクスナレッジ(フタバプラス(京都マルイ)書架で知る)
[2014.09.09]大学に関わる情報メモ 内容をアップ
[2014.09.09]IRなどについての文献メモ 文献一覧を更新
- 仲畑貴志(編)(2005).万能川柳デラックス1000 毎日新聞社(Amazon.co.jp「仲畑貴志」で知る)
- 仲畑貴志(2002).コピーのぜんぶ:仲畑貴志全コピー集 宣伝会議(Amazon.co.jp「仲畑貴志」で知る)
- 仲畑貴志(2008).みんなに好かれようとして、みんなに嫌われる。(勝つ広告のぜんぶ) 宣伝会議(Amazon.co.jp「仲畑貴志」で知る)
- 仲畑貴志(2008).ホントのことを言うと、よく、しかられる。(勝つコピーのぜんぶ) 宣伝会議(Amazon.co.jp「仲畑貴志」で知る)
- 糸井重里(1988).糸井重里の万流コピー塾 文芸春秋(Amazon.co.jp「糸井重里」で知る)
[2014.09.09]IRなどについての文献メモ 文献一覧を更新
- ミュラティアン,V.阿部寿美代(訳)(2013).パリ・ヴァーサス・ニューヨーク:二つの都市のヴィジュアル・マッチ ビー・エヌ・エヌ新社(狐塚(2013)で知る)
[2014.09.08]ホーム「お知らせ」欄を変更
- 口頭発表「どうすれば教職員の考えをインスティテューショナルリサーチ(IR)につなげられるか」(大学行政管理学会第18回(2014年度)定期総会・研究集会) 資料集のページ数を掲載
[2014.09.08]IRなどについての文献メモ 文献一覧を更新
- 橋本智也(2014).正課とラーニングコモンズをつなぐ:学科の要望と学修支援内容の接続、IRの活用 高等教育質保証学会第4回大会発表資料集,113.
- 橋本智也(2014).初年次教育の添削課題における「学習行動の改善を促す報告書」の開発:学生・教員の要望の組み入れとIRの活用 初年次教育学会第7回大会発表要旨集,60-61.
- 橋本智也(2014).どうすれば教職員の考えをインスティテューショナルリサーチ(IR)につなげられるか 2014(平成26)年度大学行政管理学会第18回定期総会・研究集会資料集,107-108.
[2014.09.08]IRなどについての文献メモ 文献一覧を更新
- ヘレーン,F.鍋野和美(監訳)・鍋野和美(訳)(2005).スウェーデン式アイデア・ブック ダイヤモンド社(Amazon.co.jpレコメンド機能で知る)
- 嶋浩一郎(2007).嶋浩一郎のアイデアのつくり方 ディスカヴァー・トゥエンティワン(Amazon.co.jpレコメンド機能で知る)
- 高橋宣行(2013).キーメッセージのつくり方:「想い」を言葉化する ディスカヴァー・トゥエンティワン(Amazon.co.jpレコメンド機能で知る)
- フォスター,J.青島淑子(訳)(1999).アイデアのヒント TBSブリタニカ(Amazon.co.jpレコメンド機能で知る)
[2014.09.05]ホーム「お知らせ」欄を変更
- 口頭発表「初年次教育の添削課題における「学習行動の改善を促す報告書」の開発:学生・教員の要望の組み入れとIRの活用」(初年次教育学会第7回大会) 発表要旨集のページ数を掲載
[2014.08.29]ホーム「お知らせ」欄を変更
- ポスター発表「正課とラーニングコモンズをつなぐ:学科の要望と学修支援内容の接続、IRの活用」(高等教育質保証学会第4回大会) 資料集のページ数を掲載
[2014.08.29]IRなどについての文献メモ 文献一覧を更新
- Keup, J. R., & Kilgo, C. A. (2014). Conceptual considerations for first-year assessment. New directions for institutional research, 160, 5-18.(New Directions for Institutional Researchのcontent alertで知る)
- Tukibayeva, M., & Gonyea, R. M. (2014). High-impact practices and the first-year student. New directions for institutional research, 160, 19-35.(New Directions for Institutional Researchのcontent alertで知る)
- Goodman, K. M. (2014). Good practices for whom? A vital question for understanding the first year of college. New directions for institutional research, 160, 37-51.(New Directions for Institutional Researchのcontent alertで知る)
- DeAngelo, L. (2014). Programs and practices that retain students from the first to second year: Results from a national study. New directions for institutional research, 160, 53-75.(New Directions for Institutional Researchのcontent alertで知る)
- Bers, T., & Younger, D. (2014). The first-year experience in community colleges.New directions for institutional research, 160, 77-93.(New Directions for Institutional Researchのcontent alertで知る)
[2014.08.29]IRなどについての文献メモ 文献一覧を更新
- 西内啓(2013).統計学が最強の学問である ダイヤモンド社(Amazon.co.jpレコメンド機能で知る)
[2014.08.29]IRなどについての文献メモ 文献一覧を更新
- 小田博志(2010).エスノグラフィー入門:「現場」を質的研究する 春秋社(酒井(2010)で知る)
[2014.08.28]IRなどについての文献メモ 文献一覧を更新
- 狐塚康己(2013).図説アイデア入門:言葉、ビジュアル、商品企画を生み出す14法則と99の見本 宣伝会議(宣伝会議書籍案内で知る)
- Martin, B., & Hanington, B.郷司陽子(訳)(2013).Research & design method index:リサーチデザイン、新・100の法則 ビー・エヌ・エヌ新社(Lankow et al.浅野(訳)(2013)で知る)
- ラプトン.E.(編)郷司陽子(訳)(2012).問題解決ができる、デザインの発想法 ビー・エヌ・エヌ新社(Amazon.co.jpレコメンド機能で知る)
- 秋元康(2009).企画脳 PHP研究所(木村(2012)で知る)
[2014.08.23]IRなどについての文献メモ 文献一覧を更新
- Few, S. (2012). Show me the numbers: Designing tables and graphs to enlighten. Burlingame, Calif: Analytics Press.(Lankow et al.浅野(訳)(2013)で知る)
[2014.08.22]IRなどについての文献メモ 文献一覧を更新
- 樽本徹也(2014).ユーザビリティエンジニアリング:ユーザエクスペリエンスのための調査、設計、評価手法 オーム社(Amazon.co.jpレコメンド機能で知る)
- 黒須正明・松原幸行・八木大彦・山崎和彦(編)黒須正明(著)(2013).人間中心設計の基礎 近代科学社(Amazon.co.jpレコメンド機能で知る)
[2014.08.22]IRなどについての文献メモ 文献一覧を更新
- 米盛裕二(2007).アブダクション:仮説と発見の論理 勁草書房(棚橋(2009)で知る)
- 木村健太郎・磯部光毅(2013).ブレイクスルーひらめきはロジックから生まれる 宣伝会議(Amazon.co.jpレコメンド機能で知る)
- 市川伸一(1997).考えることの科学:推論の認知心理学への招待 中央公論社(Amazon.co.jpレコメンド機能で知る)
- 木谷哲夫(2012).成功はすべてコンセプトから始まる:「思い」を「できる」に変える仕事術 ダイヤモンド社(Amazon.co.jpレコメンド機能で知る)
- 酒井穣(2013).これからの思考の教科書:論理・直感・統合:ビジネスに生かす3つの考え方 光文社(Amazon.co.jpレコメンド機能で知る)
[2014.08.22]IRなどについての文献メモ 文献一覧を更新
- 嶋田学(2011).地域を活性化させる図書館活動とは:公共図書館政策と東近江市立図書館の実践 図書館界,63(1),16-23.[PDF]
[2014.08.08]IRなどについての文献メモ 文献一覧を更新
- Lankow, J., Ritchie, J., & Crooks, R.浅野紀予(訳)(2013).ビジュアル・ストーリーテリング:インフォグラフィックが切り拓くビジネスコミュニケーションの未来 ビー・エヌ・エヌ新社(丸善丸の内本店書架で知る)
- 高橋佑磨・片山なつ(2014).伝わるデザインの基本:よい資料を作るためのレイアウトのルール 技術評論社(丸善丸の内本店書架で知る)
- 棚橋弘季(2009).デザイン思考の仕事術:ひらめきを計画的に生み出す 日本実業出版社(丸善丸の内本店書架で知る)
[2014.08.08]IRなどについての文献メモ 文献一覧を更新
- ドーリー,S.,&ウィットフト,S.藤原朝子(訳)(2012).メイク・スペース:スタンフォード大学dスクールが実践する創造性を最大化する「場」のつくり方 阪急コミュニケーションズ(Amazon.co.jpレコメンド機能で知る)
[2014.08.07]ホーム「お知らせ」欄を変更
- ポスター発表「正課とラーニングコモンズをつなぐ:学科の要望と学修支援内容の接続、IRの活用」(高等教育質保証学会第4回大会)を掲載
[2014.08.07]IRなどについての文献メモ 文献一覧を更新
- Borden, V. M. H., & Pike, G. R.(Eds.)(2009). Assessing and accounting for student learning: Beyond the spellings commission. New directions for institutional research, Assessment supplement 2007.(Amazon.co.jp「institutional research」で知る)
- Burke, J. C., & Minassians, H. P.(Eds.)(2003). Reporting higher education results: Missing links in the performance chain. New directions for institutional research, 116.(Amazon.co.jp「institutional research」で知る)
- Gaither, G. H.(Ed.)(1998). Quality assurance in higher education: An international perspective. New directions for institutional research, 99.(Amazon.co.jp「institutional research」で知る)
- Harper, S. R., & Museus, S. D.(Eds.)(2008). Using qualitative methods in institutional assessment. New directions for institutional research, 136.(Amazon.co.jp「institutional research」で知る)
- Herzog, S.(Ed.)(2010). Diversity and education benefits. New directions for institutional research, 145.(Amazon.co.jp「institutional research」で知る)
- Howard, R. D., & Borland Jr, K. W.(Eds.)(2002). Balancing qualititative and quantitative information for effective decision support. New directions for institutional research, 112.(Amazon.co.jp「institutional research」で知る)
- Ishitani, T. T.(Ed.)(2008). Alternative perspectives in institutional planning. New directions for institutional research, 137.(Amazon.co.jp「institutional research」で知る)
- John, E. P. St., & Wilkerson, M.(Eds.)(2006). Reframing persistence research to improve academic success. New directions for institutional research, 130.(Amazon.co.jp「institutional research」で知る)
- Levy, G. D., & Valcik, N. A.(Eds.)(2012). Benchmarking in institutional research. New directions for institutional research, 156.(Amazon.co.jp「institutional research」で知る)
- Luan, J., & Zhao, C. M.(Eds.)(2006). Data mining in action: Case studies of enrollment management. New directions for institutional research, 131.(Amazon.co.jp「institutional research」で知る)
- Mullin, C. M., Bers, T., & Hagedorn, L. S.(Eds.)(2012). Data use in the community college. New directions for institutional research, 153.(Amazon.co.jp「institutional research」で知る)
- Penn, J. D.(Ed.)(2011). Assessing complex general education student learning outcomes. New directions for institutional research, 149.(Amazon.co.jp「institutional research」で知る)
- Seifert, T. A.(Ed.)(2011). Longitudinal assessment for institutional improvement. New directions for institutional research, Assessment supplement 2010.(Amazon.co.jp「institutional research」で知る)
- Terkla, D. G.(Ed.)(2008). Institutional research: More than just data. New directions for institutional research, 141.(Amazon.co.jp「institutional research」で知る)
- Toutkoushian, R. K., & Massa, T. R.(Eds.)(2009). Conducting institutional research in non-campus-based settings. New directions for institutional research, 139.(Amazon.co.jp「institutional research」で知る)
- Toutkoushian, R. K., & Paulsen, M. B.(Eds.)(2007). Applying economics to institutional research. New directions for institutional research, 132.(Amazon.co.jp「institutional research」で知る)
- Volkwein, J. F.(Ed.)(1999). What is institutional research all about? A critical and comprehensive assessment of the profession. New directions for institutional research, 104.(Amazon.co.jp「institutional research」で知る)
- Volkwein, J. F.(Ed.)(2010). Assessing student outcomes: Why, who, what, how. New directions for institutional research, Assessment supplement 2009.(Amazon.co.jp「institutional research」で知る)
- Voorhees, R. A.(Ed.)(1997). Researching student aid: Creating an action agenda. New directions for institutional research, 95.(Amazon.co.jp「institutional research」で知る)
- Voorhees, R. A.(Ed.)(2001). Measuring what matters: Competency-based learning models in higher education. New directions for institutional research, 110.(Amazon.co.jp「institutional research」で知る)
[2014.08.07]IRなどについての文献メモ 文献一覧を更新
- 嶋田学(2004).アグレッシブな配架の研究:思わず手が出る棚作りとディスプレイ 図書館評論,45,41-50.(Googleアラート「図書館」で知る)
[2014.08.06]IRなどについての文献メモ 文献一覧を更新
- 日本リメディアル教育学(監修)(2012).大学における学習支援への挑戦:リメディアル教育の現状と課題 ナカニシヤ出版(Amazon.co.jp「リメディアル教育」で知る)
- 山内乾史(編著)(2012).学生の学力と高等教育の質保証Ⅰ 学文社(Amazon.co.jp「リメディアル教育」で知る)
- 山内乾史・原清治(編著)(2014).学生の学力と高等教育の質保証Ⅱ 学文社(Amazon.co.jp「リメディアル教育」で知る)
- 佐々木英洋(2014).大手前短期大学におけるリメディアル教育【数学・基礎】の実施報告(7) 大手前短期大学研究集録,33,39-53.(CiNii Articles「リメディアル教育」で知る)
- 高橋京子(2013).十文字学園女子大学におけるリメディアル教育の取り組み 私学経営,465,34-39.(CiNii Articles「リメディアル教育」で知る)
- 森田雅義(2013).「学力低下」は本当か?:英語基礎力テストから見えてくるもの 歯科学報,113(2),178-184.[PDF](CiNii Articles「リメディアル教育」で知る)
- 廣瀬史典・上之薗和宏・古宮誠一(2013).リメディアル教育のためのCAIシステム:学習者モデルと不得意分野探索アルゴリズム 電子情報通信学会技術研究報告.KBSE,知能ソフトウェア工学,112(496),97-102.[PDF](CiNii Articles「リメディアル教育」で知る)
- 柳沢昌義・久保田まり・秋本倫子・下坂英(2013).リメディアル教育の実践及び携帯ポータルサイトを用いた読書活動の必修化の効果 日本教育工学会研究報告集,13(1),63-70.(CiNii Articles「リメディアル教育」で知る)
- 鈴木崇義(2013).相談事例からみる学修支援の現状と課題についての覚書 國學院大學教育開発推進機構紀要,4,73-82.(CiNii Articles「リメディアル教育」で知る)
- 谷岡弘二・上野貴史・水谷隆(2013).本学入学生における基礎学力とリメディアル教育の状況について 大阪女子短期大学紀要,38,71-86.(CiNii Articles「リメディアル教育」で知る)
- 赤松貴文・楠瀬千春・松本明夫・津田治敏・喜多大三・藤野博史(2013).管理栄養士課程におけるリメディアル教育への取り組み 九州栄養福祉大学研究紀要,10,257-270.(CiNii Articles「リメディアル教育」で知る)
- 金田徹(2013).理工系学生のための工学系・技術系文章リテラシー育成:初年次における実験レポート・論文執筆スキル向上の一事例 リメディアル教育研究,8(2),254-258.(CiNii Articles「リメディアル教育」で知る)
- 中臺由佳里・田島ますみ(2013).社会体験を目的とした授業における「書くこと」の指導 リメディアル教育研究,8(2),250-253.(CiNii Articles「リメディアル教育」で知る)
- 宮﨑文彦(2013).アカデミック・ライティングにおける「自分の頭で考えること」の重要性:スタディ・スキルとビジネス・スキル リメディアル教育研究,8(2),244-249.(CiNii Articles「リメディアル教育」で知る)
- 矢島彰・森友令子・栃澤健史・屋葦素子(2013).専門情報教育を意識した「書く力」の育成 リメディアル教育研究,8(2),228-235.(CiNii Articles「リメディアル教育」で知る)
- 秋山英治(2013).高大連携による日本語文章教育の取組:愛媛大学附属高等学校の実践を通して リメディアル教育研究,8(2),220-227.(CiNii Articles「リメディアル教育」で知る)
- 橋本美香(2013).川崎医科大学における書く力の養成を目指したNIEの取り組み リメディアル教育研究,8(2),216-219.(CiNii Articles「リメディアル教育」で知る)
- 塚越久美子(2013).北海道工業大学の文章表現教育 リメディアル教育研究,8(2),211-215.(CiNii Articles「リメディアル教育」で知る)
- 長尾佳代子(2013).大阪体育大学における日本語作文指導 リメディアル教育研究,8(2),203-210.(CiNii Articles「リメディアル教育」で知る)
- 椋本洋・薄井道正・吉岡路(2013).「特殊講義(アカデミック・リテラシー)【日本語の技法】」について:学部横断型初年次日本語教育の実践 リメディアル教育研究,8(2),199-202.(CiNii Articles「リメディアル教育」で知る)
- 山本裕子(2013).日本人大学生の「書く力」の発達に関する縦断的研究:小論文に見られる特徴から リメディアル教育研究,8(1),101-116.(CiNii Articles「リメディアル教育」で知る)
- 長尾佳代子(2013).明治時代の接続教育:学びへのまわり道 リメディアル教育研究,8(1),67-82.(CiNii Articles「リメディアル教育」で知る)
- 谷川裕稔(2013).リメディアル教育と初年次教育の概念枠組みに関する研究:中教審答申による定義の限界とその対案について リメディアル教育研究,8(1),55-66.(CiNii Articles「リメディアル教育」で知る)
- 杉谷祐美子(2013).初年次教育の実践内容の類型化からみえるリメディアル教育 リメディアル教育研究,8(1),49-54.(CiNii Articles「リメディアル教育」で知る)
- 谷川裕稔・長尾佳代子(2013).再考:「リメディアル教育」概念 リメディアル教育研究,8(1),43-48.(CiNii Articles「リメディアル教育」で知る)
- 中園篤典(2012).『日本語を書くトレーニング』の教材研究:新しい教材作りに向けて リメディアル教育研究,7(2),293-296.[PDF](CiNii Articles「リメディアル教育」で知る)
- 野畑友恵・新藤照夫(2012).初年次演習における論証型文章作成の取り組み:レポートに意見を書くことの意識づけ リメディアル教育研究,7(2),245-253.[PDF](CiNii Articles「リメディアル教育」で知る)
- 南俊朗・大浦洋子(2012).学生の成長を助ける学習支援への模索:授業データ解析による支援方法発見への試み 九州情報大学研究論集,14,39-50.[PDF](CiNii Articles「リメディアル教育」で知る)
- 中園篤典(2012).大規模クラスにおける日本語リメディアル教育の方法:『日本語を書くトレーニング』と『日本語文章能力検定』を利用して 人間環境学研究,10,89-104.[PDF](CiNii Articles「リメディアル教育」で知る)
- 中園篤典(2012).教材解説『日本語を書くトレーニング』の教材研究 リメディアル教育研究,7(2),107-110.(CiNii Articles「リメディアル教育」で知る)
- 橋本美香・新見明子・黒田裕子(2012).日本語力向上のための初年次教育の実践:日本語教員と看護科教員の協働による下位クラスの学生に対する「文章表現」の取り組み 川崎医学会誌 一般教養篇,38,25-32.(CiNii Articles「リメディアル教育」で知る)
- 椿ますみ(2011).リメディアル教育としての検定受験指導の有効性 修文大学短期大学部紀要,50,53-60.(CiNii Articles「リメディアル教育」で知る)
- 要弥由美・吉里さち子(2011).アカデミック・ライティング指導による言語表現の事前・事後テストにおける変化:全文検索システム『ひまわり』を用いた量的報告 リメディアル教育研究,6(2),172-181.[PDF](CiNii Articles「リメディアル教育」で知る)
- 馬場眞知子・野崎浩成・河住有希子・小野澤佳恵・たなかよしこ(2011).学力向上の指標となる言語力育成のために:日本語力をいかに測るか リメディアル教育研究,6(1),26-30.[PDF](CiNii Articles「リメディアル教育」で知る)
- 速水香織・深津睦夫(2011).日本語プレースメントテストの結果の利用事例:進級条件に利用 リメディアル教育研究,6(1),21-25.[PDF](CiNii Articles「リメディアル教育」で知る)
- 渡辺誠治(2011).日本語プレースメントテスト活用の可能性 リメディアル教育研究,6(1),16-20.[PDF](CiNii Articles「リメディアル教育」で知る)
- 河住有希子・小野澤佳恵・たなかよしこ(2011).語彙力育成を目的としたアクティビティ実践 リメディアル教育研究,6(1),10-15.[PDF](CiNii Articles「リメディアル教育」で知る)
- 佐藤尚子(2011).大学での学びに必要な語彙力の養成 リメディアル教育研究,6(1),6-9.[PDF](CiNii Articles「リメディアル教育」で知る)
- 馬場眞知子・たなかよしこ・小野博(2011).日本人大学生の日本語力の養成について リメディアル教育研究,6(1),3-5.[PDF](CiNii Articles「リメディアル教育」で知る)
- 工藤俊郎・長尾佳代子(2010).1年次前期の作文指導の効果:一般教養科目「文学」課題レポートに現れた向上 リメディアル教育研究,5(2),177-184.[PDF](CiNii Articles「リメディアル教育」で知る)
- 野村和代(2010).教科書『わかる!できる!大学生のための日本語の基礎(表現編)』の作成とその活用:授業での実践を通して リメディアル教育研究,5(2),139-145.[PDF](CiNii Articles「リメディアル教育」で知る)
[2014.07.29]IRなどについての文献メモ 文献一覧を更新
- 金成隆一(2013).ルポMOOC革命:無料オンライン授業の衝撃 岩波書店(丸善丸の内本店書架で知る)
[2014.07.29]IRなどについての文献メモ 文献一覧を更新
- 岩﨑千晶(2014).ラーニング・アシスタントの実践的思考に関する分析:初年次教育“スタディスキルゼミ”における学習支援を基に 関西大学高等教育研究,5,29-38.[PDF](Google Scholarアラート「ラーニングコモンズ」で知る)
- 佐渡島紗織・太田裕子(編)(2013).文章チュータリングの理念と実践:早稲田大学ライティング・センターでの取り組み ひつじ書房(Amazon.co.jpレコメンド機能で知る)
- 関西地区FD連絡協議会・京都大学高等教育研究開発推進センター(編)(2013).思考し表現する学生を育てるライティング指導のヒント ミネルヴァ書房(丸善丸の内本店書架で知る)
[2014.07.29]IRなどについての文献メモ 文献一覧を更新
- アンブローズ,S.A.,ブリッジズ,M.W.,ディピエトロ,M.,ラベット,M.C.,&ノーマン,M.K.栗田佳代子(訳)(2014).大学における「学びの場」づくり 玉川大学出版部(Amazon.co.jpレコメンド機能で知る)
- サルマン,K.三木俊哉(訳)(2013).世界はひとつの教室:「学び×テクノロジー」が起こすイノベーション ダイヤモンド社(Amazon.co.jpレコメンド機能で知る)
- 秋田喜代美(2014).対話が生まれる教室:居場所感と夢中を保障する授業教育開発研究所(Amazon.co.jpレコメンド機能で知る)
[2014.07.29]IRなどについての文献メモ 文献一覧を更新
- ジョナサン,B.&アーロン,S.上原裕美子(訳)(2014).反転授業:基本を宿題で学んでから授業で応用力を身につける オデッセイコミュニケーションズ(Amazon.co.jpレコメンド機能で知る)
[2014.07.29]IRなどについての文献メモ 文献一覧を更新
- Fisman, R., & Sullivan, T. 土方奈美(訳)(2013).意外と会社は合理的:組織にはびこる理不尽のメカニズム 日本経済新聞出版社(Amazon.co.jpレコメンド機能で知る)
- 有馬淳・丸山研二・渡部信雄(2014).卓越した組織になるために「改革」を変える 日経BP社(Amazon.co.jpレコメンド機能で知る)
- 清宮普美代(2008).質問会議 なぜ質問だけの会議で生産性が上がるのか? PHP研究所(Amazon.co.jpレコメンド機能で知る)
- 野口吉昭(2011).コンサルタントの「ひと言」力 PHP研究所(Amazon.co.jpレコメンド機能で知る)
[2014.07.29]IRなどについての文献メモ 内容をアップ
- 岡田聡志(2009).私立大学におけるInstitutional Researchの実態と意識-大学類型との関連性 大学教育学会誌,31(2),116-122.[内容]
[2014.07.25]IRなどについての文献メモ 文献一覧を更新
- 東京大学(2014).大学におけるIR(インスティテューショナル・リサーチ)の現状と在り方に関する調査研究報告書(平成24-25年度文部科学省大学改革推進委託事業)[PDF]
[2014.07.24]IRなどについての文献メモ 内容をアップ
- 高橋哲也(2013).大阪府立大学における教学IRと大学IRコンソーシアム 大学マネジメント,9(3),8-13.(CiNii Articles「特集 教学IRの実践に向けて」の検索で知る)[概要][詳細をローカルPCに保存]
- 本間政雄(2013).大学執行部から見たIR 大学マネジメント,9(3),29-34.(CiNii Articles「特集 教学IRの実践に向けて」の検索で知る)[概要][詳細をローカルPCに保存]
[2014.07.23]IRなどについての文献メモ 内容をアップ
- 石本雄真・真田樹義・小沢道紀・小野勝大・辰野有・川那部隆司・鳥居朋子(2014).学生自らの学習改善への貢献からとらえなおした学習成果測定結果の活用:学生個人へのフィードバックの試み 立命館高等教育研究,14,57-70.[PDF][内容](立命館高等教育研究バックナンバーで知る)
[2014.07.10]IRなどについての文献メモ 文献一覧を更新
- 齊尾恭子・三浦真琴(2014).授業について「かたる」こと、「きく」こと 関西大学高等教育研究,5,57-64.[PDF](Google Scholarアラート「ラーニングコモンズ」で知る)
[2014.07.10]IRなどについての文献メモ 文献一覧を更新
- 岩崎保道(2014).日本型大学IRの現状:組織形態に注目して 関西大学高等教育研究,5,49-55.[PDF](Google Scholarアラート「インスティテューショナル・リサーチ」で知る)
[2014.07.08]IRなどについての文献メモ 文献一覧を更新
- 沖清豪(研究代表)(2009).私立大学におけるIRの現状:2008年度全国私立大学調査報告書(2008年度早稲田大学教育総合研究所B14部会研究成果報告書)(沖・岡田(編著)(2011).『データによる大学教育の自己改善:インスティテューショナル・リサーチの過去・現在・展望』で知る)(岡田(2009)で知る)
- Delaney, A. M. (1997). The role of institutional research in higher education: Enabling researchers to meet new challenges. Research in higher education, 38(1), 1-16.(IRの機能;岡田(2009)で知る)
- Knight, W. E., Moore, M. E., & Coperthwaite, C. A. (1997). Institutional research: Knowledge, skills, and perceptions of effectiveness. Research in higher education, 38, 419-433.(IRの機能;岡田(2009)で知る)
- Volkwein, J. F. (1990). The diversity of institutional research structures and tasks. New directions for institutional research, 66, 7-26.(IRの機能;岡田(2009)で知る)
- 金子元久(1996).高等教育大衆化の担い手 天野郁夫・吉本圭一(編)学習社会におけるマス高等教育の構造と機能に関する研究 放送教育開発センター研究報告,91,37-59.(私立大学を類型化;岡田(2009)で知る)
- 天野郁夫(1984).大学分類の方法 慶伊富長(編)大学評価の研究 東京大学出版会,pp.57-69.(国立大学を類型化;岡田(2009)で知る)
- 吉田文(2002).国立大学の諸類型 国立学校財務センター研究部(編)国立大学の構造分化と地域交流 国立学校財務センター研究部 pp.183-193.(国立大学を類型化;岡田(2009)で知る)
- 光田好孝(2004). 日本の大学のカーネギー分類 大学財務経営研究,1,69-82.(国立大学を類型化;岡田(2009)で知る)
- 小林雅之(2002).システムの構造分化:統計的分析 国立学校財務センター研究部(編)国立大学の構造分化と地域交流 国立学校財務センター研究部 147-182.(国立大学を類型化;岡田(2009)で知る)
- 島一則(2006).法人化後の国立大学の類型化:基本財務指標に基づく吉田類型の再考 大学財務経営研究,3,59-85.(国立大学を類型化;岡田(2009)で知る)
- 村澤昌崇(2007).大学の機能別分化と大学人:大学評価と意思決定のためのリアリティ構築に向けて 大学評価研究,6,27-36.(国立大学を類型化;岡田(2009)で知る)
[2014.07.08]IRなどについての文献メモ 文献一覧を更新
- 渡部蓊(2006).臨時教育審議会―その提言と教育改革の展開 学術出版会(Amazon.co.jp「臨時教育審議会」で知る)
- 吉田文(2009).大学改革は何をもたらしたのか:臨時教育審議会からの総括 高等教育研究,12,155-165.(CiNii Articles「臨時教育審議会」で知る)
- 大膳司(2009).臨時教育審議会以降の大学教員の構造と機能の変容:教育・研究活動を中心として 高等教育研究,12,71-94.(CiNii Articles「臨時教育審議会」で知る)
- 朴澤泰男(2007).書評 渡部蓊著『臨時教育審議会--その提言と教育改革の展開』 戦後教育史研究,21,153-156.(CiNii Articles「臨時教育審議会」で知る)
[2014.07.01]IRなどについての文献メモ 内容をアップ
- 田村洋一(2006).組織の「当たり前」を変える:組織開発ファシリテーションの最前線 ファーストプレス(京都光華女子大学図書館蔵書検索「組織」で知る)[概要][詳細をローカルPCに保存]
[2014.07.01]IRなどについての文献メモ 文献一覧を更新
- 金井壽宏・高橋潔(2008).組織理論における感情の意義 組織科学,41(4),4-15.(組織科学バックナンバーで知る)
- 長瀬勝彦(2008).感情と理性の折り合いとしての意思決定 組織科学,41(4),16-26.(組織科学バックナンバーで知る)
- 崎山治男(2008).感情労働と組織:感情労働への動員プロセスの解明にむけて 組織科学,41(4),39-47.(組織科学バックナンバーで知る)
- 伊東昌子・河崎宜史・平田謙次(2008).高達成度プロジェクトマネジャーは組織の知とどう関わるか 組織科学,41(2),57-68.(組織科学バックナンバーで知る)
- 北居明・鈴木竜太(2008).組織文化と組織コミットメントの関係に関する実証研究:クロスレベル分析を通じて 組織科学,41(2),106-116(組織科学バックナンバーで知る)
- 長瀬勝彦(2005).意思決定と理由:なぜ意思決定に理由が必要とされるのか 組織科学,39(1),58-68.(組織科学バックナンバーで知る)
- 出口弘(2004).組織の失敗と評価のランドスケープ学習 組織科学,38(2),29-39.(組織科学バックナンバーで知る)
- 古川久敬(2003).目標による管理の新たな展開:モチベーション,学習,チームワークの観点から 組織科学,37(1),10-22.(組織科学バックナンバーで知る)
[2014.06.30]「私立大学職員によるIR文献メモ」メルマガ バックナンバーを更新
[2014.06.28]IRなどについての文献メモ 文献一覧を更新
- ガルブレイス,J.R.梅津祐良(訳)(2002).組織設計のマネジメント:競争優位の組織づくり 生産性出版(Amazon.co.jp「組織 設計」で知る)
- 沼上幹(2004).組織デザイン 日本経済新聞社(Amazon.co.jp「組織 設計」で知る)
- 三宅秀道(2012).新しい市場のつくりかた:明日のための「余談の多い」経営学 東洋経済新報社(Amazon.co.jp「組織 設計」で知る)
- ロビンス,S.P.木晴夫(訳)(2009).組織行動のマネジメント:入門から実践へ ダイヤモンド社(ブログ「ignorant of the world -散在思考-」(yo4ma3さん)の書籍紹介で知る)
- チャルディーニ,R.B.社会行動研究会(2014).影響力の武器:なぜ、人は動かされるのか 誠信書房(ブログ「ignorant of the world -散在思考-」(yo4ma3さん)の書籍紹介で知る)
- ゴールマン,D.,ボヤツィス,R.,&マッキー,A.土屋京子(訳)(2002).EQリーダーシップ:成功する人の「こころの知能指数」の活かし方 日本経済新聞社(ブログ「ignorant of the world -散在思考-」(yo4ma3さん)の書籍紹介で知る)
- バウワー,A.村井章子(訳)(2004).マッキンゼー経営の本質:意思と仕組み ダイヤモンド社(ブログ「ignorant of the world -散在思考-」(yo4ma3さん)の書籍紹介で知る)
- イアコブッチ,D.(編著)奥村昭博・岸本義之(監訳)(2001).マーケティング戦略論:ノースウェスタン大学大学院ケロッグ・スクール ダイヤモンド社(ブログ「ignorant of the world -散在思考-」(yo4ma3さん)の書籍紹介で知る)
- 北居明(2014).学習を促す組織文化:マルチレベル・アプローチによる実証分析 有斐閣(有斐閣サイト内書籍検索「組織論」で知る)
- 鈴木竜太(2013).関わりあう職場のマネジメント 有斐閣(有斐閣サイト内書籍検索「組織論」で知る)
- 高尾義明・王英燕(2012). 経営理念の浸透:アイデンティティ・プロセスからの実証分析有斐閣(有斐閣サイト内書籍検索「組織論」で知る)
- 金井壽宏・楠見孝(2012).実践知:エキスパートの知性 有斐閣(有斐閣サイト内書籍検索「組織論」で知る)
- 古川久敬・山口裕幸(2012).<先取り志向>の組織心理学:プロアクティブ行動と組織 有斐閣(有斐閣サイト内書籍検索「組織論」で知る)
- 中野勉(2011).ソーシャル・ネットワークと組織のダイナミクス共感のマネジメント 有斐閣(有斐閣サイト内書籍検索「組織論」で知る)
- 三戸浩・池内秀己・勝部伸夫(2011).企業論 有斐閣(有斐閣サイト内書籍検索「組織論」で知る)
- 釘原直樹(2011).ループ・ダイナミックス:集団と群集の心理学 有斐閣(有斐閣サイト内書籍検索「組織論」で知る)
- 金井壽宏・佐藤郁哉・クンダ,G.・ヴァン マーネン,J.(2010).組織エスノグラフィー 有斐閣(有斐閣サイト内書籍検索「組織論」で知る)
- 桑田耕太郎・田尾雅夫(2010).組織論:補訂版 有斐閣(有斐閣サイト内書籍検索「組織論」で知る)
- 田尾雅夫・吉田忠彦(2009).非営利組織論 有斐閣(有斐閣サイト内書籍検索「組織論」で知る)
- 二村敏子(2004).現代ミクロ組織論:その発展と課題 有斐閣(有斐閣サイト内書籍検索「組織論」で知る)
- 十川廣國(編著)(2006).経営組織論 中央経済社(中央大学シラバス「経営組織論」(遠藤健哉先生)で知る)
- 金井壽宏(1999).経営組織:経営学入門シリーズ 日本経済新聞社(法政大学シラバス「経営組織論Ⅱ」(長岡健先生)で知る)
- 金井壽宏・高橋潔(2004).組織行動の考え方:ひとを活かし組織力を高める9つのキーコンセプト 東洋経済新報社(京都光華女子大学図書館蔵書検索「経営組織 金井」で知る)
[2014.06.28]IRなどについての文献メモ 文献一覧を更新
- 中島健一郎・中嶋一恵・甲斐晶子・白石景一・下釜綾子・永野司・中村浩美(2012).教育評価システムとその活用に関する研究:学生指導の事例から 長崎女子短期大学紀要,36,45-52.(保育実習における他者評価と自己評価をレーダーチャートで示して個別指導を行っている事例、自らの評価が個別に可視化されることによって学生が気づきを得る;石本他,2014で知る)
[2014.06.28]ホーム「お知らせ」欄を変更
- 口頭発表「初年次教育の添削課題における「学習行動の改善を促す報告書」の開発:学生・教員の要望の組み入れとIRの活用」(初年次教育学会第7回大会)の発表時刻を掲載
- 口頭発表「どうすれば教職員の考えをインスティテューショナルリサーチ(IR)につなげられるか」(大学行政管理学会第18回(2014年度)定期総会・研究集会)の発表時刻を掲載
[2014.06.16]IRなどについての文献メモ 文献一覧を更新
- 水野将樹(2004).心理学研究における「信頼」概念についての展望 東京大学大学院教育学研究科紀要,43,185-195.[PDF](Google「信頼 心理学 site:ac.jp」で知る)
- 山岸俊男(1998).信頼の構造:こころと社会の進化ゲーム 東京大学出版会(信頼を扱った実証的研究;水野(2004)で知る)
- 天貝由美子(2001).信頼感の発達心理学:思春期から老年期に至るまで 新曜社(水野(2004)で知る)
- 山岸俊男(1999).安心社会から信頼社会へ:日本型システムの行方 中央公論新社(信頼を扱った実証的研究;水野(2004)で知る)
- 小杉素子・山岸俊男(1998).一般的信頼と信頼性判断 心理學研究,69(5),349-357.(信頼を扱った実証的研究;水野(2004)で知る
[2014.06.13]IRなどについての文献メモ 内容をアップ
- 宮本美沙子・奈須正裕(編著)(1995).達成動機の理論と展開 金子書房(市川(2001)で知る)[概要][詳細をローカルPCに保存]
[2014.06.13]IRなどについての文献メモ 文献一覧を更新
- 川那部隆司・笠原健一・鳥居朋子(2013).教学IRにおける学生調査の手法開発:量的アプローチと質的アプローチを併用した学業成績変化過程の検討 立命館高等教育研究,13,61-74.[PDF](Google「学力 データ 教育改善」で知る)
- 森雅生・佐藤仁・高田英一・小湊卓夫(2009).アメリカ型IRの日本における実現可能性について 日本高等教育学会第12回大会自由研究発表資料(九州大学附属図書館「類似資料」機能で知る)(経営支援機能を担う人材の育成と経営情報システム(データウェアハウス)の重要性を指摘;中島(2010)で知る)[PDF]
- Peterson, M. W. (1999). The role of institutional research: From improvement to redesign. New directions for higher education, 104, 83-103. (IR室の専門性はThorpe(1999)のIRの9機能のうち計画策定支援・意思決定支援・政策形成支援に現れる;中島(2010)で知る)
- Saloner, G., Shepard, A., & Podolny, J. (2001). Strategic management. John Wiley & Sons, Inc.(サローナー,G.シェパード,A.&ポドルニー,J.石倉洋子(訳)(2002).戦略経営論 東洋経済新報社)(戦略計画に必要な情報が組織内で流通するチャネルが作られている組織では経営情報を扱う専門の部署を持たなくてもトップマネジメントの戦略計画立案機能が制限されることはない;中島(2010)で知る)
[2014.06.13]IRなどについての文献メモ 文献一覧を更新
- 重田勝介(2014).反転授業:ICTによる教育改革の進展 情報管理,56(10),677-684.(CiNii Articles「学習時間」で知る)
[2014.06.12]IRなどについての文献メモ 文献一覧を更新
- 酒井穣(2008).あたらしい戦略の教科書 ディスカヴァー・トゥエンティワン(日本ではトップマネジメントの多くが幅広い部署での長期間のOJTによる訓練を経て内部から昇進しているためトップマネジメントは戦略立案上の重要な情報を自ら収集するチャンネルを多数保有している;中島(2010)で知る)
- 垂見裕子(2013).学習時間の比較:日本・上海・香港における小中高校生調査から 日本教育社会学会大会発表要旨集録,65,78-79.(CiNii Articles「学習時間」で知る)
- 畑野快・溝上慎一(2013).大学生の主体的な授業態度と学習時間に基づく学生タイプの検討 日本教育工学会論文誌,37(1),13-21.[PDF](CiNii Articles「学習時間」で知る)
- 教育研究推進プロジェクトチーム(2013).学修時間の確保に関する教員の意識調査 山口県立大学学術情報,6,1-10.[PDF](CiNii Articles「学習時間」で知る)
- 松本高志・清水栄子(2013).学習時間と学習傾向に関する分析:『学生生活と学習に関する実態調査』2011、2012集計結果から 電気学会研究会資料,FIE 2013(1-14),49-52.(CiNii Articles「学習時間」で知る)
- 藤村正司(2013).大規模学生調査から学習成果と学習時間の構造を掴む:横断的・時系列的分析 大学論集,44,1-17.[PDF](CiNii Articles「学習時間」で知る)
- 関田一彦(2013).学生の授業外学習時間増進に資する予習・復習課題の工夫:協同学習の視点からのいくつかの提案 教育学論集,64,125-137.(CiNii Articles「学習時間」で知る)
- 池宗佐知子・成島朋美・東條正典・緒方昭広・佐々木健・大越教夫(2012).過去問反復学習を取り入れた国家試験への取組とその効果の検証 筑波技術大学テクノレポート,20(1),57-60.[PDF](CiNii Articles「学習時間」で知る)
- 松本高志・清水栄子(2012).学校外学習時間にみる新入生の学習状況について:新入生アンケートおよび実態調査を手がかりとして 電気学会研究会資料,FIE 2012(19),7-10.(CiNii Articles「学習時間」で知る)
- 土田邦彦・工藤雅之(2012).協働学習によるe-learning利用促進の取り組み:授業外における英語学習時間の確保 工学教育研究講演会講演論文集 平成24年度(60),114-115.[PDF](CiNii Articles「学習時間」で知る)
- 井上加寿子(2012).大学適応度から見る学習成果:初年次英語プレースメントテストと適応調査に関する分析 教育総合研究叢書,5,89-102.[PDF](CiNii Articles「学習時間」で知る)
- 吉田博・金西計英(2012).学生の授業外学習を促進する授業:2年にわたる授業実践を通して 大学教育研究ジャーナル,9,1-10.[PDF](CiNii Articles「学習時間」で知る)
- 吉田博・戸川聡・金西計英(2011).大学の授業における学生が授業外学習を行う要因 日本教育工学会論文誌,35(Suppl.),153-156.[PDF](CiNii Articles「学習時間」で知る)
- 三好登(2011).短大生の授業外学習時間 大学教育学会誌,33(1),114-121.[PDF](CiNii Articles「学習時間」で知る)
- 野上俊一(2011).大学生は学習目標の難易度や学習時間の経過に応じてどのような学習時間配分の方略的知識を持つのか 中村学園大学・中村学園大学短期大学部研究紀要,43,93-96.(CiNii Articles「学習時間」で知る)
- 吉田博・金西計英・Fukuda Steve T.・戸川聡(2011).学生の学習動機をもとにしたFDの構築に関する考察:学生の授業外学習を促す要因に注目して 大学教育研究ジャーナル,8,32-42.[PDF](CiNii Articles「学習時間」で知る)
- 須藤康介(2010).学習方略がPISA型学力に与える影響:階層による方略の違いに着目して 教育社会学研究,86,139-158.[PDF](CiNii Articles「学習時間」で知る)
- Fukuda Steve T.・坂田浩(2010).学生の授業外学習時間の現状とこれからの課題 大学教育研究ジャーナル,7,138-146.[PDF](CiNii Articles「学習時間」で知る)
- 谷村英洋(2010).大学生の学習時間と学習成果 大学経営政策研究,1,71-84.[PDF](CiNii Articles「学習時間」で知る)
- 植田正暢(2009).福岡女学院大学短期大学部における学習時間増加のための取り組み:単位制度の実質化の視点から リメディアル教育研究,4(2),155-161.[PDF](CiNii Articles「学習時間」で知る)
- 谷村英洋(2009).大学生の学習時間分析:授業と学習時間の関連性 大学教育学会誌,31(1),128-135.(CiNii Articles「学習時間」で知る)
- 平尾智隆(2009).学習時間を決定する要因:学生生活状況調査データの分析 大学教育実践ジャーナル,7,9-16.[PDF](CiNii Articles「学習時間」で知る)
[2014.06.12]IRなどについての文献メモ 文献一覧を更新
- 田村洋一(2006).組織の「当たり前」を変える:組織開発ファシリテーションの最前線 ファーストプレス(京都光華女子大学図書館蔵書検索「組織」で知る)
- 佐藤郁哉(2004).制度と文化:組織を動かす見えない力 日本経済新聞社(京都光華女子大学図書館書架で知る)
- 太田肇(2004).ホンネで動かす組織論 筑摩書房(京都光華女子大学図書館書架で知る)
- グローバルタスクフォース(2004).ポーター教授『競争の戦略』入門:ビジネスバイブル 総合法令出版(京都光華女子大学図書館書架で知る)
- 井上善海・佐久間信夫(編著)(2008).よくわかる経営戦略論 ミネルヴァ書房(京都光華女子大学図書館書架で知る)
[2014.06.12]IRなどについての文献メモ 文献一覧を更新
- 日本能率協会コンサルティング(2008).「仮説」の作り方・活かし方 日本能率協会マネジメントセンター(京都光華女子大学図書館書架で知る)
[2014.06.12]IRなどについての文献メモ 文献一覧を更新
- 河合塾(編)(2010).初年次教育でなぜ学生が成長するのか:全国大学調査からみえてきたこと 東信堂(京都光華女子大学図書館蔵書検索「初年次教育」で知る)
- 初年次教育学会(2013).初年次教育の現状と未来 世界思想社(京都光華女子大学図書館蔵書検索「初年次教育」で知る)
[2014.06.11]IRなどについての文献メモ 文献一覧を更新
- Upcraft, M. L., Gardner, J. N., & Barefoot, B. O. 山田礼子(監訳)(2007).初年次教育ハンドブック:学生を「成功」に導くために 丸善(京都光華女子大学図書館蔵書検索「初年次教育」で知る)
- 山田礼子(2012).学士課程教育の質保証へむけて:学生調査と初年次教育からみえてきたもの 東信堂(京都光華女子大学図書館蔵書検索「初年次教育」で知る)
[2014.06.11]IRなどについての文献メモ 文献一覧を更新
- 米谷優子・北克一(2014).大学生の情報活用の現況と大学図書館サービスの課題:情報検索及び利用に関するアンケート結果をふまえて 情報学,11(1),51-59.[PDF](Google Scholarアラート「ラーニングコモンズ」で知る)
[2014.06.10]IRなどについての文献メモ 文献一覧を更新
- 波頭亮(1999).組織設計概論:戦略的組織制度の理論と実際 産能大出版部(Amazon.co.jp「波頭亮」で知る)
- 波頭亮・冨山和彦(2011).プロフェッショナルコンサルティング 東洋経済新報社(Amazon.co.jp「波頭亮」で知る)
[2014.06.10]IRなどについての文献メモ 文献一覧を更新
[2014.06.09]IRなどについての文献メモ 内容をアップ
- 奈須正裕(1996).学ぶ意欲を育てる:子どもが生きる学校づくり 金子書房(市川(2001)で知る)[概要][詳細をローカルPCに保存]
[2014.06.08]IRなどについての文献メモ 文献一覧を更新
- 鳥居朋子(2014).質保証に向けた教育・学習マネジメントにおける学生データの活用:ヘルシンキ大学のLEARN フィードバック・システムに注目して 立命館高等教育研究,14,147-160.[PDF](立命館高等教育研究バックナンバーで知る)
- 宮浦崇・山田勉・鳥居朋子・青山佳世(2011).大学における内部質保証の実現に向けた取り組み:自己点検・評価活動および教学改善活動の現状と課題 立命館高等教育研究,11,151-166.[PDF](立命館高等教育研究バックナンバーで知る)
[2014.06.07]IRなどについての文献メモ 文献一覧を更新
- 菅岡強司・折田充(2014).大学における成績評価の基礎 大学教育年報,17,9-26.(CiNii Articles「成績評価 大学」で知る)
- 有田博之・粟生田忠雄・大橋慎太郎・権田豊・箕口秀夫・村上拓彦・山下沙織・生田孝至・後藤康志・佐藤喜一(2013).カリキュラムマップを用いた成績評価に基づく学習成果の可視化(2) 新潟大学高等教育研究,1(1),9-16.[PDF](CiNii Articles「成績評価 大学」で知る)
- 五十嵐由利子・中村和吉・高木幸子・高橋桂子・山口智子・杉村桃子・生田孝至・後藤康志・佐藤喜一(2013).カリキュラムマップを用いた成績評価に基づく学習成果の可視化(1):科目の到達目標からのボトムアップアプローチ 新潟大学高等教育研究,1(1),1-8.[PDF](CiNii Articles「成績評価 大学」で知る)
- 葛城浩一(2013).非選抜型大学における教育の質保証の問題について考える 大学教育学会誌,35(1),45-49.(CiNii Articles「成績評価 大学」で知る)
- 教育研究推進プロジェクトチーム(2013).学修時間の確保に関する教員の意識調査 山口県立大学学術情報,6,1-10.[PDF](CiNii Articles「成績評価 大学」で知る)
- 宮澤賀津雄・額田順二・末廣啓子・笹井宏益(2013).シラバスで公開された授業の方法・目的類型別に見た大学の成績評価の実態分析:横浜国立大学におけるケーススタディ 技術マネジメント研究,12,27-36.[PDF](CiNii Articles「成績評価 大学」で知る)
- 半田智久(2012).学士課程教育の質改善に寄与する高機能GPAのエビデンス 技術マネジメント研究,12,27-36.(CiNii Articles「成績評価 大学」で知る)
- 沖裕貴・井上史子・林泰子(2012).日本の大学におけるルーブリック評価導入の方策と課題:客観的,厳格かつ公正な成績評価を目指して 年会論文集,28,166-169.[PDF](CiNii Articles「成績評価 大学」で知る)
- 三田村保・塚越久美子・高村政志・秋山敏晴・本間芳樹・太田佳樹(2012).北海道工業大学における入学時学力調査と初年次教育について 工学教育研究講演会講演論文集 平成24年度,60,626-627.[PDF](CiNii Articles「成績評価 大学」で知る)
- 高村政志(2012).北海道工業大学の総合成績評価指標QfGPA 工学教育研究講演会講演論文集 平成24年度,60,530-531.[PDF](CiNii Articles「成績評価 大学」で知る)
- 笠原千絵(2011).学習成果の評価方法とルーブリックの活用:アメリカの高等教育関連団体と大学におけるインタビュー調査から 研究紀要,12,47-55.[PDF](CiNii Articles「成績評価 大学」で知る)
- 加藤鉱三・奉鉉京(2011).信州大学が目指すべきGPAの形について 信州大学人文社会科学研究,5,128-141.[PDF](CiNii Articles「成績評価 大学」で知る)
- 青木人志(2010).講演 GPA制度の本格導入と課題 一橋大学大学教育研究開発センター全学FDシンポジウム報告書,13,4-12.(CiNii Articles「成績評価 大学」で知る)
- 松塚ゆかり(2010).講演GPA本格導入のインパクト 一橋大学大学教育研究開発センター全学FDシンポジウム報告書,13,13-20.(CiNii Articles「成績評価 大学」で知る)
- 上野山達哉(2010).講演GPAの卒業要件化と学生の変化 一橋大学大学教育研究開発センター全学FDシンポジウム報告書,13,21-46.(CiNii Articles「成績評価 大学」で知る)
- 柿本竜治・山尾敏孝(2010).教育の質の保証のシラバスによる検証 工学教育,58(2),70-75.(CiNii Articles「成績評価 大学」で知る)
- 林直嗣(2010).大学教育のガバナンスと成績評価基準(下)質保証とGPA制度 経営志林,47(3),57-72.[PDF](CiNii Articles「成績評価 大学」で知る)
- 林直嗣(2010).大学教育のガバナンスと成績評価基準(中)質保証とGPA制度 経営志林,47(2),39-47.[PDF](CiNii Articles「成績評価 大学」で知る)
- 林直嗣(2010).大学教育のガバナンスと成績評価基準(上)質保証とGPA制度 経営志林,47(1),85-93.[PDF](CiNii Articles「成績評価 大学」で知る)
- 柿本竜治(2010).熊本大学における教育の質の保証に向けたシラバスの検証 熊本大学政策研究,1,41-52.[PDF](CiNii Articles「成績評価 大学」で知る)
- 立松潔(2008).教養教育科目GPA分析:適正な成績評価に向けて 山形大学高等教育研究年報:山形大学高等教育研究企画センター紀要,2,51-55.[PDF](CiNii Articles「成績評価 大学」で知る)
- 豊田雄彦・市川博(2007).GPA制度の導入による適切な成績評価 自由が丘産能短期大学紀要,40,81-93.[PDF](CiNii Articles「成績評価 大学」で知る)
- 半田智久(2006).GPA制度:カテゴリー錯誤の問題と解決 大学教育学会誌,28(1),117-125.(CiNii Articles「成績評価 大学」で知る)
- 岡本英雄(2006).日本私立大学連盟WEBアンケート調査成績評価・GPA制度に関する調査結果 大学時報,55(307),98-101.(CiNii Articles「成績評価 大学」で知る)
- 近末久美子・小郷正則・下田健治・松田信義(2006).点数評価法とGPA(Grade Point Average)評価法の比較検討(第2報) 川崎医療短期大学紀要,26,53-59.(CiNii Articles「成績評価 大学」で知る)
- 近末久美子・小郷正則・下田健治・松田信義(2005).点数評価法とGPA(Grade Point Average)評価法の比較検討(第1報) 川崎医療短期大学紀要,25,73-79.(CiNii Articles「成績評価 大学」で知る)
- 半田智久(2012).学士課程教育の質改善に寄与する高機能GPAのエビデンス 大学教育学会誌,34(2),13-16.(CiNii Articles「半田智久」で知る)
- 半田智久(2011).GPA制度に関する国際調査研究 高等教育研究,14,287-307.(CiNii Articles「半田智久」で知る)
- 半田智久(2008).機能するGPAとは何か 静岡大学教育研究4,27-56.[PDF](CiNii Articles「半田智久」で知る)
- 半田智久(2006).GPA制度に対する関心と導入の状況 静岡大学教育研究,2,1-9.[PDF](CiNii Articles「半田智久」で知る)
- 半田智久(2005).GPA制度の欠陥と解決:問題発生のシミュレーション結果 日本教育社会学会大会発表要旨集録,57,223-224.[PDF](CiNii Articles「半田智久」で知る)
- 半田智久(2012).GPA制度の研究 大学教育出版(Amazon.co.jp「GPA」で知る)
- 半田智久(2012).GPA算法の比較検証:従前のGPAからfunctional GPAへの移行とその最適互換性をめぐって 高等教育と学生支援:お茶の水女子大学教育機構紀要,2,22-30.[PDF](CiNii Articles「半田智久」で知る)
- 半田智久(2011).成績評価の厳正化とGPA活用の深化:絶対的相対評価/教員間調整/functional GPA 地域科学研究会.(Amazon.co.jp「成績評価 大学」で知る)
- 高等教育情報センター(編)(2003).成績評価の厳格化と学習支援システム:GPA運用と学生の履修管理力の育成 地域科学研究会.(Amazon.co.jp「成績評価 大学」で知る)
- 山本寿(2013).GPA制度の技術的欠陥とその改善から見えてくるもの 第18回FDフォーラム報告集,139-159.[PDF](Google「GPA」で知る)
[2014.06.07]IRなどについての文献メモ 内容をアップ
- Deci, E. L., with Flaste, R. (1995). Why we do what we do: The dynamics of personal autonomy. New York: Putnam's Sons.(デシ,E.L.・フラスト,R.櫻井茂男(訳)(1999).人を伸ばす力:内発と自律のすすめ 新曜社)[概要](京都光華女子大学図書館書架で知る)[詳細をローカルPCに保存]
[2014.06.04]IRなどについての文献メモ 文献一覧を更新
- 池田佳奈子・當間亜紀子・桑名杏奈(2014).ラーニング・コモンズにおける学生支援(3):ラーニング・アドバイザ制度の概観 高等教育と学生支援:お茶の水女子大学教育機構紀要,4,50-53.[PDF](CiNii Articles「ラーニングコモンズ」で知る)
- 清水禎文・田中光晴・山﨑直也・杉本和弘(2014).ラーニング・コモンズに注目したコンピテンシー・ベースト・カリキュラムの開発研究 東北大学大学院教育学研究科教育ネットワークセンター年報,14,77-82.[PDF](CiNii Articles「ラーニングコモンズ」で知る
- 南俊朗・馬場謙介(2014).図書館貸出データを用いた学習グループ候補の発見:利用者の社会的ネットワーク発見への試み 九州情報大学研究論集,16,13-25.(CiNii Articles「ラーニングコモンズ」で知る)[PDF]
- 情報サービス課(2014).ラーニング・コモンズにおけるピア・サポート:留学生コンシェルジュの導入事例報告 東北大学附属図書館調査研究室年報,2,45-49.(CiNii Articles「ラーニングコモンズ」で知る)[PDF]
- 野中陽一朗・横山香・中間玲子・宮元博章・丸毛幸太郎・山中一英・古川雅文(2014).ラーニングコモンズ導入期における学生の空間利用状況 兵庫教育大学研究紀要,44,207-218.[PDF](CiNii Articles「ラーニングコモンズ」で知る)
- 小山憲司(2014).図書紹介 加藤信哉・小山憲司共編訳『ラーニング・コモンズ:大学図書館の新しいかたち』 教育学雑誌:日本大学教育学会紀要,49,92-94.(CiNii Articles「ラーニングコモンズ」で知る)
- 山田政寛(2014).基調講演 新たな学びの空間 ラーニングコモンズ 関西学院大学高等教育研究,4,117-126.[PDF](CiNii Articles「ラーニングコモンズ」で知る)
- 長澤多代(2013).主体的な学びを支える大学図書館の学修・教育支援機能:ラーニングコモンズと情報リテラシー教育を中心に 京都大学高等教育研究,19,99-110.[PDF](CiNii Articles「ラーニングコモンズ」で知る)[PDF]
- 長澤公洋(2013).ラーニング・コモンズと学修環境整備に関して IDE:現代の高等教育,556,58-62.(CiNii Articles「ラーニングコモンズ」で知る)
- 北爪佐知子(2013).近畿大学の学習支援:近畿大学英語村E³[e-cube] IDE:現代の高等教育,556,53-57.(CiNii Articles「ラーニングコモンズ」で知る)
- 佐藤恵一(2013).金沢工業大学における学修の場:夢考房など IDE:現代の高等教育,556,48-52.(CiNii Articles「ラーニングコモンズ」で知る)
- 美馬のゆり(2013).公立はこだて未来大学の共鳴・進化する学習活動と空間 IDE:現代の高等教育,556,44-48.(CiNii Articles「ラーニングコモンズ」で知る)
- 溝上智恵子(2013).ラーニング・コモンズ:海外からの示唆 IDE:現代の高等教育,556,38-43.(CiNii Articles「ラーニングコモンズ」で知る)
- 石川巧(2013).大正大学ラーニング・コモンズにおける学習支援 IDE:現代の高等教育,556,27-33.(CiNii Articles「ラーニングコモンズ」で知る)
- 米澤誠(2013).ラーニング・コモンズの大いなる可能性:東北大学での事例をまじえ IDE:現代の高等教育,556,23-27.(CiNii Articles「ラーニングコモンズ」で知る)
- 井上真琴(2013).ラーニング・コモンズの理念と目的を探して:同志社大学の経験から IDE:現代の高等教育,556,17-22.(CiNii Articles「ラーニングコモンズ」で知る)
- 金子元久(2013).経営課題としての学習基盤 IDE:現代の高等教育,556,17-22.(CiNii Articles「ラーニングコモンズ」で知る)
- 赤澤久弥(2013).ラーニング・コモンズと大学図書館 図書館界,65(4),233.(CiNii Articles「ラーニングコモンズ」で知る)
- 沖裕貴(2013).教育から学習への転換を支えるもの:教員・職員・学生の認識の共有をどう実現するか 大学教育学会誌,35(2),18-23.(CiNii Articles「ラーニングコモンズ」で知る)
- 山内祐平(2013).大学における対面空間とオンライン学習環境 大学教育学会誌,35(2),15-17.(CiNii Articles「ラーニングコモンズ」で知る)
- 小幡誉子(2013).大正大学における図書館外ラーニング・コモンズの効果と課題:アンケートによる比較調査の結果から 大学マネジメント,9(7),27-34.(CiNii Articles「ラーニングコモンズ」で知る)
- 米澤誠(2013).アクティブな教育と学習の場としてのラーニング・コモンズ考 大学マネジメント,9(7),21-26.(CiNii Articles「ラーニングコモンズ」で知る)
- 小山憲司(2013).大学図書館の「あたらしいかたち」:ラーニング・コモンズをとおして見るあらたな役割と課題 大学マネジメント,9(7),9-15.(CiNii Articles「ラーニングコモンズ」で知る)
- 米澤誠(2013).研究文献レビュー 学びを誘発するラーニング・コモンズ カレントアウェアネス,317,22-26.(CiNii Articles「ラーニングコモンズ」で知る)
- 松本仁美・井上真琴(2013).学習を促し教学改善を導くラーニング・コモンズ:同志社大学が意図した学習空間 図書館雑誌 107(9), 560-562.(CiNii Articles「ラーニングコモンズ」で知る)
- 石塚由布子・與安拓馬・柳澤要(2013).千葉大学附属図書館の新学習空間におけるケーススタディ:大学における先進的な学習空間に関する研究(その2) 日本建築学会大会学術講演梗概集,475-476.(CiNii Articles「ラーニングコモンズ」で知る)
- 與安拓馬・石塚由布子・柳澤要(2013).アクティブラーニング空間を中心としたケーススタディ:大学における先進的な学習空間に関する研究(その1) 日本建築学会大会学術講演梗概集,473-474.(CiNii Articles「ラーニングコモンズ」で知る)
- 川角典弘・菅原幹人・中元希(2013).大学図書館の空間構成分析と動線計画に関する研究 日本建築学会大会学術講演梗概集,235-236.(CiNii Articles「ラーニングコモンズ」で知る)
- 栗山和也・横田隆司・飯田匡・伊丹康二(2013).大学図書館における諸室の利用実態に関する研究:ラーニング・コモンズに着目して 日本建築学会大会学術講演梗概集,231-232 .((CiNii Articles「ラーニングコモンズ」で知る)
- 山岡俊介・佐藤涼介・五十嵐勇里・矢野裕芳・渡辺富雄(2013).大学図書館のラーニングコモンズの現状:国内の14の大学図書館の事例 日本建築学会大会学術講演梗概集,229-230.(CiNii Articles「ラーニングコモンズ」で知る)
- 小村愛美・土出郁子・森石みどり(2013).ラーニングコモンズデザイン会議@大阪(報告) 大学図書館問題研究会誌,36,11-17.(CiNii Articles「ラーニングコモンズ」で知る)
- 川井奏美・野田晶子(2013).米国大学図書館における利用者行動調査とラーニング・コモンズの整備について:ロチェスター大学とジョージア工科大学の事例 大学図書館研究,98,51-62.(CiNii Articles「ラーニングコモンズ」で知る)
- 山内祐平(2013).大学の学習環境とICT:MOOCからラーニングコモンズまで 電子情報通信学会技術研究報告.DE,データ工学,113(105),13.
- 小山憲司(2013).場としての大学図書館:ラーニング・コモンズがもたらすもの 現代の図書館,51(2),81-90.(CiNii Articles「ラーニングコモンズ」で知る)
- 井上真琴(2013).ラーニング・コモンズは大学図書館を変える 私学経営,460,30-36.(CiNii Articles「ラーニングコモンズ」で知る)
- 栗山和也・横田隆司・飯田匡・伊丹康二(2013).大学図書館における諸室の建築計画と利用実態に関する研究:ラーニング・コモンズに着目して 日本建築学会近畿支部研究報告集.計画系,53,93-96.[PDF](CiNii Articles「ラーニングコモンズ」で知る)
- 野田啓子・鈴木克明・渡邊あや・合田美子(2013).学習支援の担い手としての学生スタッフ育成に向けた研修・評価プログラムの基本設計 日本教育工学会研究報告集,13(2),19-22.(CiNii Articles「ラーニングコモンズ」で知る)
- 池田佳奈子・桑名杏奈(2013).ラーニング・コモンズにおける学生支援(2):第18回FDフォーラムでの報告をふまえて 高等教育と学生支援:お茶の水女子大学教育機構紀要,3,90-95.[PDF](CiNii Articles「ラーニングコモンズ」で知る)
- 児玉英明(2013).教学改革における高等教育センターの役割とIR機能の構築:広島大学高等教育研究開発センター「第40回研究員集会」の参加報告 高等教育フォーラム,3,88-91.(CiNii Articles「ラーニングコモンズ」で知る)[PDF]
- 濱地賢太郎・山村良平・大坂寿之・前直弘・俵口忠功(2013).図書館ラーニングコモンズにおける学習支援活動の報告 日本物理学会講演概要集,68(1-2),466.(CiNii Articles「ラーニングコモンズ」で知る)[PDF]
- 重田真裕美・赤川貴雄(2013).大学図書館におけるラーニング・コモンズの学習支援環境に関する研究 日本建築学会研究報告.九州支部.3,計画系,52,73-76.[PDF](CiNii Articles「ラーニングコモンズ」で知る)
- 岩﨑千晶・池田佳子(2013).考動力を育む学習環境”コラボレーションコモンズ”のデザイン 関西大学高等教育研究,4,9-17.[PDF](CiNii Articles「ラーニングコモンズ」で知る)
- 竹内比呂也・山田礼子・小山憲司・野末俊比古(2013).パネルディスカッション ラーニング・コモンズに求められるもの 大学図書館研究,97,85-89.(CiNii Articles「ラーニングコモンズ」で知る)
- 野末俊比古(2013).教育・学習支援とラーニング・コモンズ:英国大学図書館の動向を中心に 大学図書館研究,97,82-85.(CiNii Articles「ラーニングコモンズ」で知る)
- 小山憲司(2013).ラーニング・コモンズを再考する 大学図書館研究,97,79-82.(CiNii Articles「ラーニングコモンズ」で知る)
- 山田礼子(2013).学習効果につながるアクティブ・ラーニングとそれを支える学習環境 大学図書館研究,97,77-79.(CiNii Articles「ラーニングコモンズ」で知る)
- 日本図書館協会大学図書館部会大学図書館シンポジウム担当(2013).平成24年度大学図書館シンポジウム「質的転換を図る大学教育と図書館:ラーニングコモンズの先にあるもの」報告 図書館雑誌,107(3),168-171.(CiNii Articles「ラーニングコモンズ」で知る)
- 青柳英治(2013).大学図書館の教育支援:情報リテラシー教育と生涯学習力 図書の譜:明治大学図書館紀要,17,115-119.(CiNii Articles「ラーニングコモンズ」で知る)
- 国立大学図書館協会教育学習支援検討特別委員会事務局(2013).国立大学図書館協会ニュース ラーニング・コモンズ再考:平成24年度国立大学図書館協会シンポジウム 大学図書館研究,97,77-89.(CiNii Articles「ラーニングコモンズ」で知る)
- 国公私立大学図書館協力委員会シンポジウム企画運営委員会(2013).平成24年度大学図書館シンポジウム「質的転換を図る大学教育と図書館:ラーニングコモンズの先にあるもの」報告 大学図書館研究,97,71-76.(CiNii Articles「ラーニングコモンズ」で知る)
- 長澤多代(2013).主体的な学びを支える大学図書館の学修・教育支援機能:ラーニングコモンズと情報リテラシー教育を中心に 京都大学高等教育研究,19,99-110.(CiNii Articles「ラーニングコモンズ」で知る)
- 神谷知子・高橋里江・池上佳芳里(2013).報告要旨 平成24年度第1回東海地区大学図書館協議会研修会 オーストラリアの大学図書館におけるラーニング・コモンズの整備及び学習支援の現状 東海地区大学図書館協議会誌,58,15-21.(CiNii Articles「ラーニングコモンズ」で知る)
- 橋洋平・森部圭亮・仲秋雄介(2013).報告要旨 平成24年度第1回東海地区大学図書館協議会研修会 香港・シンガポールの大学図書館におけるラーニング・コモンズの整備及び学習支援の現状 東海地区大学図書館協議会誌,58,5-14.(CiNii Articles「ラーニングコモンズ」で知る)
- 當間亜紀子・池田佳奈子・桑名杏奈(2013).情報教育支援の実践報告:お茶の水女子大学附属図書館ラーニング・コモンズにおける学生支援 情報知識学会誌,23(2),253-258.(CiNii Articles「ラーニングコモンズ」で知る)[PDF]
- 上田祥代・笹倉理子(2013).図書館内に設置したPC自動貸出ロッカーの利用状況 情報知識学会誌,23(2),247-252.(CiNii Articles「ラーニングコモンズ」で知る)[PDF]
- 中沢正江・児玉英明・池田恵子・小倉都子・篠崎大司・今井美裕子・藤原めぐみ(2013).主体的に学び、学び続ける活力を得られる学習場:『ラーニングコモンズ』の構築に向けたヒアリング調査報告 高等教育フォーラム,3,65-80.(CiNii Articles「ラーニングコモンズ」で知る)PDF]
[2014.06.04]IRなどについての文献メモ 内容をアップ
- 鹿毛雅治(編)(2012).モティベーションをまなぶ12の理論:ゼロからわかる「やる気の心理学」入門! 金剛出版(京都光華女子大学図書館書架で知る)[概要][詳細をローカルPCに保存]
[2014.06.03]IRなどについての文献メモ 文献一覧を更新
- 博報堂ブランドデザイン(2013).チームのアイデア力。アイデアが出るチームになるための5つのステップ 日本能率協会マネジメントセンター(Amazon.co.jp「アンケート 改善」で知る)
- Boyd,D., & Goldenberg, J.池村千秋(訳)(2014).インサイドボックス 究極の創造的思考法 文藝春秋(Amazon.co.jpレコメンド機能で知る)
[2014.06.03]IRなどについての文献メモ 文献一覧を更新
- 鳥巣泰生・佐々木英洋(2014).リアルタイム授業評価システムを活用した授業改善(10) 大手前大学論集,14,331-352.(CiNii Articles「アンケート 改善」で知る)
- 磯谷俊輔・塩野美里・木村茲(2014).カイゼンにつなげるためのネガティブアンケート 医療アドミニストレーター:病院事務管理者のための病院経営情報誌,4(48),34-40.(CiNii Articles「アンケート 改善」で知る)
- 船山俊介(2014).真の患者ニーズをくみ取り、改善へつなげる不満足度調査:GRPDCAが確立 医療アドミニストレーター:病院事務管理者のための病院経営情報誌,4(48),26-33.(CiNii Articles「アンケート 改善」で知る)
- 田中和秀・市村麻衣(2014).アンケートの有用性、考え方、つくり方 医療アドミニストレーター:病院事務管理者のための病院経営情報誌,4(48),20-25.(CiNii Articles「アンケート 改善」で知る)
- 阪本研一(2013).アンケートが現場を変える:短期集中型業務改善(第6回・最終回)病院改革はアンケートから始まった 病院,72(9),725-727.(CiNii Articles「アンケート 改善」で知る)
- 阪本研一(2013).アンケートが現場を変える:短期集中型業務改善(第5回)医師部門に与えたインパクト 病院,72(8),652-654.(CiNii Articles「アンケート 改善」で知る)
- 阪本研一(2013).アンケートが現場を変える:短期集中型業務改善(第4回)業務改善策の作成 病院,72(7),573-575.(CiNii Articles「アンケート 改善」で知る)
[2014.06.03]IRなどについての文献メモ 内容をアップ
- 外山美樹(2011).行動を起こし、持続する力:モチベーションの心理学 新曜社(京都光華女子大学図書館書架で知る)[概要][詳細をローカルPCに保存]
[2014.06.03]IRなどについての文献メモ 文献一覧を更新
- 筒井美紀(2006).ノートをとる学生は授業を理解しているのか?:<大事なところは色を変えて板書してほしい=83%>を前にして 現代社会研究,9,5-21.(はてなブックマークインタレスト「大学」で知る)[PDF]
- 奈須正裕(1990).学業達成場面における原因帰属、感情、学習行動の関係 教育心理学研究,38(1),17-25.(失敗の原因を内的で安定的な要因(自身の能力)に帰属するとあきらめ感情が喚起され学習行動を抑制し学業成績が低下する、日本の中学生を対象にした調査;外山美樹(2011).『行動を起こし、持続する力』で知る)[PDF]
[2014.06.02]IRなどについての文献メモ 文献一覧を更新
- 中沢正江・尾崎良子(2014).学びの場を創造する:主体的な学習態度の形成に向けて ラーニングコモンズ・セミナー実施報告 高等教育フォーラム,4,128-134.[PDF]
[2014.06.02]IRなどについての文献メモ 文献一覧を更新
- Gray, J., Chambers, L., & Bounegru, L. (2012). The data journalism handbook. Beijing: O'Reilly.(Amazon.co.jp「データジャーナリズム」で知る)
[2014.06.02]IRなどについての文献メモ 文献一覧を更新
- 深堀聰子(研究代表)(2012).学習成果アセスメントのインパクトに関する総合的研究 国立教育政策研究所(Google「アメリカ 学習成果」で知る)[PDF]
- 山岸直司(2012).アメリカ各州における学習成果アセスメント IDE:現代の高等教育,543,71-75.(CiNii Articles「アメリカ 学習成果」で知る)
- 森利枝(2012).学習成果に関わる大学情報公開の現状と課題:アメリカ IDE:現代の高等教育,542,47-52.(CiNii Articles「アメリカ 学習成果」で知る)
- 渋井進・金性希・林隆之・井田正明(2012).学習成果に係る標準指標の設定へ向けた検討:国立大学法人評価における評価結果報告書の分析から 大学評価・学位研究,13,3-19.(Google「アメリカ 学習成果」で知る)
- 株式会社ベネッセコーポレーション(2008).先導的大学改革推進委託事業 大学卒業程度の学力を認定する仕組に関する調査研究(平成20年度調査 報告書)(Google「アメリカ 学習成果」で知る)[PDF]
- 関西国際大学・日本高等教育学会(2009).平成20年度文部科学省<先導的大学改革推進委託>調査研究報告 学生の大学卒業程度の学力を認定する仕組みに関する調査研究(Google「アメリカ 学習成果」で知る)[PDF]
[2014.06.01]ホーム「お知らせ」欄を変更
- 口頭発表「初年次教育の添削課題における「学習行動の改善を促す報告書」の開発:学生・教員の要望の組み入れとIRの活用」(初年次教育学会第7回大会)を掲載
- 口頭発表「どうすれば教職員の考えをインスティテューショナルリサーチ(IR)につなげられるか」(大学行政管理学会第18回(2014年度)定期総会・研究集会)を掲載
[2014.06.01]IRなどについての文献メモ 内容をアップ
- 内田千代子(2011).大学生の中途退学の実態と対策~国立大学の調査から~ 大学マネジメント,7(8),2-7.[内容]
[2014.05.21]IRなどについての文献メモ 文献一覧を更新
- 内田千代子(2011).大学生の中途退学の実態と対策~国立大学の調査から~ 大学マネジメント,7(8),2-7.
[2014.05.19]IRなどについての文献メモ 文献一覧を更新
- 石本雄真・真田樹義・小沢道紀・小野勝大・辰野有・川那部隆司・鳥居朋子(2014).学生自らの学習改善への貢献からとらえなおした学習成果測定結果の活用:学生個人へのフィードバックの試み 立命館高等教育研究,14,57-70.[PDF](立命館高等教育研究バックナンバーで知る)
[2014.05.19]IRなどについての文献メモ 文献一覧を更新
- 大友愛子・岩山豊・毛利隆夫(2014).学内データの活用:大学におけるIR(Institutional Research)への取組み FUJITSU,65(3),41-47.(Google Scholarアラート「"institutional research"」で知る)[PDF]
- 松本高志(2014).ティーチング・ポートフォリオとインスティテューショナル・リサーチを組み合わせたFD活動の試み 論文集「高専教育」,37,483-488.(Google Scholarアラート「"institutional research"」で知る)
[2014.05.02]IRなどについての文献メモ 内容をアップ
- 鳥居朋子(2013).質保証に向けた教学マネジメントにIRはどう貢献できるのか?:立命館大学における教学IRの開発経験から 大学マネジメント,9(3),2-7(別紙1枚).[内容]
[2014.05.02]IRなどについての文献メモ 文献一覧を更新
- 中原淳(2012).経営学習論:人材育成を科学する 東京大学出版会(Google「具体 抽象 往復」で知る)
[2014.04.25]IRなどについての文献メモ 文献一覧を更新
- Gannon-Slater, N., Ikenberry, S., Jankowski, N., & Kuh, G. (2014). Institutional assessment practices across accreditation regions. National Institute for Learning Outcomes Assessment.(Google Scholarアラート「"institutional research"」で知る)[PDF]
[2014.04.25]IRなどについての文献メモ 文献一覧を更新
- 国際交流基金(2011).学習を評価する ひつじ書房(京都光華女子大学図書館蔵書検索「評価」で知る)
- OECD(編著)松田岳士(訳)(2011).学習成果の認証と評価:働くための知識・スキル・能力の可視化 明石書店(京都光華女子大学図書館蔵書検索「評価」で知る)
- 山田礼子(2012).学びの質保証戦略 玉川大学出版部(京都光華女子大学図書館蔵書検索「評価」で知る)
- 田中耕治(編)(2010).よくわかる教育評価 第2版 ミネルヴァ書房(京都光華女子大学図書館蔵書検索「評価」で知る)
- 田中耕治(編著)(2011).パフォーマンス評価:思考力・判断力・表現力を育む授業づくり ぎょうせい(京都光華女子大学図書館蔵書検索「評価」で知る)
[2014.04.25]IRなどについての文献メモ 文献一覧を更新
- 兵藤健志・天野絵里子・森玲奈・山田政寛(2014).アクティブラーニング支援をするためのライブラリアン育成ワークショップの試行 日本教育工学会研究報告集,14(1),333-338.(Google Scholarアラート「ラーニングコモンズ」で知る)
[2014.04.24]IRなどについての文献メモ 文献一覧を更新
- 本田寛輔(2013).米国の学習成果の診断:教育プログラム次元のルーブリック 独立行政法人大学評価・学位授与機構講演会資料[PDF]
- 片山英治・小林雅之・劉文君・服部英明(2009).東大-野村大学経営ディスカッションペーパー No.12(大学の戦略的計画(1):インテグリシティとダイバーシティ実現のためのツール) 東京大学大学総合教育研究センター[PDF]
[2014.04.23]IRなどについての文献メモ 内容をアップ
- 沖清豪(2010).大学における情報の発信とIR(Institutional Research) 大学マネジメント, 6(6), 8-17.[内容]
[2014.04.23]ホーム 「このサイトの紹介」を変更
- 「扱う内容」欄の「学習支援やラーニングコモンズなどについて書かれた文献も扱っていこうと思います。IRを使って何をするかを考えるときの参考にするための文献です。」を「学習支援やラーニングコモンズなどについて書かれた文献も扱っています。IRを使って何かをより良いものにしていくときには、その対象のことを深く知っておくことが役に立つと考えています。」
- 「サイトの管理者・経歴」欄に「IRを担当する部署の専従職員として業務に携わっています。」と「子どもと大人の「ことば」のやりとりをデータベースにして分析し、特徴を見つけるというようなことをしていました。」を追記
[2014.04.21]IRなどについての文献メモ 内容をアップ
- 小湊卓夫(2010).大学におけるIR具体化の可能性:九州大学の事例から 大学マネジメント,6(6),18-26.(沖・岡田(編著)(2011).『データによる大学教育の自己改善:インスティテューショナル・リサーチの過去・現在・展望』で知る)[概要][詳細をローカルPCに保存]
[2014.04.21]IRなどについての文献メモ 内容をアップ
- 伊達千代・内藤タカヒコ(2006).デザイン・ルールズ:デザインをはじめる前に知っておきたいこと エムディエヌコーポレーション(京都光華女子大学図書館蔵書検索「デザイン」で知る)[概要][詳細をローカルPCに保存]
[2014.04.21]IRなどについての文献メモ 文献一覧を更新
- Sanders, L., & Filkins, J. (2009). Effective reporting. 2nd ed. Tallahassee, Florida: Association for Institutional Research.(鳥居朋子・八重樫文・川那部隆司(2013).立命館大学の教学マネジメントにおけるIRの開発と可視化のプロセスに関する考察で知る)
- Delaney, A. M. (2009). Institutional researchers' expanding roles: Policy, planning, program evaluation, assessment, and new research methodologies. New directions for institutional research, 143, 29-41.(鳥居朋子・八重樫文・川那部隆司(2013).立命館大学の教学マネジメントにおけるIRの開発と可視化のプロセスに関する考察で知る)
- Swing, R. L. (2009). Higher education counts: Data for decision support. In Olson, G., & Presley, J.(Eds.)The future of higher education. Boulder: Paradigm Publishers. pp.139-147. (鳥居朋子・八重樫文・川那部隆司(2013).立命館大学の教学マネジメントにおけるIRの開発と可視化のプロセスに関する考察で知る)
[2014.04.20]IRなどについての文献メモ 文献一覧を更新
- 金子大輔(2014).入学時と後期終了時における情報に関する基礎知識調査の結果の比較 日本教育工学会研究報告集,14(1),327-332.(CiNii Articles「初年次教育」で知る)
- 小野和宏・西山秀昌・八木稔・ステガロユロクサーナ・重谷佳見・山村健介・井上誠・前田健康(2014).大学学習法ヘのパフォーマンス評価導入における実践的課題 新潟大学高等教育研究,1(2),5-8.(CiNii Articles「初年次教育」で知る)
- 稲垣太一・夏目達也(2014).初年次教育における体験型学習と学生の学びの深化 名古屋高等教育研究,14,37-56.(CiNii Articles「初年次教育」で知る)[PDF]
- 藤浦五月・中川祐香(2013).初年次アカデミック・ライティングクラスのための構造積み上げ型教材の開発と学習者評価 日本語教育方法研究会誌,20(2),14-15.(CiNii Articles「初年次教育」で知る)[PDF]
- 山田裕憲(2013).学習の動機つけと将来目標を考えさせる初年次教育:学習の習慣作りとリアルな産業教育の効果 学教育研究講演会講演論文集 平成25年度,61,32-33.(CiNii Articles「初年次教育」で知る)[PDF]
- 小山治(2013).初年次教育としての学習技法型授業の効果:1年生と4年生の共時比較 大学評価研究,12,121-130.(CiNii Articles「初年次教育」で知る)
- 澤田忠幸(2013).協同学習に基づく初年次教育の取り組みと効果の検証 大学教育学会誌,35(1),116-125.(CiNii Articles「初年次教育」で知る)
- 高橋正克(2013).長崎大学教養セミナー:初年次教育としての役割と評価の検証 長崎大学大学教育機能開発センター紀要,4,39-58.(CiNii Articles「初年次教育」で知る)
- 吉田正高(2013).大学初年次教育へのNIE活用に関する実験的演習の実践報告:リメディアル教育への効果的な導入に向けて 東北芸術工科大学紀要,20,102-113.(CiNii Articles「初年次教育」で知る)
- 山本啓一・松本幸一(2013).PROGテストと初年次文章表現科目によるジェネリックスキルの測定と育成 九州国際大学法学論集,19(3),51-62.(CiNii Articles「初年次教育」で知る)[PDF]
- 塚越久美子・三田村保・秋山敏晴・高村政志・本間芳樹・太田佳樹(2013).北海道工業大学における入学時学力調査と初年次教育 リメディアル教育研究,8(2),277-282.(CiNii Articles「初年次教育」で知る)
- 山田礼子(2013).学生の特性を把握する間接評価:教学IRの有用性 Journal of JSEE,61(3),3_27-3_32.(CiNii Articles「初年次教育」で知る)
- 寺島和夫・小池俊隆・野間圭介(2012).経営学部における初期情報教育への試みと検証(2):4年間の比較分析を中心に 龍谷大学経営学論集,52(2/3),1-16.(CiNii Articles「初年次教育 検証」で知る)[PDF]
- 後藤文彦(2012).初年次教育の有効性に関する実証的研究 高等教育フォーラム,2,1-8.(CiNii Articles「初年次教育 検証」で知る)[PDF]
- 寺島和夫・小池俊隆・野間圭介(2012).経営学部における初期情報教育への試みと検証(1):高校の教科「情報」を中心に 龍谷大学経営学論集,51(4),14-30.(CiNii Articles「初年次教育 検証」で知る)[PDF]
[2014.04.20]IRなどについての文献メモ 文献一覧を更新
- 鳥居朋子(2014).質保証に向けた教育・学習マネジメントにおける学生データの活用:ヘルシンキ大学のLEARN フィードバック・システムに注目して 立命館高等教育研究,14,147-160.(立命館高等教育研究バックナンバーで知る)
- 石本雄真・真田樹義・小沢道紀・小野勝大・辰野有・川那部隆司・鳥居朋子(2014).学生自らの学習改善への貢献からとらえなおした学習成果測定結果の活用:学生個人へのフィードバックの試み 立命館高等教育研究,14,57-70.(立命館高等教育研究バックナンバーで知る)
- 宮浦崇・山田勉・鳥居朋子・青山佳世(2011).大学における内部質保証の実現に向けた取り組み:自己点検・評価活動および教学改善活動の現状と課題 立命館高等教育研究,11,151-166.(立命館高等教育研究バックナンバーで知る)
[2014.04.18]IRなどについての文献メモ 文献一覧を更新
- 村上祐介(2011).教育学における事例研究の方法論再考:定性的研究における比較の方法 教育學研究,78(4),398-410.(CiNii Articles「事例研究の方法」で知る)[PDF]
- 三毛美予子(2009).社会福祉実践を支える事例研究の方法:これまでの研究成果から考えること 社会福祉研究,104,76-87.(CiNii Articles「事例研究の方法」で知る)
- 三毛美予子・池埜聡(2003).日本における「実践理論」構築を目的としたソーシャルワーク研究法の課題 社会学部紀要,95,123-131.(CiNii Articles「事例研究の方法」で知る)
- 石坂庸祐(2005).「事例研究」の方法論的意義について 九州共立大学経済学部紀要,101,1-17.(CiNii Articles「事例研究の方法」で知る)[PDF]
- 大原興太郎(2002).フィールドワークと個別事例研究の方法・態度 三重大学フィールド研究・技術年報,1,27-40.(CiNii Articles「事例研究の方法」で知る)[PDF]
- 喜多祐荘(2002).事例研究のすすめかた:福祉の立場からの試論 学校メンタルヘルス,5,107-113.(CiNii Articles「事例研究の方法」で知る)
- 岩間伸之(2001).対人援助のための事例研究の方法 総合ケア,11(7),12-17.(CiNii Articles「事例研究の方法」で知る)
- 根本博司(2000).理論構築のための事例研究の方法 ソーシャルワーク研究,26(1),11-18.(CiNii Articles「事例研究の方法」で知る)
- アレキサンダー,G.,&アンドリュー,B.泉川泰博(訳)(2013).社会科学のケース・スタディ:理論形成のための定性的手法 勁草書房(Google「事例研究 理論」で知る)
- 米本秀仁・高橋信行・志村健一(編著)(2004).事例研究・教育法:理論と実践力の向上を目指して 川島書店(Google「事例研究 理論」で知る)
- ヘイグ,J.小松陽一・野中郁次郎(訳)(1978).理論構築の方法 白桃書房(Google「事例研究 理論」で知る)
- 深谷美枝・大滝敦子(1995).実践から理論を導き出すために(1)グラウンデッド・セオリーによるソーシャルワーク研究の可能性 ソーシャルワーク研究,21(1),39-43.(Google「理論構築の方法」で知る)
- 深谷美枝・大滝敦子(1995).実践から理論を導き出すために(2)グラウンデッド・セオリーによるソーシャルワーク研究の可能性 ソーシャルワーク研究,21(2),126-130.(Google「理論構築の方法」で知る)
- 戈木クレイグヒル滋子(2006).グラウンデッド・セオリー・アプローチ:理論を生みだすまで 新曜社(Google「グラウンデッドセオリー」で知る)
- 戈木クレイグヒル滋子(編)(2005).質的研究方法ゼミナール:グラウンデッドセオリーアプローチを学ぶ 医学書院(Google「グラウンデッドセオリー」で知る)
[2014.04.17]IRなどについての文献メモ 文献一覧を更新
- 雨森聡・松田岳士・森朋子(2012).教学IRの一方略:島根大学の事例を用いて 京都大学高等教育研究,18,1-10.(CiNii Articles「institutional research」で知る)[PDF]
- 浅野茂・本田寛輔・嶌田敏行(2014).米国におけるインスティテューショナル・リサーチ部署による意思決定支援の実際 大学評価・学位研究,15,33-54.(CiNii Articles「institutional research」で知る)[PDF]
- 大山篤之・小原一仁(2013).Institutional Researchへの示唆:企業、米国大学からの視点 大学時報,62(350),52-59.(CiNii Articles「institutional research」で知る)
[2014.04.17]IRなどについての文献メモ 文献一覧を更新
- 堀一成・坂尻彰宏(2014).阪大生のためのアカデミック・ライティング入門 大阪大学全学教育推進機構(あさがおMLで知る)[PDF]
- 堀一成・坂尻彰宏(2014).「阪大生のためのアカデミック・ライティング入門」ライティング指導教員マニュアル 大阪大学全学教育推進機構(あさがおMLで知る)[PDF]
[2014.04.17]IRなどについての文献メモ 文献一覧を更新
- 笠原嘉(1988).退却神経症:無気力・無関心・無快楽の克服 講談社(大学のメンタルヘルス関係者に「ステューデントアパシー」という言葉を紹介;内田(2011).大学生の中途退学の実態と対策で知る)
[2014.04.05]IRなどについての文献メモ 内容をアップ
- 佐藤好彦(2008).デザインの教室:手を動かして学ぶデザイントレーニング エムディエヌコーポレーション(京都光華女子大学図書館蔵書検索「デザイン」で知る)[概要][詳細をローカルPCに保存]
[2014.04.02]IRなどについての文献メモ 内容をアップ
- 市川伸一(1998).開かれた学びへの出発:21世紀の学校の役割 金子書房(市川(2001)で知る)[概要][詳細をローカルPCに保存]
[2014.03.31]IRなどについての文献メモ 内容を追記
[2014.03.31]「私立大学職員によるIR文献メモ」メルマガ バックナンバーを更新
[2014.03.26]IRなどについての文献メモ 文献一覧を更新
- 鎌田均(2014).図書館という場を超えた利用者支援:エンベディッド・ライブラリアンを中心に 大学間連携共同教育推進事業 学都いしかわ・課題解決型グローカル人材育成システムの構築「図書館機能強化プログラム」シンポジウム「大学図書館におけるこれからの学習支援 -ラーニングコモンズを超えて-」発表資料[PDF]
- 長澤多代(2014).大学の教育改革に大学図書館の学修支援を組み入れる諸方策 大学間連携共同教育推進事業 学都いしかわ・課題解決型グローカル人材育成システムの構築「図書館機能強化プログラム」シンポジウム「大学図書館におけるこれからの学習支援 -ラーニングコモンズを超えて-」発表資料[PDF]
[2014.03.16]IRなどについての文献メモ 文献一覧を更新
- 大橋禅太郎(2005).すごい会議:短期間で会社が劇的に変わる! 大和書房(Amazon.co.jp「会議」で知る)
- 大橋禅太郎・雨宮幸弘(2007).秘伝すごい会議 大和書房(Amazon.co.jp「会議」で知る)
- 斎藤岳(2008).1回の会議・打ち合わせで必ず結論を出す技術 東洋経済新報社(Amazon.co.jp「会議」で知る)
- 永井祐介(2012).たった1日でチームを大変革する会議 サンマーク出版(Amazon.co.jp「会議」で知る)
- 山崎将志(2006).会議の教科書 強い企業の基本の「型」を盗む! ソフトバンク クリエイティブ(Amazon.co.jp「会議」で知る)
[2014.03.16]IRなどについての文献メモ 文献一覧を更新
- シュック,J. 成沢俊子(訳)(2009).トヨタ式A3プロセスで仕事改革:A3用紙1枚で人を育て、組織を動かす 日刊工業新聞社(Amazon.co.jp「A3」で知る)
- 酒井進児(2013).トヨタの伝え方 幻冬舎ルネッサンス(Amazon.co.jpレコメンド機能で知る)
- ライカー,J.K. 稲垣公夫(訳)(2004).ザ・トヨタウェイ(上) 日経BP社(Amazon.co.jpレコメンド機能で知る)
- ライカー,J.K. 稲垣公夫(訳)(2004).ザ・トヨタウェイ(下) 日経BP社(Amazon.co.jpレコメンド機能で知る)
[2014.03.16]IRなどについての文献メモ 文献一覧を更新
- デュアルテ,N.中西真雄美(訳)(2012).ザ・プレゼンテーション ダイヤモンド社(Amazon.co.jp「プレゼンテーション」で知る)
- ドノバン,J.中西真雄美(訳)(2013).TEDトーク 世界最高のプレゼン術 新潮社
[2014.03.16]IRなどについての文献メモ 文献一覧を更新
- 山田秀(2006).TQM 品質管理入門 日本経済新聞社(Amazon.co.jp「TQM」で知る)
- 山田秀(2006).品質管理のためのカイゼン入門 日本経済新聞社(Amazon.co.jpレコメンド機能で知る)
- 永田靖(2006).品質管理のための統計手法 日本経済新聞社(Amazon.co.jpレコメンド機能で知る)
- 原崎郁平・西沢和夫(2001).現場で役立つQC工程表と作業標準書 ISO9000対応 日刊工業新聞社>日刊工業新聞社(Amazon.co.jpレコメンド機能で知る)
- ダイヤモンドシックスシグマ研究会・眞木和俊(1999).図解 コレならわかるシックスシグマ ダイヤモンド社(Amazon.co.jp「シックスシグマ」で知る)
- ウルリヒ,D.,カー,S.,&アシュケナス,R.高橋透・伊藤武志(訳)(2003).GE式ワークアウト 日経BP社(Amazon.co.jp「ワークアウト」で知る)
- 奥野宣之(2010).仕事の成果が激変する 知的生産ワークアウト:あなたが逆転するための73のメニュー ダイヤモンド社(Amazon.co.jp「ワークアウト」で知る)
[2014.03.09]IRなどについての文献メモ 文献一覧を更新
- 松田岳士(2014).教学IRの役割と実践事例:エビデンスベースの教育質保証をめざして 教育システム情報学会誌,31(1),19-27.(Googleアラート「インスティテューショナル・リサーチ」で知る)
[2014.03.09]IRなどについての文献メモ 文献一覧を更新
- 中野民夫・森雅浩・鈴木まり子・冨岡武・大枝奈美(2009).ファシリテーション 実践から学ぶスキルとこころ 岩波書店(第11回SDフォーラム「参加型の場を創る:ワークショップの実践知に学ぶ」で知る)
- 中野民夫・堀公俊(2009).対話する力―ファシリテーター23の問い 日本経済新聞出版社(第11回SDフォーラム「参加型の場を創る:ワークショップの実践知に学ぶ」で知る)
- 中野民夫(2003).ファシリテーション革命 岩波書店(第11回SDフォーラム「参加型の場を創る:ワークショップの実践知に学ぶ」で知る)
[2014.03.05]IRなどについての文献メモ 文献一覧を更新
- 伊垣尚人(2012).子どもの力を引き出す自主学習ノートの作り方 ナツメ社(Amazon.co.jp「自習」で知る)
- 伊垣尚人(2013).子どもの力を引き出す自主学習ノート 実践編 ナツメ社(Amazon.co.jpレコメンド機能で知る)
- 石田淳・長野雅弘(2013).行動科学に基づいた驚異の「復習継続法」 パンローリング(Amazon.co.jpレコメンド機能で知る)
- 主婦の友社(編)(2011).やる気スイッチが入る 秋田県式家庭学習ノートで勉強しよう! 主婦の友社(Amazon.co.jpレコメンド機能で知る)
- 池末翔太・野中祥平(2011).中高生の勉強あるある、解決します。 ディスカヴァー・トゥエンティワン(Amazon.co.jpレコメンド機能で知る)
- 天流仁志(2010).学習の作法 ディスカヴァー・トゥエンティワン(Amazon.co.jpレコメンド機能で知る)
[2014.03.05]IRなどについての文献メモ 文献一覧を更新
- 視覚デザイン研究所(編)(1998).7日間でマスターするレイアウト基礎講座 視覚デザイン研究所(Amazon.co.jpレコメンド機能で知る)
[2014.03.05]IRなどについての文献メモ 文献一覧を更新
- 井上岳久(2007).無料で1億人に知らせる門外不出のPR広報術101 明日香出版社(Amazon.co.jp「広報」で知る)
- 福西七重(2007).もっと!冒険する社内報 ナナコーポレートコミュニケーション(Amazon.co.jp「広報」で知る)
[2014.03.05]IRなどについての文献メモ 文献一覧を更新
- 日産自動車(株)V-up推進・改善支援チーム(2013).日産V-upの挑戦 カルロス・ゴーンが生んだ課題解決プログラム 中央経済社(Amazon.co.jp「日産 会議」で知る)
- 漆原次郎(2011).日産 驚異の会議 改革の10年が生み落としたノウハウ 東洋経済新報社(Amazon.co.jp「日産 会議」で知る)
[2014.02.27]IRなどについての文献メモ 内容をアップ
- Reynolds,G.熊谷小百合(訳).(2011).ガー・レイノルズ シンプルプレゼン 日経BP社(Amazon.co.jpレコメンド機能で知る)[概要][詳細をローカルPCに保存]
- 平井雷太(2005).どの子にも学力がつく:セルフラーニング 新曜社(市川(2001)で知る)[概要][詳細をローカルPCに保存]
- 畑村洋太郎(2006).失敗学 ナツメ社(京都光華女子大学図書館蔵書検索「畑村洋太郎」で知る)[概要][詳細をローカルPCに保存]
- 稲垣佳世子・波多野誼余夫(1989).人はいかに学ぶか:日常的認知の世界 中央公論社(市川(2001)で知る)[概要][詳細をローカルPCに保存]
[2014.02.24]ホーム「お知らせ」欄を変更、過去の「お知らせ」に追加
- 京都光華女子大学EM・IR部のポスター発表「スモールサイズIRの有効活用」(大学コンソーシアム京都「第19回FDフォーラム」)に「終了しました」を追記し、「過去の「お知らせ」」に掲載
[2014.02.24]IRなどについての文献メモ 文献一覧を更新
- 杉江修治・関田一彦・安永悟・三宅なほみ(2004).大学授業を活性化する方法 玉川大学出版部(大学教育での協調学習事例;鈴木(編著)(2009).『学びあいが生みだす書く力:大学におけるレポートライティング教育の試み』で知る)
- 戸田山和久(2002).論文の教室 NHK出版(複数の問いを連続して投げかける(ビリヤード法;本当に?、どのような意味?、いつからいつまで?、どこで?、誰が?、どのように?、他は?、どうすべき?など);鈴木(編著)(2009).『学びあいが生みだす書く力:大学におけるレポートライティング教育の試み』で知る))
[2014.02.24]IRなどについての文献メモ 内容をアップ
- 情報デザインフォーラム(編)(2010).情報デザインの教室:仕事を変える、社会を変える、これからのデザインアプローチと手法 丸善(京都光華女子大学図書館蔵書検索「デザイン」で知る)[概要][詳細をローカルPCに保存]
- 濱名篤・川嶋太津夫(編著)(2006).初年次教育:歴史・理論・実践と世界の動向 丸善(京都光華女子大学図書館蔵書検索「初年次教育」で知る)[概要][詳細をローカルPCに保存]
- 鈴木宏昭(編著)(2009).学びあいが生みだす書く力:大学におけるレポートライティング教育の試み 丸善プラネット(京都光華女子大学図書館蔵書検索「鈴木宏昭」で知る)[概要][詳細をローカルPCに保存]
[2014.02.23]IRなどについての文献メモ 文献一覧を更新
[2014.02.20]IRなどについての文献メモ 文献一覧を更新
- 福島真司(2009).山形大学のEnrollment Management 大学職員ジャ-ナル,13,44-55.(CiNii Articles「福島真司」の検索で知る)
[2014.02.20]IRなどについての文献メモ 内容をアップ
- 市川伸一(2001).学ぶ意欲の心理学 PHP研究所(Amazon.co.jp「意欲」で知る)[概要][詳細をローカルPCに保存]
- 森時彦(2007).ファシリテーター養成講座:人と組織を動かす力が身につく! ダイヤモンド社(京都光華女子大学図書館蔵書検索「ファシリテーター」で知る)[概要][詳細をローカルPCに保存]
- 清水亮・橋本勝(編著)(2012).学生・職員と創る大学教育:大学を変えるFDとSDの新発想 ナカニシヤ出版(鮫島輝美先生/京都光華女子大学からの紹介で知る)[概要][詳細をローカルPCに保存]
[2014.02.19]「私立大学職員によるIR文献メモ」メルマガ バックナンバーを更新
[2014.02.15]ホーム 「お知らせ」欄を変更
- 京都光華女子大学EM・IR部のポスター発表「スモールサイズIRの有効活用」(大学コンソーシアム京都「第19回FDフォーラム」)を掲載
[2014.02.15]IRなどについての文献メモ 文献一覧を更新
- 吉田文(2011).外部対応から内部改革へ:普及途上のイギリスのIR 大学評価研究,10,47-54.
- 潮木守一(2009).「証拠に基づく政策」はいかにして可能か?:教員需要推計の事後検証をもととして 高等教育研究,12,169-187.(沖・岡田(編著)(2011).『データによる大学教育の自己改善:インスティテューショナル・リサーチの過去・現在・展望』で知る)
- 沖清豪(研究代表)(2009).私立大学におけるIRの現状:2008年度全国私立大学調査報告書(2008年度早稲田大学教育総合研究所B14部会研究成果報告書)(沖・岡田(編著)(2011).『データによる大学教育の自己改善:インスティテューショナル・リサーチの過去・現在・展望』で知る)
- 沖清豪(2013).IR組織等を有効活用している大学の特徴 日本私立大学協会附置私学高等教育研究所 中長期経営システムの確立、強化に向けて 日本私立大学協会附置私学高等教育研究所 pp.49-58.(沖・岡田(編著)(2011).『データによる大学教育の自己改善:インスティテューショナル・リサーチの過去・現在・展望』で知る)
- 小湊卓夫・中井俊樹(2007).国立大学法人におけるインスティテューショナル・リサーチ組織の特質と課題 大学評価・学位研究,5,17-34.(沖・岡田(編著)(2011).『データによる大学教育の自己改善:インスティテューショナル・リサーチの過去・現在・展望』で知る)
- 小湊卓夫(2011).アメリカにおけるIR人材育成プログラムと日本の課題 大学評価研究,10,21-28.(沖・岡田(編著)(2011).『データによる大学教育の自己改善:インスティテューショナル・リサーチの過去・現在・展望』で知る)
- 小湊卓夫(2010).大学におけるIR具体化の可能性:九州大学の事例から 大学マネジメント,6(6),18-26.(沖・岡田(編著)(2011).『データによる大学教育の自己改善:インスティテューショナル・リサーチの過去・現在・展望』で知る)
- 森雅生・佐藤仁・高田英一・小湊卓夫(2009).アメリカ型IRの日本における実現可能性について 日本高等教育学会第12回大会自由研究発表資料(九州大学附属図書館「類似資料」機能で知る)[PDF]
- 私学高等教育研究所(2009).高等教育の新しい側面:IRの役割と期待 私学高等教育研究所シリーズ,36.(沖・岡田(編著)(2011).『データによる大学教育の自己改善:インスティテューショナル・リサーチの過去・現在・展望』で知る)[PDF]
- 私学高等教育研究所(2012).IRの基本原理と活用:国際比較と日本型IR 私学高等教育研究所シリーズ,45.(日本私立大学協会サイト内「私学高等教育研究所シリーズ(研究報告)」で知る)[PDF]
- 菅田節朗(2012).入学試験における歩留率の「歩留率モデル」に基づく解明 大学入試研究ジャーナル,22,251-258.(沖・岡田(編著)(2011).『データによる大学教育の自己改善:インスティテューショナル・リサーチの過去・現在・展望』で知る)
- 鳥居朋子(2011).米国の大学における戦略的計画を通じた質保証:根拠に基づくプログラム点検 大学評価研究,10,55-66.
- 大学評価コンソーシアム(2013).データ収集作業のガイドライン:効率的・効果的な評価作業のためのデータ収集の課題と対応(沖・岡田(編著)(2011).『データによる大学教育の自己改善:インスティテューショナル・リサーチの過去・現在・展望』で知る)[PDF]
- 高橋哲也(2013).大阪府立大学の教学IR:現状と課題 第19回大学教育研究フォーラム配布資料(沖・岡田(編著)(2011).『データによる大学教育の自己改善:インスティテューショナル・リサーチの過去・現在・展望』で知る)
- 鳥居朋子(編)(2008).大学のカリキュラム開発とインスティチューショナル・リサーチの有機的連携に関する研究 平成18・19年度科学研究費補助金(基盤研究(C))研究成果報告書(沖・岡田(編著)(2011).『データによる大学教育の自己改善:インスティテューショナル・リサーチの過去・現在・展望』で知る)
- 鳥居朋子(2012).大学マネジメントにおける上級管理職とIRの機能的連携に関する研究 平成21-23年度科学研究費補助金(基盤研究(C))研究成果報告書(沖・岡田(編著)(2011).『データによる大学教育の自己改善:インスティテューショナル・リサーチの過去・現在・展望』で知る)
- 鳥居朋子(2013).質保証に向けた教学マネジメントにIRはどう貢献できるのか?:立命館大学における教学IRの開発経験から 大学マネジメント,9(3),2-7(別紙1枚).
- 本間政雄(2013).大学執行部から見たIR 大学マネジメント,9(3),29-34.(CiNii Articles「特集 教学IRの実践に向けて」の検索で知る)
- 山本幸一(2013).PDCAサイクルの基盤となるマネジメント志向IRの開発と定着:明治大学における内部質保証システムの整備を事例に 大学マネジメント,9(3),22-28.(CiNii Articles「特集 教学IRの実践に向けて」の検索で知る)
- 高田英一・森雅生(2013).我が国における「IR人材」の育成プログラムのあり方について 大学マネジメント,9(3),14-21.(CiNii Articles「特集 教学IRの実践に向けて」の検索で知る)
- 高橋哲也(2013).大阪府立大学における教学IRと大学IRコンソーシアム 大学マネジメント,9(3),8-13.(CiNii Articles「特集 教学IRの実践に向けて」の検索で知る)
- 中島英博(2010).経営支援機能としての経営情報システムの必要性に関する実証分析:米国のインスティテューショナル・リサーチに注目して 高等教育研究,13,115-128.(沖・岡田(編著)(2011).『データによる大学教育の自己改善:インスティテューショナル・リサーチの過去・現在・展望』で知る)
- 独立行政法人日本学生支援機構(2011).大学、短期大学、高等専門学校における学生支援の取組状況に関する調査(平成22年度)(沖・岡田(編著)(2011).『データによる大学教育の自己改善:インスティテューショナル・リサーチの過去・現在・展望』で知る)[PDF]
- 独立行政法人日本学生支援機構(2009).大学、短期大学、高等専門学校における学生支援の取組状況に関する調査(平成20年度)(独立行政法人日本学生支援機構サイト内「大学等における学生支援の取組状況に関する調査」で知る)[PDF]
- 本田寛輔・井田正明(2007).高等教育機関の戦略計画と大学情報:米国ニューヨーク州の事例 大学評価・学位研究,6,67-82.(沖・岡田(編著)(2011).『データによる大学教育の自己改善:インスティテューショナル・リサーチの過去・現在・展望』で知る)
- 村澤昌崇(2008).大学中途退学の計量的分析:高等教育研究への計量分析の応用(その3)フリーソフトRを用いて 比治山高等教育研究,1,153-165.(CiNii Articles「村澤昌崇」の検索で知る)[PDF]
- 村澤昌崇(2006).学生の入学以前・入学時点の学習状況と大学での学習成果:DEAの応用による一考察 COE研究シリーズ,18,71-100.(CiNii Articles「村澤昌崇」の検索で知る)[PDF]
- 山田剛史(2012).学生の学びと成長を捉えるために不可欠な入学者調査 Between,2・3月号,12-13.(沖・岡田(編著)(2011).『データによる大学教育の自己改善:インスティテューショナル・リサーチの過去・現在・展望』で知る)[PDF]
- 山田剛史(2012).組織的活動の評価:大学評価・質保証文脈におけるIRの展開 京都大学高等教育研究開発推進センター(編)生成する大学教育学 ナカニシヤ出版 pp.201-215.(沖・岡田(編著)(2011).『データによる大学教育の自己改善:インスティテューショナル・リサーチの過去・現在・展望』で知る)
- 山田剛史(2013).学びと成長を促すアセスメントデザイン Between,4・5月号,32-34.(沖・岡田(編著)(2011).『データによる大学教育の自己改善:インスティテューショナル・リサーチの過去・現在・展望』で知る)[PDF]
- 山田剛史・森朋子(2010).Evidenceに基づく初年次教育プログラムの構築:モデル授業の効果検証を踏まえて 初年次教育学会誌,2(1),56-63.(沖・岡田(編著)(2011).『データによる大学教育の自己改善:インスティテューショナル・リサーチの過去・現在・展望』で知る)
[2014.02.15]IRなどについての文献メモ 原文PDFへのリンクを追加
- 鳥居朋子(2009).質保証の枠組みにおける豪州大学のインスティチューショナル・リサーチと教育改善:シドニー大学およびメルボルン大学の事例を通して 大学評価・学位研究,9,43-61.[PDF]
- 岡田聡志(2008).Institutional Researchの組織化と変容:米国における差異と欧州における展開 早稲田大学大学院文学研究科紀要第1分冊,54,67-77.[PDF]
- 野田文香(2009).アウトカム評価としてのインスティテューショナル・リサーチ機能 立命館高等教育研究,9,125-140.(米国の教学改善に関する取組事例;ブログ「よしなごと」(otani0083さん)の記事で知る)[PDF]
- 松塚ゆかり(2009).高等教育のナレッジマネージメント:米国のIRが進める学部横断的「知」の共有 大学論集,41,455-471.[PDF]
- 大佐古紀雄(2007).Institutional Researchとしての学生調査ノウハウ構築に向けて(1)P短期大学学生調査から 育英短期大学研究紀要, 24, 1-13.[PDF]
- Terenzini, P. T. (1999). On the nature of institutional research and the knowledge and skills it requires. New directions for higher education, 104, 21-29.[PDF]
- Volkwein, J. F. (2008). The foundations and evolution of institutional research. New directions for higher education, 141, 5-20.[PDF]
[2014.02.15]IRなどについての文献メモ 文献一覧を更新
- 森眞理子・河上志貴子・横山美佳・ユキョンラン(2013).大学のグローバル化における図書館の役割:留学生サービスから考える 平成25年度京都大学図書館機構講演会資料[PDF]
[2014.02.06]IRなどについての文献メモ 内容をアップ
- 鈴木誠(2008).意欲を引き出す授業デザイン:人をやる気にするには何が必要か 東洋館出版社(京都光華女子大学図書館蔵書検索「意欲」で知る)[概要][詳細をローカルPCに保存]
- 中嶋秀隆(監修)・中憲治(著)(2000).プロジェクトマネジメント 実践編 総合法令出版(Amazon.co.jp「プロジェクトマネジメント」で知る)[概要][詳細をローカルPCに保存]
- 佐藤学(2000).「学び」から逃走する子どもたち 岩波書店(鮫島輝美先生(京都光華女子大学)からの紹介で知る)[概要][詳細をローカルPCに保存]
- Aronson, E., Blaney, N., Stephin, C., Sikes, J. & Snapp, M. (1978). The jigsaw classroom. Beverly Hills, CA: Sage Publishing Company.(アロンソン,E.他 松山安雄訳(1986).ジグソー学級:生徒と教師の心を開く協同学習法の教え方と学び方 原書房)[概要][詳細をローカルPCに保存]
[2014.02.06]IRなどについての文献メモ 内容をアップ
- Norman, D. A. (2011). Living with complexity. Cambridge, Mass.: MIT Press.(ノーマン, D.A.伊賀聡一郎・岡本明・安村通晃(訳)(2011).複雑さと共に暮らす:デザインの挑戦 新曜社)(京都光華女子大学図書館蔵書検索「デザイン」で知る)[概要][詳細をローカルPCに保存]
- 山崎亮(2013).コミュニティデザインの時代:自分たちで「まち」をつくる 中央公論新社(京都光華女子大学図書館蔵書検索「デザイン」で知る)[概要][詳細をローカルPCに保存]
- 玉沖仁美(2012).地域をプロデュースする仕事 英治出版(京都光華女子大学図書館蔵書検索「地域」で知る)[概要][詳細をローカルPCに保存]
- Norman, D. A. (1988). The psychology of everyday things. New York: Basic Books.(ノーマン, D.A.野島久雄(訳)(1990).誰のためのデザイン?:認知科学者のデザイン原論 新曜社)(京都外国語大学付属図書館蔵書検索「認知科学」で知る)[概要][詳細をローカルPCに保存]
- Baker, W. (2000). Achieving success through social capital: Tapping the hidden resources in your personal and business networks. San Francisco: Jossey-Bass.(ベーカー,W.中島豊(訳)(2001).ソーシャル・キャピタル:人と組織の間にある「見えざる資産」を活用する ダイヤモンド社)(京都光華女子大学図書館蔵書検索「ソーシャルキャピタル」で知る)[概要][詳細をローカルPCに保存]
[2014.02.06]IRなどについての文献メモ 文献一覧を更新
- 寄藤文平(2009).ラクガキ・マスター 描くことが楽しくなる絵のキホン 美術出版社(Amazon.co.jpレコメンド機能で知る)
- 寄藤文平(2012).絵と言葉の一研究 「わかりやすい」デザインを考える 美術出版社(Amazon.co.jpレコメンド機能で知る)
[2014.02.05]「私立大学職員によるIR文献メモ」メルマガ バックナンバーを更新
[2014.01.31]IRなどについての文献メモ 内容をアップ
- 鈴木誠(2008).意欲を引き出す授業デザイン:人をやる気にするには何が必要か 東洋館出版社(京都光華女子大学図書館蔵書検索「意欲」で知る)[概要][詳細をローカルPCに保存]
- 中井俊樹・鳥居朋子・藤井都百(編)(2013).大学のIR Q&A 玉川大学出版部(Googleアラート「institutional research」で知る)[概要][詳細をローカルPCに保存]
[2014.01.31]IRなどについての文献メモ 文献一覧を更新
- 杉森公一(2014).書評:『大学のIR Q&A』 大学教育学会誌,35(2),150-151.
- 喜多村和之(1973).アメリカにおける「大学研究」の展開:序説 大学論集,1,20-31.[PDF](日本にIRを初めて紹介した論文;中井俊樹・鳥居朋子・藤井都百(編)(2013).『大学のIR Q&A』で知る)
[2014.01.30]IRなどについての文献メモ 文献一覧を更新
- 木村博之(2010).インフォグラフィックス:情報をデザインする視点と表現 誠文堂新光社(Amazon.co.jp「インフォグラフィックス」で知る)
- メイヤー,E.K.山口美紀夫・鈴木眞里子(訳)(1998).インフォメーショングラフィックス エムディエヌコーポレーション(情報デザインアソシエイツ(編)(2002).『情報デザイン:分かりやすさの設計』で知る)
- ウィルバー,P&バーク,M.猪股裕一(訳)(2000).図説インフォメーショングラフィックス:情報をデザインするための法則と事例 エムディエヌコーポレーション(Amazon.co.jp「インフォグラフィックス」で知る)
- ウールマン,M.郷司陽子(訳)(2003).Digital Information Graphics 毎日コミュニケーションズ(Amazon.co.jp「インフォグラフィックス」で知る)
- 櫻田潤(2013).たのしいインフォグラフィック入門 ビー・エヌ・エヌ新社(Amazon.co.jp「インフォグラフィックス」で知る)
[2014.01.28]IRなどについての文献メモ 内容をアップ
- 三宅なほみ(編著)(2003).学習科学とテクノロジ 放送大学教育振興会(学習者に学習の先が見えるように工夫する(学習科学では人の賢さが発現する仕組みについての知見を授業改善に活かす実践実証型の研究が積み重ねられている;三宅他(2011)で知る)[概要][詳細をローカルPCに保存]
- 堀公俊・加藤彰(2006).ファシリテーション・グラフィック:議論を「見える化」する技法 日本経済新聞社(京都光華女子大学図書館蔵書検索「ファシリテーション」で知る)[概要][詳細をローカルPCに保存]
- 中原淳・荒木淳子・北村士朗・長岡健(2006).企業内人材育成入門 ダイヤモンド社[概要][詳細をローカルPCに保存]
- 堀公俊(2006).組織変革ファシリテーター:「ファシリテーション能力」実践講座 東洋経済新報社(Amazon「ファシリテーター」で知る)[概要][詳細をローカルPCに保存]
- 堀公俊(2003).問題解決ファシリテーター:「ファシリテーション能力」養成講座 東洋経済新報社(Amazon「ファシリテーター」で知る)[概要][詳細をローカルPCに保存]
- 苅宿俊文・佐伯胖・高木光太郎(編)(2012).場づくりとしてのまなび 東京大学出版会(Amazon「ワークショップ」で知る)[概要][詳細をローカルPCに保存]
- 美馬のゆり・山内祐平(2005).「未来の学び」をデザインする:空間・活動・共同体 東京大学出版会(上田・中原(2013)、ブクログ「プレイフル・ラーニングの本棚」で知る)(アクティブラーニング型の授業を円滑に導入するためには学習環境として空間・活動・共同体・人工物を有機的にデザインする必要がある;奥田(2012)で知る)[概要][詳細をローカルPCに保存]
- 堀公俊・加藤彰(2008).ワークショップ・デザイン:知をつむぐ対話の場づくり 日本経済新聞出版社(Amazon「ワークショップ」で知る)[概要][詳細をローカルPCに保存]
- 森時彦・ファシリテーターの道具研究会(2008).ファシリテーターの道具箱:組織の問題解決に使えるパワーツール49 ダイヤモンド社(Amazon「ファシリテーター」で知る)[概要][詳細をローカルPCに保存]
- 川喜田二郎(1970).続・発想法:KJ法の展開と応用 中央公論社(Amazon「KJ法」で知る)[概要][詳細をローカルPCに保存]
[2014.01.28]IRなどについての文献メモ 文献一覧を更新
- 情報デザインアソシエイツ(編)(2002).情報デザイン:分かりやすさの設計 グラフィック社(情報デザインフォーラム(編)(2010)『情報デザインの教室』で知る)
- ワーマン,R.S.金井哲夫(訳)(2007).それは「情報」ではない。:無情報爆発時代を生き抜くためのコミュニケーション・デザイン エムディエヌコーポレーション(情報デザインフォーラム(編)(2010)『情報デザインの教室』で知る
- Reynolds,G.熊谷小百合(訳).(2009).プレゼンテーションZEN ピアソン桐原(Amazon.co.jpレコメンド機能で知る)
- Reynolds,G.熊谷小百合(訳).(2011).ガー・レイノルズ シンプルプレゼン 日経BP社(Amazon.co.jpレコメンド機能で知る)
- ダン,R.小川 敏子(訳).(2009).描いて売り込め! 超ビジュアルシンキング 講談社(ラフィーヴァー,L.庭田よう子(訳)(2013).『わかりやすく説明する練習をしよう。 伝え方を鍛える コミュニケーションを深める』で知る)
- カーマイン,G.井口耕二(訳)(2010).スティーブ・ジョブズ驚異のプレゼン:人々を惹きつける18の法則 日経BP社(Amazon.co.jpレコメンド機能で知る)
[2014.01.28]IRなどについての文献メモ 文献一覧を更新
[2014.01.28]IRなどについての文献メモ 文献一覧を更新
- 播摩早苗(2004).目からウロコのコーチング:なぜ、あの人には部下がついてくるのか? PHP研究所(Amazon.co.jp「コーチング」で知る)
- 本間正人・松瀬理保(2006).セルフ・コーチング入門 日本経済新聞社(Amazon.co.jp「コーチング」で知る)
- 本間正人・松瀬理保(2006).コーチング入門 日本経済新聞社(Amazon.co.jp「コーチング」で知る)
- 伊藤守(2002).コーチングマネジメント:人と組織のハイパフォーマンスをつくる ディスカヴァー・トゥエンティワン(Amazon.co.jp「コーチング」で知る)
- 播摩早苗(2006).今すぐ使える!コーチング PHP研究所(Amazon.co.jp「コーチング」で知る)
- 菅原裕子(2007).子どもの心のコーチング:一人で考え、一人でできる子の育て方 PHP研究所(Amazon.co.jp「コーチング」で知る)
- ウィットワース,L.,キムジーハウス,H.,&サンダール,F.CTIジャパン(訳)(2002).コーチング・バイブル:人がよりよく生きるための新しいコミュニケーション手法 東洋経済新報社(Amazon.co.jp「コーチング」で知る)
[2014.01.06]ホーム ページ構成を変更
[2014.01.06]IRなどについての文献メモ 内容をアップ
- 茂木一司(編集代表)・苅宿俊文・佐藤優香・上田信行・宮田義郎(編)(2010).協同と表現のワークショップ:学びのための環境のデザイン 東信堂[概要](Amazon「ワークショップ」で知る)[詳細をローカルPCに保存]
- 上田信行(2009).プレイフル・シンキング:仕事を楽しくする思考法 宣伝会議[概要][詳細をローカルPCに保存](Amazon「上田信行」で知る)
- 中野民夫(2001).ワークショップ:新しい学びと創造の場 岩波書店[概要][詳細をローカルPCに保存](上田・中原(2013)、ブクログ「プレイフル・ラーニングの本棚」で知る)
[2014.01.06]「私立大学職員によるIR文献メモ」メルマガ バックナンバーを更新
[2014.01.06]IRなどについての文献メモ ページ紹介文を変更
- 「[要約をローカルPCに保存]」を「[詳細をローカルPCに保存]」に変更
[2014.01.06]ホーム 「このサイトの紹介」を変更
- 「さらに、学習支援やラーニングコモンズなどについて書かれた文献も扱っていこうと思います。主に日本語の文献が対象です。IRを使って何をするかを考えるときの参考にするための文献です。」を追記
[2013.12.30]IRなどについての文献メモ 詳細をローカルPCに保存
- 佐藤学(2000).「学び」から逃走する子どもたち 岩波書店(鮫島輝美先生(京都光華女子大学)からの紹介で知る)[詳細をローカルPCに保存]
- 中嶋秀隆(監修)・中憲治(著)(2000).プロジェクトマネジメント 実践編 総合法令出版[詳細をローカルPCに保存]
- 人間教育研究協議会(編)(2003).基礎学力を育てる 金子書房(京都光華女子大学図書館蔵書検索「基礎学力」で知る)[詳細をローカルPCに保存]
- 中井俊樹・鳥居朋子・藤井都百(編)(2013).大学のIR Q&A 玉川大学出版部(Googleアラート「institutional research」で知る)[詳細をローカルPCに保存]
- 小山内優・小澤芳明・地域科学研究会高等教育情報センター(2011).研究計画書の点検と進化の実際:"基金化" 審査のポイント チェックリストと改善例 Q&A:科研費の申請・獲得マニュアル 地域科学研究会(Amazon.co.jp「科研費」で知る)[詳細をローカルPCに保存]
- 鈴木誠(2008).意欲を引き出す授業デザイン:人をやる気にするには何が必要か 東洋館出版社(京都光華女子大学図書館蔵書検索「意欲」で知る)[詳細をローカルPCに保存]
- 市川伸一(2001).学ぶ意欲の心理学 PHP研究所(Amazon.co.jp「意欲」で知る)[詳細をローカルPCに保存]
- Norman, D. A. (2011). Living with complexity. Cambridge, Mass.: MIT Press.(ノーマン, D.A.伊賀聡一郎・岡本明・安村通晃(訳)(2011).複雑さと共に暮らす:デザインの挑戦 新曜社)(京都光華女子大学図書館蔵書検索「デザイン」で知る)[詳細をローカルPCに保存]
- 山崎亮(2013).コミュニティデザインの時代:自分たちで「まち」をつくる 中央公論新社(京都光華女子大学図書館蔵書検索「デザイン」で知る)[詳細をローカルPCに保存]
- Norman, D. A. (1988). The psychology of everyday things. New York: Basic Books.(ノーマン, D.A.野島久雄(訳)(1990).誰のためのデザイン?:認知科学者のデザイン原論 新曜社)(京都外国語大学付属図書館蔵書検索「認知科学」で知る)[詳細をローカルPCに保存]
- 玉沖仁美(2012).地域をプロデュースする仕事 英治出版(京都光華女子大学図書館蔵書検索「地域」で知る)[詳細をローカルPCに保存]
- Baker, W. (2000). Achieving success through social capital: Tapping the hidden resources in your personal and business networks. San Francisco: Jossey-Bass.(ベーカー,W.中島豊(訳)(2001).ソーシャル・キャピタル:人と組織の間にある「見えざる資産」を活用する ダイヤモンド社)(京都光華女子大学図書館蔵書検索「ソーシャルキャピタル」で知る)[詳細をローカルPCに保存]
- 森時彦(2007).ファシリテーター養成講座:人と組織を動かす力が身につく! ダイヤモンド社(京都光華女子大学図書館蔵書検索「ファシリテーター」で知る)[詳細をローカルPCに保存]
[2013.12.30]IRなどについての文献メモ 文献一覧を更新
- アドラー,M.J.・ドーレン,C.V.外山滋比古・槇未知子(訳)(1997).本を読む本 講談社(Amazon.co.jpレコメンド機能で知る)
[2013.12.30]IRなどについての文献メモ 文献一覧を更新
- 山田ズーニー(2001).伝わる・揺さぶる!文章を書く PHP研究所(Amazon.co.jpレコメンド機能で知る)
- 池上彰(2002).相手に「伝わる」話し方:ぼくはこんなことを考えながら話してきた 講談社(Amazon.co.jpレコメンド機能で知る)
- 本多勝一(2005).日本語の作文技術 講談社(Amazon.co.jpレコメンド機能で知る)
- 堀公俊・加藤彰(2009).ロジカル・ディスカッション 日本経済新聞出版社(Amazon.co.jpレコメンド機能で知る)
[2013.12.29]更新履歴・IRなどについての文献メモ ページ構成を変更
- 「内容を紹介している文献」欄を「IR」と「IR以外」に分離
[2013.12.29]IRなどについての文献メモ 文献一覧を更新
- 浅野攝郎・大森彌・川口昭彦・山内昌之(編)(2000).東京大学は変わる:教養教育のチャレンジ 東京大学出版会(Amazon.co.jpレコメンド機能で知る)
- 岸本裕史(2001).続見える学力、見えない学力:読み、書き、計算は学力の基礎 大月書店(Amazon.co.jpレコメンド機能で知る)
[2013.12.29]IRなどについての文献メモ 文献一覧を更新
- 香西秀信(1995).反論の技術:その意義と訓練方法 明治図書出版(Amazon.co.jpレコメンド機能で知る)
- 福澤一吉(2002).議論のレッスン 日本放送出版協会(Amazon.co.jpレコメンド機能で知る)
- 島宗理(2004).インストラクショナルデザイン:教師のためのルールブック 米田出版(Amazon.co.jpレコメンド機能で知る)
- 石原千秋(2005).国語教科書の思想 筑摩書房(Amazon.co.jpレコメンド機能で知る)
- 西林克彦(2005).わかったつもり:読解力がつかない本当の原因 光文社(Amazon.co.jpレコメンド機能で知る)
- 山田ズーニー(2006).あなたの話はなぜ「通じない」のか 筑摩書房(Amazon.co.jpレコメンド機能で知る)
- 山田ズーニー(2008).考えるシート 講談社(Amazon.co.jpレコメンド機能で知る)
- 石黒圭(2008).文章は接続詞で決まる 光文社(Amazon.co.jpレコメンド機能で知る)
- アンホルト,R.H.R.鈴木炎・リー,I.S.(訳)(2008).理系のための口頭発表術:聴衆を魅了する20の原則 講談社(Amazon.co.jpレコメンド機能で知る)
- 村井瑞枝(2009).図で考えるとすべてまとまる クロスメディア・パブリッシング(Amazon.co.jpレコメンド機能で知る)
- 山本昭生(2010).論理的に話す技術:相手にわかりやすく説明する極意 ソフトバンククリエイティブ(Amazon.co.jpレコメンド機能で知る)
- 山口周(2012).外資系コンサルのスライド作成術:図解表現23のテクニック 東洋経済新報社(Amazon.co.jpレコメンド機能で知る)
- 川嶋直(2013).KP法:シンプルに伝える紙芝居プレゼンテーション みくに出版(Amazon.co.jpレコメンド機能で知る)
- ラフィーヴァー,L.庭田よう子(訳)(2013).わかりやすく説明する練習をしよう。 伝え方を鍛える コミュニケーションを深める 講談社(Amazon.co.jpレコメンド機能で知る)
[2013.12.21]IRなどについての文献メモ 文献一覧を更新
- 衛藤廣隆・藤井広志・船倉武夫(2013).大災害時における地域の公共図書館の役割とその支援体制 千葉科学大学紀要,5, 35-54.[PDF]
[2013.12.21]IRなどについての文献メモ 文献一覧を更新
- 土持ゲーリー法一(2006).戦後日本の高等教育改革政策:「教養教育」の構築 玉川大学出版部(京都光華女子大学図書館蔵書検索「教養教育」で知る)
- 斎藤兆史(2013).教養の力:東大駒場で学ぶこと 集英社(京都光華女子大学図書館蔵書検索「教養教育」で知る)
- 山田芳子・久保さつき・川又俊則・寺田喜朗(2009).教養教育の新たな学び:現代を生きるストラテジー 大学教育出版 (京都光華女子大学図書館蔵書検索「教養教育」で知る)
- ロスブラット,S.吉田文・杉谷祐美子(訳)(2009).教養教育の系譜:アメリカ高等教育にみる専門主義との葛藤 玉川大学出版部(京都光華女子大学図書館蔵書検索「教養教育」で知る)
- 慶應義塾大学教養研究センター(編)(2003).「教養」を考える:現代を読みとくために 慶應義塾大学教養研究センター(京都光華女子大学図書館蔵書検索「教養教育」で知る)
- 林哲介(2013).教養教育の思想性 ナカニシヤ出版(CiNii Books「教養教育」で知る)
- 寄川条路(2011).若者の未来をひらく:教養と教育 角川学芸出版(CiNii Books「教養教育」で知る)
- 杉谷祐美子(編).(2011).大学の学び:教育内容と方法 玉川大学出版部(CiNii Books「教養教育」で知る)
- 司馬春英・星川啓慈(編)(2010).「教養」のリメーク:大学生のために 大正大学出版会(CiNii Books「教養教育」で知る)
- 宇佐美寛(2010).作文の教育:「教養教育」批判 東信堂(CiNii Books「教養教育」で知る)
- 上垣豊(2009).市場化する大学と教養教育の危機 洛北出版(CiNii Books「教養教育」で知る)
- 葛西康徳・鈴木佳秀(編)(2009).これからの教養教育:「カタ」の効用 東信堂(CiNii Books「教養教育」で知る)
- 近森節子(編著)(2007).もうひとつの教養教育:職員による教育プログラムの開発 東信堂(CiNii Books「教養教育」で知る)
- 名古屋大学高等教育研究センター(2006).大学における教養教育カリキュラムの比較研究 名古屋大学高等教育研究センター(CiNii Books「教養教育」で知る)
- 大学教育学会25年史編纂委員会(編)(2004).あたらしい教養教育をめざして:大学教育学会25年の歩み:未来への提言 東信堂(CiNii Books「教養教育」で知る)
- 中央教育審議会(2002).新しい時代における教養教育の在り方について:答申(CiNii Books「教養教育」で知る)
- 寺崎昌男(2002).大学教育の可能性:教養教育・評価・実践 東信堂(CiNii Books「教養教育」で知る)
- 中央教育審議会(2000).新しい時代における教養教育の在り方について:審議のまとめ(CiNii Books「教養教育」で知る)
- 吉田文(2013).大学と教養教育:戦後日本における模索 岩波書店(Amazono.co.jp「教養教育」で知る)
- 竹内洋(2003).教養主義の没落:変わりゆくエリート学生文化 中央公論新社(Amazono.co.jp「教養教育」で知る)
- 廣川洋一(1990).ギリシア人の教育:教養とはなにか 岩波書店(Amazono.co.jp「教養教育」で知る)
- 石原千秋(2000).教養としての大学受験国語 筑摩書房(Amazono.co.jp「教養教育」で知る)
- 主婦と生活社ライフ・プラス編集部(編)(2011).名門大学の「教養」:NHK爆問学問 爆笑問題のニッポンの教養:東京大学 慶應義塾大学 京都大学 早稲田大学 東京藝術大学 主婦と生活社(Amazono.co.jp「教養教育」で知る)
- 岸本裕史(1996).見える学力、見えない学力 大月書店(Amazono.co.jp「教養教育」で知る)
[2013.12.21]IRなどについての文献メモ 文献一覧を更新
- 向後千春(2012).いちばんやさしい教える技術 永岡書店(Amazon.co.jpレコメンド機能で知る)
- 吉田たかよし(2005).「分かりやすい話し方」の技術:言いたいことを相手に確実に伝える15の方法 講談社(Amazon.co.jpレコメンド機能で知る)
- 藤沢晃治(1999).「分かりやすい表現」の技術:意図を正しく伝えるための16のルール 講談社(Amazon.co.jpレコメンド機能で知る)
- 藤沢晃治(2002).「分かりやすい説明」の技術 最強のプレゼンテーション15のルール 講談社(Amazon.co.jpレコメンド機能で知る)
- 藤沢晃治(2004).「分かりやすい文章」の技術:読み手を説得する18のテクニック講談社(Amazon.co.jpレコメンド機能で知る)
- 永田豊志(2009).頭がよくなる「図解思考」の技術 中経出版(Amazon.co.jpレコメンド機能で知る)
- 福嶋隆史(2009).「本当の国語力」が驚くほど伸びる本:偏差値20アップは当たり前! 大和出版(Amazon.co.jpレコメンド機能で知る)
- 佐々木かをり(2010).計画力面白練習帳 新訂版 日本能率協会マネジメントセンター(橋口美智留先生/京都光華女子大学からの紹介で知る)
[2013.12.18]IRなどについての文献メモ 文献一覧を更新
- 呑海沙織・溝上智恵子・孫誌衒(2013).韓国の大学図書館における学習支援:インフォメーション・コモンズからの飛躍に向けて 図書館情報メディア研究,11(1),47-58.[PDF](はてなブックマークインタレスト「ラーニングコモンズ」で知る)
[2013.12.08]IRなどについての文献メモ 文献一覧を更新
- 椿本弥生・大塚裕子・高橋理沙・美馬のゆり(2012).大学生を中心とした持続可能な学習支援組織の構築とピア・チュータリング実践 日本教育工学会論文誌,36(3),313-325.[PDF](CiNii Articles「正課 支援」で知る)
- 和泉徹彦(2011).キャンパス内通貨流通の構想と課題 嘉悦大学研究論集,54(1),19-34.[PDF](CiNii Articles「正課 支援」で知る)
- 井下理(2008).大学教育における正課外活動 IDE:現代の高等教育,498,32-37.(CiNii Articles「正課外」で知る)
[2013.12.06]IRなどについての文献メモ 原文PDFへのリンクを追加
- 溝上慎一(2007).アクティブ・ラーニング導入の実践的課題 名古屋高等教育研究,7,269-287.(アクティブラーニングが導入された授業実践に関する広範な文献調査、アクティブラーニングを講義型・演習型(課題探求型/課題解決型)に分類;小島・井上(2011)で知る)[PDF][内容]
- 畠山珠美(2011).ライティング・センター:構想から実現へ 情報の科学と技術,61(12),483-488.[PDF][内容](CiNii Articles「大学 チューター」の検索で知る)
- 廣田未来(2011).お茶の水女子大学附属図書館の学生支援:ラーニング・コモンズとLiSAプログラム 情報の科学と技術,61(12),489-494.[PDF][内容](CiNii Articles「大学 チューター」の検索で知る)
- 山田剛史(2004).過去-現在-未来にみられる青年の自己形成と可視化によるリフレクション効果:ライフヒストリーグラフによる青年理解の試み 青年心理学研究,16,15-35.[PDF][内容](舘野(2012)で知る)
- 三宅なほみ・齊藤萌木・飯窪真也・利根川太郎(2011).学習者中心型授業へのアプローチ:知識構成型ジグソー法を軸に 東京大学大学院教育学研究科紀要,51,441-458.[PDF][内容](CiNii Articles「ジグソー法」で知る)
- 宮崎洋・佐々木康浩・前間孝久・木村孝・魚住剛一郎(2006).「見える化」実践のポイント 三菱総合研究所所報,47,134-155.[PDF][内容]
[2013.11.20]「私立大学職員によるIR文献メモ」メルマガ バックナンバーを更新
[2013.11.12]大学に関わる情報メモ 内容をアップ
[2013.11.10]大学に関わる情報メモ 内容を追記
[2013.11.10]IRなどについての文献メモ 内容をアップ
- 佐藤浩章・城間祥子・大竹奈津子・香川順子・安野舞子・倉茂好匡(2011).授業コンサルテーションの現状と可能性 大学教育学会誌,33(2),50-53.(<事例紹介>愛媛大学:4名のコンサルタントで年間約40件の依頼に対応、2009年度から農学部の全教員にコンサルティングを実施、今後の課題はコンサルタントの育成・授業アンケートとの目的分化など、徳島大学:支援プロセスは授業参観→コンサルタントによる授業分析→授業研究会でのフィードバックと議論、滋賀県立大学:希望した教員に対して実施、支援者は改善すべき点を「交換ノート」に書く、教員はコメントを書いて支援者に返却する、支援者は指摘事項だけはなく具体的な改善方法・授業の良い点も書く、基本的技術(板書・発声など)に問題がある場合が多い、コンサルテーションの初期にはその基本的技術について改善提案をする、即効性があるので効果を実感してもらいやすい、その上で段階的に改善提案をしていく、<授業コンサルテーションの分類>プロフェッショナルによる指導型・同僚教員による支援型(midterm student feedbackの部分であれば職員の担当も可能)、<コンサルテーションの対象>新任教員がよい、<導入する際の課題など>小規模大学では教員と学生が顔見知りという状態なので第三者によるコンサルテーションが難しい、そのため複数の大学で連携して実施するという方法が考えられる、普及に時間をかける必要がある、1人のコンサルタントが全ての能力(傾聴・教育方法の知識・カリキュラムの理解・人間関係構築など)を身につけることは不可能、複数のコンサルタントの配置が望ましい;「ファカルティ・ディベロッパー養成講座in京都」佐藤浩章先生の配布資料で知る)
[2013.11.08]大学に関わる情報メモ 内容をアップ
[2013.10.26]IRなどについての文献メモ 文献一覧を更新
- 市川伸一(2001).学ぶ意欲の心理学 PHP研究所(Amazon.co.jp「意欲」で知る)
- 稲垣佳世子・波多野誼余夫(1989).人はいかに学ぶか:日常的認知の世界 中央公論社(市川(2001)で知る)
- 波多野誼余夫・稲垣佳世子(1984).知力と学力:学校で何を学ぶか 岩波書店(市川(2001)で知る)
- 鹿毛雅治(1996).内発的動機づけと教育評価 風間書房(市川(2001)で知る)
- 宮本美沙子・奈須正裕(編著)(1995).達成動機の理論と展開 金子書房(市川(2001)で知る)
- 奈須正裕(1996).学ぶ意欲を育てる:子どもが生きる学校づくり 金子書房(市川(2001)で知る)
- 市川伸一(1998).開かれた学びへの出発:21世紀の学校の役割 金子書房(市川(2001)で知る)
- 市川伸一(2011).学習と教育の心理学 岩波書店(市川(2001)で知る)
- 平井雷太(2005).どの子にも学力がつく:セルフラーニング 新曜社(市川(2001)で知る)
- 畑村洋太郎(2006).失敗学 ナツメ社(京都光華女子大学図書館蔵書検索「畑村洋太郎」で知る)
- 畑村洋太郎(2009).回復力:失敗からの復活 講談社(京都光華女子大学図書館蔵書検索「畑村洋太郎」で知る)
- 松尾睦(2011).「経験学習」入門 ダイヤモンド社(第11回SDフォーラムで知る)
[2013.10.20]IRなどについての文献メモ 文献一覧を更新
- 鈴木誠(2008).意欲を引き出す授業デザイン:人をやる気にするには何が必要か 東洋館出版社(京都光華女子大学図書館蔵書検索「意欲」で知る)
- 奈須正裕(2002).やる気はどこから来るのか:意欲の心理学理論 北大路書房(京都光華女子大学図書館蔵書検索「意欲」で知る)
- 上淵寿(編)(2004).動機づけ研究の最前線 北大路書房(京都光華女子大学図書館書架で知る)
- 外山美樹(2011).行動を起こし、持続する力:モチベーションの心理学 新曜社(京都光華女子大学図書館書架で知る)
- 鹿毛雅治(編)(2012).モティベーションをまなぶ12の理論:ゼロからわかる「やる気の心理学」入門! 金剛出版(京都光華女子大学図書館書架で知る)
- Deci, E. L., with Flaste, R. (1995). Why we do what we do: The dynamics of personal autonomy. New York: Putnam's Sons.(デシ,E.L.・フラスト,R.櫻井茂男(訳)(1999).人を伸ばす力:内発と自律のすすめ 新曜社)(京都光華女子大学図書館書架で知る)
- Border, L., Fisch, L., & Weimer, M. (2002). Ideas for campus newsletters. In K. J. Gillespie, L. R. Hilsen, & E. C. Wadsworth(Eds.), A guide to faculty development: Practical advice, examples and resources. Bolton: Anker Publishing Company. pp.123-132.(Amazonなか見!検索「A guide to faculty development」で知る)
- Norman, D. A. (2011). Living with complexity. Cambridge, Mass.: MIT Press.(ノーマン, D.A.伊賀聡一郎・岡本明・安村通晃(訳)(2011).複雑さと共に暮らす:デザインの挑戦 新曜社)(京都光華女子大学図書館蔵書検索「デザイン」で知る)
- 山崎亮(2013).コミュニティデザインの時代:自分たちで「まち」をつくる 中央公論新社(京都光華女子大学図書館蔵書検索「デザイン」で知る)
- Norman, D. A. (1988). The psychology of everyday things. New York: Basic Books.(ノーマン, D.A.野島久雄(訳)(1990).誰のためのデザイン?:認知科学者のデザイン原論 新曜社)(京都外国語大学付属図書館蔵書検索「認知科学」で知る)
- 情報デザインフォーラム(編)(2010).情報デザインの教室:仕事を変える、社会を変える、これからのデザインアプローチと手法 丸善(京都光華女子大学図書館蔵書検索「デザイン」で知る)
- 佐藤好彦(2008).デザインの教室:手を動かして学ぶデザイントレーニング エムディエヌコーポレーション(京都光華女子大学図書館蔵書検索「デザイン」で知る)
- 伊達千代・内藤タカヒコ(2006).デザイン・ルールズ:デザインをはじめる前に知っておきたいこと エムディエヌコーポレーション(京都光華女子大学図書館蔵書検索「デザイン」で知る)
- 川崎紀弘・アレフ・ゼロ(2011).実例で学ぶ「伝わる」デザイン グラフィック社(京都光華女子大学図書館蔵書検索「デザイン」で知る)
- 柘植ヒロポン(2011).新人デザイナーのための色彩デザイン・配色のルールを学べる本 ソシム(京都光華女子大学図書館蔵書検索「デザイン」で知る)
- Baker, W. (2000). Achieving success through social capital: Tapping the hidden resources in your personal and business networks. San Francisco: Jossey-Bass.(ベーカー,W.中島豊(訳)(2001).ソーシャル・キャピタル:人と組織の間にある「見えざる資産」を活用する ダイヤモンド社)(京都光華女子大学図書館蔵書検索「ソーシャルキャピタル」で知る)
- 玉沖仁美(2012).地域をプロデュースする仕事 英治出版(京都光華女子大学図書館蔵書検索「地域」で知る)
- 濱名篤・川嶋太津夫(編著)(2006).初年次教育:歴史・理論・実践と世界の動向 丸善(京都光華女子大学図書館蔵書検索「初年次教育」で知る)
- 鈴木宏昭(編著)(2009).学びあいが生みだす書く力:大学におけるレポートライティング教育の試み 丸善プラネット(京都光華女子大学図書館蔵書検索「鈴木宏昭」で知る)
- 太田信夫(編著)(2008).記憶の心理学 放送大学教育振興会(放送大学科目ナビ「記憶」で知る)
- Aronson, E. (1992). The social animal. New York: W.H. Freeman and Co.(アロンソン,E.岡隆・亀田達也(共訳)(1994).ザ・ソーシャル・アニマル:人間行動の社会心理学的研究 サイエンス社)(アロンソン,E.他 松山安雄訳(1986).ジグソー学級で知る)
[2013.10.15]IRなどについての文献メモ 内容をアップ、文献一覧を更新
- 安野舞子(2011).学生参加型授業コンサルテーションの試行とその効果検証 横浜国立大学 大学教育総合センター 紀要,1,16-27.[PDF][概要](CiNii Articles「授業コンサルティング」で知る)
- 藤江康彦(2008).授業コンサルテーションの理論と実践的方法の開発に関する研究 関西大学人間活動理論研究センターTechnical Reports,7,1-10.[PDF](授業コンサルテーションとは「教師が授業実践を、同僚や研究者とともに対象化し省察することを通して改善することを促す支援システム」;安野(2011)で知る)
[2013.10.15]「私立大学職員によるIR文献メモ」メルマガ バックナンバーを更新
[2013.10.14]IRなどについての文献メモ 内容をアップ
- Teeter, D. J., & Brinkman, P. T. (1992). Peer institutions. In M. A. Whiteley, J. D. Porter, & R. H. Fenske(Eds.), The primer for institutional research. Tallahassee, Florida: Association for Institutional Research. pp.63-72.[内容]
[2013.10.12]IRなどについての文献メモ 文献一覧を更新
- Brinkman, P. T. (1987). Conducting interinstitutional comparisons. New direction for institutional research, 53. San Francisco: Jossey-Bass.(自大学と他大学を比較するときに役立つデータ、それらのデータの分析方法;Teeter & Brinkman(1992)で知る)
- Ewell, P. T. (1987). Enhancing information use in decision-making. New direction for institutional research, 64. San Francisco: Jossey-Bass.(自大学と他大学を比較するときの情報の使い方、意思決定者との共有;Teeter & Brinkman(1992)で知る)
- Teeter, D. J. (1983). The politics of comparing data with other institutions. In J. W. Firnberg & W. F. Lasher(Eds.), The politics and pragmatics of institutional research. New direction for institutional research, 38, 39-48. San Francisco: Jossey-Bass.(自大学と他大学を比較するときのデータ交換;Teeter & Brinkman(1992)で知る)
- Teeter, D. J. ,& Christall, M. E. (1987). Establishing peer groups: A comparison of methodologies. Planning for higher education, 15(2), 8-17.(自大学と他大学を比較するときの様々な方法を紹介;Teeter & Brinkman(1992)で知る)
[2013.10.12]IRなどについての文献メモ 内容をアップ
- 佐藤浩章(2009).FDにおける臨床研究の必要性とその課題:授業コンサルテーションの効果測定を事例に 名古屋高等教育研究,9,179-198.[PDF][概要](CiNii Articles「授業コンサルティング」で知る)
[2013.10.12]IRなどについての文献メモ 文献一覧を更新
- Border, L., Fisch, L., & Weimer, M. (2002). Ideas for campus newsletters. In K. J. Gillespie, L. R. Hilsen, & E. C. Wadsworth(Eds.), A guide to faculty development: Practical advice, examples, and resources. pp.123-132.(Amazon.co.jp「A guide to faculty development」で知る)
- Lewis, K. G. (2002). The process of individual consultation. In K. J. Gillespie, L. R. Hilsen, & E. C. Wadsworth(Eds.), A guide to faculty development: Practical advice, examples, and resources. pp.59-73.(授業コンサルテーションは最も時間がかかるが最も有益な活動;佐藤(2009)で知る)
- Diamond, N. A. (2002). Small group instructional diagnosis: Tapping student perceptions of teaching. In K. J. Gillespie, L. R. Hilsen, & E. C. Wadsworth(Eds.), A guide to faculty development: Practical advice, examples, and resources. pp.83-91.(学期の中期間に学生の意見を活かした授業コンサルタントを行う、1980年代にワシントン大学で開発された;佐藤(2009)で知る)
- Nyquist, J. D., & Wulff, D. H. (2001). Consultation using a research perspective. In K. Lewis & J. Povlacs (Eds.), Face to face: A sourcebook of individual consultation techniques for faculty/instructional developers 2nd ed. Stillwater, OK: New Forums Press. pp. 45-62.(授業コンサルテーションに必要な5つのステップ、①[問題・課題・疑問の特定](クライアントの悩みを大切にする)、②[データ収集](量的手法・質的手法)、③[データ分析](分析ができないクライアントに生データを渡すと誤解の原因)、④[データ解釈](モデル・枠組み・アイデアを提示する)、⑤[データ変換](授業改善の立案をクライアントとともに行う、何をするかを決めるのはクライアント);佐藤(2009)で知る)
[2013.10.11]IRなどについての文献メモ 内容をアップ
- 楢林建司・佐藤浩章(2005).ワークショップ型授業の試みと授業コンサルティングサービス 大学教育実践ジャーナル,3,45-55.[PDF][概要](「ファカルティ・ディベロッパー養成講座in京都」佐藤浩章先生の配布資料で知る)
[2013.10.11]IRなどについての文献メモ 文献一覧を更新
- 阿部和厚・西森敏之・小笠原正明・細川敏幸・大滝純司(2000).北海道大学FDマニュアル 高等教育ジャ-ナル,7,29-125.[PDF](ワークショップ型FDの報告、授業スキルの向上のためにグループでの授業を開発し模擬授業を実施する;楢林・佐藤(2005)で知る)
- 京都大学高等教育教授システム開発センター(編)(1997).開かれた大学授業をめざして:京都大学公開実験授業の一年間 玉川大学出版部(公開授業型FDの報告、複数の参観者で授業参観を行う、その後に検討会も行う;楢林・佐藤(2005)で知る)
- 京都大学高等教育教授システム開発センター(編)(2001).大学授業のフィールドワーク:京都大学公開実験授業 玉川大学出版部(公開授業型FDの報告、複数の参観者で授業参観を行う、その後に検討会も行う;楢林・佐藤(2005)で知る)
[2013.10.10]大学に関わる情報メモ ページタイトルを変更
[2013.10.10]IRなどについての文献メモ 文献一覧を更新
- 加藤毅・鵜川健也(2010).大学経営の基盤となる日本型インスティテューショナル・リサーチの可能性 大学論集,41,235-250.[PDF]
[2013.10.09]IRなどについての文献メモ 文献一覧を更新
[2013.10.08]ホーム 「お知らせ」欄、過去の「お知らせ」に追加
[2013.10.08]IRなどについての文献メモ 文献一覧を更新
- 米澤誠(2013).学びを誘発するラーニング・コモンズ カレントアウェアネス,317,22-26.[HTML](Twitter(@ca_tweetさん)で知る)
- 永田治樹(2009).インフォメーションコモンズ・ラーニングコモンズ:新たな学習環境(場)の提供 図書館雑誌,103(11),746-749.(学習方法の見直しという文脈から図書館の再定義がされつつある、ラーニングコモンズの全体像を歴史的文脈の中で説明;米澤(2013)で知る)
- 河西由美子(2010).自律と協同の学びを支える図書館 山内祐平(編著)学びの空間が大学を変える ボイックス pp.102-127.(先行研究・事例報告を踏まえてラーニングコモンズを総括的に解説、自律と協同の学びを支える図書館としてラーニングコモンズを捉えている;米澤(2013)で知る)
- マクマレン, S.(2012).米国の大学図書館:今日のラーニング・コモンズ・モデル 加藤信哉・小山憲司(編訳)ラーニング・コモンズ-大学図書館の新しいかたち- 勁草書房 pp.25-36.(ラーニングコモンズの構成要素について具体例を示しながら説明;米澤(2013)で知る)
- リッピンコット, J. K.(2012).インフォメーション・コモンズを学習に結び付ける 加藤信哉・小山憲司(編訳)ラーニング・コモンズ-大学図書館の新しいかたち- 勁草書房 pp.141-162.(ラーニングコモンズをグループ学習の視点から捉えている、ラーニングコモンズは学生に学問と交流の両方の環境を提供;米澤(2013)で知る)
- 竹内比呂也(2012).“ラーニング・コモンズ”を超えて 加藤信哉・小山憲司(編訳)ラーニング・コモンズ-大学図書館の新しいかたち- 勁草書房 p.277-279.(日本のラーニング・コモンズの多くは機能ではなく空間としてしか存在していないと指摘;米澤(2013)で知る)
- 矢野正也(2009).学習環境デザインと「ラーニング・コモンズ」 IDE:現代の高等教育,510,60-65.(ラーニングコモンズの入門的な記事;米澤(2013)で知る)
- 矢野正也(2010).図書館における学習環境デザインの必要性:ラーニング・コモンズの事例より 短期大学図書館研究,30,101-105.(ラーニングコモンズの入門的な記事;米澤(2013)で知る)
- 村上孝弘(2010).ラーニング・コモンズの展開と大学図書館の今後 大学職員ジャーナル,14,32-37.(ラーニングコモンズの入門的な記事;米澤(2013)で知る)
- 病院図書館会編集部(2011).ラーニング・コモンズ 病院図書館,31(2),74-78.[PDF](ラーニングコモンズの入門的な記事;米澤(2013)で知る)
- 永田治樹(2008).大学図書館における新しい「場」:インフォメーション・コモンズとラーニング・コモンズ 名古屋大学附属図書館研究年報,7,3-14.[PDF](ビーグルの提唱するインフォメーションコモンズの3つのレベル(物理的・仮想的・文化的)について紹介;米澤(2013)で知る)
- 永田治樹(2010).図書館とインフォメーション・コモンズ:情報社会における共有資源 情報管理,53(7),370-380.[PDF](各大学図書館はインターネット環境を整備して電子ジャーナルや情報データベースへのアクセスを可能にした;奥田(2012)で知る)(ラーニングコモンズは大学図書館だけではなく公共図書館でも機能する;米澤(2013)で知る)
- 呑海沙織・溝上智恵子(2010).北米の大学図書館における学習支援空間の歴史的変容-ブリティッシュ・コロンビア大学の事例から カナダ教育研究,8,1-17.[PDF](CiNii Articles「呑海沙織」の検索で知る)(インフォメーションコモンズからラーニングコモンズへの展開を開設;米澤(2013)で知る)
- 相田芙美子・渡邊浩之・小川ゆきえ・山下大輔・古庄敬文(2011).ラーニングコモンズの要素分析:日本における導入を前提として 私立大学図書館協会研究助成報告書[PDF](ラーニングコモンズを導入する際のモデルを提示;米澤(2013)で知る)
- 小山憲司(2012).国内の大学図書館におけるラーニング・コモンズの現状:アンケート調査を中心に 加藤信哉・小山憲司(編訳)ラーニング・コモンズ-大学図書館の新しいかたち- 勁草書房 pp.203-269.(2010年時点での30大学のラーニングコモンズの一覧表;米澤(2013)で知る)
- 上田直人・長谷川豊祐(2008).わが国の大学図書館におけるラーニング・コモンズの事例研究 名古屋大学附属図書館研究年報,7,47-62.[PDF](ラーニングコモンズの事例を比較;米澤(2013)で知る)
- 立石亜紀子(2011).ラーニング・コモンズの現況:米国の現状調査と日米の比較 三田図書館・情報学会研究大会発表論文集 2011年度,21-24.(ラーニングコモンズの事例を比較;米澤(2013)で知る)
- 立石亜紀子(2012).日本の大学図書館におけるラーニング・コモンズ機能受容の過程 三田図書館・情報学会研究大会発表論文集 2012年度,21-24.(ラーニングコモンズの事例を比較;米澤(2013)で知る)
- ダリス, D., & ウォルターズ, C.(2012).コモンズ環境におけるレファレンス・サービス 加藤信哉・小山憲司(編訳)ラーニング・コモンズ-大学図書館の新しいかたち- 勁草書房 pp.163-184.(ラーニングコモンズで行っているレファレンス・サービスの事例;米澤(2013)で知る)
- ダニエルズ, T., & バラット, C. C.(2012).ラーニング・コモンズに共通するものは何か?この変化する環境でレファレンス・デスクを見ると 加藤信哉・小山憲司(編訳)ラーニング・コモンズ-大学図書館の新しいかたち- 勁草書房 pp.185-202.(ラーニングコモンズのレファレンスデスクについての調査;米澤(2013)で知る)
- 加藤信哉(2008).ラーニング・コモンズをもっと知るために:図書と雑誌論文の紹介 名古屋大学附属図書館研究年報,7,63-67.[PDF](ラーニングコモンズについての文献レビュー;米澤(2013)で知る)
- 加藤信哉・小山憲司(2012).ラーニング・コモンズ文献案内:翻訳論文のまえがきに代えて 加藤信哉・小山憲司(編訳)ラーニング・コモンズ-大学図書館の新しいかたち- 勁草書房 pp.1-23.(ラーニングコモンズについての文献レビュー;米澤(2013)で知る)
- 畠山珠美(2007).新しい情報空間の構築 畠山珠美・浅野智美・久保誠・黒澤公人・松山龍彦・山本裕之・長野由紀(2007)図書館の再出発:ICU図書館の15年 大学教育出版 pp.25-42.(国際基督教大学の学習支援の事例、国際基督教大学は日本で最も早く実績を上げたラーニングコモンズ;米澤(2013)で知る)
- 松山龍彦(2007).利用者サービス 畠山珠美・浅野智美・久保誠・黒澤公人・松山龍彦・山本裕之・長野由紀(2007)図書館の再出発:ICU図書館の15年 大学教育出版 pp.56-83.(国際基督教大学の学習支援の事例、国際基督教大学は日本で最も早く実績を上げたラーニングコモンズ;米澤(2013)で知る)
- 利根川樹美子(2012).ライティングサポートデスク:国際基督教大学図書館のラーニングコモンズの機能 大学の図書館,31(11),190-192.(国際基督教大学の学習支援の事例、国際基督教大学は日本で最も早く実績を上げたラーニングコモンズ;米澤(2013)で知る)
- 堀一成(2011).附属図書館ラーニング・コモンズを利用した教育実践の試み 大阪大学大学教育実践センター紀要,7,81-84.[PDF](大阪大学のライティング支援の事例;米澤(2013)で知る)
- 上原恵美・赤井規晃・堀一成(2011).ラーニング・コモンズ:そこで何をするのか何がやれるのか 図書館界,63(3),254-259.[PDF](大阪大学のライティング支援の事例;米澤(2013)で知る)
- 堀一成(2012).附属図書館ラーニング・コモンズを利用した大阪大学における学修支援の取り組み 図書館雑誌,106(11),765-767.(大阪大学のライティング支援の事例;米澤(2013)で知る)
- 歳森敦 筑波大学図書館情報学図書館でのラーニング・コモンズ誕生:教育との連携による小規模モデルの試み LISN,144,1-5.(筑波大学のラーニングコモンズの事例;米澤(2013)で知る)
- 松本紳・逸村裕・歳森敦(2011).筑波大学情報学群知識情報・図書館学類について:人材養成を中心に 大学図書館研究,91,9-14.[PDF](筑波大学のラーニングコモンズの事例;米澤(2013)で知る)
- 竹谷喜美江(2010).新潟大学ラーニング・コモンズについて 大学の図書館,29(7),143-146.[PDF](新潟大学のラーニングコモンズの事例;米澤(2013)で知る)
- 立石亜紀子(2010).ラーニング・コモンズと横浜国立大学中央図書館:これまでとこれから,LISN,144,6-10.(横浜国立大学のラーニングコモンズの事例;米澤(2013)で知る)
- 茎田美保子(2010).静岡大学附属図書館リニューアルLearning Park構想 大学の図書館,29(7),141-143.(CiNii Articles「図書館 リニューアル」で知る)(静岡大学のラーニングコモンズの事例;米澤(2013)で知る)
- 杉本昌彦(2010).多目的学習スペースの創設と学習支援:上智大学図書館の試み LISN,144,11-15.(上智大学のラーニングコモンズの事例;米澤(2013)で知る)
- 澁田勝(2012).広義のラーニングコモンズを目指して:獨協大学図書館の現状分析 大学時報,61(343),78-85.[slideshare](獨協大学のラーニングコモンズの事例;米澤(2013)で知る)
- 三井悟(2010).新たな場としての図書館サービスに向けて LISN,144,16-19.(東海大学のラーニングコモンズの事例;米澤(2013)で知る)
- 和田由季・津村光洋・日野美穂(2011).英国大学図書館におけるインフォメーション・コモンズと情報リテラシー教育 大学図書館研究,92,48-56.[PDF](英国のラーニングコモンズの事例;米澤(2013)で知る)
- 林一雅(2010).ケーススタディ:駒場アクティブラーニングスタジオ(東京大学) 山内祐平(編著)学びの空間が大学を変える ボイックス pp.18-42.(東京大学のラーニングコモンズの事例、スタジオ型教室でアクティブラーニングを用いている;米澤(2013)で知る)
- 望月俊男(2010).能動的な学びを促進するスタジオ型教室 山内祐平(編著)学びの空間が大学を変える ボイックス pp.46-74.(東京大学のラーニングコモンズの事例、スタジオ型教室でアクティブラーニングを用いている;米澤(2013)で知る)
- 山内祐平(2010).大学の学習空間をデザインする 佐伯胖(監修)・渡部信一(編)「学び」の認知科学事典 大修館書店 pp.239-249.(アクティブラーニングの解説;米澤(2013)で知る)
- 米田奈穂(2012).アカデミック・リンクという理想:本物のラーニング・コモンズをめざして 館灯,50,22-28.[PDF](千葉大学のラーニングコモンズの事例、アクティブラーニングを用いている;米澤(2013)で知る)
- 藤木剛康(2011).課題解決型学習の可能性:三重大学の事例をもとに 和歌山大学経済学会研究年報,15,133-139.[PDF](三重大学のラーニングコモンズの事例、全学的に取り組んでいるPBLをラーニングコモンズでも実施、建築学の研究者と連携;米澤(2013)で知る)
- 三根慎二(2012).ラーニング・コモンズはどのように利用されているか:三重大学における事例調査 三田図書館・情報学会研究大会発表論文集 2012年度,25-28.(三重大学のラーニングコモンズの事例、全学的に取り組んでいるPBLをラーニングコモンズでも実施、建築学の研究者と連携;米澤(2013)で知る)
- 柴山依子・加藤彰一・毛利志保(2012).大学キャンパスにおける問題発見型学習(PBL)用ラーニングコモンズの利用実態に関する研究 日本建築学会東海支部研究報告書,50,493-496.[PDF](三重大学のラーニングコモンズの事例、全学的に取り組んでいるPBLをラーニングコモンズでも実施、建築学の研究者と連携;米澤(2013)で知る)
- 澤口隆(2012).PBL手法を用いたワークショップの実践とプログラミング教育:湘北ラーニング・コモンズの活用 湘北紀要,33,147-161.(湘北大学のラーニングコモンズの事例、PBLの授業と連携;米澤(2013)で知る)
- 高橋可奈子(2009).湘北スタイルのラーニング・コモンズを目指して 図書館雑誌,103(12),833.(湘北大学のラーニングコモンズの事例、PBLの授業と連携;米澤(2013)で知る)
- ビーグル, D.(2008).ラーニング・コモンズの歴史的文脈 名古屋大学附属図書館研究年報,7,25-34.[PDF](ラーニングコモンズをアクティブラーニングとして位置付ける、事例も紹介;米澤(2013)で知る)
- キャロル, W.(2008).ラーニング・コモンズ:学生支援との連携 大学図書館研究,83,6-10.(ラーニングコモンズをアクティブラーニングとして位置付ける、事例も紹介;米澤(2013)で知る)
- ベネット, S.(2012).高等教育における学習スペースの設計に当たって最初に問うべき質問 加藤信哉・小山憲司(編訳)ラーニング・コモンズ-大学図書館の新しいかたち- 勁草書房 pp.103-139.(ラーニングコモンズを[単独学習と協同学習][学習スペースの静寂][他者と並んで座る「孤独な学習」]という視点から考察、米澤(2013)で知る)
- 小林一章(2009).マイライフ・マイライブラリー:東京女子大学 IDE,510,32-37.(東京女子大学のラーニングコモンズの事例、学生・教職員・地域住民などが交流して新たな学びを創り出す活動を支援(拡張的学習支援);米澤(2013)で知る)
- 西森年寿(2010).ケーススタディ:マイライフ・マイライブラリー(東京女子大学) 山内祐平(編著)学びの空間が大学を変える ボイックス pp.78-99.(東京女子大学のラーニングコモンズの事例、学生・教職員・地域住民などが交流して新たな学びを創り出す活動を支援(拡張的学習支援);米澤(2013)で知る)
- 茂出木理子(2008).ラーニング・コモンズの可能性:魅力ある学習空間へのお茶の水女子大学のチャレンジ 情報の科学と技術,58(7),341-346.[PDF](ラーニングコモンズの出現は情報のデジタル化による図書館不要論や入館者の減少が背景にある、お茶の水女子大学の図書館は小規模という利点を生かしている、図書館が主体となって協働の場を推進するためのポイント:図書館がやる気があることを学内にアピールする・できることから着手する・学生を運用に巻き込む、柱の周りにPC用の机を置いて限られた施設面積を有効活用している、学生用PCをシンクライアント方式で管理している、学生から見ると管理部署がどこかかではなく使いやすいかが重要、教員には資料がある場所として認識されているが教育の場としてはあまり認識されていない、図書館に入ってまず目にするものが図書館に対する意識を形成する;奥田(2012)で知る)(お茶の水女子大学のラーニングコモンズの事例、学生・教職員・地域住民などが交流して新たな学びを創り出す活動を支援(拡張的学習支援);米澤(2013)で知る)
- 餌取直子・茂出木理子(2008).お茶の水女子大学附属図書館における学習・教育支援サービスのチャレンジ:図書館の学習・教育支援サービスに限界はない 大学図書館研究,83,11-18.[PDF](お茶の水女子大学のラーニングコモンズの事例、学生・教職員・地域住民などが交流して新たな学びを創り出す活動を支援(拡張的学習支援);米澤(2013)で知る)
- 呑海沙織(2010).溶ける境界線:利用者と図書館の間で 情報管理,52(10),618-621.(ラーニングコモンズで学生と協働している事例、従来サービスを受ける側であった利用者(学生)がサービスを提供する側に立って活動を行う;米澤(2013)で知る)
- 椿本弥生(2010).ケーススタディ:公立はこだて未来大学 山内祐平(編著)学びの空間が大学を変える ボイックス pp.130-153.(ラーニングコモンズで大学図書館の範囲にとどまらない学びを提供;米澤(2013)で知る)
- 柳澤要(2010).開かれた大学を実現するコミュニケーションスペース 山内祐平(編著)学びの空間が大学を変える ボイックス pp.156-179.(公立はこだて未来大学のラーニングコモンズの事例、大学図書館の範囲にとどまらない学びを提供;米澤(2013)で知る)
- 小山和伸・北村隆之・中野 宏一(2011).ラーニング・コモンズ:公立はこだて未来大学の事例 経済貿易研究,37,149-152.[PDF](公立はこだて未来大学のラーニングコモンズの事例、大学図書館の範囲にとどまらない学びを提供;米澤(2013)で知る)
[2013.10.07]ページを立ち上げ(更新履歴、大学に関わる情報メモからリンク)、内容をアップ
[2013.10.06]IRなどについての文献メモ 文献一覧を更新
- 杉森公一(2012).私立大学におけるリメディアル教育の実践と課題(上) 週刊教育資料,1219,28-29.(CiNii Articles「杉森公一」で知る)
- 杉森公一(2012).私立大学におけるリメディアル教育の実践と課題(下) 週刊教育資料,1221,28-29.(CiNii Articles「杉森公一」で知る)
- 杉森公一・岡野大輔・側垣順子(2013).リメディアル教育・初年次教育の連携と学習支援への展開 日本リメディアル教育学会第9回全国大会口頭発表(金沢大学研究者情報で知る)
- 楢林建司・佐藤浩章(2005).ワークショップ型授業の試みと授業コンサルティングサービス 大学教育実践ジャーナル,3,45-55.[PDF](「ファカルティ・ディベロッパー養成講座in京都」佐藤浩章先生の配布資料で知る)
- 山地弘起(編著)(2007).授業評価活用ハンドブック 玉川大学出版部(「ファカルティ・ディベロッパー養成講座in京都」佐藤浩章先生の配布資料で知る)
- 東北大学高等教育開発推進センター(編)(2010).学生による授業評価の現在 東北大学出版会(「ファカルティ・ディベロッパー養成講座in京都」佐藤浩章先生の配布資料で知る)
- 佐藤浩章・城間祥子・大竹奈津子・香川順子・安野舞子・倉茂好匡(2011).授業コンサルテーションの現状と可能性 大学教育学会誌,33(2),50-53.(「ファカルティ・ディベロッパー養成講座in京都」佐藤浩章先生の配布資料で知る)
- 日置善郎・宮田政徳・川野卓二・香川順子・吉田博・奈良理恵(2013).2012年度徳島大学全学FD推進プログラムの実施報告 大学教育研究ジャーナル,10,152-175.[PDF](CiNii Articles「授業コンサルティング」で知る)
- 井上史子・土持ゲーリー法一・沖裕貴(2012).大学授業の改善(1):学生による授業コンサルティングの導入と訓練プログラムの開発 年会論文集,28,170-173.[PDF](CiNii Articles「授業コンサルティング」で知る)
- 日置善郎・宮田政徳・川野卓二・香川順子・吉田博・奈良理恵(2012).2011年度徳島大学全学FD推進プログラムの実施報告 大学教育研究ジャーナル,9,152-171.[PDF](CiNii Articles「授業コンサルティング」で知る)
- 日置善郎・宮田政徳・川野卓二・香川順子・田中さやか・吉田博・奈良理恵(2011).2010年度徳島大学全学FD推進プログラムの実施報告 大学教育研究ジャーナル,8,172-191.[PDF](CiNii Articles「授業コンサルティング」で知る)
- 安野舞子(2011).学生参加型授業コンサルテーションの試行とその効果検証 横浜国立大学 大学教育総合センター 紀要,1,16-27.[PDF](CiNii Articles「授業コンサルティング」で知る)
- 田中さやか・香川順子・神藤貴昭・川野卓二・吉田博・宮田政徳・曽田紘二(2010).大学における授業コンサルタントのスキルに関する考察:徳島大学の事例をもとに 日本教育工学会論文誌,34(Suppl.),169-172.[PDF](CiNii Articles「授業コンサルティング」で知る)
- 曽田紘二・宮田政徳・川野卓二・香川順子・田中さやか・吉田博・奈良理恵(2010).大学教育研究ジャーナル,7,211-226.[PDF](CiNii Articles「授業コンサルティング」で知る)
- 柘植雅義・河場哲史・赤松博子・尾崎朱・田中裕一・太田聡子・高田善彦・米澤公子・鳴海正也・雑賀美恵子(2010).小学校通常学級の授業研究会に特別支援教育の視点を如何に盛り込むか:兵庫県A小学校での授業コンサルテーションの試み 兵庫教育大学研究紀要,36,39-51.[PDF](CiNii Articles「授業コンサルティング」で知る)
- 尾澤重知・牧野治敏・岡田正彦・西村善博(2009).授業改善コンサルティングに基づく大学授業支援システムの開発と評価 日本教育工学会研究報告集,2009(5),39-44.(CiNii Articles「授業コンサルティング」で知る)
- 佐藤浩章(2009).FDにおける臨床研究の必要性とその課題:授業コンサルテーションの効果測定を事例に 名古屋高等教育研究,9,179-198.[PDF](CiNii Articles「授業コンサルティング」で知る)
- 曽田紘二・宮田政徳・川野卓二・齊藤隆仁・香川順子・奈良理恵(2009).2008年度徳島大学全学FD推進プログラムの実施報告 大学教育研究ジャーナル,6,171-189.[PDF](CiNii Articles「授業コンサルティング」で知る)
- 藤江康彦(2007).教室談話研究に基づく授業コンサルテーションの可能性 日本教育学会大會研究発表要項,66,148-149.[PDF](CiNii Articles「授業コンサルティング」で知る)
- 神藤貴昭(2007).大学における授業コンサルテーションの実施とその評価 日本教育心理学会総会発表論文集,49,492.[PDF](CiNii Articles「授業コンサルティング」で知る)
- 小野瀬雅人・塩見邦雄・中田栄・藤澤伸介・水野治久・田村節子・石隈利紀(2003).学校心理士として授業コンサルテーションをどう進めるか 日本教育心理学会総会発表論文集,45,S54-S55.[PDF](CiNii Articles「授業コンサルティング」で知る)
[2013.10.05]大学に関わる情報メモ 内容をアップ
[2013.09.26]大学に関わる情報メモ 内容を修正
[2013.09.22]大学に関わる情報メモ 内容をアップ
[2013.09.21]大学に関わる情報メモ 内容を修正
[2013.09.21]大学に関わる情報メモ 内容を修正
[2013.09.19]大学に関わる情報メモ 内容を修正
[2013.09.19]大学に関わる情報メモ 内容をアップ
[2013.09.18]IRなどについての文献メモ 内容を追記
[2013.09.14]大学に関わる情報メモ 内容をアップ
[2013.09.14]IRなどについての文献メモ 文献一覧を更新
- 中井俊樹・鳥居朋子・藤井都百(編)(2013).大学のIR Q&A 玉川大学出版部
[2013.09.14]更新履歴・IRなどについての文献メモ ページ構成を変更
[2013.08.13]IRなどについての文献メモ 文献一覧を更新、詳細をローカルPCに保存
- Aronson, E., Blaney, N., Stephin, C., Sikes, J. & Snapp, M. (1978). The jigsaw classroom. Beverly Hills, CA: Sage Publishing Company.[詳細をローカルPCに保存]
[2013.08.01]IRなどについての文献メモ 内容をアップ
- 中山留美子・長濱文与・中島誠・中西良文・南学(2010).大学教育目標の達成を目指す全学的初年次教育の導入 京都大学高等教育研究,16,37-48.[PDF](教育の望ましい姿:学生が教育目標をはっきり理解している・教育目標に対応した授業が行われている・教育目標に基づいて評価が行われている、三重大学の教育目標は4つの力の育成:感じる力・考える力・生きる力・コミュニケーション力、しかし4つの力が具体的にどのような能力・スキルと対応するかが明示されていなかった、そこで学生と教員が教育目標について理解・議論する機会として初年次教育科目を開講した、開講する前に「高等教育創造開発センター」の教員間で合意を得た、授業の冒頭でその日の授業のテーマ・内容・4つの力との関連・到達目標・90分の流れを明示するようにした、授業ではグループ活動でまとめた意見をクラス全体で共有する活動を行った、4つの力を理解するだけではなく具体的な実践方法を体得できる授業構成にした、毎回の授業後に4つの力の下位要素を示したワークシートでグループ活動の振り返りをした、全クラスを参観可能にした、学内での報告活動・学生の特性についての情報交換を行うことで学部を越えた議論が生まれた;CiNii Articles「初年次教育」で知る)
[2013.07.31]IRなどについての文献メモ 文献一覧を更新
- 高木香織(2008).保育者養成校における「日本語表現」の実践:大学の特色を活かす授業実践の試み 埼玉純真短期大学研究論文集,1,65-71.[PDF](CiNii Articles「保育者養成」で知る)
- 平松紀代子(2013).保育者養成校における地域貢献としてのひろば事業に関する一研究 京都聖母女学院短期大学研究紀要,42,113-124.[PDF](CiNii Articles「保育者養成」で知る)
- 斉藤美和子(2013).保育者養成におけるピアノ指導の現状と課題 人間生活学研究,4,71-77.[PDF](CiNii Articles「保育者養成」で知る)
- 北川剛司・三宅啓子(2013).大学による地域の保育者再就職支援:先行研究レビューを通して 高田短期大学紀要,31,89-96.[PDF](CiNii Articles「保育者養成」で知る)
- 宮崎つた子・小池はるか・山崎征子(2013).大学による地域の保育者再就職支援の調査研究(1) 高田短期大学紀要,31,97-105.[PDF](CiNii Articles「保育者養成」で知る)
- 上村晶(2013).保育者養成段階における保育実践力の向上に関する一考察(2) 高田短期大学紀要,31,79-88.[PDF](CiNii Articles「保育者養成」で知る)
- 田中崇教・柴田玲子・井上範子・池内裕二・出木浦孝・小西博子・中村多見・山本幾代・山田純子・田中弓子(2013).「カリキュラムの考え方と特色」改訂をテーマとした保育学科ファカルティ・ディベロップメント活動の実施報告:保育者養成カリキュラムの構造化と教育責任の明確化に向けた新たな試み 研究紀要,58・59,183-197.[PDF](CiNii Articles「保育者養成」で知る)
- 木村達志・石山由美・松永有三(2013).保育者養成校(短期大学)と付属幼稚園との連携による幼児教育現場での幼児体育Iの実施:第2報 プログラムの学習効果 安田女子大学紀要,41,169-175.[PDF](CiNii Articles「保育者養成」で知る)
- 石山由美・木村達志・松永有三(2013).保育者養成校(短期大学)と付属幼稚園との連携による幼児教育現場での幼児体育Iの実施:第1報 プログラム実現化までのプロセス 安田女子大学紀要,41,155-168.[PDF](CiNii Articles「保育者養成」で知る)
- 太田裕子・松田知明・花田嘉雄(2013).短期大学の保育者養成課程における入学前教育の検討(3):小論文課題の導入に着目して 羽陽学園短期大学紀要,9(3),95-111.[PDF](CiNii Articles「保育者養成」で知る)
- 広渡純子・讃岐京子(2012).保育者養成カリキュラムにおける科目間連携(1):「保育内容言葉」と「保育表現技術」の連携 聖和論集,40,69-78.[PDF](CiNii Articles「保育者養成」で知る)
- 中平勝子・赤羽美希・深見由紀子(2012).ピアノ弾き歌い教育の質保証 日本教育工学会論文誌,36(3),291-299.[PDF](CiNii Articles「保育者養成」で知る)
- 林悠子・森本美佐・東村知子・森本美佐・東村知子(2012).保育者養成校に求められる学生の資質について:保育現場へのアンケート調査より 紀要,43,127-134.[PDF](CiNii Articles「保育者養成」で知る)
- 川俣美砂子(2012).保育者養成過程におけるカリキュラムの比較分析:大学・短期大学・専門学校に焦点をあてて 福岡女子短大紀要,77,15-26.[PDF](CiNii Articles「保育者養成」で知る)
- 廿日出里美(2012).実践知の創造を支援するワークショップのアクションリサーチ:「芸術における学習」を保育者養成に導入する試み 日本教育学会大會研究発表要項71,196-197.[PDF](CiNii Articles「保育者養成」で知る)
- 新海節(2012).保育者養成校におけるピアノ教育 藤女子大学紀要第II部,49,147-153.[PDF](CiNii Articles「保育者養成」で知る)
- 大谷彰子・平化恵美子・平化恵美子(2012).保育者養成課程における実習に対する課題と不安の変容 甲子園短期大学紀要,30,67-73.[PDF](CiNii Articles「保育者養成」で知る)
- 沢登芙美子・山田千明・高野牧子・池田政子・堀井啓幸・池田充裕・鳥居美佳子・古屋祥子(2012).力量ある保育者養成教育の試み:「乳幼児観察研究」の授業を通して 山梨県立大学人間福祉学部紀要,7,49-58.[PDF](CiNii Articles「保育者養成」で知る)
- 五十嵐淳子・宍戸良子(2012).保育者養成校におけるサービスラーニングのあり方:保育現場のアンケート結果から 桜の聖母短期大学紀要,36,115-129.(CiNii Articles「保育者養成」で知る)
- 西本佳代・国広勝代(2012).保育者養成課程における専門性育成の課題 山口福祉文化大学研究紀要,6,21-30.[PDF](CiNii Articles「保育者養成」で知る)
- 音山若穂・利根川智子・井上孝之・上村裕樹・三浦主博・河合規仁・安藤節子・和田明人(2012).保育者養成における実習指導への対話的アプローチの導入に関する基礎研究 群馬大学教育実践研究,29,219-228.[PDF](CiNii Articles「保育者養成」で知る)
- 太田裕子・松田知明・花田嘉雄(2012).短期大学の保育者養成課程における入学前教育の検討(2):プレキャンパスの実施に着目して 羽陽学園短期大学紀要,9(2),243-256.[PDF](CiNii Articles「保育者養成」で知る)
- 吉村啓子・岡野聡子(2011).保育者養成校における就職活動の特徴と課題:就職支援の実践から見えるもの 京都光華女子大学短期大学部研究紀要,49,1-6.[PDF](CiNii Articles「保育者養成」で知る)
- 川俣美砂子(2011).保育者養成カリキュラムの現状と課題:学校間比較を中心として 日本教育社会学会大会発表要旨集録,63,340-341.[PDF](CiNii Articles「保育者養成」で知る)
- 萩尾ミドリ・池田可奈子・椎山克己(2011).保育者養成校における子育て支援活動の実際と学生への教育的効果 久留米信愛女学院短期大学研究紀要,34,117-124.[PDF](CiNii Articles「保育者養成」で知る)
- 廿日出里美(2011).保育者養成という現場の日常:人々を実践に向かわせる知の再構成 教育社会学研究,88,65-86.[PDF](CiNii Articles「保育者養成」で知る)
- 石川正子(2011).保育者養成校における子育て支援の取り組み 盛岡大学短期大学部紀要,21,23-31.[PDF](CiNii Articles「保育者養成」で知る)
- 重成久美・篠永洋・吉牟田美代子(2011).保育者養成課程における「環境を通して行う保育」を重視した授業の展開1:保育実習1に向けた教科間の連関を通して 活水論文集 健康生活学部編,54,91-101.[PDF](CiNii Articles「保育者養成」で知る)
- 橋本弘道(2011).保育者養成の視点から見た仏教保育と教育の原理 鶴見大学紀要第3部 保育・歯科衛生編,48,77-82.[PDF](CiNii Articles「保育者養成」で知る)
- 碓井幸子(2011).今日求められる保育の質と保育者養成の課題:保育内容に要求される保育の専門性 清泉女学院短期大学研究紀要,30,11-21.[PDF](CiNii Articles「保育者養成」で知る)
- 佐藤智恵(2011).保育者養成校で学ぶ学生がもつ保育観に関する研究:取得資格による比較より 幼年教育研究年報,33,31-39.[PDF](CiNii Articles「保育者養成」で知る)
- 佐藤智朗(2011).短期大学における保育者養成の課題(2):学生の意欲を引き出す試み 山口芸術短期大学研究紀要,43,11-29.(CiNii Articles「保育者養成」で知る)
- 千古利恵子(2011).「私の指導法」検証:保育者養成科目担当者の課題 京都文教短期大学研究紀要,50,61-69.[PDF](CiNii Articles「保育者養成」で知る)
- 菊地達夫(2011).保育者養成課程における環境問題を題材とした主体的学習の実践と意義 北翔大学短期大学部研究紀要,49,17-27.[PDF](CiNii Articles「保育者養成」で知る)
- 谷川夏実(2010).幼稚園実習におけるリアリティ・ショックと保育に関する認識の変容 保育学研究,48(2),202-212.[PDF](CiNii Articles「保育者養成」で知る)
- 中根淳子(2010).保育者養成校におけるいのちの教育:出生前診断をテーマとした取り組み 研究紀要,32,41-52.[PDF](CiNii Articles「保育者養成」で知る)
- 坂東宏和・大即洋子・大島浩太・小野和(2010).幼稚園および保育者養成校での利用を想定した幼児用電子掲示板システムの提案 情報処理学会研究報告 コンピュータと教育研究会報告,2010-CE-106(7),1-7.[PDF](CiNii Articles「保育者養成」で知る)
- 椛島香代(2010).大学内子育て支援施設の保育者養成への活用 日本教育学会大會研究発表要項,69,252-253.[PDF](CiNii Articles「保育者養成」で知る)
- 杉原徹・小島一久(2010).保育者養成校と附属幼稚園との連携のあり方に関する研究:教育実習事前指導重点化のための試みを通して 高知学園短期大学紀要,40,57-68.[PDF](CiNii Articles「保育者養成」で知る)
- 小川圭子・水野智美(2009).保育者養成校で扱われている発達障害に関する内容:発達障害に関する新任保育者の知識と困り感との関係から 障害理解研究,11,11-17.(CiNii Articles「保育者養成」で知る)
- 開仁志・橋本麻里(2009).保育者養成における合同授業の試み:理論・実技・実践のつながり 富山短期大学紀要,44,81-92.[PDF](CiNii Articles「保育者養成」で知る)
[2013.07.26]IRなどについての文献メモ 文献一覧を更新
- 森時彦(2007).ファシリテーター養成講座:人と組織を動かす力が身につく! ダイヤモンド社(京都光華女子大学図書館蔵書検索「ファシリテーター」で知る)
[2013.07.26]大学に関わる情報メモ 内容を修正
[2013.07.24]IRなどについての文献メモ 文献一覧を更新
- 堀水潤一(2009).京都市立堀川高校 二兎を追いながら自立する18歳を育む カレッジマネジメント,27(2),22-25.[PDF](CiNii Articles「堀川高校」で知る)
- 勝見明(2009).成功の本質(第42回)京都市立堀川高校 Works,14(6),36-41.[PDF](CiNii Articles「堀川高校」で知る)
- 荒瀬克己・高島三幸(2008).ロングインタビュー 荒瀬克己 京都市立堀川高校校長 日経ビジネスassocié 7(3),96-103.(CiNii Articles「堀川高校」で知る)
- 山本正志(2008).第七二回[高等教育研究会]定例研究会・二〇〇七年七月二十三日 これからも大きく変わる京都の学校:奇跡と呼ばれた学校(堀川高校)の実践を踏まえて 大学創造,20,36-45.(CiNii Articles「堀川高校」で知る)
- 堀水潤一(2007).キャリア教育で学校を変える。教師が変える。シリーズ・改革者たち(第16回)京都市立堀川高校 校長 荒瀬克己 キャリアガイダンス,39(1),58-63.[電子ブック](CiNii Articles「堀川高校」で知る)
[2013.07.24]IRなどについての文献メモ 文献一覧を更新、内容をアップ
- 菅田徹・伴浩美・沢野 伸浩(2005).e-Learningを用いた大学初年用基礎学力養成システム 電子情報通信学会技術研究報告.ET, 教育工学,105(124),19-22.[PDF](より多くの基礎問題を効率よく繰り返しこなしていくシステムをExcelのマクロで作った(高度な知識をわかりやすく教えるのではない)、教員に問題作成・採点の負担をかけない、統一的に学ばせるのではなく学生のレベルに合わせて学習させる、問題を200問用意してWeb上に掲載した、問題の解き方は分野・設問ごとに学生が作った、問題はランダムに出題される、学生は解答をExcelファイルに入力して専用のメールアドレスにファイル添付で送る、教員は添付ファイルを指定フォルダにコピーする、集計マクロを実行するとファイル取り込み・採点・順位づけ・問題の難易度のグラフ化・成績の累積が自動で行われる;CiNii Articles「基礎学習」で知る)
[2013.07.23]大学に関わる情報メモ 内容をアップ
[2013.07.19]IRなどについての文献メモ 文献一覧を更新
- 堀公俊(2004).ファシリテーション入門 日本経済新聞社(Amazon.co.jp「ファシリテーター」で知る)
[2013.07.15]IRなどについての文献メモ 文献一覧を更新
- 堀公俊・加藤彰(2006).ファシリテーション・グラフィック:議論を「見える化」する技法 日本経済新聞社(京都光華女子大学図書館蔵書検索「ファシリテーション」で知る)
[2013.07.14]ホーム 「お知らせ」欄、過去の「お知らせ」に追加
[2013.07.09]IRなどについての文献メモ 文献一覧を更新、内容をアップ
- 中島彰子(2009).「確認くん」を活用した入学前教育 大手前大学CELL教育論集,1,9-12.[PDF](携帯電話対応型LMS(learning management system)を利用して入学前教育を行った、学内で開発・運用を行っている、合格決定時期に合わせて2期で実施した、第1期:1月31日~3月21日、第2期:3月7日~3月28日、実施科目:日本語表現・英語表現・情報活用、回答方法:事前に配布された小冊子を見ながら回答する、課題配信の間隔:課題は1週ごとに3週間LMSで配信、4周目に内容が理解できているかを確認するテスト、この[3週間の学習+4週目のテスト]は初年次必修科目の教育システムと連動している、動機づけを促す仕組み:[課題を提出すると即座に画面上で○が表示される(スタンプとして可視化)]+[期限が過ぎると提出できない]、スクーリング:期間の最後の週にスクーリング(保護者の参加も可)で[初年次教育システムの概要説明]+[3科目の課題を90分にまとめた授業]を行った、学習意欲を持続させる仕組み:メール+電話で質問を受け付けた、入学前の段階から大学・学生でコミュニケーションがとれることにつながった、課題の提出率(3科目の平均):第1期が80.6%・第2期が74.7%、提出率が高かった理由:PC環境がなくても携帯電話で課題提出ができる・スタンプで学習活動が可視化される・人による学習支援に力を入れた、アンケートの結果:携帯電話を使った課題提出についての設問で「郵送よりも楽で良かった」が91.9%;CiNii Articles「基礎学習」で知る)
- 川西雪也・新井野洋一・湯川治敏・小松川浩(2008).e-Learningを活用した入学前教育に関する実証研究 メディア教育研究,5(1),87-95.[PDF](e-Learningの今後の課題は実施目標・状況に応じた使い分けや学習者の意欲の長期持続;中島(2009)で知る)
- 小松川浩(2009).入学前教育 リメディアル教育向けeラーニング活用:千歳科学技術大学での事例を介して リメディアル教育研究,4(1),25-30.(e-Learningの今後の課題は実施目標・状況に応じた使い分けや学習者の意欲の長期持続;中島(2009)で知る)
[2013.07.08]IRなどについての文献メモ 文献一覧を更新、内容をアップ
- 八木澤ちひろ(2013).大学図書館における学生協働について:学生協働まっぷの事例から カレントアウェアネス,316,10-14.[HTML](大学図書館での学生協働の活動形態について調査した、活動が出てきた背景:主体的な学びが求められるようになったことに対して「空間」(ラーニングコモンズ))と「人材」(学生協働)の側面から支援、「学生協働まっぷ」:大学図書館の学生協働の取り組みの事例集(2011年3月~2012年5月に収集)・73事例を掲載・悉皆調査ではない・「①図書館業務サポート」「②学生選書」「③学習支援」「④学生サークル・その他」で分類、①図書館業務サポート:独自名称で学生スタッフのアイデンティティを高めている例が多い、②学生選書:定期・不定期に学生が書店で希望図書を購入する形態が多い、③学習支援:学習相談・レポート作成支援が主な活動・上級生や院生がチューターをしている例が多い、④学生サークル・その他:学生団体が図書館内で活動するものなど、学生協働を通して学生が得ること:図書館について理解を深める(運営側の視点)・他者と連携する力・自主的な企画立案、図書館側の利点:図書館に協力的な学生を発掘・職務内容を教える中で職員自身のスキルアップ・職員の同士の連携が深まる・職員数の不足をカバー、学生協働の問題点:有償の場合は財源が必要・学生スタッフのモチベーション維持;Twitter(@ca_tweetさん)で知る)
- 久保山健(2013).図書館スタッフによる学習支援の実践:「プレゼン入門 話す基本技術」 大阪大学高等教育研究,1,77-83.[PDF](授業外で学習支援を行った、目標は人前でロジカルに話す力を身につけること、教員と図書館スタッフが協働した、授業休業期(2月半ば~3月初め)に2コマで実施した、構成:1コマ目:自己紹介(受講理由の紹介など)・スピーチの基本(トピックセンテンス・パラグラフ)について解説+1分間スピーチで実践、2コマ目:声や間を意識しながら自己紹介・デリバリー技術(導入と結び・つなぎの言葉・声・アイコンタクト)について解説+1分間スピーチで実践、1分間スピーチ:ペアでお互いにフィードバックしながら練習(聞くことの楽しさを感じてもらう)・1コマ目は自席で立ち上がるだけだが2コマ目は全身が見える位置でスピーチ、役割分担:良い点をコメント・改善点をコメント・コメントシートに記入、コメントするときも1分間で話してもらう(スピーチ時の時間感覚を体験)、受講生のアンケートで高い評価だった(5段階評価、1コマ目平均4.5・2コマ目平均4.6)、高評価の背景:話す技術について学習する機会が少ない、継続性の確保が課題;CiNii Articles「基礎学習」で知る)
[2013.06.28]大学に関わる情報メモ 内容をアップ
[2013.06.16]IRなどについての文献メモ 文献一覧を更新
- Taylor, J., Hanlon, M., & Yorke, M. (2013). The evolution and practice of institutional research. New Directions for Institutional Research, 2013(157), 59-75.(Google Scholar「institutional research」で知る)
[2013.06.16]IRなどについての文献メモ 文献一覧を更新、詳細をローカルPCに保存
- 中原淳・荒木淳子・北村士朗・長岡健(2006).企業内人材育成入門 ダイヤモンド社[詳細をローカルPCに保存]
- 堀公俊・加藤彰(2006).ファシリテーション・グラフィック:議論を「見える化」する技法 日本経済新聞社[詳細をローカルPCに保存]
- ドナ・ウォン(村井瑞枝翻訳)(2011).ウォールストリート・ジャーナル式図解表現のルール かんき出版[詳細をローカルPCに保存]
- 茂木一司(編集代表)・苅宿俊文・佐藤優香・上田信行・宮田義郎(編)(2010).協同と表現のワークショップ:学びのための環境のデザイン 東信堂(Amazon.co.jp「ワークショップ」で知る)[詳細をローカルPCに保存]
- 堀公俊(2003).問題解決ファシリテーター:「ファシリテーション能力」養成講座 東洋経済新報社(Amazon.co.jp「ファシリテーター」で知る)[詳細をローカルPCに保存]
- 堀公俊(2006).組織変革ファシリテーター:「ファシリテーション能力」実践講座 東洋経済新報社(Amazon.co.jp「ファシリテーター」で知る)[詳細をローカルPCに保存]
- 三宅なほみ(編著)(2003).学習科学とテクノロジ 放送大学教育振興会(学習科学では人の賢さが発現する仕組みについての知見を授業改善に活かす実践実証型の研究が積み重ねられている;三宅他(2011)で知る)[詳細をローカルPCに保存]
- 中原淳(2011).知がめぐり、人がつながる場のデザイン:働く大人が学び続ける"ラーニングバー"というしくみ 英治出版(上田・中原(2013)、ブクログ「プレイフル・ラーニングの本棚」で知る)[詳細をローカルPCに保存]
[2013.06.15]IRなどについての文献メモ 文献一覧を更新
- Chan, D. L., & Wong, G. K. (2013). If you build it, they will come: An intra-institutional user engagement process in the Learning Commons. New Library World, 114(1/2), 44-53.(Google Scholar「learning commons」で知る)
- Hunley, S., & Schaller, M. (2009). Assessment: The key to creating spaces that promote learning. EDUCAUSE Review, 44(2), 26-35.[PDF](EDUCASE Review Onlineサイト内検索「learning space」で知る)
- Lippincott, J. K. (2009). Learning spaces: Involving faculty to improve pedagogy. EDUCAUSE Review, 44(3), 16-.25[PDF](EDUCASE Review Onlineサイト内検索「learning space」で知る)
- Dugdale, S. (2009). Space strategies for the new learning landscape. EDUCAUSE Review, 44(2), 51-63.[PDF](EDUCASE Review Onlineサイト内検索「learning space」で知る)
- Lippincott, J. K., van den Blink, C. C., Lewis, M., Stuart, C., & Oswald, L. B. (2009). A long-term view for learning spaces. EDUCAUSE Review, 44(2), 10-11.[PDF](EDUCASE Review Onlineサイト内検索「learning space」で知る)
- Long, P. D., & Ehrmann, S. C. (2005). Future of the learning space: Breaking out of the box. EDUCAUSE Review, 40(4), 42-58.[PDF](EDUCASE Review Onlineサイト内検索「learning space」で知る)
- Milne, A. J. (2007). Entering the interaction age: Implementing a future vision for campus learning spaces...today. EDUCAUSE Review, 42(1), 12-31.[PDF](EDUCASE Review Onlineサイト内検索「learning space」で知る)
- Lomas, C. (2005). Learning space design photos and interviews. EDUCAUSE Review Online, January 1, 2005 <http://www.educause.edu/ero/article/learning-space-design-photos-and-interviews> (June 15, 2013)[HTML](EDUCASE Review Onlineサイト内検索「learning space」で知る)
- Wedge, C. C., & Kearns, T. D. (2005). Creation of the learning space: Catalysts for envisioning and navigating the design process. EDUCAUSE Review, 40(4), 32-38.[PDF](EDUCASE Review Onlineサイト内検索「learning space」で知る)
- Valenti, M. S. (2005). Learning space design precepts and assumptions. EDUCAUSE Review, 40(4), 40.[PDF](EDUCASE Review Onlineサイト内検索「learning space」で知る)
- Brown, M. (2005). Learning space design theory and practice. EDUCAUSE Review, 40(4), 30.[PDF](EDUCASE Review Onlineサイト内検索「learning space」で知る)
- Grummon, P. T. H. (2009). Best practices in learning space design: Engaging users. EDUCAUSE Review Online, March 26, 2009 (June 15, 2013) <http://www.educause.edu/ero/article/best-practices-learning-space-design-engaging-users> [HTML](EDUCASE Review Onlineサイト内検索「learning space」で知る)
- Webster, K. (2010). The library space as learning space. EDUCAUSE Review, 45(6), 10-11.[PDF](EDUCASE Review Onlineサイト内検索「learning space」で知る)
- McGlynn, M., Peters, A., & Rafferty, S. (2012). If you build it, Will they come? Library learning spaces and technology. EDUCAUSE Review Online, November 1, 2012 (June 15, 2013) <http://www.educause.edu/ero/article/if-you-build-it-will-they-come-library-learning-spaces-and-technology>[HTML](EDUCASE Review Onlineサイト内検索「learning space」で知る)
- Aspden, E. J., & Thorpe, L. (2009). "Where do you learn?": Tweeting to inform learning space development. EDUCAUSE Review Online, March 26, 2009 (June 15, 2013) <http://www.educause.edu/ero/article/where-do-you-learn-tweeting-inform-learning-space-development>[HTML](EDUCASE Review Onlineサイト内検索「learning space」で知る)
- Walker, J. D., Brooks, D. C., & Baepler, P. (2011). Pedagogy and space: Empirical research on new learning rnvironments. EDUCAUSE Review Online, December 15, 2011 (June 15, 2013) <http://www.educause.edu/ero/article/pedagogy-and-space-empirical-research-new-learning-environments>[HTML](EDUCASE Review Onlineサイト内検索「learning space」で知る)
- Whiteside, A., Brooks, D. C. & Walker, J. D. (2010). Making the case for space: Three years of empirical research on learning environments. EDUCAUSE Review Online, September 22, 2010 (June 15, 2013) <http://www.educause.edu/ero/article/making-case-space-three-years-empirical-research-learning-environments>[HTML](EDUCASE Review Onlineサイト内検索「learning space」で知る)
- Britnell, J. C., Andriati, R., & Wilson, L. (2009). Learning space design with an inclusive planning process promotes user engagement. EDUCAUSE Review Online, December 22, 2009 (June 15, 2013) <http://www.educause.edu/ero/article/learning-space-design-inclusive-planning-process-promotes-user-engagement> [HTML](EDUCASE Review Onlineサイト内検索「learning space」で知る)
- MacPhee, L. (2009). Learning spaces: A tutorial. EDUCAUSE Review Online, March 26, 2009 <http://www.educause.edu/ero/article/learning-spaces-tutorial> (June 15, 2013) [HTML](EDUCASE Review Onlineサイト内検索「learning space」で知る)
- Hammons, A., & Oswald, L. B. (2009). Collaborative learning spaces at Missouri University of Science and Technology. EDUCAUSE Review Online, March 26, 2009 (June 15, 2013) <http://www.educause.edu/ero/article/collaborative-learning-spaces-missouri-university-science-and-technology>[HTML](EDUCASE Review Onlineサイト内検索「learning space」で知る)
- Long, P. D. (2005). Learning space design in action. EDUCAUSE Review, 40(4), 60.[PDF](EDUCASE Review Onlineサイト内検索「learning space」で知る)
- Herz, J. C. (2005). The space between: Creating a context for learning. EDUCAUSE Review, 40(3), 30-39.[PDF](EDUCASE Review Onlineサイト内検索「learning space」で知る)
- Long, P. D., & Holeton, R. (2009). Signposts of the revolution? What we talk about when we talk about learning spaces. EDUCAUSE Review, 44(2), 36-49.[PDF](EDUCASE Review Onlineサイト内検索「learning space」で知る)
- Graetz, K. (2006). The psychology of learning environments. EDUCAUSE Review, 41(6), 60-75.(EDUCASE Review Onlineサイト内検索「learning space」で知る)
[2013.05.15]IRなどについての文献メモ 文献一覧を更新、内容をアップ
- 宮崎洋・佐々木康浩・前間孝久・木村孝・魚住剛一郎(2006).「見える化」実践のポイント 三菱総合研究所所報,47,134-155.[PDF][内容]
[2013.05.13]IRなどについての文献メモ 内容をアップ
- 三宅なほみ・齊藤萌木・飯窪真也・利根川太郎(2011).学習者中心型授業へのアプローチ:知識構成型ジグソー法を軸に 東京大学大学院教育学研究科紀要,51,441-458.[PDF][内容](CiNii Articles「ジグソー法」で知る)
[2013.05.09]IRなどについての文献メモ 文献一覧を更新
- 金子元久(2011).IR:期待、幻想、可能性 IDE:現代の高等教育,528,4-12.
- 柳浦猛(2011).「アメリカのIRの本質」?:日本でIRが根付いていくために必要なこと IDE:現代の高等教育,528,12-17.
- 本田寛輔(2011).アメリカのIRと日本への示唆 IDE:現代の高等教育,528,17-25.
- 関口正司(2011).IRから見た大学評価の課題 IDE:現代の高等教育,528,25-30.
- 山田礼子(2011).学生調査とIR IDE:現代の高等教育,528,30-35.
- 高田英一(2011).大学評価を基礎とするIR:九州大学大学評価情報室における試行的取組について IDE:現代の高等教育,528,35-39.
- 村上雅人(2011).芝浦工業大学の教学改革とIR IDE:現代の高等教育,528,39-43.
- 鳥居朋子(2011).立命館大学における教学領域のIR IDE:現代の高等教育,528,43-47.
- 鈴木敏之(2011).東京大学のIRと評価をめぐる課題:「行動シナリオ」とその実行 IDE:現代の高等教育,528,48-52.
- 高倉翔(2011).第二期の認証評価:自己点検・評価の実質化を IDE:現代の高等教育,528,52-56.
[2013.05.09]IRなどについての文献メモ ページ構成を変更
[2013.04.26]大学に関わる情報メモ 内容をアップ
[2013.04.15]IRなどについての文献メモ 内容をアップ
- 山田剛史(2009).大学での学習成果 研究所報,51,100-106.[PDF][概要](山田・森(2008)で知る)
[2013.04.11]IRなどについての文献メモ 文献一覧を更新
- 鈴木克明(1995)「教室学習文脈へのリアリティ付与について:ジャスパープロジェクトを例に 教育メディア研究,2(1),13-27.[WEB](Google「The Jasper Project」で知る)
[2013.04.10]IRなどについての文献メモ 文献一覧を更新
- 小方直幸(2008).学生のエンゲージメントと大学教育のアウトカム 高等教育研究,11,45-64.(大学教育のアウトカムを重視する傾向が強まっている;山田・森(2008)で知る)
- Moon, J. (2002). The module & programme development handbook:A practical guide to linking levels, learning outcomes & assessment. London: Kogan Page.(ラーニングアウトカムを「学習者が学習期間終了後に知り、理解し、できるようになることが期待されることについて、また、どのようにしてその学習(の成果)が示されるべきかについて表明」されたものとして定義(川嶋(2008)訳);山田・森(2008)で知る)
- 川嶋太津夫(2008).ラーニング・アウトカムズを重視した大学教育改革の国際的動向と我が国への示唆 名古屋高等教育研究,8,173-191.[PDF](Moon(2002)のラーニングアウトカムの定義の訳を掲載;山田・森(2008)で知る)
- 吉本圭一(2007).卒業生を通した「教育の成果」の点検・評価方法の研究 大学評価・学位研究,5,75-107.[PDF](教育機関の説明責任が強く問われる時代が来ている、「教育の成果」を点検・評価することが多くの高等教育機関の中長期計画における具体的な取り組みの課題として明記されるようになってきている、大学教育に関する効果検証は充分に研究されていない、カリキュラムの外(アルバイトやサークルなど)で学生が自ら育つという環境提供も評価の枠組みに組み込んでおく必要がある;山田・森(2008)で知る)
- 松繁寿和(編著)(2004).大学教育効果の実証分析:ある国立大学卒業生たちのその後 日本評論社(大学教育に関する効果検証は充分に研究されていない;山田・森(2008)で知る)
- Pascarella, E. T., & Terenzini, P. T. (2005). How college affects students: A third decade of research. San Francisco: Jossey-Bass.(カレッジ・インパクト理論、「大学の効果は、キャンパスでの学術的、対人的、そして正課外の活動への個々人の努力と関与によって大きく規定される」;山田・森(2008)で知る)(アメリカのカレッジインパクト研究について2500あまりの論文をレビュー、教員中心のティーチングから学生志向のラーニングへ変化、学生の主体的な関わりなしには効果的な学習成果は得られない、大学教育は双方向的でホーリスティックな性格を持つ;藤村(2013)「大規模学生調査から学習成果と学習時間の構造を掴む」で知る)
- Astin, A. W. (1993). Assessment for excellence: The philosophy and practice of assessment and evaluation in higher education. Phoenix, Ariz: Oryx Press.(I-E-O(Input, Environment, Outcome/Output)モデル;山田・森(2008)で知る)
- Kuh, G. D., Palmer, M., & Kish, K. (2003). The value of educationally purposeful out-of-class experiences. In T. L. Skipper & R. Argo(Eds.), Involvement in campus activities and the retention of first-year college students (The first-year experience monograph series, No.36). Columbia, SC: University of South Carolina. pp.19-34(大学適応についてエンゲージメントとアウトカムの関連から調査;山田・森(2008)で知る)
- Kuh, G. D. (1993). In their own words: What students learn outside the classroom. American Educational Research Journal, 30(2), 277-304.(授業外での活動経験の役割;山田・森(2008)で知る)
- Kuh, G. D. (1995). The other curriculum: Out-of-class experiences associated with student learning and personal development. The Journal of Higher Education, 66(2), 123-155.(授業外での活動経験の役割;山田・森(2008)で知る)
- 山田剛史(2004).現代大学生における自己形成とアイデンティティ:日常的活動とその文脈の観点から 教育心理学研究,52(4),402-413.[PDF](学生にとって重要な日常活動に関する記述をKJ法で分類して6カテゴリーを抽出した、[授業・講義に関する活動][クラブ・サークルに関する活動][アルバイト活動][自己研さんに関する活動][遊び・対人関係に関する活動][生活習慣に関する活動];山田・森(2008)で知る)
- 山田剛史(2009).大学での学習成果 研究所報,51,100-106.(学修内容と卒業後のキャリアが直結する学部系統は比較的高い汎用的技能を持っている;山田・森(2008)で知る)
- 溝上慎一・中間玲子・山田剛史・森朋子(2009).学習タイプ(授業・授業外学習)による知識・技能の獲得差違 大学教育学会誌,31(1),112-119.(学修内容と卒業後のキャリアが直結する学部系統は比較的高い汎用的技能を持っている、大学教育改革は[正課・正課外を含むトータルな視点]や[学生の成長・発達という視点]から捉えていく必要がある、またその研究・実践を蓄積していく必要がある;山田・森(2008)で知る)
[2013.04.09]IRなどについての文献メモ 文献一覧を更新
- 東京大学大学発教育支援コンソーシアム推進機構(2011).自治体との連携による協調学習の授業づくりプロジェクト 大学発教育支援コンソーシアム推進機構(小中高で授業改善のための学習コミュニティ(教員・研究者・教育委員会・一般社会人など)を形成、個人内での知識の統合を明示的に支援する「知識構成型ジグソー法」を実践・評価している;三宅他(2011)で知る)
- Sawyer, R. K.(Ed.) (2003). The cambridge handbook of learning sciences. Cambridge: Cambridge University Press.(学習科学では人の賢さが発現する仕組みについての知見を授業改善に活かす実践実証型の研究が積み重ねられている;三宅他(2011)で知る)
- 三宅なほみ(編著)(2003).学習科学とテクノロジ 放送大学教育振興会(学習科学では人の賢さが発現する仕組みについての知見を授業改善に活かす実践実証型の研究が積み重ねられている;三宅他(2011)で知る)
- Brown, A. L. (1978). Knowing when, where, and how to remember: A problem of metacognition. In R. Glaser(Ed.), Advances in instructional psychology. Mahwah, N.J.: Lawrence Erlbaum Associates. pp.77–165.(認知的能力の知見を授業改善に活かすための研究、学習困難児であっても潜在的に自己の学習のプロセスをモニタリングする能力をもっていることに依拠する授業;三宅他(2011)で知る)
- Palinscar, A. S., & Brown, A. L. (1984). Reciprocal teaching of comprehension monitoring activities. Cognition and Instruction, 1, 117-175.[PDF](学習活動中に能力の高いメンバーが繰り返し自己モニタリングを行う様子が見られる;三宅他(2011)で知る)
- Miyake, N. (1986). Constructive interaction and the iterative processes of understanding. Cognitive Science, 10, 151-177.[PDF](人は潜在的に他人と関わり合いながら自分の考えの抽象度を上げて適用範囲を広げる能力を持っている、協調学習で1人ひとりの学習者が何を学んでいるかを見るためには個人ごとの分析が必要、表向き2人が一緒に考えているように見えても実際は各自が自分なりの理解・納得をしている、[自分の考えてを相手に説明する役]と[相手が説明する過程や内容を評価する役]を交代して視野を広げながら考えを統合して納得できる解を導き出そうとしていた;三宅他(2011)で知る)
- The Cognition & Technology Group at Vanderbilt (1997). The Jasper Project: Lesson in curriculum, instruction, assessment,and professional development. Mahwah, N.J.: Lawrence Erlbaum Associates.(主に教育困難校の生徒を対象にして算数・数学の問題解決能力を育成する目的で始められたプロジェクト(The Jasper Project)、ドラマ仕立てのビデオを多用した教材群、現実社会にありそうな場面を使う;三宅他(2011)で知る)
- Jacobson, M. J., Kin, B., Miao, C., Shen, Z., & Chavez, M. (2010). Design perspectives for learningin virtual worlds. In J. Jacobson & P. Reimann(Eds.), Designs for learning environments of the future: Internatinal learning sciences theory and research perspectives. New York: Springer-Verlag.(Webを使ったゲーム性の強い学習支援;三宅他(2011)で知る)
- Clark, D., & Linn, M. C. (2003). Designing for knowledge integration: The impact of instructional time. The Journal of the Learning Sciences, 12(4), 451-493.(生徒同士の話し合いにかける時間を十分に確保することが深い理解のために重要、選択肢問題は話し合いの時間を減らしても正解率が落ちなかった、しかし選択理由の記述の質は話し合いの時間が短くなるほど落ちた;三宅他(2011)で知る)
- Bereiter, C., & Scardamalia, M. (2006). Knowledge building: Theory, pedagogy, and technology. In R. K. Sawyer(Ed.), The cambridge handbook of learning sciencies. Cambridge: Cambridge University Press. pp.97-117.([知っていることを伝えるだけのknowledge tellingな書き方]と[書くことによって自分自身の考えを深め広げていくknowledge transformingな書き方]を区別し後者を積極的・系統的に支援する;三宅他(2011)で知る)
- Roschelle, J. (1992). Learning by collaborating: Convergent conceptual change. Journal of the Learning Sciences, 2(3), 235-276.[PDF](協調的な活動の有効性についてのひとつの説明、複数の人の異なったアイデアが共通の問いを説く場に持ち出されて1つの答えに収斂していく(「収斂説」);三宅他(2011)で知る)
- 三宅なほみ(1985).理解におけるインタラクションとはなにか 佐伯胖(編)認知科学選書4 理解とは何か 東京大学出版会 pp.69-98.(協調学習で1人ひとりの学習者が何を学んでいるかを見るためには個人ごとの分析が必要、表向き2人が一緒に考えているように見えても実際は各自が自分なりの理解・納得をしている、[自分の考えてを相手に説明する役]と[相手が説明する過程や内容を評価する役]を交代して視野を広げながら考えを統合して納得できる解を導き出そうとしていた;三宅他(2011)で知る)
- Shirouzu, H., Miyake, N., & Masukawa, H. (2002). Cognitively active externalization for situated reflection. Cognitive Science, 26, 469–501.[PDF](協調学習で1人ひとりの学習者が何を学んでいるかを見るためには個人ごとの分析が必要、表向き2人が一緒に考えているように見えても実際は各自が自分なりの理解・納得をしている、[自分の考えてを相手に説明する役]と[相手が説明する過程や内容を評価する役]を交代して視野を広げながら考えを統合して納得できる解を導き出そうとしていた;三宅他(2011)で知る)
- Bereiter, C., & Scardamalia, M. (1993). Surpassing ourselves: An inquiry into the nature and implications of expertise. Chicago: Open Court.(知識を得ることが次の学習の準備になるという学習形態;三宅他(2011)で知る)
- Bereiter, C. (2002). Education and mind in the knowledge age. Mahwah, N.J.: Lawrence Erlbaum Associates.(知識を得ることが次の学習の準備になるという学習形態、発展的な質問はその場での理解の深さよりも将来の学びにつながる理解の仕方を表す;三宅他(2011)で知る)
- Engle, R. A., & Conant, F. R. (2002). Guiding principles for fostering productive disciplinary engagement: Explaining an emergent argument in a community of learners classroom. Cognition and Instruction, 20(4), 399-483.(知識を得ることが次の学習の準備になるという学習形態;三宅他(2011)で知る)
- Schwartz, D., & Martin, T. (2004). Inventing to prepare for future learning: The hidden efficiency of encouraging original student production in statistics instruction. Cognition and Instruction, 22, 129-184.[PDF](発展的な質問はその場での理解の深さよりも将来の学びにつながる理解の仕方を表す;三宅他(2011)で知る)
- Miyake, N., & Norman, D. A. (1979). To ask a question, one must know enough to know what is not known. Journal of Verbal Learning and Verbal Behavior, 18(3), 357–364.(自分の解が他人と違うために感じる不完全感・未到達感が次の学びを引き起こす可能性が高い;三宅他(2011)で知る)
- 稲垣佳世子・波多野誼余夫(1971).事例の新奇性にもとづく認知的動機づけの効果 教育心理学研究,19(1),1-12.[PDF](自分の解が他人と違うために感じる不完全感・未到達感が次の学びを引き起こす可能性が高い;三宅他(2011)で知る)
[2013.04.04]IRなどについての文献メモ 内容をアップ
- 山田剛史・森朋子(2010).学生の視点から捉えた汎用的技能獲得における正課・正課外の役割 日本教育工学会論文誌,34(1),13-21.[PDF][概要](河井(2012)で知る)
- 津村光洋(2011).鳥取大学附属図書館のラーニング・コモンズ 鳥取大学教育研究論集,1,97-102.[PDF][概要](奥田(2012)で知る)
[2013.04.04]IRなどについての文献メモ 文献一覧を更新
- 谷川裕稔(代表編集)(2012).学士力を支える学習支援の方法論 ナカニシヤ出版(鮫島輝美先生(京都光華女子大学)からの紹介で知る)
- 清水亮・橋本勝(編著)(2012).学生・職員と創る大学教育:大学を変えるFDとSDの新発想 ナカニシヤ出版(鮫島輝美先生(京都光華女子大学)からの紹介で知る)
- 清水亮・橋本勝・松本美奈(編著)(2009).学生と変える大学教育:FDを楽しむという発想 ナカニシヤ出版(鮫島輝美先生(京都光華女子大学)からの紹介で知る)
- 三宅なほみ(2011).東京大学大学発教育支援コンソーシアム推進機構の試み:知識構成型ジグソー法による授業づくりを軸に IDE:現代の高等教育,536,40-44.(CiNii Articles「ジグソー法」で知る)
- 三宅なほみ・齊藤萌木・飯窪真也・利根川太郎(2011).学習者中心型授業へのアプローチ:知識構成型ジグソー法を軸に 東京大学大学院教育学研究科紀要,51,441-458.[PDF](CiNii Articles「ジグソー法」で知る)
- 三宅なほみ(2011).概念変化のための協調過程:教室で学習者同士が話し合うことの意味 心理学評論,54(3),328-341.(CiNii Articles「ジグソー法」で知る)
- 清宮悠磨(2010).中学校数学科におけるジグソー法の一考察:式,表,グラフの活用をテーマとした指導法 数学教育論文発表会論文集,43(2),513-518.[PDF](CiNii Articles「ジグソー法」で知る)
- 浅野真紀子(2010).学びを創る学校図書館のコラボレーション:中学校社会科「協調型調べ学習」の実践から 学校図書館学研究,12,73-82.(CiNii Articles「ジグソー法」で知る)
- 長田尚子・鈴木宏昭・小田光宏・杉谷祐美子(2008).ジグソー法による多人数会話における役割分担・交替に関する検討 言語・音声理解と対話処理研究会,52,59-64.[PDF](CiNii Articles「ジグソー法」で知る)
- 長田尚子・鈴木宏昭・三宅なほみ(2006).ジグソー法を用いたグループ活動による論証スタイルの理解支援:大学の「レポートの書き方」の授業における発話分析 日本認知科学会大会発表論文集,23,62-63.(CiNii Articles「ジグソー法」で知る)
- 長田尚子・鈴木宏昭・三宅なほみ(2005).大学の導入教育におけるblogを活用した協調学習の設計とその評価 知能と情報:日本知能情報ファジィ学会誌,17(5),525-535.[PDF](CiNii Articles「ジグソー法」で知る)
- 渋谷和彦(2005).ユビキタス・ジグソー法による協同学習の構想:ネットワーク構成型協同学習へ向けて シミュレーション&ゲーミング,15(1),24-34.(CiNii Articles「ジグソー法」で知る)
- 三崎隆(2000).ジグソー法の導入によって授業がわかる生徒を育てる 理科の教育,49(7),480-483.(CiNii Articles「ジグソー法」で知る)
- 山田政寛(2010).ラーニング・コモンズにおける学習空間と学習支援を考える LISN,144,20-23.(ライティングセンターなどの学習支援は個人に閉じた学習になる、ラーニングコモンズではグループ学習の支援を重視;津村(2011)で知る)
- Bennett, S. (2008). The Information or the learning commons: Which will we have? Journal of Academic Librarianship, 34, 183-185.[PDF](ラーニングコモンズは大学のミッションや教育目標と深い関連性を持つ必要がある;茂出木(2008)で知る)
[2013.04.03]IRなどについての文献メモ 内容をアップ
- 茂出木理子(2008).ラーニング・コモンズの可能性:魅力ある学習空間へのお茶の水女子大学のチャレンジ 情報の科学と技術,58(7),341-346.[PDF][概要](奥田(2012)で知る)
[2013.04.01]IRなどについての文献メモ 文献一覧を更新
- Seymour, D. T. (1991). TQM on campus: What the pioneers are finding. American Association for Higher Education Bulletin, 44(3), 10-13.(TQMの効果を20を超える大学で調査した、不要な手順・失敗・冗長を取り除けた、学部をまたいで協力した、ミッションを深く理解した、財政的に節約ができたなど;Heverly(1992)で知る)
- Sherr, L. A. & Teeter, D. J. (Eds.)(1991). Total Quality Management in Higher Education. New Directions for Institutional Research, 71. San Francisco: Jossey-Bass.(高等教育でのTQM;Heverly(1992)で知る)
[2013.04.01]IRなどについての文献メモ 文献一覧を更新、内容をアップ
- 吉田武大(2012).アメリカにおけるバリュールーブリックの活用動向 教育総合研究叢書,5,103-111.[PDF](バリュールーブリックは15項目から構成される、AAC&Cが定義した学士課程教育段階の「基本学習成果(essential learning outcomes)」を測定するために作成された、科目・コース・機関を越えて活用することが可能、ただし活用にあたっては必要に応じて表現を書き換えるなどの対応をしないといけない、バリュールーブリックを書き換えて活用している事例を紹介:全く達成していない状態をレベル0とする・学士課程教育段階の学生の能力を超える評価基準を含めない・評価基準の表現を主観的ではなく客観的なものにする・評価の観点について関係する複数の教員で時間をかけて協議する、日本の高等教育でバリュールーブリックを活用するために考慮すべきこと:評価基準の表現を客観的にする(複数の教員が学生の答案サンプルなどを使って表現の解釈にずれが生じないかを検証)・学生が身につける能力を学習教材や宿題などで具体的に設定する;CiNii Articles「ルーブリック」で知る)
- Heverly, M. A. (1992). Total quality management. In M. A. Whiteley, J. D. Porter, & R. H. Fenske(Eds.), The primer for institutional research. Tallahassee, Florida: Association for Institutional Research. pp.100-112.[概要]
- 溝上慎一(2009).「大学生活の過ごし方」から見た学生の学びと成長の検討:正課・正課外のバランスのとれた活動が高い成長を示す 京都大学高等教育研究,15,107-118.[PDF](授業外学習時間は1日に1時間未満、授業外での活動・学習が学生の知識・技能の習得などの学習成果に結びつく、これまでの大学生調査研究では大学生活をどう過ごすかという個人的な観点から学生をタイプ分けしている研究が見られる、大学生活の中で学習に重きを置かない学生が一定するいる;河井(2012)で知る)
[2013.03.30]IRなどについての文献メモ 内容をアップ
- 蒋逸凡・高橋徹・岩倉光助・中井孝幸(2012).大学図書館における学習スタイルと座席選択について:居場所の形成からみた大学図書館の施設計画に関する研究 その2 東海支部研究報告集,50,461-464.[PDF][概要](CiNii Articles「中井孝幸」で知る)
- 岩倉光助・高橋徹・蒋逸凡・中井孝幸(2012).大学図書館の施設構成からみた学習スタイルについて:居場所の形成からみた大学図書館の施設計画に関する研究 その1 東海支部研究報告集,50,457-460.[PDF][概要](CiNii Articles「中井孝幸」で知る)
[2013.03.28]IRなどについての文献メモ 文献一覧を更新、内容をアップ
- 山田政寛・橋洋平・香川文恵・岡部幸祐(2011).図書館における協調学習空間と学習の情意面の関係に関する調査 日本教育工学会論文誌,35,53-56.[PDF][概要](CiNii Articles「教育工学」で知る)
- 鈴木雅之(2011).ルーブリックの提示が学習者に及ぼす影響のメカニズムと具体的事例の効果の検討 日本教育工学会論文誌,35(3),279-287.[PDF](ルーブリックを提示する影響について調査した、中学2年生が対象、テストの目的に納得している学生ほどテストに対する認識が変わった;CiNii Articles「ルーブリック」で知る)
- Brown, G. T. L., & Hirschfeld, G. H. F. (2008). Students' conception of assessment: Links to outcomes. Assessment in Education: Principles, Policy & Practice, 15, 3-17.([学習者へのテストの影響]は[学習者がテストや評価の実施をどう捉えるか]が大きく影響する;鈴木(2011)ルーブリックの提示が・・・で知る)
- Peterson, E. R., & Irving, S. E. (2008). Secondary school students' conception of assessment and feedback. Learning and Instruction, 18, 238-250.([学習者へのテストの影響]は[学習者がテストや評価の実施をどう捉えるか]が大きく影響する;鈴木(2011)ルーブリックの提示が・・・で知る)
- 鈴木雅之(2009).テスト観の構造及び目標志向性・学習観・成績との関連 日本テスト学会第7回大会発表論文抄録集,212-215.([学習者へのテストの影響]は[学習者がテストや評価の実施をどう捉えるか]が大きく影響する、テストは学習改善に役立つといった認識を強く持つことで学習意欲が高まる;鈴木(2011)ルーブリックの提示が・・・で知る)
- 村山航(2006).テスト形式スキーマへの介入が空所補充型テストと学習方略との関係に及ぼす影響 教育心理学研究,54(1),63-74.[PDF](評価の意図・基準について学習者が理解できるようにテストを行うと学習者の動機づけや学習行動がポジティブに方向づけられる;鈴木(2011)ルーブリックの提示が・・・で知る)
- 鈴木雅之(2011).ルーブリックの提示による評価基準・評価目的の教示が学習者に及ぼす影響:テスト観・動機づけ・学習方略に着目して 教育心理学研究,59(2),131-143.[PDF](評価の意図・基準について学習者が理解できるようにテストを行うと学習者の動機づけや学習行動がポジティブに方向づけられる、テストをフィードバックするときにルーブリックを提示した群は提示しなかった群に比べてテストの学習改善という目的・役割を強く認識した;鈴木(2011)ルーブリックの提示が・・・で知る)
- 田中耕治(2008).学力調査と教育評価研究 教育學研究,75(2),146-156.[PDF](ルーブリックを学習者に提示することで学習行動や自己評価の指針を示すことが可能;鈴木(2011)ルーブリックの提示が・・・で知る)
[2013.03.26]IRなどについての文献メモ 内容をアップ
[2013.03.21]IRなどについての文献メモ 文献一覧を更新
- 田中毎実(2003).大学教育学とは何か 京都大学高等教育研究開発推進センター(編)大学教育学 培風館 pp.1-20(大学教育を取り巻く状況が急激に変化している、大学に対する社会のニーズが変化してきている;奥田(2012)で知る)
- 吉見俊哉(2011).大学とは何か 岩波書店(大学教育を取り巻く状況が急激に変化している;奥田(2012)で知る)
- 舘昭(2004).学士課程教育構築の課題 絹川正吉・舘昭 学士課程教育の改革 東信堂 pp.5-23(大学に対する社会のニーズが変化してきている;奥田(2012)で知る)
- 早田幸政・青野透・諸星裕(編)(2010).高等教育論入門:大学教育のこれから ミネルヴァ書房(大学に対する社会のニーズが変化してきている;奥田(2012)で知る)
- 寺崎昌男(1999).大学教育の創造:歴史・システム・カリキュラム 東信堂(学生は教員の専門的知識を書き留めるという受動的な学習態度が求められてきた;奥田(2012)で知る)
- 中村博幸・内田和夫(2009).ゼミを中心としたカリキュラムの連続性:学生が育つ授業・学生を育てる授業-教員と学生が授業をつくる 嘉悦大学研究論集,51(3),1-13.[PDF](学生は教員の専門的知識を書き留めるという受動的な学習態度が求められてきた、大学教育といっても各大学に固有の文脈がある、学ぶ学生も一様ではない;奥田(2012)で知る)
- 日本私立大学連盟(編)(1999).大学の教育・授業の変革と創造:教育から学習へ 東海大学出版会(「教育から学習」へという教育観の転換;奥田(2012)で知る)
- ノイマン, K.(大膳司・渡邊隆信(訳))(2009).大学における教育文化から学習文化への転換:大学教授学と大学改善のためのカリキュラム計画 大学論集,40,327-341.[PDF] )(「教育から学習」へという教育観の転換;奥田(2012)で知る)
- 米澤誠(2008).ラーニング・コモンズの本質:ICT時代における情報リテラシー オープン教育を実現する基盤施設としての図書館 名古屋大学附属図書館研究年報,7,35-45.[PDF](初等・中等教育に見られる「オープン教育」への変化、インターネット環境の整備により大学教員や大学院生にとって図書館の利用が必然的なものではなくなった;奥田(2012)で知る)
- Engeström, Y. (1987). Learning by expanding: An activity - Theoretical approach to developmental research. Helsinki: Orienta-Konsultit.[PDF](社会文化的学習観、集団間の矛盾や葛藤が新たな学びを創発する;奥田(2012)で知る)
- 河合塾(編著)(2011).アクティブラーニングでなぜ学生が成長するのか:経済系・工学系の全国大学調査からみえてきたこと 東信堂(学生による主体的・能動的な学習は総じてアクティブ・ラーニングと呼ばれる;奥田(2012)で知る)
- 溝上慎一(2010).概説:アクティブ・ラーニングとは Guideline,11,44-51.(アクティブラーニングの定義、「学生の能動的な学習を取り込んだ授業を総称する用語;奥田(2012)で知る)
- 美馬のゆり・山内祐平(2005).「未来の学び」をデザインする:空間・活動・共同体 東京大学出版会(アクティブラーニング型の授業を円滑に導入するためには学習環境として空間・活動・共同体・人工物を有機的にデザインする必要がある;奥田(2012)で知る)
- 柴山依子・ハサウネファヘッド・加藤彰一(2010).学習形態と学習施設の関係に関する研究:三重大学におけるラーニングコモンズの改修計画を事例として 日本建築学会大会学術講演梗概集,463-464.[PDF](大学教育において全国的に学習環境への関心が高まっている;奥田(2012)で知る)
- 米澤誠(2006).インフォメーション・コモンズからラーニング・コモンズへ:大学図書館におけるネット世代の学習支援 カレントアウェアネス,289,9-12. (大学へのラーニングコモンズ設置という動きは図書館改革としてのインフォメーションコモンズ設置がきっかけ、この論文で「ラーニング・コモンズ」という用語が紹介された;奥田(2012)で知る)
- Beagle, D. (2008). The learning commons in historical context 名古屋大学附属図書館研究年報,7,15-24.[PDF](大学へのラーニングコモンズ設置という動きは図書館改革としてのインフォメーションコモンズ設置がきっかけ;奥田(2012)で知る)
- Beagle, D. (2006). The information commons handbook. New York:Neal-Schuman Publishers.(「学習を支援するために組織された、物理的、デジタル的、人的、社会的な資源を関係付けた、ネットワーク利用のためのアクセスポイントと、関連する情報技術(IT)の道具の集合体」;奥田(2012)で知る)
- 茂出木理子(2008).ラーニング・コモンズの可能性:魅力ある学習空間へのお茶の水女子大学のチャレンジ 情報の科学と技術,58(7),341-346.[PDF](情報のデジタル化による図書館不要論や入館者の減少;奥田(2012)で知る)
- 永田治樹(2010).図書館とインフォメーション・コモンズ:情報社会における共有資源 情報管理,53(7),370-380.[PDF](各大学図書館はインターネット環境を整備して電子ジャーナルや情報データベースへのアクセスを可能にした;奥田(2012)で知る)
- Bailey, D. R. & Tierney, B. G. (2008). Transforming library service through information commons: Case studies for the digital age. Chicago: American Library Association.(各大学図書館はインターネット環境を整備して電子ジャーナルや情報データベースへのアクセスを可能にした;奥田(2012)で知る)
- 奥田雄一郎・小柏伸夫(2011).ユビキタス・キャンパスにおける学生主体プロジェクトを通した大学生の学び 共愛学園前橋国際大学論集,11,53-64.(大学のキャンパス全体がインフォメーションコモンズと呼べる学習環境を持つ大学の事例;奥田(2012)で知る)
- 小圷守(2009).情報リテラシーとラーニング・コモンズ:日米大学図書館における学習支援 情報の科学と技術,59(7),328-333.[PDF](「インフォメーション・コモンズは「ハコ」、ラーニング・コモンズは「ひとを介したサービス」」;奥田(2012)で知る)
- 原郭二・加藤彰一(2010).学習スタイルの変化から見た大学図書館のコモンスペースの計画と利用に関する研究:ラーニングコモンズのファシリティマネジメント研究 東海支部研究報告集,48,369-372.[PDF](ラーニングコモンズでは学生の主体的な学習活動を重視する、また学生が自主的に問題解決を行い自分の知見を加えて発信するという学習活動全般を支援する、そのための施設とサービスを提供する;奥田(2012)で知る)
- Bennett, S. (2008). The Information or the learning commons: Which will we have? Journal of Academic Librarianship, 34, 183-185.[PDF](ラーニングコモンズでは学生の主体的な学習活動を重視する、また学生が自主的に問題解決を行い自分の知見を加えて発信するという学習活動全般を支援する、そのための施設とサービスを提供する;奥田(2012)で知る)
- 佐藤翔(2008).「学びの場の新しいカタチ」と「新しい学びのカタチ」:第17回大図研オープンカレッジ参加報告 大学の図書館,27(8),162-163.[PDF](大学図書館の役割が変化した、ラーニングコモンズとして学生のアウトプットを生み出す過程を支援;奥田(2012)で知る)
- 松野辰彦(2010).日本の大学図書館におけるラーニング・コモンズの現状 筑波大学情報学群知識情報・図書館学類 2010年度卒業論文抄録[PDF](本文は筑波大学図書館情報学図書館内の端末のみ閲覧可能)(全国の大学図書館のうちラーニングコモンズ相当の施設があるのは3.5%(18大学)、悉皆調査による;奥田(2012)で知る)
- 津村光洋(2011).鳥取大学附属図書館のラーニング・コモンズ 鳥取大学教育研究論集,1,97-102.[PDF](ラーニングコモンズの利用者が一部の優秀な学生に限られるケースもある;奥田(2012)で知る)
- 藤井文武・山本節夫(2008).受講生の目的意識喚起と起業家精神育成を狙う授業科目の企画と実施 大学教育,5,35-45.[PDF](企業家精神育成のためのアクティブラーニングの事例;奥田(2012)で知る)
- 島崎薫(2009).学習コミュニティーの形成を目指した取り組みとその考察 言語科学論集,13,59-69.[PDF](学習コミュニティの形成をねらって取り組んだがコミュニティが持続しなかった事例;奥田(2012)で知る)
- 秦喜美恵・板井芳江・片山智子・清水昭子・住田環(2011).アクティブラーニングプログラム「FIRST」で学生は何をどう学びどのように変化したか:2010年秋FIRST参加学生の追跡調査より Polyglossia,21,69-77.[PDF](「学習者にどのような気づきがあり、その気づきから何を学び、その後どのように変容していったのかについて、実践活動過程そのものに視点をおいた研究は少ない」;奥田(2012)で知る)
- 阿部秀二郎(2011).FDとラーニング・コモンズ 和歌山大学経済学会研究年報,15,151-166.[PDF](ラーニングコモンズで展開される「学生たちの主体的な学び」の構造に迫る理論的検討がなされていない;奥田(2012)で知る)
- 安斎勇樹・森玲奈・山内祐平(2011).創発的コラボレーションを促すワークショップデザイン 日本教育工学会論文誌,35(2),135-145.[PDF](Engeström(1987)の拡張的学習の視点からワークショップという実践における創発性について検討;奥田(2012)で知る)
[2013.03.14]IRなどについての文献メモ 内容をアップ
- 河井亨(2012).学生の学習と成長に対する授業外実践コミュニティへの参加とラーニング・ブリッジングの役割 日本教育工学会論文誌,35(4),297-308.[PDF][概要](CiNii Articles「学習支援 大学」で知る)
[2013.03.12]IRなどについての文献メモ 文献一覧を更新
- 武内清(編)(2003).キャンパスライフの今 玉川大学出版部(学生の学習志向が高まっている;河井(2012)で知る)
- 武内清(編)(2005).大学とキャンパスライフ 上智大学出版(授業外学習時間は1日に1時間未満;河井(2012)で知る)
- 溝上慎一(2009).「大学生活の過ごし方」から見た学生の学びと成長の検討:正課・正課外のバランスのとれた活動が高い成長を示す 京都大学高等教育研究,15,107-118.[PDF](授業外学習時間は1日に1時間未満、授業外での活動・学習が学生の知識・技能の習得などの学習成果に結びつく、これまでの大学生調査研究では大学生活をどう過ごすかという個人的な観点から学生をタイプ分けしている研究が見られる、大学生活の中で学習に重きを置かない学生が一定するいる;河井(2012)で知る)
- 溝上慎一(2010).現代青年期の心理学 有斐閣(「よく学び、よく遊ぶ」学生は力強く成長する;河井(2012)で知る)
- Kuh, G. D. (2003). What we're learning about student engagement from NSSE. Change, 35(2), 24-32.(授業外での活動・学習が学生の知識・技能の習得などの学習成果に結びつく;河井(2012)で知る)
- 山田剛史・森朋子(2010).学生の視点から捉えた汎用的技能獲得における正課・正課外の役割 日本教育工学会論文誌,34(1),13-21.[PDF](授業外での活動・学習が学生の知識・技能の習得などの学習成果に結びつく;河井(2012)で知る)
- 小山治(2010).新規大卒労働市場における大学教育の就職レリバンス:学習理論に着目した新しい分析モデルの提出 大学教育学会誌,32(2),95-103.(学生の学習に関する大学生調査研究では学習研究の知見を活かしていくことが課題の1つ;河井(2012)で知る)
- Lave, J. & Wenger, E. (1991). Situated learning: Legitimate perioheral participation. Cambridge: Cambridge University Press.(学習研究における状況論アプローチ;河井(2012)で知る)
- 山住勝宏・エンゲストローム, Y.(編)(2008).ノットワーキング:結び合う人間活動の創造へ 新曜社(活動領域の境界を横断することで協同関係が創発的に再編成される;河井(2012)で知る)
- 佐伯胖・若狭蔵之助・中西新太郎(1996).学びの共同体 青木書店(活動領域の境界を横断することで課題が持ち込まれて再定式化される、そして新しい解決手段が作り出される;河井(2012)で知る)
- 香川秀太(2008).「複数の文脈を横断する学習」への活動理論的アプローチ:学習転移論から文脈横断論への変移と差異 心理学評論,51(4),463-484.[PDF](複数の文脈を横断する中での学習論では学習を個人ではなく様々な道具や人々との関係性で捉えるなど様々なタイプの文脈横断について研究が進められている;河井(2012)で知る)
- 荒木淳子(2007).企業で働く個人の「キャリアの確立」を促す学習環境に関する研究:実践共同体への参加に着目して 日本教育工学会論文誌,31(1),15-27.[PDF](複数の文脈を横断することで個人レベルの省察につながる;河井(2012)で知る)
- 荒木淳子(2009).企業で働く個人のキャリアの確立を促す実践共同体のあり方に関する質的研究 日本教育工学会論文誌,33(2),131-142.[PDF](複数の文脈を横断することで個人レベルの省察につながる;河井(2012)で知る)
- 中原淳(2010).職場学習論:仕事の学びを科学する 東京大学出版会(複数の文脈を横断することで個人レベルの省察につながる;河井(2012)で知る)
- Barron, B. (2006). Interest and self-sustained Learning as catalysts of development: A learning ecology perspective. Human Development, 49, 193-224.[PDF](学校の外での学習が学校の中での学習とどのように関連しているかを調べた、複数の場面での学習とその間の関係が重要であった;河井(2012)で知る)
[2013.03.10]IRなどについての文献メモ 内容をアップ
- 鈴木秀子・桑原理恵(2011).中央図書館ブックハンティング(選書ツアー)実施報告:学生による選書の試み2011/11/26 図書の譜:明治大学図書館紀要,16,191-205.[概要](CiNii Articles「ブックハンティング」で知る)
[2013.03.10]ホーム 「お知らせ」欄を変更
[2013.03.10]IRなどについての文献メモ 文献一覧を更新
- 植松貞夫(2008).これからの図書館像とそれを実現する図書館建築 近代建築,62(4),78-81.(CiNii Articles「図書館 設計」で知る)
- 小川俊彦(2008).管理者として見た望ましい図書館建築 近代建築,62(4),82-83.(CiNii Articles「図書館 設計」で知る)
- 鳴海雅人(2008).都市サバイバルとしての図書館 近代建築,62(4),84-85.(CiNii Articles「図書館 設計」で知る)
- 柳瀬寛夫(2008).「開架スペース」の建築計画的アプローチ 近代建築,62(4),86-87.(CiNii Articles「図書館 設計」で知る)
[2013.03.10]IRなどについての文献メモ 文献一覧を更新
[2013.03.09]IRなどについての文献メモ 文献一覧を更新
- 今井健・今井光映(2003).大学エンロールメント・マーケティング:大学EMの4Cスクェアーパラダイム 中部日本教育文化会(Twitter(@yochipumiさん)で知る)
- 今井健(2001).大学マーケティングの理念と戦略:学生コンシューマリズムに応えるために 中部日本教育文化会(Twitter(@yochipumiさん)で知る)
- 日本私立大学協会(編)(1998).米国の大学経営戦略:マーケティング手法に学ぶ 学法文化センター出版部(Twitter(@yochipumiさん)で知る)
- Maguire, J., Butler, L., & their colleagues at Maguire Associates (2008). EM=C2: A new formula for enrollment management. Bloomington, IN: Trafford Publishing.(Twitter(@yochipumiさん)で知る)
[2013.03.09]過去の「お知らせ」 リンク先を変更
- 「山形大学(主催)と京都光華女子大学(共催)が「第3回EMIR勉強会」を行います」のリンク先をプログラムから京都光華女子大学新着情報に変更
[2013.03.05]ホーム 「お知らせ」欄を変更
- 「京都光華女子大学でのEM・IRの取り組みが報告されます」を削除し、「過去の「お知らせ」」に移行
[2013.03.04]IRなどについての文献メモ 内容をアップ
- 野地有子・柿川房子・加城貴美子・吉山直樹・堀良子・直成洋子・岡村典子・長瀬亜岐(2006).PBLチュートリアルにおけるチュータートレーニングとシナリオ開発に関する研究 学長特別研究費研究報告書2005,1-13.[概要](CiNii Articles「大学 チューター」で知る)
[2013.03.04]IRなどについての文献メモ 文献一覧を更新
- 野地有子・加城貴美子・加藤光實・田中キミ子・冨川孝子・佐々木美佐子・加固正子・深澤佳代子・吉山直樹・関谷伸一・堀良子・井上みゆき・岡村典子(2005).学長特別研究費研究報告書2004,1-13.(学生がPBLという新しい学習方法に不安感を持つ、組織的対応が必要;野地他(2006)で知る)
- 吉田一郎・大西弘高(編)(2004).実践PBLテュートリアルガイド 南山堂(「問題組み立て用チェックリスト」;野地他(2006)で知る)
- David, M. H. & Harden, R. M. (1999). AMEE Medical Education Guide No.15: Problem-based learning: A practical guide. Medical Teacher, 21(2), 130-140.(PBLの実践ガイド;野地他(2006)で知る)
[2013.03.03]IRなどについての文献メモ 内容をアップ
- 川野卓二(2005).Problem Based Learning 法のためのチューター訓練講座の効果 徳島大学大学開放実践センター紀要,15,17-27.[概要](CiNii Articles「大学 チューター」で知る)
[2013.03.02]IRなどについての文献メモ 内容をアップ
- 岡本真・李明喜・内沼晋太郎・洛西一周・常世田良・植松貞夫・柳瀬寛夫・鳴海雅人(2011).第12回図書館総合展 キハラ株式会社 創業96周年記念講演会 図書館をデザインする:情報デザインと主題プロデュースの手法 LISN,147,2-16.[概要](LISN(キハラ株式会社)のバックナンバー目次一覧で知る)
[2013.03.02]IRなどについての文献メモ 文献一覧を更新
- 岡本真・李明喜・内沼晋太郎・洛西一周・常世田良・植松貞夫・柳瀬寛夫・鳴海雅人(2011).第12回図書館総合展 キハラ株式会社 創業96周年記念講演会 図書館をデザインする:情報デザインと主題プロデュースの手法 LISN,147,2-16.(LISN(キハラ株式会社)のバックナンバー目次一覧で知る)
[2013.03.01]IRなどについての文献メモ 内容をアップ
- 矢田部順二(2010).広島修道大学における学習支援センターの役割(1)活動のあるべき姿をもとめて 私学経営,419,42-50.[概要](CiNii Articles「学習支援 大学」で知る)
[2013.02.28]IRなどについての文献メモ 内容をアップ
- 舘野泰一・大川内隆朗・平野智紀・中原淳(2010).ライティング・センターにおけるチューターの指導を支援するシステムの開発 日本教育工学会研究報告集,2010(5),29-36.[概要](CiNii Articles「大学 チューター」で知る)
[2013.02.28]IRなどについての文献メモ 文献一覧を更新
- 舘野泰一・木村充・関根雅泰・中原淳(2011).職場外の勉強会に参加する社会人に関する探索的研究 日本教育工学会研究報告集,2011(4),139-146.(CiNii Articles「舘野泰一」で知る)
- 鈴木宏昭・舘野泰一・杉谷祐美子・長田尚子・小田光宏(2007).Toulminモデルに準拠したレポートライティングのための協調学習環境 京都大学高等教育研究,13,13-24.[PDF](CiNii Articles「舘野泰一」で知る)
- 井下千以子(2008).大学における書く力考える力:認知心理学の知見をもとに 東信堂(アカデミック・ライティングの指導は大学の基礎科目の中核的な活動となってきている;舘野ら(2010)で知る)
- 正宗鈴香(2009).章力支援のためのティーチング・アシスタント向けマニュアル素案:ライティングセンター(仮称)設置にむけて 麗沢大学紀要,89,109-125.[PDF](ライティング・センターは1970年代のアメリカで母国語教育の一環として設置が始まった、ライティング・センターが正課課程外で活動を行う理由:授業内で学生に個別で指導する時間が足りない・授業内で作成する過程を深める指導は時間の制約上難しい;舘野ら(2010)で知る)
- 正宗鈴香(2007).聴き手を意識した口頭発表授業:効果的に伝えるための発表原稿作成指導 麗沢大学紀要,85,71-87.[PDF](CiNii Articles「正宗鈴香」で知る)
- 杉谷祐美子(2004).大学管理職からみた初年次教育への期待と評価 大学教育学会誌,26(1),29-36.(初年次教育で設置された授業科目のうち「レポートや論文の書き方」に関するものは38.3%;舘野ら(2010)で知る)
- 大島弥生(2005).大学初年次の言語表現科目における協働の可能性:チーム・ティーチングとピア・レスポンスを取り入れたコースの試み 大学教育学会誌,27(1),158-165.(アカデミック・ライティングについて初年次生を対象にした学生同士のピアレビューを取り入れた実践;舘野ら(2010)で知る))
- North, S. M. (1984). The idea of a writing center. College English, 46(5), 433-446.(ライティング・センターの指導理念:レポートを直すのではなく書き手自身の成長を促す、書く過程を支援する;舘野ら(2010)で知る))
- 佐渡島沙織(2005).大学における「書くこと」の支援:早稲田大学国際教養学部における「ライティング・センター」の発足 全国大学国語教育学会発表要旨集,109,193-196.(ライティングセンターでは「添削」ではなく「指導」が重要、チューターの育成はライティング・センターの課題の1つ;舘野ら(2010)で知る)
- 三宅なほみ・白水始(2002).内省 日本認知科学会(編)認知科学辞典 共立出版 p.626(リフレクションとは学習者が自らの学習について意図的に吟味するプロセス;舘野ら(2010)で知る)
- 出口明子・稲垣成哲・山口悦司・舟生日出男(2004).理科教育におけるテクノロジを利用したリフレクション支援の研究動向 科学教育研究,31(2),71-85.(リフレクションの支援にテクノロジを使う理由:思考の可視化・共有化;舘野ら(2010)で知る)
- 長田尚子・鈴木宏昭・三宅なほみ(2005).大学の導入教育におけるblogを活用した協調学習の設計とその評価 知能と情報:日本知能情報ファジィ学会誌,17(5),525-535.[PDF](アカデミック・ライティング支援にblogを使いプロセスを可視化、ただしどのように書いたかはわからない;舘野ら(2010)で知る)
- 長田尚子・鈴木宏昭・三宅なほみ(2006).ジグソー法を用いたグループ活動による論証スタイルの理解支援:大学の「レポートの書き方」の授業における発話分析 日本認知科学会大会発表論文集,23,62-63.(CiNii Articles「長田尚子」で知る)
- 長田尚子・村田信行(2011).サービス・ラーニングを手がかりとした職業実践的プロジェクトの展開:学生によるリフレクションの深化に注目した活動のデザインと評価 京都大学高等教育研究,17,39-51.[PDF](CiNii Articles「長田尚子」で知る)
- 舘野泰一・大川内隆朗・平野智紀・中原淳(2011).ライティング・センターにおける学生の執筆プロセスに着目した指導の実践 日本教育工学会第27回全国大会講演論文集,547.(tate-lab「少し前のことになりますが、日本教育工学会第27回全国大会(2011年9月17日(土)-19日(月)@首都大学東京)で発表をしてきました!」で知る)
[2013.02.27]IRなどについての文献メモ 内容をアップ
- 神永侑子・田中雄一郎・秋野崇大・中井孝幸(2012).図書館の特色による利用者の館内行動について:場選択と利用者意識からみた図書館計画に関する研究 その2 東海支部研究報告集,50,473-476.[PDF][概要](CiNii Articles「中井孝幸」で知る)
- 秋野崇大・神永侑子・田中雄一郎・中井孝幸(2012).使い分け行動に基づく図書館の特色と選択意識について:場選択と利用者意識からみた図書館計画に関する研究 その1 東海支部研究報告集,50,469-472.[PDF][概要](CiNii Articles「中井孝幸」で知る)
[2013.02.27]IRなどについての文献メモ 文献一覧を更新
- 中井孝幸(2011年度~2013年度).「場」の概念からみた図書館における来館を促す建築的魅力に関する研究 文部科学省科学研究費補助金,研究課題番号:23560751.
[2013.02.25]ホーム 「お知らせ」欄を変更
- 「山形大学(主催)と京都光華女子大学(共催)が「第3回EMIR勉強会」を行います」を削除し、「過去の「お知らせ」」に移行
- 「京都光華女子大学EM・IR部がポスター発表を行います」を削除し、「過去の「お知らせ」」に移行
[2013.02.25]ホーム ページ構成を変更
[2013.02.25]IRなどについての文献メモ 文献一覧を更新
- 根本淳子・鈴木克明(2005).ゴールベースシナリオ(GBS)理論の適応度チェックリストの開発 日本教育工学会論文誌,29(3),309-318.[PDF](Twitter(@ikejiriryoheiさん)で知る)
- 根本淳子・柴田喜幸・鈴木克明(2011).学習デザインの改善と学習の深化を目指したデザイン研究アプローチを用いた実践 日本教育工学会論文誌,35(3),259-268.[PDF](CiNii Articles「根本淳子」で知る)
- 鈴木克明・根本淳子(2011).教育設計における社会・文化的配慮についての動向 日本教育工学会研究報告集,2011(4),185-188.[PDF](CiNii Articles「根本淳子」で知る)
- 根本淳子・上田勇仁・上田公代(2011).グループワークを支援するICTデザイン:eラーニングを利用したグループ発表評価実践報告 教育システム情報学会研究報告,26(1),41-44.[PDF](CiNii Articles「根本淳子」で知る)
- 鈴木克明・根本淳子(2011).教育設計についての三つの第一原理の誕生をめぐって 教育システム情報学会誌,28(2),168-176.[PDF](CiNii Articles「根本淳子」で知る)
- 村木純偉・喜多敏博・鈴木克明・根本淳子(2010).OPTIMALモデルチェックリストの開発 日本教育工学会論文誌,34(Suppl.),177-180.[PDF](CiNii Articles「根本淳子」で知る)
- 朴恵一・喜多敏博・根本淳子・鈴木克明(2010).ゴールベースシナリオ(GBS)理論に基づく情報活用能力育成教育の実践 日本教育工学会論文誌,34(Suppl.),165-168.[PDF](CiNii Articles「根本淳子」で知る)
- 根本淳子・朴恵一・北村隆始・鈴木克明(2010).問題解決型学習デザインの研究動向:GBSとSCCを中心に 日本教育工学会研究報告集,2010(5),151-158.[PDF](CiNii Articles「根本淳子」で知る)
- 根本淳子・小山田誠・柴田喜幸・鈴木克明(2009).「学びのスケッチ」でリフレクションを促す試み 教育システム情報学会研究報告,24(4),70-73.[PDF](CiNii Articles「根本淳子」で知る)
- 根本淳子・鈴木克明(2008).大学教育実践ステークホルダーインタビュー分析:米国の大学院プログラムを題材にして 日本教育工学会研究報告集,2008(2),27-34.[PDF](CiNii Articles「根本淳子」で知る)
- 根本淳子・鈴木克明(2009).大人の学びとインストラクショナル・デザイン 看護,61(14),16-21.(CiNii Articles「根本淳子」で知る)
- 田中裕也・井ノ上憲司・根本淳子・鈴木克明(2006).オープンソースCMSの実証的比較分析と選択支援サイトの構築 日本教育工学会論文誌,29(3),405-413.[PDF](CiNii Articles「根本淳子」で知る)
- 北村士朗・根本淳子(2006).ID(インストラクショナル・デザイン)の魅力とその効果 人材教育,18(2),24-28.(CiNii Articles「根本淳子」で知る)
- 田中裕也・井ノ上憲司・根本淳子・鈴木克明(2005).CMSの比較分析と講義に適したCMS選択のガイドライン提案 日本教育工学会研究報告集,2005(1),59-66.[PDF](CiNii Articles「根本淳子」で知る)
- 市川尚・鈴木克明(2012).認知的方略の学習を支援する教材シェルの検討:インストラクショナルデザイン理論の学習者による活用 日本教育工学会研究報告集,2012(1),333-336.(CiNii Articles「鈴木克明」で知る)
- 高橋暁子・喜多敏博・中野裕司・市川尚・鈴木克明(2011).課題分析図を用いた学習内容選択支援ツールの開発:Moodleブロックによる学習者向け機能の実装 日本教育工学会論文誌,35(1),17-24.[PDF](CiNii Articles「鈴木克明」で知る)
- 市川尚・高橋暁子・鈴木克明(2008).複数の制御構造の適用と学習のための統合型ドリルシェル「ドリル工房」の開発 日本教育工学会論文誌,32(2),157-168.[PDF](CiNii Articles「鈴木克明」で知る)
- 市川尚・鈴木克明(2008).インストラクショナルデザイン自動化ツールの研究動向 教育メディア研究,14(2),33-44.(CiNii Articles「鈴木克明」で知る)
- 井ノ上憲司・高橋義昭・藤原康宏・市川尚・鈴木克明(2006).日本教育工学会論文誌,29(Suppl),85-88.[PDF](CiNii Articles「鈴木克明」で知る)
- 斐品正照・岡田ロベルト・鈴木克明(2006).CMC技術を利用した個別学習指導における学習者の心理的な状態変化 教育システム情報学会研究報告,20(6),109-114.(CiNii Articles「鈴木克明」で知る)
- 市川尚(2009).インストラクショナルデザインの自動化を志向した教材シェルの開発 学位論文(博士) 熊本大学大学院[PDF](CiNii Articles「市川尚」で知る)
[2013.02.24]IRなどについての文献メモ 内容をアップ
- 山田かおり(2005).図書館利用教育の評価:嘉悦大学1年生を対象としたアウトカム測定の試み 大学図書館研究,73,15-24.[概要](山田(2010)で知る)
[2013.02.24]IRなどについての文献メモ 文献一覧を更新
- 山田かおり(2005).図書館利用教育の評価:嘉悦大学1年生を対象としたアウトカム測定の試み 大学図書館研究,73,15-24.(山田(2010)で知る)
- Carter, E. W. (2002). Doing the best you can with what you have: Lessons learned from outcomes assessment. The Journal of Academic Librarianship, 28(1), 36-41.[PDF(有料)](図書館に関する講義を受ける前と学期末に同じテストを実施、正答率を比較して講義の成果を測る;山田(2005)で知る)
- 戸田あきら(2003).顧客満足度及びアウトカム測定の試み:文教大学越谷図書館における利用者アンケート調査 日本図書館情報学会研究委員会(編)図書館の経営評価:パフォーマンス指標による新たな図書館評価の可能性 勉誠出版 pp.145-167.(図書館の利用やサービスによって学生の学問的な実績が向上したかどうかを客観的に測定するのは難しい;山田(2005)で知る)
[2013.02.23]大学に関わる情報メモ マークアップをXHTML1.0StrictからHTML5に移行、SNSボタン(Twitter・Google+・はてなブックマーク)を追加
[2013.02.22]大学に関わる情報メモ ページタイトルの付け方を変更
- 変更前:パンくずリスト全てを記載(例:"ホーム → 大学に関わる情報メモ → 職員勉強会で行ったKJ法の記録")
- 変更後:パンくずリストの最後尾のみ記載(例:"職員勉強会で行ったKJ法の記録")
[2013.02.22]大学に関わる情報メモ マークアップをXHTML1.0StrictからHTML5に移行
[2013.02.21]大学に関わる情報メモ ページ構成を変更
[2013.02.20]IRなどについての文献メモ 文献一覧を更新
- 安斎勇樹・森玲奈・山内祐平(2011).創発的コラボレーションを促すワークショップデザイン 日本教育工学会論文誌,35(2),135-145.[PDF](Twitter(@tatthiyさん)で知る)
- 森玲奈(2008).学習を目的としたワークショップのデザイン過程に関する研究 日本教育工学会論文誌,31(4),445-455.[PDF](CiNii Articles「森玲奈」で知る)
- 森玲奈(2009).ワークショップ実践家のデザインにおける熟達過程:デザインの方法における変容の契機に着目して 日本教育工学会論文誌,33(1),51-62.[PDF](CiNii Articles「森玲奈」で知る)
[2013.02.20]IRなどについての文献メモ 詳細をローカルPCに保存
- 堀公俊・加藤彰(2008).ワークショップ・デザイン:知をつむぐ対話の場づくり 日本経済新聞出版社(Amazon.co.jp「ワークショップ」で知る)[詳細をローカルPCに保存]
[2013.02.19]IRなどについての文献メモ 内容をアップ
- 山田かおり(2010).嘉悦大学における<学生に火をつける>学習支援環境 短期大学図書館研究,30,55-57.[概要](CiNii Articles「学習支援 大学」で知る)
- 矢田部順二(2010).広島修道大学における学習支援センターの役割(2)初年次教育の検証からみる課題と将来像 私学経営,422,49-58.[概要](CiNii Articles「学習支援 大学」で知る)
[2013.02.19]IRなどについての文献メモ 文献一覧を更新
- 山田かおり(2005).図書館利用教育の評価:嘉悦大学1年生を対象としたアウトカム測定の試み 大学図書館研究,73,15-24.(山田(2010)で知る)
[2013.02.18]IRなどについての文献メモ 内容をアップ
[2013.02.18]IRなどについての文献メモ 文献一覧を更新
- 中井孝幸(2012).行動観察調査からみる「場」としての図書館利用(前編) LISN,153,13-16.(LISN(キハラ株式会社)のバックナンバー目次一覧で知る)
- Buschman、J. E. & Leckie, G. L.(Eds.) (2006). The library as place: History, community, and culture. Westport, Connecticut: Libraries Unlimited.(川崎良孝・久野和子・村上加代子(訳)(2008).場としての図書館:歴史、コミュニティ、文化 京都大学図書館情報学研究会,日本図書館協会(発売))(中井(2012)で知る)
[2013.02.18]IRなどについての文献メモ 内容を修正
- 中井孝幸・秋野崇大(2010).滞在型利用の傾向と図書館選択の理由について:図書館の雰囲気が場の選択に与える影響に関する研究 その1 日本建築学会大会学術講演梗概集,323-324.[PDF](CiNii Articles「秋野崇大」で知る)
[2013.02.15]大学に関わる情報メモ 内容を修正
[2013.02.13]大学に関わる情報メモ 内容を修正
[2013.02.13]大学に関わる情報メモ 内容をアップ
[2013.02.10]IRなどについての文献メモ 内容を修正
[2013.02.09]ホーム ページ構成を変更
- 「お知らせ」欄を追加
- 「お知らせ」欄に山形大学(主催)と京都光華女子大学(共催)による「第3回EMIR勉強会」を掲載
- 「お知らせ」欄に京都光華女子大学EM・IR部のポスター発表(大学コンソーシアム京都「第18回FDフォーラム」)を掲載
- 「お知らせ」欄に京都光華女子大学のEM・IR取り組み報告(「大学教育改革フォーラムin東海2013」;阿部一晴(京都光華女子大学))を掲載
- Twitterのリンクに「@HashimotoTomoya」を追記
[2013.02.08]IRなどについての文献メモ 内容をアップ
- 山田剛史(2004).過去-現在-未来にみられる青年の自己形成と可視化によるリフレクション効果:ライフヒストリーグラフによる青年理解の試み 青年心理学研究,16,15-35.[PDF][内容](舘野(2012)で知る)
[2013.02.06]IRなどについての文献メモ 文献一覧を更新
- 野村信威・橋本宰(2001).老年期における回想の質と適応との関連 発達心理学研究,12(2),75-86.(青年は否定的階層やネガティブな出来事を再評価する傾向が老年者よりも高い、青年の適応度の高さをはその傾向で説明できる;山田(2004)「過去-現在-未来…」で知る)[PDF]
- 山田剛史(2004).大学生の語りにみられる否定的な過去体験の認知的再構成~契機としての自己と他者のダイナミクスに着目して~ 日本発達心理学会第15回大会発表論文集,232.(自己形成は未来だけではなく過去の側面も重要、「否定的な過去体験の認識内における肯定的方向への再構成」;山田(2004)「過去-現在-未来…」で知る)
- 山田剛史(2004).現代大学生における自己形成とアイデンティティ:日常的活動とその文脈の観点から 教育心理学研究,52(4),402-413.[PDF](自己形成は未来だけではなく現在の側面も重要、「現在の日常的活動に対して付与される肯定的認知的評価」;山田(2004)「過去-現在-未来…」で知る)
[2013.01.29]IRなどについての文献メモ 文献一覧を更新
[2013.01.26]IRなどについての文献メモ 文献一覧を更新
- 橋本広信(2005).山田論文「過去-現在-未来にみられる青年の自己形成と可視化によるリフレクション効果:ライフヒストリーグラフによる青年理解の試み」へのコメント(意見) 青年心理学研究,17,78-82.(CiNii Articles「ライフヒストリーグラフ」で知る)
- 出版年を2006から2005に修正(「更新履歴」掲載分も修正)
- 山田剛史(2004).過去-現在-未来にみられる青年の自己形成と可視化によるリフレクション効果:ライフヒストリーグラフによる青年理解の試み 青年心理学研究,16,15-35.[PDF](舘野(2012)で知る)
- 橋本広信(2005).山田論文「過去-現在-未来にみられる青年の自己形成と可視化によるリフレクション効果:ライフヒストリーグラフによる青年理解の試み」へのコメント(意見) 青年心理学研究,17,78-82.[PDF](CiNii Articles「ライフヒストリーグラフ」で知る)
[2013.01.26]IRなどについての文献メモ 文献一覧を更新
- 苅宿俊文(2012).イントロダクション:ワークショップの現在 苅宿俊文・佐伯胖・高木光太郎(編)まなびを学ぶ 東京大学出版会 pp.1-22.(Amazon.co.jp「ワークショップ」で知る)[詳細をローカルPCに保存]
- 坂口順治(1994).体験的参加型学習の意義と展開 社会教育,49(10),6-10.(苅宿(2012)で知る)
- 木原孝久(1994).体験的参加型学習のすすめ 社会教育,49(10),12-18.(苅宿(2012)で知る)
- 楠原彰(1994).ワークショップ考 社会教育,49(10),20-24.(苅宿(2012)で知る)
- 薗田碩哉 (1994).ワークショップの仕立て方:ワークショップの基礎知識 技術と技法を考える 社会教育,49(10),26-30.(苅宿(2012)で知る)
- 藤見幸雄 (1994).ワークショップの概念とその可能性並びに課題点:欧米における心理学ワ-クショップの体験を通じて 社会教育,49(10),32-42.(苅宿(2012)で知る)
- (不明) (1994).開発のための教育:ユニセフによる地球学習の手引き 指導者用手引きパイロットバージョン 序論の抜粋 社会教育,49(10),44-59.(苅宿(2012)で知る)
- (不明) (1994).体験的参加型学習とワークショップの活動事例 社会教育,49(10),60-67.(苅宿(2012)で知る)
[2013.01.25]IRなどについての文献メモ 詳細をローカルPCに保存
- 今村光章(2009).アイスブレイク入門:こころをほぐす出会いのレッスン 解放出版社(Amazon.co.jp「アイスブレイク」で知る)[詳細をローカルPCに保存]
- 川喜田二郎(1970).続・発想法:KJ法の展開と応用 中央公論社(Amazon.co.jp「KJ法」で知る)[詳細をローカルPCに保存]
- 苅宿俊文・佐伯胖・高木光太郎(編)(2012).まなびを学ぶ 東京大学出版会(Amazon.co.jp「ワークショップ」で知る)[詳細をローカルPCに保存]
- 苅宿俊文・佐伯胖・高木光太郎(編)(2012).場づくりとしてのまなび 東京大学出版会(Amazon.co.jp「ワークショップ」で知る)[詳細をローカルPCに保存]
- 森時彦・ファシリテーターの道具研究会(2008).ファシリテーターの道具箱:組織の問題解決に使えるパワーツール49 ダイヤモンド社(Amazon.co.jp「ファシリテーター」で知る)
- 美馬のゆり・山内祐平(2005).「未来の学び」をデザインする:空間・活動・共同体 東京大学出版会(上田・中原(2013)、ブクログ「プレイフル・ラーニングの本棚」で知る)[詳細をローカルPCに保存]
- 中野民夫(2001).ワークショップ:新しい学びと創造の場 岩波書店(上田・中原(2013)、ブクログ「プレイフル・ラーニングの本棚」で知る)[詳細をローカルPCに保存]
- 上田信行(2009).プレイフル・シンキング:仕事を楽しくする思考法 宣伝会議(Amazon.co.jp「上田信行」で知る)[詳細をローカルPCに保存]
[2013.01.25]IRなどについての文献メモ ページ構成を変更
- 「IRなどについての文献一覧」に挙げている文献のうち、詳細をローカルPCに保存しているものについて「[詳細をローカルPCに保存]」と記載するように変更
- 「IRなどについての文献一覧」の冒頭の説明文に「詳細をローカルPCに保存している文献には「[詳細をローカルPCに保存]」と書いています。」を追記
[2013.01.24]IRなどについての文献メモ 文献一覧を更新
- 刑部育子(2012).図工の時間というワークショップ:お茶の水女子大学附属小の実践 苅宿俊文・佐伯胖・高木光太郎(編)場づくりとしてのまなび 東京大学出版会 pp.137-153.(Amazon.co.jp「ワークショップ」で知る)
- 舘野泰一(2012).大学教育とワークショップ 苅宿俊文・佐伯胖・高木光太郎(編)場づくりとしてのまなび 東京大学出版会 pp.197-219.(Amazon.co.jp「ワークショップ」で知る)
- 山田剛史(2004).過去-現在-未来にみられる青年の自己形成と可視化によるリフレクション効果:ライフヒストリーグラフによる青年理解の試み 青年心理学研究,16,15-35.(舘野(2012)で知る)
- 橋本広信(2005).山田論文「過去-現在-未来にみられる青年の自己形成と可視化によるリフレクション効果:ライフヒストリーグラフによる青年理解の試み」へのコメント(意見) 青年心理学研究,17,78-82.(CiNii Articles「ライフヒストリーグラフ」で知る)
[2013.01.19]IRなどについての文献メモ 文献一覧を更新
- 茂木一司(編集代表)・苅宿俊文・佐藤優香・上田信行・宮田義郎(編)(2010).協同と表現のワークショップ:学びのための環境のデザイン 東信堂(Amazon.co.jp「ワークショップ」で知る)
- 苅宿俊文・佐伯胖・高木光太郎(編)(2012).まなびほぐしのデザイン 東京大学出版会(Amazon.co.jp「ワークショップ」で知る)
- 津村俊充(2012).プロセス・エデュケーション:学びを支援するファシリテーションの理論と実際 金子書房(Amazon.co.jp「上記文献(まなびほぐしのデザイン)の「この商品を買った人はこんな商品も買っています」」で知る)
- 佐伯胖(1995)「わかる」ということの意味 新版 岩波書店(Amazon.co.jp「上記文献(まなびほぐしのデザイン)の「この商品を買った人はこんな商品も買っています」」で知る)
- 上田信行(2009).プレイフル・シンキング:仕事を楽しくする思考法 宣伝会議(Amazon.co.jp「上田信行」で知る)
[2013.01.13]IRなどについての文献メモ 文献一覧を更新
- 沖清豪・岡田聡志(編著)(2011).データによる大学教育の自己改善:インスティテューショナル・リサーチの過去・現在・展望 学文社(Amazon.co.jp「institutional research」で知る)
- 美馬のゆり・山内祐平(2005).「未来の学び」をデザインする:空間・活動・共同体 東京大学出版会(上田・中原(2013)、ブクログ「プレイフル・ラーニングの本棚」で知る)
- 中野民夫(2001).ワークショップ:新しい学びと創造の場 岩波書店(上田・中原(2013)、ブクログ「プレイフル・ラーニングの本棚」で知る)
- 中原淳(2011).知がめぐり、人がつながる場のデザイン:働く大人が学び続ける"ラーニングバー"というしくみ 英治出版(上田・中原(2013)、ブクログ「プレイフル・ラーニングの本棚」で知る)
- 苅宿俊文・佐伯胖・高木光太郎(編)(2012).まなびを学ぶ 東京大学出版会(Amazon.co.jp「ワークショップ」で知る)
- 苅宿俊文・佐伯胖・高木光太郎(編)(2012).場づくりとしてのまなび 東京大学出版会(Amazon.co.jp「ワークショップ」で知る)
- 堀公俊・加藤彰(2008).ワークショップ・デザイン:知をつむぐ対話の場づくり 日本経済新聞出版社(Amazon.co.jp「ワークショップ」で知る)
- 堀公俊(2003).問題解決ファシリテーター:「ファシリテーション能力」養成講座 東洋経済新報社(Amazon.co.jp「ファシリテーター」で知る)
- 堀公俊(2006).組織変革ファシリテーター:「ファシリテーション能力」実践講座 東洋経済新報社(Amazon.co.jp「ファシリテーター」で知る)
- 森時彦・ファシリテーターの道具研究会(2008).ファシリテーターの道具箱:組織の問題解決に使えるパワーツール49 ダイヤモンド社(Amazon.co.jp「ファシリテーター」で知る)
- 川喜田二郎(1967).発想法:創造性開発のために 中央公論社(Amazon.co.jp「KJ法」で知る)
- 川喜田二郎(1970).続・発想法:KJ法の展開と応用 中央公論社(Amazon.co.jp「KJ法」で知る)
- 今村光章(2009).アイスブレイク入門:こころをほぐす出会いのレッスン 解放出版社(Amazon.co.jp「アイスブレイク」で知る)
- 小泉直樹(2010).知的財産法入門 岩波書店(Twitter(@K0Eiさん)、Amazon.co.jp「知的財産」で知る)
[2013.01.13]IRなどについての文献メモ ページ構成を変更
- 変更前:内容を紹介している文献、近々読む予定の文献、後日読む予定の文献、IRなどについての文献一覧
- 変更後:内容を紹介している文献、後日読む予定の文献、IRなどについての文献一覧(「近々読む予定の文献」を「後日読む予定の文献」に統合)
[2013.01.13]IRなどについての文献メモ 文献一覧を更新
[2013.01.12]IRなどについての文献メモ 内容をアップ
- 沢村要・横山俊祐(1996).公共図書館における利用者の空間の嗜好性と過ごし方 日本建築学会大会学術講演梗概集,11-12.[PDF][概要](村松・前田(2007)で知る)
- 山崎俊裕・花岡雄太・和田后司(2007).私立大学図書館の施設面積と機能の現状について:私立大学図書館施設の現状と今日的課題に関する調査研究 その1 日本建築学会大会学術講演梗概集,111-112.[PDF][概要](CiNii Articles「図書館 設計」で知る)
- 常広一信(2008).学生を引きつける大学図書館デザインへの取り組み:「建築デザイン」から「利用デザイン」へ 図書館雑誌,102(6),380-381.[概要](CiNii Articles「図書館 設計」で知る)
- 赤木隆(2005).図書館の増築と改修 情報の科学と技術,55(11),500-505.[PDF][概要](CiNii Articles「広島修道大学図書館」で知る)
- 石丸仁士(2005).第20回日本図書館協会建築賞を受賞して 情報の科学と技術,55(11),486-492.[PDF][概要](CiNii Articles「広島修道大学図書館」で知る)
- 竹谷喜美江(2010).新潟大学ラーニング・コモンズについて 大学の図書館,29(7),143-146.[PDF][概要](CiNii Articles「図書館 リニューアル」で知る)
- 桂英史(2008).図書館建築のデザイン思想 図書館雑誌,102(6),369-372.[概要](CiNii Articles「図書館 設計」で知る)
- 原真由美・奥泉和久・高橋和子(2008).横浜女子短期大学図書館における学習支援の試み:図書館とFD 横浜女子短期大学研究紀要,23,99-124.[PDF][概要](CiNii Articles「学習支援 大学」で知る)
- 佐々木緑(2010).自律学習支援のための学習者コミュニティーの構築 教育総合研究叢書,3,97-107.[PDF][概要](CiNii Articles「学習支援 大学」で知る)
- 入江貴之・遠田敦・渡辺仁史(2008).図書に囲まれた空間構成が作業生産性に与える影響 日本建築学会大会学術講演梗概集,153-154.[PDF][概要](CiNii Articles「図書館 設計」で知る)
[2013.01.12]IRなどについての文献メモ 文献一覧を更新
- 桂英史(2008).図書館建築のデザイン思想 図書館雑誌,102(6),369-372.(CiNii Articles「図書館 設計」で知る)
- 冨江伸治(2008).図書館建築:そのデザインの変遷 図書館雑誌,102(6),373-375.(CiNii Articles「図書館 設計」で知る)
- 寺田芳朗(2008).デザイン・場としての図書館づくり、その向こう側にあるもの:設計者も出会い学び変わるということ 図書館雑誌,102(6),376-377.(CiNii Articles「図書館 設計」で知る)
- 分須正弘(2008).広いフロアをデザインする:さいたま市立中央図書館の試み 図書館雑誌,102(6),378-379.(CiNii Articles「図書館 設計」で知る)
- 常広一信(2008).学生を引きつける大学図書館デザインへの取り組み:「建築デザイン」から「利用デザイン」へ 図書館雑誌,102(6),380-381.(CiNii Articles「図書館 設計」で知る)
- 川井国孝(2008).コミュニケーションセンターのデザイン:利用者が作っていくデザイン 図書館雑誌,102(6),382-383.(CiNii Articles「図書館 設計」で知る)
- 戸松恵美(2008).図書館活用という時間軸をデザインする 図書館雑誌,102(6),384-385.(CiNii Articles「図書館 設計」で知る)
- 石丸仁士(2005).第20回日本図書館協会建築賞を受賞して 情報の科学と技術,55(11),486-492.[PDF](CiNii Articles「広島修道大学図書館」で知る)
- 赤木隆(2005).図書館の増築と改修 情報の科学と技術,55(11),500-505.[PDF](CiNii Articles「広島修道大学図書館」で知る)
- 大村文誉(2005).岡山県立図書館の資料移転:担当者の体験談 情報の科学と技術,55(11),480-485.[PDF](CiNii Articles「図書館 リニューアル」で知る)
- 植松貞夫(2005).総論:図書館の成長・変化に対応した施設改善:使い続けられる図書館のために 情報の科学と技術,55(11),468-473.[PDF](CiNii Articles「図書館 リニューアル」で知る)
- 香川文恵(2010).KULIC-αと共に歩む 大学の図書館,29(7),136-138.(CiNii Articles「図書館 リニューアル」で知る)
- 大前梓(2010).24時間学習室のこれまでとこれから 大学の図書館,29(7),138-141.(CiNii Articles「図書館 リニューアル」で知る)
- 茎田美保子(2010).静岡大学附属図書館リニューアルLearning Park構想 大学の図書館,29(7),141-143.(CiNii Articles「図書館 リニューアル」で知る)
- 竹谷喜美江(2010).新潟大学ラーニング・コモンズについて 大学の図書館,29(7),143-146.[PDF](CiNii Articles「図書館 リニューアル」で知る)
- 鈴木秀子・桑原理恵(2011).中央図書館ブックハンティング(選書ツアー)実施報告:学生による選書の試み2011/11/26 図書の譜:明治大学図書館紀要,16,191-205.(CiNii Articles「ブックハンティング」で知る)
- 沢村要・横山俊祐(1996).公共図書館における利用者の空間の嗜好性と過ごし方 日本建築学会大会学術講演梗概集,11-12.[PDF](村松・前田(2007)で知る)
- 小島泰典・押田拓也・宮本文人(2003).コーナー設置状況と機能構成把握の方法について:公共図書館におけるコーナー配置と機能構成に関する研究 その1 日本建築学会大会学術講演梗概集,295-296.[PDF](村松・前田(2007)で知る)
- 押田拓也・小島泰典・宮本文人(2003).施設の部分及び全体にみられる機能構成の傾向について:公共図書館におけるコーナー配置と機能構成に関する研究 その2 日本建築学会大会学術講演梗概集,297-298.[PDF](CiNii Articles「押田拓也」で知る)
- 原郭二・加藤彰一・木下誠一(2009).大学図書館におけるコモンスペースのプレースメイキングに関する考察:電子ジャーナル化に伴うコモンスペースの利用変化に関する研究,日本建築学会東海支部研究報告集,47,421-424.[PDF](原・加藤(2009)で知る)
- 小泉公乃(2011).図書館経営における経営戦略論 情報の科学と技術,61(8),294-299.[PDF](CiNii Articles「図書館 マーケティング」で知る)
- 南俊朗(2011).図書館のマーケティング活動:その意義と課題 情報の科学と技術,61(8),304-310.[PDF](CiNii Articles「図書館 マーケティング」で知る)
- 南俊朗(2010).図書館利用者理解への試み:貸出データを通して探る利用者プロフィール 九州大学附属図書館研究開発室年報2010/2011,9-18.[PDF](CiNii Articles「図書館 マーケティング」で知る)
- 南俊朗(2010).利用者満足度アップを目指す図書館マーケティング:データ解析による図書館サービス進化への期待 情報の科学と技術,60(6),242-248.[PDF](CiNii Articles「図書館 マーケティング」で知る)
- 南俊朗(2011).図書館マーケティングのための"友人関係"に関する考察:基本概念とその適用 九州情報大学研究論集,13,23-34.[PDF](CiNii Articles「図書館 マーケティング」で知る)
- 上岡真紀子(2009).利用者調査の結果を活かす:マーケティングの視点から 情報の科学と技術,59(10),492-497.[PDF](CiNii Articles「図書館 マーケティング」で知る)
- 岡部幸祐・金成真由子(2009).図書館プロモーションビデオ「週5図書館生活,どうですか?」の企画と制作:利用案内ビデオから学生志向のプロモーションビデオへ 大学図書館研究,85,1-11.[PDF](CiNii Articles「図書館 マーケティング」で知る)
[2013.01.09]IRなどについての文献メモ 文献一覧を更新、内容をアップ
- 関昭典(2011).学習アドバイザーの学習支援活動に関する考察-東京経済大学英語学習アドバイザーにおける取り組みを事例として 東京経済大学人文自然科学論集,130,95-106.[PDF][概要](CiNii Articles「学習支援 大学」で知る)
- 社団法人日本能率協会学校経営支援センター(2010).「第2回 大学教育力向上に関する調査」結果の発表(速報).[PDF][概要](関(2011)で知る)
- 小貫有紀子(2005).アメリカ高等教育における学習支援プログラムの基準と評価システム 大学教育学会誌,27(2),81-87.[概要](関(2011)で知る)
- 大学評価・学位授与機構(2011).高等教育に関する質保証関係用語集(第3版) National Institution for Academic Degrees and University Evaluation.[PDF][概要](関(2011)で知る)
- United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization(2002). The role of student affairs and services in higher education: A practical manual for developing, implementing and assessing student affairs programmes and services. Paris: UNESCO.[PDF][概要](関(2011)で知る)
- 清水栄子(2009).大学における学習助言活動の「評価」の重要性について:アメリカ13大学の学習助言(Academic Advising)プログラム評価を手がかりにして 大学教育学会誌,31(2),140-148.[概要](関(2011)で知る)
- 清水栄子(2010).アメリカにおける学習助言(Academic Advising)の発展とその背景:実践主体とそれを支える組織を手がかりとして 大学論集,41,361-375.[PDF](CiNii Articles「清水栄子」で知る)
[2013.01.08]IRなどについての文献メモ 文献一覧を更新
- 橋本健広(2010).授業担当者と学生支援室チューターの連携による英語文法復習プログラム-2007年度の取組における問題点と学習者の動機づけ 関東学院大学経済経営研究所年報,32,212-232.[PDF](CiNii Articles「大学 チューター」で知る)
- 木村拓也・池田光壱・西原俊明・大橋絵理・田山淳・竹内一真・井ノ上憲司・山口恭弘(2012).長崎大学における入学前教育の枠組みと効果測定:学生チューターを交えたヴィジョン形成教育の組織化と基礎学力向上の取組 大学入試研究ジャーナル,22,95-104.[PDF](CiNii Articles「大学 チューター」で知る)
- 依田紀久(2007).根拠に基づいた図書館業務の設計:実践家の成果の共有を目指すEBLIPの動向 カレントアウェアネス,291,8-12.[PDF](CiNii Articles「図書館 設計」で知る)
[2013.01.06]IRなどについての文献メモ 文献一覧を更新
- Ewell, P. T., Parker, R., & Jones, D. P. (1988). Establishing a longitudinal student tracking system: An implementation handbook. National Center for Higher Education Management System, P.O. Drawer P, Boulder, CO 80301-9752.[PDF(ERIC;登録が必要)](学生トラッキングシステム;Clagett(1992)で知る)
[2013.01.06]IRなどについての文献メモ 文献一覧を更新
- Brinkman, P. T. (1987). Conducting interinstitutional comparisons. New direction for institutional research, 53. San Francisco: Jossey-Bass.(他大学と比較する方法、比較するときに役立つデータ・それらのデータの分析方法について;Teeter & Brinkman(1992)で知る)
- Ewell, P. T. (1987). Enhancing information use in decision-making. New direction for institutional research, 64. San Francisco: Jossey-Bass.(他大学と比較する方法、情報の使い方・意思決定者との共有について;Teeter & Brinkman(1992)で知る)
- Teeter, D. J. (1983). The politics of comparing data with other institutions. In J. W. Firnberg & W. F. Lasher(Eds.), The politics and pragmatics of institutional research. New direction for institutional research, 38, 39-48. San Francisco: Jossey-Bass.(他大学と比較する方法、データの活かし方;Teeter & Brinkman(1992)で知る)
[2013.01.04]IRなどについての文献メモ 文献一覧を更新
- 上田信行・中原淳(編著)(2013).プレイフル・ラーニング:ワークショップの源流と学びの未来 三省堂(Twitter(@nakaharajunさん)で知る)
- 岩倉光助・高橋徹・蒋逸凡・中井孝幸(2012).大学図書館の施設構成からみた学習スタイルについて:居場所の形成からみた大学図書館の施設計画に関する研究 その1 東海支部研究報告集,50,457-460.[PDF](CiNii Articles「中井孝幸」で知る)
- 蒋逸凡・高橋徹・岩倉光助・中井孝幸(2012).大学図書館における学習スタイルと座席選択について:居場所の形成からみた大学図書館の施設計画に関する研究 その2 東海支部研究報告集,50,461-464.[PDF](CiNii Articles「中井孝幸」で知る)
- 秋野崇大・神永侑子・田中雄一郎・中井孝幸(2012).使い分け行動に基づく図書館の特色と選択意識について:場選択と利用者意識からみた図書館計画に関する研究 その1 東海支部研究報告集,50,469-472.[PDF](CiNii Articles「中井孝幸」で知る)
- 神永侑子・田中雄一郎・秋野崇大・中井孝幸(2012).図書館の特色による利用者の館内行動について:場選択と利用者意識からみた図書館計画に関する研究 その2 東海支部研究報告集,50,473-476.[PDF](CiNii Articles「中井孝幸」で知る)
- 秋野崇大・竹安建人・中井孝幸(2011).利用者の着座行為と座席選択の状況について:居場所選択からみた図書館の平面計画に関する研究 その2 東海支部研究報告集,49,413-416.[PDF](CiNii Articles「中井孝幸」で知る)
- 竹安建人・秋野崇大・中井孝幸(2011).図書館における時刻変動と場所選択について:居場所選択からみた図書館の平面計画に関する研究 その1 東海支部研究報告集,49,409-412.[PDF](CiNii Articles「中井孝幸」で知る)
- 谷口桃子・千田梨沙・蒋逸凡・中井孝幸(2011).地方都市における図書館を中心とする公共施設の情報ネットワークに関する研究 東海支部研究報告集,49,405-408.[PDF](CiNii Articles「中井孝幸」で知る)
- 秋野崇大・中井孝幸(2010).場の選択からみた利用者が求める図書館における開放性について:図書館の雰囲気が場の選択に与える影響に関する研究 その2 日本建築学会大会学術講演梗概集,325-326.[PDF](CiNii Articles「中井孝幸」で知る)
- 谷口桃子・山本智奈津・中井孝幸(2010).公共図書館における属性別座席選択からみた来館を促す場の魅力に関する研究 東海支部研究報告集,48,385-388.[PDF](CiNii Articles「中井孝幸」で知る)
- 秋野崇大・宮口晃・中井孝幸(2010).選択理由からみた図書館の場所性について:インターネット時代における「場」としての図書館に関する研究 その2 東海支部研究報告集,48,381-384. [PDF](CiNii Articles「中井孝幸」で知る)
- 青山裕亮・中井孝幸(2009).公共図書館における図書・資料の探索行動からみた書架レイアウトに関する研究 日本建築学会大会学術講演梗概集,307-308.[PDF](CiNii Articles「中井孝幸」で知る)
- 安田純一・中井孝幸(2009).曜日別の利用者属性からみた図書館利用行動に関する研究 東海支部研究報告集,47,429-432.[PDF](CiNii Articles「中井孝幸」で知る)
- 青山裕亮・中井孝幸(2009).主題別配架における利用者の蔵書探索行動に関する研究 東海支部研究報告集,47,425-428.[PDF](CiNii Articles「中井孝幸」で知る)
- 中井孝幸・伊藤禎浩・青山裕亮(2008).図書館利用者の滞在利用の時刻変動と着座行為:公共図書館における滞在利用からみた開架スペースの建築計画に関する研究 その1 日本建築学会大会学術講演梗概集,147-148.[PDF](CiNii Articles「中井孝幸」で知る)
- 青山裕亮・中井孝幸・伊藤禎浩(2008).座席タイプからみた利用者の場所選択:公共図書館における滞在利用からみた開架スペースの建築計画に関する研究 その3 日本建築学会大会学術講演梗概集,151-152.[PDF](CiNii Articles「中井孝幸」で知る)
- 伊藤禎浩・中井孝幸・青山裕亮(2008).利用者属性と行為内容からみた閲覧席の使われ方:図書館における滞在利用からみた開架スペースの建築計画に関する研究 その2 日本建築学会大会学術講演梗概集,149-150.[PDF](CiNii Articles「中井孝幸」で知る)
- 青山裕亮・中井孝幸(2008).公共図書館における利用者の蔵書探索に関する研究 東海支部研究報告集,46,553-556.[PDF](CiNii Articles「中井孝幸」で知る)
- 中井孝之・秋野崇大(2010).滞在型利用の傾向と図書館選択の理由について:図書館の雰囲気が場の選択に与える影響に関する研究 その1 日本建築学会大会学術講演梗概集,323-324.[PDF](CiNii Articles「秋野崇大」で知る)
- 益子一彦(2011).図書館空間のデザイン:デジタル化社会の知の蓄積 丸善出版(Amazon.co.jp「図書館 設計」で知る)
- Agnoli, A. (2009). Le piazze del sapere: Biblioteche e libertà. Roma, Bari: Laterza.(アンニョリA.萱野有美(訳)(2011).知の広場:図書館と自由 みすず書房)
- 大串夏身(2010).大学図書館の可能性:学術情報基盤、学生の自主的学習の場、そして知の創造的な場として 館灯,48,1-8.[PDF](CiNii Articles「大串夏身」で知る)
- (著者不明)(2012).既存図書館への増築による学習空間の再編 千葉大学アカデミックリンク 新建築,87(15),152-159.(CiNii Articles「図書館 設計」で知る)
- 兵藤健志・天野絵里子・中園晴貴(2011).学図書館活用セミナーをリデザインする:インストラクショナル・デザインを意識した図書館ガイダンスの取り組み 九州大学附属図書館研究開発室年報,24-31.[PDF](CiNii Articles「図書館 設計」で知る)
- 三宅常之(2010).学校図書館を使いやすく:就学者のニーズに応え飲食や24時間利用を可能に 日経アーキテクチュア,937,63-70.[日経BP](CiNii Articles「図書館 設計」で知る)
- Khasawneh, F. A., Kato, A., & Shibayama, Y.(2010).Analysis on innovative campus learning commons desing in light of emerging pedagogies: A study of problem based learning as a place maker in university facilities 日本建築学会大会学術講演梗概集,1069-1070.[PDF](CiNii Articles「図書館 設計」で知る)
- 川角典弘・小倉早貴・吉田知央・松榮将也・川邊秀明(2010).アメニティ性と行動選択からみた空間構成に関する研究(その2):附属図書館の使われ方と利用イメージの観察調査 日本建築学会大会学術講演梗概集,761-762.[PDF](CiNii Articles「図書館 設計」で知る)
- 一木拓太・本杉省三(2010).閲覧席における利用行為と閲覧席選択について:東京都北区立中央図書館を事例として 日本建築学会大会学術講演梗概集,327-328.[PDF](CiNii Articles「図書館 設計」で知る)
- 鈴木裕一・山崎俊裕・後藤和也(2010).都内公立2図書館の利用圏と利用実態について:「滞在型」公立図書館の施設機能と運営・利用実態に関する調査研究 その2 日本建築学会大会学術講演梗概集,319-320.[PDF](CiNii Articles「図書館 設計」で知る)
- 山崎俊裕・後藤和也・鈴木裕一(2010).都内公立2図書館における利用者の時刻変動と滞留分布特性について:「滞在型」公立図書館の施設機能と運営・利用実態に関する調査研究 その1 日本建築学会大会学術講演梗概集,317-318.[PDF](CiNii Articles「図書館 設計」で知る)
- 原郭二・加藤彰一(2009).学習スタイルの変化から見た大学図書館におけるコモンスペースの在り方に関する研究:ラーニング・コモンズのファシリティマネジメント研究 日本建築学会大会学術講演梗概集,457-458.[PDF](CiNii Articles「図書館 設計」で知る)
- 後藤和也・花岡雄太・山崎俊裕・能登谷明(2009).神奈川県内公共4図書館における利用者の館内滞留行動に関する調査 日本建築学会大会学術講演梗概集,323-324.[PDF](CiNii Articles「図書館 設計」で知る)
- 入江貴之・遠田敦・渡辺仁史(2008).図書に囲まれた空間構成が作業生産性に与える影響 日本建築学会大会学術講演梗概集,153-154.[PDF](CiNii Articles「図書館 設計」で知る)
- 金銀子・南俊朗(2008).利用者行動調査に基づく図書館スペース配置の改善:韓国果川図書館と九大附属図書館における図書館マーケティングの試み 九州大学附属図書館研究開発室年報,1-10.[PDF](CiNii Articles「図書館 設計」で知る)
- 花岡雄太・山崎俊裕・和田后司(2007).私立大学図書館の施設機能と運営実態について:私立大学図書館施設の現状と今日的課題に関する調査研究 その2 日本建築学会大会学術講演梗概集,113-114.[PDF](CiNii Articles「図書館 設計」で知る)
- 山崎俊裕・花岡雄太・和田后司(2007).私立大学図書館の施設面積と機能の現状について:私立大学図書館施設の現状と今日的課題に関する調査研究 その1 日本建築学会大会学術講演梗概集,111-112.[PDF](CiNii Articles「図書館 設計」で知る)
- 依田紀久(2007).根拠に基づいた図書館業務の設計:実践家の成果の共有を目指すEBLIPの動向 カレントアウェアネス,291,8-12.(CiNii Articles「図書館 設計」で知る)
- 村松奈美・前田博子(2007).公共図書館におけるテラス空間の評価に関する研究 東海支部研究報告集,45,581-584.[PDF](CiNii Articles「図書館 設計」で知る)
[2013.12.27]IRなどについての文献メモ 内容をアップ
- 呑海沙織・溝上智恵子・大学図書館研究グループ(2011).大学図書館におけるラーニング・コモンズの学生アシスタントの意義 図書館界,63(2),176-184.[内容](CiNii Articles「呑海沙織」で知る)
[2013.12.25]IRなどについての文献メモ 内容をアップ
- Howard, R. D., Snyder, J. K., & McLaughlin, G. M. (1992). Faculty salaries. In M. A. Whiteley, J. D. Porter, & R. H. Fenske(Eds.), The primer for institutional research. Tallahassee, Florida: Association for Institutional Research. pp.51-62.[概要]
[2013.12.25]IRなどについての文献メモ 説明文を更新
- 「内容を紹介している文献については、更新日が新しいものを上に挙げ、各文献について概要、読もうと思った理由・感想、詳細を書いています。」の後に「(文献によっては概要だけを書いています。)」を追記
[2013.12.25]IRなどについての文献メモ 内容をアップ
- 毛利美穂(2009).自律学習を支援するコミュニティの構築 大手前大学CELL教育論集,1,13-16.[PDF][概要](CiNii Articles「大学 チューター」で知る)
- 高橋知音・阿久津昌三・伊藤武廣・相澤徹・小林正信・森下徳雄(2004).信州大学における学生サービスへのニーズ 信州大学教育システム研究開発センター紀要,10,85-95.[PDF][概要](CiNii Articles「大学 チューター」で知る)
- 井口良子・藤原美佳・小幡誉子・横田地妙・近藤裕子(2010).大学図書館の学習支援 事例紹介 私立大学図書館協会会報,134,120-125.[概要](CiNii Articles「学習支援 大学」で知る)
- 成田真澄・松林世志子・ジョージヘイズ・前田ジョイス・金澤洋子・花岡修(2012).学生ライティングチューターによる支援効果 東京国際大学論叢 言語コミュニケーション学部編,8,75-86.[概要](CiNii Articles「大学 チューター」で知る)
- 姫野完治・長瀬達也・小松正武・浦野弘(2004).放課後学習チューター事業の展開過程の分析とモデル化 秋田大学教育文化学部教育実践研究紀要,26,77-87.[PDF][概要](CiNii Articles「大学 チューター」で知る)
[2012.12.21]IRなどについての文献メモ 内容をアップ
- 呑海沙織・溝上智恵子・大学図書館研究グループ(2011).大学図書館におけるラーニング・コモンズの学生アシスタントの意義 図書館界,63(2),176-184.[内容](CiNii Articles「呑海沙織」で知る)
[2012.12.20]IRなどについての文献メモ 文献一覧を更新
- 難波輝吉(2012).「使える」IR の基盤づくりを目指す実務的考察-米国IR 視察から学んだことを参考に- 大学・学校づくり研究,4,31-44.[PDF](CiNii Articles「難波輝吉」で知る)
- 勝又美智雄(2012).学習支援の先進的な取り組み例:国際教養大学図書館の場合 図書館雑誌,106(11),770-771.(ほぼ全寮制に近いためいつでも利用できるようにとの思いで24時間365日開館、デザイン性が高い、市民にも開放されている;CiNii Articles「学習支援 大学」で知る)
- 根津知佳子・前原裕樹・松本金矢・中西良文(2009).学生開発型のものづくり授業実践における「対話」の研究-授業案作成から実践に至るまで寄り添うチューターの視点から 三重大学教育学部附属教育実践総合センター紀要,29,39-45.[PDF](大学生が幼稚園・小学校・中学校の教育業務の補助と授業を行った、大学院生がチューターを務めた;CiNii Articles「大学 チューター」で知る)
[2012.12.14]IRなどについての文献メモ 内容をアップ
- 廣田未来(2011).お茶の水女子大学附属図書館の学生支援:ラーニング・コモンズとLiSAプログラム 情報の科学と技術,61(12),489-494.[PDF][内容](CiNii Articles「大学 チューター」で知る)
[2012.12.13]IRなどについての文献メモ 内容をアップ
- 畠山珠美(2011).ライティング・センター:構想から実現へ 情報の科学と技術,61(12),483-488.[PDF][内容](CiNii Articles「大学 チューター」で知る)
[2012.12.10]IRなどについての文献メモ 文献一覧を更新
- 難波輝吉(2009).教育現場から発信するIRのシステム構築に向けて 教育情報研究,増刊,75-78.[PDF](CiNii Articles「難波輝吉」で知る)
- 難波輝吉(2012).「使える」IR の基盤づくりを目指す実務的考察-米国IR 視察から学んだことを参考に- 大学・学校づくり研究,4,31-44.(CiNii Articles「難波輝吉」で知る)
- 岡田聡志・沖清豪(2008).アメリカの高等教育機関におけるInstitutional Researchをめぐる論争史 早稲田教育評論,22(1),63-81.(CiNii Articles「沖清豪」で知る)
- 沖清豪(2006).高等教育における情報の公開性に関する研究 早稲田教育評論,20(1),279-295.(CiNii Articles「沖清豪」で知る)
- 沖清豪(2010).イギリスにおける全国学生調査(National Student Survey)の導入と課題-IR(機関調査研究)のためのデータ収集という観点から 早稲田大学教育研究フォーラム,2,3-20.(CiNii Articles「沖清豪」で知る)
- 沖清豪(2011).日本の私立大学におけるInstitutional Research (IR)の動向 大学評価研究,10,37-45.(CiNii Articles「沖清豪」で知る)
- 沖清豪(2011).学校化された高等教育機関における学生支援の「再」構築 大学と学生,91,41-48.(CiNii Articles「沖清豪」で知る)
- 沖清豪(2012).大学から高校に望むこと 教育展望,58(4),39-42.(CiNii Articles「沖清豪」で知る)
- 山田礼子・沖清豪・森利枝・杉谷祐美子(2002).私立大学における一年次教育の実際:『学部長調査』(平成13年)の結果から 日本教育社会学会大会発表要旨集録,54,206-211.(CiNii Articles「沖清豪」で知る)
- 柳浦猛(2011).「アメリカのIRの本質」?-日本でIRが根付いていくために必要なこと IDE:現代の高等教育,528,12-17.(CiNii Articles「柳浦猛」で知る)
- 溝上慎一(2006).カリキュラム概念の整理とカリキュラムを見る視点:アクティブ・ラーニングの検討に向けて 京都大学高等教育研究,12,153-162.[PDF](CiNii Articles「溝上慎一」で知る)
- 溝上慎一(2004).大学新入生の学業生活への参入過程:学業意欲と授業意欲 京都大学高等教育研究,10,67-87.[PDF](CiNii Articles「溝上慎一」で知る)
- 山田剛史・溝上慎一(2004).大学教育における協調学習の果たす役割と効果:対人環境における異学年交流に着目して 神戸大学発達科学部研究紀要,12(1),175-187.(CiNii Articles「溝上慎一」で知る)
- 田口真奈・藤田志穂・神藤貴昭・溝上慎一(2004).FDとしての公開授業の類型化:13大学の事例をもとに 日本教育工学雑誌,27(suppl),25-28.[PDF](CiNii Articles「溝上慎一」で知る)
- 溝上慎一・田口真奈(2003).授業者の成長を促す大学の授業参観方式 日本教育工学雑誌,27(2),165-174.[PDF](CiNii Articles「溝上慎一」で知る)
- 溝上慎一(2003).大学新入生の学業生活への適応過程(2):大学生活における学業の位置づけ効果 日本青年心理学会大会発表論文集,11,58-59.[PDF](CiNii Articles「溝上慎一」で知る)
- 溝上慎一(2003).<第1章>学び支援プロジェクト(学び探求編)の実施:理論的背景・授業デザイン・授業ツール・成果 京都大学高等教育叢書,17,1-37.[PDF](CiNii Articles「溝上慎一」で知る)
- 溝上慎一・杉浦健・尾崎仁美(2003).主体的に生きる大学生の心理構造と居場所の構造-学生の主体的生き方につながる教育実践を目指して マツダ財団研究報告書 青少年健全育成関係,16,47-62.(CiNii Articles「溝上慎一」で知る)
- 溝上慎一(2002).学びの導入教育としての自己理解教育実践:大学生活の視点からのアプローチー 日本教育工学会大会講演論文集,18,447-448.(CiNii Articles「溝上慎一」で知る)
- 溝上慎一・水間玲子・尾崎仁美・小沢一仁・田中毎実(2002).大学生活を支援する自己理解教育実践:学びとの接合を目指して 日本教育心理学会総会発表論文集,44,S42-S43.[PDF](CiNii Articles「溝上慎一」で知る)
- 溝上慎一(1996).大学生の学習意欲 京都大学高等教育研究,2,184-197.[PDF](CiNii Articles「溝上慎一」で知る)
- 石上浩美・高橋登・大仲政憲(2012).教員志望大学生の体験による学び 大阪教育大学紀要 第Ⅳ部門 教育科学,61(1),117-130.[PDF](CiNii Articles「大学 チューター」で知る)
- 上原徳子・竹内七奈(2012).宮崎大学におけるチューター活動に関する考察:チューター活動後のアンケート分析より 宮崎大学教育文化学部紀要 教育科学,27,1-20.[PDF](CiNii Articles「大学 チューター」で知る)
- 岡谷英明(2012).大学生学習チューターの現状と課題に関する研究:高知市教育委員会の「学習チューター派遣事業」を中心に 高知大学教育実践研究,26,173-180.(CiNii Articles「大学 チューター」で知る)
- 木村拓也・池田光壱・西原俊明・大橋絵理・田山淳・竹内一真・井ノ上憲司・山口恭弘(2012).長崎大学における入学前教育の枠組みと効果測定―学生チューターを交えたヴィジョン形成教育の組織化と基礎学力向上の取組― 大学入試研究ジャーナル,22,95-104.(CiNii Articles「大学 チューター」で知る)
- 成田真澄・松林世志子・ジョージヘイズ・前田ジョイス・ 金澤洋子・花岡修(2012).学生ライティングチューターによる支援効果 東京国際大学論叢 言語コミュニケーション学部編,8,75-86.(CiNii Articles「大学 チューター」で知る)
- 畠山珠美(2011).ライティング・センター:構想から実現へ 情報の科学と技術,61(12),483-488.[PDF](CiNii Articles「大学 チューター」で知る)
- 山内祐平(2011).ラーニングコモンズと学習支援 情報の科学と技術,61(12),478-482.[PDF](CiNii Articles「大学 チューター」で知る)
- 廣田未来(2011).お茶の水女子大学附属図書館の学生支援:ラーニング・コモンズとLiSAプログラム 情報の科学と技術,61(12),489-494.[PDF](CiNii Articles「大学 チューター」で知る)
- 青野正太・余野桃子(2011).都立中央図書館における利用者サポートの実践 情報の科学と技術,61(12),495-500.[PDF](CiNii Articles「大学 チューター」で知る)
- 矢田俊文・庄ゆかり・野原ゆかり(2011).ウェビナーを活用したデータベース利用者教育 情報の科学と技術,61(12),501-506.[PDF](CiNii Articles「大学 チューター」で知る)
- 眞榮城和美(2011).学習チューター活動の支援方法に関する検討:大学内におけるセンター型支援・ネットワーク型支援の在り方 清泉女学院大学人間学部研究紀要,8,15-25.[PDF](CiNii Articles「大学 チューター」で知る)
- 舘野泰一・大川内隆朗・平野智紀・中原淳(2010).ライティング・センターにおけるチューターの指導を支援するシステムの開発 日本教育工学会研究報告集,2010(5),29-36.(CiNii Articles「大学 チューター」で知る)
- 橋本健広(2010).授業担当者と学生支援室チューターの連携による英語文法復習プログラム-2007年度の取組における問題点と学習者の動機づけ 関東学院大学経済経営研究所年報,32,212-232.(CiNii Articles「大学 チューター」で知る)
- 根津知佳子・前原裕樹・松本金矢・中西良文(2009).学生開発型のものづくり授業実践における「対話」の研究-授業案作成から実践に至るまで寄り添うチューターの視点から 三重大学教育学部附属教育実践総合センター紀要,29,39-45.[PDF](CiNii Articles「大学 チューター」で知る)
- 毛利美穂(2009).自律学習を支援するコミュニティの構築 大手前大学CELL教育論集,1,13-16.[PDF](CiNii Articles「大学 チューター」で知る)
- 野地有子・柿川房子・加城貴美子・吉山直樹・堀良子・直成洋子・岡村典子・長瀬亜岐(2006).PBLチュートリアルにおけるチュータートレーニングとシナリオ開発に関する研究 学長特別研究費研究報告書2005,1-13.(CiNii Articles「大学 チューター」で知る)
- 伊藤哲章・大高泉(2005).高大連携事業におけるチューターの役割:遺伝子組換え実験体験講座を事例として 年会論文集,29,439-440.(CiNii Articles「大学 チューター」で知る)
- 川野卓二(2005).Problem Based Learning 法のためのチューター訓練講座の効果 徳島大学大学開放実践センター紀要,15,17-27.(CiNii Articles「大学 チューター」で知る)
- 姫野完治・長瀬達也・小松正武・浦野弘(2004).放課後学習チューター事業の展開過程の分析とモデル化 秋田大学教育文化学部教育実践研究紀要,26,77-87.[PDF](CiNii Articles「大学 チューター」で知る)
- 高橋知音・阿久津昌三・伊藤武廣・相澤徹・小林正信・森下徳雄(2004).信州大学における学生サービスへのニーズ 信州大学教育システム研究開発センター紀要,10,85-95.[PDF](CiNii Articles「大学 チューター」で知る)
- 金井壽宏・山内祐平・中原淳(2012).インタラクションデザインを通じて創造的な実践コミュニティを編み出す:起業者活動支援の場、学生の学習・教育の場、社会人の学習・相互刺激の場 ヒューマンインタフェース学会誌,14(3),169-176.(CiNii Articles「山内祐平」で知る)
- 安斎勇樹・森玲奈・山内祐平(2011).創発的コラボレーションを促すワークショップデザイン 日本教育工学会論文誌,35(2),135-145.[PDF](CiNii Articles「山内祐平」で知る)
- 舘野泰一・大浦弘樹・望月俊男・西森年寿・山内祐平・中原淳(2011).アカデミック・ライティングを支援するICTを活用した協同推敲の実践と評価 日本教育工学会論文誌,34(4),417-428.[PDF](CiNii Articles「山内祐平」で知る)
- 舘野泰一・大浦弘樹・望月俊男・西森年寿・中原淳・山内祐平(2008).アカデミックライティングにおける協同推敲活動環境の構築と評価 日本教育工学会研究報告集,2008(3),59-62.(CiNii Articles「山内祐平」で知る)
- 勝又美智雄(2012).学習支援の先進的な取り組み例:国際教養大学図書館の場合 図書館雑誌,106(11),770-771.(CiNii Articles「学習支援 大学」で知る)
- 呑海沙織・溝上智恵子(2012).日本の大学図書館における学習支援の現状 大学図書館問題研究会誌,35,7-18.(CiNii Articles「学習支援 大学」で知る)
- 藤田毅・加藤誠之(2012).大学生による私立高等学校での学習支援活動に見る高校生の学びと学校改革への視点 人間関係学研究,18(1),33-39.(CiNii Articles「学習支援 大学」で知る)
- 川越博美・櫻井雅代・佐々木静枝・棚橋さつき・山田雅子(2012).座談会 「訪問看護師」をどう育むか?:基礎教育・現任教育の両側面から 訪問看護と介護,17(5),380-389.(CiNii Articles「学習支援 大学」で知る;特集「訪問看護師」をどう育むのか 地域拠点としての「大学」と「ステーション」)
- 阿保順子(2012).長野県看護大学における在宅現場との連携 訪問看護と介護,17(5),390-394.(CiNii Articles「学習支援 大学」で知る;特集「訪問看護師」をどう育むのか 地域拠点としての「大学」と「ステーション」)
- 谷垣靜子・岡田麻里・長江弘子・酒井昌子・乗越千枝・仁科祐子・片山陽子(2012).在宅看護に求められる看護実践能力の育成:連携教育に焦点を当てた大学の取り組み 訪問看護と介護,17(5),395-399.[医中誌Web](CiNii Articles「学習支援 大学」で知る;特集「訪問看護師」をどう育むのか 地域拠点としての「大学」と「ステーション」)
- 酒井郁子(2012).在宅ケアを補完する長期ケア施設の看護管理者の能力開発:実践と学業を両立する大学院教育 訪問看護と介護,17(5),400-406.[医中誌Web](CiNii Articles「学習支援 大学」で知る;特集「訪問看護師」をどう育むのか 地域拠点としての「大学」と「ステーション」)
- 本田彰子(2012).実践の場における訪問看護師学習支援プログラムの開発:「OJTで自ら学べる」をめざして 訪問看護と介護,17(5),407-411.[医中誌Web](CiNii Articles「学習支援 大学」で知る;特集「訪問看護師」をどう育むのか 地域拠点としての「大学」と「ステーション」)
- 中村順子(2012).大学から「訪問看護」を地域にアピールするサポーターとして 訪問看護と介護,17(5),412-416.(CiNii Articles「学習支援 大学」で知る;特集「訪問看護師」をどう育むのか 地域拠点としての「大学」と「ステーション」)
- 河井亨(2012).学生の学習と成長に対する授業外実践コミュニティへの参加とラーニング・ブリッジングの役割 日本教育工学会論文誌,35(4),297-308.[PDF](CiNii Articles「学習支援 大学」で知る)
- 山村総一郎・石黒太・山下倫実(2012).学生支援業務における教育学習支援部門と学生相談部門に関わるスタッフ間での協働イベント活動の試みについての考察 流通経済大学社会学部論叢,22(2),95-115.(CiNii Articles「学習支援 大学」で知る)
- 鈴木加奈子(2012).大学院生との連携によるラーニングアドバイザー制度:立教大学図書館における学習支援の取り組み事例 SALA会報,20,5.[PDF](CiNii Articles「学習支援 大学」で知る)
- 呑海沙織(2012).大学図書館における学習支援サービス再考:学習支援を再構築するラーニング・コモンズ SALA会報,20,2-3.[PDF](CiNii Articles「学習支援 大学」で知る)
- 南俊朗・大浦洋子(2012).学生の成長を助ける学習支援への模索-授業データ解析による支援方法発見への試み 九州情報大学研究論集,14,39-50.[PDF](CiNii Articles「学習支援 大学」で知る)
- 木村寛(2012).自ら学ぶ意欲を育てる学習支援の在り方について(その2) 広島工業大学紀要 教育編,11,67-72.(CiNii Articles「学習支援 大学」で知る)
- 久保山健(2012).図書館総合展での教育支援・学習支援に関する発表 大学の図書館,31(1),6-8.(CiNii Articles「学習支援 大学」で知る)
- 藤澤公也(2011).講義支援へのtwitterの活用:スライドにtweetを表示する試み システム/制御/情報:システム制御情報学会誌,55(10),446-451.[PDF](CiNii Articles「学習支援 大学」で知る)
- 今野文子・三石大(2011).授業改善・高度化のための授業リフレクションと情報技術活用 システム/制御/情報:システム制御情報学会誌,55(10),439-445.[PDF](CiNii Articles「学習支援 大学」で知る)
- 森本康彦(2011).高等教育におけるeポートフォリオの最前線 システム/制御/情報:システム制御情報学会誌,55(10),425-431.[PDF](CiNii Articles「学習支援 大学」で知る)
- 林敏浩・矢米雄(2011).教育・学習システムにおける学習者支援の動向 システム/制御/情報:システム制御情報学会誌,55(10),418-424.[PDF](CiNii Articles「学習支援 大学」で知る)
- 松永公廣(2011).ICTを活用した教育・学習支援の展開と課題 システム/制御/情報:システム制御情報学会誌,55(10),404-411.[PDF](CiNii Articles「学習支援 大学」で知る)
- 多久島寛孝・羽田野花美(2011).看護大学生の職業コミットメントと学習支援 保健科学研究誌,8,23-30.[PDF](CiNii Articles「学習支援 大学」で知る)
- 関昭典(2011).学習アドバイザーの学習支援活動に関する考察-東京経済大学英語学習アドバイザーにおける取り組みを事例として 東京経済大学人文自然科学論集,130,95-106.[PDF](CiNii Articles「学習支援 大学」で知る)
- 井口良子・藤原美佳・小幡誉子・横田地妙・近藤裕子(2010).大学図書館の学習支援 事例紹介 私立大学図書館協会会報,134,120-125.(CiNii Articles「学習支援 大学」で知る)
- 矢田部順二(2010).広島修道大学における学習支援センターの役割(1)活動のあるべき姿をもとめて 私学経営,419,42-50.(CiNii Articles「学習支援 大学」で知る)
- 矢田部順二(2010).広島修道大学における学習支援センターの役割(2)初年次教育の検証からみる課題と将来像 私学経営,422,49-58.(CiNii Articles「学習支援 大学」で知る)
- 松尾剛・杉村智子(2010).学習支援ボランティアにおける学生の学びを促すカンファレンス構造の検討-事後の振り返りとフィードバックに注目して 教育実践研究,18,119-126.(CiNii Articles「学習支援 大学」で知る)
- 佐々木緑(2010).自律学習支援のための学習者コミュニティーの構築 教育総合研究叢書,3,97-107.[PDF](CiNii Articles「学習支援 大学」で知る)
- 山田かおり(2010).嘉悦大学における<学生に火をつける>学習支援環境 短期大学図書館研究,30,55-57.(CiNii Articles「学習支援 大学」で知る)
- 原真由美・奥泉和久・高橋和子(2008).横浜女子短期大学図書館における学習支援の試み:図書館とFD 横浜女子短期大学研究紀要,23,99-124.[PDF](CiNii Articles「学習支援 大学」で知る)
- 原真由美・奥泉和久・高橋和子(2010).横浜女子短期大学図書館における学習支援の試み-授業との連携(続報) 横浜女子短期大学研究紀要,25,107-121.(CiNii Articles「学習支援 大学」で知る)
- 中林雅士(2010).明治大学図書館の学習支援への取り組み 薬学図書館,55(2),135-141.(CiNii Articles「学習支援 大学」で知る)
- 呑海沙織・溝上智恵子・大学図書館研究グループ(2011).大学図書館におけるラーニング・コモンズの学生アシスタントの意義 図書館界,63(2),176-184.(CiNii Articles「呑海沙織」で知る)
- 呑海沙織・溝上智恵子(2011).大学図書館における学習支援空間の変化:北米の学習図書館からラーニング・コモンズへ 図書館界,63(1),2-15.(CiNii Articles「呑海沙織」で知る)
- 土出郁子・呑海沙織・大学図書館研究グループ(2010).日本における学術機関リポジトリの発展過程と現状 図書館界,62(2),158-168.[PDF](CiNii Articles「呑海沙織」で知る)
- 呑海沙織・溝上智恵子(2010).北米の大学図書館における学習支援空間の歴史的変容-ブリティッシュ・コロンビア大学の事例から カナダ教育研究,8,1-17.[PDF](CiNii Articles「呑海沙織」で知る)
- 呑海沙織(2010).図書館をみせる-双方向のパブリック・リレーションズに向けて 図書館雑誌,104(4),202-204.(CiNii Articles「呑海沙織」で知る)
- 呑海沙織(2010).大正期の私立大学図書館-大学令下の大学設置認可要件としての図書 日本図書館情報学会誌,56(1),1-16.(CiNii Articles「呑海沙織」で知る)
- 呑海沙織(2009).パブリック・リレーションズ戦略の実際 マスコット・キャラクターと選書ツアー 情報管理,52(6),370-374.[PDF](CiNii Articles「呑海沙織」で知る)
- 呑海沙織(2004).大学図書館におけるサブジェクト・ライブラリアンの可能性 情報の科学と技術,54(4),190-197.[PDF](CiNii Articles「呑海沙織」で知る)
[2012.11.19]IRなどについての文献メモ 内容を修正
- 溝上慎一(2007).アクティブ・ラーニング導入の実践的課題 名古屋高等教育研究,7,269-287.
- 「読もうと思った理由・感想」の「初年児」を「初年次」に修正
[2012.11.15]IRなどについての文献メモ 内容をアップ
- 溝上慎一(2007).アクティブ・ラーニング導入の実践的課題 名古屋高等教育研究,7,269-287.(アクティブラーニングが導入された授業実践に関する広範な文献調査、アクティブラーニングを講義型・演習型(課題探求型/課題解決型)に分類;小島・井上(2011)で知る)[PDF][内容]
[2012.11.14]IRなどについての文献メモ 内容を修正
- 林(2010)
- ページ数「919-920」を「113-116」に修正
- PDFへのリンクを追加
[2012.11.13]IRなどについての文献メモ 文献一覧を更新
- 林一雅(2010).ICT支援型協調学習教室における授業の類型化―東京大学アクティブラーニングスタジオの事例から- 日本教育工学会第26回全国大会講演論文集,113-116.(アクティブラーニングを4つに分類;小島・井上(2011)で知る)
- 小島健太郎・井上仁(2011).アクティブラーニングへの取り組みと課題-学習空間整備と授業実践をふまえて- 大学教育,16,55-64.[PDF]
- 溝上慎一(2007).アクティブ・ラーニング導入の実践的課題 名古屋高等教育研究,7,269-287.(アクティブラーニングが導入された授業実践に関する広範な文献調査、アクティブラーニングを講義型・演習型(課題探求型/課題解決型)に分類;小島・井上(2011)で知る)[PDF]
- 山田耕路(2011).アクティブラーニングについて 大学教育,16,41-53.[PDF]
- 山内祐平(編著)(2010).学びの空間が大学を変える ボイックス
[2012.11.02]大学に関わる情報メモ 内容を修正
[2012.11.01]大学に関わる情報メモ 内容をアップ
[2012.10.15]IRなどについての文献メモ 内容をアップ
- McGuire, M. D. (1992). Faculty demand. In M. A. Whiteley, J. D. Porter, & R. H. Fenske(Eds.), The primer for institutional research. Tallahassee, Florida: Association for Institutional Research. pp.37-50. [内容]
[2012.10.07]IRなどについての文献メモ 内容を修正
- Endo, J. (1992). Student impacts. In M. A. Whiteley, J. D. Porter, & R. H. Fenske(Eds.), The primer for institutional research. Tallahassee, Florida: Association for Institutional Research. pp.25-36.[内容]
- 「読もうと思った理由・感想」欄の「モデルを考える目的は○○○ことと、△△△こと」を「モデルを考える目的は1.○○○ことと、2.△△△こと」に修正
- 「扱って文献」を「扱っている文献」に修正
[2012.09.26]大学に関わる情報メモ 内容をアップ
[2012.09.25]IRなどについての文献メモ 内容をアップ
- Endo, J. (1992). Student impacts. In M. A. Whiteley, J. D. Porter, & R. H. Fenske(Eds.), The primer for institutional research. Tallahassee, Florida: Association for Institutional Research. pp.25-36.[内容]
[2012.09.16]IRなどについての文献メモ 文献一覧を更新
- Bender, K. (2012). Developing institutional adaptability using change management processes. In R. D. Howard, G. W. McLaughlin, & W. E. Knight, The handbook of institutional research. San Francisco: Jossey-Bass. pp.107-130.
- Boon, R. D. (2012). Regulated ethics: Institutional research compliance with IRBs and FERPA. In R. D. Howard, G. W. McLaughlin, & W. E. Knight, The handbook of institutional research. San Francisco: Jossey-Bass. pp.325-339.
- Borden, V. M. H., & Kezar, A. (2012). Institutional research and collaborative organizational learning. In R. D. Howard, G. W. McLaughlin, & W. E. Knight, The handbook of institutional research. San Francisco: Jossey-Bass. pp.86-106.
- Carpenter-Hubin, J., Carr, R., & Hayes, R. (2012). Data exchange consortia: Characteristics, current examples, and developing a new exchange. In R. D. Howard, G. W. McLaughlin, & W. E. Knight, The handbook of institutional research. San Francisco: Jossey-Bass. pp.420-433.
- Cheslock, J., & Kroc, R. (2012). Managing college enrollments. In R. D. Howard, G. W. McLaughlin, & W. E. Knight, The handbook of institutional research. San Francisco: Jossey-Bass. pp.221-236.
- Dooris, M. J., & Rackoff, J. S. (2012). Institutional planning and resource management. In R. D. Howard, G. W. McLaughlin, & W. E. Knight, The handbook of institutional research. San Francisco: Jossey-Bass. pp.183-202.
- Eimers, M. T., Ko, J. W., & Gardner, D. (2012). Practicing institutional research. In R. D. Howard, G. W. McLaughlin, & W. E. Knight, The handbook of institutional research. San Francisco: Jossey-Bass. pp.40-56.
- Ferren, A. S., & Merrill, M. C. (2012). The role of institutional research in international universities. In R. D. Howard, G. W. McLaughlin, & W. E. Knight, The handbook of institutional research. San Francisco: Jossey-Bass. pp.57-72.
- Fife, J. D., & Spangehl, S. D. (2012). Tools for improving institutional effectiveness. In R. D. Howard, G. W. McLaughlin, & W. E. Knight, The handbook of institutional research. San Francisco: Jossey-Bass. pp.656-672.
- Fink, G. M., & Muntz, C. (2012). Federal higher education reporting databases and tools. In R. D. Howard, G. W. McLaughlin, & W. E. Knight, The handbook of institutional research. San Francisco: Jossey-Bass. pp.354-370.
- Fuller, C., Lebo, C., & Muffo, J. (2012). Challenges in meeting demands for accountability. In R. D. Howard, G. W. McLaughlin, & W. E. Knight, The handbook of institutional research. San Francisco: Jossey-Bass. pp.299-309.
- James, G. W. (2012). Developing institutional comparisons. In R. D. Howard, G. W. McLaughlin, & W. E. Knight, The handbook of institutional research. San Francisco: Jossey-Bass. pp.644-655.
- Keller, C. M. (2012). Collective responses to a new era of accountability in higher education. In R. D. Howard, G. W. McLaughlin, & W. E. Knight, The handbook of institutional research. San Francisco: Jossey-Bass. pp.371-385.
- Kelly, H. A., Seybert, J. A., Rossol, P. M., & Walters, A. M. (2012). Measuring and evaluating faculty workload. In R. D. Howard, G. W. McLaughlin, & W. E. Knight, The handbook of institutional research. San Francisco: Jossey-Bass. pp.550-572.
- Krist, P. S., Jones, E. A., & Thompson, K. (2012). Accreditation and the changing role of the institutional researcher. In R. D. Howard, G. W. McLaughlin, & W. E. Knight, The handbook of institutional research. San Francisco: Jossey-Bass. pp.310-324.
- Krotseng, M. V. (2012). System- and state-level data collection issues and practices. In R. D. Howard, G. W. McLaughlin, & W. E. Knight, The handbook of institutional research. San Francisco: Jossey-Bass. pp.386-403.
- Luan, J., Kumar, T., Sujitparapitaya, S., & Bohannon, T. (2012). Exploring and mining data. In R. D. Howard, G. W. McLaughlin, & W. E. Knight, The handbook of institutional research. San Francisco: Jossey-Bass. pp.478-501.
- Luna, A. L. (2012). Data, discrimination, and the law. In R. D. Howard, G. W. McLaughlin, & W. E. Knight, The handbook of institutional research. San Francisco: Jossey-Bass. pp.340-353.
- Lyddon, J. W., McComb, B. E., & Mizak, J. P. (2012). Tools for executing strategy. In R. D. Howard, G. W. McLaughlin, & W. E. Knight, The handbook of institutional research. San Francisco: Jossey-Bass. pp.625-643.
- Lyddon, J. W., McComb, B. E., & Mizak, J. P. (2012). Tools for setting strategy. In R. D. Howard, G. W. McLaughlin, & W. E. Knight, The handbook of institutional research. San Francisco: Jossey-Bass. pp.611-624.
- McLaughlin, G., Howard, R., & Jones-White, D. (2012). Analytic approaches to creating planning and decision support information. In R. D. Howard, G. W. McLaughlin, & W. E. Knight, The handbook of institutional research. San Francisco: Jossey-Bass. pp.459-477.
- McLaughlin, J. S, & Amoroso, L. M. (2012). Managing sustainability. In R. D. Howard, G. W. McLaughlin, & W. E. Knight, The handbook of institutional research. San Francisco: Jossey-Bass. pp.268-294.
- Milam, J., & Brinkman, P. (2012). Building cost models. In R. D. Howard, G. W. McLaughlin, & W. E. Knight, The handbook of institutional research. San Francisco: Jossey-Bass. pp.203-220.
- Milam, J., Porter, J., & Rome, J. (2012). Business intelligence and analytics: The IR vision for data administration, reporting, data marts, and data warehousing . In R. D. Howard, G. W. McLaughlin, & W. E. Knight, The handbook of institutional research. San Francisco: Jossey-Bass. pp.434-454.
- Noble, J., & Sawyer, R. (2012). Institutional research with published instruments. In R. D. Howard, G. W. McLaughlin, & W. E. Knight, The handbook of institutional research. San Francisco: Jossey-Bass. pp.523-549.
- Posey, J. T., & Pitter, G. W. (2012). Supporting the provost and academic vice president. In R. D. Howard, G. W. McLaughlin, & W. E. Knight, The handbook of institutional research. San Francisco: Jossey-Bass. pp.145-164.
- Purcell, J., Harrington, C., & King, B. (2012). Supporting institutional governance. In R. D. Howard, G. W. McLaughlin, & W. E. Knight, The handbook of institutional research. San Francisco: Jossey-Bass. pp.133-144.
- Reichard, D. J. (2012). The history of institutional research. In R. D. Howard, G. W. McLaughlin, & W. E. Knight, The handbook of institutional research. San Francisco: Jossey-Bass. pp.3-21.
- Rice, G. A., & Russell, A. B. (2012). Refocusing student success: Toward a comprehensive model. In R. D. Howard, G. W. McLaughlin, & W. E. Knight, The handbook of institutional research. San Francisco: Jossey-Bass. pp.237-255.
- Ronco, S., Archer, S., & Ryan, P. (2012). Tools for measuring the effectiveness of institutional research. In R. D. Howard, G. W. McLaughlin, & W. E. Knight, The handbook of institutional research. San Francisco: Jossey-Bass. pp.673-688.
- Ruddock, M. S. (2012). Developing K–20+ state databases. In R. D. Howard, G. W. McLaughlin, & W. E. Knight, The handbook of institutional research. San Francisco: Jossey-Bass. pp.404-419.
- Sanders, L., & Filkins, J. (2012). Effective reporting. In R. D. Howard, G. W. McLaughlin, & W. E. Knight, The handbook of institutional research. San Francisco: Jossey-Bass. pp.594-610.
- Simone, S., Campbell, C. M., & Newhart, D. W. (2012). Measuring opinion and behavior. In R. D. Howard, G. W. McLaughlin, & W. E. Knight, The handbook of institutional research. San Francisco: Jossey-Bass. pp.502-522.
- Teodorescu, D. (2012). Examining faculty recruitment, retention, promotion, and retirement. In R. D. Howard, G. W. McLaughlin, & W. E. Knight, The handbook of institutional research. San Francisco: Jossey-Bass. pp.165-182.
- Toutkoushian, R. K., & Kramer II, D. A (2012). Analyzing equity in faculty compensation. In R. D. Howard, G. W. McLaughlin, & W. E. Knight, The handbook of institutional research. San Francisco: Jossey-Bass. pp.573-593.
- Volkwein, J. F., Liu, Y. J., & Woodell, J. (2012). The structure and functions of institutional research offices. In R. D. Howard, G. W. McLaughlin, & W. E. Knight, The handbook of institutional research. San Francisco: Jossey-Bass. pp.22-39.
- Voorhees, R. A. & Hinds, T. (2012). Out of the box and out of the office: Institutional research for changing times. In R. D. Howard, G. W. McLaughlin, & W. E. Knight, The handbook of institutional research. San Francisco: Jossey-Bass. pp.73-85.
- Watt, C. (2012). Academic space management and the role of institutional research. In R. D. Howard, G. W. McLaughlin, & W. E. Knight, The handbook of institutional research. San Francisco: Jossey-Bass. pp.256-267.
[2012.09.05]IRなどについての文献メモ 内容を修正
- 加藤信哉・小山憲司(編訳)(2012).ラーニング・コモンズ-大学図書館の新しいかたち- 勁草書房[内容]
[2012.09.05]IRなどについての文献メモ 内容をアップ
- 加藤信哉・小山憲司(編訳)(2012).ラーニング・コモンズ-大学図書館の新しいかたち- 勁草書房[内容]
[2012.09.03]大学に関わる情報メモ 内容を修正
[2012.09.03]IRなどについての文献メモ 内容をアップ
- Clagett, C. (1992). Enrollment management. In M. A. Whiteley, J. D. Porter, & R. H. Fenske(Eds.), The primer for institutional research. Tallahassee, Florida: Association for Institutional Research. pp.12-24.[内容]
[2012.08.28]IRなどについての文献メモ 文献一覧を更新
- Bers, T. H. (1987). Exploring institutional images through focus group interviews. In R. S. Lay, & J. J. Endo(Eds.), Designing and using market research. New directions for institutional research, 54, 19-29. San Francisco: Jossey-Bass.(IRにおいて分析対象のグループに焦点を当てる方法;Clagett(1992)で知る)
- Bers, T. H.(Ed.) (1989). Using student tracking systems effectively. New directions for community colleges, 66. San Francisco: Jossey-Bass. (学生トラッキングシステム;Clagett(1992)で知る)
- Ewell, P. T., Parker, R., & Jones, D. P. (1988). Establishing a longitudinal student tracking system: An implementation handbook. National Center for Higher Education Management System, P.O. Drawer P, Boulder, CO 80301-9752.(学生トラッキングシステム;Clagett(1992)で知る)
- Goldman, A. E., & McDonald, S. S. (1987). The group depth interview: Its principles and practice. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall. (分析対象のグループに焦点を当てる方法;Clagett(1992)で知る)
- Palmer, J. (1990). Accountability through student tracking: A review of the literature. American Association of Community and Junior College, National Center for Higher Education, One Dupont Circle, #410, Washington, DC 20036. (学生トラッキングシステム;Clagett(1992)で知る)
[2012.08.20]大学に関わる情報メモ 内容をアップ
[2012.08.18]IRなどについての文献メモ 文献一覧を更新
- Dolence, M. G. (1989-1990). Evaluation criteria for an enrollment management program. Planning for higher education, 18(1), 1-13. (EMを扱った初期の文献、組織の観点からEMを考える;Clagett(1992)で知る)
- Dolence, M. G., Miyahara, D. H., Grajeda, J., & Rapp, C. (1987-88). Strategic enrollment management and planning. Planning for higher education, 16(3), 55-74. (EMを扱った初期の文献、組織の観点からEMを考える;Clagett(1992)で知る)
- Fenske, R. H.(Ed.) (1989). Studying the impact of student aid on institutions. New directions for institutional research, 62. San Francisco: Jossey-Bass. (EMの取り組みを考えるときに学内のいろいろな情報をどう解釈するか;Clagett(1992)で知る)
- Glover, R. H. (1986). Designing a decision-support system for enrollment management. Research in higher education, 24(1), 15-34. (EMの取り組みを考えるときに学内のいろいろな情報をどう解釈するか;Clagett(1992)で知る)
- Hossler, D.(Ed.) (1986). Managing college enrollments. New directions for higher education, 53. San Francisco: Jossey-Bass. (EMを扱った初期の文献、組織の観点からEMを考える;Clagett(1992)で知る)
- Hossler, D. (1987). Creating effective enrollment management systems. New York, N.Y.: College Entrance Examination Board. (EMを扱った初期の文献、組織の観点からEMを考える;Clagett(1992)で知る)
- Hossler, D.(Ed.) (1991). Evaluating student recruitment and retention programs. New directions for institutional research, 70. San Francisco: Jossey-Bass. (EMの取り組みを考えるときに学内のいろいろな情報をどう解釈するか;Clagett(1992)で知る)
- Kemerer, F. R., Baldridge, J. V., & Green, K. C. (1982). Strategies for effective enrollment management. Washington, D.C.: American Association of State Colleges and Universities. (EMを扱った初期の文献、組織の観点からEMを考える;Clagett(1992)で知る)
- Lay, R. S., & Endo, J. J.(Eds.) (1987). Desinging and using market research. New directions for Higher Education, 54. San Francisco: Jossey-Bass. (EMの取り組みを考えるときに学内のいろいろな情報をどう解釈するか;Clagett(1992)で知る)
- Leslie, L. L., & Brinkman, P. T. (1987). Student price response in higher education. Journal of higher education, 58(2), 181-203.(EMの取り組みを考えるときに学内のいろいろな情報をどう解釈するか;Clagett(1992)で知る)
[2012.08.12]IRなどについての文献メモ 内容をアップ
- Middaugh, M. F. (1992). Persistence. In M. A. Whiteley, J. D. Porter, & R. H. Fenske(Eds.), The primer for institutional research. Tallahassee, Florida: Association for Institutional Research. pp.1-11.[内容]
[2012.08.11]IRなどについての文献メモ 文献一覧を更新
- 加藤信哉・小山憲司(編訳)(2012).ラーニング・コモンズ: 大学図書館の新しいかたち 勁草書房
[2012.08.11]大学に関わる情報メモ 内容をアップ
[2012.08.10]大学に関わる情報メモ ページを立ち上げ(ホームからリンク)、内容をアップ
[2012.08.10]ホーム 経歴紹介の記載を追加、リンクを設定
[2012.08.09]IRなどについての文献メモ 内容をアップ
- オンデマンド授業流通フォーラム大学イノベーション研究会(編)(2011).地域に愛される大学のすすめ 三省堂[内容]
[2012.08.06]IRなどについての文献メモ 文献一覧を更新
- 江原昭博(2011).アメリカの大学における卒業生の研究再考-Alumni Studiesの歴史的変遷とIRの関係 日本私立大学協会附置私学高等教育研究所 私学高等教育研究叢書 高等教育におけるIR(Institutional Research)の役割,43-62.[PDF]
- 広島大学高等教育研究開発センター(2012).これからの大学経営~誰がどのような役割を担うのか~第39回(2011年度)研究員集会の記録 高等教育研究叢書,118[PDF]
- 金子元久・両角亜希子(2002).推計 特別企画 2012年までの大学進学需要予測-全体に落ち込むが地域差が大きい カレッジマネジメント,115,47-53.
- 黒田壽二・両角亜希子(2010).インタビュー:黒田壽二 中教審大学分科会質保証システム部会長に聞く 大学の自主的な情報公開に向け カレッジマネジメント,161,4-10.[PDF]
- 森利枝(2011).私立大学におけるインスティテューショナル・リサーチ構築に向けての検討 日本私立大学協会附置私学高等教育研究所 私学高等教育研究叢書 高等教育におけるIR(Institutional Research)の役割,15-24.[PDF]
- 両角亜希子(2000).私立大学のガバナンス-概念的整理と寄附行為の分析 東京大学大学院教育学研究科紀要,39,235-243.[PDF]
- 両角亜希子(2001).大学経営研究の基礎概念 大学研究,22,275-293.[PDF]
- 両角亜希子(2001).大学の組織・経営-アメリカにおける研究動向 高等教育研究,4,157-176.[PDF]
- 両角亜希子(2003).大学の教育コスト IDE:現代の高等教育,454,27-33.
- 両角亜希子(2004).マンチェスター大学の合併 IDE:現代の高等教育,463,72-77.
- 両角亜希子(2006).米国都市型大学における地域コミュニティとの関係-ペンシルバニア大学の事例 三田評論,1095,24-29.
- 両角亜希子(2007).高等教育費負担の国際比較 IDE:現代の高等教育,492,42-47.
- 両角亜希子(2008).国立・私立を越えた大連携 京都教育大学大学院連合教職実践研究科 カレッジマネジメント,149,10-14.[PDF]
- 両角亜希子(2009).大学生の学習行動の大学間比較-授業の効果に着目して 東京大学大学院教育学研究科紀要,49,191-206.(藤村(2013)「大規模学生調査から学習成果と学習時間の構造を掴む」で知る)
- 両角亜希子(2009).大学の寄付募集の取り組みと課題 月報私学,133,6-7.[PDF]
- 両角亜希子(2009).学習行動と大学の個性 IDE:現代の高等教育,515,26-31.
- 両角亜希子(2010).大学生の経済環境と学習・生活 IDE:現代の高等教育,520,41-47.
- 両角亜希子(2010).私立大学における戦略的経営-財務調査からみる現状と課題 私学高等教育研究所 財務、職員調査から見た私大経営改革 pp.5-24.
- 両角亜希子(2010).私立大学の経営と拡大・再編-1980年代後半以降の動態 東信堂
- 両角亜希子(2010).職員の将来像と育成の課題・職員調査から IDE:現代の高等教育,523,45-49.
- 両角亜希子(2011).地域の大学間連携による職員養成―四国地区SPOD-SDプログラム カレッジマネジメント,166,26-29.[PDF]
- 両角亜希子(2011).大学経営・政策コースの取り組み:東京大学 IDE:現代の高等教育,535,24-28.
- 両角亜希子(2011).大学生の生活・学習と経済状況 家計経済研究,91,22-32.
- 両角亜希子(2012).5年一貫制大学院でのグローバルリーダー養成:京都大学大学院思修館(構想中) カレッジマネジメント,173,24-27.[PDF]
- 両角亜希子(2012).韓国における私立大学の自律性―「経営不良大学」をめぐる政策動向を中心に 大学経営政策研究,2,41-63.[PDF]
- 両角亜希子(2012).認証評価と大学独自戦略の併存に向けて カレッジマネジメント,172,22-25.[PDF]
- 両角亜希子(2012).シリーズ大学経営論第1回:私立大学の中長期計画 文部科学教育通信,296,15-17.
- 両角亜希子(2012).私立大学の財政-現状と課題 高等教育研究,15,93-113.
- 両角亜希子・齋藤芳子・小林信一.(2004).知識社会における大学教育と職業:情報系人材の知識・スキル変化を題材として 大学論集,34,109-131.[PDF]
- 両角亜希子・小方直幸(2011).大学の経営と事務組織:ガバナンス、人事制度、組織風土の影響 東京大学大学院教育学研究科紀要,51,159-174.[PDF]
- 岡田聡志(2011).私立大学におけるIR機能の担当箇所と今後の方向性との関係 日本私立大学協会附置私学高等教育研究所 私学高等教育研究叢書 高等教育におけるIR(Institutional Research)の役割,25-42.[PDF]
- 沖清豪(2011).イギリスにおけるIRの研究開発-Mantz Yorkeの研究に基づいて 日本私立大学協会附置私学高等教育研究所 私学高等教育研究叢書 高等教育におけるIR(Institutional Research)の役割,63-72.[PDF]
- 山田礼子(2011).ベンチマーク評価と連動する学生調査とIR-日本版学生調査(JCIRP)の役割と活用 日本私立大学協会附置私学高等教育研究所 私学高等教育研究叢書 高等教育におけるIR(Institutional Research)の役割,1-14.[PDF]
[2012.08.04]IRなどについての文献メモ 内容をアップ
- 海老原嗣生・倉部史記・諸星裕・山内太地・山崎徹・山本繁・渡辺千鶴・井上久男(2012).危ない大学 洋泉社[内容]
[2012.08.03]IRなどについての文献メモ 文献一覧を更新
- Middaugh, M. F. (1992). Persistence. In M. A. Whiteley, J. D. Porter, & R. H. Fenske(Eds.), The primer for institutional research. Tallahassee, Florida: Association for Institutional Research. pp.1-11.
- Clagett, C. (1992). Enrollment management. In M. A. Whiteley, J. D. Porter, & R. H. Fenske(Eds.), The primer for institutional research. Tallahassee, Florida: Association for Institutional Research. pp.12-24.
- Endo, J. (1992). Student impacts. In M. A. Whiteley, J. D. Porter, & R. H. Fenske(Eds.), The primer for institutional research. Tallahassee, Florida: Association for Institutional Research. pp.25-36.
- McGuire, M. D. (1992). Faculty demand. In M. A. Whiteley, J. D. Porter, & R. H. Fenske(Eds.), The primer for institutional research. Tallahassee, Florida: Association for Institutional Research. pp.37-50.
- Howard, R. D., Snyder, J. K., & McLaughlin, G. M. (1992). Faculty salaries. In M. A. Whiteley, J. D. Porter, & R. H. Fenske(Eds.), The primer for institutional research. Tallahassee, Florida: Association for Institutional Research. pp.51-62.
- Teeter, D. J., & Brinkman, P. T. (1992). Peer institutions. In M. A. Whiteley, J. D. Porter, & R. H. Fenske(Eds.), The primer for institutional research. Tallahassee, Florida: Association for Institutional Research. pp.63-72.
- Smith, D. G. (1992). Diversity. In M. A. Whiteley, J. D. Porter, & R. H. Fenske(Eds.), The primer for institutional research. Tallahassee, Florida: Association for Institutional Research. pp.73-85.
- Morrison, J. L. (1992). Environmental scanning. In M. A. Whiteley, J. D. Porter, & R. H. Fenske(Eds.), The primer for institutional research. Tallahassee, Florida: Association for Institutional Research. pp.86-99.
- Heverly, M. A. (1992). Total quality management. In M. A. Whiteley, J. D. Porter, & R. H. Fenske(Eds.), The primer for institutional research. Tallahassee, Florida: Association for Institutional Research. pp.100-112.
- Hanson, G. R., & Price, B. R. (1992). Academic program review. In M. A. Whiteley, J. D. Porter, & R. H. Fenske(Eds.), The primer for institutional research. Tallahassee, Florida: Association for Institutional Research. pp.113-126.
- Haberaecker, H. J. (1992). Cost analysis. In M. A. Whiteley, J. D. Porter, & R. H. Fenske(Eds.), The primer for institutional research. Tallahassee, Florida: Association for Institutional Research. pp.127-139.
[2012.08.02]IRなどについての文献メモ 文献一覧を更新
- Middaugh, M. F. (1990). A handbook for newcomers to institutional research. North East Association for Institutional Research, c/o University of Delware, Newark, DE 19716. (退学せずに在籍し続ける学生に関するデータの作り方・見せ方;Middaugh(1992)で知る)
- Noel, L., Levitz, R., Saluri, D, & Associates. (1986). Increasing student retention. San Francisco: Jossey-Bass. (退学せずに在籍し続ける学生に関するデータの作り方・見せ方;Middaugh(1992)で知る)
- Pascarella. E. T., & Terenzini, P. T. (1991). How college affects students. San Francisco: Jossey-Bass. (学生と大学のマッチング;Middaugh(1992)で知る)
- Porter, O. F. (1989). Undergraduate completion and persistence at four-year colleges and universities: Completers, persisters, stopouts, and dropouts. National Institute of Independent Colleges and Universities, Suite 750, 122 C St. NW, Washington, DC 20001-2190.[PDF] (退学せずに在籍し続ける学生に関するデータの作り方・見せ方;Middaugh(1992)で知る)
- Tinto, V. (1987). Leaving college: Rethinking the cause and cures of student attrition. Chicago: University of Chicago Press. (学生と大学のマッチング;Middaugh(1992)で知る)
- Upcraft, M. L., & Gardner, J. N. (1989). The freshman year experience. San Francisco: Jossey-Bass. (学生と大学のマッチング;Middaugh(1992)で知る)
[2012.08.01]IRなどについての文献メモ 内容をアップ
- 高野篤子(2012).アメリカ大学管理運営職の養成 東信堂[内容]
[2012.07.31]IRなどについての文献メモ 文献一覧を更新
- 林未央(2008).アメリカのサーティフィケート IDE現代の高等教育,502,45-49.
- 文部科学省高等教育局(2008).平成二十二年度高等教育行政の展望 日本学生支援機構(編)大学と学生,26-53.[PDF]
[2012.07.27]IRなどについての文献メモ 内容をアップ
- 寺﨑昌男(2007).大学改革 その先を読む 東信堂[内容]
[2012.07.27]サイト立ち上げ
HTML5 CSS Level 3